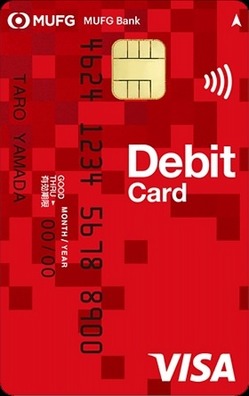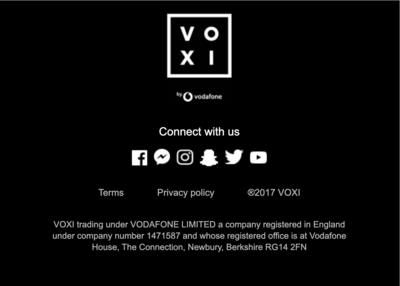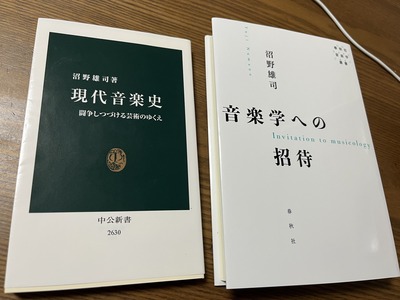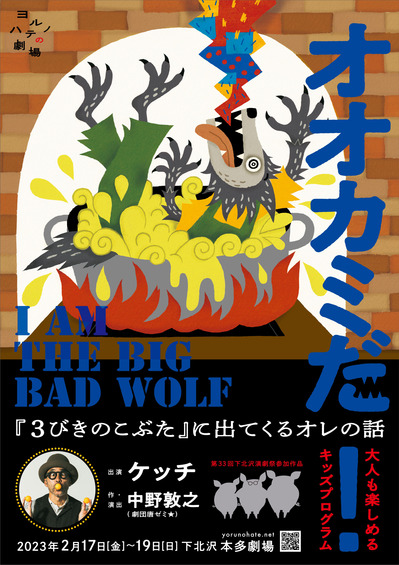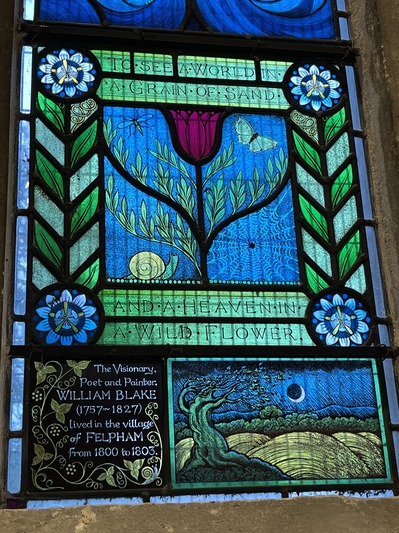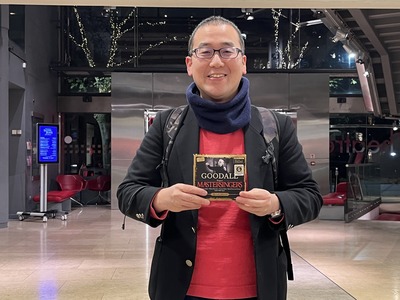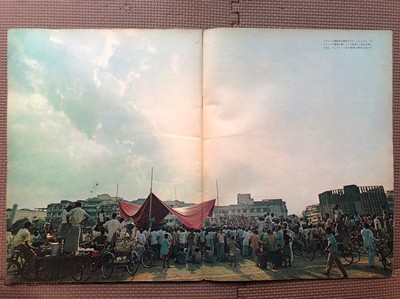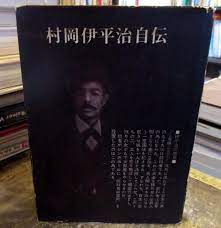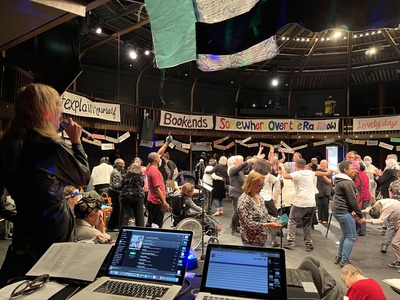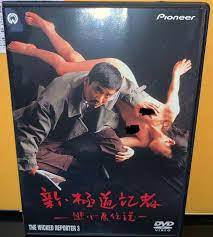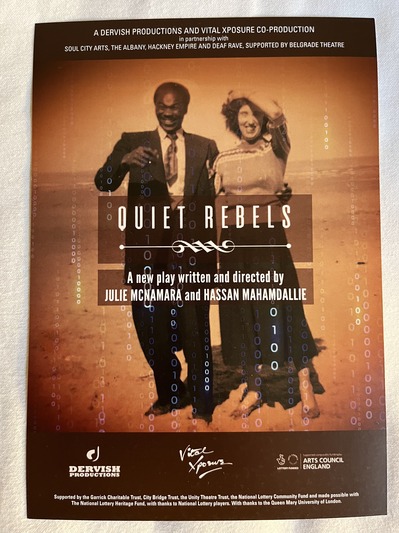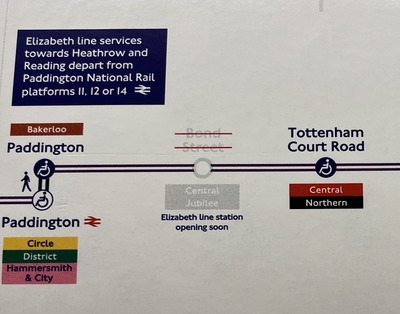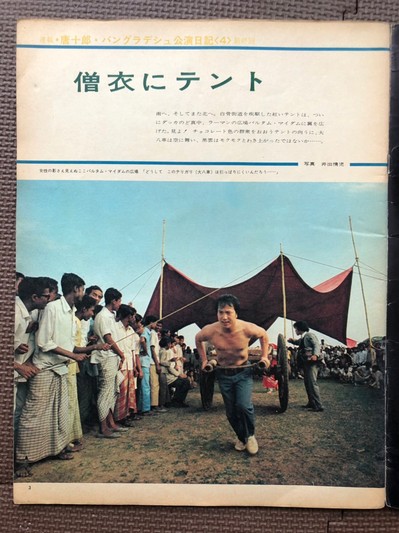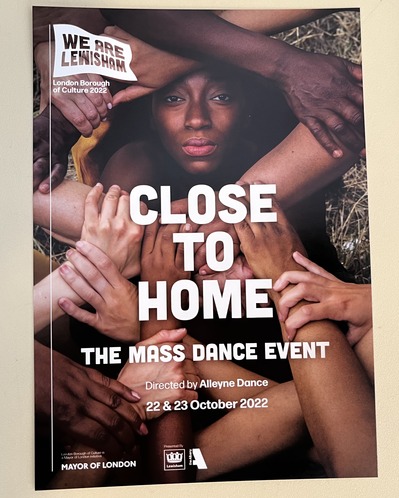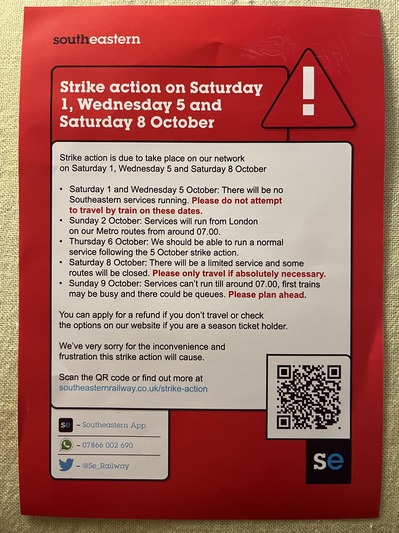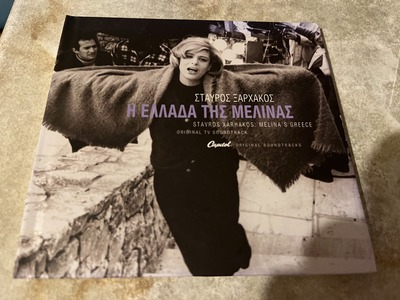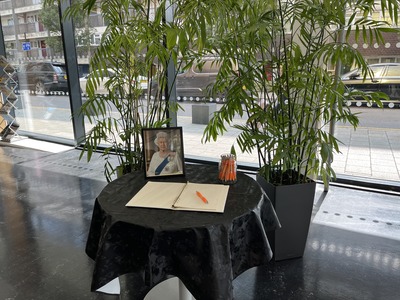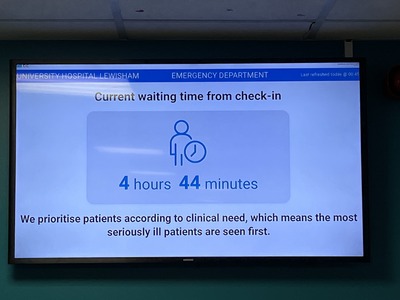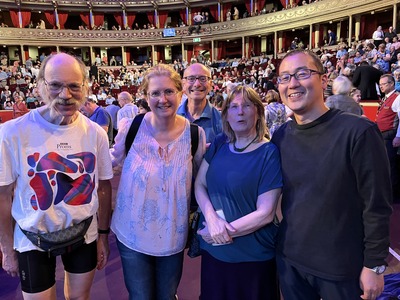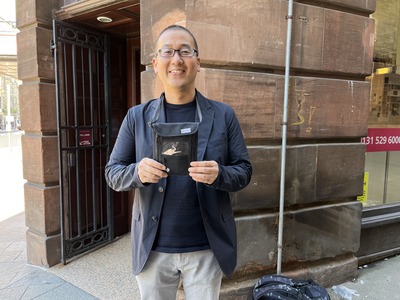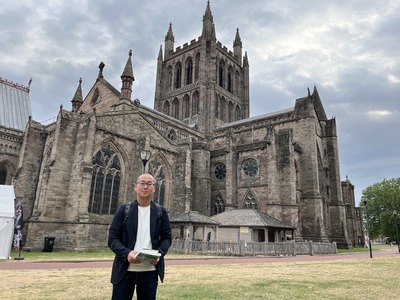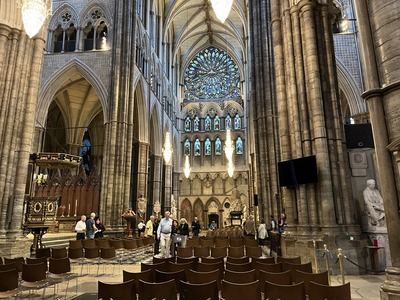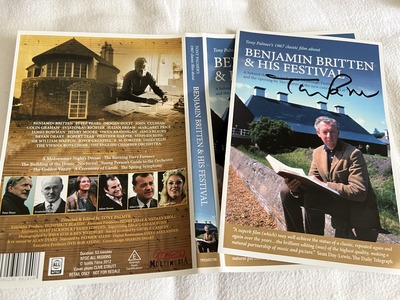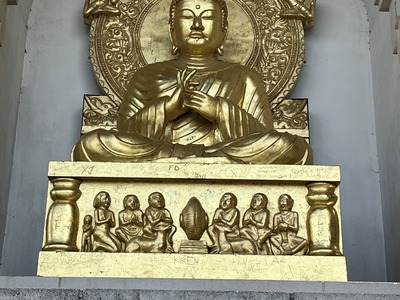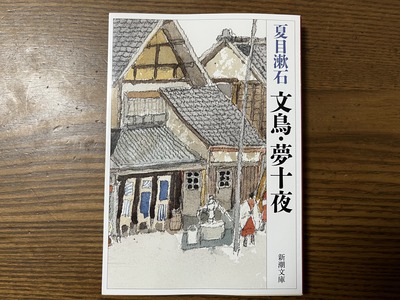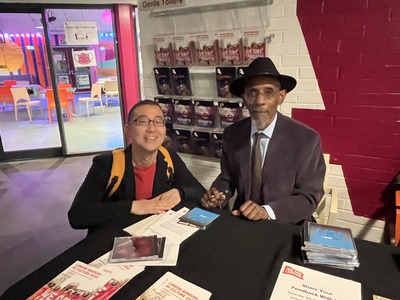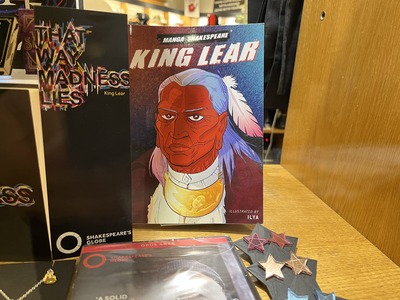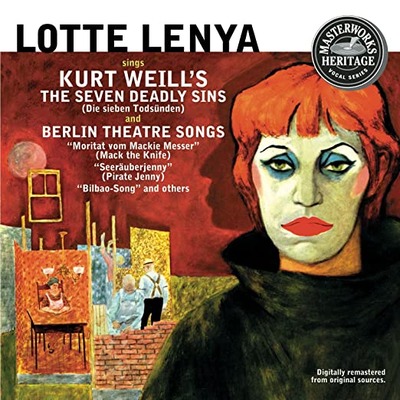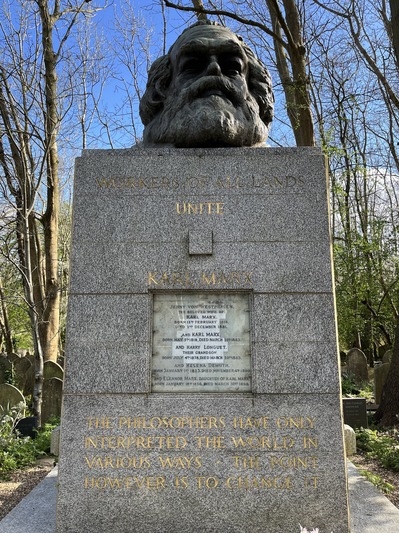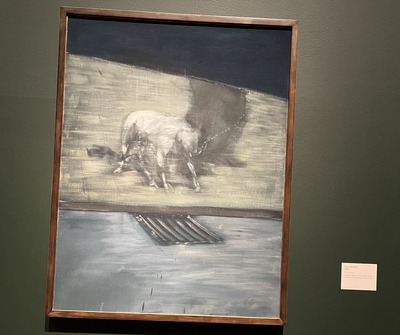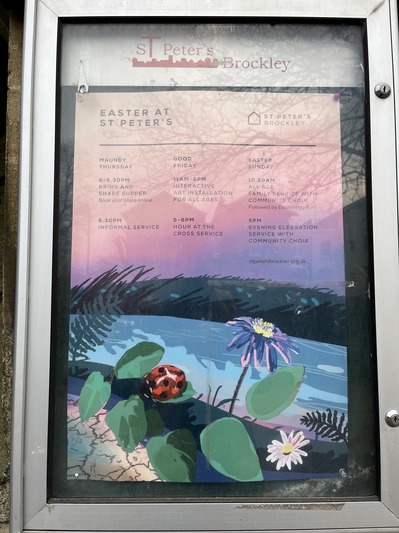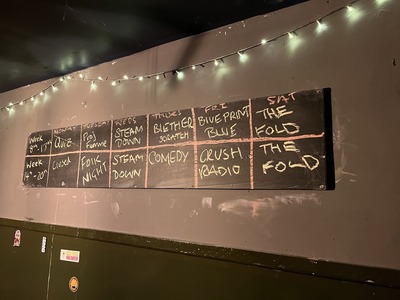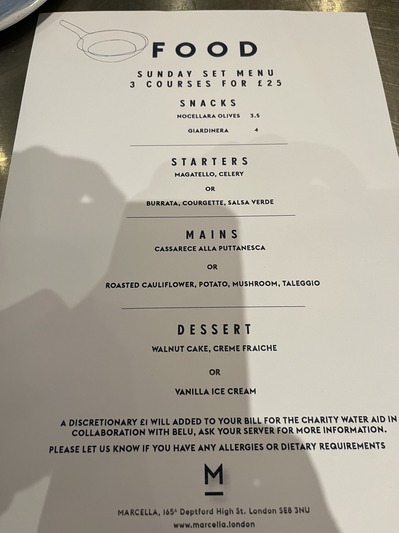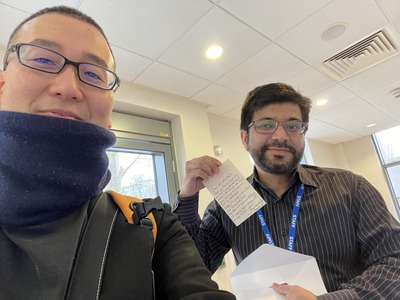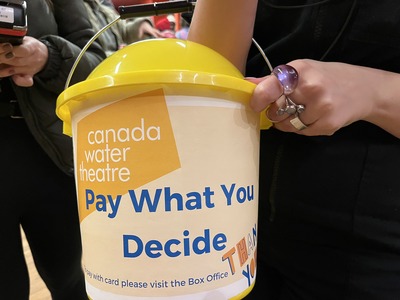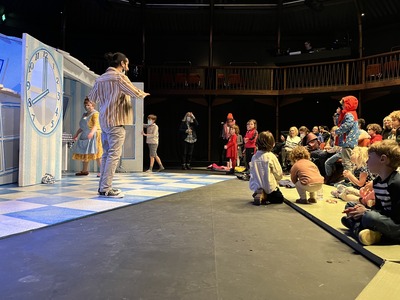2025年4月21日 Posted in
2022イギリス戦記 ↑こういうのにずいぶん助けられました。これはサンプルです
今日、隙間時間を見つけて銀行に行きました。
デビットカードを更新するためです。
2年8ヶ月ぶりに、気になって先延ばしにしていた用事をやっと果たす
ことができました。
2022年1月。ロンドンに発つ10日ほど前。
私は海外研修の先輩から、デビットカード自体の存在を教えられました。
「それがないと現金おろせないよ」という実に的確なアドバイスを
頂いたのです。それまでの私は、近所のコンビニでキャッシュカードが
使えるのだから、ロンドンでだってそれができるに違いないと思い
こんでいました。デビットカードそのものを知らなかった。
出発の数日前に届いたカードに、自分は救われることになりました。
それから時間が経ち。
ロンドンでお金をおろすときは、いつも緊張していました。
あの国では、地下街とか、スーパーの外壁とか、囲いも無しに
ATMがついているのです。
よく、近くに物乞いがいました。
私はいつも、ひょっとしたら後ろから殴られ、現金を奪われるん
じゃないかと警戒しながら現金をおろしていました。
そして2022年8月頭。
乗り換えに使うカナリーワーフのATMで、別のことに気を取られていた
私は、間違った暗証番号を連続で押してしまったのです。
結果、カードはロックされ、椎野を通じて日本の窓口に電話したところ
「解除するには来店してください」という一点張りに途方に暮れました。
だいたいの買い物はクレジットでしたが、時には現金が必要です。
特に、家賃は現金払いしていましたから。
椎野が新たにデビットカードを作ってくれて、2週間後にはそれが
届きました。だから滞在の後半は、椎野の口座から現金をおろして
しのぎました。
帰国してからの2年数ヶ月、そのうちに手続きにいかなければ、
と思い続けてきましたが、ついつい後回しにしてきました。
それを、ついに今日果たすことができました。
ロンドンにギリギリ間に合って生活を支えてくれたカード。
グリニッジ駅前のスーパー・セインズベリーで画面表記の英語が
さっぱりわからず四苦八苦しながらお金をおろしたカードに
ハサミが入りました。
新しいデビットカードは、1週間ほどで届くようです。
2023年1月27日 Posted in
2022イギリス戦記 ↑これ! 送られてきたレシートのテンプレート!
やはり起こってしまった。
ロンドンは相変わらずのロンドンである。
どういうことかというと、去年11ヶ月間、イギリス滞在の間に使っていた
ケータイのキャリア、Vodafoneからしれっとメールが届いたのである。
曰く、1/26に35ポンドを引き落としました。
要するにレシートを送りつけてきたのだ。
・・・これをずっと警戒してきた。
どうせこうなるような気がしていたので、念入りに店を訪ね、
本当に大丈夫だろうねえ?と念押ししてから帰国した。
なのに、である。
ロンドンでのケータイ契約はまことに簡単で、
お店に行ってSIMカードを買うだけで番号がもらえる。
1ヶ月の通話時間とか、受信できるデータ量とかは会社と料金によるが
日本のような煩わしさが全くない。
止めない限り、1ヶ月ごとに勝手に更新される。
契約した時、
解約するときはどうすれば良いのか?と質問した私に、
店員は、SIMカードを抜けば勝手に契約関係は解消される、と答えた。
・・・何か信用できなかったので、
帰国前にお店に行き、12/31で契約解消してもらって結構だと伝えたら、
店員はカタカタとパソコンを打ち、「これでもう大丈夫。安心して良いですよ。
イギリスにいる間、使ってくれてありがとう」などと着実かつ口当たりの良いことを
言って送り出された。
なのに、である。
やはりレシートは知らん顔で届き、このままだと永遠に月額35ポンドを
巻き上げる気らしい。これがイギリスだ。腹立たしいし油断ならない。
早速にブチギレたメールを返信したら、どうやら送信専用のアドレスらしく
弾き返された。ウェブからの侵入を試みるも、連絡先は極めて分かりにくい。
ログインしないといけないらしいが、そのログイン情報は
英国で使っていた番号に紐付きのショートメールに送られてくるのだ。
つまり、今の自分ではそのログインができない。
しかし、こんなこともあろうかと、私には家の近くに住んでいた
日本語の通じる友だちがいる。いざとなれば彼女に店に行ってもらおうと思うが、
ほんとうにナメた話だ。
できるだけ早期にケリをつけてやる!
そんなことを考えながら鼻息荒く一日を過ごしていたら、ミミから電話があった。
生真面目で優しい友人だ。それにどうやら、自分は英語をさほど忘れてはいない
ようで、安心した。イギリスやロンドン全体を否定するのは止めるけれども、
やっぱりVodafoneは許せん!!!
2023年1月14日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑ここ数日で読んで面白かった本。本文と関係なし
ロンドンから荷物が届いた。
ダンボールにぎっちり詰め込んだものが二箱。
12/23に送ったものが案外と早く着いて、私が不在の間に重い重いそれを
係の人が階段をのぼって届けてくれた。
さっそく荷をほどきをして、
上の方に入れた衣類を出し、全体のいくらかをクリーニングに出した。
夏の間にずっと着ていて汚れたジャケットなどがリフレッシュしてくれるのは
嬉しい。戦争の影響で日本から荷物を送ることができないと知った時は
途方に暮れたけれど、なんとかTK-MAXXXXという安く衣類を売る店で
揃えることができた。それらを着て歩きまくった日々は確かにあったのだと
思い出させてくれた。
CDも大量に出てきた。
容積と重さを軽減するため、一度ケースを外してやっと収納したが、
日本に着くなり注文しておいた大量買いのプラケースに復帰させることが
できた。ピーター・フィッシャーを筆頭に、サラ・コノリー、
ハリー・クリストファーズ、ジャッキー・ダンクワースなどが
サインやメッセージを書いてくれたもの。
お墓に持って行ったレジネルド・グッドオールのものもあって、
ここ数日はほんとうにロンドン生活があったのかどうか
半信半疑の感覚が強まっていたけれど、一気にそれぞれの時を思い出した。
また、昨年夏以来、ずっと奥歯の痛みが気になってきた。
必ずや虫歯に違いないと思ってきたが、実際に歯医者に行ってみて、
それらが決して虫歯ではないとわかった。
なんだかんだと英国生活は緊張の連続だったから、
朝起きると奥歯を噛み締めて寝ていたこともしばしばだった。
・・・という具合に、わずかに残った作業も一つ一つ味わっている。
そうだ! 文化庁に提出するはずのレポートも残っている。
これも日本での仕事が軌道に乗る前に倒してしまわなければ。
2022年12月31日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑ヒースロー空港にて。
荷物の重量オーバーや日本独自のコロナ対応への申請作業など、
不安も多かったが、無事にチェックインを済ませることができた。
今から飛行機に乗り帰国する。
1/31以来つづけてきた「2022イギリス戦記」もこれでおしまい。
読んでくれた皆さん、どうもありがとうございました。
2022年12月30日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑『オオカミだ!』仮チラシも完成。すでに走っている!
ロンドン生活も大詰め、名残惜しさに美術館と演奏会場を回った。
家での梱包作業や掃除や、私が帰国した後にダイアンが
不自由しないよう買い物をして回らなければならないので、
11か月の中で気に入ってきたものを、短時間で。
一軒目はナショナルギャラリー。
ダヴィンチもゴッホもヤン・ファン・エイクもタダで観られるこの場所で
自分が一番気に入ったのはレンブラントのこの絵だった。
作者自身、画題に興味があるというより、明らかに自分の得意技を発揮できる
一コマを日常から切り取った感じがして、気に入った。
これで、4度目。
二軒目はザ・ウォーレス・コレクション。
ここも入場無料。お金持ちによる私設の美術館だがタダ。
一番有名な絵画はフラゴナールの『ぶらんこ』だが、
正直に言って初めて生を観た時から全く感銘しない。
フラゴナールが描く人物の目はどれも瞳孔が開ききっており、
なんだか頭が悪そう。キューピーのお人形と至近距離で
向かい合っているような感覚。
何を考えているかさっぱりわからない目をしている。
私がここで気に入ったのは鎧兜のコレクション。
昔、子供の頃にガンダムシリーズに「騎士ガンダム」というのがあって、
西洋の甲冑に憧れた。が、実際に観てみると、とにかく戦いの中で
自分の体が傷つかないよう必死過ぎる。
あらゆる隙間を塞ぎにかかった結果、それはとても重そうで、
兜など、ほとんど視界を覆ってしまっているから逆に危ないのではないか。
もっとも、こんな装備を身につけるような人物は、後方で指揮を取るのみで
乱戦の場には立つことがないような気もする。
最後に通い慣れたウィグモアホール。
ここは高級そうでいてけっこう親しみやすい。
目当ての演奏家がくる時はもちろん、特に観聴きしたいものが無い時こそ
ここに来て音楽を聴いた。そうして聴いた知らない音楽家の中に、
ずいぶんユニークな人たちがいることを知ることができた。
昨日もホールに寄ることが目的だったから、知らない演奏家だった。
グリーグに『ホルベルク組曲』というのがあり、あれのピアノ版があるのを
初めて知った。ルズヴィ・ホルベアという17世紀後半から18世紀前半を
生きたノルウェーの劇作家を題材にした曲だ。
「北欧のモリエール」というのがホルベアのあだ名だった。
彼は喜劇の作家だったのだ。
音楽は颯爽として、ホルベアの疾走感が伝わってくる。
思わず胸がすき、開放的な気分になった。
イギリスの美術館は写真撮影OKだし、コンサートホールではグラスを客席に
持ち込んで飲みながら演奏を聴いて良い。そういう習慣ともお別れの日だった。
日本に帰ればそれらは禁止事項だし、またマスクを付けての生活が始まる。
けれども、やっぱり日本での仕事と生活のためにこの11ヶ月間を
過ごして来たから、試してみたいことがたくさんある。
勝手知ったる日本に帰れる。そういう開放感が強い。
やっと自分の持ち場に戻る!
2022年12月29日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑この景色はブレイクの過ごした220年前も同じだったのではないか。
昨日はFelpham(フェルパム)に行った。
ロンドンから南に2時間ほどのところにある海岸沿いの街だ。
真南に行くと有名なブライトンがある。
海沿いに西に行くと日本人が名前だけ知っているポーツマスがある。
フェルパムはその間にあるマイナーな街。
ここは詩人ウィリアム・ブレイクの関連地で行き残した最後の場所だった。
ずっと気にかかっていたが、遠出でもあるし、特段イベントもなく
いつでも行けるものだから後回しになり、ついに帰国の日が迫ってしまった。
それで、早起きして行くことにした。
生きている間は不本意な仕事しかできなかったブレイクは
生粋のロンドンっ子で、70年の生涯のほとんどをロンドンで過ごした。
けれども、あまりの困窮に3年だけロンドンを離れる。
そこで移り住んだのがフェルパムだった。
明らかな都落ちだから、きっと寒村だろうと想像していた。
けれども、実際に訪れたフェルパムは観光地で、店も多かった。
ブレイクが暮らしたのは1800-1803年だから一概に同じとは言えないが、
暖かで風光明媚なことに変わりはなかったと思う。
昨日は寒いし、雨だし、強風だったけれど、
ここが冬でなければとても過ごしやすい土地であることはすぐに分かった。
ブレイクが暮らしたコテージは博物館として保存されている。
残念ながら修繕が間に合わずに中に入ることはできなかったが、
外から眺めることができた。この場所で彼は中年の三年間を過ごしたのだ。
今までは、何か寂しげな三年を想像していたが、実際に来てみると
英気を養うような期間だったのではないか。そう思えてきた。
そのコテージの目と鼻の先にあるパブ、The Fox Innで食事した。
創業は1790年だからブレイクが越してくる10年前からここにあったわけだ。
このパブでブレイクは反動的な演説を打ち、逮捕されたという。
さらに3分ほどのところにある聖マリー教会。
誰もいない建物の周囲をウロウロしながら、たまたまやって来た男性に
声をかけると、電気を点けて中を案内してくれた上、ブレイクを記念した
ステンドグラスの場所を教えてくれた。ちゃんと隅の方にキャプションがある。
一番の収穫はビーチだった。
行きしな、小雨・強風の荒々しい海辺づたいに歩いて縁の地一帯に辿り着いた。
風が強過ぎて傘がさせない。体を前に傾けないと進めないような風。
あまりに強過ぎて、すれ違う人たみなと笑いながら挨拶を交わし合った。
ふとみると、カモメが何匹も飛び立とうとしていた。
海の方に向かって風に乗ろうとする。けれど、誰も彼もが押し戻されて
着地を余儀なくされていた。けれども、飽きることなく、もう一回、もう一回。
海辺とカモメのこと。
この景色はブレイクの頃と変わらずにあるものだろう。
これを見て、彼は励まされたかも知れないと思った。
そうしてロンドンに戻ったのかも知れない。
1803年から20年数年間、ブレイクはロンドンで足掻いた後に亡くなる。
移動時間合計5時間。滞在時間2時間半という小旅行だった。
強風すぎて傘もさせず濡れたから、帰国前に風邪をひかないようにしなければ。
2022年12月28日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note 
渡英した時、トランク一個。リュック一個。書類かばん一個で出発した。
書類かばんはわざわざ買った。なぜかというと、ロンドンではリュックを
してはいけないと聞いたから。治安の悪いロンドンでは、
背負ったリュックですら気付かぬうちに背後からの盗みに遭う。
そういう触れ込みだった。書類かばんは肩からかけると体の前にくる。
が、ここで暮らすうちに、リュックは大丈夫だとわかってきた。
都心ではいつも足早に歩いているか、催し物会場の中にいる。
あまりカフェにもパブにも行かない。それが良かったのだろう。
幸い、泥棒には遭わなかった。書類かばんを持って、
荷物が常に自分の前にくるようにしていたのは
ほんの半月ほどの間だけだった。
ともかくも、行きの時にはトランクの重さを量りさえしなかった。
春夏用の服は後で送って貰えばいいやと高を括り、
当座の衣類しか持って来なかったことも荷物を軽くした。
この計画は、渡英後に起こった戦争により挫かれることになった。
だから服を買った。それからCDを買い、少し本を買い、
何より書類が増えた。300以上観た公演に関する全ての付属資料、
当日パンフレットとかチラシとか、それらをいちいち保存してきたから、
とてつもなく重くなってしまった。
で、現在である。
先週、ダンボール二個を日本に送り出した。
24kgの荷物が二つ。制限25kgだからパンパンに詰め込んだ。
それから昨日はトランクを二つ作った。
23kg制限で二つ。
こちらでできた友だちに体重計を借りて、いちいち掴んで乗り、
自分の体重を引きながら量る。結果、一つは22.5kgで収まったが、
残る一つは8割入れたところで30kgに達した。
完璧な超過である。仕方ない。料金を払って凌ぐしかない。
それにしても、お金で全てが解決できるわけではなく、
オーバーも9kgまでが限界だそうだ。最後まで闘いは続く。
しかし、20kgくらいの荷物でやってきて、
帰りは100kgに到達してしまっているということだ。
生活は恐ろしい。帰国したのち、これらがどこに収納させるのかという
問題もある。闘いは続く。
2022年12月27日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑イギリスでは汁物にありつくのが難しかった。Deli-Xでよくこれを食べてきた
いよいよイギリスを離れる前に、何軒か店を回っている。
どれも格別に親切にしてくれたレストランと喫茶店。
まずは、イタリアンのマルチェラ。
イギリス人にはアルデンテという概念がなく、
大概のスパゲッティを食べると猛烈に後悔する。
実際、イギリスのサイゼリヤのような店でカルボナーラを頼み、
水っぽくてブヨブヨしたものを食べた時はずいぶんと
落ち込んだ。ひたすら胡椒をかけてごまかす。しかも2,000円強。
が、このマルチェラは違う。
研修先の劇場のすぐそばにあり、決して安くはないが、
クオリティが抜きん出ていた。渡英直後に初めてまともな食事をしたのが
ここだった。それから、ちょっと贅沢したいときに行き、
知り合いを招いての食事に使ってきた。最後にシェフたちに挨拶した。
それからDeli-X。
ヴァイオリニストの友人ピーター・フィッシャーとの溜まり場だが、
コメダ珈琲的に居心地が良いので、一人でよくパソコン仕事をした。
電源を繋ぐことができたからだ。夏の暑い盛りは、ここでミネストローネを
食べて凌いできた。通常は2枚のパンがいつも3枚付いてきたのは、
オーナーのダニエルさんの心づくしだった。
あとは、自炊。
イギリスでは一度も料理をしたことがなかったが、
12/25クリスマスはどの店も閉まり交通機関も停止したために、
前日に材料を買っておいて初めて料理した。最初で最後の料理。
今週は最終週だから、フィッシュ&チップスやパイ&マッシュも食べるつもりだ。
特に後者の店で食べられるウナギの煮凝り、ジェリード・イールには相当に
はまってきた。イギリス人のほとんどが忌避するそれを私は気に入ってきた。
和食屋の付き出しに出てくる魚の煮凝りのような感じで、美味いと思うのだが。
2022年12月26日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野WS『ベンガルの虎』 ↑スタンダードなベンガルトラ
第11回=最終回の『ベンガルの虎』本読みでした。
同時に、これは2022年最後のWSであり、
私がロンドンからお送りするラストの開催でもありました。
前回、月光仮面を名乗ってイキった銀次が巨大ハンコで
グリグリされかかり、追い詰められたところまでやりました。
このグリグリに対し、猛然とカンナが助けに入ります。
が、『薔薇族』というゲイ雑誌のエディターに扮した中年男=二幕の
予想屋・将軍が乱入し、敵方はますます強大になるばかり。
ここからは、70年代の唐作品ではお馴染み決闘シーンに入ります。
今回はフェンシング。基本的に終盤に決闘があるのは
唐さんが大好きなマカロニ・ウェスタンの影響ですが、
フェンシングといえばハムレット。
きっとこの世界的台本もヒントになっています。
しかも、唐さんの方が遥かにコミカルです。
さっさと追い込まれた銀次に変わりカンナが名乗りを上げて
俗物隊長と死闘を演じますが、胸元を切られたカンナが乳房を
閃かせながら立ち回りし、ゲイ設定のエディターがいたたまれずに
目を背けるところなどは、なかなかのふざけっぷりです。
ことに、町内会長たる俗物が町会メンバーから癒着感たっぷりの
声援を受けた際、カンナが俗物に放つ「だまれ、 旦那芸!」
という啖呵は、罵り言葉としてはなかなかの名ぜりふです。
そしてこの珍妙さと悪ふざけの入り混じった殺陣は、
カンナを庇いに入った水島をカンナが偶然に刺してしまうことで、
突然に収束します。
それから一旦、銀次と二人きりになるも、
今や、この世に生まれ落ちることができなかったことが明白となったカンナ、
白骨街道からこだまする死の虎の吠え声を背後にまとった彼女を、
銀次は支えることができません。
このシーン、カンナの「あたしは形が欲しいんだ。形のあるものが欲しいんだ」
というせりふも、彼女の境遇を思えば悲痛です。
水を汲みに行くと言って銀次は退場。
すると、再度、母のマサノがトドメのお迎えのように現れ、
カンナは生を渇望する死者として、リンの光すら周囲に浮かび上がらせます。
そして、いよいよカンナは行李に入る。その時、虎の吠え声も響きます。
つまり、死を司どる虎を行李になぞらえ、行李=虎に飲み込まれる
シーンが出来します。
すわ、勝負あったかというところで、銀次が再登場する。
彼は別の行李を掲げ、この自分流の行李にカンナを背負い、
生に向かう道を切り開いてみせると宣言する。
気弱な水島くんだった銀次が、いよいよ、一幕でカンナがけしかけていた
「ライオンと闘える男」に覚醒した瞬間です。
銀次の「行李に入っていろ、女っ。今度はぼくが旅をするんだ!」という
最後のせりふ、フェミニズム的には問題がありますが、劇の文脈を押さえると、
これがカンナにとって待望の、頼り甲斐のある男の宣言であることは明白です。
死の遠吠えにより迫るベンガルの虎に対峙する銀次、という構図で物語は集結。
まさに死中に活を求める銀次の旅が始まるところで物語が幕を閉じます。
『鬼滅の刃』、鬼となった禰豆子を背負う炭治郎と同じ構図ですね。
劇終盤、カンナは「虎」をめぐって銀次に2種類のオーダーをします。
(1)恐ろしい虎と闘ってほしい
(2)虎のようになって恐ろしい虎と闘ってほしい
ここで扱われる「虎」が正反対の意味だから読者やお客は混乱する。
でも、そんな風に正反対を矢継ぎ早に繰り出し、心地よい混乱を勢いを
竜巻のように生み出すのも、唐さんの才能です。
↓(1)恐ろしい虎を引っ張ってきて闘ってくれと頼む場合。「虎」は恐ろしい悪者
(2)カンナが銀次に、虎のように強くなって、恐ろしい虎と闘ってくれと頼む場合
↓この場合、「虎」は正義の味方です。
ちなみに、これはワークショップ本編では触れそびれたのですが・・・
最後まで読み切った上で、劇全体の冒頭のト書きに返ってみるとさらに愉しい。
ト書き冒頭の三行は一見すると『ビルマの竪琴』、白骨街道を示すもののように
見えて、実はカンナの渇望を暗示するものだったことがはっきり理解できます。
もう一度、冒頭を味わってください。それからカンナが登場することの意味。
白骨街道には日本人兵士の骨だけでなく、
それより以前に南洋に散った不幸な女たちの境遇、
生まれ落ちることができなかった小さな命の無念も含まれているのではないか。
実に唐さんらしい視点です。
唐さんの戦争批判を超えた根源的ないたわりの心と想像力。
弱いものへの慈しみを感じとることができます。
『ベンガルの虎』、傑作です。
次回は2023年1月8日(日)から。
19:30-21:30の時程で『秘密の花園 初演版』に入ります。
ご参加お待ちしています。
2022年12月23日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑いつもカフェで気さくに話してくれたギャビン。威圧感が微塵もない人た
昨日、12/22(木)に語学学校を卒業した。
当初は12/9(金)の卒業予定の10ヶ月コースだったが、
通い始めて2ヶ月目にはAlbanyの活動が軌道に乗り、
毎週火曜日を休まざるを得なくなった。
そこで、休む分を延長してくれたのだ。
そのようなわけで、初めの半年は週4で通っていたが、
8月に入ってからは地方遠征が増えてやや崩れた。
もう躍起になって各地を廻り、Albanyでのミーティングも増えたから
不良学生に転落していった。
極め付けは11月以降。帰国を控えて来年の企画が本格化するに従い、
英国時間の朝=日本の夕方にオンライン会議を組まざるを得なくなった。
しばらく不登校みたいになり、登校すると「久しぶり」と言われるように
なってしまった。
今週はすでにクリスマス休暇の学生も多くて、
閑散とした学校に最後の思い出として通った。
初期に自分のモチベーションをかなり高めてくれたエリザベス先生は
先週で年内の仕事がおしまいだったから、初めて食事に行った。
「スシが食べたい」と言われてグリニッジの良さげな店に行き、
ばらちらしの食べ方を伝授した。
刺身をつける醤油にわさびを溶くのは御法度だが、
ちらし寿司に限ってはそれで掻っ込む無作法こそ美徳となる。
『江戸前の旬』という週間漫画ゴラク掲載の有名なマンガにも
そういう教えを説いた回がある。そう伝えておいた。
帰りに本をプレゼントされて、帰国後の英語での読書を推奨された。
良い先生だったし、友人として付き合ってくれた。
そしてAlbany。
12/24(土)にキッズプログラムを観に行くのが私のAlbany納めだが、
昨日は最後の総括としてギャビンと話した。
スタッフの雇用形態とか、レジデントカンパニーとの関係性、
後継者問題から来年度の運営形態に至るまで、ここぞとばかりに
しつこい質問をした自分に丁寧に答えてくれた。
最後にWhatsAppを交換して、今後も連絡を取りやすくした。
貴重な時間をとってくれたのだから、
昨日のギャビンとの時間には多くの準備を費やして臨んだ。
質問事項をあらかじめ紙に書き出したり、今年に自分が観てきた
プログラムを整理した表を見せながら喋った。
Albanyのプログラムは72公演を観た。
レギュラーのキッズ・ファミリープログラム有り。
貸し館あり。もちろん2022年に注力したフェスティバルプロあり。
3月23日19:00には、2022年を総括するミーティングが行われる。
ミーティングと言っても、テレビ番組みたいな仕立てで面白い。
今年の3月に誰が誰ともわからず参加した時には、英語がまたまだ
難しくて難儀したけれど、全てを知り尽くした今度の会議は愉しめそうだ。
日本時間では、3/24 AM4:00からの開催。
久しぶりにみんなに会えるのだと思うと、喜んで起きるだろう。
折り詰めの寿司でも買っておいて、見せびらかしながら参加しよう。
2022年12月22日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑光るパペットとともに歩く4,000人強の人たち
昨夜はAlbanyのメンバー、ソフィー、メグらと連れ立って
Beckenham Place Parkに行った。
ルイシャム地区の南の方にある大きな公園だ。
発音が難しい。カタカナにするとベッケンハム・プレイス・パークとなる。
しかし、私にはどうしてもバッキンガムパレス・パークに聞こえてしまう。
打合せ初期、私はずっとバッキンガム宮殿の前の公園で
何か催しをやるのだと思い込んでいた。
同時に、一年間行ってきた地域のフェスティバルの終幕を
どうしてルイシャム外でやるのか?マークで頭がいっぱいだった。
が、チラシを見て得心した。
確かにルイシャム地区には似た発音の公園があったのだ
公園に着くととても暗かった。
こちらも日本での野外イベントの経験が多数あるが、
安全管理上、日本だったら明らかに問題がある暗さだった。
足元が見えないし、好き放題に走る子どもをすぐに見失ってしまいそうだ。
その中で、各所でリハーサルが進行していた。
合唱したり、楽器が演奏されたり。霧がかった広くて暗い公園のあちこちで
ポツリポツリと人々が動き、合唱したりしている光景は、
UFOを呼ぶ儀式のようだった。
スタート1時間前だから、まだ人の気配は薄い。
この公園でのメインコンテンツはサーカスである。
若手のフィジカルパフォーマンス系のサーカス団がテントを建て、
12月半ばから1月上旬まで興行を行う。
それを土台に、先ほど道すがら見てきたフィナーレが展開するという趣向。
まずはテントに入り、セレモニーに立ち会った。
今年一年間のフェスティバルを記念して、Albany代表のギャビンや
ルイシャムカウンシルの偉い人、代表的なクリエイターが次々と登壇し、
スピーチを行った。面白いのは、こういう場で、皆さんはポケットに手を
突っ込んで喋ったりする。これが普通なのだ。
ギャビンの紹介で、これまでやってきた数多くの、
ほんとうに数多くのイベントの映像がダイジェストされた。
その場にいた中で、自分は最も多くそれらに立ち会ったのではないか。
まるで走馬灯のようだった。それぞれの場にいた聴衆、スタッフ、クリエイターを
思い出して、各地各時間に繰り出された莫大なエネルギーの総量を思った。
ほんとうに途方もない。
イベントの中には数千人を集めて大いに熱狂したものもあった。
が、中には、荒削りなもの。チラシが完成したのはやっと10日前だったもの。
聴衆がさっぱり集まらなかったものも多数あった。
けれども、こちらのメンバーはそういったことを引きずることもなく、
とにかく乱打戦を制するように協力しあって前進してきた。
聴衆がほとんど関係者だけだった時も、限られたメンバーで
熱心に拍手して、胸を張って一つ一つのイベントを凌いだ。
ダイジェスト映像に見入っていると、
自分にはなぜか、そういう爆発しきれなかった光景の方が胸に迫った。
よく凌ぎ切ったスタッフたちへの敬意が込み上げてくる。
小一時間ほどそんな会があって外に出ると、驚いた。
その前まで閑散としていた公園に、4,000人超の聴衆が溢れていた。
自分はこの企画にはノータッチだったから、あまり内容も知らず、
本当に初見の一人として驚きながらこれに加わった。
最後のイベントは、こんな具合。
林の中から、光るパペットが生まれて、それは小学校一年の子どもの大きさくらい。
彼が別に光る球体を追いかけて、公園の歩道を進む。聴衆はその周りをゾロゾロと
ついて行く。途中、合唱や、ライトを振り回すダンスや、この地区の皆さんによる
パフォーマンスに遭遇し、コミュニケーションしていく。
ある地点までいくと、光るパペットは成長し、巨大な4メートルくらいの大きさになる。
彼は多くの人たちにハイタッチしながら、木を愛でたり、鼓笛隊と絡んだりしながら
公園中を闊歩し、やがて大きな教会の前まで来て皆に仕草で挨拶をした。
そして、その光を失い、建物の中に消えていった。
その前のテントでのセレモニーが終わった時、すでに気温は4度くらいだった。
初め、あまりに寒かったので、風邪を引かないかどうか心配だった。
このイベントは1時間くらいあると聞いていたから、かなりビビった。
けれども、始まってすぐに時が経つのを忘れた。
4,000人以上の人々を引き連れて霧深い闇の中を光る人形が先頭をゆく。
大行進だった。ルイシャムらしく、あらゆる人種の人たちがいた。
子どもも、赤ん坊も、お年寄りも、車イスの人も。犬もいた。
そういう人いきれが大移動していく光景に見惚れながら歩くうちに
あっという間に終わってしまった。寒さも感じない。
高揚して、風邪など引こうはずがない。
終着地点の教会の前で熱狂する人々を見て、
気がつくと代表のギャビンが立っていた。
普段から、こういう場所でギャビンはいつも傍観しているのみだ。
実際に手を動かしているのを見たことがない。
そして、けっこうな割合で一人ポツンと立っている。
ここに集まった人たちはそれぞれによく働き、よく楽しみ、
熱狂の中で自分を燃焼させていた。
けれども、ここにいる人たちの中で、
一番基礎になっている人物こそギャビンだった。
彼がAlbanyを背負ってからの20年以上がなければ、
このイベントも、聴衆の集まりも、すべてがないのだ。
感動して後ろから彼の写真を撮っていたら、
振り返って自分に気づいたギャビンがこちらを指さして笑った。
彼の姿を、自分は一生忘れないでいようと思う。
2022年12月20日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note 
↑小さな劇場、小さなカフェだけれど、いつも人の気が充満している
昨日はその最高潮だった
昨日は3月から参加してきたシニア向け企画
"Meet Me"のクリスマス・パーティーだった。
当初は近所のパブJOB CENTERで開催する予定だったが、
1週間前に店側からキャンセルの通達があり、
プロデューサーのソフィーはげんなりしていた。
そう。英国では店側から一旦受けた予約をキャンセルされることが
ままあるのだ。日本では考えられん。
気を取り直して、
結局はいつもの稽古場で手作り開催することにした。
Albanyにはカフェがある。
そこに調理場もあるので、カフェのスタッフたちが
ヨークシャー・プティングだとかチキンのソテー、
ベジタリアンには焼きナス、人参のグラッセ、
ブロッコリーなどの和え物、じゃがいもを焼いてくれた。
昨日の出席率は極めて高く、日ごろ休みがちなシニアも沢山来ていた。
初めは、カフェスペースで合唱する。いつもアート製作に
取り組んでいるシニアたちがメインの聴衆。
そこに、カフェを利用するお客さん、クリスマス用のキッズプログラムに
訪れていた家族連れのお客さんたちも聴く側として自然に加わる。
いくつものクリスマスソングを歌ううち、
劇場事務所からもスタッフがみんな顔を出し、合唱を応援し始めた。
要するに、劇場建物に居合わせた人たちみんなが集まり、
振り付け付きで大合唱する格好になった。
唐さんの出身である長屋の家族的雰囲気が溢れ、かなり感動的な
光景だった。
それからいつものリハーサルルームに移り、みんなで食事。
みんな帽子をかぶって、クラッカーを鳴らして、
職員もボランティアスタッフもみんなで食べた。
それから、クリスマス恒例のくじ引きがあった。
続いてシニア側の幹事からボランティアスタッフたちへの
表彰があり、その中には自分も対象として入っていた。
エンテレキーアーツのスタッフで、これから産休に入るジャスミン、
それから自分は特に手厚くしてもらった自分が、順番にスピーチした。
ジャズミンは短めだったけれど、
自分にとってこれが本当に最終最後の機会だから、
日本語で挨拶する時のように時間をとって喋らせてもらった。
これまでのことを思い起こしながら込み上げてくるものが多すぎて、
御礼を伝えるのに必死で時間が経つのを忘れた。
英語についてずっと自信無く過ごしてきて、
今も大して上達しなかったという感慨の方が強い。
けれど、10分くらい、自分が英語で喋っていることを忘れて
話せるようにはなった。
そのあとはお開きとなり、一人一人と別れを惜しみつつ、
人生の先輩たちに「アツシはワイフとチルドレンを大事にしろ」と
繰り返し繰り返し言われながら彼らを見送った。
自分が一番の基礎としてきた企画が完全に終わった。
あとは明日、CEOのギャビンと総括的な話をして研修は終わる。
その後に御礼のメッセージを方々に書いて仕込んだら、Albanyはおしまい。
やること多し。もうひと越えだ。
プロデューサーのソフィーと。見た目通り終始優しかった。↓

2022年12月20日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note 
↑雪のために道をはみ出して歩くことが難しいのに・・・
最近、なぜか映画『八甲田山』が観たくて仕方ない。
YouTubeで細切れの映像を観るのだが、やはり全体が観たい。
別にロンドンに雪が降ったからではない。
ロンドンに雪が降ったのは1週間前だが、それより遥か前、
1ヶ月半くらい前からなぜか『八甲田山』が観たいのだ。
考えてみれば、これは、すぐ隣にある危機への
シンパシーではないかと思う。英国では、通い慣れたはずの
道ですらすぐに危機が訪れる。
ストライキは起こり、予告もなしに駅は閉鎖される。
先日など、都心めがけてバスに乗ったところ、
道が混みすぎているからと運転手は一言だけ放送を入れ、
途中で勝手に進路を変えた。そして、最寄りの降ろしやすい
バス停で全員を降ろしてしまった。
看板に偽りありにも程がある。
しかし、不思議だが誰も文句を言わない。
渋滞によりバスの到着が遅れて遅刻した経験はあるけれど、
バスが引き続きの運行を放棄しての遅刻とは。
果たしてこれはよくあることなのか。さっぱりわからない。
ところで、先日はまたしても郊外に出かけた。
例によってコンサートを聴くためなのだが、
途中の道にはかなり往生させられた。
こちらはナビが2時間半での到着を予想していたところを
ビビって4時間半前に家を出た。だから最寄り駅に着くのも早すぎて、
シャトルバスが迎えに来るまでに1時間半もある。
ナビを見れば30分ちょっと歩けば良いと出ていたものだから
勇んで歩き始めた。が、あっという間に民家はなくなり、
原野みたいな光景。本当にこんなところに劇場があるのかと
思いながらも、Googleナビに従って歩道のない道を前進した。
が、道半ばでNo footwayの表示。
そんなの今さら言われても困るから、ドキドキしながら小走りに前進し、
途中ビュンビュン走る車に邪険にされながらも何とか目的地に着いた。
電灯の無い道だった。
日没したあとだったら、車は私がいると気付かずに飛ばしただろう。
陽が残っていて良かった。
あと2週間で帰国したら、何か食べながら『八甲田山』を観たい。
2022年12月16日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑ミミと一緒に聴き、終演後にSarah Connollyに挨拶に行った。
一ヶ月くらい前に発見して小躍りしたコンサートに行ってきた。
今回はお世話になってきたミミを連れて。
開場前にミミの好きなレストランに行ってご馳走になり、
こちらはチケットをプレゼントした。
Middle Temple Hallという都心にあるサロンでのコンサート。
クリスマス用の特別な会だったから、休憩時間にドリンクサービスもあり、
内容も変わっていた。
サラ・コノリーの歌だけでなく、ヴァイオリンの演奏、
ベケットやクリスマスの童話を面白おかしく語る朗読。
Temple Church付属の男声合唱、子どもたちが登場してプレゼントを
置いていく演出まであった。
初めはかなり権威的な感じがして面食らったけれど、
休憩時間を挟んで後半になると、お客さんも酔っ払って
座が砕けた感じになり、面白かった。
サラ・コノリーはいつも通り素晴らしく、
シューベルトも良かったけれど、初めて聴いたフーゴー・ヴォルフが
特に美しかった。そして、彼女は遊びでピアニストと連弾をし、
さらに弾き語りまで行った。
終演後に挨拶に行き、ピアニストとしても称えた。
私のイギリスでのボスです、とミミも紹介して楽しく話すことができた。
ホールのスタッフの一人、黒人のおじさんはかなり面白い人で、
初めて訪れた私たちを丁寧に案内してくれた。下の写真は、
「ここでシェイクスピアの『十二夜』が初めてレコーディングされた」
という記述に注目して撮影した。
ここでの上演が、映像として記録されたということか?
ちょっと分からないけれど、私のカバンにはAlbanyでお土産にもらった
『Twelfth Night』のカッコいい本がたまたま入っており、
三人で盛り上がって撮影。
ずっと一人でこんなこともしてきたと、ミミに伝えられて嬉しかった。
2022年12月15日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑ こちらでの毎日が溢れている品々
昨日は水曜日だった。
The Albanyでは毎週水曜15:00にカフェで集まりがある。
別になんの強制力もない会。おやつとコーヒーが出るので、
オフィスにいる人、その時間に余裕がある人はカフェに集まっておしゃべりする。
今年のAlbanyはあまりに忙しかったから、これは今月の頭から始めた習慣。
昨日はミミと約束があり、特に時間前に余裕を持って行くようにして、
パソコン仕事をテーブルに座ってしていた。
すると、みんな集まってきて、いつもより盛んにコーヒーを勧める。
妙に熱心だから、進行中のメールづくりを中断して輪に加わった。
いつもはもっとフリーな雰囲気だけど、
不思議に思いながらコーヒーを注いでミルクを入れようとしたら、
自分のためにちょっとしたセレモニーと贈り物の時間が始まった。
来週、忘年会があると聞いていたから、その時がお別れで
その時に挨拶しようと思っていた。だから、これは不意打ちだった。
みんなの中には、今週末で仕事を終えてクリスマス休暇に入る人もいる。
だから、昨日になったのだ。
みんなの前で挨拶をして、Albanyの素晴らしさと感謝を伝えた。
ここは建物は小さいし、煌びやかな作品をいつもやっているわけではない。
けれど、日常を大切にしている。
今日も、周辺地域の人たちが望むことをやって、
多くのクリエーターたちが間借りした事務所で新たな展望を語りあって、
いつも活気のある食堂やパブのような劇場だ。
プレゼントを開いたら、
一年間のフェスティバルの中で体験してきた全ての事業のチラシ、
一緒にした作業の合間に食べて私が「美味い!」と気に入った現地のお菓子
(スーパーで売っているやつ)
私がいつも食べてみんなにもプレゼントしていたパン屋のパン、
自分が発見してみんなに教えた近所のカフェのキャンドル、
この作家が好きと話していた英国作家のビンテージ本などが入っていた。
こういう人たちなのだ。
彼らは、日ごろ自分とした会話をよく覚えていてくれて、
その証言を持ち寄って、今日のプレゼントを仕立ててくれたのだ。
ロンドン市から受託したフェスティバルのおかげで、
今年のAlbanyスタッフがイギリス人にあるまじき忙しさだった。
折に触れ、何人かに「もっと一緒に食事したり、出かけられなくてゴメンね」
と言われてきた。
その度に私は「気にしないで。おかげで、たくさんの催しを体験できるから」
と返事してきた。
プレゼントを見て、彼らが、自分との限られた時間、
なかなか上達しない英語でのコミュニケーションの中でも、
いつもこちらに興味を持って、注意を払ってくれていたのが伝わってきた。
英国は契約社会で競争も激しい。
何人かは契約を終えて劇場を去り、何人かは契約更新の是非を巡って
これから打ち合わせに入る。すでにステップアップを決めた人もいる。
けれど殺伐とせず、上記のような配慮を忘れない。
だからこそ、常に緊張感を持って自分の腕を磨いている。
システムや制度や肩書きや役割で振る舞うのではなくて、
人間の裁量を常に重視している。
これからの目標がはっきりと見えてきた。
なぜ自分が唐さんやテント演劇が好きで、
神奈川の仕事をするようになってからも、なぜ各地を走り回って、
シニアや障害者の人たちとの企画をつくってきたのか。
その中で何を押し通そうとしてきたのか。はっきりわかってきた。
2022年12月14日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑粘土細工しながらクリスマスソングを大声で歌うシニアたち
昨日は"Meet Me"というシニア用レギュラーWSの年内最終回だった。
いつも通り合唱をし、アート製作をし、ここ一ヶ月取り組んできた
特別プログラム"陶芸WS"も行った。
初めて参加した3月から半年以上が経ち、今では全員と顔見知りになった。
ボランティアスタッフの中には新たに加わる人もいて、こちらが道具の
しまい場所を教えてあげることもある。
シニアたちが休憩時間に飲むお茶について、
それぞれの好みを把握するまでになって、
みんなも打ち解けて話してくれるようになった。
何枚もクリスマスカードをもらって、こちらの習慣を実感した。
先週に都心の劇場で行ったイベントで年内一区切りという人もいるし、
二日前に降った雪の影響で欠席する人も多かったけれど、
いつも通り歌を歌った後に、皆さんにお礼を伝えた。
その後に先生の仕切りで、来年は何が歌いたいかという話し合いが持たれ
みんなが一曲一曲大合唱していくのが面白かった。
その中には、唐さんが『少女仮面』の中で使った『悲しき天使』もあった。
来週まで集まりはあるけれど、次回はパーティーだ。
お世話係のソフィーは、予約してあったはずのパブ「ジョブセンター」が
店側からパーティーをキャンセルしてきたことにゲンナリしていて
おかしかった。いかにもイギリスらしい。
来週は早めに集まって、パーティー会場になったいつもの稽古場を飾り付け、
料理をする必要がある。その時がほんとうに最後になりそうだ。
中には90代の人もいるから、今生の別れは必至。
数多くのアーティストにも会ったけれど、
ここで出会う近所の人々との交流こそめっぽう面白かった。
みんな自信に満ちていて強気だ。明らかに生命力が強い。
英語も、彼らによって鍛えてもらった。
2022年12月13日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑この人に会って一緒に食事した
今回の11ヶ月間の研修中、先週末は明らかなハイライトだった。
前半の山場は7/28-30に行ったThree Choirs Festivalだと感じた。
今回は後半の山場。
場所はミルトン・ケインズ。
友人のピーター・フィッシャーが誘ってくれたので、
ロンドン郊外のこの新興都市にジャズのクリスマスコンサートを聴きに行った。
正直、初めは侮っていた。
地方都市の郊外にあるさほど大きくもない劇場。
自分はJazzに詳しくないので、出演メンバーが誰かもわからなかった。
行きの車の中でピーターに、「今日は何のコンサートなの?」と聴いたくらい。
彼は色々と教えてくれたけれど、知らない固有名詞が多くて
自分にはよくわからなかった。
が、始まってすぐに異変に気づいた。
聴衆は近所の人たちばかりなのだが、やたらと質が高い。
だから終わる頃には、ピーターにくっ付いて翌日もこの演奏会に
立ち会うべきだと思った。
その後、バンドのリーダーとメインの歌手に誘われて、
彼らの家で遅い夕食をご馳走になった。美術館のようなお家だ。
すると、かなり高齢の女性がその食事に加わった。
彼女の名前はCleo Laine。95歳。
メインの歌手はJacqui Dankworth。
バンマスはAlec Dankworth。
Cleoの子どもたちだった。
毎年クリスマスになると、彼らは自宅の隣にある小さな劇場で、
恒例のクリスマスコンサートを開いてきた。
始まったのは50年以上前。Cleoは旦那さんのJohnny Dankworthと一緒に
この催しを始め、現在は子どもや孫を中心に集まる仲間たちに
それが引き継がれている。それがこのコンサートだった。
夜中にロンドンに戻り、翌日は夕方までの時間に買い物をした。
CDを買って、それからジャパンセンターで良さそうな梅酒を買った。
二日目はなお自由度が増したコンサートだった。
終わってまた食事。
乾杯の時に差し入れた梅酒で「カンパイ!」と言ってくれた。
そこからまた、ピーターとロンドンに戻ったのが午前4時。
二日経つが、いまだに現実感がない。
あれは何だったんだろうか。
「来年は家族を連れてきなさい」と言われたけれど。
2022年12月 9日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note 
いつ日本に帰るのか?
そう訊かれることが増えてきたので、12月31日と答えている。
すると一様に、それじゃどこでハッピー・ニューイヤーか
分からないね、と言って笑う。
12月20日(火)と21日(水)に大きなパーティーがあるから、
大半の人たちとはそこでお別れになる。
と、思っていたら、一昨日は先制パンチを喰らった。
ずっとAlbanyのチケット売り場や入場管理係として
お世話になってきたマチルダが、任期満了で退職することになった。
たった11ヶ月の滞在でさえ、これまでに何人も同じような人たちを
送り出してきた。これがイギリス流の働き方で、だいたいが一年契約。
契約者と息が合えばそれを更新するし、他に行ってもみければ
新たにチャレンジする。そうやって次々と職場を移っていくのだ。
だからこそ、今接している人たちへの敬意と
何もかも自分の腕次第という緊張感を持って働いている
感じがする。一方で、体を壊したらどうするんだろう?とか。
産休とか育休は?とか。なかなか厳しい社会でもある。
終身雇用の方が安心して安定した力を発揮できる。
人間にはそういう側面もあると思う。
イギリスで住んでいるダイアンの家にはプリンターが無いから、
自分はいつもマチルダに添付ファイルを送って印刷してもらった。
明らかに仕事に関係ない、旅行の予約や公演チケットなどを
オーダーすると、かえって丁寧に封筒に包んでプレゼントしてくれた。
イギリス人としては異例に細やかなマチルダ。
またしても突然に切り出されて面食らったメレど、
何度も御礼を言ってマチルダとお別れすることができた。
それから、夜は都心でのコンサートを聴いた後、
強行軍でAlbany近くのライブハウスにも行った。
渡英直後、衝撃を受けた音楽表現の一つが、
このMatchStick PieHouseで聴いたSteamdownというバンドだった。
ジャンルはFolkとJazzのフュージョン。
当時は特に日本でのコロナ対策感覚が残っていたから特にたまげた。
超過密なスタンディングで皆が上着を脱ぎ捨て、
熱気でサウナ状態になりながら、毎週水曜日の定例ライブで
深夜まで盛り上がってきたのだが、いきなり年内最後だと
言われたので、行かないわけにいかなかった。
24時近くになってやっとライブが終わると、
一気に解放された出入り口から強烈な冷気が入り込んで
気持ち良かったが、片付けをしているジョージに話しかけた。
みんな、アンクル・ジョージと呼んで慕っている彼は、
ライブハウスでのギグを斡旋するプロデューサーだ。
明らかにあまり儲かりそうにない業態なのだが、
それだけにいつもミュージシャンとへの愛情と熱意に溢れていて、
ある時などは、二つの会場で別々のライブを同時進行させて
本人は自転車で30分ほどの距離を行き来していた。
Folkに関心があると伝えると、いま期待できるのは彼ら!
とすぐにオススメを教えてくれて、見知らぬ土地にある会場で
ジョージと待ち合わせたのも面白かった。
別日にこのライブハウスで行われているFolk Sessionにも彼は参加し、
自らギターを片手に即興で風刺的な歌を歌って全員を爆笑させる。
この会はアマチュアの会だから、中にはそれほど上手くない人もいる。
そういう時にみんなの私語がいきすぎると、
「音楽家と歌にリスペクトを持とう」と言ってみんなを嗜め、
歌い手を励ますのも彼だった。
「アツシはファミリーはいるか?」と訊かれて家族構成を伝えると、
「オレは奥さんに離婚されちゃったよ」と言っていた。
イギリスで出会ってきた中で、最も温かみを感じる人の一人。
忘れえぬ人だ。

2022年12月 8日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑右から、司会でヴァイオリン奏者の女の子、リーダー、リーダーがハモる時の
パートナー、自分。そういえば、誰も名前を知らない!?
ああ、お別れの始まりだなと思った。
何をすれば良いか、何が観られるのかよくわからなかった初期の頃とは違い、
今ではロンドンのさまざまな催しをキャッチできるようになった。
だから、昨日も4択あった。
いつものウィグモアホールでバロック音楽を聴く。
ロンドンの南に小一時間行ったところの地方都市にルーマニアの楽団が来ている。
ヴァージニア・ウルフの『オーランドー』が都心の劇場でかかっている。
そしてAlbany近くのライブハウスで行われるフォークソングの集まり。
悩んだけれど、4番目を選択した。
2週にいっぺん、火曜日の夜に開催されるこの会に何度参加してきただろう。
春までは欠かさず、夏場になると遠出やAlbanyの催しが重なって少し遠のく。
秋になって戻ってきたら、集まる人がずいぶん増えて、歌を楽しむより
飲み会の雰囲気が強まった。
まだ12/21にもあると思ったけれど、ひょっとしたらと思って
いつものMatchStick PieHouseに行ったら、冒頭に「今日が年内最後です」
というアナウンスがあって、やっぱり来て良かったと思った。
大人数が集まって超密度、
ホットワインの香りが充満し、揮発したアルコールに頭がクラクラしたけれど
クリスマスソングを皆が思い思いに持ち寄ったステキな会だった。
上手い人、素朴に一心に歌って味わいがある人、
騒ぎ屋の若者、いかにも腕に覚えがあるというおじさん、
色々な人がいるけれど、時間が経つと酔っ払って、一人の歌に
歌と楽器で次々に相乗りしていくインプロが始まって、
期待していた通りの面白い会になった。
この中で自分は、いつもオーガナイザーの女性が歌うのを楽しみにしてきた。
4年前にこの会を始めたという彼女は、いつも少しだけ仕切って、
あとはみんなが歌うままに任せて、でも、流れが途切れると、
自分が静かに歌い始めた。彼女が歌うとみんな静かになって聞き耳を立てる。
それだけの突出した声質と歌唱力を持っている。
正直に言うと、日に一度か二度歌う彼女の歌のために、
自分は熱心に通ってきたようなものだ。
あとは、日本では決して得ることのできない全体の雰囲気。
最後に挨拶をして、写真を撮ってもらった。
例えイギリスに来たとしても、今後この会への参加は至難だろう。
ひとつひとつ行うお別れがついに始まってしまったと思わずにいられなかった。
↓この空気感はまさしくここだけのもの。
2022年12月 7日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑この作業中に強烈に思い出してしまった。
ロンドンでの滞在も残り3週間ちょっとになった。
正直、今は日本に帰る日が待ち遠しい。
何しろ、この慢性的な肩こり、奥歯の痛み、夜の部屋の寒さが
一気に解決するのだ。そう思って、残りの期間は我慢して過ごす。
せっかくいるのだから、
劇場でこちらの人たちと可能な限り熱くやりとりし、
少しでも多くのものを観聴できるよう予定を入れている。
人間は無いものねだりである。
帰国後、数日も経てばまたロンドンに帰りたいと思うに違いないとも思う。
だから、できるだけ後悔しないように。
食べ物の高価なのにはいい加減にくたびれた。
旅先に行けば、もっぱらタイ、ベトナム、韓国、インド料理が希望となる。
暮らし慣れた近所では馴染みの安心できる店があるが、
初めての土地は暗中模索である。
高いお金を出してハズレに当たると侘しい気持ちになる上、
悔しさまでが込み上げてくる。だから、ハズレの少ない上記4カ国が
生命線なのだ。
カーディフでも、夕暮れ後の寒空の下を2kmちょっと歩いてタイ料理屋
に行った。グリーンカレーを注文して、やはり間違いがない。
Albany近辺ではもっぱらベトナム料理。
三軒も良店があるので強いて日本食が無くてもオレはぜんぜん大丈夫!
そう思っていた。
が、昨日、自分がそこそこ飢えていることに気づかされた。
ロンドンに戻り、Albanyでの陶芸ワークショップをやっていたところ、
粘土をテーブルに押し付けて棒状にのばす作業をしながら、
つい日本蕎麦のことを思い出してしまったのだ。
私が蕎麦を本気で食べたいときには秦野市に行く。
野外劇『実朝出帆』に挑みながら発見した名店の数々が
あの街にはたくさんある。店周辺の景色の美しさも含め
都会ではちょっと勝ち目の無いクオリティだ。
もちろん横浜市内、自宅の近所にだってよく行くお店がある。
ああ、今年は年越しそばが食べられないのだな、と思ったりして。
昨日のワークショップでは、ファシリテーターが提供する
匂いにインスパイアされて形を造形する内容だったから、
例えばシナモンの匂いをかいだりした。
すると何故か、これまで大して好きでもなかった八ツ橋が
思い出されるのである。自分でも不思議だが、
シナモンの匂いは自分にとって決してアップルパイなどでなく、
あの「おたべ」のことだったのだ。
あまり自覚してこなかったが、無意識にこたえているらしい。
先日、実家の姉からLINEが来た。
「日本に帰ってきたらみんなでステーキを食べに行こう!」
という明るい誘いだった。・・・大変ありがたい呼びかけだが、
なぜステーキなのか!?
姉だって、学生時代にイギリスとタスマニア島で暮らした。
彼女は同じように感じなかったのだろうか。
特に長く滞在したタスマニアでは、牡蠣をはじめとした魚介が格安で
豊富で、恵まれていたのかも知れない。
姉ながら、どこか日本離れした不思議な感覚を持っている人だ。
↓一個700円以上する赤いきつねを、果たして誰が買うのだろうか?
2022年12月 5日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑Srangwyn Hall
迎賓館のようなホールだった。公演だけでなくパーティーもやるらしい
日曜と月曜の二日間、ウェールズに行ってきた。
実は、英国が4つの国からなることを知ったのは数年前のことだ。
今回の研修を意識するようになるまで、自分にはイギリスと英国と
グレートブリテンとイングランドとUKの違いがよく分からなかった。
さすがに研修の試験を受ける時には多くの人から教わって知識が入り、
実際にロンドンに来てからその感覚が掴めるようになった。
これまでロンドンを拠点とし、イングランドの様々な地域に行った。
スコットランドは3回。ウェールズとアイルランドは一度も行ったこと無し。
だから、というわけではないけれど、ウェールズに行った。
先週にオックスフォードで観たウェールズ国立歌劇場。
本当は本拠地カーディフで観たかったけれど、
気づけば年内の地元開催予定が終了していたので、
ソフトとハードをバラバラにしてコンプリートした。
実際にその出来は今年観てきたオペラの中でもNo.1の面白さで、
もっと早めに追いかけ始めれば良かったと思う。
カーディフの劇場では、すでに慣れ親しんだThe Sixteenの合唱を聴いて
指揮のハリー・クリストファーズさんとロビーでお話することもできた。
それから月曜にはさらに先のスワンジーという街に行った。
この街にあるBrangwyn Hallという空間で、1981年にウェールズ国立歌劇場が
『トリスタンとイゾルデ』を録音した。これは私の特別なお気に入りで、
だから当地を訪ねてみたかったのだ。
事前の申し入れが効いて、
催し物が無いこの日に特別に入れてもらうことができた。
技術スタッフのキースさんという人が丁寧に案内してくれて、写真も撮ってくれた。
一番感激したのは、私がノートパソコンから当の音楽をかけていたところ、
音響システムにPCを繋げてくれたのだ。
キースさんの心配りには心の底から感激した↑
20世紀前半にこのホールをデザインした美術家の立派なカタログまで
お土産に持たせてくれた
指揮者レジネルド・グッドオールの伝記によれば、
1981年11月末に、この音楽はここで録音された。
大ボリュームでホールいっぱいに鳴り響く、音楽の里帰りだった。
現地に行って、なぜここが選ばれたのか事情がよく分かった。
カーディフから電車で1時間。すぐそばに海が広がるこの建物の駐車場は広い。
ホール自体も、時には結婚式などの催しに使われるものだから、
備え付けの客席ではなく、録音作業向きなのだ。
広い客席部分にテーブルや椅子を並べ、
100人を超す演奏家とキャストが録音に挑み、時にくつろいだのだと思う。
録音技師たちは、この平場にたくさんの機材をひろげたことだろう。
その中心には確かに80歳の小柄なグッドオールがいて、
采配を振るったに違いない。
すぐそばに海を臨むホール。
遥かこの海の向こうには、物語の舞台であるコーンウォールが広がっている。
2022年12月 2日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑寒空の下で屋外プロジェクション。スタッフが手分けして誘導
猫は9つの命を持ち、女は9匹の猫を飼っている。
前半は古代エジプトから伝わる言葉。
後半は17世紀イギリスの神学者トマス・フラーが付け足した。
・・・なかなかの名言だ。
猫の心はかくも気まぐれであり、
女性の心はさらに輪をかけて移ろいやすい。
昨日の晩、Catford=キャットフォードに行った。
アーケードの入り口に巨大な猫の像を持つこの街は
ルイシャム区の中心地であり、ここには市庁舎やタウンホールがある。
街の中心にある通りでパブリックプロジェクションが始まった。
初日をお祝いして、大きなパブでセレモニーも開かれた。
作品は、大気汚染を訴えるものだった。
人間の体内にいかに汚染された空気が入り込み、
時間をかけて堆積しながら人々を蝕んでいっているのかという映像。
ルイシャム・カウンシルのある庁舎から窓越しに映像を打ち込み、
向かいにある壁面に投射した。ここは南北と東西に進むバスが行き交う
交通の要所だから、両建物の間にはひっきりなしの車通り。
そのモクモクとした排気ガスを貫く仕掛けだった。
ロンドン市、ルイシャム区、Albanyの面々、
プロデューサー陣、アーティストたち。彼らを囲むロンドンのマスコミ。
日没後の気温は7度。1時間くらいスピーチやインタビュー、写真撮影が
行われた。
↓右側がパブ Ninth Life
その後、近くにあるパブ、その名も"Ninth Life"のパーティールームを
貸切にしてセレモニー。スピーチが連続する会はこちらでは珍しいが、
何人かの偉い人が「長かったフェスティバルもあと1ヶ月。これからの
未来につなげて行こう」と語って、自分に日本を思い出させた。
それにしても、"Ninth Life"。9番目の命。
さすがキャットフォードのネコ像の向かいにある名物パブのネーミングだ。
Albanyのスタッフたちもこの店は初めての人が多く、
何人かとユニークな店名の話になって、私は冒頭の格言を披露した。
「それには続きがあって、女性は・・・」
みんな一様に笑っていたけれど、
それを私が知ったのが、10代の頃に見たテレビ番組
『恋のから騒ぎ』だったとは伝えようもない。
あの頃はバブル経済の香りがまだ残っていた。
新團十郎さんの奥さんと義理のお姉さんも、あの番組から出てきたのだ。
よく考えたら、番組タイトル自体もシェイクスピアの影響。
知的な番組だったのだと今にして思う。
2022年12月 1日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note 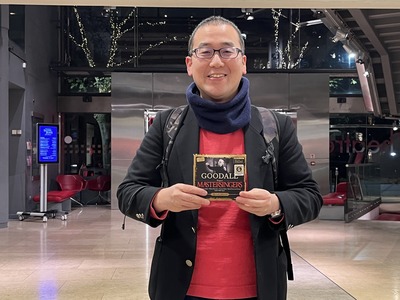
テムズ川の北は観光客用の繁華街や高級住宅地が多い。
Aegel駅の周辺もその一つだ。
お洒落な服屋やカバン屋、カフェが並び、
行くたびに青山・表参道を思い出す。
246のような大通りこそないけれど、
Aegel駅の周囲にあるお店の雰囲気はまさしくそんな感じだ。
文化的にも、
ここにはアルメイダという有名な中規模の劇場と
人形劇専門の小屋がある。そしてなんと言っても、
サドラーズ・ウェルズ劇場。
ダンスで有名な劇場だ。
クラシックからコンテンポラリーまで、
様々なダンスカンパニーがここにやってきて公演する。
日本で一緒に仕事をしてきた安藤洋子さんも、
フランクフルトバレエやザ・フォーサイス・カンパニーで
よくここに立ったらしい。
実際に私もここでフォーサイスやピナ・バウシェ作品を観た。
そしてまた、野田さんの『Q』英国公演もここで観た。
昨日はマシュー・ボーンの『Sleeping Beuty』を観た。
初日ということもあり、集まっているお客さんたちも
洗練されたファッションの人たちが多くて、
とりわけ華やかな感じがした。
この劇場は、今回の研修の候補地の一つだった。
2017年にさいたまゴールド祭で紹介された劇場が
自分の研修先選びに大きく影響している。
サドラーズ・ウェルズ劇場はシニアたちのダンス表現にも
熱心に取り組んでいるから、候補の一つにあがったのだ。
が、なんだか自分には不釣り合いな気がした。
青山・表参道的な洗練、
コンテンポラリーにアーティスティックな様子が柄じゃないように思い、
今のAlbanyにたどり着いた。ワイルドなDeptfordは上野・浅草的で
妙に馴染む。自分は唐十郎門下なのだ。
一方、この劇場には特別な思い入れがある。
サドラーズ・ウェルズは今でこそダンスの劇場だけれど、
300年以上の歴史を持ち、ダンスに特化し始めたのは20世紀に
入ってからのこと。
かつては演劇やオペラも盛んだったこの劇場で
1945年にはブリテン『ピーター・グライムズ』初演と
1968年には『ニュルンベルクのマイスタージンガー』公演が行われた。
指揮は敬愛するレジネルド・グッドオール。
彼にとってそれらは、キャリアを決定づけるエポックな公演だった。
晩年を除いていつも不遇が付きまとったグッドオールにとって
1945年は初めて脚光を浴びた公演。
それから数年で長い低迷に入った彼が復活したのが1968年の公演だった。
特に後者はライブの様子がCDになっている。
最初こそおぼつかないものの、幕が進むごとに威力を増して、
最後は宇宙的に異様な盛り上がりを見せる。
実にグッドオールらしい演奏。
大手書店フォイルズでディスクを買うことができたので、
会場前の早めの時間に行って、受付の人に写真を撮ってもらった。
この音楽は確かに、54年前にここで演奏されたのだ。
2022年11月30日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note 
毎週火曜日は恒例WSの日と決まっている。
午後から合唱の練習があった。
もうすぐクリスマス、だから12/8(木)には
都心のオールド・ヴィック座で行われるイベントに参加する。
そこで歌うために、特別に近所の小学生たちと練習。
AlbanyのあるDeptfordは移民の街だ。
アフリカ、中東、アジア・・・、まんべんなくいる。
小学生たちは95%が黒人。これが可愛い。
そして、彼らのウォーミングアップが面白かった。
国歌を歌おうという合唱指導の先生の合図で、
彼らはイギリスでなく、南アフリカ共和国の国歌を歌った。
アフリカ系でない子もいるだろうけれども、今日は南アフリカ、
そういう感じだった。
こちらのシニアメンバーの中にはアフリカ系の人もいるから、
彼らも自然に歌い始めた。それでアフリカ出身なんだと自分が
理解できた人もいた。カリブ出身も多いから、肌の色だけでは
自分には判断がつかない。
こんな風に、いくつもの出身国が当たり前に入り乱れているのが面白い。
日本にも在日の人がいて、沖縄や北海道が独自の出身地であると
誇りにしている人もいると思うが、私は日本人という人との
数の多寡がはっきりしているために、だいぶ違う。
一方で、人間みな同じだなと思うのは、先生に対する反応だった。
昨日、いつも指導に当たっているレイチェルさんがお休みだった。
一昨日の晩、彼女は自分のバンドと一緒にライブがあったのだ。
半年以上お世話になってきたレイチェル先生だし、
どんなライブハウスでどんな風に歌うか興味があって駆けつけた。
ぜんぜん別人のレイチェル。
という風に完全燃焼した翌日だからレイチェルは休んだわけだが、
代わりを務める若手の先生も大したものだった、
が、シニアメンバーの何人かは納得しないのである。
レイチェルじゃないとダメ・・・という雰囲気を漂わせて身が入らない。
こういうところは人類普遍だと思って可笑しかった。
レイチェル先生だって曖昧な指示を出したり間違えたりするが、
皆は不満に思いもしない、が、若手がやると文句が出るのだ。
・・・という具合に来週に向けて準備をしている。
オールド・ヴィック座のステージ裏に入れるのは愉しみだ。
劇を観にいったことはあるけど、裏に入るのは初めて。
高校時代、初めて手に取ったシェイクスピアの文庫本は、
新潮から出ている福田恒存訳『リチャード三世』だった。
表紙を開くと、そこには本場イギリスのロバート・ヘルプマンが
主人公を演じている写真があって、さらに「オールド・ヴィック座」
と書かれていた。今はあまりシェイクスピアなどやっていなさそうだし、
改修もされているだろうが、それでも同じ建物だ。
何か雰囲気を探ることは出来るだろう。
地震のない国の良さがここにある。
2022年11月29日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note 
↑日本ではしない替え玉。これで340円くらい
ロンドンでは、クロワッサンが一個400円する。
サンドイッチ一個とミネラルウォーターで1,000円。
だから毎日が真剣だ。
が、物価の高いロンドンにあっていくつか安いと思うものがある。
ハム、チーズ、アイスクリーム、ショーのチケット。
最後のは特に助かっている。今回の滞在はこれが目的なので。
昨日、さらに安いものを発見した。花だ。
今まで数度買い。昨日もスーパーで買って確信した。
ちょっとしたスーパーにけっこう豪華な花束がいつも置いてあって、
それらがさほど高くない。こちらの人にとって身近だからか。
そもそも花束にするような花はいずれも西欧からやってきたのが
理由か。日本で3,000円くらいしそうな薔薇の花束が、
こちらで2,500円くらい。物価の差を加味すれば半分くらいの値段。
それを持って、昨日はウィリアム・ブレイクの墓に誕生祝いに行き、
Albanyでお世話になってきた合唱のレイチェル先生のライブに行った。
こういう時、パッと花をプレゼントすることも、
自分は唐さんから教わった。人の芝居を観に行くときに、
物語に関係がある花を考えて、唐さんはよく買っていた。
が、ハム、チーズ、アイスクリーム、チケット、花、
これらは例外である。他のものは押し並べて高い。
特に高いと感じるのが日本食だ。
よく「日本食を食べたくなるでしょう?」と訊かれるが
値段を見れば到底納得できないから「いいえ」と答える。
それに、何度か経験して失敗の連続でここまで来たのだ。
親子丼、カツ丼、すし、うどん、
どれもチャレンジして強烈な違和感だけが後味として残った。
そこに、先日は一昨日は味噌ラーメンが加わった。
コンサートを聴いた帰り、いつもの通りを一本入ったところに
日本食の店を発見し、驚いた。こんな身近なところに、
しかも、閉店時間の早いロンドンなのに22:30まで営業。
それで、なんだか日本を思い出した。
何かを観て、少し食べて帰る。あれがやってみたくなった。
それで、一杯2,000円する一番安い味噌ラーメンを頼んだのである。
酷かった。ただひたすら酷かった。
スープもひどいが麺がさらにひどい。明らかに小分けにする用の
ザルでしかも茹ですぎているために(英国人はアルデンテを理解しない)、
ニチャニチャと固まった半分ダンゴのような麺が沈んでいた。
歯触りが悪すぎる。向こうから吸い付き、こちらが絡め取られる
ような食感だった。
一晩経ってもあまりにあの口の中のニチャニチャとした感覚、
おの記憶がひどいので今日は一風堂に立ち寄った。
ここは値段を除けば日本とそう変わらない。
多くの人はスープが薄いとかいうけれど自分はそう感じない。
むしろ、温度がぬるいことの方が気になる。雑なのである。
・・・という具合にトラウマを更新しないではいられなかった。
あんなに好きだった麺類そのものを嫌いさせるほどの迫力だったが、
克服して現在に至る。おかげで出費は倍。
2022年11月28日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野WS『ベンガルの虎』 ↑再びアサヒグラフより。バングラデシュで日本刀を振り回し、たくさんの行李が
押し寄せるこの劇を、現地の人たちはどう観たのだろうか?
二幕も中盤を過ぎて後半に差し掛かり、
村岡伊平治やカンナの母・マサノが入り乱れるシーンをやりました。
時間も空間もワープする。そう言われる唐作品に真骨頂です。
が、ただ単に幻想文学、ファンタジーでないところに唐作品の面白さがあります。
俗物隊長が村岡伊平治を演じていた、というオチをちゃんとつける。
唐さん流のリアリズム。
この俗物隊長=村岡伊平治を初演で演じたのは大久保鷹さんです。
その二年前には『吸血姫』で大陸浪人・川島浪速に扮し、
袴姿で日本刀を振り回した鷹さん、
唐さんの中にその成功体験があったことは間違いありません。
ストーリーに入ります。
伊平治がヒロイン・水嶋カンナの出自の謎に迫る。
母・マサノは、東京→下関→長崎?→バッタンバンに連れてこられたラシャメン。
マサノが現地にいるカンナ族の青年と駆け落ちする。
海に飛び込んで逃げようとするが、青年は死に、マサノも虫の息。
その時に産み落とされたのがカンナ。
伊平治はマサノの遺体を行李に詰めて日本に送った。
行李はバッタンバン→長崎→東京入谷町三丁目の実家に届いたが、
マサノの母がそれを東京→長崎→バッタンバンへと送り返した。
伊平治の説明の中で、カンナの出自が揺らぎます。
東京入谷町に生まれ育ったと言っていたカンナでしたが、
マサノの行李に一緒に入って東京に到着し、そこでお婆ちゃん(マサノの母)に
引き取られて育った、という風に説明しなおす。
伊平治も気付かぬうちに、生まれたての赤ん坊がどうやって行李に入れたか、
船旅をどのように生き抜いたか、これが謎です。
そしてこの謎はかなり重要です。
唐十郎作品だから何でもアリなのだ、となってしまうと、
かえってこの不思議さを見落とすことになります。
カンナは出自だけでなく、生存自体が危うい。
カンナが生きているのか死んでいるのか分からない。
それどころか、実在するのかも分からない。
そういう疑いが鮮明になるシーンです。
そしてここに、『ベンガルの虎』の中心がある。
当初はカンナに味方し、物語を追いかけてきた読者・観客が裏切られ、
揺さぶられる大事なシーンです。推理小説でいうところの
語り手が犯人という構造にも思える。
マサノの登場がそれに追い打ちをかけます。
(このマサノこそファンタジーです。実在しないものが甦って語り出す)
彼女は東京から身売りされてきた過去を語りながら
伊平治に駆け落ちを詫び、もう一度、ラシャメンとして置いてくれと訴えます。
村岡が
「マサノは死んでいる。しかも迷惑なことにカンナも来ている」と言い放つと、
娘を大人しくさせるから二人で置いてくれと頼むマサノ。
マサノのあまりの気味の悪さに、伊平治は部下に命じて彼女を退出させ、
行李の中に立てこもったカンナを始末しようとします。
すると、領事がやってきて、水をさす。
一転、彼に頭が上がらない伊平治とのコミカルな場面に突入します。
領事は「女郎屋なんてやってちゃいかん」と説教する。
この領事は、ミシン売りの中年男=予想屋の将軍を演じてきた
唐さんの役です。「おれは女房にかどわかされっぱなし」というせりふも
楽屋オチで大いにウケたはずです。
笑いの場面を挟むことで、緩急がついた物語はさらに吸引力を増します。
東京からラシャメンの骨("象牙"と隠語で呼ばれる)を詰めて叩き返された
行李が、数限りなく南洋に押し寄せる。
伊平治は悪夢的な現状を打破するため、
すべての行李を日本刀で刺し、始末してゆく。
そして最後に残った行李を串刺しにしようとすると、
ビルマ僧に扮していた銀次が正体をあらわし、カンナを救おうとする。
銀次を振り払って行李を刺し貫く伊平治。が、最後の行李の中身も、骨・・・・
次回、カンナがラシャメン姿で登場するところから二幕の終わり、
三幕の冒頭までをやります。
2022年11月25日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑入口はここですよ、分かりにくいから迷わないように。
,そう言って先方は写真まで撮って送ってくれた。10日したらここを訪ねる
今週から来週頭にかけて日本との会議が目白押しだ。
時差が9時間あるから必然的にロンドンの早朝になる。
それぞれに準備が必要だから、夜中まで詰めの作業をして、
寝て、起き抜けにミーティングする。
おかげでシャワーを浴びるのが遅く、ダイアンに文句ばかり言われている。
不眠気味な彼女は、こちらがゴソゴソとやっているのが気になるのだ。
彼女はキッパリ物を言うタチだから、翌朝に必ず刺される。
その度に誠心誠意謝るが、その夜に改善されたりさねなかったりする。
これを繰り返して、さほど嫌な感じなく過ごしている。
やり取りがあることが大切で、後に引かない。
もう一つ。
最近、夜中にハマっているのが、ウェールズ行きの計画を練ること。
来月の予定を見、他にも行き残した場所をカウントしながら
ホテルの値段をチェックする。週末は高い。
日曜から月曜にかけての一泊が安い。
何が観たいとか、どこの劇場に行きたいとか、
希望が絡むから条件は複雑になるが、これだ!というコースを発見した。
12/4(日)
11:00 本読みWSが終わる。
11:35 グリニッジから地下鉄でパディントン駅へ。
12:38 パディントン発の国鉄でカーディフ中央駅へ。
14:33 カーディフに着き、歩いて10分のホールへ。
15:00 St David's Hallで合唱団The Sixteenを聴く
17:00 ホテルにチェックイン
その後、気が向けばカーディフ・ミレニアムセンターでダンスを観る。
以前はこんな風に接続が上手くいくのかビクビクしていたが、
イギリスの交通事情にも慣れ、主要駅での乗り換えも迷わなくなってきたから
大丈夫であろう。まあ、ミスったらミスったで、コンサートが途中からに
なっても仕方ない。で、翌日が大事である。
12/5(月)
9:00 カーディフ中央駅を出発してSwansea駅を目指す
10:02 Swansea駅に到着し
11:00 Brangwyn Hall に行く
あとは一度カーディフに電車で戻りつつ、高速バスで適当に帰る。
イギリスの電車は往復で切符を買うと格段に安くなるので、
一度カーディフに戻った方が安くて速いのだ。
この Brangwyn Hall はかなり重要。
好きなCD、Sir Reginald Goodall指揮 Wales National Operaの
『トリスタンとイゾルデ』は、1980年にここで録音されたのだ。
通常だったら催し物をやっていないこの日は中に入れないが、
思い切ってメールで問い合わせて事情を説明したところ、
わざわざ日本人が来るのだからと、係の人が親切な返事をくれて
中に入れることになった。
こうなると俄然、ウェールズ贔屓である。
聞けば、今回のワールドカップにはイングランドだけでなくウェールズも
参戦しており、11/29にはご近所の両者が激突するらしいのだ。
唐作品を信奉する自分としては、常に弱いものの味方にならざるを得ない。
こんなに優しいウェールズ人の気質を思えば、なんとか勝って欲しいものだ。
2022年11月24日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑Deli-X。荒くれたデプトフォードにあって、店内だけは治安が良さそう
一昨日は興奮して寝つけなかった。
10月末を以って最後だと思っていたDame Sarah Connollyのリサイタルが
新たに開催されるらしいのだ。最近になって組まれた企画なのか、これまで
まったく告知されていなかったのに、しれっとホームページに載っていた。
朝を待ってダイアンに確認し、彼女も行くというので2枚分を押さえた。
料金ごとにエリアが違う指定と自由が半々のシステムだから、
あとは買ったエリアの中でなるべく前列を押さえるため、
開場時間前に殺到するのみだ。
ダイアンは脚が悪いので引っ張っていく格好になるだろうが、
Dame Sarahの凄みを知らしめねばならない。
以前から、ダイアンはDame Sarahの写真を見て冷やかしてばかりいた。
「彼女はほんとうは男なのではないか」そんなことばっかり。
しかし、最近になって彼女の友達(ロイヤル・オペラで働いている)から、
Dame Sarahがいかにホンモノかを聴いたらしい。
それで俄然、興味を持ち始めたのだ。きっと驚くであろう。
・・・という具合にハイに夜明かしし、早朝から『オオカミだ!』の
ミーティングに突入した。zoomごしに、時には実演もまじえる会議。
半分、稽古みたいなものだ。普通の演劇をつくるのとは勝手が違い、
実際の稽古期間は短い。その分、事前の準備に成否がかかっている。
2時間半これをやり、Albanyへ。
劇場メインプロデューサーチームとカウンシルメンバーの会議。
今年推し進めてきたフェスティバルもいよいよフィナーレの12月を控え、
皆の疲労の蓄積が如実に感じられる会議だった。
やっとここまできた。来月どうしよう。
そして、来年以降にこれをどう結びつけよう。・・・やれやれ。
そういう雰囲気で、これまでの企画を振り返るだけでお腹いっぱいの
自分たちに、さらに鞭をくれるための会議だった。
こちらとしては「Well done」としか言いようがなかった。
働き者のイギリス人たち!
その後は散会になり、こちらはDeli-Xに移動して日本の仕事をした。
明日も朝7時から会議だから、準備しなければならない。
こんな風に何時間もいられて、電源も使えて、値段も高くないカフェは
ロンドンでは珍しい。紹介してくれたピーターのおかげである。
資料を作ったあと、グローブ座に『ヘンリー5世』を観に行ったが、
これは面白くなかった。
2022年11月23日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑手づくりの器。粘土製
昨日深夜、『下町ホフマン』の打込みが終わった。
289ページ。ここまできたら300ページいっちまえよ!!! とも思ったが、
2回の休憩時間を含むと3時間45分コースである。
あと10分ちょっとでも、延びない方が良い。
ちなみに『腰巻おぼろ 妖鯨篇』は311ページだから、間違いなく4時間越え。
すごいぜ!唐さん!
こんな作業をし、昨日書いたような荷物整理をしながら、
日常を見つめ直している。思えば、ここ2ヶ月は移動の連続だったし、
観劇だって、あと40日間で31本観ることはさほど難しくない。
それよりも、最後の1か月である12月をより良く過ごすために、
ここで足元をかためようと思ったのだ。
Albanyで積み上げてきた日常的なWSへの参加を
もう一度初心にかえって眺め回そうと思って、時間に余裕を持って到着し、
スタッフや参加者との会話もよくするように心がけている。
昨日は朝に合唱、昼から粘土細工という内容だった。
合唱は近所の小学生たちと合同。
12月にはクリスマスのイベントとして、都心にあるオールド・ヴィック劇場
という由緒あるホールでの合唱があるから、これのために顔合わせと
初回の練習を行った。土地柄、黒人の子どもたちが9割で、みんなアクティブで
可愛い。自己紹介の堂々としたこと。押しだしも立派なもの。
↑庭の花を摘んで盛る
午後は、粘土を使った器づくり。
手で捻ってカップのかたちをつくり、そこに、それぞれ劇場の庭に生えている
植物を摘んで飾りつける、という趣旨だった。が、あっという間にこのルールは
崩壊し、勝手な彫刻作品をつくり始めたのが面白かった。
↓彫刻作品化しはじめる
12月に出かけたい土地はまだある。
ウェールズに行きたい、ケルト文明に触れたい、ロンドンならではの舞台が観たい、
そういうのももちろん大事だが、こんな風に日常から異界が開く瞬間を
見逃してはならないであろう。
↓リアルキノコ・オン・キノコ
2022年11月22日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑こんな風に置かれて雨に濡れていたので、反射的に家の中に引っ張り込んだ
昨日は家にいた。語学学校を休みにし、Albanyでの予定は無い。
夜に何かを観に行くのもやめにし、徹底して家にいて身辺を整理し始めた。
何しろ11月下旬だ。月日の過ぎるのは早いもの。
日本への荷物の郵送を先延ばしにしてきたが、
いよいよ本格的にこの問題に向き合い始めた。
こちらでできた日本人の友だちに聞いたら、
クロネコヤマトのロンドン支店に頼るのが一番簡単らしい。
もっと安価に済む方法もありそうだが、やり取りが円滑で、
安全に破壊されずに荷物が日本に着いて、保証も効く。
だから、ヤマト!
で、発送する荷物を判然とさせるために、まずはトランクを買いに行く。
こちらにはトランクひとつで来たが、文化庁に問い合わせたところ、
私の場合は、23キロのトランクを二つ運べるらしい。
船便は最大3か月かかるし基本的に高価だから、
自分で運べるものなら自分で運びたい。
そこで、安いトランクを求めていつものルイシャム・ショッピングセンターへ。
が、夏場はあれだけ見かけたトランクはすっかり鳴りをひそめていた。
隅っこに少しあるくらい。どうせすぐ手に入るだろうとタカを括っていたが、
どうやらあれは季節ものだったらしいのだ。
仕方なく都心に行こうかと思ってセンターを出たら、
ワイルドな露天で良い感じのを売っていた。しかも安い。
本来3万円以上するやつが7,000円くらい。バッタもんかも知れないが、
とにかくロンドンから日本まで一便だけ運ぶことができたなら、
それだけで得なのだ。それだけ保ってくれたならバッタもんだって構わない。
それを運んで家に帰り、荷物の総量を見定め、
捨てていくもの、最後まで必要だから必ずトランクで持ち帰るもの、
12月の買い物や頂き物のためにとっておくべきトランクの隙間を想定し、
郵送するものを割り出した。そして、郵送物の量に見合ったダンボールを
ヤマトに注文。こういう場合は単なる語学留学生となり、学割適応を目指す。
というわけで、家にいたと言っても周辺はウロウロした。
ダイアンに頼まれた日用品の買い物もあったから、
別方向のスーパーに行って帰り、ショッピングセンターに行って帰り、した。
ダイアンは医者に行くと言って早朝から不在だったが、
1回目の買い物を終えて帰ってみると、ドア前にまあまあ大きな段ボールがあり、
雨のためにこれが濡れている。てっきり家電でも買ったのかと思い、
急いで大切にキッチンに運び込んだ。
すると、2度目の買い物後に家に着くなり、ダイアンが激怒している。
先に帰宅した彼女が台所で発見したそれは、近所の家に届くはずの
冷凍ドッグフードだったらしい。
すぐに運送会社に電話し、配達員を呼びつけたところ、
彼は「家の中には入れないから、ドアまで持ってきて欲しい」と言い、
ダイアンは「こんな重いもん運べるか!」と問答になり、
配達員は帰ってしまったという。
本気で怒っていたダイアンには悪いが、爆笑した。
ペットがいないこの家に、巨大な冷凍ドッグフードが届いたのが面白かったのだ。
ロンドンのずさんさが極まっている。
結局、新たに呼び出した配達員に私が渡すことになった。
それにしてもデカいドッグフードだった。近所でよく見かけるデカい犬の
いずれかが、あれを貪るのだろうか。
2022年11月21日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野WS『ベンガルの虎』 ↑秋元松代さんの劇『村岡伊平治伝』だけでなく、
伊平治本人が書いた『村岡伊平治自伝』を押さえておきたいところ
昨日は日曜恒例の台本読みWS。
2幕のなかばにさしかかり、いよいよ面白い場面に。
先週に引き続き、お市とカンナの掛け合い。
ここは全体からすれば息抜きにあたるかなりコミカルな場面ですが
その中で、見逃してはならない細部が二つ。
一つは、ミシン売りの中年男=競輪の予想屋「将軍」というキャラクター。
競輪における究極の予想は勝者が確定した後でその車券を買うことだと
力説する彼は、1幕に引き続き空回っています。
初演時に唐さんが演じたことを思えば笑いの連続だったと理解できますが、
それにしても、引っ掻き回すだけ引っ掻き回す無意味なキャラクターです。
一体それは何故なのか。今後のカンナの出自をめぐるやり取りに、
このミシン売り=予想屋を読み解くヒントもあると思います。
二つ目に銀次の弱腰。
カンナは何度も銀次に「お尻をさわっちゃダメ」と注意します。
しかしこれは、銀次がお尻を触っているわけではないのです。
よく読めば、何か事が起こるたび、例えば怖そうな人が登場したり、
事件が起こるたびごとにこの問答が繰り返されているのがわかります。
つまり、銀次はお尻を触っているのではなく、ビビってカンナの後ろに隠れて
いるのです。これは、男としてデビューしたいと願う彼のキャラクターづくりに
とても重要な要素です。それだけ弱気であるという基本設定を理解する
必要があります。
ストーリーは進み、競輪選手としての水島があらわれます。
カンナを袖にした一幕とは打って変わり、
彼は強烈にカンナを自分の奥さん扱いし、銀次の名を呼ぶことに嫉妬さえ
します。いつの間にかお市は水島の母になっており、カンナはお嫁さんで、
お市がお姑さんという関係になっている。この関係をカンナに迫る唐さんの
強引さが見事なところです。
そして、水島からカンナに、改めて行李が贈られる。
しかし、バッタンバンの象牙と思われた中身は、実は人骨でした。
驚くカンナと人骨を残して、日蝕による闇が訪れます。
そこに、村岡伊平治や井上馨らしき銀行員など、明治の人物たちが
なだれ込んできます。多くの日本人女性がいわゆる「からゆきさん」
「ラシャメン」として東南アジアに渡った明治と昭和の戦後が同時に
語られ、劇が加速度的に勢いを増します。
そして、カンナの出自が語られる。
ラシャメンの一人にマサノという女がいたこと。
マサノが現地のカンナ族の青年と駆け落ちし、心中を図ったこと。
その表紙に生まれ落ちたのがカンナであること。
カンナはマサノの遺体とともに行李に詰められ、長崎へ船で、
そこからは列車で東京入谷のマサノの実家に送られたこと。
さらに、マサノの母は赤ん坊のカンナだけを引き取り、
マサノの死体を長崎から東南アジアに送り返した・・・・
この出自の部分はかなり駆け足になってしまったのと、
全編にとってあまりにも重要なので、来週は復習するところから再開します。
村岡伊平治が実際に活躍したのはマニラやシンガポールですが、
それをバングラデシュと結びつけるために、唐さんがわざと東南アジア一帯を
あいまいに、混同して書いているのも面白いところです。
ハリウッド映画で、中国・朝鮮・日本の人々が混同して描かれるように
それぞれの国の人たちは違和感を感じるでしょうが、ここは思い切って
押し切ります。それが面白さを生む!
次回は11/27(日)。
二幕後半に差し掛かり、唐さんの筆はますます調子を上げます!
2022年11月18日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑大里先生は極度のシャイだったから、こうして極端な守銭奴を演じなければ
忘年会の参加費用を徴収ができなかった。会では、大里先生のギター伴奏で
唐さんが歌を歌ったことも。
昨日、11/17は大里俊晴先生の命日だった。亡くなって13年も経つ。
亡くなったのは、室井先生を中心にスタートした7大学連携サテライトスクール
「北仲スクール」のオープニングパーティーの日だった。
朝のうちに東中野の葬儀場に行き、司会をしたような記憶がある。
その後は急いで馬車道に戻って、宴会の支度をした。
おつまみを並べ、大量のウィンナーを茹でて、お客さんに配った。
アサヒビールの横浜支社がいつも手厚く協賛してくれて、
飲み物も潤沢だった。お客さんが歓談に入ったところで、
奥の台所に引っ込み、身内でやれやれと話したのを覚えている。
やはりスクール運営の中心メンバーの一人だった梅本洋一先生が
台所を覗いて、「ほんとうはパーティーしている場合じゃないんだけどな」
と呟いたのを覚えている。その梅本先生亡くなってしまった。
大学一年生の時から、一番親しく接してくれた先生が大里さんだった。
年長者ぶったところも、権威ぶったところも無くて、
「はいはい、オレはダメ人間ですよ」という物腰でいつもこちらを
安心させてくれていた。それが、大里先生の正義感だったと思うし、
"正義"なんて言葉を嫌がる、ほんとうの正義漢だった。
大里先生の研究を多少なりとも理解できるようになったのは
むしろ亡くなった後で、そういう不躾な自分でも、多くを識る大里先生は
こちらの興味に合わせて大らかに接してくれた。
荷物の片付けや、引っ越しなんかも手伝った。
レポート採点時期になると東京まで帰るのが面倒な先生は研究室に
泊まってしまっていたから、その作業を邪魔するかのように遊びに行った。
先生はベジタリアンだったから、
大学近くのコンビニまで歩き、梅のおにぎりやあんまんを買って、
帰りに歩きながらそれらを食べて夕食を終了させていた。
それが、引っ越しを手伝った時には、西荻窪前の食堂で
野菜てんぷら定食をご馳走になったことがある。
持ち前の高潔さから美食を遠ざけていた大里さんが振る舞ってくれた、
先生の豪華料理だった。美味かったな、あれ。
大里ゼミのこととか、先生の好きなゲストを呼んでやった特別講義とか、
先生が学課の宴会の幹事をしていたこととか、新宿駅南口に買った
ペントハウス「オフィス・オオサト」のこととか、書いていたら際限なく
吹き出してきて仕方がない・・・・・。このくらいにしておきます。
2022年11月17日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑DJクリスが皆から募った曲をかけて踊らせまくっている
Albanyで"Tea Dance"があった。
前回、6月に参加したときはこれがイベント名だと思い込んで、
普通名詞であると知ったのはその後のことだった。
"Tea Dance(ティー・ダンス)"。
もともとは、イギリスの田舎で夏から秋にかけてガーデン・パーティーを開き、
踊ったり、軽食とともにお茶の飲んだのが始まりらしい。
時間は午後のお昼過ぎと決まっていて、だから、夜に開かれる場合は
"Tea Dance"とは呼ばない。"Dansant(ダンサン)"とも言う。
Albanyでは、レジデントカンパニーの代表格である
Entelechy Artsが主催して半年に一度、これを開く。
前回は劇場が他の大事業に忙殺されていて使えないために
他の文化施設に流れざるを得なかったが、私にとって二度目にして最後の
参加となる今回は、ホームグラウンドであるAlbanyのホールでの実施に
立ち会うことができた。
楕円形の劇場構造を利用し周囲にイスとテーブルが設られ、
マスコット的な存在であるクリスの司会とDJにより会は進む。
合唱、ダンス、詩の朗読、ソロの歌の披露など盛りだくさんで、
会を進行させながら、ホールの端の方では即興的なペインティングも
繰り広げられた。今回はスコーンは無かったが、前回と同じく
ケーキ、お茶、コーヒーの消費量が半端なく、皆でやりたい放題している
感じだった。
この会の始まりから20年、ずっと参加してきたシニアが
自らの思い出を語る切々としたスピーチがあった後、
サイモン&ガーファンクルの『ブックエンド』が合唱され、
それぞれの大切な人のドローイングを持ちながらダンスが踊られた。
続く青年が、友人のアコーディオン伴奏により朗々と
"Over The Rainbow"を歌い上げて周囲は感動に包まれた。
こういう時のクリスの反応は鋭く、司会のトーンを囁くような語りかけに
切り替える。そして、割れんばかりの拍手が起こった後は、
まさかのビヨンセ。結局、ビヨンセは最強で、老若男女、障害の有無を
超越した熱狂を生んで場は閉じられた。
イギリス人にとって、クラブカルチャーと、スピーチやポエトリーが
根付いていることがこの会の成功理由だと思う。
同じ仕立てを日本に移したところでお互いに恥ずかしがるだけだと
想像できるが、私たちにだって、餅つきや節分、盆踊りというイベントが
あるわけだから、ああいうものを劇場が援用すれば難しくなくできると思う。
季節感や年中行事が希薄になっていく中で、だからこそ劇場の役割が
出せるのではないかと思う。
終わった後にスタッフ会議があって意見を求められたので、
「日本には季節の変わり目に豆を投げるイベントがある」と伝えたら全員に
爆笑された。それだけで相当に意味不明だったらしいので、恵方巻き情報を
かぶせるのはやめた。彼らが節分の風景を見たら、どう思うのだろうか。
季節の変わり目に"魔"がやってくるのは同じと思うが、
こちらではハロウィーンに家々を訪ねる子どもたち=精霊たちにお菓子をあげる。
いきなり豆をぶつけて追い出す日本より、寛容だとも思える。
2022年11月16日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note 
↑スターリング大学内。劇場や図書館を含むセンター周辺の明かりを
見つけてホッとした。郊外なので、寮に住んでいる学生か劇場への観客
の他、人気はあまりない。
先週末はグラスゴーに行ってきた。
幸い天気がよく、北方にも関わらず気温もロンドンと変わらなかった。
スコットランド国立劇場の公演を観て事務局を訪ねるための
短い旅行だったけれど、この地域が持つ質実剛健さに
触れることができた。
特に初日の土曜は面白く、
グラスゴー中央駅で降りてホテルにチェックインしたらすぐに駅に戻り、
さらに北に30分強行ったところにあるStirlingまで行った。
バスも使えたけれど、初めて訪れる場所は地形もチェックしたい。
そこから小一時間歩いて目当ての公演会場を目指した。
劇場は山の上の大学の中にあった。
劇場を含むアートセンターが堂々とスターリング大学の中にあって、
一般のお客さんも自分の街の文化施設として気兼ねなく利用していた。
公演は、まるで大河ドラマだった。
シェイクスピアの歴史劇にも似て、スコットランド史に輝く英雄に
想を得ながら、現代人のセンスと美学で描いていた。
啓蒙とエンターテイメントが上手く融合した舞台で、
この地方の気質も反映してか、言葉がシンプルに書かれていたので、
自分にもよく理解できた。
現代の服装で現れた役者たちが衣裳を着て時代劇を演じ始める構造を
わざと見せるところなど、山﨑正和さんの『実朝出帆』をやった時の
ことを思い出した。
終演は22時過ぎで、向こう1時間来ないバスを待つのもかったるくなり、
結局、往復ともに駅まで歩いた。道はさらに暗く、歩道の無い箇所も
あったけれど轢かれないよう気をつけながら歩いて、
スムーズに辿り着くことができた。
日付が変わる頃にはグラスゴーのホテルに辿り着いた。
それにしても、あの坂を登る感じ。
敷地の境界が曖昧でどこからでも入れそうなセキュリティのユルさ。
電灯の少なさからくる夜の暗さ。どこもかしこも横浜国大みたいだった。
↓劇場ロビーのポスターの前で

その後にグラスゴーをウロウロして分かったが、この地域は実によく
街の景観に大学が溶け込んでいる。グラスゴー大学、市立大学、
そういったものを見かけだが、それぞれに美術館やコンサートホール、
カフェ、庭を持っており、これが周辺住民や観光客にも開かれていた。
学校が賑わっていて、留学生も多かった。日本人は見かけなかったけれど、
中国や韓国から来ている人が多くて、彼らのニーズに応える料理屋が
充実していた。久々にキムチチゲを、しかも安く食べることができた。
↓グラスゴー大学内の美術館

2022年11月15日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑プライベートでは賭け事をしない(と思う)唐さんだが、
私たちも親しくしている望月六郎監督のこの映画に出演している。
『新・極道記者 逃げ馬伝説』。唐十郎フリークの人はぜひ見て欲しい。
前回の唐ゼミ☆本読みWSを読んでくれたHさんから投稿が寄せられた。
それによると、競輪場の車券売り場のシステムについて、
唐さんは正しかったらしいのである。
『ベンガルの虎』2幕に出てくる「2-3」窓口。
つまり、2番と3番に一着二着を賭けるための車券売り場窓口が
固定されているのはおかしいのではないか、という私の意見は、
当時の実際を知る人によると完全に間違っていたらしいのだ。
正しくは、数字の組み合わせによって窓口は固定されていたらしい。
そうすると、本命ガチガチの窓口には長蛇の列ができ、
およそ勝ちそうにない大穴の窓口は閑散とすることになる。
「そういうことなんですか?」とHさんに伺ったところ、「その通り」との
回答が寄せられた。
そういうわけで、唐さんは完全に正しかったのだ。
Hさんのおかげでまたひとつ勉強になったし、次回の本読みWSで
修正しなければ!
考えてみれば、コンピューター管理される前の風習は、
後の時代を生きる者からしたら想像を絶して手間がかかっていたのだ。
『黒いチューリップ』に出てきたパチンコ屋の玉出しシステムもそうだし、
かつては芝居のチケットを買うために、わざわざ劇団事務所を訪ねる
必要があったのだ。
『ベンガルの虎』に話を戻すと、これはなかなかイマジネーションが
膨らむ話である。要するに、それぞれの売り場窓口には個性があって良い
ということなのだ。町内の全ての赤ん坊を取り出した産婆にして、
伝説の車券売り場窓口員である「お市」のいる2−3番。
こういうのは舞台美術を考える際の個性の持たせ方に直結する。
またしても良い話を聞いた。Hさんに感謝。
そして、唐さん、ごめんなさい!
2022年11月11日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note 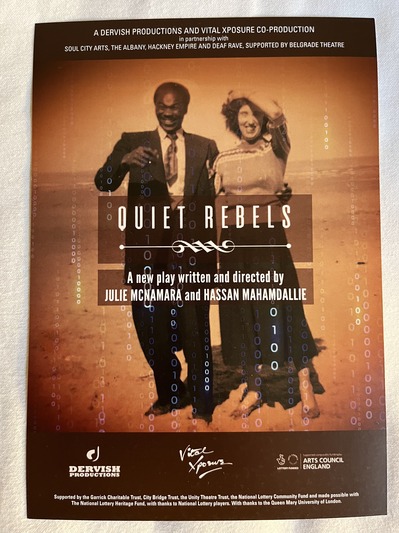
水曜日にAlbanyで公演を観た。"QUIET REBELS"というタイトル。
映像とシンプルなステージング、4人だけの出演者による舞台だったが、
若い人たちの熱気と関心が場内に溢れ、満員だった。
これは、実話に基づいた物語だ。
労働者階級に生まれた白人女性が、移民としてカリブからやってきた
黒人男性と恋愛し、結婚をした。結果的に彼女に対し、
白人社会からのものすごい圧力や嫌がらせが寄せられることになる。
それらを、実際の当事者たちのインタビューと、俳優による演技と
虚実の両方から進行させてゆくステージだった。
今年、このような闘争を描いた様々なイベントに参加してきた。
NEW CROSS FIREについて Linton Kwasi Johnsonが語るレクチャー。
カリブからの移民第一世代が往時を回顧するWINDRUSH PEONEERS。
ルイシャム・ショッピングセンター周辺で繰り広げられた
人種差別闘争の様子を収めたドキュメンタリー映画上映会。
シニア企画に参加するアフリカやカリブから渡ってきた人たち。
ここ半年を総動員して、目の前の劇を観た。
初見では捉えきれなかった言葉のやり取りについて行きたくて
今日は二度目をこれから観る。
現在、目の前でやり取りされている平穏な日常が、
どれだけの闘争の果てに成し遂げられたものか実感できる。
ダイバーシティとか多様性とかいうけれど、日本とは土台の
複雑さが違う。平和そうに見える周辺地域に底流するものを
またひとつ感じることができた。。

日本では、カプカプひかりヶ丘×新井英夫WSが
ズーラシアの近所にある実際のカプカプで本格的にスタートした。
ロンドン時間のAM1:00〜AM9:00の長尺だが、
皆さん次から次へと押し寄せる予定に、
慌ただしく活動していると聞いた。
新井さんのコンディションがちょっと心配されたが、
ふたを開けてみれば、休憩時間も惜しんで受講の皆さんに
話し続けていたらしい。新井さんによる魂の講座だし、
カプカプの利用者さんたちが全員で講師をしていることも
今回のウリだ。引き続き正対、ストレートな運営をしていこう。
次回のB日程初回は12/23。
2022年11月10日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note 昨日、友人の川口成彦くんとロンドンで落ち合った。
常にアンティークの楽器や音楽家関連の場所を見て回っている
彼にくっついて、クレメンティ・ハウスに行ってきた。
多くのピアニストを育て、作曲し、ピアノ製造まで行った
ムツィオ・クレメンティの暮らした家である。
川口くんは、彼が東京芸大院生の頃に知り合った。
唐さんの母校である入谷の坂本小学校でやなぎみわさんが書いてくれた
『パノラマ』を公演した時、相談役だった焼き鳥たけうちさんの
マスターから川口くんを紹介されtのだ。
彼はイベントに参加して書生姿に扮し、エレピを弾いてくれた。
その後、椎野と自分が結婚した時、椎野のリクエストに応えて
ショパンの『英雄ポロネーズ』を弾いてくれた。
この時も焼き鳥屋備え付けのエレピによる演奏だった。
その後、彼はアムステルダム音楽院に留学してこれを卒業すると、
ブリュージュのコンクールで2位になり、
第1回ショパン・ピリオドコンクールでも2位に輝いた。
それから一気に有名になって、現在に至る。
これから国際的キャリアを築いていこう、
という時期にパンデミックになってしまったので、
彼は日本での時間を増やして、多くの国内需要に応え続けてきた。
けれど、その間もアムステルダムの住居も維持して
アフターコロナに備えてきたそうだ。
ロンドンであれば、ウィグモアホールに登場するクラスの人だと思う。
前に川口くんのシューベルト即興曲や連弾曲を聴いたけれど、
その後に彼を凌ぐ演奏に出会ったことがない。
実力はあるのだから、あとは巡り合わせだと思う。
彼の発案で、ノッティングヒル近くにあるクレメンティ家を訪ねた。
これが面白かった。ネットには開場時間や入場料などが書いてある。
けれど、そこは本当に単なる家で、現役で暮らしている一家の長らしき、
おじいさんが案内をしてくれた。
一応、居間にはクレメンティ社で造られたスクエア・ピアノが
置いてあったが、鳴らない鍵盤もあるなど、ケアは全くされていない。
「ここにはメンデルスゾーンも来たこともあるんだよ」
おじいさんはそんなガイドを少しばかりしてくれたが、
「クレメンティの肖像画などはないのでしょうか?」という質問には、
「ここにあるのはうちの家族の写真か絵ばかり、クレメンティの肖像は
グーグルを検索しなさい」という大胆な答えが返ってきた。
「この家のどこを見ても良い」と言われて階段を登ったが、
どこもかしこもおじいさんの家族が暮らす現役の居室で、
ある部屋を覗くと、中でお孫さんの青年がくつろいでおり、
なんだか申し訳ないような気になった。
「わたしはこの家で生まれ暮らしてきた」
おじいさんはそう言い、特に親族関係も無いらしい。
こじんまりとしたギャラリーやミュージアムを想像していた私たちは
顔を見合わせて笑い、この方がよほど面白いと言い合った。
その後は近くにある中古CD屋で希少盤を漁り、日本食屋に行った。
川口くんをヴィクトリア駅に送りながら満員電車にも乗ったので
まるで東京で会ったみたいだったが、クレメンティ・ハウスだけは
圧倒的に外国だった。
夜行バスでアムステルダムに戻ったら、数日後は現地の音大生相手に
英語でマスタークラスをやるらしい。さすがだ、川口くん!
2022年11月 9日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑写真を撮るためにいつも買っていたスーパーに行った。
現在は見ただけでちょっと気持ち悪くなる。
ここ最近、体調が悪かった。
2週間くらい前に風邪をひき、そこからズルズルと忙しくなり、
書類づくりやWSの準備に追われた。
日本とイギリスを同時進行させると、時差の厳しさを痛感する。
こちらが朝起きてメールをチェックすると、日本はすでに夕方近い。
早く返事を出そうと焦っているとロンドンでの予定が迫ってくる。
イギリスで参加しなければならないプロジェクトも多数あるし、
夜は夜で何かを観に出かけたい。そのまま突入したコーンウォールへの
旅はバスばかりだったから、ずっと乗り物酔いみたいで苦しかった。
復調してきたので、こうして書いている。
何が原因だったかと考えてみると、
どうもキットカットばかり食べていたせいではないかと思う。
あれは食べ応えがあって、持ち運びができて、しかも安い。
英国の料理はマズいマズいとよく言われるが、そんなことはない。
たしかにゴワゴワのフィッシュ&チップスとか、ぞんざいな仕立ての
ものは多いが、美味しいものもちゃんとある。
しかし、決定的に不満で苦しいのは、それが高価なことだ。
庶民の味、フィッシュ&チップスやパイ&マッシュを食べると
簡単に2,000円を越えるのだ。
当地の人たちはちょっとしたカフェでサンドイッチが800円することに
不満を覚えないだろうが、こちらは日本の飲食店の味と値段を
知ってしまっている。だから、抵抗感が湧き上がってくるのだ。
結果、よくキットカットを食べた。
大型スーパーで大量に売っているのを買い込んでおいて、
お腹が空いた時にチビチビ食べていた。
すると、なんだか食べるたびに胃がムカムカするようになったけれど、
味はあの通り美味しいから、さらに食べるという生活が続いた。
今では、あれが体調不良の原因だったと睨んでいる。
さすがに懲りて、少しお金を使ってでもパン屋のパンを
食べるようにしたら、気持ち悪い感覚が無くなり、風邪も治った。
車酔いみたいな感覚が払拭されるまで、もうちょっと。
作業も峠を越えたので、気分も心持ちも楽になってきた。
さすがにキットカットはしばらく見たくない。
来年に予定している公演の現場で、ケータリングとして出されたと
したら、また手が伸びてしまいそうだけど。
2022年11月 8日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑ペンザンス唯一の目的地はここ。崖に造られたミナック・シアター
先週末はコーンウォールを訪ねた。イングランド南西部の巨大な田舎だ。
数箇所の目的地があったが、ほとんどを移動で過ごした。
しかも、電車は少なく、大方がバス。
睡眠不足や不規則な食事にならざるをえず、車酔いばかりしていた。
どこも隘路だし、運転がものすごく荒いので、
どうしても船酔いみたいになってしまったのだ。
初日に訪ねたティンタジェル城までは天気も良かったが、
あとは雨・雨・雨だったから、二日目は最低限の目的地だけに絞って、
あとはホテルで寝た。値段は安いけれど気持ちの良いホテルだったのは
ラッキーだった。
細かなトラブルを挙げればキリがない。
ロンドンからの夜行バスではドラッグ中毒の女性が騒ぎケンカが起きた。
コーンウォールに着いてみたら、バス会社の一つがストライキを
行っており、電光掲示されたバスが全く来ないというフェイントを
食らった。電車に乗ろうと駅に行ったら、電車が動かなくなったので
この高速バスに乗れと指示されて、危うく時間内に目的地に
着かないのではないかとヤキモキさせられた。
レストランの定員が計算ミスをして多く支払わされそうにもなった。
他にも細かいのがたくさん。
帰りはプリマスに寄り、友人ピーター・フィッシャーの車に乗って
ロンドンに戻る予定だったが、彼の車が壊れたために電車で戻って
くることになった。
これには驚かない。
最近、彼の車に乗るたびにアヤシイ音をたてていたからだ。
去年、4年ちょっと乗った愛車ラフェスタを廃車にせざるを
得なかった自分なので、その予感は充分にしており、
どう思うかピーターに訊かれたので、彼には辛い見立てを
正直に告げた。
けれど、実際に壊れるまで乗り続けてしまうのが人間だ。
だからいつもアクシデントになり、急な対応の連続になってしまう。
けれど、もうちょっと、もうちょっとと引っ張ってしまうのだ。
幸い、ピーター車はロンドンで壊れた。
これがプリマスに来る途上だったら大変だった。
田舎道からの移動は過酷を極め、彼の演奏に影響したと思う。
色々なことがあり、忙しなかった。
どの目的地もさすがにインパクトがあったが、
なぜかペンザンスでした昼寝がいちばん印象深い。
昼寝ができたなんて、何年ぶりだろう。
調子に乗って動き回り過ぎ、ボロボロで帰国すると
年明けの仕事に影響するだろうから、加減しなければいけないとも
思い始めた。目下、観劇数は255本。300いけるかどうか微妙だ。
2022年11月 4日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑6月にオープンした新路線エリザベス・ライン
Bond Street(ボンドストリート)駅が10/23に遅れてオープンしたが、
表示は以前のまま。車内の×印が修正されるにはまだ時間がかかるらしい。
日本がせせこましいのか、英国がルーズなのか。
イギリスの住環境は悪くなる一方である。
私が過ごしてきたごく短い期間だけでも、近所のパン屋は二度にわたる
値上げを決行した。初め500円くらいだったソーセージパンが、
いつしか600円になり、昨日から660円になった。
マジか!?
EU脱退、コロナ・パンデミック、ロシアVSウクライナの戦争と、
インフレの要因が畳みかけている。
そして、日本に比べて恐ろしく低いホスピタリティ。
今日もドラッグストアに買い物に行ったのだが、
緩慢な動きでレジを打ち始めたスタッフは何度も何度も入力を失敗し、
3分以上が経過したところで無理と見て同僚を呼んだ。
誰もレジに並んでいたわけではないのに、
歯ブラシひとつ買うのに5分以上かかった。
このように、英国生活はトラップだらけだ。
テンポよく移動と要件をこなしていこうと思っても、
いたるところで細かなブレーキがかかる。
レジ待ちが何人並んでいようと、いま会計しているお客と店員が
談笑したりしている。後ろのお客がたまりかねて文句を言うと、
不満そうに増援を呼ぶベルを叩いて助けを呼ぶが、その助けが
ぜんぜんやってこない、という光景もざらだ。
EUを離脱したことによって、多くの外国人労働者がイギリスを去ったそうだ。
特にポーランドから来ていた人たちは優秀で、かつ人件費が安かったらしい。
例えば高級車用の手洗い洗車サービスについて、彼らが去った後は
かなり粗雑なクオリティで車が返却されるようになったそうだ。
しかも、もともと3,000円程度だった料金は10,000円近くにまで高騰。
イギリス人の人件費はかくも高く、顧客にとっては良いことがないそうだ。
他方、英語をマスターした人々が大挙して帰国したポーランドの景気は
右肩上がりだそうだ。一国の判断が、そんな風に周囲の国々に影響するのも
流動性の高いヨーロッパならでは。
私は大学生時代、深夜のコンビニでアルバイトしていた。
牛乳を並べていてお客がレジに立とうものなら、カウンターに走って
戻ったものだ。ここにきて、「お・も・て・な・し」を改めてアピールしていた
理由がわかってきた。駅員も店員も、誰も彼もが仏頂面で、
スマホに釘付けな姿もよく目にする。
電車もバスも簡単に遅れる。
今まさに旅行が始まったばかりのタイミングでこれを書いた。
けっこうタイトなスケジュールを組まざるを得なかったが、
ちゃんと移動できるだろうか。駅員や各所の職員が優しいと良いのだけれど・・・
2022年11月 3日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note 
↑The London Oratory
昨日はいつもと曜日をずらして劇団や座友メンバーとの
『ベンガルの虎』本読みをやった。2幕の終わり。
いつもながら唐さんが書く3幕ものの2幕終盤は素晴らしい。
こちらがいちいち考え、理解するのを寄せ付けない勢いに満ちていた。
気持ちよく、せりふのやり取りや物語の進行に振り切られた感じだ。
直に体がうずく。
ブルース・リーの名ぜりふに"Don't think, feel."というのがある。
"考えるな、感じろ"。昔からの唐さんやアングラ・ファンの中には
こういう味わい方をしている人がたくさんいる。
けれども、遅れてきた世代である私にとって、
唐さんの作品はやっぱり考えながら読むものだと思う。
荒唐無稽に見える設定やせりふの中に唐さん流のリアリズムがある。
そうでなくては、どうやってせりふを言い、セットをつくり、
物語をつむぐのか。やる側はThinkせよ、と思ってやっている。
けれども、やっぱり唐さんの魅力の究極は、
理性ではなくて、感覚による納得でねじ伏せていく
いわく言い難い、けれども誰もが体感的に納得してしまう
吸引力や腕力だと思う。
それを存分に味わうために、私たちは分かるところは分かっておこう。
そういう考えでやっている。
そういえば、前に『トリック』という大ヒットドラマがあって、
あれも似た話だった。主人公はマジシャン、
次々と登場する霊能力者のトリックを暴きながら物語は進行する。
けれど、それは霊能力者がニセモノと言いたいために
やっているわけではない。むしろ逆。
本物の霊能力者に出会うためにこそ、
トリックを見破ること=理屈でニセモノを選り分けているのだ。
すべては、ホンモノの不思議に出会うために。
真の摩訶不思議に圧倒され、打ちのめされたい。
そういう思いで台本を読んでいる。
私たち作り手にはお客さんという存在がいるが、
まず自分たちが圧倒されて、今度はそれをお客さんにおすそ分けする。
そういう相手であると思っている。
昨日、『ベンガルの虎』二幕には気持ち良くやられた!清々しい。
イギリスでは、ここ数日は教会の催しばかりに行っている。
土曜日はオックスフォードにある大学の中のチャペルと
福音史家ヨハネ教会。
月曜にはロチェスターの大聖堂。
火曜には都心のテンプル教会。
昨日はサウスケンジントンにあるロンドン・オラトリーという
カトリックの教会、という具合。
どこも特別な内装と音響だったが、
とりわけロチェスターとオラトリーは素晴らしかった。
今日、木曜の深夜から旅に出る。
風光明媚だけれど交通の便はすこぶる悪いコーンウォールを攻める。
伝説ではアーサー王が住み、
トリスタントイゾルデの舞台ともなったティンタジェル城、
岬の野外劇場ミナックシアター。そしてプリマスの教会にも行く。
この教会ではピーターのアンサンブルによる演奏会が行われるのだ。
合い間に『下町ホフマン』研究と来年度公演の企画書づくり、
『オオカミだ!』とカプカプ×新井一座WSの準備もする。
体はイギリスの僻地、頭は日本のことを考えて過ごす週末になる。
2022年11月 2日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note 
↑終演後のクリスティは喜色満面。足元に覗くソックスの赤が眩しい
唐組が終わった後も唐さん関連の公演が続く。
流山児事務所が『ベンガルの虎』の稽古に入っているとのこと。
自分が観られないのは無念だが、コロナに捕まることなく
最後まで駆け抜けて欲しい。
それから、状況劇場の終わりから唐組初期の唐さんを支えた
俳優・菅田俊さんが率いる東京倶楽部の『ジャガーの眼』公演もある。
菅田さんはずいぶん以前に『ふたりの女』も手掛けられていた。
今回は、宣伝のためかYouTubeで1980年代半ばの唐さんについて
菅田さんがエピソードを披露されている。これが面白い!
https://www.youtube.com/watch?v=QF9aL3X3GxM
この時代は唐さんにとって困難な時期であり、
表に出てくる情報は少なかった。だから菅田さんのお話は貴重だ。
皆さんもぜひ観てください。これまで知られていなかった当時の
様子だけでなく、強面に見える菅田さんの純真さにも打たれる。
こちらも観にいけないのが悔しい!
誰か観に行って、どんな風だったかを教えてください!
ところで、今日のゼミログのタイトルは、
別に流山児さんや菅田さんが助平だというのではない。
(二人とも色っぽいが)
目下、研究中の『下町ホフマン』に"平手"というキャラクターが
出てくる。三度笠をかぶり、侠客めいた格好だから、
おそらく講談の『天保水滸伝』に出てくる強者、
平手造酒(ひらて みき)からとられた名前だと思うが、
この男が自分は助平だと連呼するのだ。
強いと言われれば弱く、弱いと言われればあべこべに異常な強さを
発揮するところが面白い。そして、オレは助平だと訴える。
ああ、これは大久保さんに宛てて書かれたのだなと
当時の配役表を見なくてもすぐにわかる。
鷹さんも色っぽい人だが、あの雰囲気で「オレは助平だ!」と
叫んで回っていたら、舞台は湧いただろう。
英国で観た助平なパフォーマーとといえば、
第一に、フランスから来ていたウィリアム・クリスティという
指揮者&チェンバロ奏者が思い浮かぶ。
演奏もそうだし、全身黒ずくめにも関わらず
足元にチラチラと覗くソックスだけは真っ赤、
ああいうところが実に助平ったらしい。
あれは彼のトレードマークで、この間に聴きに行った
演奏会では、最前列のフリークらしき客も真似して
赤いソックスを履いていたのが目立った。
あんたも好きねえ、という感じ。
カーテンコールの時など、女性奏者の腰に手を回して
褒め称えるやり方など、露骨に助平があわられている。
堂に入ったものだ。
もう一人の助平は、ザ・シックスティーンという合唱団を
率いるハリー・クリストファーズ。
一昨日の夜も彼のライブを聴きに行ったのだが、
これは希代の助平野郎だと思わずにいられなかった。
彼がクリスティと異なるのは、
一間するとひどく真面目そうなところだ。
だが、聴くべきを聴き、見るべきを見れば
彼が心底ムッツリだということがすぐにわかってしまう。
だいたい、一昨日のプログラムは環境破壊を強く訴えたもの
だったが、実際のパフォーマンスを聴けば、
それが崩壊の美を謳っていることは明らかだ。
会場はロチェスターというロンドン近郊の古い街にある
大聖堂。そこで、ルネッサンスからバロックまでの曲を順に歌い、
また同じ曲をたどりながら元の時代に戻っていくという趣向。
いわば自然の円環を表現していたわけだが、
映像作家が作ったプロジェクションと合わせて考えるに、
人類など滅びてしまえば良いと言わんばかりの美感に
溢れていて、何度も聴いてきた彼らの演奏の中でもベストの
パフォーマンスだった。
終演後に話しかけて「あなたは実に危険な巨匠ですね」と
伝えたらニヤニヤ笑っていた。あれは、真剣に環境問題に
拳を振り上げる人の態度ではない。
誰も彼もが快楽主義者だと思わずにはいられない。
そういう助平な人たちを、私は好む。
↓ハリー・クリストファーズ。真面目そうに見えてエロの塊
2022年11月 1日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑この日もDame Sarah Connollyはいつにも増して男前ないでたち
圧倒的なゴッドねえちゃん感だった
一昨日未明にサマータイムが終わった。あれはなかなか不思議な体験だ。
最近、かつてのテレビ番組『驚きももの木20世紀』にハマっている。
その日も夜中までこれを見ていたのだが、AM1:59の次の瞬間、
時刻はAM1:00になった。こうして1時間巻き戻すのである。
むろん、これネットと連動しているケータイやパソコンの時刻表示に限る。
腕時計は手巻きで1時間戻した。
3月に23時間の日を過ごしたが、日曜日は25時間あったわけだ。
週末はオックスフォードに行った。
名門大学で有名なこの街だが、目当てはOxford Liederという
歌曲のフェスティバルの最終日。
これに憧れのDame Sarah Connollyが出演したのだ。
若手、男性、サラ・コノリーと、3人の歌手でリレーしていく1時間半。
この日も彼女のパフォーマンスは頭抜けており、脳天をぶち抜かれた。
あと2ヶ月の滞在中、数回は彼女の出演するコンサートがある。
が、いずれもオケとの共演のみ。話せるとしたら最後のチャンスと思って
終演後に順番待ちして声をかけた。
すると、いきなり彼女の方から
Lovely to see you again. I read your letter, thank you.
と言われ、頭が真っ白になってしまった。
ただでさえ英語に難ありなのに、こうなるとお手上げだった。
どのようにしてかは分からないが、
9月末にウィグモアホールのスタッフに託した手紙は彼女のもとに
遅れて届き、読んでくれたらしい。
そこからは完全にテンパってしまい、言葉も出ず、
ただ、絞り出すように御礼を言って、
直近の歌曲のCDにサインしてもらった。
周囲には、マーク・パドモアをはじめ、
フェスティバルに参加していた綺羅星のような歌手が
ワイングラス片手にウロウロしており、
隔絶した世界のように思えた。
学生時代に紅テントに行き、
唐さんを囲む、麿さんや蓮司さん、魔子さん、シモンさん
鷹さんたちが談笑しているの遠巻きに眺めていたのを思い出した。
帰り道は浮き足立ってしまい、バス停まで走って帰った。
大学時代は新宿駅まで。やはり走った。そう急がなくてもいいのに。
サマータイムが終わると、陽が暮れるのが早い。
午後4時には暗くなる。渡英直後を思い出した。あと2ヶ月。
2022年10月28日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note 
↑2017年 横浜トリエンナーレの準備中。
作業中の桃山さんを訪ねるとすぐにビールを出された
水族館劇場の桃山邑さんが亡くなった。
桃山さんが病気だと聞いたのは渡英してからだった。
それから、春の水族館劇場公園には多くの人たちが駆けつけていた。
皆、それが桃山さん現場にいる最後の公演になると知っていて、
自分も列に加わりたかったけど、叶わなかった。
初めて桃山さんと喋ったのは、
入方勇さんの遺品を整理しに行った時だった。
入方さんは北海道出身の役者で、第七病棟の劇団員だった。
この劇団はたまにしか公演しない。だから入方さんは見世物小屋の
主としても活躍し、各地の縁日を賑わせていた。
私たちが初めて『下谷万年町物語』の上演に挑んだ時、
出演者募集に入方さんが応えてくれた。
役者としても面白い人だったけど、持ち前の見世物小屋設営の腕を
活かし、唐ゼミ☆のテントを飾り付けてくれた。
以来、入方さんから教わった方法をもとに、
テント劇場の外観を造作することもまた私たちの表現になった。
知り合ってから一年後、入方さんは亡くなってしまった。
「また出てくださいよ」と頼んでいたのに。
連絡を受けたのは『下谷万年町物語』再演の稽古をしていた時だった。
気持ちのやり場がなく困っているところに、
入方さんが借りていた倉庫の整理をするから手伝いに来ないか
と声をかけてくれたのが水族館劇場の皆さんだった。
入方さんは、"カッパくん"の愛称で親しまれた、水族館の常連だったのだ。
埼玉のどこだったかは忘れたけれど、
指定された倉庫に行くと桃山さんたちがいて、一緒に道具を整理した。
それから入方さんが住んでいたアパートにも行き、
荷物を運び出して作業は終わった。
それから桃山さんが誘ってくれて韓国料理屋に行った。
お酒と料理が並ぶと、桃山さんは「今日は入方の話をしよう」と
言って流れをつくってくれた。
それから、私たちの交流が始まった。
寿町や都内に、三重の芸濃町にも公演を観に行った。
桃山さんたちも唐ゼミ☆公演を観に来てくれた。
特に面白かったのは新宿中央公園で『唐版 風の又三郎』をやった時。
予約して来場した桃山さんは「山谷で揉め事が起きたので
初めだけで失礼させて欲しい。ごめん」と言い、
一幕だけテントの外から見て、台東区に殺到して行った。
自分が良かったと思うのは、
2017年横浜トリエンナーレのスピンオフ企画で水族館劇場が
寿町に夜戦攻城をたてるのをサポートできたことだ。
お世話役を横浜美術館の学芸員Sさんがしていて、
まずは誘致すべき土地を一緒に見立てて欲しいと頼まれたので、
喜んで案内して回った。Sさんは自転車、私はランニングで。
何箇所も候補を出したけれど、もちろん、水族館には寿町でしょう!
と言って、数ヶ月後に実現した。
当時一緒に働き始めていたKAATの眞野館長と一緒に桃山さんたちを
応援した。上の写真は陣中見舞いに行った時のもの。
台本が遅れることについて、
劇も劇場も千穐楽を終えてなお未完成であることについて、
桃山さんはわざとそれらを、信念を持ってやっていた。
そのことを心底理解できるようになってきたのは最近のことだ。
初日に駆けつけると、「なんで初日に来るんだよ!」と
冗談めかして怒られる、いつも桃山さんとのやりとりは
シャイで、優しくて、楽しかった。
帰国したら、また桃山さんに会いに水族館劇場に行こう。合掌。
2022年10月27日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note 
↑見た目は倉庫のようなスタジオでもオペラが上演される

↑中央線沿線にある小劇場と変わらないサイズ感だが、演目はかなり違う
ここ数日、朝は日本の仕事。
カプカプ光ヶ丘と新井英夫さんの講座が週末に始まるので、
その対応が急務。何しろ、こちらは朝6時でも、日本は午後2時。
就業時間も終盤に差し掛かる頃だ。なにか気忙しい。
これから2ヶ月、ずっとこんな感じになるのだと思う。
『下町ホフマン』が厳しい。
目の前のやりとりは大変に面白いのだけれど、
何しろ量が膨大だ。Wordに打ち込みながら読んでようやく
半分を過ぎたところだけれど、手元の台本様式にしてすでに
150ページを越えている。『腰巻おぼろ 妖鯨篇』に次ぐ長大さだ。
300ページ超と踏んでいる。
これまでのペースを維持してあと12日間かかる。
ひとりひとりのせりふが長く、ページをめくって
ビッシリ詰まった紙面を見るにつけ、
"ああ、唐さん、調子いいですね"などと対話。
朝の時間だけでは遅まりきらず、夕方、帰宅後、
空いた時間はすべて『下町ホフマン』に。
それから、昨日は良いことがあった。
残り2ヶ月を気遣ったギャビンが、劇場執行部と
ルイシャム評議会の定例会議に自分を招いてくれた。
神奈川で行ってきた仕事に置き換えると、これは
県の文化担当者との打ち合わせに同席するという感じ。
それにしては、皆さんフランクだったけれど、紛れもなく中枢だ。
今、劇場やフェスティバルが何にフォーカスして動いているか
たちどころにわかる。これからは二週に一度、これに参加。
初めてだったので固有名詞の多さに面食らったが、
何を喋っているか半分くらい分かるようになってきた。
あと、観劇について腹を括った。
年末までに観る公演数を目標300に設定した。昨日で241本目。
しかし、ただ観ればいいってもんじゃないこともわかっている。
これは!と思うものを、密度高く追いかけるようでなければ。
そもそも、自分が数字を意識するようになったのは
渡英前に海外研修の先輩に「オレは200ほど観たよ」と
言われたからだ。「多いですね」と答えたら「そうでもないよ」
と言われて、まずは200を目標に置くようになった。
ところが、これが意外に簡単だったのである。
達成したのが9月上旬。それからちょっと宙ぶらりんで
過ごしてきたが、もうこれは数にこだわった方がいい感じが
してきた。というわけで300。
金田正一投手には及ばないけれど、何となく気持ちが分かる。
昨日はロンドンから2時間かけてBath(バース)という街に行った。
古代の温泉地として有名な観光地だが、ここの小さな王立劇場で
『Dido & Aeneas』の舞台版を観ることができた。
これまでコンサート形式ばかりだったから、他で観た時より
歌手や演奏に弱いところもあったが新鮮だった。
ドラマに寄せきったストレートプレイのような上演。
最後の方にドキリとさせられる、それでいて理にかなった
良い演出があった。
今月中に250に迫ることができればイケる気がする。
バカバカしいと知りながら、けれども、後悔の無いようにしたい。
2022年10月26日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note 昨日、デイヴィットさんが引退した。
今年、イギリスにいるきっかけをつくってくれた一人だった。
私は、自分が長期にわたり外国で暮らすことになると予想していなかった。
きっかけは2つ。
ここ5年間、一緒に働かせてもらっているKAATの眞野館長に
絶対に行くよう勧められたこと。Albanyという劇場を知ったこと。
5年前、さいたまゴールド祭初回に合わせて来日した何人かの中に
Albany代表のギャビン・バロウさん、Entelechy Arts代表の
ディヴィット・スレイターさんがいた。
二人は盟友である。
ギャビンさんは劇場そのものを運営している。
Albanyは催しも手がけるが、もっとも重要な役割は場を提供することだ。
いくつもの提携団体が長屋の住人のようにこの劇場に事務所を持っている。
各団体の事業が合わさって、Albanyの力になる。
Entelechy Artsは提携団体の代表格だ。
ディヴィットさんが創立したこの法人は四半世紀に渡り、
高齢者・障害者・地域の人々を意識した創作と実験を続けてきた。
二人の存在と活動を知った私は、
外国への苦手意識を忘れ、初めて行きたい劇場が見つかった。
外国にはもちろん、ユニークで優れた舞台がたくさんある。
観たり聴いたりすることで大きな影響も受ける。
けれど、単に鑑賞するだけでなく、主体的に関わりたいと思うには
もう一つ何かが必要だった。そして、二人の話にはそれがあった。
Albanyを中心とした活動の面白さはいつも書いてきたから
ここで繰り返さない。大切なのは、昨日、ディヴィットさんが
引退したこと。実にさりげない引退だった。
"Moving Day"の座組みのみんな、15人ほどで記録映像を見た。
その後、ディヴィットさんは少しスピーチをして、
仕事にひと段落をつけた。
考えてみたら、自分が参加してからの半年強、
ディヴィットさんはずっと自身の気配を消していきながら、
後進に法人の活動を託すことを考えてきたのではないだろうか。
一貫してそういう振る舞いだった。
Entelechy Artsの手がける企画は、
すでにマディとジュリーという二人の若手(正確な年齢は訊けない!)
を中心に回ってきた。ディヴィットさんは最後の仕事として、
それぞれの営みを自然に継続させることを狙ってきたように思う
普段と変わらない、ちっとも特別なことのない午後の活動
だったけれど、やはり終わった後は、次々に立ち上がって喋る
シニアたちの涙が、彼の帰りを引き止める格好になった。
自分も、ディヴィットさんの意図に反すると知りながら、
日本の関係者からのメッセージや、花束を渡さずにはいられなかった。
今まで見たことのなかったタイプの、信念に溢れた引退だった。
ディヴィットさんによって、時代は終わらずに続いていく。
2022年10月25日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑Mass Danceのカーテンコールを側面から撮影
収穫の多い週末だった。
最大の催しはMass Dance。
ロンドンにしては珍しい嵐、ドカ雨だったが、
開催時間だけはピンポイントで雨が止み、ミミを中心とした奮闘が実った。
入れ替わり立ち替わりのダンスは合わせて1時間強の作品になっており、
"総力戦"という言葉がぴったりだった。
1日目は大イベントとして一緒に盛り上がり、
2日目は作品としての味わうことが出来た。
ドローンを含む5台のカメラで撮影された映像が完品となり、
将来に活かされていくと思う。
特に日曜は嵐がひどくて、
国鉄の線路上に倒れた大木が交通マヒを起こすような
コンディションだったけれど、よくやれたものだと思う。
日本の仕事、カプカプ光ヶ丘×新井英夫 講座の応募締め切りを
土曜に迎え、たくさん手を挙げてくださった中から、話し合いを
重ねて12人を選び出した。すぐに連絡がいく。
申し訳ないことに選びきれなかった方にも、
事業を継続していずれ直接に会えたらと思う。
もう来年度の準備が始まっている。
他には、唐ゼミ☆本読みをしたり、『オオカミだ!』会議をしたり。
細かい時間を積み上げて『下町ホフマン』にも取り組んでいる。
どう考えてもあと3週間はかかりきりになる分量だ。
見聞きしに行ったものも良くて、
イギリスに来て初めてミュージカルに行き、これが当たりだった。
家から5分のところにあるグリニッジ劇場で見た。
ここは小さな劇場で、週末だけの短い公演が多いけれど、
今月だけはオリジナル・ミュージカルを3週間ぶっ通しでやっていた。
これは何かあるな、と睨んで千秋楽の1日前に行った。
やはり心のこもった、規模は小さいけれど上質の仕事だった。
セットもシンプルにして洗練されている。
何より、主演のKatie Elin-Saltという女優がすごかった。
悪く言えば、劇場業界的にグリニッジは場末だ。
だからこそ、この場末をしてこれだけの実力者がいるのが
イギリスなのだと痛感した。
そういう凄みをせいぜい150人ほどで、間近で観られて幸せだった。
その影響で、今や後回しにしてきたミュージカルに前向きである。
近く『ファントム〜』を観に行こう、そう思っている。
↓ミュージカル『ARE YOU AS NERVOUS AS I AM?』のカーテンコール
2022年10月24日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野WS『ベンガルの虎』 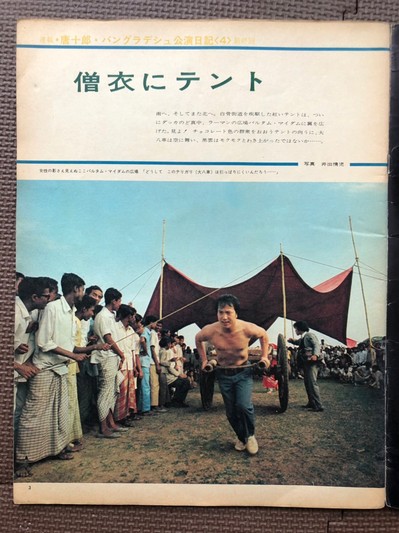
↑再び「アサヒグラフ」より。この唐さんの男ぶりを見よ!
昨日は『ベンガルの虎』本読みの2回目。
一幕半ばに差し掛かるところ。
初回から登場していたヒロイン・水嶋カンナに加え、
もうひとりの主人公である青年・銀次を登場させるのが
今回の主眼でした。
前回の終わり、中学の家庭科教師であったカンナの思い出を
横取りしたミシン売りの中年男は、謎めいたまま舞台を去ります。
取り残されたカンナは、次に町内のご意見番であるお市と対峙し、
見ない顔だと邪険にされます。
東京下町で繰り広げられる日本の村社会は、よそ者を許さない。
しょげかえったカンナに手を差し伸べたのは、
今は流しとなった元生徒の青年・水嶋でした。
冴えない生徒だった彼ですが、今や"銀次"を名乗り、
夜の街をギター担いで渡り歩く男に成長したのです。
(と、ここで、ドラマ『きついやつら』で"流し"を演じる
玉置浩二&小林薫コンビの動画を見たりして)
しかし、彼は精一杯突っ張っていても、元々は唐さんの描く
内気な主人公青年です。元先生のカンナに会うことで、
すっかりお里が知れてしまう。それどころか、キャバレーの
ホステスになってしまったカンナに大きなショックを受けます。
この辺が、彼の弱気で童貞気質なところ。
そして、ここハンコ屋の前に来た理由をカンナが銀次に説明する際、
"バッタンバンの象牙"という言葉に合わせて再びハンコ屋の扉が開く。
俗物隊長たちが扮するビルマ僧が登場し、
戦争未亡人であるお市たち町内の婆アたちと対峙します。
戦没者記念碑の建立のために寄付を募るビルマ僧たち。
が、たくましいお市は彼らを一蹴、すぐにニセモノだと喝破します。
お市らが去った後、サギ師としての正体をあかし、
ブラックジョークを言い合ってふざける馬の骨父子商会の面々・・・
というところまで進みました。
今回、特に良かったところは、銀次の登場シーンです。
格好つけ、背伸びしてワイルドに登場した彼が、
かつての先生との再会によってあっという間に素朴な青少年に
戻ってしまう。その一言一言の変化を、巧みに表現してくれました。
この短いシーンは、端的に主人公のキャラクターを表すツボであり、
一瞬一瞬が表情を変える工夫のしどころです。
それを上手くやってくれて、かなり嬉しくなりました。
それにしても、中年男のせりふ、お市婆さんのせりふ、
ビルマ僧に扮した俗物隊長のせりふと、この芝居のせりふには
たくさんの死の匂いが溢れています。
ミシンを踏みながら何気なくカンナが歌う歌もそう。
日本軍兵士が闘った戦地の過酷さを、まるで絵画のゲルニカのように
感じさせる。また、俗物隊長の部下でイジられ役の天地くんが
ふざけて歌う何気ない歌も、生まれてすぐの命が失われる歌です。
1幕冒頭のト書きによれば、この劇は「死者が見る夢」と宣言されています。
「死者」とは誰か? 基本的には『ビルマの竪琴』が下敷きですから、
亡くなった日本人兵士がそれに当たります。
が、それだけにとどまらないところにこの『ベンガルの虎』の真髄が
あると考えています。
もっとも根本的に"死んでいる死者"は誰なのか。
それを考えながら物語を追い、全編に散らばる言葉を読み解いています。
続きは来週日曜日!
2022年10月21日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note
週末のMass Danceに向け、昨日から本番会場での練習が開始された。
Sedgehill Academyという高校のサッカー場。
ここに設置された大きなテント。これが会場だ。
といっても、全面に屋根がつくわけではない。
屋根がついている部分は全部ステージで、
だから巨大な開口部になっている。
もともと、これはみんなで踊るイベントなのだ。
観に来る人たちは友達や家族が中心。
予約が必要で、手数料に300円くらいかかるけれど、基本的に入場料は
タダなので、観る人は芝生部分で思い思いに座ったり立ったりしながら
観てくれれば良い、というコンセプトだ。
我がルイシャムはロンドンにある区の中でもアフリカ・カリブ・中東
・アジア系移民が特に多い地域だ。
だから、クラブミュージックからジャズ、コンテンポラリーだけでなく
国籍を超えた数多くの舞踊を展開する。
というように、200人を超える踊り手が主役のイベント。
今週のロンドンはずっと雨がちで、夜になると冷え込むけれど、
とにかくあと数日なので力押しに練習している。
お客さんのために、本番だけはなんとか晴れてほしい。
・・・と、これを書いていたら、リズ・トラス首相が辞任した。
たった1ヶ月半の短命政権だった。
滑り出しから評判が悪かった。
英国の政界事情がよく分からないので、強気そうな彼女に対する
女性差別、男性のやっかみかとも思っていた。が、違ったらしい。
今月初め、ダイアンに「新首相は来年くらいに交替?」
と質問したところ「3週間後!」という答えが返ってきた。
冗談かと思っていたが、本当だったらしい。
私としては、円安が際限なく進んでいるから、
こちらの人たちには悪いが、もうちょっと長く地位にとどまり、
ポンドをさらに下げてくれると助かったのだが・・・
2022年10月20日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note
↑これが200人以上で踊り狂うMass Danceイベントのチラシ。
多様性をテーマにしたMimiの自信作だ。
AlbanyのチラシはA5サイズが基本でやたら分厚い紙が使用されている
昨日は水曜日だったが、変則で劇団本読みを行った。
劇団員+座友(古い言い方だけれど、良い表現!)の本読み、
唐十郎ファン用の本読みWSも、同じ『ベンガルの虎』を当たるように
なった。自分だけ何度も何度も同じ箇所を読むので、各所での説明も
話芸の完成度が上がってくる。まるで落語家。
今週末は立て込んでいる。
昨日に書いた『オオカミだ!』会議があるし、
その後はルイシャム南部にある高校に殺到してマス・ダンスの本番が
二日間連続。日曜日の朝には本読みWSがあり、夜には聴き逃せない
コンサートもある。こうなると、日本にいた時のように車があれば!
そう思わずにいられない。車が欲しい。
車が欲しい、といえば11月の遠出。
この計画を練るのにひどく頭を使っている。
たかが遊びじゃないか。てめえが勝手でやってるんじゃねえか。
と言えばそれまでだが、イギリス南西部がこんなに広大で、
しかもバスや電車の本数がこんなに少ないとは。
まるでサスペンスの犯人のような細密な予定を組まされている。
ティンタンジェル城、ミナック劇場、
プリマスで行われるピーターのアンサンブルのコンサート。
行きたいのはこの3つだけなのに、完全に3日間とられる。
久しぶりに夜行バスに乗ることになりそうだ。
最後に乗ったのは、確か野外演劇『青頭巾』で東北ツアーを
組むため、山形に行った時ではないかと思う。
あの時は、早朝に駅に降り立ち、3キロ歩いて朝6時から
やっている温泉に入った。
当然、イギリス南西部のコーンウォールに温泉はない。
いかにも寒そうなイメージだが、気温はどれくらいだろうか。
なんとなしに常に強風が吹きそうなイメージでもある。
とにかく見るべきものを見て、風邪をひかずに帰ってくる。
これが目標だ。最近は陽も短いし、今月末でサマータイムも終わるのだ。
本来は夏に行くべきところを、後手に回ってこの時期になった。
人気スポットであるにも関わらず、チケットを取りやすいのが
唯一の慰めだ。移動7時間で見るのは2〜3時間。
どこもそんな感じだ。
さらに、今年はもう何度目になるか分からないストライキの噂を聞く。
ああ、車があれば・・・。
2022年10月19日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note Albanyでのシニア企画には、ファッション部門もある。
クリーターのAlisa(右)の指導のもと、思い思いに装飾するのだ。
せっかくなので上の写真を撮ってもらった。
今週は土曜日に『オオカミだ!』会議がある。
気づけば公演まで4ヶ月を切っている。だから追い込まなければ。
さまざまな活動に参加しながらこの事ばかり考えている。
昨日もAlbanyでシニアの活動があったが、
会場であるカフェを普通に利用する家族連れがいた。
4歳と2歳くらいの子どもが駆け回っているのを見ると、
彼らにウケたいと心底思う。
実際の上演を考えてこれまで溜めてきたアイディアを
修練させていくのがこの時期の仕事だ。
が、同時に、ここまで敷いてきた絨毯をひっくり返すようなネタが
ないかと思う。そういう疑いの中で生活している。
そんなことを考えながら、自然に体は動く。
Albanyでシニアの皆さんに関わっていると、あと2ヶ月だという
思いがもたげる。民族や国籍、押し寄せる波のような
インパクトがこのメンバーにはある。
生き方はさまざまだと自然に教えられてきた。
ロンドンには、以前は全く想定できなかった人生がゴロゴロあって
些細なことが気にならなくなる。世界的都市だから忙しないところもある。
けれど、全体に大らかな感じがする。
そういえば、自分が差別を受けたことは無い。
昨晩、ふと『シャーロック・ホームズの冒険』をパラパラ読んでみた。
ホームズは中学校の頃よく読んで、イギリス行きが決まってから
英語の先生に課された課題図書のひとつだった。
簡単な英語にしたやつ。
今回は椎野に送ってもらった翻訳を作業の合間に読んだのだけど、
印象が以前とまるで違う。地名の多くを具体的に想像できるように
なっている。これは愉しい。唐さんの台本が東京に根付いているように
ロンドンと近郊にの地名が溢れている。
100年前の話だけれど、地震の無い国だし、街並みは古い。
想像するに難しくない。
11月の遠出の予定も組んでいる。
Plymouth(プリマス)や、さら先のPenzance(ペンザンス)を目指す。
ほとんどを移動時間に費やすことになるだろうど、見ておかなければ
ならない場所がある。果たして、取りこぼさずに行けるだろうか。
2022年10月18日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note 『下町ホフマン』の研究を開始したおかげでエンジンがかかってきた。
研修する、遠出する、公演を観る、飲食や睡眠、掃除など生活する。
それに『オオカミだ!』に工夫を凝らす。
初夏までのように一日の目が詰まってきた。
残る時間は少ない。意地でも力押しに鞭をくれるタイミングなのだ。

↑練習&本番会場であるSedqehill Academy
15日(土)
歩いて南下し、ルイシャムショッピングセンターから1時間のところに
ある高校に行った。ここのホールで、22-23 日に控えている
ダンスイベントの稽古。150人くらいで練習している。
10人のダンサーを中心に稽古を進行していく。
彼らが各チームに散る。
ティーンたち、障害者たち、子どもたち、シニアたち、など。
そこに国際性も入り乱れている。
アフリカやインドの舞踊も組み入れられている。
さすがのバラエティだ。
中心となるダンサー10人の動きがキビキビしていて気持ち良い。
小学生で、すごい身体にバネがある少年を見つけた。
ふざけてばかりだが、振り付けの飲み込みも異常に早い。
これから稽古や本番のたびに、彼に注目しよう。

↑演奏後のピーターと
16日(日)
『ベンガルの虎』本読みを終えて走って駅に行き、
2時間ちょっとかけてドーバー海峡に面した港町Broadstairsに到着。
この街の小さなホールで、ピーター・フィッシャーがグリーグの
ヴァイオリンソナタを3曲立て続けに演奏した。
ピータにとっては明らかにハードワークだったが、
今年聴いてきた彼のライブの中でベストの仕上がりだった。
19世紀のスタイルに規範を求める彼の美学が満ちていて惹き込まれ、
痛快だった。ソリストとしての彼に立ち会える機会は多くない。
来て良かった。
燃焼してハイになったピーターと海辺に行き、
ディケンズの別荘など見て、季節外れになったビーチ近くの
レストランでフィッシュ&チップスを食べた。
ゴールデンチッピー以外で初めて美味いと思う店に出会った。
かなりライトな仕上がりで、また違った美味しさだった。
演奏後のピーターは疲れが溜まっているのだろう。
何度も道を間違えながらグリニッジに帰宅。
ダイアンがピーターに会いたがるので、少し家に寄ってもらった。
彼らの関係は帰国後も続くだろう。

↑週末に向け通し稽古
17日(月)
学校に行き、午後はDeptford Loungeで
女王の崩御につき延期されていたMoving Dayの稽古。
演出家レミーやプロデューサーのジュリーと久々に再会できた。
前日に日本の三重で行われたジャパニーズ版との違いについて
話したりもした。彼らの心配をよそに、出演者たちの記憶は確かだった。
通し稽古をし、ミーティングして金曜日の本番に備える。
・・・と、ここまで書いているうちに、
放課後の高校生たちが図書館のテーブルを占拠し始めた。
彼らに囲まれてこれを書いていたが、エアドロップでエロ画像が
送られてきた。斜め横の五人組が「しまった!」とばかりに
キョロキョロしている。送ったのは彼らのうちの誰かだ。
こちらはお首にも出さないが、内心ニヤニヤしてしまう。
稽古後もここに残って仕事していて良かった。
どんなだか紹介できないのが残念だが、画像がエグい。
2022年10月14日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑花と伝記とCD。出世作『マイスタージンガー』とブリテン2曲。
そのバス停で降りる者は自分しかおらず、
そこからの道に歩道はなかった。
行き交うのは自動車のみで、これが田舎道らしく半端ないスピード。
語学学校をサボって良かったと思った。
帰り道が暗くなれば轢かれかねない。
20分ほど歩くと、教会があった。
ネットで調べた時に毎日オープンと記されていたが、
案の定、扉は固く閉まり、周囲に人の気配なし。
が、幸いなことに墓石の数は少なかったから、
ひとつひとつ、心に余裕を持って確認していけた。
一通り見回して、無い。
すると、散歩中の老父婦が通りかかったので、彼らに訊くことができた。
二人はグッドオール自体を知らなかったけれど、
もう1箇所、付近に同じ教会付きの霊園があることを教えてくれた。
そこを訪ね、半分くらいの墓石を見て回ったところに、目的のお墓はあり、
その老夫婦もこちらの発見を一緒によろこんでくれた。
見つからなかった役場に尋ねることもできるよ、
と言ってくれた優しい旦那さんでもあった。
花を手向け、本とCDを並べてパソコンでDJした。
彼が専門としたワーグナーの序曲をいくつか。
若い頃はベンジャミン・ブリテンとの共同作業で名を馳せたから、
彼が初演した『ピーター・グライムズ』も。
ブリテンのCDは絶版でプレミアもついていたが、
ヘリフォードで叩き売っていたのを中古屋で見つけたものだ。
到着したのが午後2時半過ぎ。
1時間くらいして肌寒くなってきたので、カンタベリーに引き上げた。
霊園の周辺にワイナリーがいくつもあるらしく、
車を飛ばす人たちはそこの職員さんのようだった。
カンタベリーでピザを食べ、大聖堂での夕べの祈りに参加した。
合唱隊は少女のみ。まったく力まず、声を張らないのに、
言葉が明晰で力のある合唱だった。
この場所の教会音響を知り尽くしているのだ。
指揮をしていた青年はすごくおとなしそうで、
はっきり言えば頼りない感じがしたけれど、すごく敏腕な指導者なのだ。
帰り道は油断しまくり、電車を乗り間違えて遠回りしながら帰ってきた。
午後10時に帰宅。
↓カンタベリー大聖堂の前で
2022年10月13日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑メッドウェイ川を渡る際、いかにもケント州に入った!という感じが
した。実際の境界線はもっとロンドン側にあるけれど。
思い立ってカンタベリーに行ってきた。突発的な小旅行。
最近、不安に思うことがある。
帰国までに行きたいところは多数あるが
果たしてすべてを訪ねることができるのか。
近々、リストをつくろうと思っている。
逆算しないと、後で後悔することになる。
ここは必ず行かなければ、というところはさして問題ない。
必ず行くからだ。むしろ、行った方がいいな、程度の場所は困ったもの。
先延ばしにしているうちに時間が尽きてしまいかねない。
カンタベリーもそういう場所だった。
有名な大聖堂もさることながら、指揮者レジネルド・グッドオールの
墓参りがしておきたい。マップで見ればカンタベリーからさらにバスで
移動した田舎道の傍にあるようだ。
小さな教会つき霊園に、彼のお墓はあるらしい。
たどり着けるだろうか。
これまでの経験からお墓探しの難しさはよくわかっている。
物言わぬ墓石を見つけるのは難しい。
まして彼は、誰もが知る有名人というわけではない。
時間がかかるだろう。
かなり閑散とした土地の感じがする。
尋ねられる人が誰もいなさそうでもある。
英国は刻一刻と冬に向かい、日を追って日没時間が早まる。
だから、語学学校の一限目を終えた後、二限目をサボって飛び出した。
最低限の仁義を切り・・・
自分のいるグリニッジは、
ロンドン都心からドーバー海峡に向かう最初の要所にある。
だから、カンタベリーには行きやすい。
駅に歩きながら、乗車切符をネットで購入し、ホームに流れ込んできた
電車に乗った。絵に描いたような田舎道だった。
有名な『カンタベリー物語』はカンタベリーを舞台にしていない。
巡礼者たちが道すがら語り明かした様子を描写するものだから、
むしろ今進んでいる道こそ、あの話の舞台だ。
ケント州に入ると、陽射しは強まった。
横浜から湘南に出たような感覚だ。そう三浦半島に似ている。
2時間かけてカンタベリー。そこからバスに乗った。
・・・長くなるので、続きは明日。
2022年10月13日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note Tea Danceのアイドル、クリスと良い感じの写真を撮ることができた
一昨日、彼はカンパニーのメンバーと一緒に、仮想の高齢者施設
『THE HOME(ザ・ホーム)』のプロモーションにやってきた。
パフォーマーたちが勧誘員に扮し、
Albanyに集まるシニアを相手に高齢者施設の勧誘をする。
マネージャーの女性による挨拶のスピーチ、少し怪しいキャッチコピーの
連呼、スタッフたちによる歌や踊り、どれも面白かったが、
最高だったのは、彼らの仲の悪さが勧誘中も浮き彫りになることだ。
自己顕示欲の塊のような敏腕マネージャーに
スタッフたちは辟易しており、歌や踊りの出番を奪い合ったり、
小声で罵り合ったり、相手がアクトしている時には
ひどくつまらなそうなリアクションをして
観客たちを大笑いさせていた。
作り込んだ資料もホンモノらしい。
日本では催眠商法やオレオレ詐欺が相変わらず猛威を
振るっているので、それをパロディにしたブラックユーモアが
炸裂していたけれど、勧誘行為自体はホンモノなので、
見事に虚実がないまぜになっていて、パフォーマンスの力を
感じさせた。
配布されたプログラムもよく出来ている。
が、これらはすべて架空の高齢者施設で、
オンライン上で皆が集まってお互いにつながったり、
こうしてパフォーマンスや、前後の交流を愉しむことが
眼目なのだ。
英国のパフォーマーのレベルの高さを再認識させるショーだった。
そしてクリス。
クリスは大変に大きな存在で、初めてクリスと会った時、
Heと言いかけてSheなのかどうかまごついていた自分を察して
「どっちでもいいよ!」と言ってくれた。
日本語では彼/彼女とあまり言わないので、
イギリスで実地に体験してこういう時の作法を覚えてきているのだが、
初期にクリスに会えたことで、安心して学ぶことができた。
その感触が半年経っても残っていて、とにかくありがたい存在なのだ。
下記のホームページを見てほしい。
OiBokkeShiの菅原直樹さんも協力してイギリス/日本 対応の
バーチャル空間を作っている。
末尾のクレジットで
クリスのフルネームがChristopher Greenということもわかったが、
やはりクリスはクリスという感じがする。
2022年10月11日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note 
『ベンガルの虎』のことを考えながらカレーを食べる(ベジ専門店)
唐さんたちはバングラデシュで毎日カレーに辟易し、
醤油を惜しみながら使ったらしい。毎日はツラそう・・・
先週末に『黒いチューリップ』を終え、
今週末より『ベンガルの虎』をWSの題材として取り上げる。
唐ゼミ☆で未上演の作品をテーマにするのは、
『少女仮面』に引き続き二度目。
「僕らが上演したときには・・・」という話はできないので、
あるべき舞台の姿をより強く思い描くワークショップになる。
「唐ゼミ☆で上演するとしたら・・・」という具合だ。
もちろん、初演時の資料を紐解いたり、この演目を持って
唐さんが行ったバングラデシュ公演に思いを馳せることになる。
新宿梁山泊の舞台も観ているので、あの上演のことも思い出したい。
あの頃、私たちは開国博で巨大バッタを使ったイベントに
奔走していた。それの初日をやった翌日、
紫テントの立つ井の頭公園に駆けつけた記憶がある。
暑い中、唐さんと並んで観た。
あの公演で、それまで"広島桂"さんだった桂さんは
ヒロインの名前"水嶋カンナ"になった。
カーテンコール、金(守珍)さんがあの甲高い声で
「水嶋カンナを演じました水嶋カンナ!」と叫んだ時、
可笑しかったけれど、度外れな情熱と真剣さが伝わってきた。
それから、前によく通った入谷坂本町の景色も甦る。
2014年のお正月に私たちは唐さんの母校、
坂本小学校でやなぎみわさんが書いてくれた劇
『パノラマを』を公演させてもらった。
その前年、春からよく入谷に通った。
小野照崎神社の御山開きや坂本小学校で行われる納涼祭にも
呼んでもらった。そしてなんと言っても、朝顔市。
あんなにも賑々しいと想像していなかったのでたいそう驚いたし、
『ベンガルの虎』三幕の景色がたちどころに理解できた。
朝顔市は『ビニールの城』でも活躍し、
読売新聞紙上で唐さんが添加した連続小説『朝顔男』の
舞台にもなってきた。
日本ではコロナへの対応が長引いている。
朝顔市、浅草のほおずき市も完全復活は来年だろうと思う。
帰国したらまた行きたい。
初回はもちろん、『ビルマの竪琴』の話から入る。
ロンドンであの映画のことを考えていると、不思議な気持ちになる。
かつて東南アジアの島々で、出征したのに一発の銃も撃てず、
ただ飢餓と病気で亡くなった兵士たちも多かったという。
2022年10月 7日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑オレンジジュースを飲みながらショートフィルム鑑賞、のはずだった
昨日、シニアたちが集まって映画鑑賞をした。
といっても、この上映会は彼らのためにあるのではない。
若手のクリエーターがコンクールに参加するべく完成させた
ショートフィルムを、Albany常連のシニアたちに観てもらい、
意見してもらおうというのだ。
会場は劇場近くにある"JOB CENTER"。
これは仕事を斡旋するセンターでなく、飲み屋の名前である。
Albanyのメンバーが利用する馴染みのパブの一つであり、
初めて劇場に来た時に連れてきてもらったのもここだった。
この店を昼過ぎから借り、スクリーンやプロジェクターをセットし
みんなで観る。
やって来た人から、ちょっとしたお菓子と飲み物を手にする。
こういうところ、運営のエンテレキー・アーツはいつも行き届いている。
自分も勧められてオレンジジュースのグラスを受け取った。
イギリスでの私の主なビタミン源はオレンジジュースだ。
風邪をひきたくない。が、フルーツはいちいち高いから
紙パックのオレンジジュースを買って、一本を3日に分けて飲んできた。
昨日でちょうど前のが空いたところだから、今日の分はこれでいい。
やった。ラッキー。そう思ってごくりと飲み込んだ。
・・・久しぶりに飲んだこの重だるい味。酒だった。
よく見れば、カウンターに大量のグラスが並んでおり、
BUSK'S FIZZと書いた紙があった。
酒を飲まないので名前に疎い。
すぐに調べたら、オレンジジュースをスパークリングワインで
割ったものだそうで、飲みやすいと書かれていた。
それから、水平をたもつのもしんどくなった。
後に会議もあり、夜にはポエトリーリーディングの公演を観に行きたい。
翌日の早朝には日本のシンポジウムで喋る予定もある。
などと考えながらも、体が錆びついたようにギシギシし始めた。
目の前では、シニアたちが嬉々として昼酒を飲み、映画に観入り、
フランクに意見を言い合って映像作家たちを緊張させていた。
他方、自分は会議の予定が迫り、1時間ちょっとでその場を後にした。
映画の内容はほとんど入ってこなかった。ただでさえ英語が難しい。
加えてこのコンディションでは・・・。
いつだったか、唐さんのお宅に伺った時、
「中野にこれを買っておいたよ」とパックのグレープフルーツジュースを
差し出されたのを思い出した。美味かったな。あのジュース。
酒が飲めたら、もっと人生が開けたと思う。
同時に、かなり能率は下がり、お金を使っただろうとも。
後に出席した会議では、何も言わないうちからミミに
「大丈夫?」と心配された。隠したつもりだったけれど、
顔に出てしまっていたのである。
病院を勧められたが、それは断った。
事務所のソファで休み、水をがぶ飲みして、昨日は思っていた予定を
強行した。夜の公演では、司会者の喋りは理解できたが、
ポエトリーはさっぱりだった。
2022年10月 6日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note 
一昨夜の帰り、ロンドン・ブリッジから不思議なものを見た。
テムズ川に浮かぶ船はどちらも背が高い。
前後を挟む二本の橋より明らかに背の高い船が、
どうしてあそこにいられるのだろう?
一昨日はエイシェント室内管弦楽団を聴き、
昨日はエイジ・オブ・エンライトメント管弦楽団を聴いた。
エイシェントは古楽、
エイジ・オブ・エンライトメントは啓蒙時代
という意味。両方、ロンドンで古参の古楽器演奏集団だ。
古楽器集団は20世紀半ばに次々と現れた。
初め、カリスマ的なリーダーが中心となって発足し、
アンティークの楽器やその演奏方法を探究して、
古い道具や奏法の中から新しい響きやスタイルを生み出した。
彼らは既存の大オーケストラとは別の道を行った。
そして、当初は違和感だった演奏が、その後のスタンダードに
汲み入れられていった。
大オーケストラの地位は揺らがないけれど、
彼らの演奏の中には、古楽器集団の奏法や感覚が息づくようになった。
日本の60年代演劇もこれに似ている。
既存の団体に受け入れられない、あるいは背を向けた人たちが
小さな集団をつくって台頭した。もちろん、唐さんもその中の一人。
今や、大きな劇場で上演される劇にも、
唐さんや寺山さんや鈴木さんや信さんや串田さんのセンスが
生きている。運営そのものを直にする人たちもいる。
そういうことだ。
エイシェント室内管弦楽団の創立者、
クリストファー・ホグウッドはすでに鬼籍に入った。
お客さんの少なさが気になったけれど、後継者たちの演奏は
実にハツラツとしていて、初めて聴くハイドンのオラトリオ
『四季』の面白さを教えてくれた。
日本では滅多に聴けない、
けれどもCDではスタンダードナンバーのひとつである。
今年は一通りの楽曲を聴くというのも目標にしている。
それに自分の周囲に置きかえて、色々なことを考える。
もう10月なので、年明けから始まる日本の生活に片足は戻っている
ような感じだ。体はロンドンだけれど、頭の中で来年の帰国後を
思い描くことが多くなってきている。
2022年10月 5日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑前回のTea Danceの仕込み風景。引っこ抜いてきた木が逆さ吊りに
なったいた。
11/15(火)にAlbanyでもひときわ盛り上がるパーティーが開かれる。
その名もTea Dance。昨日は準備のための会議が行われ、
スタッフ、参加者の代表にあたる人たちが結集していた。
司会を務めるクリスもいる。彼こそこの会のシンボルだ。
歌って踊って演奏をして、司会をする。
その振る舞いは周囲への気遣いに溢れている。
当然、みんなが""クリス!"クリス!"と言って慕っている。
前回は6月に開催され、その光景に驚いた。
それまでやってきた歌や踊りの練習、美術創作が何のためにあったのか
たちどころに氷塊した。みんな、この日のために仕込んでいたのだ。
今度は2度目なので、
準備に加わろうと思って会議への参加を希望したのだ。
みんなが前回からの改善点について話し合っている。
プログラムの順番とか、招聘するアーティストとか、
式次第をプリントして配ろう、とかそういうアイディアも出る。
なるほど、こうして意見交換しながらつくられていくのだ。
思えば、スコーンの食べ方を知ったのもあのパーティだった。
上下で半分にパックリと割り、あるいはナイフで切って、
そこにクリームとジャムを塗りたくって食べる。
自分としては濃すぎるが、こちらの人たちはそれに
ミルクティーを合わせる。
それまで、スコーンは、クッキーだパンだかわからない
中途半端なものだったが、この時に旨さがわかり、以来、
しょちゅうプレーンで食べるようになった。
そういう効能もあったのだ。
会場設営は、テーマに合わせてアーティストがデザインする。
前回はRooted=根付く ことがテーマだったので、
Albanyの庭から切り出した木を逆さに吊るしてセンターに飾っていた。
この辺のゆるさがいい。
横浜国大にいたころ、唐ゼミ☆はよくそんなことをしたものだ。
特に竹はどんどん育つので、気兼ねなくフラッグを作る時の
竿にさせてもらったのだ。
ドレスコードについても話し合われた。
別に正装である必要は全くないが、せっかくだからテーマを決めて
それに沿ったオシャレを目一杯しようというわけだ。
これから40日間。そんな風にして準備が続く。
2022年10月 4日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑生き残った片割れ。これがあれば当座は困らないが。
イギリスでどれくらいの落とし物をしてきただろう。
日本にいるのとは違いリカバリーが難しい。
語学力の不足、旅先での出来事であることが原因だ。
公演前も、こういったアクシデントはよく起こる。
忘れ物や落とし物をしてしまう。
いつもは正常稼働していた機械類が故障する。
運転中に交通違反をして切符を切られてしまうことも、ままある。
それらに対処しつつ、いちいち落ち込まないようにしてきた。
公演準備は非日常のことなので、自分でも気づかぬうちに浮つく。
ちょっとしたトラブルが起こるし、スムーズに運ばないのが普通だ。
経験とともに観念し、アクシデントを想定してやりくりするようになった。
イギリスでも、いくつかのものを失くしている。
耳かき。これはエジンバラで失くした。
地元、天王町の薬局で売っているかなり良いやつで、
ダメージを受けた。イギリスのスーパーや薬局では
そもそも耳かき自体を見かけないのでAmazon.UKで買って補った。
が、もちろん精度は及ばない。
ぜんそくの薬。これはラドローで失くした。
ストックがあるが、ひと月分くらいを失くしたので、
1日2回の吸引をしばらく1回に減らして補った。
文庫本。
これは、ロンドンのグローブ座付近の路上で落とした(と思う)。
岩波文庫に『大した問題じゃないが』という20世紀初めに
イギリスの新聞に載った名エッセイ集がある。
3分の1を読み残して落とした時、続きが気になった。
が、タイトルに励まされて悔しさを克服した。
大した問題じゃない。
・・・『少女仮面』の最後の方で、
ヅカファンの少女たちが春日野に服や髪の毛を返す場面の
せりふみたいだが、このような具合である。
いずれも致命傷を帯びるようなものではないが、
日常の便利や楽しみが少しずつ損なわれてきた。
先週末に、コンセントの変換プラグを失くした。
大小2種類の部品から構成されているこのアイテムのうち、
メインでない小さい方を失くした。イギリスでは残りの大きい方で
機能するので問題ないが、追い詰められた感じはする。
変換プラグについては、警戒して2個持ってきた。
全部失くしたらPCとケータイの充電ができない。死活問題だ。
実は、ラップトップももう一台持ってきている。
何年かに一度、自然に壊れるし、置き引きに遭うかも知れない。
そう思ってのスペアだ。
2006年に『ユニコン物語 溶ける角篇』をやっていた頃、
室井先生はサバティカルで数ヶ月間ヨーロッパに行き、
置引きか何かでパソコンを失くした。
「大問題が起こった!」という悲壮な連絡を受けた覚えがある。
あんな風になるのは絶対にイヤだと思ってもう一台持ってきた。
ただし、スペアは今回のように
グリニッジに定住しているだから可能な技だ。
常に移動しながらの一年だったら荷物が増えて仕方がないから、
スペアを持ち運ぶ余裕は無いと思う。
あと、サバイバル力を磨く機会を失っているのかも知れない、
とも思う。人間、その気になれば現地調達できるはずだ。
あるいは、諦めてそれ無しで生き抜く強さも育まれる。
そういうチャンスを放棄しているとも言える。
残すところ90日を切っているが、まだトラブルはあるのだろうか。
ちなみに今年は厄年だが、折に触れ、イギリスまで厄年は及ばないと
自分を励ましながら生活してきた。
占いにも弱い。ああいう言葉にはなんとなしに縛られてしまう。
2022年9月30日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note 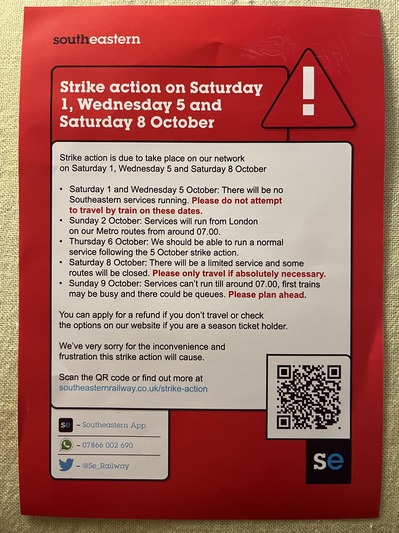
初めてチラシを受け取った。
最近、また鉄道ストライキがあるらしいと噂で聞いていた。
それが、昨日、グリニッジから都心に出るために駅に行ったところ、
気の良いお兄さんがこの宣伝チラシを配っていたのだ。
10月1日と5日、8日に実施されるようだ。噂は本当だった。
今年、何回目のストライキだろう。
特に印象的だったのはエジンバラから帰れなくなった8月第3週の
ストライキで、あの時は前日に「数は少ないけど大丈夫!」と駅員に
言われたにも関わらず、翌日になってロンドン行きが全滅、
宿泊を延長する羽目になった。
もっとも、あの素晴らしいスコティッシュ・ナショナル・シアターの
仕事に立ち会えたのは収穫だった。さらに翌日、
疑心暗鬼にかられた私はかなり早朝にエジンバラを発った。
鉄道もまた一寸先が闇、これが日本との違いだ。
郵便についても似たようなことが頻発している。
こちらでもAmazonをよく使う。"JP"ではなく"UK"。
これがしばしば、勝手にキャンセルされるのだ。
最もひどい場合はこんな具合。
「翌日に配送」とあるのでポチる。
翌日に「あと三日かかります」の通達。
さらに二日後に「明日届けます」の連絡。
当日になり「うまく届けられないのでキャンセルしました」
というメッセージが届く。・・・来る来る詐欺。
悔しいのは、待ち続けている期間に、
街のお店で目的の品物に遭遇してしまう時だ。
目の前の品を買うこともできず、かといって、
本当に届くかどうかも怪しい。
体感的には、4回買い物をするとそのうちの1回は勝手に
キャンセルという頻度。これもまた日本との違い。
10月1日(土)はタイムトライアルになりそうだ。
朝のオンラインWSを終えた後、13:30キングスクロスまで余裕を
持って移動するはずだった。が、ストライキにより想定を
変えなければならない。どの電車が止まり、どの電車は動くのか。
混むであろうバスだとどの程度かかるのか。
そんな情報収集と試行錯誤が必要だ。
少し油断するとすぐにピンチが訪れる。日本との大きな違いだ。
2022年9月29日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑英国が誇るメゾソプラノDame Sarah Connolly(左)
伴奏Joseph Middleton(右)もかなりの腕利きだった
ダイアンがギリシャのイタカに旅立った。昨日から一人暮らしである。
出かける前、彼女は何度も施錠や電灯のオン・オフについて
指導していった。ロンドンは危険なのだ。だから注意深く
それを遂行しなければならない。
出かける時にはラジオをオンにする。泥棒をビビらせるためだ。
あとは庭の水やり。けっこう時間が抱えるので、雨が降ると楽になる。
ロンドンの雨の多さが、ここでは幸いする。
朝からAlbanyのボランティアスタッフの茶話会に出た。
彼らの意見を汲み取るために定期的に行なっているらしい。
きめ細やかである。実際、彼ら無しに日々の事業の継続は難しい。
だから大切に耳を傾けて、主体性を持ち続けてもらうのだ。
「The Wating Roomに来て」と言われ、劇場の受付で訪ねたら、
そんな部屋は無いと言われた。結果的に近所にある喫茶店のことだった。
紛らわしい名前だ。語学力と土地勘が揃わないと辿り着けない。
いまだに、こうしてあちこちにぶつかりながら日々を過ごしている。
辛いところでもあるが、少し遅れたっていいやと鷹揚に構えている。
分からない原因が分かりずらいので、焦っても仕方ないのだ。
午後はキッズプログラムを観て、それから都心に出かけた。
2ヶ月前、衝撃だったThree Choirs Festivalの最終夜に登場して
その技量を見せつけたDame Sarah Connollyを聴くのだ。
男性はSir、女性はDame、騎士の称号に女性版があることを
私は彼女を通じて学んだ。
英国一のメゾソプラノだそうだが、完全に納得している。
他を聴いた数が少ないので断言できないが、絶対値がすごいことが
よくわかる。ピーターと大学の同級生らしく、若い頃から抜けていた
と教えてくれた。
数年前に大病をし、手術をして、声量が衰えたということだが、
衰えてなお恐るべき歌手である。今まで持っていたCDの多くに彼女が
登場していることが分かって、彼女を目的に音源を聴きなおすのも愉しい。
彼女の力感と演じ分けの力がフルに発揮されたバラエティ豊かな
リサイタルだった。前半は英語の歌。後半はフランス語やドイツ語の歌。
後半のトップに歌ったショーソンの歌曲の悲劇性が会全体のハイライト
だったが、その後はヴァイルなどを歌ってお洒落に愉しく終った。
最後の方は、彼女の向こうに舞台となる安酒場が視えるのだ。
高級なチープさだった。
2022年9月28日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑野外劇のカーテンコール。普段は加害者の側に回る私だが、
やっと終わったと拍手しながらかなり嬉しかった
昨日は午前中からAlbanyに行った。
再来月のパーティーに備えて、シニアたちは二班に分かれて
準備している。美術製作がしたい人たちは、飾り付けの造花を作る。
アーティストによるお手本を参考に量産していく。
もう片方のチームは、出し物の合唱の練習をしている。
『ブルーベリーヒル』『スカボローフェア』
『ワンダフルワールド』に加え、みんなで作詞して先生が曲を
振ったもう一曲をやる。昨日は3つの既存曲の練習。
パート分けしてハモるのだが、自分は高い方に配属されている。
『スカボローフェア』を歌いながら夏に二度行ったエジンバラを
思い出した。電車の窓から見えたスコットランドの海沿いの景色。
夏だけど寒そうだったあの風景が、サイモン&ガーファンクルの
描いた世界だと思う。
『ワンダフルワールド』の2番を歌っていると、自分の子どもが
生まれて2歳くらいまでを思い出す。
それなりに長く生きて来たので、歌詞が沁みるようになった。
その後はデスクワークをして、夜に野外劇を観に行った。
テムズ川沿いのベニューで、ナショナルシアターのバックアップによる
新作劇の発表があった。
18世紀、産業革命前夜に発見された不思議な牡蠣をめぐる
エピソードに、現在のジャーナリストが北極の様子を
ライブストリーミングする話が絡む、というトリッキーな物語だった。
要するに、気候変動と環境破壊を意識して創作されたストーリーだ。
俳優のレベルが高く、スタッフワークも緊密で唸ったが、
野外に必要なワイルドさには乏しかった。
明らかに膨大なコストがかかっている。
舞台は貧乏臭くてはいけないが、
あまりにテクノロジーを駆使しすぎると、
もはや劇場の中でやれば良いのではないかということになる。
そういうステージだった。
それから、昨晩は寒すぎた。
気温は10度だったのである。もっとマックスの厚着で
行けば良かったと後悔しながら観劇し、1時間50分を震えながら観た。
直前に近所のベトナム料理屋で熱々のフォーを食べたのが幸いして、
風邪をひくことはなさそうだ。一方で、隣の席に座ったおじさんは、
なぜかハーフパンツに半袖Tシャツにも関わらず余裕そうだった。
英国ではこういう人をよく見かける。
極寒なのに半袖短パン、バーの屋外席でギンギンに冷えた
ビールジョッキをあおっていたりする。
多様性という言葉を実感する。彼らは同じ人間に違いないが、
同じ人間には思えない。体感温度にも、かなり個人差があるらしい。
役者は役によって露出度高めだったり、
ずっと倒れている役の人もいて心配になってしまった。
かつて、極寒の中で自分が公演してきた様々な作品を思い出した。
2022年9月27日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note 
↑ガラの悪い街ながら壮麗な教会がある。コンサート直前の風景。
イギリス国教会の様式
Croydonという街に初めてやってきた。
といってもロンドン市内、Albanyから徒歩と電車を合わせて
南に小一時間行ったところにある街。
ああ、また一つワイルドな場所に来た。
スリや盗難に遭わないように。ケンカにも巻き込まれないように。
けれども、見るべきものは見たいのでジロジロと周囲を睨め回しながら
歩いてしまう。
目的は9月頭に都心で聴いた合唱集団The Sixteenの公演。
彼らほどの実力者であれば、同じプログラムでも何度も
聴きたくなる。むしろ、違う会場の建築を観て、
そのアコースティックをいかに彼らのものにするのか、
愉しみは膨らむ。それにしても、なかなかの土地柄・・・
こういう新たな土地、しかも経済力や治安が良くなさそうな場所を
訪れるのにも慣れてきた。パウンドランド(英国の100円均一)や
Icelandという量販店スーパーを発見したら、その土地の平均所得は
推して知るべし、ということも分かってきた。
自然に、財布やケータイを仕舞う場所を組み替える。
後ろポケットに入れていようものなら、
ヒョイとつままれてしまうこともあるからだ。
先週末、日曜日は面白かった。
ピーター・フィッシャーの出演するフィルハーモニア管弦楽団が
マーラー1番を演奏するので、この曲が最も好きだというダイアンを
連れて行った。指揮者のサントゥ・マティウス・ロウヴァリは美音で、
精妙な優雅な音楽をやる。
主題の変遷がよくわかり、綺麗な演奏だった。
これがロンドン交響楽団ならもっと躁鬱の激しくなるけれど、
彼らの演奏は温かみがあって、高齢のダイアンを招くに
もってこいだった。
ピーターがお友達割引を駆使して、特等席を格安で用意してくれた。
私たちが座った席の周りには彼の他のお友達もいて、
終演後はその中のご夫妻のご自宅に伺った。
我ながらちゃっかりしたものだが、
ダイアンは持ち前の社交性を発揮し、サウスバンク・センターと
ナショナル・シアターから徒歩5分のところにあるその家を
「ステキな部屋だ!」絶賛しながら、私と一緒にお呼ばれした。
帰り際になって、その家のご主人に、
「昔、日本人の演出家が演出した舞台を観たことがある」
と言われた。アラン・リックマンが出ていた、とも。
ということは、蜷川さんが演出し、清水邦夫さんが書いた
『タンゴ・冬の終わりに』の英語版『Tango at the end of Winter』
に違いなかった。
1991年。プロデューサーの中根公夫さんは勝負をかけた。
それまで、十八番である『王女メディア』『NINAGAWAマクベス』
に向けられた海外での評価は高かったけれど、いずれも各地で
短期に公演したイベント的な公演だった。
その点、『Tango〜』は座組を海外でつくり「興行」を目指した。
日本の演劇人が挑んだ大ジャンプだった。
会場は、ウエストエンドの中心にあるピカデリー・シアター。
結果的には、勝ったとは言えない公演だった。
初日直前にチケット販売を行っていた会社が倒産して
売れていた入場料が全く入って来なくなった。
(それでも中根さんは、わずか当日券が売れる収入や助成金を
駆使し、赤字と闘いながら予定していた公演を全うした)
演目も、西洋のリアリズム演劇の延長にある戯曲をなぜ持ってきたのか
と言われたらしい。期待された"日本"の要素は、確かに弱かった。
けれど、観劇したその人は、面白かったので二度観に行ったそうだ。
これには嬉しくなった。
帰国したら、中根さんに伝えに行きたい。
2022年9月23日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note 
Albanyに通うこと8か月が経とうとしている。
しかし、まだまだ知らないことは多い。
通い慣れた企画ですら、知らない計画が進行中ということもある。
これが日本語でのやりとりならば、注意して聴いていなくても
会話が自然と耳に入ってくる。「何それ?」と会話に割り込み、
情報を得ることができる。しかし、やはり英語は難しい。
そんな状態ではあるが、先日、
シニアたちを連れて都心に出かけると聞いた。
尋ねれば、数ヶ月に一度そういう外出をしているらしい。
連れて行ってよと頼んだら、ウェルカムと言われた。
結果、昨日は学校をサボって都心に出た。
朝10時にヴィクトリア&アルバートミュージアムに集合。
英国の黄金時代を築いた女王と旦那さんが世界から収集した品々を
展示した施設だ。南はアフリカ、東は中国まで、"帝国"という言葉を
強く実感させる展示品の数々。
10時に行ってみるとスタッフが集まっていた。
シニアたちはタクシーでやってくる。
今現在タクシーがどこにいるかはケータイでモニタリングできる。
それを眺めながら、導線を確認する。
このスロープを使おう、とか。
荷物置き場はここで、学芸員に話を聞く場所はここ。
最後に集合して軽食を取る場所はここ、という具合だ。
運営にあたるエンテレキー・アーツの面々は、サンドイッチや
スナック、フルーツを持参している。まことに余念がない。
今日の目当ては、常設展ではなく、
アフリカ・ファッションをテーマにした特別展だ。
コンテンポラリーにアフリカ色を反映したモードを展示していて、
華やかだった。その上で、常設展のアフリカ部門も見てね、
というコンセプトなのだが、今回は時間を限っているために、
シニアたちはひたすら特別展のみを見る。
果たして、タクシーから降り立ったシニアたちは輝いていた。
ルイシャム地区は移民の街。アフリカやカリブからやってきた婦人たち
なので、アフリカ・ファッションを地でいっているのだ。
展示場では一つ一つを食い入るように眺め、記念撮影をしてゆく。
とにかくじっくりと見て、キャーキャー盛り上がっている。
こういう性質の展覧会だから、おそらくファッションを学んでいる
学生たちが大勢来ていて、彼らもなかなかの洒落者揃いだったけど、
恰好も振る舞いも、うちの組は度外れに派手で周囲を圧倒していた。
ツアー開始前のスタッフ会議でお互いに確認しあったのは、
彼らをミュージアムショップに絶対に近づけてはならない、
ということだった。それだけで2時間過ぎてしまう。
そういうわけでショップには目もくれさせず、目的地まで案内した。
一通り終わった後は軽食を取り、迎えに来たタクシーにみんなで
乗り込み、にこやかに帰っていた。なかなかの遠足である。
2022年9月22日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note 昨日は日本からやってきた鷹野梨恵子さんにグローブ座で会った。
優れた女優である鷹野さんは、
今やGMBH(ゲーエムベーハー)https://www.gmbh0802.com/という集団を
立ち上げ、運営もしている。
ちょっと前にプロデュースしたイエローヘルメッツの『ヴェニスの商人』
を終えたばかりだが、疲労も感じさせずイギリスにやってきて、
シェイクスピア関係の場所を巡り歩いたらしい。
グローブ座のガイドツアーと『ヘンリー8世』を一緒に観た。
鷹野さんを初めて認識したのは彼女がまだ無名塾に在籍していた頃、
当時、よく唐ゼミ☆に出演してくれていた虎玉大介くんが
他の芝居に出るというので観に行ったら、そこに鷹野さんも出演していた。
物語の設定は昭和初期。戦争に向かっていく日本を生きた
若い芸術家たちを描いた話だったと思う。
あだっぽい踊り子役を彼女は演じていた。
持ち前の身体能力を活かしてピョンピョンと跳ねるように
舞台に現れたのが、とても目を惹いた。
それから、他の男の役者たちとせりふを応酬した後、
「あたし、ヌードはしないわよ」と言ったのをよく憶えている。
言葉のインパクトもさることながら、その見栄の切り方、
表情はせりふを凌ぐ押し出しの強さだった。
いかにも勝ち気そうな感じがしたけれど、
3年程前に再会した普段の鷹野さんはおっとりした感じで、
そのギャップに驚いた。しかし、やはり強い。
無名塾に入る前、ドイツでコンテンポラリーダンスを学ぶために
一年間留学した経験もあるという。
そんな風に国際経験もあり、踊り込んでいるから体力も違う。
渡英の翌日にはストラトフォード・アポン・エイボンに行き、
さらに翌日にはロンドン塔を巡りグローブ座に来て、二本の劇の合間に
ガイドツアーにも参加していた。
自分はといえば、渡英翌日はビザのカードを郵便局に取りに行った後は
頭痛がひどい上に買い物の仕方もよくわからなくて、ビクビクしながら
ホテルで寝ていた。実感として三日間は動けなかった。
それに比べると、イギリスでスイスイとでフル稼働し、
1週間くらいで日本に戻っていく鷹野さんは強靭だ。
研修を終えて日本に帰り、再訪したとしても自分には真似できないと思う。
シェイクスピアについての全てにキラキラした視線を送っていて、
この歴史上もっとも有名なイギリス人に、どれだけ彼女が
突き動かされているかが分かった。
それにしても、『ヘンリー8世』こそは渡英以来観てきた
シェイクスピアの中で、一番の自分のお気に入りである。
エリザベス1世の誕生シーンで締め括られるあの劇を、
プラチナムジュビリーの時に観、お葬式の周辺で観たことになる。
出生の場面では場内から大きな拍手が送られた。
幕開け直後だった6月よりも出演者が好き放題に演じていた。
細部に遊びがあって、熱演する場面の燃焼も激しく、両者のメリハリが
効いていた。バカな下ネタの数々を大胆に繰り出す中に、
それぞれの役柄の悲哀を滲ませていた。
2回目だし、作品をよく知っている鷹野さんにも教わり、
どこをカットし、何を足しているのかもよく分かる。
自立した台本としては、他に優れたものはいくつもある。
ここまで押し上げたのは現場の力だとつくづく思う。
やっぱり昨日も面白かった。
↓エリザベス1世(左)を黒人の女優が演じる。技ありのアイディア
2022年9月21日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑2011年のリサイタルより。ステージ上でいつも張り詰める唐さんも、
安保さんが横にいれば安心の表情
昨日、9/20は安保由夫さんが亡くなった日だった。
改めて思い出してみれば、2015年のこと。
もう七年も経ってしまったのかと驚く。
ほんとうに、ちょっと前まで安保さんの肉声を聞いていた
ような気がするけれども、あの時はまだ、今度6歳になる長男が
生まれる前だったから、確かに七年だ。
安保さんが亡くなった日、セレモニーはやらないと聞いたけれど、
居ても立っても居られなくて、高円寺駅南の火葬場に押しかけた。
唐組や梁山泊のメンバーはもちろん、状況劇場で同級生的な
仲間だった十貫寺梅軒さんや小林薫さんも来ていた。
式はないけれど、それに匹敵する人の輪がそこにあって、
僕らも末席に加えてもらった。
あれから、『あれからのジョン・シルバー』や『唐版 風の又三郎』を
二度ずつやった。その度に安保さんを思い出してきた。
ああ、生きていてくれたらなあ、と思う。
紅テント在籍中、卒業後も安保さんが手がけた歌で、
まだまだ知られていない劇中歌があると思う。
『音版唐組(CDで復刻し『状況劇場劇中歌集』)』に
収められたのはいずれもそれぞれの演目中、メインに歌われた唄。
けれど、ちょっとしたコミックソングや、役者たちが群れなして
歌うような記録に残りづらい劇中歌の中にも、安保さんの傑作はある。
ちょうど、劇団員たちとオンラインで『ベンガルの虎』を研究している。
10月後半から唐ゼミ☆WSも同じ演目を読むことにした。
あの中でヒロインが歌う『雑巾の唄』はもちろん良い。
でも、女性劇団員たちが唐行きさんに扮して合唱する
『鬼と閻魔』も傑作だ。
本当に、唐さんを追いかける自分たちにとって、
安保さんが逝ってしまった喪失感は大きい。
もっともっと色んな話と歌を聴きたかった。
安保さんがいた新宿のナジャに行くと、
酒が得意でない自分のために、安保さんは薄い水割りと
食べる物を作ってくれた。長芋を輪切りにしてバター醤油で炒めたもの、
日本らしくもちもちの麺でつくった特性のナポリタン・・・
今こそああいうものが食べたい。
安保さんはちょっとしたものを仕立てる料理上手でもあった。
2022年9月20日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑チェーン店ではないこのコンビニ。ここは開いているはずだと思ったが
昨日はエリザベス女王の葬儀だった。
朝から日本とのZoom会議をしたが、その後は予定が無くなった。
語学学校も研修先も劇場もどこも閉まっている。
本来はケンブリッジまでコンサートを聴きに行く予定だったが、
それも1週間前には中止の連絡が来ていた。
日用品の買い物があったから、家を出て近所を歩いた。
道すがら、あの店は閉まっている、この店も閉まっている、
しかし、やっている店もある。2割程度の稼働だった。
メジャーなスーパーは全部閉まっている。
チェーン店も大概閉まっている。
ロンドンには日本のコンビニにあたる24時間営業の店は稀で、
そのかわり雑貨屋みたいなものは無数にある。
これらもほとんど休みだった。
小さい頃のお正月を思い出した。
当時は昭和の終わりで、現在のように元旦から、
あるいは二日から店が開いているということもなかった。
三が日という言葉が生きていた。
おせち料理やお餅は、それら店舗が閉まっても食事が絶えないための
保存食だった。
小学校に入った頃からコンビニができ、
それに引きずられるようにスーパーも開き始めた。
だから学校に上がる前の、あの静だったお正月を思い出した。
予定から予定を渡り歩いている時の方が、熱心に音楽を聴こうとするし、
本だって読もうとする。今日は早朝のミーティングで燃焼してしまって
なんだか能率の悪い日になってしまった。
洗濯はした。
ロンドンは寒く、もう半袖や薄手のジャケットに活躍の機会はない。
コンパクトに畳んで、近く、日本に送るための準備を始めている。
届くのに数ヶ月かかる安い船便で送る予定。
残り三ヶ月半。100日ちょっとだ。
2022年9月19日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野WS『黒いチューリップ』 ↑鉢にはノブコ(Nobuko)の頭文字であるNの文字!
咲いてすぐ散る花の仕掛けは、当時劇団にいた安達くんが開発し、
仕掛けを実験しては盛り上がった記憶があります。
昨日は『黒いチューリップ』本読みの第7回。
2幕の終わりから、3幕冒頭をやりました。
前回に引き続き問題になっているのは、
姉ノブコが獄中からケイコに送ってきた球根入りの鉢です。
エコーがこれに触れたところ、成長は加速し、
もう少しで花開きそうなつぼみまで急激に変化していたことが判明。
これを、花にとって心地よくもとあった鉢に戻し、
いま少し見守れば見事開花、という寸前まで来ます。
途中、エコーを伝説のパチプロと思い込む泡小路の邪魔も入りますが、
彼のエコーへの一途な想いは簡単に黙殺されるギャグも挿入される。
球根が鉢に還ると俄然、身を乗り出してくるのが春太です。
彼は花屋のプロとして、黒いチューリップの生育に
病みついた者として、花弁の色が黒へと向かっていることを確認。
さらに、それが暗闇の中だけでなく、立派に世間(陽の当たる世界)
でも生きていかれるかどうかをテストします。
それこそ、この芝居の全ての場面に底流として流れる善福寺川の
川の水を注射器で含ませることで、黒い花を試そうとする。
このシーンの春太とケイコの問答は、
黒いチューリップと姉ノブコの存在と特質を重ねて見事に展開します。
同じ花を相手にしてそれぞれのせりふを言いながら、
ノブコを想うケイコ、ノブコそっちのけで花に執着する春太を
鮮やかに描き出す。
結局、ノブコの花はシャバの水には耐えられず、
その花びらを散らします。そして、花を試す春太の強行な姿勢を
恨んだケイコは、かねて練習していた毒入りキッスを
春太に食らわせようとする。
が、その時、練習中に誤って虫歯の穴に入ってしまっていた
毒薬が口の中に踊り出し、ケイコはこれを飲んでしまう。
春太は口から吐き出された一粒、自分を襲おうとした丸薬を
すぐにの農薬と見抜きます。
ケイコの遺した書き置きにより、
エコーはケイコの解毒のための景品買いの婆あサキを
訪ねる運命に直面します。これが2幕の終わり。
ここまで、ずっとタクシー運転手の菊地も刑事の泡小路も
舞台におり、しかも、80〜100人からなる警察学校の生徒たちが
それぞれに抱えたチューリップの鉢、すべての花弁が散る
というト書きは、唐さんが現場に託した挑戦状といえる
ト書きが炸裂します。
変わって3幕。
おっかなびっくりパチンコ店「黒いチューリップ」の裏手を
訪ねたエコーとサワヤカ(エコーが加勢として呼んだ)は、
サキをボスに頂く婆あの群れと対決します。
『ロミオとジュリエット(小田島訳)』をパロディしながら
このシーンは展開し、エコーはサキに課されたロミオの
せりふを見事に言ってのけ、解毒の薬の調達まで、一歩前進。
・・・というところまでやって昨日は終わりました。
いつも3幕ものでは、2幕の終わりが緊迫し、時に血を見るなど
苛烈なシーンが唐作品の持ち味ですが、この芝居は特別です。
基本的には非常にシリアスなのですが、
設定の中にはかなり間抜けというか、バカバカしく、
どこまでいってものどかななのです。
心に波風を立てず、ショッキングな要素を控え目にして、
安心して見られるのがこの演目の魅力。それを象徴するシーンの
連続です。その中に、球根の仕込まれた鉢をテストする場面では
唐さんらしく「引きこもり」の心情を描写しています。
次週は、サキがエコーの体を狙って襲い掛かるところから。
ケイコが復活するまで、物語の本質からは脱線し、
縦横に展開する唐さんのお笑い路線を楽しめる場面が連続します。
2022年9月16日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ダウンロードが隆盛だ。CDを売る店がめっきり少なくなった。
ロンドンでは、私がCDを買う店は2軒に集約されている。
都心のトットナム・コートロード駅近くにあるフォイルズという本屋と
ノッティングヒルにあるClassical Music Exchangeという中古屋だ。
最後の砦として頑張っているこれらの品揃えは良い。
が、たった2軒は淋しい。
フォイルズのジャズコーナーのおじさんと話した際、
彼は元々独立した店舗を経営していたのだと教えてくれた。
それが立ち行かなくなり、この大型書店が中に引き込んでくれたそうだ。
ここからソーホーは近く、有名なジャズクラブがいくらもある。
CDへの需要があると思うのだが、時代の波には勝てない。
最近、遠出した際、お土産物売り場でCDを売っているのを発見した。
懐メロというか歌謡曲というか、そういう類の品揃え。
日本でいうと、高速道路のSAで売っている内容のような感じだった。
そして、ひどく埃をかぶっている。
興味を持ってしげしげと見ていたら、上のCDが1,000円くらいで
売っているのを発見して即買いした。
メリナ・メルクーリはギリシャの国民的女優だ。
私が初めて彼女を認識したのは、蜷川さんの『王女メディア』の
映像を観た高校時代。あの演目をギリシャの古代劇場で上演した
ことにより蜷川さんは世界で頭角をあらわしたのだが、その時の
ギリシャの文化大臣がメルクーリだった。
カーテンコールの映像。
かつては自分も演じた役を、日本人の平幹二朗が演じているのを
涙にくれながら称賛していた。文化大臣だから前列のVIP席で観ていた
彼女は、観客の拍手に応えるステージ上の平さんの前に進み、
何か言いながらキスをしている。
そのキスが、なにやら頭突きみたいな迫力なのだ。
パッチギと言った方が良いくらいの獰猛さ。
興奮して平さんの顔面にゴンゴンやっているようにしか見えない。
あれは印象に残った。
さすがギリシャ悲劇のヒロインをことごとく演じてきただけあると
感心した。ゴツい魅力なのだ。
次に彼女を意識したのは、唐さんとのやりとりの中だった。
唐さんが20代の頃に観て虜になった映画に『Phaedra』という
ギリシャ悲劇を現代化したものがある。邦題は『死んでもいい』。
彼女はその主演なのだ。
※DVDは無いけれど、下記アドレスにフルアップされている
https://www.youtube.com/watch?v=JQVbuCbpZ_c
監督は彼女の夫のジュールズ・ダッシン。
二人の仕事としては『Never On Sunday』の方が有名だ。
邦題は『日曜はダメよ』(見事な翻訳!)。
唐さんは『死んでもいい』の主題曲のメロディが好きで、
その影響は『腰巻お仙 義理人情いろはにほへと篇』や
『続ジョン・シルバー』『吸血姫』にあらわれている。
ここから先は自分の想像だが。
メルクーリの歌声を聴き、駆け出しの唐さんは彼女の声質を、
隣にいる李さんに重ね合わせていたのではないかと思う。
低音域がよく出るところ、それがちょっとかすれるようなところ、
それでいて音域広く高音まで出るところが、似ている。
ひょっとしたら、野心に燃える唐さんは、
メリナ・メルクーリのような魅力で李さんを押し出していこうと
恰好の好例として捉えたのかもしれない。
・・・というような様々な思いが10秒くらいで過ぎり、CDを即買い。
ギリシャでテレビに出演した際に歌っていた主題歌を集めたもの。
なぜこんなものがお土産物屋の軒先にあったのか、それは謎だ。
2022年9月15日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑ゴールデンチッピーのオーナー・クリスさん。
若い時の苦労、商売人としての重厚さが笑顔の奥に滲み出ている。
エリザベス女王の死で霞んでしまったが、
先週は英国に新しい首相が誕生した。リズ・トラス首相。
滞在していた城に新首相を迎えて任命した後、
2日して女王は亡くなった。だから、首相の初の大仕事は
旧国王の葬儀と、新国王の戴冠とを国家代表として仕切り、
立ち会っていくことになる。
外交的に彼女は一気に顔が売れるだろうけれど、
これから女王を頂いていたいくつかの国で
英国王室との距離感をめぐって様々な動きが出てくるだろうから、
これらに対応するのは骨が折れるだろう。
旧大英帝国領の国々にとっては、
ここで動かなければズルズルいってしまうと必死になるだろうし、
英国内の国民だって、あの女王だから許せていた予算の捻出を
今後も維持するモチベーションがあるかどうか。
宮殿7つは多すぎるよ、と英国人の知り合いが言っていた。
日本のロイヤルはそれに比べるとだいぶ質素だよ、と教えた。
マーガレット・サッチャー元首相は現職時、
女性として女王よりも前に出過ぎないように気を遣ったらしい。
それはそうだろう。
主演女優と同じ色の衣裳を二番手が着てはいけない。
若手女優が主演である場合、クレジットの最後に来るような大物女優と
かぶってもいけない。まして、初めて女性として首相になったのだから
先例もなく、大変に気を遣ったと思う。
英国3人目の女性宰相はこの悩みから解放されたとも言える。
トラス首相は地元の人だそうだ。
ホストマザーのダイアンがどこからか彼女の家がグリニッジにあると
教えてくれた。そこでゴールデン・チッピーに行った際にオーナーの
クリスさんに訊いたのだ。
こういうネタは、地元の繁盛店の店主に訊くのが一番。
結果、やはりクリスさんの店の裏手の丘を上がったところに
大きな家があるそうだ。
クリスさんの店は地域ナンバーワン フィッシュ&チップスの呼び声高い。彼は若い時にトルコからやってきて、
働きに働いてこの繁盛店をつくり上げたそうだ。
いつもひっきりなしに多くのお客が出入りするから、
自然とこの界隈の情報は彼に集まる。だからなんでもよく知っていて
「あの辺だ」と指差しながら教えてくれた。
着任後すぐに、トラス首相には若いボーイフレンドがいるという話題が
メディアに抜かれた。夫とは別に、二年間に渡って付き合ってきた彼が
いるらしい。
君主の死がこのニュースを覆ってしまったが、
例え女王の話題がなかったとしても、こちらでは、例えば首相を
辞任させられたりする程のニュースではなさそうだ。
2022年9月14日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑テイト・モダンの前に掲げられたバナー
「用意していた!」
これは、唐さんの作品の中でも80年代の傑作『ビニールの城』二幕に
出てくるせりふだ。相棒である人形「夕顔」を探し続けていた
腹話術師「朝顔」の前に、水槽に封じられた夕顔が現れる。
水に潜って助けなければ!
すると朝顔はポケットから水中眼鏡と水泳キャップを取り出す。
こういう事態を予測し、彼はあらかじめ完璧な用意をしていたのだ。
先のせりふはここで出てくる。なぜこんな周到な準備ができるのか。
もちろん、芝居だからだ。すべて唐さんの思うまま。
しかし、このせりふを言うことで、劇の進行とともに緊迫感に
包まれていた客席に笑いが起きる。
唐さんの、実にズルい手である。
目下、ロンドンはエリザベス女王に染まっている。
至るところに彼女の写真を見る。
娘時代、王位を継いだ頃、貫禄に満ちてきた頃、皆が見慣れた晩年。
それにしても、本当に、驚くべきスピードで、
これらの遺影はあっという間にロンドン中に溢れた。
店先で、バスの停留所で、地下鉄の駅で・・・。
もっとも良いなと思ったのは、テムズ川沿いのテイト・モダンだ。
現代美術を専門に扱うこのギャラリーのバナーも、
いつの間にか、あっという間に女王になっていた。
亡くなってからデザインし、確認し、印刷したのでは
絶対に間に合わない速さで流布したのを見るだに、この国がいかに
女王の死に備えていたのか体感することになった。
不謹慎だから誰も表立っては言わないけれど、
ちゃんと用意してきたのだ。いつの頃からかは分からない。
けれど、実に鮮やかな手口だと思った。
葬儀が9月19日(月)に決まり、その日に予約していたライブは
キャンセルになった。
2022年9月13日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note 写真では多く見えるけど、イスの数は300くらい。大きなホールより
かなり少ないので、いつも売り切れる。
朝起きたら、霧がかかっていた。
すっかり忘れていたが、確かに春までのロンドンはこんな感じだった。
必然、やや肌寒い。
こちらでは先週の木曜に女王が亡くなり、
興行が停止するかと思いきや、予定通り行われるものもある。
自分が予約していたものはたまたまそれにあたり、
金土日と夜は何かを観て過ごした。
いずれも音楽がらみだったから、冒頭はGod Save The Kingを捧げる
ところからは始まる。同じ曲のタイトルがQueenからKingに変わった。
土曜に行ったペッカムは、
治安の悪い南ロンドンの中でも札付きの一つだ。
ブリストン、ニュークロス、デトフォード、ルイシャム・・・
ペッカムでは語学学校の友人がケータイを奪われた。
バス停のベンチに腰掛けてスマホを操作していたところ、
ヒョイと持ち上げて逃走されたのだ。
そういう場所の、駅前のビルでフィルハーモニア管弦楽団の
コンサートは行われた。映画館とかゲームセンター、ビアガーデンが
雑居するビルの立体駐車場がライブ会場として使われており、
そこでラフマニノフのピアノ協奏曲2番をやった。
この場所とこのオケの組み合わせは3回目だ。
この夏に行われた演奏会をすべて聴いた。
とにかく会場が好きなのだ。手の届きそうな天井により
増幅された轟音、隣近所で飲む若者たちの声、脇を走る国鉄の
レールの軋み、そういったものがガンガンに闘うのだ。
いつも演目は1曲か2曲で、1時間くらいで終わった。
それでいて入場料は一律4,000円。
都心の立派なホールで2時間半の公演を1,800円くらいの席で
聴くより割高な感じがする。けれど、好きなのだ。
演奏スペース近くの吹き抜けの部分はカーテンで覆っているけれど、
客席半ばくらいからは外の景色とコンクリートの隙間から沢山
のぞいている。なにせ駐車場なのだ。
冷暖房なしだから、夏限定の会場だ。
ずいぶん愉しませてもらったけれど、今年はこれでおしまい。
来年またやるかどうか分からないけれど、やったとしても
自分はいない。今後イギリスに来ることがあっても、
まずは仕事だろうから最後かもしれない。
だから、3回とも行った。
メインシーズンが帰ってくると、こういう遊びの公演も終わる。
2022年9月 9日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑公演するはずだった図書館の受付前に置かれた女王の写真と記帳セット
一昨日にチェーホフの『かもめ』を観て、
これまで鑑賞してきた催し物数が200本になった。
昨日はスタンダップコメディのコンテストを観たので、現在は201本。
今週から、イギリスでは新しい年度が始まった。
だから、各劇場でも次々と新シーズの演目が開幕している。
観たいものがたくさんあるので、まだまだ増えそうだ。
試しに確認してみたら、現在、336日の滞在予定のうち、221日目だ。
鑑賞数300本は無理だろうけれど、それに迫る数字にはなると思う。
あらゆる物価が高いこの国で、なぜかチケットは安い。
正確に言うと、ほとんどの催しが安い席を用意してくれている。
語学学校にも通っているので、学割もしばしば使える。
これには助かっている。
ところで、帰りの飛行機をどうしたら良いか思案している。
ルールとしては、45日前に海外研修の事務局に連絡して航空券を
手配してもらうのが基本なのだが、どうしたものか。
と言うのも、今回の研修期間はビザによって決定した。
文化庁的には350日まで滞在が許されたのだが、
取得できたビザの上限が335日だったので、
それでイギリスにいられる期間が決まった。
残りの1日は飛行機の上にいる。それで336日。
現在のところ今年の大晦日にヒースロー空港を発ち、
元旦に羽田空港に着くつもりだ。
が、何かの拍子に、例えば大雪などで
イギリスを発てなかったとしたらどうなるのだろうか。
ビザが切れているのに滞在し続け、これが問題化すると、
今後10年はイギリスに入れなくなるらしい。
そうなれば、せっかくつくった人間関係や土地勘の意味が激減する。
用心を重ねて12/30に発った方が良いのか、
それとも予定通り12/31まで使い切ろうか、
やむを得ないトラブルであれば許してくれるのか。
ちょっと早いが、そんなことも気にし始めている。
慣れない海外のことだから、何がどんな具合かよくわからない。
何が本当に厳格で、どういう時には許されるのか。
この研修を終えたら、だいたいの落としどころは身につくと
思うのだけれど。
・・・と、ここまで書いたところで
エリザベス女王が亡くなったことが発表された。
新しい首相を任命する際、こやかなに笑って談笑する写真を
今朝の新聞で見たばかり。夕方に不調が報じられた数時間後に
その死が発表された。
Albanyのみんなが騒いでいる。
これから喪に服し、Albanyでは催しをストップするらしい。
新国王はチャールズ3世と
2022年9月 8日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑昨日は観客に合わせてイスを用意。演者が移動するとイスも一緒に移動
最近、雨がちである。
時にはカミナリも鳴る。英語でサンダーというがどうもしっくりこない。
ファイナル・ファンタジーを思い出してしまう。
いよいよ、噂に聞いていたロンドンの本領発揮と思う。
暗くて曇りがちなロンドンという定番の印象が、自分にはない。
1月末に渡英して以来、日々、春に向かって時間が過ぎたし、
何より一つ一つの行動に必死すぎてよくわからなかったのだ。
今、季節は冬に向かっている。
だから今度はロンドン独自の気候を存分に味わえると思う。
そして、もっと暗くて寒い1月を自分はパスする。
日本の予定やビザ取得に難儀してたまたま2〜12月の滞在になったが、
これが9〜7月だとずいぶん印象が違ったと思う。
日照時間が長く活動的で、旅行に向いた季節を失わなくて良かった。
秋の始まりに、シニアたちの本番に立ち会っている。
先週はショッピング・センターでの本番だったが、
今週は図書館に場所を移して、別のメンバーで構成された本番が
始まった。
物語は基本的に同じなのだが、
先週はコミカルだった。メンバーにアフリカ系の陽気な人が多かったし
ショッピングセンターの賑やかさが方向性に拍車をかけていた。
今週は本格派ストレートプレーの趣きで、
聴衆は会話をよく聴き、演者たちはあまり声を張らずに内容を聴かせる。
先週は民族衣装を着てくるというコンセプトでかなり派手だったが、
今週は日常に近い格好で、「移民」「引っ越し」をテーマにした社会派の
匂いがする。こういうのも、演出のレミーはきちんと計算している。
休憩時間の過ごし方も2チームで全く違って、
先週はお茶を飲んでワイワイ歓談し、人によっては食事や買い物に
行っていたけれど、今週の面々は演技の改善に余念がない。
中には、上手くいかなかったところを悔やむ人もいて、
周囲が彼女を慰め、「まだ次がある!」と鼓舞していた。
1日に2回ずつ、週末にも上演する予定なので、
次の回への対策を話しながら、一緒にサンドイッチを食べていると愉しい。
ああ、一年ぶりに劇をつくっているな、と実感する。
2022年9月 7日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑ジャマイカ出身の野菜カラルー。花が咲いているが葉を食べる
毎週火曜日は定例となっているシニア向けWSに参加する。
だいぶ慣れてきたが、それでも細部に発見がある。
昨日は合唱の練習が終わり、参加者がそれぞれのペースで帰宅する時、
Albanyの庭で採れた野菜を持ち帰る人がいた。
Albanyには広めの庭があり、ここで植物が育てられている。
英国人が庭を愛することはダイアンやミミの情熱に接して知っていたが
劇場でもそれは同じだ。
よくスタッフが庭を手入れしているのを目にする。
植物に水をやり、必要な栄誉剤をやり、雑草を間引き、掃除する。
温室まである。劇場受付やチケット販売業務の傍らに庭を世話する。
しかも、楽しそうにやっているのが良い。
今日、参加者が持ち帰ったお土産はSpinach=ほうれん草だった。
また一つ英単語を覚えた。
ただのほうれん草ではなく、カラルー(Callaloo)というものらしい。
これはもともとジャマイカの野菜だそうだ。
野菜なのに高たんぱくで、しかも鉄分やカルシウムも
驚異的に含んでいるらしい。
ロイシャム地区にいると、ジャマイカ移民の存在感をひしひしと
感じる。彼らが、ハングリーな生活や日常的な闘争を経て
市民権を獲得してきたことが切実に理解できる。
もちろん、レゲエという音楽も彼らとともにやってきた。
国境を超える時には、水分、植物、動物、昆虫なども
厳格に管理される。生態系に影響するからだが、
(そういえばロンドンではセミを見なかった)
人が動けばそういったものも移動するのだろう。
カラルーが、多くの栄養や効能で大勢の人たちの身体や健康を
支えてきたことを想像すると、野菜ひとつにもロンドンを感じる。
ちなみに、ルッコラはロチェットと言い、
ダイアンのお遣いの際にそれを教わった。
パプリカはペッパー。特にフレッシュ・ペッパーという。
前にペッパーを買うよう頼まれて、胡椒を買いそうになった。
2022年9月 6日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑開演前のリージェントパーク・オープン・エア・シアター
昨日はリージェント・パークというところで野外劇を観た。
演目は『アンティゴネー』。ソフォクレスの原作を
Albanyでポエトリーの催しをしていたイヌラ・エラムスが
翻案したものだ。
彼は移民の問題を背負いつつ、優しい語り口の詩や台本で
ファンを得ている。ナショナル・シアターで2018年に上演した
『バーバーショップ・クロニクルズ』が代表作、
日本語にすると『床屋年代記』、魅力的なタイトルだ。
同じ日に、各国の床屋で起こる小さな事件を集積させることで
この台本は成り立っている。上手いアイディアだと思う。
かつて巨大な帝国を築き、今は移民の街となったロンドンの劇だ。
今回はギリシャ悲劇が原作だけれど、
彼はこれを家族からテロリストを輩出したムスリム家庭の葛藤に
読み替えていた。
反社会性力の最たる者として扱われるテロリストの死を
その妹であるアンティゴーは弔うことができるのか、という問い。
ソフォクレスの原作では国王だったクレオンは首相という
立場になっている。
この公演に興味を持ったダイアンが、
自分の障害者手帳を利用して格安の良席を手に入れてくれて
贅沢な環境で環境で観ることができたし、天気も持ち堪えた。
『アンティゴネー』野外劇といえば、
去年のゴールデンウィークにSPACによる上演を観た。
会場は駿府城公園だった。
こういう観劇を重ねていると野外劇場とギリシャ劇への思いが募る。
小さい頃にアニメ『聖闘士星矢』を見て以来、
ギリシャは憧れの地なのだ。小学校の頃に、
名古屋の科学館に通って星座に関わる神話をたくさん聞きもした。
ギリシャといえば、私にはなんと言っても
蜷川さんのプロデューサーだった中根公夫(ただお)さんだ。
1960年代にパリに留学し、
夏はいつもギリシャに行っていたという中根さんの話を思い出す。
日本人でもっとも沢山のギリシャ悲劇を観た中根さんは
それから20年後に蜷川さんを擁してギリシャに乗り込んだ。
『王女メディア』に出演していた金田龍之介さんのエッセイに、
現場の様子が臨場感をもって描かれている。
今は神奈川芸術劇場の館長である眞野(純)さんも、
2004年に野村萬斎さんがオイディプスを演じた公演で
古代劇場を体験ずみだ。うらやましい。
リージェントパークでさまざまなことを思い出した。
ウェールズにはミナック・シアターという海辺の岩場を利用した
素晴らしい野外劇場があるという。ここにも行ってみたい。
2022年9月 2日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑右から2番目が演出家のレミー。もうすぐ新作詩集が出版され、
ドラマーとしてスペインに演奏の仕事にもいく多才の人。
男性出演者は勝手にどこかに行ってしまい、この写真に写っていない。
昨日はシニアたちによる移動型演劇を公演した。
近所にあるルイシャム・ショッピング・センターという商用施設内の
メインストリート、ギャラリー、事務所スペースを使い、
お客さんを連れ回しながら物語の進行させる。
初めのシーンはかなり往来なのでピンマイクを使い、
そこからは静かな空間に入っていくので、
マイクを外してせりふを通していた。
シニアたちはいずれもキャリアがあり、強メンタル。
高揚はしていても緊張はしていなかった。
衣裳はそれぞれの国の民族衣装という指定で、
アフリカ系の人がほとんどなので、ド派手な格好で家からやってきて
2ステージこなし、そのままの姿で意気揚々と帰っていった。
面白い人たちだとつくづく思う。
とりわけ興味深かったのは、
2ステージあるうちの休憩時間の過ごし方だ。
初回が終わり、皆よろこんでいたが、演出のレミーから
2回目に向けての作戦会議が提案される。
集合時間も告げられた。
皆は1回目のお客さんと喋った後、
思い思いに軽食を取ったり、休憩したりしていたが、
会議の時間になり、女子がビシッそろった。
が、男は来ない。
一人はテイクアウトのコーヒーを買いに行ったまま
なかなか戻って来ず、もう一人はそのカフェで、観に来てくれた
息子さんと娘さんとガッチリ昼飯を食べていたところを後で
発見された。女性たちは演技の工夫と詰めに余念がない。
見事なコントラストだった。
小学生の頃、掃除の時間にふざけていたのはいつも男子だった。
女子はいち早くトレンディドラマを観て大人になっていくのに、
私も含めて、ミニ四駆やガンダムのプラモデルをぶつけ合って
喜んでいた。
場所がロンドンだろうが、年齢が80歳オーバーだろうが、
この構図は普遍だった。2回目の本番、男子たちは段取りを
飛ばしたり勝手なことを喋り始めたりしてスタッフを大いに
焦らせることになった。
明後日も2ステージやる。彼らに幸あれ。
2022年9月 1日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑白い衣裳がジャンヌ・ダルクを演じた俳優さん
バイセクシャルを公言しており、鎧をまとう時の腋毛が印象的。
横浜国大の先輩、黒木香さんを思い出した。
9/1といえば関東大震災。
うちの子どもたちも保育園で避難訓練をしているらしい。
関東大震災は1923年に起こったから、来年で100年が経つ。
自分が生きてきた期間だけでも、
阪神淡路大震災、中越沖地震、東日本大震災と
大きな地震が続いてきた。かなりの頻度だ。
子どもの頃にはわからなかったけど、
親になって避難訓練の大事さがわかった。
災害はいつも不測の事態だけれど、それでも、
訓練があるのとないのとではだいぶ違う。
テント公演をする時にも、私たちは避難誘導訓練をする。
演劇史的には、
関東大震災は築地小劇場の成立に影響を与えた。
震災後は建築基準法がゆるみ、建てられる建物のバリエーションに
幅が出た。その機に乗じて新劇の始祖たるあの劇場は成立したらしい。
第一次世界大戦の敗戦国であるドイツやロシアの貨幣価値が下がり
留学しやすくなったこと。震災の影響。といったもので
演劇ムーヴメントが成立したとは。因果なものだ。
さて、昨日のこと。
だいぶ豪快に間違えてしまった。
グローブ座で新たな演目がスタートしたので観に行った。
ずいぶん前に日本から取り寄せていたシェイクスピア『ジョン王』の
台本も読み、歴史も調べ、予習はバッチリだった。
いつものように、5ポンドの立ち見席へ。
しかし、冒頭シーンからかなり違う。
女の子が出てきて独白を始めた。そして剣を振りかざす。
グローブ座は基本的に原点主義だから、
ここまで原作と違うとは何事かと思った。
カバンに入っていた台本と見比べても、冒頭シーンからぜんぜん違う。
そして気づいた。これは『ジョン王(John)』ではない。
よく見ると、タイトルは『I, Joan』→"わたし、ジョアン"だ。
つまり、ジャンヌ・ダルクの劇。
作者はシェイクスピアですらなく、
現代作家が書いた新作のお披露目だったらしい。
グローブ座では、シェイクスピアでは無い作家もの劇もかけるのだ!
そこからは、必死にせりふを追いかけて内容を追った。
セットはほとんどないから情報源は圧倒的に言葉。難しかったけれど、
有名なジャンヌ・ダルクの一生をベースにしたものだから、
その本案やパロディとして何とかついていけた。
グローブ座に何度も来るうち、何人か顔を覚えた役者もいて、
彼らを応援しながら愉しむやり方もわかってきた。劇団の魅力だ。
それにしても、あまりにも基本的な、こっぴどい間違いだった。
愕然とする。ロンドンではこういうことがたびたび起こる。
かなり情けない気持ちにもなるが、笑ってすますことにする。
2022年8月31日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note 
↑投稿内容とは関係がない写真
Albanyの主催でスウェーデンの作家Ruke JerramのGAIAという作品を
展示した。てっぺんとそこの部分から3方向ずつワイヤーを引っ張って
安定させる。良いロケーションだったが、プロデューサーのメグが
仕込みも含めて4日間つきっきりだった。巨大バッタの展示を思い出した
マジでビビっている。
英国での暮らしは気楽で愉しいばかりではない。
まず体が痛い。2013年にKAATでの『唐版 滝の白糸』を
上演した後から、整体に通い始めた。
劇団員だった禿恵の紹介だったが、
あっという間に彼女より通うようになった。
回数券を買い、1ヶ月に一度身体が痛くても痛くなくても行く。
走ったり歩いたり習慣化した頃とも重なり、ルーティンになった。
と、このように、床屋、歯医者、整体、これらに月にいっぺん行く。
日本にいた頃は。
ロンドンではたくさん歩く。街が狭く交通費が高いからだ。
それは良いのだが、パソコンとスマホを見ている時間も長い。
これが結構堪える。そしてシャワーのみで風呂はないから慢性的に
首が痛い。これから寒くなる。大丈夫だろうか。
先ほど歯医者を挙げたが、歯も不安だ。
日本の自宅の隣の隣には近所で評判の歯医者がある。
これにしょっちゅう行っていた。
初め、痛かった奥歯をたちどころに治療してくれて、感激したのだ。
英国の歯医者は劣悪だと聞いた。
ロンドンで歯科治療を受けた場合、噛み合わせが悪くなることも
充分にあるらしい。語学力的に、細かく症状を伝える自信もない。
だから、歯医者に行かないために必死だ。
機会があれば歯磨き、歯磨き。
で、最後の難問は目である。
最近は目がかすむ。視力が落ちてきているのではないか。
基本的に英国の室内照明は暗い。
そしてホストマザーのダイアンは間接照明が好きなのだ。
ロシアとウクライナの戦争による電気料金の高騰は節電に拍車をかけた。
ますます、夜が暗い。
ひょっとして老眼か、とも思う。
早めにきているのかも知れない。
が、とにかく出来ることをしなければ、と思って最近は
スーパーでブルーベリーを買うことにした。
物価が高いのでブルーベリーも高い。
ひとパック400円くらいするが、仕方ない。
薬だと思って買っている。
残すところ4ヶ月である
英語に慣れ、知り合いも増え、色んなものを見聞きできたのは良いが、
この11ヶ月間の後遺症が残らないようにしなければならない。
2022年8月30日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑必ずしもヨーロッパ人が強気で日本人が従順なわけではないと思う。
救急医療で待ち時間4時間44分は、日本では許されないだろう。
が、皆さん、おとなしく待っていた。
研修先 The Albany Theatre のあるルイシャムは悪名高い。
多くの移民が住み、治安が良くないのだ。
知り合ったロンドンっ子に研修先を切り出すと、大概の人に
「気をつけて」と言われる。家のあるグリニッジは高級住宅街だ。
だから住所を伝えると「ラッキーだね」と言われる。
2キロくらいしか離れていないのだが。
そのルイシャムの病院に行くことになった。
ホストマザーのダイアンが私の不在中に救急車を呼んだらしい。
めまいがしてそのようにしたようだ。
Albanyが地区内の公園でやっていた野外の美術展示の帰り、
たまたま近くを通りかかっていた時に、ダイアンから電話があった。
日曜の21時くらい。それで家ではなく病院に向かうことにした。
結果的には何事もなかったが、
診察や血液検査にやたら時間がかかった。
何しろ、待ち時間表示に「あと4時間・・・」などと平気で出ている。
隣に「スタッフには待ち時間の詳細を訊かないでください」という
張り紙も。体調が悪そうな人たちがたくさんいたが、
これではさらに悪化を招きかねない。
ただし、これは日本人感覚だと思う。
スーパーも駅のチケット売り場も、そして病院も、
待っている人を気にすることなく一人一人に時間をかけるのが英国流だ。
待ち時間が長かったので、興味深い人たちをたくさん見た。
待っている間、大いびきをかいて寝ているおじさん。
若い女性は、苦しそうに姿勢を崩して床に倒れてしまったために
看護師たちが足を上げたりして応急処置しながら奥に運んでいった。
ネイルがやたらと長い女性が、高速でスマホを打ち続ける音が
待合室に響く。爪がスマホのモニターにカツカツと当たるのだ。
ずっとヘアセットをし合っている母親と娘。
震え続けている車椅子の老女。などなど。
極め付けは、警官二人を両脇に連れている男。
彼はプリズナー=囚人らしい。体調が悪いので仕方なく病院に
連れてきたらしいが、手錠も無く、一般人と同じ待合室で
待っていることに衝撃を受けた。軽微な罪なのだろうか。
それにしては、左右のポリスマンたちがゴツすぎる。
囚人さんは、あたり構わず周囲の人たちに話しかけていた。
まるで、人と話すことのできるチャンスを惜しむかのように
人の会話に割り込み、コミュニケーションのきっかけを拾い集めていた。
ずっと孤独なのだろうか。
ダイアンは温かいものが飲みたいと希望したが、
ロンドンに24時間営業の店やコンビニはほとんどない。
帰りもタクシーがなかなか捕まらず、夜中の1:30に往生した。
翌日はたまたま祝日だったから良かった。
劇場やイベントに行くより、バラエティ溢れるものを見た。
やっぱり好きだな、ルイシャム。
2022年8月26日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note
昨日はシニアたちの移動型演劇 "Monving Day"の
ドレスリハーサルだった。要するに、セットと衣裳を本腰入れてやる
本番直前の通し稽古だ。
この公演には赤組と黄組があって、
赤組は図書館で、黄組はショッピングセンターで、
それぞれの施設の中のさまざまなポイントを
演者と観客で動きながら鑑賞する。
今日は赤組の稽古だった。。
発表初日は9月1日だけれど、出演者であるシニアたちにも予定がある。
だから、昨日やって、手直しを8/31(水)にやったら、
あとは公演当日の朝にさらって本番。
こういう企画のためには知恵が必要だとつくづく思う。
豪華なセットやスタッフワーク、入念な準備というのは
コミュニティワークの一環として行う演劇には余計である。
それらはお金も人のかかりすぎる。
コストがかかりすぎると続かない。継続性が大切なのだ。
かといってチープなだけで良いかというと、絶対にそうではない。
本質的に訴えるものがなければ、
演じる側にも、観る側にも迫力を生まない。
これらをどう両立させるのかがクリエイターに問われる。
運営をしているエンテレキーアーツの面々は達者だと思う。
スタッフの一人、カミラは手作りで段ボール製のバナーを
作ってきた。良い出来だ。こういうのがパッとできる。
とても大事な素養だ。いちいち外注などしていられない。
代表のデイヴィット・スペンサーさんは、
俳優として出演することにした。物語の流れ自体は固定だが
せりふ自体は即興だから可能だとも言えるけれど、
人が足りないなら自分がやると言って自然に演者になる。
組織の代表が身をもって創作の身近さを示しているから、
みんなが安心して演じることを愉しむ。
演技や創作をすることに対する精神的なハードルが低い。
構成・演出を担当するレミーは巧者で、
劇の中に、出演者が個人史を語るシーンを盛り込んである。
誰だって過去には多くの問題があり、多くの問題を乗り越えた
あるいは、乗り越えられなかった経験がある。
真率なエピソードは人に届く。
そういう力を巧みに解放して武器に変えている。
本番では、自分も役割を与えられた。
移動中の演者のマイクの着脱を担当することになった。
こういうこともパッとやるのだ。
日本代表なので"そんなの簡単にできますよ"という風に平然と
引き受けているのだが、心中穏やかではない。
果たして上手くできるだろうか。
2022年8月25日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note 
昨日は書き物の一日だった。
年明けにケッチさんとテツヤ(岡島哲也P)と作る舞台の準備をしている。
イギリス民話『3びきのこぶた』を題材にしたサイレントコメディの
ステージを作る。それで構成台本を書いているのだ。
いつもとは逆で、自分の書いたものに意見をもらって書き直す作業だ。
自分はせりふの台本は書かないけれど、イベントの構成台本を書いたり、
依頼が来て寄稿したりすることは度々ある。
それぞれに、テレビマンにエッセイストになったつもりで書く。
書くことは苦しいけれど、後から考えると充実する。
震災の後に吉原町内会から頼まれてやった節分イベントの
出し物は自信作で、ステージを見ながら近所のおばちゃんたちが
「よく出来てる!」と褒めてくれた。
吉原なので、『助六』を題材にした。
よく唐ゼミ☆に出てくれている鷲見くんがヒロインの揚巻に扮して
鬼たちが襲おうとすると上半身はだかのレスラー姿になり、
プロレス技でやっつける。彼の立派なお腹に「フライド・ロール」
というリングネームが墨で書かれているという他愛もないもの
だったけれど、よくウケたな。
東京乾電池が初期にビアガーデンでやっていた出し物は
こんな感じだったのではないかと、自分なりに考えた。
エッセイの方は、最近は岩波書店の月刊誌「図書」に書いたものが
来月に出る。こちらは、ロンドンでの生活を読書に絡めて書いた。
語学学校が終わり、Albanyでの用事が無かったので、
ロイヤル・アルバート・ホールに行って夜の演奏会の当日券を買った。
その後、ベンチに座ってZoomでテツヤにアドバイスをもらった。
ハイドパークで書き直し、テツヤの寝起きに届くよう送った。
ロンドンにはたくさんの自然豊かな公園がある。
ハイドパークはその王様だ。ハイドパークに行くということが
休日の立派なイベントになるのだ。
宮殿やモニュメント、池やアミューズメントがある。
それ以上に、やたら広くて伸び伸びとした公園だ。
こういう公園の芝生に敷物を敷いて食事したり寝転がったり
するだけで休日や遊びが成立するのが英国人なのだ。
ハイドパークのベンチで、
周りで遊んでいる子どもたちを眺めながら、
とにかく彼らにウケたい、大ウケしたいと心から願って台本を直した。
その後、夜の演奏会は22:15開演だからやたらと時間があり、
公園の反対側の中古CD屋に久々に行き、厚遇してもらえて気を良くした。
初めてハイドパークやこのCD屋に来たのは渡英直後の寒々しい2月だった。
あの時は不気味で幻想的な感じもした夕暮れだったけど、
今はのどかな馴染みの景色になった。
あと4ヶ月ジタバタして、あっという間に帰国。
帰国後の仕事について、徐々に直面し始めている。
2022年8月24日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑外見からは何の建物かよくわからない。
誰もが気になりながら、
よく実態がわからないあの組織の本部がロンドンにある。
しかも、割と気軽に入れて、お土産物屋まであると言うのだ。
実は、この建物は渡英直後から気になっていた。
教会のような感じだけど、それよりはそっけない。
企業のビルにしては「売店開いてます」的な看板がある。
ロンドンの中心部にあるものだから、
あっちこっちと訪ね歩く際に何だろう?と気になってきたが、
あれがそれだとようやく気付いたのだ。
フリーメーソン。
モーツァルトが入っていたことで何より有名で、
この世界を操る真の黒幕とも、いやいや只の友愛を目的とした
紳士たちの親交団体とも言われている。
正直、自分はよくわからない。
よくわからないけれど、ライトな感じでとりあえず
行ってみた。行ってみておいて日本に帰り、
あるいはこの先、本など読むかも知れない。
その時に「あ、オレはあそこ行ったな」と思えれば、
とりあえずいい。
入口の荷物チェックは他より厳しめだった。
ロンドンでは、色々なところに出入りする際に荷物チェックを受ける。
でも、かなりかったるそうに係員が流し見ているのが実際だ。
けれど、ここはガッチリ、丁寧に、全てのジッパーを開けて
紹介した。
ホールがあって、時にはコンサートをやっているらしいけれど、
今日はその日ではないので、ギャラリーを観て、お土産物屋さんを
眺めた。展示の量はあるけれども、内容は自分にはさらりとした感じで
グッズショップは面白かったけど、節約しているから何も買わなかった。
この素っ気なさは不気味と言えば不気味だ。
何人かお客さんがいて、誰もが自分よりかなりお金持ちそうに
見えて、訳ありな感じに見える。けれど、無効にすれば
自分がそう見えているかも知れない。
謎である。深淵である。どうも底が見えない。
帰ってきてからも気になっている。
2022年8月23日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑ほんとうに善い人たちばかりなのだ。決してスノッブでなく、
素朴で人情味のあるご近所さんといった雰囲気の集い
自分がクラシック音楽を好きになったのは明確なきっかけがあって、
唐さんと同時期に横浜国大で私たちの先生だった大里俊晴先生と
許光俊先生の影響である。
大里先生は現代音楽が専門で、許先生はドイツ文学の研究に加えて
クラシックの音楽批評もされている。自分が28歳の時に
大里先生が亡くなって、学生時代を思い出しているうちに
色々と聴くようになり、好きになった。
ロンドンはウエストエンドに象徴される演劇都市だが、
それ以上に音楽都市でもあって、次から次へと世界的音楽家たちの
出入りがある。自然と方々へ出かけることになった。
で、BBCプロムスである。
イギリスを代表するこのクラシック音楽の祭典のことを
自分は3ヶ月前まで知らなかった。
が、何人かの人に「もうすぐプロムスだね」と言われて
その存在に気づいた。7月中旬からの9月中旬は欧米の年度末
=シーズンオフだ。この期間に国営放送のBBCの主催で毎日
コンサートをやり、ライブで観にくるお客さんを集めつつ、
放送にかけるという趣旨なのだ。
すでに自分は何回か行っている。
はっきり言って、超絶的な感動体験はありそうにない催しである。
会場のロイヤル・アルバート・ホールは5000人以上入るデカすぎる
場所だし、どうも音楽的に散漫な感じがするのだ。
でも、シーズンオフだから他はやっていないし、
豪華出演陣だし、珍しい曲もたくさんやる。
何より当日の立ち見席が安いので行ってしまう。
そんな感じなのだ。
昨日も出かけて行った。
ケルン放送交響楽団が目当てだった。
この楽団の印象は、ギュンター・ヴァント、若杉弘、
ガリー・ベルティーニという指揮者たちとともに覚えている。
CDで聴いてきた親近感にかられたのだ。
早めに行って当日券を買い、
アリーナ席の床に座り込んでPCで書き物しながら開演を待った。
すると、自分の周りの人々がやたらとよく喋る。
先に来ている人が、後からやってくる人を迎えて盛り上がっている。
そうこうするうちに、自分を真ん中に置いて5人くらいでお喋りする
恰好になってしまった。たまらないな、と思った。
が、開演が迫ってきたので、トイレに行くために話しかけて
荷物を見ておいてもらうようお願いしたところから、一気にその
均衡は崩れ、用を足して戻ると自分も輪に加わってガンガン喋り始めた。
聞けば、彼らは毎日来ているそうである。
何人かは仕事の都合で飛び飛びのレギュラーだけど、
中には本当の皆勤賞もいる。どうも、そういう通しのチケットが
あるらしいのだ。2ヶ月弱の間に、全部で72のコンサートがある。
ある女性は「本当にくたびれている。あと3週間もある」と
こぼしていた。だったらやめればいいじゃん、というのは愚問である。
とにかく来る。とにかく聴く。聴きすぎて記憶が曖昧になり
何が楽しいのかさっぱりわからなくなった果ての境地があるのだ。
昨日は日曜だったから、朝11時と19時半からの二本立てだった。
その間に何をしていたのか。家は近いのか。色々と気になったが
そこまで話し込む余裕はなかったし、語学力も足りなかった。
中には夜の回に続く、レイトショー的な回もある。
こういう時は23:30頃に終演する。自分も目当てのものがあって
1回行ったが、帰宅はかなり遅くなった。
友情が芽生えているようである。
次を訊かれたので、水曜に来ますよ、と言って別れた。
水曜のレイトショーが、ザ・シックスティーンというすごく良い
合唱団なのだ。常連と知り合ったことによりインセンティブが付き、
これからは今までより愉しめそうだ。初心者の自分としては
興味深い人たちだ。
肝心のケルン放送響は期待外れだった。
ブラームスの3番はあんなに淡白なもんじゃないはずだ。
1曲目の『フィンガルの洞窟』は良いぞ!と思ったが、
だんだん心が離れていくという珍しいパターンの鑑賞体験だった。
ケルンで聴いたらもっと凄そう。
2022年8月19日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑青いドレスの女性はメディアではない。メディアに殺されてしまう
王の娘が、このバージョンでは登場するのだ。女性二人が対決すると
笑いがいっぱい起きた。
結局、エジンバラから帰れなかった。
サヴァール二日目朝のコンサート(プログラムが違う)を終え、
機嫌よくエジンバラ駅まで歩く。悠々13:30には着くと、
電光掲示板のにはロンドン(キングス・クロス駅)行きが示されていた。
余裕じゃねえか、と思ってホームに行くと"電車は来ない"との表示。
おかしいなと思って見渡すと、電光掲示板によって言うことが違う。
ロンドン行きがあったり無かったり、時間も違うし、ホーム番号も違う。
このいい加減さ。
さすがイギリスだと思って駅員に訊いたら、
「今日はロンドンまで行くものはありません。
その手前のヨークやドンカスターで止まってしまいます」との説明。
その二つの街で高速バスを捕まえれば帰れるかも、
ということで駅員二人に協力してもらって粘り強く調べた結果、
ロンドンまで帰る望みは無いと判断し、もう一泊することになった。
現在、先週に泊まったドミトリーの三段ベッド。
真ん中の段でこれを書いている。これまで何度か泊まった時は
いつも最上段だったから、天井の低さが際立つ。
姿勢のバリエーションが少ない。暗いし、強制的に眠い。
朝のサヴァールはもちろん良かった。
1日目はマイク付きだったけど、2日目のコンサートは完全に
アコースティックで彼の演奏の美しさとニュアンスが際立っていた。
1日目を聴いたという高齢者女性に話しかけられて、
彼女がサヴァールと写真を撮るのに協力したりした。
頂いた名刺のメールアドレスに写真を送ったが、
どうやら彼女は画家らしい。ちゃんと届いていれば良いが。
それから、何となしに街をウロウロして
スコットランド国立劇場のギリシャ悲劇『メディア』も観た。
先週とは違い、夜になるとめっきり冷え込む。
北国らしい気候にヒートテックやネックウォーマーも
動員している。この1週間でフリンジに参加するパフォーマーたちは
かなりふるい落とされたようだ。ストライキによる来訪者の少なさも
手伝い、ちょっと路地に入ると閑散としている。
エジンバラは基本的に、落ち着いた渋い街だとよくわかった。
どこか物悲しげだ。
2022年8月18日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑写真を撮ってもらうことができた
昨日から再びエンジンバラに来た。
と言っても、一泊だけして今日帰る予定。
予定、と書いたのは訳があって、またぞろストライキなのだ。
だから昨日、ロンドンの玄関口であるキングスクロス駅で切符を
買おうとしたら、駅のチケット売り場の人に止められた。
明日はストライキだから帰って来れなくなるかもよ、
電車無しとは言わないけれど、数が少ない、
来週にすれば? とか言ってくる。
そんなこと言ったって、
チケットは買ってあるしホテルの予約もしてある。
「帰れなくなったらもう一泊します。ずっと立って帰るのでもいい」
と伝えたら「グットラック」と言って売ってくれた。
そういうわけで、これから帰れるかどうか不安である。
ロンドンに向かう最終が14:30ということは昨日に確認したから、
とにかく早めに来て待っているところだ。
通路でも何でも良いから、乗って終えば勝ちなのだ。
ロンドンまで4時間半。さらにロンドンに着いてから
全部歩く羽目になるかもしれないけれど、仕方がない。
エジンバラに着いたら、まず、先週に置き去りにしたパスポートを
回収しに行った。無事に完了。
それから、ジョルディ・サヴァールのコンサートを聴き、
日本ではソロか、せいぜい3人での演奏を数回聴いていたところを、
今回は彼が率いるエスペリオン21の総力戦を聴くことができた。
初日は14世紀に活躍したイスラム圏の冒険家イブン・バトゥータを
主人公に、彼の行動遍歴を音楽的に追ってみようという試みだ。
西はモロッコを出発点に東は東南アジア、中国まで行っていたらしい。
だからゲスト奏者に中国の琵琶や琴を弾く女性たちを招いて
いるわけだが、彼女らのソロパートにじっと聴き入り、かすかに頷く
サヴァールの物腰は、まるで仙人・達人のようでもあるし、
それでいてかなりエロいことを考えていそうでもある、
という具合なのだ。
↓すごい色男っぽいかった
これまで、東京で彼のバロック音楽演奏を聴いたことはあったけれど、
歴史上の人物や地域にまつわる音楽をジャンルを越えて追究する姿に
初めて生で接することができた。
(ドン・キホーテとかコロンブスとか、アルバムがいっぱいある)
今日、これから、18世紀初めのイスタンブールにまつわる
コンサートを聴いて帰る予定。ひょっとしたら帰れないかも知れないし、
ひどい帰り道になるかも知れないけれど、まったく後悔がない。
サヴァールは81歳、いつまで元気に演奏を聴かせてくれるのか
わからないのだ。
2022年8月17日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野WS『黒いチューリップ』 ワークショップ参加者や劇団ファンの人から
『黒いチューリップ』を読む上で重要でおもしろい情報が寄せられた。
ありがたいことだ。
↑
この写真のように、
かつてはこんな様子で人力で玉を出していたらしい。
今の複雑な構造を持つパチンコ台からは想像しがたいが、
このように隙間を行き来してスタッフが当たりを出していた。
(電話交換手みたいなもの)
↑座ってやるものという印象が強いが、かつては立って打つスタイルも
しかも、人力であるがゆえにこの玉出し係(正式名称は何だろう?)
の気まぐれで、気に入りの客にはちょっと多めに出すとか、
当たり前に行われていたらしい。
そういうわけで、
唐さんが『黒いチューリップ』で描いた描写はかなり
リアリズムであるということがいよいよ分かってきた。
ヒロインのケイコのように、
さすがにその場所に部屋をつくって棲みついている
というのは芝居がかった飛躍に違いないけれど、
エコーをからかってパチンコ玉が飛んでくる場面は
あながち嘘ではないということだ。
それに、天魔が鴉天狗のようにこの台の上の細い面を
駆け抜けてくる場面も、想像できる。
地方ならば1970年代くらいまでこんな感じの店舗が
見受けられたとも教わった。(Hさんに感謝!)
これからも情報があったら教えてください。
昔からパチンコ大好きでやり込んできた唐十郎ファンが
いたら、ぜひ話を聞いてみたい。
2022年8月16日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑今は枯れ果てているが、渡英直後はフサフサだった↓
ここ1ヶ月、ほとんど雨が降らなない。
日本にとってのゲリラ豪雨が異常であるように、英国にとっては
この干上がり方が異常らしい。
8月に入り、週に三日くらいは夜に家にいるようになった。
主だった劇場がシーズンオフになったのと、遠出の際にまとめてお金を
つかうために意識してそのようにした。
英国の就業体制は厳格だ。午後6時にオフィスが閉まる。
だから夕方に劇場を出てスーパーなどに寄りながら家に帰ってくる。
午後9時くらいまで明るいので、途中、公園のベンチに寝そべって
本を読む。2週間くらい前に初めてこれをやって、
我ながら優雅なものだと思った。日本では考えられん。
先週半ばから読み始めた『カンタベリー物語』は中巻に入った。
上巻では、作中の巡礼者たちはロンドンブリッジの南を出発し、
Albanyのあるデプトフォードとグリニッジを通った。
面白いものだと思う。
そんな風に読み進めていると、昨日は8時半頃から雨が降った。
イギリスの公園は大きくて緑が豊富だから、
まるで『トトロ』のように大木の下で雨宿りをして、
雨脚が弱まったところでさっと帰ってきた。
考えてみれば、公園も、家の周りも、あのおとぎ話のようだった
緑の豊かな芝生は、今ではすっかり痩せて、枯れた草が地面に
こびりついたような具合になっている。
明日も夕立があり、明後日は本格的な雨が降るようだ。
同時に気温もガクンと下がって、20度周辺で落ち着くらしい。
明後日にはもう一度エジンバラに行く。
今度こそ、避暑地としてのスコットランドを味わえるかもしれない。
パスポートも早く回収しなければ。
2022年8月15日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野WS『黒いチューリップ』 ↑パチンコ台の奥から部屋が現れた瞬間です。妙に安アパート風。
ひどくだらしなく寝ているようト書きの指示を守っています。
(2004年秋の唐ゼミ公演より)
昨日は『黒いチューリップ』本読みWSの2回目でした。
『蛇姫様 わが心の奈蛇』を経て『黒いチューリップ』に入った
タイミングでお久しぶりでご参加の皆さんが帰ってきてくれました。
別に演目のせいではないと思いますが、これはやっぱり嬉しい。
長編をやっていると、どうしても途中から入って来られる方には
敷居が高くなるとも思います。ロンドンにいる間は長いものを
予定していますが、今後、作品を選ぶ際の参考に思います。
あるいは、
以前に単発で『特権的肉体論』に取り組んだ回があったのですが、
一回こっきりで参加できる回を良いなと思います。お試しになる。
例えば、唐ゼミ☆だけでなく、近く上演が予定されている台本に
取り組めば、もっともっと上演が愉しめるようになるはずだ、
とも考えています。
さて、肝心の『黒いチューリップ』2回目。
今日は物語が徐々に動き始める場面をやりました。
前回はトップシーンですから、インパクトが大事だった。
100台が唸るパチンコ屋に100人の客がいる。
その喧騒の中を、声帯模写芸人のエコーがやってきて、
お客や景品ショップの婆さんに絡まれる、という趣向でした。
今回は、エコーがこのパチンコ屋にやってきた理由が徐々に明らかに
なります。
まずは、前回の最後のシーン。
勝手に玉が出てくる不思議な黒いチューリップ(当たり穴)の台の正体を
エコーは見極めようとします。思わず台を掴み、揺さぶる。
すると、この姿がインチキをしていると誤解を生んで、
釘師の「天魔(てんま)」と孫娘の「グリコ」が駆け込んでくる。
この天魔はカイマキ(着物型布団)を着ています。
グリコも薄汚い少女だという設定ですから、このパチンコ屋に
棲みついて働いているらしいことが想像されます。
そんな彼らからすれば、エコーの行為は許せない。
そして、誤解が解ききれず揉めているうちに次の登場人物が現れる。
パチンコについて一家言持ち、あっという間に100人の客を煽動してしまう
男の正体を、天魔は見抜きます。この男は刑事だったのです。
この刑事は伝説のパチプロ「一本指」を追っており、
一本指が自らの目印とした池袋の喫茶店ネスパのマッチを振りかざし、
一本指に憧れる他の客たちをますます煽ります。
実は当の天魔も、同じく一本指に身構えていたのでした。
近所のパチンコ店「アイウエオ会館」「アトム」「三角ホール」を
次々に閉店に追い込んだ凄腕・一本指に備え、ひどく厳しい釘設定を
仕掛け、強敵の襲来に備えていたことが明らかになる。
と、偶然その場にいたエコーを、この刑事は一本指だと思い込みます。
エコーが違うと言ってもそれを信じず、先ほどまで黒いチューリップ台と
親密に語らっていたエコーこそ、パチプロの中のパチプロと決めつけます。
皆の言いがかり、熱狂を恐れたエコーはその場を逃げ出し、
ほとんどの人間が彼を追います。
先ほどまでの喧騒が去り、静寂のパチンコ店内。
そこへ、エコーが忍び足で帰ってきました。
彼は黒いチューリップに再び語りかける。恋をささやくように。
(このあたり『ロミオとジュリエット』的です)
すると、パチンコ台が外れ、中から不思議な部屋が現れます。
ここには女が住んでおり、この黒いチューリップ台の玉は、
この女の人力で供給されていたらしいのです。
(唐さん得意の可笑しな設定!)
ここから、いよいよエコーの主目的が明らかになる。
初めは寝起きだったこの女「ケイコ」が身支度を整えると、
エコーは彼女に封筒を取り出します。営業で呼ばれた結婚式場の
女性用トイレで拾った封筒、その中に入る10万円が入っていました。
封筒に書かれたパチンコ店を頼りに、をエコーはお金を返しに来たのです。
大喜びするケイコ。
しかし、エコーは10万円のうち1万円を使い込んでいました。
前回に読んだシーンで、エコーは同居するサワヤカ少年の数学塾の月謝を
この封筒から失敬していたのです。
お礼の1割だと主張するエコーの理屈は彼女には通じません。
が、使い途が塾代と知った彼女は同情し、エコーにパチンコで1万円稼がせる
ことで穴埋めをしようとします。(ひどい癒着!)
というところまで、昨日はやりました。
蜷川さんと唐さんが気に入って展開してきた「六本指」というモチーフが
ここではパチンコにちなみ「一本指」に変化しているのも面白いところです。
あと、この芝居には「キス」という行為が象徴的な役割を果たします。
蜷川さんの商業演劇デビューだった『ロミオとジュリエット』は
キスばかり登場する芝居であり、「チュウ・リップ」という語呂合わせ
でもあるわけです。
次回は3回目。
血みどろの決闘も、強姦や近親相姦のような悲惨も、この台本にはありません。
この圧倒的なのどかさも、紛れもなく唐さんの面白さのひとつです。
読んでいて朗らかにたのしい。そういう特性を味わってもらえたらと思います。
2022年8月12日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note 
↑黒い服に黒い鞄で分かりにくいので、アップ写真も↓

昨日のゼミログを書いたのは帰りの電車の中だった。
エジンバラ〜ロンドン間は4時間半かかる。
東京から九州に迫ろうという時間だ。
日本にいたら長く感じるだろう。
飛行機で行こうかな、とも考えるだろう。
しかし、イギリスでは断固電車だ。
まず、景色に慣れていないから見飽きない。
そして何より確実性。
ロンドンにはたくさんの空港があり、
待ち時間があり、時間の調整があり、燃料代も変化する。
だったら、安定の電車。そう思っていた。
帰りの電車はうるさかった。
座った席が、ちょうど大家族に囲まれる具合だったために、
彼らがひっきりなしに行き来するし、頭越しに会話してくる。
イギリスの電車には必ず大騒ぎする人たちがいる。
どう処したら良いのか。物申して良いのか、自分にはわからない。
そんな中でゼミログを書き終えた。
すると彼らは二つ目くらいのニューカッセルという駅で降りた。
やれやれ。
と、この瞬間、気づいてしまった。
ずっとTシャツの中に忍ばせていた貴重品入れ。あれがない。
中には、これから観る公演チケット、国際運転免許証、
そして、パスポートが入っている。
しばらくゴソゴソやって、いよいよ手元にないことを確認する。
すると、アラン・カミング観劇中にチケットをしまうため、
客席で胸から取り出したことを思い出した。あそこに置き去り!
それから、ミミに電話し、劇場に電話し、
どちらも電話に出なかったので、問い合わせフォームに
メッセージを打った。
ピーターはその夜もエジンバラで演奏している。
明日、彼が回収してきてくれないかな、などと期待したが、
ともかく劇場に連絡をつけることが先決だ。
ちなみに、昨日に観劇したBURNはあの演目の千秋楽で、
夜公演はない。終演後、あの芝居が気になっていたピーターに
「ひどくつまらなかった」と3分くらいかけて悪口メールを打ったので、
自分は一番最後に客席を出た。だから係員以外に発見は不可能。
という好条件ではあるものの、ドキドキする。
結局、ミミにも状況をメールして、昨日はまっすぐ家に帰り、
夜遅かったので、シャワーを浴びて寝た。
ダイアンに「どうだった?」と訊かれ、「良かったよ」と簡単に伝えて寝た。
翌朝になりミミから返事があったので、どんな貴重品入れだったか、
羽田空港で撮った自分の写真などを送って説明した。
朝食時にダイアンに打ち明けると、涙目になって神に祈り始めた。
・・・やはり、昨夜に黙っていたのは正解だった。
ピーターに連絡を取ったが、彼は早朝からグラスゴーに移動していた。
今夜に別の演奏があるらしい。忙しいそうだ。
ピーター「帰りに戻ろうか?」と言ってくれたが、
見つかりさえすれば来週に自分で回収できるから安心してほしい。
そう伝えた。
すると、ミミが通常より早く電話で劇場オフィスをこじ開け、
話をつけてくれた。自分が送った写真も先方に送ってくれたらしい。
さすが劇場関係者。話が早い。あとはアツシで電話するべし、とも。
早速に先方の担当者とスピーカーホンで話し始めたところ、
横から猛烈な勢いでダイアンが喋り始め、あっさりと自分の物だと
確認された。「これはかなり重要ですね」と先方は笑っていた。
イギリス人のいい加減さに知り尽くすダイアンは油断がない。
相手が何日の何時に確かに劇場にいるかを確認し、
「変更があったら私に電話をしてくれ!」と迫っていた。
そういうわけで、今朝9:30をもって問題にはケリがつき、
巻き込んでしまったみなさんに現状と御礼を伝えて、
通常スケジュールに入っていった。
シニアの街頭劇の稽古に立ち会い、日本とZoom会議をし、
Albanyで会議をして、現在に至る。
2010年以来ファンになったフィルハーモニア管弦楽団の面々と
一気に繋がることができたので、浮かれたのだと思う。
ヤキモキした分、今日はやたら小銭を拾う。人生、正負の法則。
旅行時の装備について、もう一度考え直さなければ。
2022年8月11日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note 
↑一本目に観た子どもたちのための劇。素朴な感じの二人だったが、
主役の老人人形がフルに活きるよう計算し尽くされた造形だった。
最終日、エジンバラ三日目は二つの作品を観た。
1本目:A VERY OLD MAN with ENORMAOUS WINGS
シルヴプレさんが観たという人形劇を観ようと思っていたが、
道すがら、チラシ配りの女子が渡してくれたフライヤーを見て
ピント来た。開演は10分後だったが、急いで駆けつけて観劇。
しっかり者の女性とトボけた男性のコンビによる、
人形や映像、サンプラーを駆使したキッズプロだった。
と言ってもギミックではなく、マンパワーを主体として、
お客さんの想像力に訴える。ボケてニワトリ小屋に住む
老人に周囲のみんなが困惑するのだけれど、最後にはこの
おじいさんが天に召される。
最小限の規模に考え抜かれた美術の造形ひとつひとつが見事で
さりげない恰好のパフォーマーが周囲を活かしきる姿を
観ている側がどんどん好きになる公演だった。
2本目:BURN(詩人ロバート・バーンズのこと)
スコットランドの国民詩人にまつわる一人芝居を
同じく地元の名優アラン・カミングが演じるという趣向。
しかし、演出家がイフェクトを多用しすぎて、肝心のアランの
魅力が立ち上がってこない。観客は皆、くだんの個性派俳優を
観たくてきているというのに、もったいなかった。
実に嘆かわしい。最後に、緞帳の前に出たアランがカマチに
腰掛け、観客に語りかけるシーンがほんの少しだけあって、
初めからそれをやれよ!と思った。
ライティングとプロジェクションを組み合わせて、
彼の顔がよく見えない。重要なところで、
あまり上手いとはいえないダンスを見せられた。
体は鍛えられているが、そういうことではないと思った。
一本目と二本目の間に、韓国料理を食べようと思った。
学割の効く良さげな店を、昨日のうちに発見していたのだ。
が、開店までに時間があったので、木陰で寝そべってラジオを
聴いた。立ち上がると、近くのカフェからこちらを呼ぶ声がする。
ピーターとフィルハーモニア管最古参の女性奏者だった。
エレナーさんという方。日本に20回以上きたことがあるという。
席を勧められたのでコーヒーをご馳走になり、
かつてのボスであるジュゼッペ・シノーポリの話を聴いた。
昨日『ルサルカ』を観たのでオペラの話になり、歌舞伎について
訊かれたので、現在の市川猿翁が演出して、吉井澄雄さんが
ライティングした『影のない女』の話をして盛り上がった。
ロンドンに帰ったら、リハーサルを観にきなよ、と言われた。
北仲スクールをやっていた2010年にフィルハーモニアと
サロネンによる『中国の不思議な役人』を聴いてクラシックに
興味を持った。これもピーターのおかげだ。
ピーターが主宰するチェンバー・アンサンブル・オブ・ロンドンは
11月にプリマスで公演するということだ。
プリマス〜コーンウォール〜ミナックシアターの旅を
ここに入れようかと思っている。
エジンバラにはまた来週行く。
2022年8月10日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑24:30くらい。スリー・クワイヤーズ・フェスからエジンバラへ
ハードスケジュールを嘆くミュージシャンたち
3日間の滞在の真ん中に当たる昨日は、
泊まっているドミトリーに荷物を置き、軽装で出かけることができた。
まず、開園時間にお城に行ったら、すでに予約で入場券が完売していた。
明日もダメ。来週に来るから、持ち越そうか。
ただでさえ有名観光地の最盛期に来てしまった。
そこから朝ごはんを食べて、チケットを買いに行った。
エジンバラに限ったことでなく、英国での買い物は時間がかかる。
スーパーでも、駅でも、ボックスオフィスでも、窓口がフル稼働している
のは稀だし、何人並んでいようが受付の人が常にゆっくりなので
当て込んでいた時間の3倍かかったりする。
時間もできたし、あとがタイトにならないように。
1本目:ウィル・テルと悪い男爵
ケッチさんがアドバイザーに加わった子ども用作品。
女の子版ドン・キホーテみたいな話で、ウィリアム・テルに憧れる
少女が身の回りの品で英雄に扮し、悪の男爵の城を探し当てて
これを倒す。造形や動きで観せる。何回か、子どもたちをステージに
上げて助っ人として活躍してもらうことにより、彼らをどんどん味方に。
最後は全員でゴールした感じだった。
お金持ちの子どもたちが多く観に来ているのか、子どもたちの誰からも
エレガントでゴージャスな感じがした。
2本目:ラッカス(騒ぎ)
当てずっぽうに入ったこれは、女優の一人舞台。
男女のゴタゴタを描くせりふ芝居で、ゆえに置いて行かれた。
ファック・ミーと何度も吠えていた。うっかり最前列に座って
しまったので、眠らないように最後まで頑張って消耗した。
早すぎる英語を聴いていると眠くなる。
終わった後、キットカットを食べた。
3本目:一人でロード・オブ・ザ・リング
黒つなぎに地下たびの男性俳優が例の三部作を一人で、
1時間で演じ切っていた。あらゆる役と情景を声と体の動きで表現。
途中に起こるDVDの交換まで。頭空っぽで大笑いしながら観た。
第一部を映画館で観て、エンディングで三部作だと気づいたこと。
第二部を唐さんも観ていて、オーランド・ブルームについて喋ったこと。
第三部はヨコハマ・ウォーカーの葉書応募で当てて先行で観たことを
思い出した。一人で映画を演じるといえば、マルセ太郎さんも
思い出した。
4本目:歌劇ルサルカ
ドヴォルザークのオペラ。セットと照明、演出が良かった。
歌と音楽が先行するオペラでは、オーセンティックでない演出が
成功することは稀だ。どこか足りなかったり、やりすぎて素材を
邪魔していたり、訳わからなかったりするけれど、これは実に巧みに
一体化していた。巨大な蓋つきのセットで水底の世界を巧みに表現。
コミカルなシーンもふんだんにあって、けれども聴かせどころでは
この作曲家のフォークソング的に単純素朴な魅力が全開だった。
終わった後は、ピーター・フィッシャーの手引きでパブへ。
フィルハーモニア管弦楽団の女性ヴァイオリニストたちと
おしゃべりして、これまで来日コンサートで聴いてきた曲目を
伝えた。なぜかイギリスの地方都市であるポーツマスの話題になり、
昔、大里先生に教わったポーツマス・シンフォニアの話を振ったら
ピーターしか知らなかった。で、YouTubeでこのオケが演奏する
『ツァラトゥストラ』を彼らに聴かせたら、大喜びしていた。
あと、明日はイギリスの名優アラン・カミングの一人芝居を観る
と伝えたら、4人のうち誰も彼を知らなかった。
この人ですよ、とスマホで画像を見せたが、反応薄。
終いに「あ、アランはスコティッシュだ。私たちイングランド
だから知らないんだ」と皆が言い出して、冗談の中にイギリス人たち
の国民意識を知ることになった。
静かにシャワーを浴び、午前2時頃寝る。
2022年8月 9日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note 
↑ホルーリード・パークの崖の上
昨日からエジンバラに来ている。
有名なエジンバラ・フェスティバルに合わせてやってきた。
噂には聞いていたが、街に降り立って面食らった。
人、人、人。もう観光客がぎっしり。
街中の至るところにショーのチラシやポスターが貼り出されていて、
大きなものから小さなものまで、千や二千のプログラムが
ひしめいているのだと実感し、眩暈がした。
今回、私が目標に置いてきたものはわずか。
①ケッチさんに勧められブライトンでも観たジュリア・マシリーのショー
②ケッチさんがアドバイザーを務めたシアター・フェデリ・フェデリ
③ピーターがオケに加わっているドヴォルザークの『ルサルカ』
④清水宏さんが激闘したパブThe World's Endに行く
⑤エジンバラ城に行く
と、このくらい。
が、日曜日にロンドンでパントマイム「シルヴプレ」のお二人に
会えたことにより、目標が増えた。名優アラン・カミングが当地の詩人
バーンズの生涯を一人舞台にして公演しているらしい。
そこで、これを⑥に。
さらに、街で『一人でロード・オブ・ザ・リング』というポスターを
発見したので⑦。Summer hallという会場の演目が面白そうなので⑧。
朝からやっているパペットの公演を⑨とした。
到着から3時間で街を歩き、タイ料理屋に入ってこういう計画を組んだ。
その後は、なんだか人いきれにヘトヘトになってしまったので、
焦ってジタバタしないことにした。ジュリアのショーは22時頃に始まる。
3時間以上あるから、近くのホルーリード・パークに登ることにした
丘というか、山というか、崖というか。
数時間かかりそうだなと思ったが、麓で寝そべっているおじさんに
訊いたら「30分かからんよ」ということなので、歩き出した。
かなり簡単に辿り着き、フォース湾と市街地を眺め、
「アーサー王の玉座」と言われる岩肌も発見した。
なかなかの眺望で、『マクベス』のことを考えたり、
メンデルスゾーンの3番を聴いたりして頂上で1時間くらい過ごした。
降りるときに、一回転んで尻餅をついた。
筑波山でも、大山でも、降りるときはいつもこうだ。
ジュリアのショーは完成版というより、
エジンバラで観せるために刈り込まれていた。
ポップになっていて客席はウケていたけれど、
クリエイター力の発揮具合はブライトンの方が上だった。
ここには時間制限もある。なかなかに厳しい環境だ。
2022年8月 8日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野WS『黒いチューリップ』 ↑暴れるラムネ。懐かしい学生時代の上演です。
昨日は『黒いチューリップ』第1回WSの初回でした。
いつも初回は特に準備をして臨みます。
内容以前に、唐さんがどうやってこの台本を書いたか、
経緯や、当時の唐さんを囲む面々について話す必要があるからです。
が、昨日は出鼻をくじかれました。
恐ろしいZoomトラブル。ついさっきまで正常に稼働していたzoomが
いざ時間になって正式に入ろうとしたところ、インストールが必要だ
といきなり言い出し、慌てました。
皆さんに待って頂いて応急処置をし、
ブラウザから入る方法で何とか成立させることが出来ましたが、
冒頭がかなり滞ってしまいました。申し訳ないです。
終了後に最新版をインストールして正常起動を確認しましたが、
便利と思っていたテクノロジーの落とし穴です。怖い。怖い。
さて、肝心のWS内容です。
経緯については、こんな感じの話をしました。
・これまで蜷川さんと作ってきた作品のモチーフが生きている
→「六本指」「大人数の出演」「池」
・根津甚八さんと小林薫さんという看板を失った唐さんの試行錯誤
→李さんの相手役探しでもある
・前年に本多劇場柿落とし『秘密の花園』で活躍した柄本明さんの抜擢
・蜷川さんの商業演劇デビュー作『ロミオとジュリエット』がベース
・1980年に状況劇場が行ったサンパウロ公演から、南米の鳥
グアーチャロ(アブラヨタカ、Oilbird)のアイディアを得たはず
そこから冒頭シーンへ。
100人のお客がひしめくパチンコ屋から劇はスタートし、
主人公エコーのモノローグが始まるのが見事です。
エコーは売れない声帯模写で、パフォーマーとしての腕は
イマイチだが、声無き者の声を代弁するのに長けている。
だから「エコー」という名だとアピールします。
洞窟の奥に棲み、視覚は弱いけれど聴覚でコミュニケーションする
グアーチャロとの共通点にもここにあり、この劇のテーマを強く
打ち出すシーンでもあります。
それから、景品交換所の婆さんとぶつかります。
※後に「サキ」という名だとわかる彼女、「咲き」からきています。
そこから水が異常に噴き出すラムネ瓶と取っ組み合ったり、
エコーがもともと持っていたセブンスターのタバコを巡って、
婆さんに難クセをつけられたりします。
パチンコの玉とお金をいきなり交換することはできないので、
パチンコ店ではキーアイテムと玉を交換、それを少し離れた場所に
ある景品買いに買い取ってもらうことで現金化するシステムについて
話しました。このパチンコ店では「セブンスター」が交換のアイテム。
婆さんの意に従って100人の客がエコーのセブンスターを奪い、
人々の手から手へ渡ります。そして、必死でそれを追いかけるエコーは
一台のパチンコ台を壊してしまう。それこそ、黒いチューリップ
(※「チューリップ」とはパチンコ玉が入る当たり穴のこと)を持つ
壊れた台でした。物言わぬ黒いチューリップに、否応なく惚れ込むエコー。
と、ここに、エコーの同居人である少年サワヤカ君がやってきます。
彼の爽やかさはパチンコ店にたむろする客たちを慄かせ、エコーを守る。
けれど、二人が暮らすアパートの家賃とサワヤカの通う塾の月謝の滞納が
明らかになります。特に塾で学ぶ数学については熱心なエコーは危機感を
募らせ、懐に忍ばせた訳ありの封筒から、一万円を取り出してサワヤカに
渡します。去っていく少年。
すると、一人になったエコーの前に新たな不思議が起こります。
壊れたパチンコ台、黒いチューリップの口からジャラジャラと玉が出てくる。
しかも、まるで生きているように戸惑うエコーとやりとりしながら。
明らかに誰かが隠れている。そう思わせながら冒頭シーンはおしまいです。
ひしめくパチンコ台と大人数の喧騒。
ビンから噴き出るラムネを使ったギャグ。
というスペクタクルから、一気にパチンコ台の当たり口にフォーカスという
極小の対象にフォーカスする唐さんの着想が冴えています。
グアーチャロというモチーフは難しいけれど、それもおいおい明らかに。
次回、第2回のzoomは特に念入りにバッチリにして臨みます!
2022年8月 5日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note 
↑Lewisham Shopping Center 内部
昨日は、シニアたちと進めてきた街頭劇の稽古が
(と言っても建物内での公演だが)いよいよ本格化した日だった。
会場は慣れ親しんだルイシャム・ショッピング・センター。
ここが本番の会場であり、中のメインストリートとかギャラリー、
Albanyが今年のフェスティバルに合わせて構えたフリースペースなど
複数箇所を使って劇の各シーンが進行する。
構成・演出のレミーのテキパキとした指示のもと、
まずはどの会場でどの場面を演じるのか、それぞれで動きを
付けながら当たっていく作業が続けられた。
いつもの稽古は90分強だが、今日は2時間半以上やったので
最後にはシニアたちもくたびれていたが、開放的で賑やかな空間に
やって来られたことに誰もが嬉しそうだった。
実際、やりとりも活き活きしてきた。
もちろん、昨日の稽古はセンターの許可を得てやっているが、
普通のお客さんが往来する場所で稽古は進められ、自然と衆目が
集まったり、赤ちゃんに絡まれたりするのも面白かった。
警備員が、それとなく見守っているようだった。
思えば、自分のこのショッピング・センターに対する思いは
この半年で劇的に変化してきた。初めてここを訪れたのは渡英2日目。
中にある郵便局にビザカードを取りに来るというミッションが
あったからだが、あの時ははっきり言って怖かった。
治安への不安、言葉の壁が立ちはだかる。
政府から届けられた郵便を受け取るだけの作業にぐったりした。
それが、ダイアンの家に住み始めた頃から、
この場所はあらゆる買い物が安く便利に住む場所になった。
日用品から衣類、食料品まで、ほんとうに何でも揃うのだ。
この中にあるH&MとTK-Maxxxの服で自分の春夏秋ものを買った。
Wilkoというホームセンターでタオルや傘、歯磨き粉を買う。
他にも、パウンドランドがある。
アイスランドという、いつもオレンジジュースを買う定番の店も
すぐ近くにある。油断は禁物だが、安心していられる場所になった。
本番は9月の上旬、二日かけて3回行われる。
あと3回のリハーサルで公演だ。恐るべきスピード。
2022年8月 4日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note 
↑アーネスト・ダウスンの墓参を終えた。
明らかに誰にも顧みられていなさそうだったので、年内に再訪し、
掃除してから帰国しようと思う。
※今日は生々しい話になるので注意してください。
昨日は久々にハードなやつが来た。突然に。
ダイアンには、ロンドンでは道で話しかけられても絶対に相手を
するなと厳命されている。しかし、習慣というのは拭い難いもので、
ついつい立ち止まってしまうのだ。相手もまた、
そういう自分を見透かして声をかけるのか、とも思う。
Albanyの近くで、黒人の女性に声をかけられた。
30歳くらいだろうか。彼女は私を呼び止め、
ワンピースのすそに付いたたくさんの血を見せながら
2ポンドくださいと頼んできた。
生理がきてしまったので生理用品を買いたい。ということなのだ。
オレは英語がわからん!ごめん!
と言って振り切ったが、なかなかの威力だった。
その後、最近ピーターに教わったレバノン料理屋に行った。
鶏肉をタレに漬け込んで焼いたものに、ライスとサラダが付いて7ポンド。
こちらにしてはリーズナブルな値段で味が良く、量が多い。
何より焼き方が優れている。
炭火の管理をせっせとして、うちわであおぎながら焼いてる。
焼き加減を確認するしぐさは日本の鰻屋そっくり。
調理が雑で、基本的に焼き過ぎパサパサのロンドンでは珍しい丁寧さ。
肉がジューシーなまま出てくる。さすがピーターの紹介。
昨日しくじったアーネスト・ダウスンの墓参りも達成できた。
開園時間中の霊園に入ったところ案内がないので、しばらくウロウロした。
物言わぬ墓を探すのは難しい。まして藪の中みたいなところに
いくつもの墓石が見える。暑いし、虫が多いし、植物も棘だらけなので、
そういう場所を探すのは至難の技だ。今が冬であれば!
今日もダメかと思いながら、
向こうからやってきた数少ない通り掛かりの人に訊き、
通常は留守中の管理室に施錠にやってきた係員にも訊いて、
やっと発見できた。
ダイアンからもらったあじさいと文庫本を備えて手を合わ、。
ヘタクソな英語で彼の代表作を誦じた。
昨日の彼の誕生日を祝いに来た者は自分だけのようだった。
清々しい気持ちである。
その後に冒頭の女性に声をかけられ、
今日も一日、ふんだんに人間を味わった。
来週はエジンバラに行く。今週はできるだけ大人しく
リーズナブルに過ごして、エジンバラに備えよう。
2022年8月 3日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑この霊園のどこかにアーネスト・ダウスンは眠っている
昨日は収穫なし!
それなりにウロウロしてさまざまなことに手を出したが、
どうも決め手に欠いた。
早朝に日本とのzoom会議をし、
それからAlbanyでシニア向けWSに参加し、合唱の練習をした。
その後、久々に墓参りをしようと計画していた。
「風と共に去りぬ」「酒と薔薇の日々」という言葉を生み出した詩人
アーネスト・ダウスンの墓参り。私は15年くらい前に出た彼の短編小説の
ファンなのだが、彼がルイシャムで生まれ、死んだ人だと渡英後に知った。
生家のあたりも、亡くなった場所も、家から歩いて行ける距離だ。
ライムハウスというテムズ川沿いの街で家業の船着場を
営んでいたらしいが、ここも電車でよく通る。
仲間たちと遊び歩いたソーホーも、簡単に想像できるようになった。
さらに調べると、家から4キロほどの墓地に彼は眠り、
8/2が誕生日ということだった。普通は命日だろうが、
亡くなった2/23は過ぎてしまったから、ひとつ、誕生祝いを
してやろうと思ったのだ。ダイアンの庭からあじさいの花を一輪もらった。
しかし、午後に急に会議に参加することになり、
4時半頃にやっと劇場を出て5時過ぎに霊園に到着すると、
門はすでに閉まっていた。4時閉園なのだそうだ。早い。
そこから、多少はジタバタしたが、結局どうもにならなくて
仕方なく出直すことに。
それから、ロイヤル・アルバート・ホールに行った。
6月にオールドバラ音楽祭でパトリシア・コパチンスカヤの
ショスタコーヴィチ ヴァイオリン協奏曲1番を聴いて凄かったので、
同じ曲を違う団体と共演すると知って行ったのだ。
が、このホールはデカ過ぎ、しかも満員のために音響はさらにデッド。
BBCプロムスに集まるお客の騒々しさで、6月に比べるとかなり
貧弱で散漫なものになっていた。それでも、さすがは彼女の熱演で
多くのお客が熱狂していたけれど、やっぱりあの空間を牛耳ったとは
いえない出来だった。
というわけで、何か煮え切らない1日だった。そういう日もある。
それは分かっているが、期限付きの滞在においてはいかにも無念だ。
2022年8月 2日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑この大聖堂と奥にいる合唱隊が主役なのだ
先週末、7/30(土)は特別な日だった。
ちょうど渡英から6ヶ月。あと5ヶ月を残しているけれど、
こと音楽鑑賞に関してあの日を超える体験はないと思う。
そう断言できる。
2ヶ月前まで、Three Choirs Festivalそのものを知らなかった。
自分がロンドンで聴いて気になった団体がこれに参加すると
知ったところから、この音楽祭の存在を知った。
ヴァイオリニストのピーター・フィッシャーに訊いたところ、
歴史ある音楽祭らしかった。そして、名門フィルハーモニア管弦楽団の
一員として彼も舞台に上がることが分かった。
日曜の朝はWSだから、土曜日の最終日は立ち会うことができない。
そう思っていたところ、ピーターは「絶対に最後の夜のエルガーを
聴くべきだ。コンサートが終わったら、一緒に車で帰ろう」と
言ってくれた。別にエルガーを好きでもなく、聞き覚えのない
曲が演奏されるらしかったけれど、言われるがままに予約した。
↓ピーターよ、ありがとう。
木曜に当地に行き、いくつものコンサートを聴くうち、
演奏の素晴らしさだけでなく、音楽祭のコンセプトもわかってきた。
イングランドとウェールズの間あたりに、
ウスター、グロスター、ヘリフォードという都市がある。
どれも大聖堂を持つ古い街だ。聖堂に合唱隊は欠かせない。
だから、合唱を主体にしたフェスティバルが始まった。
1715年にスタートし、各都市が持ち回りで会場となる。
だから、3年に1回わが街にやってくるのだ。
今年はヘリフォードという街が会場で、そこに行った。
面白いのは、アマチュアの合唱隊が舞台に上がることだ。
ただし、オケもソリストも超一流が集まる。
アマチュア団体が渡り合えるのかと思うけれど、渡り合う。
大聖堂のアコースティックが、彼らを支えている。
それに、8日間の期間中のラインアップがすごい。
1日のクライマックスを飾る曲目だけ並べるとこうだ。
7/23(土)ドヴォルザーク『レクイエム』
7/24(日)マーラー 交響曲4番
7/25(月)George Dyson『クオ・ヴァディス』
7/26(火)ハイドン『天地創造』
7/27(水)Richard Blackford『ピエタ』
7/28(木)Luke Styles『ヴォイス・オブ・パワー』(世界初演)
7/29(金)プーランク『スターバト・マーテル』
7/30(土)エルガー『ゲロンティアスの夢』
現代曲、新作、マイナー曲、何でも来いのラインアップ。
要するに2日目を除いて合唱隊はフル稼働。
メインじゃない演目の中に合唱曲が際限なくある。
教会だから、夕方のお祈りもこなす。
曲を覚え、歌いこなすだけでも大変なのに、
コンサートだから、当退場や演奏中の起立・着席・移動など
段取りも無数にある。それをみんながこなすのだ。
ものすごく厳しいことを言えば、アンサンブルやソロパートが
弱い時もある。けれど、大聖堂という音響装置が彼らを昇華させる。
何より、これだけの過酷な連続技をこなす彼らはゾーンに入っている。
一年をこの8日間のために研鑽しなければ不可能、
というくらいの音楽祭だった。
プロの力と、アマチュアの献身や情熱、
この場所でなければ!という音響空間とローカリティ、
それぞれの良いところが溶け合っていた。
最後の夜に演奏された『ゲロンティアスの夢』は、
死の恐怖に慄く爺さんが神に救われる、という『ファウスト』の
終盤だけをやるような物語だった。エルガーはこの地で全盛期を
過ごしたらしく、銅像もあった。
地元の人たちにとっては、このオラトリオはこの地が誇る聖曲らしかった。
教会だから、見切れどころか、ステージが完全に見えない数多くの席も
びっしりと超満員で、すごいひといきれだったけれど、みんな陶然として
聴いていた。合唱隊が、主人公を導く天使になったり、苛む悪魔になったり
しながら大活躍して、彼らが主役の音楽祭を表現を以って示していた。
終わった後、聖堂の中で、周囲の庭で、合唱隊も、演奏家たちも、
普段は近寄り難いソリストたちも、そこここでおしゃべりしていた。
音楽鑑賞に関して、このイギリス滞在の紛れもないピークだったと確信している。
あれから二日間。夜は家にいておとなしく本を読んでいる。
身体が余韻でいっぱいだし、お金もかなり使ってしまったのだ。
分厚い音楽祭のパンフレットを何度も見返している。
英語の歌詞を読んで、自分が聴いたものの意味をもっと知りたくなる。
特別な夜の力は、今も生きている。
↓ゲロンティアスを歌ったニッキー・スペンス。
強靭な声を生み出す体格だけでなく、ミサイルのような頭のかたちも凄い。
2022年8月 1日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note 3人のあやとりが広がっていく。友情に溢れたエンディング!
(撮影:伏見行介)
昨日は『蛇姫様 わが心の奈蛇』WSの最終回でした。
この大長編が、どうやって大団円を迎えるのか
10人で読み込みました。
物語は、ヒロインあけびの父親探しを基調にしています。
自分の父親は誰か。自分はどこから来たのか。
前回、バテレンが過去を暴きたてる場面をやりました。
朝鮮戦争中にアメリカ兵の引き上げ船「白菊丸」の中で起こった出来事、
そこに居合わせた人が誰で、あけびの母を集団で強姦したのは
誰だったのか。それが、あけびの父と思しき人物であるはずです。
本物の伝二が登場し、薮野一家が死に絶えていたことが知れると、
これまで伝二を騙っていた男は李東順(り とうじゅん)を名乗ります。
薮野一家の面々もニセモノが居座っていたと暴露される。
ここからが昨日のシーン。
まず、あけびが畳み掛けます。
肝心の部分がハングルで書かれた母シノの日記を読み解けば、
李東順を名乗り、薮野一家だと言い張る男たちは朝鮮人かと思いきや、
そうではなく、彼らもまた日本人だというのです。
このあたりの事情が込み入って非常に分かりにくいとWS参加者から
問い合わせがあったので、よく整理をして重点的にやりました。
こういう質問というか、オーダーは、こちらも助かります。
細部をいい加減にせずに、まずは筋立てて考え抜くことが大切です。
整理しながら、
朝鮮戦争が起こっていた1950-53年に朝鮮半島から15歳で引き上げて
くる日本人がいるとすれば、それはもう太平洋戦争の残留孤児に
違いない。そういう推理を立てました。
・・・が、唐さんはこの問題に回答を与えていません。
突き詰めて考えていくと、伝二を騙り、李東順を名乗る男、
あけびの父親らしきこの男が何者か、決定的な尻尾が掴めない。
朝鮮人かと思いきや日本人かも知れない。
しかし、やっぱり究極的な正体が判らない。
・・・だから彼は「蛇」なのです。正体不明な「蛇」なのです。
考えた末に、
「蛇」は「蛇」であり、「蛇」は「謎」である、
と今回は結論づけました。
あけびの父親は巨大な「謎」なのです。
これはなかなか唐さんの素敵なところだと感じます。
「蛇」で強引に押し切る。考え抜いて尚、辻褄を合わさせない。
これでいい。これがいい。
結局、この謎の男は大蛇になって天に逃げました。
かなり破天荒で強引な幕引きです。スペクタクルを駆使して、
強硬に逃げ切っている。だからあけびの謎は解けずじまい。
あけびも小林も落ち込みますが、
最後に、もう一度まむしに噛まれたタチションを、
あけびは再び身を挺して救います。
目標の探偵事務所取得は遠ざかる一方ですが
小林はあけびを励まし、あけびはタチションと3人で事務所を
やろうと提案します。これで、タチションを加えたトライアングルが
完成します。
最後は、1幕で小林とあけびの出会いのきっかけになった
スリのやり合いを、今度は3人でやってエンディングを迎えます。
皆、スリへの用心のために赤い紐をつけているから、
3人を頂点に、赤い紐はキレイな三角形を描く。
この物語は終始、どこか子どもじみています。
「お姫様ごっこ」を思わせるのどかさで全体が進行する。
大人の男女関係や友情は複雑ですが、
3人は子どもの世界に生きてるからこそ、このトライアングルが可能です。
友情パワーにより、唐作品の中でもかなり幸せいっぱいのエンディング。
三ヶ月かけてやってきた長編もこれでおしまいです。
皆さん、ありがとうございました。
唐ゼミ☆にとってかなり手応えの大きかった作品なので、久々に思い出しました。
来週から10月の半ばまでかけて『黒いチューリップ』をやります。
唐作品の中ではそれほど有名な演目ではありませんが、
唐十郎流に「引きこもり」を追究する物語です。
蜷川幸雄さんと行ってきた一連の作品群の最終形でもある。
ポップで面白い台本です。ぜひ参加してください!
2022年7月29日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note 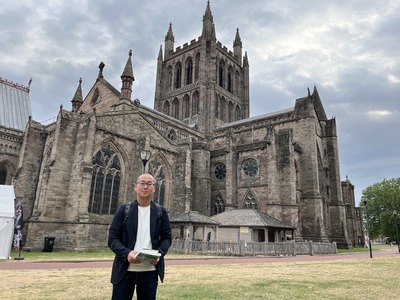
↑ヘリフォード大聖堂
昨日から旅行している。ロンドンに戻るのは日曜の早朝。
英国の真ん中あたり、ヘリフォードという街を中心に
行われている"スリー・コーラス・フェスティバル"にやってきた。
この音楽祭、
これまで全く知らなかったが300年以上の歴史を持ち、
周辺の3つの都市が持ち回りでメイン会場を受け持つことから、
こういう名前だという。当然、コーラスに力を入れている。
これに興味を持ったのは、
前にウィグモア・ホールで聴いたフレットワークという
ヴィオール集団がきっかけだった。
面白いと思った彼らがこのフェスに参加する。
それでフェス自体が気になるようになり、
ピーター・フィッシャーにどんなものか問い合わせたところ、
彼もフィルハーモニア管弦楽団の一員として当地に逗留、
演奏を連続的にするということだった。
こういう話を聞く過程で、メインが合唱ものだとわかったし、
スケジュール的な事情もあって、当のフレットワークは諦め、
フェスティバルが最高潮に達する最終3日間を狙うことになった。
問題が多かったのはホテルの予約だ。とにかく予約が取れない。
超高額か、車移動なら宿泊が可能なテント泊というのを音楽祭が
推していた。それとて、結構な値段だ。
考えてみれば、ヘリフォードの人口は5万人。
そんなところに普段からたくさんホテルがあるわけはない。
それに、出演するミュージシャンたちが先に近場を押さえている
に違いない。そのような事情から、自分が泊まるのは電車で
30分ほど移動した先にあるラドローという街に落ち着いた。
こちらは人口1万人強。さらに田舎だが、古城で有名らしい。

↑ラドロー城
まずはラドローに着いて古い城を見物してから、
ホテルにチェックインして荷物を置き、ヘリフォードに来た。
ラドロー城は良かった。先日に観た『リチャード3世』。
あれに殺されてしまう二人の少年王子が出てくる。
兄の方が、主人公であるグロスター公リチャードの兄
エドワード4世の長男にあたる。
彼はこのラドロー城で帝王学を学んでいたところ、
父の死の報せを受け取り、王位を継承するためにロンドンに向かった。
そしてロンドン塔に幽閉され、例の叔父さんによって殺されてしまう。
また、『ヘンリー8世』で離婚させられてしまう賢妻のキャサリン。
あの人もこの地の出身なんだそうで、なかなか高貴な場所のようだし、
実際に行ってみて、その雰囲気はかなり伝わってきた。
そしてヘリフォード。コンサートのメイン会場である大聖堂の立派さ。
これは規模と美観において、渡英以来随一と断言できる。
こんな田舎に、忽然とこんな立派なものがあるなんて。
そういえば、神奈川県には寒川神社がある。
相州一宮というくらいだから県内で格式が高さは抜きん出ている。
そして寒川町はこの神社を頂くことで、横浜市民の私から見ても、
かなり自信満々な感じがするのだ。

↑寒川神社(去年の12月)
似ている。
ちょっとした中庭なども古い建物と植物が一体になり、
よく手入れされていて抜群に美しい。
フェスティバルのために周囲に建てられた運動会用テントや
仮設トイレは美観を損なっているけれど、それにしても壮麗だ。
帰るのは日曜の早朝。あとまるまる二日間、滞在する。

↑ヘリフォード大聖堂のコンサート開演前
2022年7月28日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note 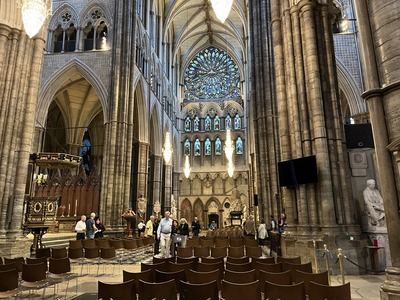
↑ウェストミンスター寺院は11世紀に造られた。パーセルが生きた
時点ですでに500年の伝統を持っていた
ヘンリー・パーセルの生没年は1659-1695年だから、
約36年の短い生涯だった。
衛生環境、医療、栄養、あらゆる条件が劣悪だったから、
子どもが成長するのが大変だった時代だ。
実際、パーセルの子どもたちは1歳に満たず何人も亡くなった。
彼の父親もウェストミンスター寺院に勤めた音楽家で、
ヘンリーの息子も同様だったらしい。職業選択の自由はない。
面白いのは、要するに国家公務員的ミュージシャンである
彼の一生が条件闘争の連続だったことだ。
さして多くはない給料はすぐに未払いになる。
さらに、国王に随行して音楽演奏する際、移動費が自費負担に
ならないよう交渉したともいう。
つまり、それまでは出張費を自分で出していたのだ。
出かけたがるのは王様なのに、あまりに理不尽だ。
このように、当時の労働条件はなかなか過酷だったらしい。
制服にあたる衣裳が擦り切れると、これを新調するための折衝が始まる。
17世紀後半といえば、エリザベス1世の統治時代を経て、
国王が斬首されたクロムウェルのピューリタン革命も乗り越え、
王政復古がなされた時代だ。王室の財政も不安定だった。
王が旅先から帰ってくる時、パーセルは様々な詩人の詩に曲を
つけて王を迎えた。オード(頌歌 しょうか)というやつだ。
くだらない詩もあれば、優れた詩人の作もある。
それからもちろん、教会でのセレモニーのために
アンセムをつくった。讃歌とか祝歌とかのことだ。
今回のロンドン滞在中、
沢山の教会のイブニング・コラールに参加してきた。
オルガン演奏からスタートし、開会の挨拶、懺悔の言葉、
ここから合唱と神父(牧師)や会衆(氏子総代?)による
詩篇朗読が繰り返される。合唱団と神父さんが対話的に
歌う時もあって、まだ規則性や手続きの順番を完全には
掴み切れていない。
こういう時に立つ。こういう時は座る。
こういう時はひざまづく。一緒に歌を歌う。
最後に寄付を(自分はほんの少し)する。
全部見よう見まねで、ワタシは外国人です!
という空気を振り撒きながら参加している。
いずれ立派に手順をこなせるようになってから帰国したいけれど、
この時点でも、パーセルが何のために曲を作り、オルガンその他の
楽器を演奏し、時にはバスとカウンターテナーで歌ったのかが
想像できるようになった。
彼は一生をずっとウェストミンスターの周りに住み、職場とした。
ロンドンを離れるのは国王の随行時だが、上記のことから想像するに、
そんなに生やさしいものではなかっただろう。
食事中の演奏を所望され、聴いても聴いていなくも演奏し続ける
という習慣が当たり前だった時代だ。
パーセルは劇場用の曲も作ったから、これまではそちらに惹かれてきた。
『ディドとエネアス』の他に、『妖精の女王』『アーサー王』
『テンペスト』『インディオの女王』などを好きで聴いてきたけれど、
今回の滞在を通じてオードやアンセム、王や女王の死に捧げた葬送曲を
もっと聴いてみたくなった。
作曲の経緯が経緯だから、似たり寄ったりの曲がたくさんあって、
駄作も傑作も入り乱れているらしいけれど、とにかく聴いてみたい。
生で聴いて、録音で確認して、そういう繰り返しの残り5ヶ月に
なると思う。
2022年7月27日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑ようやく訪れたウェストミンスター寺院の入り口で
ロンドンに住んで足跡を訪ねてみたい人が何人かいる。
①ウィリアム・シェイクスピア(劇作家、俳優)
②ウィリアム・ブレイク(詩人、画家、彫版師)
③レジネルド・グッドオール(指揮者)
そして、④ヘンリー・パーセル(作曲家)である。
もともと、パーセルのことは、
横浜国大でお世話になった茂木一衛先生に教わった。
先生は私が大学入試を受けた時の面接官の一人で、
おかげで唐さんに師事できたと思っている。
だからという訳ではないが、先生の退官講義の時にはお手伝いを
させてもらった。そしてその講義についてあれこと打ち合わせする中で、
『ディドとエネアス』というオペラがあることを教えてもらった。
それから幾つものCDを聴いて、今をときめく
テオドール・クルレンツィス指揮のものを気に入った。
彼の指揮もさることながら、ヒロインのディドを演じる
シモーネ・ケルメスという歌手に惚れ込んでしまったのだ。
唐さんはよく、歌いすぎたら語れ、と言う。
せりふが流暢になってくると、ついつい歌い上げてしまう。
劇中歌もやはり、メロディに飲まれて歌いすぎてしまう。
それでは良くない。
それでは、言葉が言葉としての意味や魅力を失ってしまう。
役者の喋り方、歌い方というのはやっぱり言葉が基本だ。
優れた役者はリズムは韻律を持って聴かせるものだけれど、
心地よいだけでなく内容が観る人の胸に迫るためには、
語ることが必要なのだ。
そこへいくと、このシモーネ・ケルメスという人の在り方は
そのお手本のような感じだ。確かに歌っている。
けれども、まるで話すように、喋るように歌うのである。
メロディと詩が一体になって攻めてくる。
だから、いつか彼女の実演を聴いてみたいと思い続けている。
で、ヘンリー・パーセル。
先日、椎野からパーセルの伝記を含む荷物が届いた。
数年前に、神田の中古レコード屋で見つけて買ったものだ。
渡英前に日本でも読んだけれど、正直あまり面白くなかった。
彼が生きた17世紀後半のロンドンや教会がまったく想像できなかった。
内容が入ってこなかったのだ。
が、今はこれがめっぽう面白い。ロンドンに住んで多くの教会に行った。
コラール・イブニング(夕べの祈り)に行くと、本当に珍しい合唱や
オルガン曲が山のように聴ける。しかも、ところによっては無料。
メディア的に有名な音楽家でないにせよ、
腕達者なオルガン奏者や歌手がゴロゴロいて、しかも、
教会建築という音響装置にかかると、その魅力が何倍にも増幅される。
そうこうするうちに、本に書かれているアンセムやオードが
どういう歌で、教会のオルガニストがどういう仕事か、
体感的に想像できるようになってきた。親しみが湧くようになった。
パーセルはイギリス王室の寺院であるウェストミンスター周辺で
生まれ、暮らし、この寺院を職場とした。
長くなったから二日に分けよう。
また、明日。
2022年7月26日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑少年少女のためのプレイグラウンド。日本だったら"危険"とみなされる
に違いない。
今、馴染みのカフェDeli-Xで暗然としてこれを書いている。
長らく愛用してきたリュックサックのジッパーが壊れたのだ。
これは、椎野が彼女の父からプレゼントされたもので、
それを借り続けているうちに自分のものになった。
5年以上は世話になってきたと思う。それが、ついに壊れた。
英国に来て以来、特に荷物を満載にする機会が多かったのが
負担だったのだと思う。ダイアンに訊いて、修理してくれそうな店を
何軒か訪ねたが、いずれも無理だと言われた。残念だが仕方がない。
週半ばから遠出するし、アウトドア系の店で大きくて丈夫なやつを
買いたい。都心のあたりでセールとかやっていれば良いが。
ところで、先週末のAlbanyは壮絶だった。
二つのフェスティバルに同時開催するというスタッフ泣かせの
スケジュールが強行されたのだ。
一つは、"Liberty Festival"。
ロンドン市長の肝入りで予算がついた障害者のための祭典だ。
パフォーマーたちは皆どこかに障害がある。彼らによる表現を
立て続けに観せようという企画だ。
どのプログラムも周到に組まれたスタッフワークがあって見事だった。
自分の観たものを挙げると、
①2038年時点の地球の環境破壊をSFテイストで物語る、知的障害者たちに
よる自由奔放な野外劇。その完璧なコスプレの絶叫の破壊力。
②芝居がかったガードマンの案内で、音楽学校の教室を巡りながら
聾者、聴覚障害者、少年たちのダンスを見て回る移動型上演。
③車イスの男性ダンサーと、その上に乗った女性ダンサーの
アクロバティックなダンス。また、雲梯を駆使して足の不自由なダンサーの
上半身のパワーを最大限に活かした振り付け。
④義足の女性ダンサーが複数の義足や車イスを操りながら見せる
脅威のスローモーションを展開。
⑤トランスジェンダーかつダウン症のコスプレ5人チーム
その名も「ドラッグ・シンドローム」による歌とダンス。
⑥車イスと聾者の女優二人が、映画俳優としてデビューする過程を描く
ストレートプレイ。
⑦劇場周辺の高架下などで、瞑想やフォークソングをくり広げる
視覚障害者のためのお散歩企画
⑧稽古場に完全なリラクゼーション空間が出現し、そこで全ての人々を
リラックスさせる瞑想企画
など。全ての企画に立ち会えた訳ではないが、粒ぞろいだった。
そして、二つ目はルイシャム地区が主導する"Climate Home"。
これは、温暖化をはじめとする異常気象を強く訴える
青少年たちのプログラムで、この夏いっぱいをかけて開催される。
そのフェスティバルのオープニングが、金曜に行われた。
会場が実にユニークで、学童のプレイグラウンドなのだと説明された。
木で造られた要塞のようなアスレチック群の真ん中に、そこだけ屋根の
ついた野外ステージがあり、観客は好きな場所に腰掛けたり、
スタンディングで見る。
ダンスや歌などもあったが、一番見事だったのは
10歳くらいの少年少女がひとりずつ披露するポエトリーだった。
自身の主張を詩に変え、これを謳いあげることに
日本人は馴染みがない。しかし、こちらの人々は実にこれを巧みに
実践し、また聴き手としても喝采を送る。さすがシェイクスピアの国だ。
少年たちはまったく臆することなく、自作の詩を韻律に乗せて披露していく。
そして高らかに歌い切った後は、拍手を浴びて興奮のあまり
アスレチックを駆け回っていた。
チームに分かれて運営に奔走しているAlbanyスタッフが心配になる
企画数だが、内容だけでなく、さまざまな空間を新たに発見できた
という意味でも、面白い体験だった。
これらは公金を投下し、入場料無料でやっている。
だから、思い切った実験的企画が多かった。
お金を稼ぐための企画、地域貢献のための企画、
CEOギャビンによる切り分け、メリハリの付け方が見事だと思う。
唐ゼミ☆で野外劇をやったりした際、いつも空間を探してきた。
日常の中にハッとさせられるような場所はあるものだ。
そういうことを知っているから、よりAlbanyの面白さが分かる。
けれど、同じように問題があって、
こういうもので収益を上げたり、芸術として評価したり、
批評を得るのは難しい。そういう話を、チーフプロデューサーの
ヴィッキーとした。面白いけれど、ロイヤル・オペラ・ハウスや
ロイヤル・シェイクスピア・カンパニーと同列に語られない。
あるいは、同列に語る必要がない、という違う評価軸が整っていない。
これからの仕事である。
↓野外でリサイクルの重要性を訴える、その迷いない力強さ。突破力。
2022年7月25日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野WS『蛇姫様 わが心の奈蛇』 Posted in
中野note 
↑本物の伝治が登場して、ニセモノが暴かれる。胸には骨壷。
その中身は本物の薮野一家の骨。しかし、こんな格好で働いている人は
この世にいないだろう。これも唐十郎流のギャグ(撮影:伏見行介)
昨日は『蛇姫様 わが心の奈蛇』WSでした。
謎解きが立て続けに展開し、劇の興奮が高まっていくシーンです。
唐さんの筆も乗っているし、その勢いに任せて読んでいけば面白い。
けれども、ところどころ、唐さんの強引すぎる設定を味わいながら読むと
さらに面白い。もちろん、唐さんは、そういうことをわかって書いています。
辻褄の合わなさをシャレにして笑い飛ばしています。
まず、二つの映像を見るところから始めました。
天知茂主演 明智小五郎VS怪人二十面相の予告編
https://www.youtube.com/watch?v=DU2nSdNmYY4
片岡千恵蔵主演 多羅尾伴内シリーズ 正体を明かす場面
https://www.youtube.com/watch?v=xkheg50m3rw
これらを観ておくと、唐さんが思い描いたノリや
造形がよく見えてきます。両作とも、演技が二枚目すぎて笑いの域に
達しているので、おもしろ動画としても楽しめます。
その上で、
ドラゴン=鏡 という引用元不明の理論。
小林と伝治の対決による、小林の敗北。
バテレンの加勢が序盤。
というシーンが展開。
そしてここから、バテレンの壮大な謎解きが始まります。
まとめてみると、
①伝治はニセモノである
これまで伝治を名乗ってきた男はニセモノだと暴かれる。
彼は白菊丸に乗って密航した男で、当時は12歳。
シノが輪姦されるのを見ていたに過ぎない。
ちなみに、バテレンは従軍牧師として乗船していた。
②本物の"伝治"は日本人
小倉で乳飲み児(あけび)を抱えた恩人
シノを世話した。その東京に出て薮野一家の居候をしていたが、
脳卒中で倒れ、今は半身に障害を抱えてバスの整理係をしている。
シノが送った写真を、自分のニセモノになる男にユスられる
③薮野一家もニセモノである
大きい兄ちゃん(蛇)、文化や青色申告、知恵も密航者。
三年前に死に絶えた床屋の薮野一家を乗っ取った。
内縁は、もともとの薮野一家で生き残ったお婿さん、
だから文化たちを恐れている。
④白菊丸で起こったこと
シノが輪姦されたことは間違いない。
しかし、ニセモノ伝治が加わっていたかは不明。
バテレンは、当時12歳だった少年にそれは無理だという。
一方、ニセモノ伝治本人は満15歳だったと主張。
そのため、相変わらず自分はあけびの父親かも知れないと強硬に主張。
真の名前は「李東順(りとうじゅん)」
※唐さんによる「李東順」という名の引用元は不明
・・・と、このように、さまざまなロジックが展開します。
シリアスとコミカルが激しく交錯して、真剣なのかふざけているのか
分からないのがポイントです。劇的なやり取りが連続しながら、
あけびの出生がますます謎めいたことは確かで、
だからこそショックを受けた彼女は三度目の癲癇の兆候を見せます。
次の7/31(日)で最終回。かなりの力技で大団円に突入します!
2022年7月22日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑間違いはここで起きた
ロンドンで生活することを本気で想定し始めたのは年明けだった。
呑気なものである。1/31渡英が決まっていたものの、
用意されているのは文化庁が用意してくれる航空券のみで、
ビザが降りたのが1月半ば、渡英後に宿泊するホテルの予約を始めたのも
同じ頃だった。
他にも、コロナ対策として、
パッセンジャー・ロケーター・フォームの記入とか、
ホテルに政府公認の抗原検査を送るとか、さまざまな手続きを
すべて松の内があけてからの同時期に仕留めたと記憶している。
デビットカードの存在と重要性に気づいたのは、
1/20前後だった。それまで、海外に長期滞在する経験の無い私は、
自分の手持ちのキャッシュカードは、世界の大都市のどこでも
通用すると思い込んでいた。
2種類を愛用しているうち、横浜銀行はややローカルだが、
UFJはメガバンクだ。ロンドンはほとんどキャッシュレスと聞いていたし、
たまにおろせばいいんだろと高を括っていた。
しかし、何かの拍子に知ったのである。
ロンドンでは国産キャッシュカードによる引き出しができない。
デビットカードというものが必要だ、と。
早速に申し込んだ。
出国までに届かなければ、荷物と一緒に送ってもらえればいいやと、
この後に及んでも軽く考えていたが、果たして6日ほどで
ピカピカのカードは届き、晴れてデビットカードを持って
日本を出られることになった。
結果的に、これが功を奏する。
床屋とか、カレー屋とか、こちらでも稀に現金のみの店がある。
もっとも重要なのが、ダイアンに家賃を払う時だ。
彼女の主義は、ニコニコの現金払いなのだ。
もちろん、当初は彼女の家に居候することになるとは知るよしも無い。
で、先週の日曜である。
オペラのマチネを観た私は、いつもの電車を乗り継いで
上機嫌で帰ってきた。こちらでは滅多に昼の公演を観ない。
だから、帰り道にまだ陽が高いのが嬉しかったのだ。
調子付いた私はATMに立ち寄ることにした。
そろそろ月末、来月分の家賃をおろしにかかったのだ。
ところが、スムーズにお金が引き出せない。
こちらのATMは色々と質問してくる。
言葉は何が良いか、とか。
手数料に納得できない点があるか、無いか。
レシートが要るか、要らないか、などと。
その日に選んだ機械は妙にしつこかった。
これらの質問が煩わしく感じながら操作するうちに、
私は自分が使っているいくつかのパスワードのうち
間違った方を連打してしまった。結果、お金が引き出せない。
まあ、連続でミスったから、時間を置くか、
悪くても翌日にトライすればいけるだろうと、その日は諦めて帰った。
そして翌日にもう一度試す。が、このカードは使えない、の一点張り。
別のATMでも同じ反応だった。
仕方がないので日本に電話すると、
「暗証番号番号の誤操作が続いたので、ロックしました。
これを解除するには、ご本人様が帰国後に直接、銀行に来てください」
ということだった・・・
対応窓口の女性の声が持つ、圧倒的な機械的物言い。
ラチがあかないことは明白だった。
・・・というわけで、渡英前にテキトーに作って、
2月に横浜の家に届いていたネットバンクの口座のデビットカードを
椎野に送ってもらうことにした。
ここにもいくつかのハードルがあって、
いくつかの郵送サービスのうち、最も速いものに限ってこういった類の
カードや重要書類が送れないとか、あらゆる郵送物に戦争の影響で時間が
かかるかと、クレジットカードからチャージしたお金は買い物はできるが、
現金をおろすことができない、とか。
要するに、このネットバンクの口座に、他の口座から振り込みを
行った金額のみ現金化できる、というルールがあることがわかった。
椎野にも迷惑をかけながら試行錯誤して、やっと目処がたったけど、
手元にカードが届くのは半月くらい先になりそうだ。
それまで、ダイアンに家賃の支払いを待ってもらっている。
ごめんよ、と言って、彼女の好物のスモークサーモン550円相当を
渡したら喜んでいた。
2022年7月21日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑テンプル・チャーチにて。会が終わったあとはワインが振る舞われた
昨日はぐっと気温が下がって最高でも30度いかないくらいだったが、
寝ようとするとじわっと自分の体が熱を持っていることに気づいた。
日焼けだ。日本にいた時みたいに窓を開けっぱなしにして
寝たいところだが、それはダイアンによって禁じられている。
うちは一階にあるので、セキュリティを慮ってのことだ。
暑くて寝られないというほどではないが、
朝起きて、窓を全開にした。そしてこれを書いている。
昨日はせわしなかった
学校→WS"Moving Day(シニアたちの街頭劇創作)"
→New Earth Theatreのクミコさんに会う
→テンプル・チャーチでコラール・イヴニング(夜の讃美歌)参加
→帰り道に電車を間違えて、かなり時間をかけて帰る
→その間にひたすら本を読む
という具合だ。
WSのシニア参加者の出席率は半分以下だった。
まだ外出への警戒が解かれていない。が、秋の本番に向けて
配役の発表がなされ、外部から参加する若手の役者も加わって、
稽古の密度が明らかに上がった。
役が決まったことによる興奮が伝わってきた。
その後、New Earth Theatreのクミコさんに初めて会った。
6月に『ソニック・フォー』という、ベトナム料理を食べながら
在英ベトナム人の語りを聴くというユニークなイベントに参加した縁で
「会って話をしましょう」と声をかけて頂いた。
初対面だったけれど、一所懸命しゃべってお互いの興味を理解し、
今後、さまざまな案内をくれることになった。
ちなみに、彼女のお母さんが日本人とのことだったが、
日本語は喋れないそうで、もちろん英語で頑張った。
そして、走ってデプトフォード駅に行き、
電車でブラックフライヤーズに移動。テンプル・チャーチまで急いだ。
夕方のお祈りは18:00から。別に信心はないが目的は二つ。
教会建築を見ることと、声楽曲を生で聴くこと。
今回は大当たりだった。「ロンドン 教会」とググると、
ウェストミンスター寺院、聖ポール寺院と並んでここが出てくる。
建築的にかなり立派だったし、合唱団のレベルが高かい。
女声4人による完璧な倍音と教会の反響で陶然としたり、
カウンター・テナーまで擁しているのに贅沢を感じた。
帰りがけに知ったが、英国のレーベルからいくつかCDも出ている。
ウィリアム・バード、パレストリーナ、バッハの音楽を聴けた。
セレモニーが終わると神父様(プロテスタントだと牧師様)の
話がある。何軒もの教会の儀式に参加して気づいたが、
どの人も必ずスピーチで笑いをとる。彼らの人格の柔和なこと。
笑いの基本である緊張と緩和の典型例だということでもある。
かのテンプル騎士団によって造られたという教会の内部には
展示コーナーも充実していて、見応えがあった。
もちろん、テンプル騎士団といえば、唐さんの劇『河童』を
思い出す。テンプル騎士団が天ぷらを揚げるというシーンがあった。
開催時間1時間という軽めの鑑賞体験だったから読書がはかどった。
『ユリシーズ』3巻目を読み終わって、いよいよ最終4巻だ。
週末までに読み終わりたい。
2022年7月20日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note 
↑22:15開演→23:00終演という大人の集まりだった。帰りは涼しかった。
昨日は火曜日恒例のWS"Meet Me"だったが、オンライン化された。
最高気温40度というあまりの高気温であったために、シニアたちに
とって劇場に来るプロセスそのものが危険と判断されたためだ。
そこで、スカイプによる電話ミーティングが繰り広げられた。
要するに、ビジュアル無しでグループ通話をしたのだ。
Zoomやモニター付きの会議でないのは、
シニアたちのメディア環境に配慮してのことだ。
みんな、電話には慣れている。
結果的には1時間以上も話していたために、
皆さんの腕や耳が疲れないか心配したが、それは大丈夫だそうだ。
このあたり、パンデミックのロックアウトの経験が生きている。
話題として、来年の"Meet Me"10周年をどう祝うかが
話し合われた。そう。この企画が誕生してから、間も無く
10年が経つのだ。参加者たちから次々にアイディアが出て面白かった。
・それぞれの家族を巻き込みたい
・それぞれの出身地・出身国の特色を出したい
・お世話になってきたボランティア・スタッフにお礼がしたい
・これまでを振り返るレトロスペクティブがやりたい など。
初めてこの企画に誘われて参加した時のエピソードを
話し始めるシニアもいて、感慨深い話し合いだった。
10人強のメンバーずつ、2グループに分かれて、
約1時間ずつ行われた。
その間、私はずっと家の、自分の部屋から会議に参加していたが、
今日はダイアンの友人一家が泊まりがけで遊びに来る日で、
隣の部屋でパーティーめいたランチが繰り広げられた。
休憩時間にあいさつした。
会議を終えて近所に買い物に出た。日用品を買う。
あまりの直射日光と気温だから、日本から持ってきた
善光寺の笠を付けた。
買い物をするたびに店員に話しかけられるので、
これは日本の風習であると伝えた。我が国ではみんな被っている。
夏の常識である。特にこのモデルは最近の流行りである。
という具合だ。
それから、ベトナム料理屋にも行った。
ベトナムには似たような笠「ノンラー」があるから
親近感があるらしかった。米食民族同士、親しみが湧くのだ。
そして、このままBBCプロムス行く。
ハーフパンツに善光寺笠だが、やむを得ない。
昨日、ロイヤル・オペラ・ハウスでハーパン・Tシャツを
何人も見かけたので、強気である。
カジュアルにクラシックを愉しむ。それがBBCプロムスなのだ。
郊外に住むミミの家の近所では、山火事が自然発生しているらしい。
2022年7月19日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note 
↑暑さがもっとも伝わりやすいからこれを選んだ。撮影は先日の土曜
日本の終戦記念日を思わせる暑さである。
快晴。真上から直射日光が照りつき、影が短く、濃い。
40度近くまでいっているらしい。おかげで街から人がいなくなった。
ロンドンは涼しいと思い続けてきたが、今週は暑さのケタが違う。
当地に住む人たちにとってみれば、これは異常事態のようである。
この気温は、仕事を休むに足る立派な理由だそうだ。
そのようなわけで、今日はWSも打ち合わせもキャンセルされ、
午後はフリーになってしまった。
お金持ちは都会を離れ、所有するカントリーハウスに行ったという。
9月を以って任期を終えるボリス・ジョンソン首相も例外ではなく、
自身の別荘で、お得意のパーティーをまた開いたらしい。
コロナ禍の度重なるパーティー開催により国民感情を逆撫でした彼は、
すこしも臆することなく昨日もこれを続けている。筋金入りのパリピ。
本気になって怒っているイギリス人には言えないが、
私はそんな彼が嫌いではない。
皆の家は暑くて仕方ないという。
学校も、劇場も、両方の友人たちが口々にそう言う。
暑くて寝られない、昼間は家にいられない、そういう状態らしい。
ところがダイアンの家は、冷房もないのに何故か涼しい。
分厚いレンガの壁と、二重サッシのおかげだと思う。
ここにきて、都心の居心地が良い。
普段は人で溢れかえっているのに、何しろ人がいない。
閑散としていて気持ちが良い。暑いことに違いはないが、
自分の地元、あの蒸し蒸しする名古屋と同じくらいだと思う。
Albany近くのカフェでミネストローネを食べ(夏野菜!)、
馴染みのパイ&マッシュの店でサイドメニューである
ジェリード・イール(うなぎ!)のみをオヤツに頂く。
そういう充実の食事を摂って、今日もロイヤル・オペラ・ハウスへ。
演目は『オテロ』。
私が買ったのは2,000円程度の立ち見席だが、
お金持ちたちは15,000〜30,000円くらいの席を軽々と放棄する。
必然、私の目の前には幾つも空席が現れ、開演と当時に、
これにサッと座るのがロンドン流。
日本では考えられないが、より良い席が空いていた場合、
こちらの愛好家たちは躊躇なく席を移り、
よほどマナーが悪くなければスタッフがこれを見咎めることもない。
むしろ、幾つかの劇場では、最安席に座っている人を、
案内係が率先して前に移るよう促してくることすらある。
ルーズというか、余裕というか、ロンドンはゆるい。
とここまでが昨日のこと。
今日の気温は41度まで上がると言っている。観測史上、最高だそうだ。
2022年7月15日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note シェイクスピアの故郷を旅行して気づいたのだが、
Tシャツの数が足りない。私は毎週土曜日に洗濯することにしている。
が、手持ちの半袖が6枚しかない。
これまでは必ずに肌寒い日があったのだが、
遠出の時には洗濯日もズレ込むだろうし、余分も持って
おいた方が良い。というわけで、Tシャツを買い足した。
場所は気に入りのルイシャム・ショッピングセンター。
カフェやレストランが高いイギリスだが、服は高くない。
増して貧しき者の味方のルイシャム地区なので、
良いものが買えた。
しかし、英国ではほとんどのTシャツが柄モノかロゴ入りだ。
私には、どこのブランドやメーカーか分かるものを着るのが恥ずかしい。
やっと無地を見つけたと思っても、胸にポケットがついている。
Tシャツの左胸のポケットに何か入れている人を
私は見たことがない。あれは、なんのためについているのか。
さすがのロンドンも暑くなり、30度を超える日が頻発するように
なった。それに伴い、ダイアンが庭の植物を心配している。
最近の私は、通学前にアジサイに水をやるようになった。
根っこの部分だけでなく、葉っぱや花びらの部分に上から水をかける。
日本ならば根腐れするほどの量を容赦なくかける。
それでも、あっという間に乾燥する。これが英国の気候だ。
語学学校では、トルコ人の女子がやたらと話しかけてくるようになった。
彼女の上半身は常に水着のような格好だが、手にはいつも毛皮の
カーディガンを持っている。暑さ寒さに極端で、中間部が全くないのが
面白い。露出度の高いロンドンの人々の中でも、彼女の極端さは
際立っている。
辛いものが食べたくなってインド料理屋に行くと、
今日は店員だけでなく、オーナーもいるのを発見する。
彼は面白い人で、店に入る時、食べ終わって出る時、握手を求めてくる。
今日はアレが美味かったと伝える。インドの梅干みたいなやつを
付けてくれるようになった。暑さの分だけ、美味く感じる。
バケーションを重視するヨーロッパ人にあって、
今年のAlbanyは特殊だ。一年間のフェスティバル期間中、
夏が最盛期なので、フル稼働する予定なのだ。
今日も目前のイベントへの準備が優先されて、定例会議が中止になった。
皆、顔を真っ赤にして働き続けているが、土台、働き方に対する
意識が進んでいる分、この先、誰かが音を上げるのではないか。
野外イベントが増えるに伴い、
私が渡英時に持ち込んだ善光寺笠の出番が迫っているのを感じる。
あれを日本で付けているとたいそう目立ったものだが、
こちらでは大したことがないように思う。
人種だけでなく、人々の格好も、こちらはバリエーション豊かだ。
2022年7月14日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note 
奥さん、アン・ハサウェイの実家。目下読んでいるジョイスの
『ユリシーズ』では、彼女は徹底してエロ女扱いを受けている
いま思い返してみると、
ストラトフォード・アポン・エイボン行きは完全に修学旅行だった。
だいたい、修学旅行生が多い。あの様子はおそらく中学生だろう。
街に溢れかえっていると言って良いレベルだった。
私もベタなコースを回った。
シェイクスピアの生家、彼が成功者として買った屋敷跡。
勉強し、初めて旅回りの劇団の芝居を見たという学校。
友人たちの家の跡、埋葬された教会、奥さんの実家。
こんなところだ。そしてエイボン川に浮かぶ白鳥を眺め、
川沿いを歩く。
必然的に、どこもかしこも修学旅行の群れ。
彼らのほとんどはシェイクスピアに興味無いだろうが、
イギリス人はこうして国民作家に通じる教養をインプット
されるのだ。私たち日本人が誰でも奈良の大仏を知っているように、
彼らはいくつかの劇のタイトルを言えるくらいに仕込まれるのだ。
ケータイでシェイクスピアが育った家を撮影していたら、
「私たちのことを撮っているでしょ!」と女子中学生に
怒られたのも面白かった。イエゼンタイヲトリタイ、と
訴えてどいてもらった。
あと、学校の案内をしてくれたおじいさんが熱心すぎて
大幅に時間を取られてしまったこと、それと、
昨日、水曜日は特別に教会の営業時間が短く、
結果的にシェイクスピアのお墓参りができなかったのは残念だった。
ウィリアムと妻アン、二人の実家の距離感や、
ともにお金持ちの出であったことを実地に確認できたのも良かった。
そういうことは、彼の描く恋愛に、必ず反映されてしまうものだと思う。
予約した安めのホテルは居酒屋の2階で、
それだって物価の高いイギリス、観光のメッカたる当地では
1万円くらいかかったけれど、これも趣きがあって良かった。
観劇を終えて帰ったところ、開け放しにした窓から大量の虫が
入ってきていたが、部屋を暗くしてあっという間に追い出せた。
何か、旅籠屋という言葉を思い出させる宿泊だった。
名古屋の小学生として、京都・奈良県物をしたことを思い出した。
とてもおもしろかったです。
2022年7月13日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note 
RSCとはロイヤル・シェイクスピア・カンパニーのこと
昨晩、この劇団の本拠地ストラトフォード・アポン・エイボンで
『リチャード3世』を観た。結果、期待したほどではなかった。
この劇の魅力はタイトル・ロールを演じる俳優に依存するところが
大きいと思うけれど、さほど惹かれなかった。
何より、この劇場の構造が良くないと思った。
どう良くないかと言うと、同じシェイクスピアを専門にする
グローブ座と比べると判りやすいと思う。
自分はグローブ座が好きだ。
先日に書いた通り、特に『ヘンリー8世』は最高だった。
けれど、グローブ座が好きだとロンドンで劇場関係者に言うと、
意外に思われる。「あそこは観光施設だからね」という
コメントも即座に寄せられる。
だから、私は好きなのだ。
あの劇場の役者たちは、観光客を相手に闘っている。
正確に言うと、闘わなかったりもする。
まるでうらぶれた芸人のようにやる気がないかと思えば、
急に大熱演して場内を盛り上げ、また急速に意気をしぼませたりする。
要するに、緩急を心得ているのだ。
それに、人間としての自然の姿があって、好感が持てる。
要するに芸能、大衆演芸的なのだ。
そこへいくと、RSCも街ぐるみで観光客を相手にしているが、
彼らは芸術家っぽい感じで、どこかお高い。
劇場は近現代風で、中身もそうかと言えば、ステージ様式は
グローブ座と同じ張り出しを採用しており、演出家の美学が
あらわれにくい。この辺が中途半端なのだ。
何より重要なのは、シェイクスピアは明らかに大衆演芸路線の
作家だということだ。私はグローブ座で、なぜこの作家が書く
台本にラブシーン、下ネタ、残酷シーン、決闘が多いのかを知った。
あれは明らかに、野外上演で途切れがちな集中をつなぎ止め、
庶民で構成される客席のウケを狙ったものなのだ。
チケット料金の取り方や客席の様子も違う。
グローブ座は、舞台近くの立ち見はすべて5ポンド、
椅子席には25〜75ポンドをとる。そして観劇中も飲み食いできる。
野外なので、完全暗転はないし、昼の上演は明るい。
RSCは全て椅子席で、ステージ近くが高くて最高値が65ポンド。
安い席でも40ポンドする。中には10ポンドの席もあるが、
これは柱で視界がさえぎられる席だ。客席は暗く、
周囲に迷惑をかけないように飲み物を口にすることはできる。
ちなみに、双方ともにせりふが徹底的に上手い。
このあたりはさすが専門家だ。
世間の評価は逆だろうけれど、私にはグローブ座の圧勝に思える。
この後は『テンペスト』『ジョン王』『ヘンリー5世』
『タイタス・アンドロニカス』が控えている。
『タイタス〜』では、我が子の死体でつくったミート・パイを母親が
食べてしまうシーンを、観客を大爆笑しながら観るのではないか。
残虐極まりないがゆえに、突き抜けすぎてギャグになってしまう。
芝居とシェイクスピアの不思議な魅力、その真骨頂だと思う。
2022年7月12日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note 
↑車窓からは山羊が見えた。シェイクスピアは田舎の小さな村から
世界に挑んだのだ
リチャード3世のことである。
今、ストラトフォード・アポン・エイボンに向かいながら
これを書いている。午前中にAlbanyのシニア向けWSを終えて、
ロンドンを飛び出した。シェイクスピアの故郷で、
これからロイヤル・シェイクスピア・カンパニーによる
『リチャード3世』を観る。
現地に到着してから開演までさほど時間は無いだろうから、
各所を見て回るのは明日だ。
そういうわけで、先週末は読み進めていた『ユリシーズ』を一時中断、
シェイクスピアの伝記と『リチャード3世』の台本をおさらいした。
思えば、高校2年の時に初めて読んだシェイクスピアがこの本だった。
以前より格段に面白く読めた。
ロンドンに暮らすことになって5ヶ月半。
台本を読みながら、彼が王位を手に入れるため、あるいは、
望みを叶えてからは逆賊を退けるために、いかに素早く立ち回ったか、
実地に想像できるようになっていることに気づいた。
何にもの邪魔者に矢継ぎ早に死を与え、
同時に、必要な人間は最短距離で口説き落としている。迅速だ。
史実としては、リチャードはもっと時間をかけて
一手一手、策を実行に移していったのかもしれないけれど、
シェイクスピアのスピード感は5日間くらいの出来事のように感じさせる。
ロンドン塔、聖ポール寺院、ホルボーン、
ベイナード城があったブラックフライアーズ、
戴冠をしただろうウエストミンスター・・・・など、
新宿区の端から端までの広さをひたすらかけずり回っている。
「ロンドン、街路」とあるだけのト書き、今まで無味乾燥だった
このト書きが色彩を帯びて、豊かに想像できる。
そこここに、忙しなく行き交っては足を止め、持ち前の饒舌を尽くす。
そんなに広くないセントラル・ロンドンをコマネズミのように立ち回り、
口八丁と切った張ったで人生を切り抜けていったことがわかる。
後半の敵軍との闘いのために進軍した場所も想像できる。
最近は英国地図と首っ引きで旅行計画を練っているためだ。
それぞれの都市の位置と距離感がだんだん身体に入ってきた。
そういえば、前にYouTubeの動画で銀座のママさんが語っていた。
デキる男は皆、素早くて可愛げがあるのだそうだ。
グロスター公リチャードは素早くて、可愛げがある。
主人公のキャラ立ちは良くても、若書きだから緊密さに欠けると思っていた。
けれど、辣腕政治家の一代記として、この台本は面白い。
面白いように出世して、政務を取る間も無く殺される。
作者のタイムコントロールに喝采してしまう。
もうすぐ目的地だ。
2022年7月11日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野WS『蛇姫様 わが心の奈蛇』 
↑シノとあけびの対話。シノ随一の見せ場である(撮影:伏見行介)
難所だった前回を経て、昨日はまたもとのペースで物語が進み始めました。
3幕の中盤です。
あけびが小倉に戻って死体処理と朝鮮半島への輸送に反対していた
小林ですが、その際に必要な帰化手続きを巡って、彼の心が揺らぎます。
日本人の身元引き受け人として、あけびは小林を指名したのです。
それはつまり、最も心の許せる相手であるという告白に他なりません。
さらにあけびは、1幕で切り落とされた小林の指を大切に
保管していました。そして、それを書類に押すハンコとして
使わせて欲しいと小林に懇願します。
それに感じ入り、自らの血を印肉として捺印を完成させようと
小林は提案。写真ボックスの傍に落ちていた三角形のガラス破片
(『唐版 風の又三郎』3幕とまったく一緒の小道具!)
を用いて、傷口から血を得ようとします。
・・・ちょっとグロテスクなシーンです。
が、ここにはハンコというものの本質があります。
ハンコとはもともと、骨と血を以って誓いをたてる呪いめいたもの。
二人の結びつきが強まります。
と、ここにタチションが飛び込んでくる。
ガラスの破片とはいえ刃物ですから、あけびが小林を傷つけようと
していると思って、兄貴分を助けようとしたのです。
(ここは、本作第2幕の終盤と一緒)
しかし、助けに入り、手に入れたバー箱師の権利書を持ち出して
二人で探偵事務所を立ち上げようというタチションを、小林は拒絶。
それだけあけびとの結びつきが強まっているとはいえ、小林を慕って
ここまで尽くし、しかも袖にされるタチションは可哀想です。
そこに、タチションを恨む権八の弟子たちの邪魔だてもあり、
舞台はまた小林とあけびに。今度こそ帰化の手続き書類を完成
させようとする二人に、今度はシノや薮野一家が割って入ります。
薮野一家が千恵の身体を使ってあけびの母・シノを操り、
薮野のハンコを使ってあけびの帰化を果たそうとする。
それによって将来の利益を得ようとする。
ここは、シノの見せ場で、薮野一家に脅かされながらも、
彼女は心の内で娘のあけびに小林という仲間ができたことを喜び、
あけびが自由に生きていくように願います。
薮野一家のハンコを使ってはいけないとメッセージする。
・・・というシーンまでをやりました。
面白かったのは、参加者の中にはこの台本が初めて掲載された
雑誌「新劇」をチェックしながら参加してくださっている方がいて、
シノの見せ場については、書かれていないことを指摘してくれました。
要するに、執筆時の唐さんは、
暴力されながら娘の幸せを願うシノのクドキを初執筆時には
書いておらず、稽古や上演の中で付け足していったことがわかりました。
この役は映画界のスターである清川虹子さんをゲストに招いて
上演した記録があるので、きっと清川さんに合わせて書き足されたものと
推測します。一方、舞台上で彼女をリンチしていることには変わりなく、
この辺が唐さんと清川さんの付き合いの面白いところだと思います。
あと、3回で終了。
クライマックスに向けて、物語が加速します。
2022年7月 8日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑小柄だけれど、出てくる音は大きなアントニオ・パッパーノ監督。
名前も鳴りが良さそうだ。
今週はロイヤルオペラハウスに通っている。
月から水曜までで『コシ・ファン・トゥッテ』
『カヴァレリア・ルスティカーナ』『道化師』
『マダム・バタフライ』を観た。
バタフライを除いて立ち見席を押さえることができた。
立ち見は良い。途中で座ることができるし、伝統あるオペラハウスの
あの狭い席に押し込められるより、結局は疲れない気がする。
周囲との距離感も良い。座席に座ると、両隣の人がどんな風で
あるかによってかなりコンディションが変わる。
昨日のバタフライなどは、その最たるもので、
蝶々さんの自殺で終わるエンディングに口笛をもって歓呼するとは
どういう了見なのだろう。
この国の客席は盛り上がる。拍手も口笛もブラボーも大きい。
けれど、それが必ずしも良いかといえば、そうでもない。
人間には、静かに余韻を味わうべき時があるのだ。
最も良かったのは、二日目のヴェリズモ・オペラ2作だった。
アントニオ・パッパーノ指揮のもと歌手も演奏家も解放されていて
何より演出が優れていた。古典劇的にヒロイックなところと
近代劇的に会話や心理が緊密なところ、両方の良いところを
美味しいところどりしたような上演で、見事だった。
だいたい、オペラはかったるいものだと思う。
もともと貴族の遊びなのだ。魂の叫びや、人生を揺さぶられるような
体験を求められるものではないのだ。ダラダラ進むのも仕方ない。
心に余裕がある人が特権で観るものという感じがする。
YouTubeの広告にイライラするような現代人では愉しめないのも当然だ。
という感覚からしても二日目は良かった。
と言いながらも、
昨日はAlbanyでインスタレーション・オペラの『Sun & Sea』を観て、
今日もまた、これからロイヤル・オペラ・ハウスに行く。
たまたまそういう週になってしまった。
明日は『The Blue Woman』という新作オペラの初演。
これにはかなり興味がある。もともとが絶滅危惧種的ジャンルだし、
コストがかかる分、わざわざ作る意味を考え抜いた結果、
珍妙なことが起こりやすい。期待できそうだ。
ちなみに立ち見席の値段は2,500〜4,000円だ。
高い席は40,000円くらいするが、これくらいだから手が届くのだ。
2022年7月 7日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note 
書類を作り、他にもいくつもの文章を書いている。
外国にいてもけっこう日本の案件があるし、それができるのが現代だ。
パンデミックを経験した今、オンライン会議も常識だ。
書き物をするときは、各地を転々とする。
授業後の語学学校の教室、Albanyのデスク、観劇前のロビーを渡り歩く。
行き詰まると場所を変える。すると、歩きながら頭の中が整理され、
また書き進められるようになる。
昨日はカフェにも寄った。Albanyの近所にあるDeli-Xだ。
ピーター・フィッシャーに紹介されたここは居心地が良く、値段も安い。
コンセントも使えるから、たくさんの人たちがパソコンをつなげて
仕事している。よし、原稿の最終直しをするぞ!
そう意気込んでコーヒーを注文し、奥のソファを見ると
ピーターが座っていた。
即座に、仕事を放り出した。ちょうど、彼を必要としていたのだ。
二日前、私はスリー・コーラス・フェスティバルという音楽祭を発見した。
期間は今月末。場所はイングランドとウェールズの境目にある
ヘリフォード(Hereford)という小都市を中心に、
周囲の街を巻き込んで行われるらしい。
これは面白そうだ。
田舎町に点在する教会を総動員して、各地でプログラムが組まれている。
小規模な城砦めぐりもできそうだ。
さらに調べてみると、フィルハーモニア管弦楽団がやたら出演している。
ピーターはこのオケによく参加しているから、話を聞きたかったのだ。
果たして、彼も出演し、オケと一緒にずっとヘリフォードに滞在することが
わかった。どこに宿をとったら良いかも訊くことができた。
そんな話をしていると、ネコが割り込んでくる。
Deli-Xには一匹の飼いネコがいて、彼の名前はビスマルクというそうだ。
店主のダニエルによれば、ビスマルクこそこの店のCEOらしい。
こういう冗談の感覚は、日本も英国も変わらない。
2022年7月 6日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note
昨日は不意打ちのような別れがあった。
火曜の朝は語学学校を休み、Albanyに行く。
いつも開かれるシニア向けWSに参加するためだが、
今日はマネージャーのソフィーが休みだった。
代わりにロミカがいた。
みんなで美術製作を行った。97歳最高齢の女性と、
初めてWSに参加した女性の相手をすることになり、
二人の間に挟まれて一緒にペイントをした。
今日の仕切りはジャスミンというエンテレキー・アーツの
腕利きスタッフ。なかなかの無茶振りだった。
こちらだってKAATで多くのシニアを相手にしてきたのだ。
語学力の不足を除けば引けを取るものではないと自分を鼓舞して
4時間の長丁場を持ち堪えた。特に新人さんはいかにも
不慣れだったから、いろんな話を必死に聞き出しながら、
作業も逐一いっしょにやり、最後まで見送って「来週も会おう!」と
何度も何度も約束して別れた。
今日は特別に長時間やる日だったから、ボランティアスタッフも、
途中でひとりふたりと帰っていく。
最後の片付けまで残ったのは自分も入れて4人だけだった。
ふりかえりのミーティングをして、解散。
すると、ロミカがジャスミンと抱き合い始めた。
なぜ?と訊くと、ロミカは今日が最後だと言う。
正確に言うと、先週で劇場との契約が終わっていたのだけれど、
今日は、前に自分が担当していたWSのメンバーに会うためにやって
きたのだった。
これが英国だ。
終身雇用とはかけ離れたところで働くのが自然なのだけれど、
ロミカは初期に特によくオフィスで顔を合わせていたので
ショックを受けた。
この劇場のスタッフにはいつも仲の良い。
けれど、この仲の良さは常に離合集散を繰り返す
英国スタイルゆえなのかも知れないと思う。
だからこそお互いに敬意を持ち、一緒にいる時間を大切にする。
残る半年間にも同じようなことがありそうだ。
あるいは、自分が帰国して3年も経ったら知り合いが誰も
いなくなりそうな気もする。
みんな、己の腕一本で生きているのだ。
2022年7月 5日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑背中に貫禄がある。いかにも目利きという迫力だ。
7/3(日)はミス・ダイアンの誕生日だった。
日本人ならば、自分のバースデーについては殊更に知らせることなく、
慎ましくするものと思うが、彼女はそうではなかった。
もともと、私は4月の時点で彼女の年齢と誕生日に気づいた。
自分のイギリスでの健康保険証取得のために試行錯誤した時に、
ダイアンが実物を見せてくれたためだ。
あ、7月3日生まれなんだ。
そう理解したことを、私は悟られまいとした。
それで、当日になってワッとお祝いしてやろうと思っていた。
しかし、彼女は遥かその上をいった。
5月下旬には自分の誕生日を私に伝え、その日の予定を開けて
おくよう厳命。それからは、週に一度のペースで予定を確認され
何度も「大丈夫だ!」と答え続けた。
その時点で、エリザベス2世のプラチナム・ジュビリーなど
ダイアンのバースデーの露払い程度のイベントに思えた。
それからある日、リビングにはムンク展のチラシが堂々と
張り出され、「ここに行くのだ」と言い渡される。
彼女が傾倒する国はインド。大好きなインド料理を食べるために
飛び切りの店が予約されたらしかった。
何しろ、あらゆる予約情報が、メールをしない彼女の代理で、
私のアドレスに届く。レストランが3人予約になっているので、
「他に誰か来るの?」と訊くと、「来ない。こうすれば大きな
テーブルが押さえられる」と自分の流儀を示して自信満々。
当日の朝、日本との深夜のミーティング続きでヘトヘトになりながら
起き出し、ガラガラ声でGood Morningと伝えると、
「アツシよ、あたしにハッピーバースデーはないのか?」と迫ってくる。
そこで、部屋から急いで隠しておいたプレゼントを取り出しながら
Happy Birthday to Youの歌ってやると嬉しくて泣きだす始末・・・
ダイアンとした初めての都心への外出は面白かった。
電車待ちの間、近くのベンチで大声を出して喋る女性を見咎めると、
ここでは書けない言葉で罵り倒す。
乗り換え時に不案内だった駅員に対しても容赦ない辛辣さ。
がカバンの中に見当たらないと、すぐに泥棒に違いない!と訴える。
常に本気か冗談かわからない物腰なので、こちらはずっと爆笑。
ムンクを見にThe Coutauldというギャラリーに初めて行きましたが、
素晴らしかった。ルネサンスや印象派の有名絵画が溢れんばかり。
そして、それらの常設展示物を経てムンクの遍歴を辿る展示を見れば、
彼がいかに多くの先行様式に学びながら、『叫び』で有名な
あの独特の画風にたどり着いたのかを知ることができました。
展覧会の作り方が、とにかく上手かった。
ちなみに、今回の展示に有名な『叫び』は無く、
『メランコリー』などがメインディッシュでしたが、満足しました。
それから、ダイアンの40年来の友人が営む有名パブに顔を出し、
インド料理屋でたらふく食べて、電車とタクシーを乗り継いで帰宅。
その間、普段は節約を旨とする彼女が、店員や運転手に惜しげもなく
チップを弾むことに驚きました。ハレとケが、マジ徹底している。
「夕食は私が払う!」と言って聞かなかったので、
クリスマスはこちらで持とうと誓いつつ、お祝いの一日が過ぎた。
2022年7月 4日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野WS『蛇姫様 わが心の奈蛇』 
↑かつて、小学校にはバケツを持って廊下に立つという罰があった。
そういう話をして盛り上がったのも、時間が押した原因かも。
劇団の稽古もそんな感じです。脱線なくして良い本番なし。
(写真:伏見行介)
昨日は難所につき、いつも20ページを目安にしている
進行ペースを大幅に下回り、約10ページを進めるのがやっとでした。
それほどまでに昨日のシーンは難しかった。
場面は3幕中盤の、小林とあけびが再開するところ。
主人公二人の会話だけで15ページほど続く箇所です。
ここは要するに、2幕で仲違いし夢破れた二人が、
もう一度お互いの目標を設定し直し、協力し合うまでを描く場面です。
この会話を成立させる、駆け引きがとにかく難しい。
初め、挨拶だけして小倉に去ろうとしたあけびを
気のふれた振りをした小林が引き止めます。
そして、1幕で約束した探偵事務所の話題を持ち出し、
あけびの出自がわかり、「蛇姫様」などと浮かれるにはあまりにも
過酷な出生を引き受けた上で、二人の夢をやり直したいと希望する。
それを受けたあけびは、探偵事務所のパトロンになると宣言する。
当然ながら、小林はよろこびます。探偵事務所を開いて、
二人の目標である白菊谷、そこに咲く黒あけびを探そう。
そうやって、再び意気投合する。
ところが、今度はその方法が問題となる。
あけびが目当てにしている資金調達の方法から、
彼女が身支度をして小倉に帰ろうとしていた理由が明らかになります。
それは、朝鮮戦争の終結に伴うキャンプ・ジョーノの解体による
最後の死体処理業務に従事するという仕事でした。
しかも、処理する死体とは、朝鮮半島から誤って運ばれた現地の人々の
それということも分かる。つまり、
①朝鮮半島→②北九州→③アメリカ→④北九州→⑤朝鮮半島
という長時間を経ながらあっちこっちを行き来した死体について、
④⑤の過程のエンバーミング・輸送という仕事だったのです。
従来のアメリカ兵に関する仕事よりさらに過酷。
それゆえに小林の探偵事務所を支え得る高ギャランティが期待されるも、
それを聞いた小林が、今度は止めにかかる。
という具合に、それぞれが相手を思いやりながらも、
犠牲や力の無さゆえに起こるチグハグ、足並みの揃わなさを
ほんとうに丁寧に追いました。
こういう場面をなんとなくでやってしまうと、
お客さんが主人公とヒロインの関係を形式的にだけ追うことに
なってしまいます。これから迎えるエンディングを心から
感情移入してもらうために、まるで公演を想定した稽古のように
丁寧にやりました。
思えば、2010年に唐ゼミ☆で上演した時も、
ここの場面の稽古には時間がかなり時間がかかり、
けれども、その分だけ身入りが大きかった。
終わった後に充実感がある、良いWSができました。
オンラインWSとしてはやりすぎたかも知れないけれど、
参加者の皆さんに感謝です。会話に終始した今回でしたが、
次週はタチションが加わって賑やかになります。
2022年7月 1日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑ホルボーンの教会で通行人のおじさんに撮ってもらった。
たいてい一人で行動するので、自撮りでなくするのに骨が折れる。
スマホを渡したら、そのまま逃げられるリスクがあるのがロンドンだ。
この場合は親切な人だった。一回一回が賭けである。
"義手"についての興味とおそれは唐さん譲りのものだ。
『宝島』に出てくるジョン・シルバーからその興味は始まる。
その『ジョン・シルバー』シリーズを、これまでに自分は
何度上演してきただろう。
また、『腰巻お仙 義理人情いろはにほへと篇』のドクター袋小路や
『少女仮面』に登場する腹話術人形も「♪俺の体は義手義足〜」と
歌い上げる。この歌はもともと、麿さんが得意だったらしい。
そんな唐さんの義手に対する好みが最高潮に高まったのは、
2000年春に初演された『夜壺』だと思う。
もともとのタイトルは『人形の都』だったとも聞いている。
ズラリと並んだ義手と義足がいっせいに動き出す脅威の舞台は、
いまも記憶に鮮やか。
ある日の朝食時、ロンドンの危険についてミス・ダイアンが語り始めた。
ロンドンにいる数多くのスリのなかで、最も巧妙だった女の手口について。
その女は路上に立ち、
赤ん坊を抱えながらスペイン語で困窮を訴えてきたという。
泣き止まない赤ん坊をこちらに傾けられれば、人はそれを支えざると
得ない。生粋のブリティッシュで、常に警戒を怠らないダイアンも、
この時ばかりは赤ん坊を半分、抱かずにはいられなかったという。
しかし、そこに罠があったのだ。
後から考えれば、その女の右腕はぎこちなかったという。
つまり義手だ。そして、大きなワンピースに隠した、本物の右手を使い、
赤ん坊でできた死角からダイアンのバッグの財布を抜き取ったという。
財布は、彼女の本物の手に握られ、そのままワンピースの中に収まる。
・・・・・。
果たして、そんなことが可能なのだろうか。
ロンドンは都会中の都会だが、かなり魔術的な雰囲気のする話でもある。
ここまでやられたら、悪くはないような気さえする。
唐さんに伝えたら、きっと喜ばれるだろう。
2022年6月30日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑終了後に、客席から後方のオルガンと合唱スペースを眺める。
お香の香り、水とパンを口にする仕掛けも含め、五感を総動員させて
立ち会う者を巻き込むスペクタクルが展開する。おそるべき装置だ!
お金をかけない愉しみを覚えてきている。
月に一度は遠出をしたい。場合によっては二度行く。
どうしてもお金がかかるから、温存しておかなければならない。
しかし、かといってAlbanyでの用事を終えてじっとしていたのでは
つまらない。何より、ロンドンにいる意味がない。
そういう時、教会の催しは良い。
セレモニーは当然ながら無料。
建築的にも風習的にも面白く、何より珍しい音楽が聴ける。
昨日は再び、ワーグナーの達人指揮者、
レジネルド・グッドオールが働いたという
聖アルバン・マーティル・ホルボーンに行ってきた。
通例は日曜朝に行われるミサだが、昨日は水曜の夜にも行われたのだ。
初めて、パレストリーナという作曲家の合唱曲を聴いた。
カソリック音楽の父と呼ばれる16世紀イタリアの作曲家だ。
彼は自身の曲もさることながら、ハンス・プフィッツナーという
19〜20世紀の作曲家がつくった、その名も『パレストリーナ』
というオペラで有名だ。
それで、大元のパレストリーナ自身の曲もCDで聴いたことが
あったけれど、いまいちピンと来なかったので生で聴きたかったのだ。
まず、この教会の音響的に優れていることに唸らされる。
前回はオルガニストの練習に立ち会って感心したが、
伴奏にかぶせて数人の合唱が増大されて空間を満たす。
ちなみに、演奏や合唱はすべて客席後方のバルコニーで行われ、
聴くものは降り注ぐサラウンドを浴びながら、向き合うのは
神父様、その向こうにいる神様のみ、という格好だ。
素晴らしく良く演出されていて、しかもこの教会は特に
飛び抜けている。
ラテン語もイタリア語もよく分からないが、
こういう反響の中、幾つもの声が重なっても歌詞が聴き取り易い
よう工夫したのが、パレストリーナの功績だそうだ。
すべての曲は、セレモニーの進行と完全に一体化しており、
説教や聖書の朗読、いろいろと取り決められた所作ごとが目の前で
繰り広げられるなか、時に伴奏になり、時にメインになりながら
歌われ、演奏されていった。要するに「作品」ではない。
家に帰り、早速に今日聴いた合唱のCDを買った。
一回、生で聴けば、録音もそれぞれの違いがよく分かって面白くなる。
こうして、知っている曲が増えるのは楽しい。
アマゾンUKを使えば、CDも600円くらいで手に入る。
教会は数知れず、各地にある。宝の山だ。
2022年6月29日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑夜はアート・アンサンブル・オブ・シカゴのロスコー・ミッチェルを聴く
英語の成長実感が無い。困ったことだ。
語学学校の学友たちはメキメキと腕を上げている感じがする。
彼らは授業後も連れ立っているから、どんどんツーカーになっている。
それに比べてオレは・・・。
また、英国人同士が目の前で容赦ないネイティブトークを展開すると
完全に振り切られて、左耳の先がピクピクいうようになってきている。
ストレスだろうか。気になる。
そんな中でも、いつも会っている人たちならば
徐々に人間関係ができてきている。
今日のようにWSがある時には、お茶の注文をとって回る。
・コーヒーと紅茶、どちらが良いか?
・ミルクの有無は? また、その加減は?
・砂糖は入れるか? 入れるとしたらホワイトか、ブラウンか?
・クッキーは欲しいか? 4種あるうちのどれが良いか?
こんな具合で、聞き取れなければ、もう一回!と言えるようになって
来ている。参加者のシニアたちも、分かりやすく発音してくれる。
今日は長い時間、80歳を過ぎた女性の話を聴いた。
彼女は1963年に一家でコロンビアからやってきて以来、
ずっとロンドンに住んでいるという。
「コロンビア、きっとマイナーだから知らないわよね。
あっ、そうだ! ベネズエラ! ベネズエラの隣よ!」
そう言われて思わず笑ってしまったが、
コーヒー豆のおかげでコロンビアが有名であること、
ベネズエラの方がむしろマイナーだと伝えた。
彼女はあまり外国には行ったことがないそうだ。
けれど、スペインとフランスには行ったことがあり、
良い思い出だそうだ。
左脚の悪い彼女は、イスから立ち上がる時にサポートを必要とし、
私の右腕を借りて、休み休み、お迎えの車まで歩く。
左足を持ち上げる道具を常に持っていて、今日はその使い方を
教えてくれて、初めて見送りを一人で完璧にすることができた。
そこへ、ちょうど代表のギャビンが来たので、
彼女を「大事なパティシパントです」と紹介し、
「私は今や、パティシパントのパティシパントです」と伝えたら
笑っていた。まさにそんな感じなのだ。
彼女が劇場に来始めて5年、毎週が楽しく、幸せだそうだ。
2022年6月28日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note 
↑これがウィリアム・ブレイクのステンドグラス
先週末は久々に現場仕事をした。
都心にあるキングス・プレイスという会場で「能」のイベントを手伝った。
早朝に家を出、帰りは24時を過ぎた。鉄道ストライキも気苦労の理由だった。
面白い人たちの現場にいさせてもらったけれど、疲れた。
翌日曜日はワークショップや劇団本読みをして、そのあと遊びに出かけた。
2週間前に訪ね、閉まっていたバタシーの教会でセレモニーがあったのだ。
あの教会は基本的に午前中しか開いていない。
この機会でなければ、午前中は学校かAlbanyにいる私が訪ねるのは難しい。
バスを乗り継ぎ、片道1時間半。今度こそ扉は開いていた。
私が興味を持ったのは、詩人ウィリアム・ブレイクが婚式を行ったからだ。
教会内には彼を表すステンドグラスもある。
儀式に参加するわけだから、入り口で聖書を受け取った。
聴衆は20人。コーラスが15人。オルガンの伴奏でアンセムが歌われ、
説教師のお話が繰り返された。そこで事件が起きた。
1時間が過ぎたところで、説教師の話が途切れ、
突然、奇声とともに倒れたのだ。明らかに癲癇の発作だった。
もちろん、人がこんなことになるのを初めて見た。
皆が慄き、合唱隊の一人が救急車を呼んだ。
ピアノをどかしてマットを敷き、彼を寝かせる。
聴衆はそれぞれの判断で、五月雨にその場を去った。
悪いことに、私は最前列の一番端に座っていたから、
立ち去りずらくなってしまった。ここに座ったのは、
すぐ横にブレイクのステンドグラスがあったからだ。
通路をバタバタと人が行き交う間、
私はじっと祭壇を見て、周りの状況が落ち着いたところで
そっとその場を後にした。そして水を飲みながらすぐそばのテムズ川を眺めた。
それから気付いたのだ。自分の怪しさに。
考えてみれば、ここはローカルな教会だ。
あの場にいたのは誰も彼もが知り合いに決まっている。
しかも、外に置いてあった看板を読んだところ、
この日は、永年ここに勤めてきたあの説教師の、
引退前、最後のセレモニーだったらしいのだ。
思い返せば、合唱隊の若者の何人かは騒然とする教会の中で
私の方を見ていた。200人以上入る席の中で私だけが変な位置に
座っていたし、見知らぬ顔だし、無表情だし、一言も喋らず、
なかなか動かなかった。あの視線には明らかに、
何か不気味なものを見る感じがあった。
確かに、ドストエフスキーやブルガーコフの小説に出てくる悪魔は、
さっきまでの自分みたいな物腰なのだ。
このままではいけないと思った。
しばらく待ち、戸口で救急車を見送った若者に挨拶することにした。
自分の身分やここに来た訳を話し、また来ますと伝えた
彼は初めは訝るような感じだったが、少しフレンドリーになった。
救急車に乗せられていく説教師を見る限り、命に別状は無さそうだった。
2022年6月24日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑Albanyのチケット売り場も、当然カード決済。これが読み取り機。
ロンドンではほとんど現金を使わない。多くの場合、カード決済なのだ。
私にとってこれは喜ばしい。記録が残りやすいし、スリを恐れてポケットに
ねじ込む財布も厚くならず、かなり薄くて済む。
エスニック料理店のうちのわずか何軒かが、
うちは現金のみでと言うが、紙幣もコインも、だからあまり持たない。
カード決済には2種類の方法がある。
読み取り機会にカードを差し込んで支払う方法と、
ピッとカードをタッチするやり方だ。
渡英当初から、私はもっぱら前者を選んできた。
タッチでの支払いをしたことが無かったし
私の持っているクレジットカードには、もともとその機能が無いのだ。
が、しばらく生活するうち、皆が皆、タッチ支払いしているのに気づいた。
速いし、手軽なのだ。が、危険も感じる。挿入支払いにはパスワード入力が
必要だが、タッチにはその必要さえない。つまり、カードを落としたら
使われ放題になる。恐ろしい。
そんなある日、現金の引き出しのため、
渡英直前につくった手持ちのデヴィットカードが、
タッチ対応していることがわかった。
便利に違いないし、大概の人がタッチ支払いだから、
会計のたびに店員と問答し、彼らが機械を翻すのにもくたびれてきた。
だから試してみようと思ったのだ。
なるほど、確かにこれは便利だ。レジでの流れも極めて良い。
郷に入っては郷に従うのも悪くはないか。そう思った矢先、
しくじりがあった。その日、私はケータイ・ホルダーに
英国のSuicaであるオイスターカードと、デヴィットカードを
一緒に入れてしまったのだ。
結果、地下鉄の支払い機は同時に2枚を読み取り、
ネットでキャンセルせよと駅員に告げられた挙げ句、
厄介な手続き方法に四苦八苦するうちに時間が過ぎて
約260円を失う羽目になってしまった。
あんなことは二度とゴメンだ。
そう誓った私は、すぐにまた元の挿入支払いスタイルに戻った。
いちいち暗証番号を打ち込むから間違いもないのだ。
今日も私は、タッチを求める店員にCan I insert?と切り出す。
すると店員は、OK!と言って機械をクルリと反転させる。
やはり安全が一番だ。お金は安全第一!
2022年6月23日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑今日からAlbanyでは、特に注力して準備してきた"Sun and Sea"が始まる。
レセプション会場の飾り付け、DJブースの準備もバッチリ。
今日は知り合いから聞いた話をしたい。本当に驚いた。
彼女の家には週に一度ハウスキーパーさんが来る。
その人は、フィリピンから来た男性だそうだ。渡英して40年になる。
週に一度やってきて、家中を掃除し、庭やゴミ捨て場を整え、
買い物のサポートもしてくれるそうだ。始業時間は朝8:00。
買い物も含めると午後まで働くらしい。
ところが、彼はいつも朝7:00にやってくる。
ロンドンでは電車よりバスの方が安い。けれど時間がかかるので、
5:30には家を出てやってくるらしい。
そして早めに到着し、電話をかける。フィリピンに向かって。
家族との会話の時間だ。
奥さんと喋り、お子さんと喋り、お孫さんと喋る。
ただし、彼はそのお孫さんに会ったことがない。
40年間、国に帰っていないからだ。
国に帰るのにはお金がかかる。
そしてそれ以上に、彼は観光ビザでイギリスに入ったので、
一度帰ったらロンドンに戻ることができなくなる。
彼にはロンドンのパートナーがいて、おそらくフィリピンの奥さんにも
別の相手がいるのだろうということだ。
今のようにWhatsAppやLINE、Facebookメッセンジャーなど、
無料で国際電話できるようになる前はどうしていたのだろうとも思うが、
ともかくも今の彼は家族で電話している。
不思議な関係だ。
40年会っていないという状況を私は想像することができない。
おそらく、彼が話しているお孫さんに彼が会うことは、この先もないだろう。
そんな風に思いを巡らせてしまう。
そして、それが当たり前の彼にはまったく悲壮感がないらしい。
極めて明るい人だそうだ。そりゃ、人間はいつも悲しんではいられないもの。
だけれど、やはり不思議だ。
こういう生き方を知ると、優れた劇場プログラムと同じくらい、
いや、それ以上に、ロンドンにきて良かったと何故か思う。
2022年6月22日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑5種類ある魚のうちHaddockを選んだ。タラ系の魚だ。
今週は鉄道のストライキ週間。
火曜、木曜、土曜とそれは行われるらしい。
過去30年間で最大級規模という
たまたま昨日は電車を使う予定がなかった。
朝からAlbanyに行き、午後は劇団のオンライン会議や事務をして
夜は近所で行われるフォークソングの集まりに行く。
すべてが徒歩だから問題はない。そう思っていた。
が、生活に影響がある。
周辺の店がけっこう休んでいるのだ。
確かに、電車が停まるということで、職場や学校をオンラインに
しているところが多数あると聞いた。
ということは、飲食店にとってお客さんが減るわけだし、
従業員が店にやってくるのも大変だ。ええい、休んでしまえ!
と休みことに対して常に前向きなイギリス人が判断するのは当然だ。
そういうわけで、Albany周辺のカフェもインド料理屋も、
ベトナム料理屋も休業しているためにランチ難民になり、
結局はゴールデンチッピーに行くことになった。
私はこの店が休んでいるのを一日しか見たことがない。
バンクホリデーのその日にだけ開いていなかった以外、
ずっと11-23時で営業している。
おかげで午後5時にやっと昼食を食べることができた。
面倒なことが目に見えているので、珍しく昨日は出かけるのをやめ、
日用品の買い出しに精を出した。
戦争の影響により、何もかもが値上がりしている。
貧しい人たちが住むゾーンまで歩いていって、
トイレットペーパーを買いだめした。
高いものは十分に在庫があるが、
4ロールで1ポンドというのは稀になってしまった。
6セット買い、まるでオイルショックのようだと思いながら、
大荷物を抱えて家に帰る。久々によく寝た。
2022年6月21日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑すごく良い人だった。彼への感謝は尽きない
先週末もいつくかの場所に出かけたが、やはり遠出は印象深い。
DVDで予習済みのオールドバラ音楽祭に行ったのが面白い体験だった。
まず、ロンドンを出る際のやり方は相変わらず難解だ。
リバプールストリート駅から北東に進む電車に乗れとナビが入っているが
駅に着いたところで自動券売機が壊れまくっている。
仕方なく窓口に並ぶと、スムーズに券は買えた。
次は正確な電車が停まっているレーンを探さなければならないが、
これがよく分からない。だらしなく立つ駅員に訊いたら、
その人にも分からないという。
イギリスでは、どの電車がどのレーンに入るか、
場合によっては直前になるまで分からないのだ。
出発10分前になり、不安になりかけたところでようやく
電光掲示板に13番と出た。急いでそこに入ってみると、
今度は改札が開かない。なぜだ? さっき買ったばかりの切符を
通しているのに。駅員に訊きたくとも、改札の中、
10mくらいのところに立っている二人はおしゃべりに夢中だ。
役に立たない奴らよ。
かなり遠いところにいた駅員のところまで走ると、
彼がチケットを確認して入れてくれた。他にも同じ事情で
困る人たちがいて、私の後に続いた。
電車の中は空いていて、快適だった。
1時間ほど行ったところで乗り換え、そこから3駅の単線無人駅に
降り立つ。そこから8キロのところに会場はある。
送迎車があると聞いたが、ぜんぜん来ない。
不安にかられて事務所に電話すると
「あなただけ? すぐ迎えにやるから!」と電話が切れた。
そして、電話を切った瞬間に向こうの駐車場から一台の車が動し
こちらに向かってきた。待機はしていたが、誰も来ないので
運転手がぐうたらしていたのだ。ロンドンの駅員とは違い、
彼の高木ブー的な感じに好感を持った。
距離は遠いが田舎道なのであっという間に着く。
この時点で、帰りはタクシーを予約しなければならないことが
分かった。コンサートが終わる時間に送迎サービスはないらしい(何故?)
なんとか歩けないことはない距離だが、狭い道に歩道は無く、
車がかっ飛ばすので危ない。それに、動物に襲われる可能性もある。
親切なブーちゃんがタクシー予約を手伝ってくれた。
会場に着く。そこは、ブリテンがウィスキー工場を改造してつくった
施設群だ。ひなびていて、アートセンターという言葉は似つかわしくない。
工芸品を売る店があり、楽器を売る店があり、ギャラリーがいくつもある。
もちろん、食事や酒を売る売店やパブもあり、川下りも楽しめる。
それに、美術の野外展示が多くて、どれも変テコで面白かった。
例によってCDやパンフレットを買ってしまいながら、開演を待つ。
バームンガム市交響楽団によるブリテンの曲がメインのプログラムだが、
私の目当てはパトリシア・コパチンスカヤのショスタコーヴィチ
ヴァイオリン協奏曲1番一択だ。恐るべき弱音を聴きたいし、
一番安かったので、最前列、ソリストの目の前の席を買った。
アンサンブルは捨てる。
当たりだった。聴いているとこっちまで身体が熱くなる演奏だった。
昔、巨人時代の清原が大嫌いな阪神・薮を相手にホームランを打った瞬間
「ボケェ!」と叫んでしまった。あんな感じなのだ。
ソリスティックな部分をガンガンに弾きまくり、オケにつなぐ時など、
彼女は「オラァ!」という感じで後ろを向く。最高だった。
終演後、例のタクシーが来るまで時間があった。
聴衆もスタッフも引き上げてしまって、自分ひとり、時間を潰すために
もう一度オブジェを見て回った。すると、向こうから演奏を終えたばかりの
パトリシアが一人でやってきた。思わずデカい声でリアリィ!?と言ったら
笑っていた。彼女は、ずっと誰かとビデオ電話していた。
帰り道はあっという間で、ナビよりも常に早めの電車に乗り継ぎながら、
2時間ちょっとで帰ってくることができた。
地元のシニア・ボランティアが大活躍して支えている
実に人間味のある音楽祭だった。
2022年6月17日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note 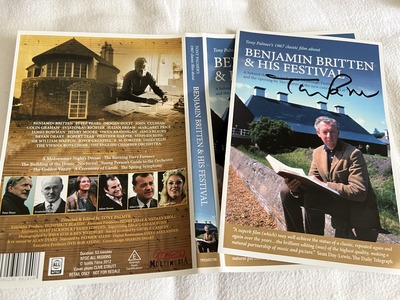
↑わざわざスコアを持たされて撮影したのだろう。
後ろに見えるホールに行く予定。
今週末、再び遠出するつもりだ。
前回に行ったブライトンとグラインドボーン音楽祭から3週間。
次なる目的地はオールドバラ音楽祭である。
これは『戦争レクイエム』で有名なベンジャミン・ブリテンが
1948年に創立した音楽祭だ。彼は20世紀イギリスが生んだ最大の
作曲家だが、その最晩年期に自分の故郷オールドバラでの音楽祭を
立ち上げるに至った。ロンドンから電車で2時間半の土地。
その後、彼自身は1976年に亡くなってしまったが、
半世紀を越えた今も、音楽祭は健在、今年も6月に行われている。
音楽もさることながら、ホール自体も愉しみだ。
もともとウィスキー工場だったところを改装してできたというのだ。
音楽祭が開始されて程なく火事になったが、また復元されたらしい。
趣きもあって音響も良いと聞くから、期待が高まる。
ところで、先日、いつも都心に出た時に立ち寄る大型書店で、
この音楽祭に関するDVDを発見した。これは行く前に見ておきたい。
けれど15ポンド=2,500円する。一回見てしまえばおしまいなのに
高いと思い、Amazon UKを調べたら2ポンド送料無しの出物を発見、
注文した。
たった三日で届き、蓋を開けると監督のサインまで付いていた。
サインしてもらったのにとも思うが、ふとどき者のせいで恩恵に
あずかることができた。早速に本編を見たら、創立時の様子、
ブリテンの奮闘、若かりし日のエリザベス女王が祝辞を述べるところまで、
経緯が良くまとめられていた。
ホールの様子も 予習することができたが、
そのうち、気になることが出てきた。妙に少年たちがものを
食べるカットのインサートが多いのだ。
それに、ボーイソプラノのコーラスの稽古を熱心にやるブリテンにも
しつこいくらいにフォーカスしていた。
・・・要するに、そういうことなのだ。
ブリテンの盟友といえばピーター・ピアーズという男性歌手であり、
その関係が公私にわたるものであることは有名だ。
加えて、この監督は、ブリテンが音楽祭を立ち上げるに至った
モチベーションを潜ませたのではないかと思う。
少年たちを故郷の田舎に集め、熱心に指導をし鍛え上げる。
当然、都会からは遠いので合宿状態。
これは、ブリテンのモチベーションを大いに高めたに違いない。
私は、こういう仕事の仕方が心から好きだ。
個人的な動機があってこそ、仕事はただの仕事以上の迫力を帯びる。
そう考えてみると、『春の交響曲』『シンプル・シンフォニー』
『青少年のための管弦楽入門』など、ブリテンの仕事はまた違った
角度からも強く輝き始める。明日の昼過ぎ、オンラインの本読みを
終えたら出発だ。
2022年6月16日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑目を凝らすと台座に落書きが見える。罰当たりな奴らよ。
学校が終わったところで、今日が自由であることに気づいた。
皆さん、昨日のTea Danceで燃え尽きているので、Albanyに行っても
会える人が少ない。特筆すべき会議も無い。
そこで、繰り出すことにした。
前から行きたかった聖マリー教会バタシーに向かう。
ここは極めてマイナーな場所だが、ウィリアム・ブレイクが
結婚式を挙げた場所だ。アクセスが極めて悪いから、
こうして大きな時間がとれないと訪ねることができない。
チャンスだと思ったのだ。
徒歩→バス→電車→徒歩という工程は面白かった。
東京都心から芝浦の方に向かう感じなのだ。
工場や倉庫が増え、テムズ川を挟んで対岸はお金持ちゾーンを
思わせるが、やはり南側はハングリーだ。
駅を降り、小ぶりかつワイルドな商店街を抜けた川沿いに
目的の教会はあった。結婚式の前後に、ブレイクもこの川面を
眺めたのだと思うと良い気持ちだ。言い忘れたが、今日から
気温は急上昇に、ロンドンにも夏が来た。
すっかり良い気持ちになって教会に入ろうとしたところ、
扉が閉まっている。側面に入り口があるのだろうと回り込んだが
そんなものはどこにもない。ネットで見たら18:00まで開いている
と書いてあったのに。教会の半地下にある幼稚園を覗いたら、
保母さんが出てきて優しく教えてくれた。
最近は昼で閉めるようになっていて、今日の営業はおしまい・・・。
別組織なので、私はカギを持っていなくてごめんなさい。
せっかく来たのに中に入れなかった。
でもまあ、道を付けたので次は早い。
自分なりに安く、早く来られる方法も発見できた。
ナビもまた当てにならないのがイギリスだ。
そう思って歩き出した。次の予定はウィグモアホールで、
かなり離れている。夏到来で汗だくになるので、途中からバスを
利用することにした。バタシー公園の反対側に、都合の良い
バス停がある。スタスタと公演を抜けるべく歩いていると、
八角堂を発見した。生まれたばかりの釈尊が天を指差し、
「天王天下・・・」とやっている黄金の像も見えた。
曹洞宗系の高校を卒業しているので、親しみを感じる。
かつて我が演劇部は、いつも仏像のある講堂で稽古していたのだ。
テムズ川沿いにあるこのお堂は日本人の手によるものらしく、
なんちゃって、でなく本モノだった。材料の調達から、
こちらの大工さんとの共同作業まで、さぞ苦労したろうと思う。
そしてよく見ると、神をも恐れぬ落書きがあった。
まことに罰当たりな話だが、台座にアルファベットが書かれていた。
新鮮で、ちょっと面白いと思ってしまった。
神様は見られなかったが、立派な仏様を見ることができた。
ウィグモアでは、今日からイザベル・ファウストによる
ベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタ全集が始まった。
3日通って全部聴くつもりだ。日本にいたらこんなスケジュールは
絶対無理なので、これも海外研修の贅沢だ。
人が燃焼し尽くすのにドキュメント的に立ち会う苦労が良いのだ。
『ジョン・シルバー』シリーズを連続でやった時に立ち会ってくれた
唐ゼミ☆のお客さんへの感謝も思い出す。
それにしても、先週のサー・シフの協奏曲全集といい、
本当はベートーヴェン生誕250周年だった2020年に公演される
予定だったのではないかと思う。ほとんどの人がマスクをしない
ロンドンにも、パンデミックの残滓がある。
2022年6月15日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑15台以上のポットが使われて壮観だった。
昨日は、「ティー・ダンス」という催しが行われた。
会場は、ゴールドスミス・コミュニティ・センター。
キャットフォードという街にある地区センターだ。
会場に着くと、すでに昨日からエンテレキー・アーツのメンバーを中心に
仕込みが行われていて、パーティーの様相が整えられていた。
「Rooted 21 Century Tea Dance」というのが会の正式名称で
イス・机の他に「Rood」→植物にまつわる飾り付けがなされている。
もちろん、音楽演奏や合唱、朗読をするための設え、
お茶やケーキを食べるための準備もなされていた。
いつもWS「Meet Me」「Moving Day」に参加している
シニアたちがお洒落して集まり、会の中で発表する合唱の仕上げをした。
その中の何人は、一人で詩の朗読に挑戦し、別の男性は得意の
『ダニー・ボーイ』を独唱するようだ。
そして、別の曜日にやっていて、私がまだ加わったことのない
障害者向けWSのメンバーも集まってきた。
クリスという、歌も演奏も司会もできる万能パーソナリティの
仕切りで会が始まった。恰好は女性用のワンピースで、
「彼」と「彼女」、どっちで呼べば良いか訊いたら、
どっちでも良いということだった。
前回はWS中に会って、その時は男性の恰好をしていたけど、
今日が本領発揮だそうである。英語も性別も難しいね、
と笑いながら話した。
参加者とスタッフ、併せて100人くらいの大パーティーだった。
前後に、お迎えや、タクシーでの送りの管理もあるから、
エンテレキーの中心スタッフ、ジャスミンやロクサーヌは
大変そうだった。こちらは、英語と会への不慣れの二重苦を乗り越え、
ちょっとずつ手伝うことができた。イベントのアテンドは、
どこの地域に行っても似たようなものだから、勘は働く。
ああ、このために日ごろのWSがあったのだなと合点がいった。
飾り付けに使われたバナーなんかも、美術の時間に創作されたものだし、
歌も、この時のために練習されたものだった。
美術には植物を使ったり、楽しい歌、悲しい歌、思い出の歌を
取り混ぜたり、会の趣旨に合うよう、日常的に行われてきたWSが緻密に
計算されていたことが分かった。会場デザイン、進行台本づくり、
すべてアーティストの仕事だ。こちらの芸術家は、自分たちの職能が
社会に向けて広範に役立つことを知っていると思った。
美術館やオペラハウスを頂点とするような、
芸術分野の中のヒエラルキーからも自由な感じがした。
人間や社会のためのものなので、どっちでもいいじゃん、
という物腰だった。これは強い。
恐るべき量のチョコレートケーキ、レモンのパウンドケーキ、
生クリームとジャムを塗ったスコーンが供され、皆が一斉に食べてゆく
様子は壮観だった。日本だと、餅つき大会みたいな盛り上がりだった。
半年に一度行われるわけだから、次の会は12月だろう。
その時はAlbanyでやるようだ。今回のことで全体像を理解できたので、
これからの日々行われるWSの意味を噛み締めながら参加してゆける。
長期スパンで研修できるありがたさを実感した。
それにしても、クリスの仕切りはすばらしかった。
そして、もっともすべての人を狂騒に巻き込んだ最強コンテンツは
シヴァ先生による「ジャマイカ・スカ」だった。カリブ海の文化は強い。
Linton Kwesi Johnsonがレゲエを武器とした理由を実感した。
2022年6月14日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note 
↑単にタダ飯を食べたのではないが、それにしても美味かった。
ロンドンにもようやく夏の気配が感じられる。
日差しも強いし、昼間にひなたを歩いていると汗ばむ。
日本と違ってじめじめしていないので、夜になると冷え込む。
いつも朝8:30過ぎに家を出、方々巡り歩いて帰るのは23:00頃だから
どうしても寒い状態に衣類を合わせる。昼間は余計に暑い。
先週の土曜はかなりユニークなイベントに参加した。
Albanyの一角に事務所を構えるレジデントカンパニーのひとつ
New Earth Theatreによるイベント"Sonic Pho"だ。
Pho=フォーとは、あのベトナム料理屋で出てくる麺類のこと。
ルイシャム地区にはベトナム人コミュニティがあり、
食を絡めた面白い劇場プログラムをつくり、
同時に相互交流を図ろうという狙いだ。
受付を済ませると、スタジオに行き、
そこで、フォーづくり、主にスープづくりのデモンストレーションを見る。
ハーブや香味野菜について説明を受けながら匂いを嗅ぎ、
出汁の取り方も目の前で料理してもらいながら、見る。
普通はチキンだが、ベジタリアン用には昆布を使う。
昆布だしなんて、4ヶ月半ぶりだった。
試飲させてもらったが、さすがにしみる。
アジア人が大好きな、これがグルタミン酸ナトリウム。
昔、唐さんが飲み会で上等の生ハムを食べながら
「これはアジアじゃ無理だ!」と絶賛していたのを思い出した。
ああ、オレも慎ましきアジア人の一人。
同時に、ベトナム人女優さんが、簡単にベトナムの現代史、
特にベトナム戦争の影響で世界中にベトナム人コミュニティができた
エピソードを紹介してくれた。
そして、移動。
近所のベトナム料理に皆で移動して、席についた。
そこでは、配られたヘッドホンをして、供されるフォーに向かう。
メインの具は好みによって指定でき、私はビーフにした。
本格的なフォーだ。
別皿にミント、もやし、コリヤンダー、唐辛子の輪切りが大量に盛られ
レモンも付いている。明らかに移民の人による店。
英国人は麺をすする音を嫌うから気を付けて食べ始めると、
すぐにヘッドホンから音楽が、続いて、ベトナム戦争を含めた現代史を
誦じる詩。要するに『ミス・サイゴン』的に国を追われた人たちが
この本格的なフォーをロンドンに持ち込んだのだ。
私はヒヤリング能力の貧弱さゆえにけっこう美味しく一杯を食べたが、
周囲の参加者にとって、けっこう苦い味だったのではないかと思う。
戦争の話題とフォーの味・・・。
はっきり言って今はあまり上手くいっているとは言えない
実験段階の企画だったけれど、その心意気が素晴らしい。
味覚をきっかけに地域のコミュニティにアプローチしたいという
着想が面白い。こちらも一所懸命アンケートを書き、連絡先を交換した。
近く、事務所に行くつもりだ。
劇団スペヤタイヤ、エンテレキー・アーツに続いて、
知り合った三つ目の団体ニュー・アース・シアター。
今回行ったベトナム料理屋にも、
これからアジアの味を求めて通うことになるだろう。
2022年6月13日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野WS『蛇姫様 わが心の奈蛇』 ↑角隠しをまとい亡き母が現れる(写真:伏見行介)
唐さんの3幕物はいつも2幕がすごい。
2幕の中盤から終盤に差し掛かるところをやったので自然と盛り上がる。
バカバカしさと悲劇性が矢継ぎ早に入り混じる場面を追いかけました。
あけびは伝治のもとでエンバーミング修行し、
晴れて一人前になることを目指しています。
そのための教則本は、伝治が書いた『日本人の恥骨』。
変なタイトル。
伝治はあけびを調子付かせるため、
一人前になったらあけびにテレビ取材が殺到すると予言します。
今風に言えば「美人すぎるエンバーマー」として世間にデビューする。
そういう感じです。
そして、予行演習をする。
権八一家の部下たちが鏡をカメラに見立て、あけびにインタビューする。
頭にわらじを乗せたまま取材を受けるあけび。
この際、徹底してNHKを持ち上げ、
その他の民間放送を邪険にあしらうところが面白い。
この芝居の初演は1977年春。一方、当時の唐さんたちは翌年の
お正月から始まる大河ドラマ『黄金の日々』を控えていました。
撮影がすでに始まっていたか、そうでなくても、キャスティングや
打ち合わせは確実に進行していたはずです。
舞台の上で、徹底してNHKをヨイショする唐さん。
こういうところが洒落っ気というか、興行師としての才覚というか
唐さんの面白いところです。せっかくなので「NHK」を
キーワードに、後に唐さんが三枝健起監督とつくることになる
テレビドラマについても紹介しました。
骨のある仕事です。NHKならでは。私たちはドラマでも唐さんの
世界に触れることができます。
転じて、一人の女性の登場により、舞台の空気は一変します。
角隠しをした、あけびの母シノが亡霊のように現れる。
これは、薮野一家の妹・知恵が霊媒としての才能を発揮したもので、
当時のスピリチュアル系番組が隣のスタジオで収録中という設定で
取材を受けるあけびの前にシノを降臨させたのです。
(唐さんなりの、強引なリアリズム!)
シノの口から語られるあけびの出生はおぞましいものでした。
朝鮮戦争のさなか、北九州に向けて出港する屍体輸送船「白菊丸」には
何人かの密航者が紛れ込んでいました。シノもその一人。
アメリカ兵たちの死体に紛れて同じく船に乗り込んだ男たちに
輪姦されて生まれた子どもこそ、あけびだとシノは語ります。
あまりのショックに、持病の癲癇の兆候が徐々に現れるあけび。
と、ここで重要なのは、ふと冷静になることです。
かなり勢いと迫力があるシーンですから、私たちはすぐに飲まれて
しまいますが、なぜ伝治がこんな道具立て(テレビ取材や知恵の霊媒)を
駆使してあけびに迫るのか、それを忘れてはなりません。
3幕終盤で、伝治の意図が明らかになります。
唐さんの仕掛けに思い切り飲まれながら、どこかで冷静さを忘れない。
しかし、やはり大いに飲み込まれてしまう。
矛盾する二つのベクトルを同時に兼ね備えることが、唐さんと渡り合う
方法論だと思います。昨日やったところは、好例のなかの好例。
来週は2幕が終わります。
2022年6月10日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑画像はネット上から引っ張ったイメージです。左側の感じ。
すっかりルーティン化していた語学学校で久々に震撼した。
授業中にブルガリアから来ている女の子と喋っていたら、
彼女が面白い話をしてくれたのだ。
まず、彼女は常にビジャブをしている。
ムスリムの女性が頭に巻く布だ。英語が上手く、
たちどころに発表のための文章を書く。なぜ、このクラスに?
聡明、という言葉がぴったりだ。単に賢いのではない。聡明なのだ。
年齢は19歳だそうだ。そして既婚者。
早い!と驚いたが、彼女の国では常識の範囲内なのだそうだ。
それだけで凄いと思ったが、いつも熱心に授業を聴く彼女が
今日だけはチラチラと窓の外を気にしている。
どうしたの? と訊いたら、旦那さんが外にいるのだそうだ。
歩いて30分ほどのところに住んでいるらしいのだが、
30分の休憩時間を狙って会いに来たらしい。青春である。
結婚したのは2月で、それから彼女はロンドンで暮らし始め、
これから就職するために英語を学んでいるそうだ。
てっきり彼と一緒にブルガリアから引っ越してきたのだと思った。
どうやって出会ったの?と訊いたら、こともなげに
「アツシはインスタを知ってるか?」と言う。
なんと、彼女はインスタ上で彼に出会い、
同じブルガリア出身で7年前からロンドンに住んでいる彼と
結婚するために、英国にやってきたのだという。
出会ったのは去年の秋。
驚いた。結婚適齢期はそれぞれのお国柄があるだろうが、
この果断さ、行動力については国境を超えたパッションを絶大に感じる。
物腰は大人しめなのに、ふつふつと燃えたぎっている。
家では、ブルガリア語、トルコ語、英語が飛び交うという。
クラスの中でもっとも控えめに見えた彼女は
実はもっともアグレッシブな女性だったのだ。
放課中に旦那さんと少し話したが、「結婚の時は大変だったよ」と言う。
てっきり家族の反対とか、そういうことかと思ったら、
「彼女が乗った飛行機がなかなか着かなくて」と言っていた。
唖然とした。「おめでとう!」と言うのが精いっぱいだった。
2022年6月 9日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑足元に転がるチープなカップにより、ポンドが動くのだ
昨日は会議が無くなったので、午後に時間ができた。
そこで、Albanyには行かずに美術館に行く。テート・ブリテン。
ダイアンが一番好きだというターナーを観に行った。
ロンドンの美術館は巨大で、しかもここは無料だから、
こうして何度でも来ることができる。自分はじっくりと
絵を観て回るのが苦手だから、散歩がてら来て、
興味が湧いたコーナーだけを観、また別に関心が湧けば、
何度も来たらいいと思っている。
先週末の連休で力尽きたとみえ、ロンドンの都心は静かだ。
実に歩きやすい。こういう時は逆にベタなルートで
歩いてみようと思い。ウェストミンスターからロンドン・アイという
巨大観覧車に向かう橋を渡ってみた。
そこに面白いものが。
橋の中腹で、数人を相手におじさんが張り切っていた。
三つのカップに球を入れ。カップの並び位置をサッサッと変える。
さて、球を入れたカップはどれでしょう?
というお馴染みのマジックをやっていた。
面白いのは、ここにお金がかけられることだ。
当たると賭け金が倍になって戻り、外れると賭け金を没収される。
恐ろしく分かりやすいシステムだ。
興味本位の人が参加して、おじさんはけっこう負けていた。
球のありかがさほど難しくなく分かるのだ。
しかし、少し離れた位置から眺めていると、
そのうち、勝っている何人かがおじさんの仲間だとわかる。
そして、通行人を誘って、その人が大きく賭けた時に初めて本気を出す。
この単純さに、ハマる人はハマってしまうだろうけれど、
なんだか、この分かりやすさといかがわしさ、簡単さとスピード感に
好感を持った。晴れ渡る青空のもと、観光地のど真ん中で
こんなことも行われている。きっと警察が来たら雲の子散らすのだろう。
ロンドンに溢れる人間味を、またひとつ発見できた。
2022年6月 8日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑この劇評にオレも撃沈。腹立つわ!
最近観た劇の中で一番おもしろかったのは
グローブ座の『ヘンリー8世』だ。
最近、というよりも英国で観たすべての劇の中で一番だった。
観劇前はくたびれていたのだけれど、
終わった後はあまりの面白さにすっかり元気になって、
すぐにまた来ようと思った。それくらいの興奮で帰ったのだ。
なのに、今朝、ダイアンが見せられた新聞評を観て驚いた。
三つ星。これがレストランなら最高位だが、劇評の場合は五つ星が最高。
二つ星以下を見たことがないから、要するに低評価。
文章を一生懸命に読んだが、あまり誉めていない。
これには落ち込んだ。
グローブ座はゆるい。
囲み形式の客席になっていて、天井は空いているし、観光地だし、
特に立ち見席は安くて日本円で800円くらい。座る席は高いけれど、
立ち見は極端に安い。だから、疲れて途中で帰ってしまう人もいる。
そういう環境に立ち向かっている俳優たちは、
みな、シェイクスピアのせりふを言いこなす技量があるとともに、
ゆるくて、どこか芸人的だ。観客とのコントタクト多めだし、
それでいて、いざという時には熱演して、聴かせる。
反面、ダレ場の抜き方も心得ている感じがする。
ムラもあるだろうし、あまり芸術家然としていないところが
むしろ自分は好きで、大らかな人間の自然を感じる。
その中でも、『ヘンリー8世』は出色の出来だと思った。
前に観た『ジュリアス・シーザー』チームには悪いけれど、
座組みも、予算投下も、何よりアイディアが格別だった。
下ネタのオンパレードだったから、それが文句言われている
ようだけれど、それらは山田風太郎的で、大笑いして見ながら、
大好きになったのだが。
やっぱり劇は、リビングルームで満たされぬ家族や性を
じくじくと悩んでいなければならないのか、と疑問に思う。
ロンドンではここに人種の問題が加わる。
当の『ヘンリー8世』は、最後に生まれるエリザベス1世を
黒人の女優が演じていて痛快だった。
巨大なキャラクターや大きな物語。
それでいてバカバカしい公演に触れたいと思っている自分には
あの三つ星が五つ星以上に見える。
もっと観に行きたくなった。
10月まで飛び飛びで、レパートリーシステムでやっているから。
新聞の低評価を受けて、むしろあれを応援したいと思う自分の心が
燃え上がっている。
2022年6月 7日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note 
↑向こうの方にグランドピアノが見える。天井が低い!
先日、ピーター・フィッシャーに誘われて面白い催しを見た。
会場はペッカム。なかなかガラの悪い場所で、語学学校の同級生は
この街でケータイを擦られた。駅前の歩道はゴミの散乱がすごい。
それで、迷いながらフラフラとナビを頼りに進んだら、
ゲームセンターみたいな建物の裏手にたどり着いた。
名門フィルハーモニア管がこんなところでやるか!
っていう場所で、立体駐車場の上の方でたった1時間の
コンサートをやるという。
どうせ客は少ないだろうと舐めきって受付に行ったら
完売だと言われて返り討ちに遭い。しょげていたところを
ピーターのショートメールが助けてくれた。
これを見せろ!と。
で、スマホのモニター見せたら、
仕方ないなあと正価で入れてくれた。ああ、友よ!
入っていってのけぞった。
こんなんで満席って頭おかしいんじゃないか、と。
どんどん入れりゃ、いくらでも入るような隙間がいっぱいあって
演奏が始まってからも壁が吹き抜けてるから、ノイズだらけ。
近所を通る国鉄の軋みはすごいし、周囲のゲームセンターの放送も
元気よくなだれ込んでくる。
一方、肝心のフィルハーモニア管は、
大男だったら頭擦っちゃうんじゃないかという低い天井の空間で
ノイジーなスクリャービンを2曲弾いた。
『法悦の詩』『プロメテウス』という、
どっちも官能性充分、ノイズも充分という曲なので、
周囲の雑音と妙にマッチしちゃって、後ろの方の聴衆はみんな
ケータイかざして聴いてるし。心から堪能した。
まざまざ思い出したのは、
自分の青テントの舞台を後ろの方から眺めているあの感覚。
同時に、オレたちはいつも周囲のノイズにハラハラしてたけど、
案外と観客は平気なもんだって気づいて、開き直りも含めた
無頼な気持ちになった。
こんな感じでここれまでやって来たし、
我ながらやっぱり好きだなあという確認。
他方、こういうのは忘れ難くて最高だけど、
一回性のイベントで処理されちゃうから、
本心からやりたいこっちと、作品を評価するラインに乗せた公演、
両方やらなきゃならんのだあということをこのオケから教わりました。
周囲のノイズに負けないために音圧を強くして、
反響しすぎる空間に対処するため、アーティキュレーションを
クッキリ。彼らの腕前もいつもより分かった公演だった。
音楽について、これは2度と無い経験だろうなと思う。
またテントを自分でやって味わおう。
2022年6月 7日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野WS『蛇姫様 わが心の奈蛇』 
↑わらじを頭に載せる。汗の量がすごい初夏の芝居(写真:伏見行介)
昨日は本読みワークショップでした。
二幕も半ばに差し掛かり、再び再開したヒロイン・あけびと小林が
"蛇姫様""白菊谷""黒あけび"にまつわる妄想を育むシーンです。
冷静に考えると、二人は二十歳を過ぎているわけですし、
かなりイタい大人の男女だとも言えます。
が、
一人は小倉から出て来たばかり、床屋見習いのてんかん持ち、
しかも自分の父親や亡くなった母の出自もよく分からない。
一人は、グレてスリに手を染めたところ、指を詰めさせられた
パチンコ屋の新人店員ということで、なかなかに過酷な現実を
生きています。
こうして二人で蛇姫様ごっこしていないとやっていられないよ!
という彼らの切実な願いは、唐十郎ファンなら誰しも共感できるはずです。
それに、このシーンは全体のキモです。
小林が妄想する白菊谷の描写、暗いところに沢山のヘビがウネウネしている。
直視できないほどの不気味さゆえに、Barハコシ開店お祝いの鏡を使って
間接的に見なければならないほどの光景のおぞましさ、
という伏線が、劇の終盤で明かされるあけびの出自に繋がっていきます。
現実には、Barのセットの中で二人が探検ごっこしているだけなのですが、
この妄想をお客さんに共有してもらうことはかなり大事で、上演する側と
しては難所でもあります。てんかん予防にワラジを頭に載せて冒険する
あけびは可愛らしく、これも楽しんで欲しい。
さらにその後、伝治が登場してエンバーミング=死体化粧の
何たるかを語り始めると、舞台は一転、闇の雰囲気に包まれます。
朝鮮戦争時代の小倉に現れた凄惨な死体処理現場が
唐さん一流の長ぜりふによって想像力の中に現れる。
この陰と陽の目まぐるしい切り替え。
参加者の皆さんも心得たもので、コミカルの中にあるシリアスと
シリアスの中にあるシリアスを縦横に操ってもらいました。
ことばの力を借りて観客を弄ぶ快感。役者に弄ばれる観客の快感。
それらを同時に味わえる名シーンです。
あけびの床屋修行が、実はエンバーミング修行であったことも分かる。
次週は、そんなあけびが一人前の死体化粧師になり、
テレビ各社の取材が殺到するという奇想天外な場面からいきます。
大河ドラマ『黄金の日々』を翌年に控えた唐さんの露骨なまでのHNKびいき。
これが炸裂する洒落っ気に満ちたシーンです。
途中参加でもかなり楽しめます。ご興味ある方はぜひ!
2022年6月 3日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑ヘンリー8世の巨大な黄金マラに場内は大喜び
昨日は良い休日だった。
ウィリアム・ブレイクに関するいくつかの土地をめぐることが出来た。
生まれた家→洗礼をした教会→彫刻師としての作品が飾られた美術館
→創作が最高潮に達した時の家を渡り歩き、土地柄を把握できた。
地震のないロンドンでは、日本よりかなり多くの建物が保存されている。
100年前のビルは新しい、などというのは言い過ぎだと思うけれど。
ブレイクが暮らしたのは、いずれも都心の貧しい地域であることが
如実に実感できた。
自分には、彼のこじれっぷりが面白い。
現世的にはまったく成功できなかった人だから、
打ちのめされた彼は鋭くて巨大な内面世界を築いた。
普通、現代人は「経験」という言葉を肯定的な意味で使う。
「良い経験をさせてもらいました」10代の若者までもがこんな常套句を
使いこなす。
けれど、ブレイクは「経験」を悪しきものと断じた。
生まれた時が最高潮で、経験も人を汚すものだ、
そう考えて自分に閉じ籠り、そして死後に評価される結果を残した。
・・・と云うことが分かった時、
『無垢と経験の詩』というタイトルと、それぞれの詩の真意が理解できた。
唐さんが『吸血姫のテーマ』のベースにした『愛の園』もこの中にある。
ブレイクがこれを著したのは30代後半。当時、暮らしたランベスという土地は、
ロンドンの中心地であるウェストミンスターのテムズ川対岸にある。
ガラの悪い土地で、彼がここの自らの無垢を鍛えたことがわかった。
今後は、晩年を暮らした土地やお墓、たった3年だけ地方に暮らした
家も訪ねてみよう。
↓今の建物にもちゃんと印がある。
そして、夜にはグローブ座で『ヘンリー8世』を観た。
彼はエリザベス1世の父親だから、最後は女王が生まれるシーンで終わる。
世間とはまた違ったエリザベス2世へのお祝いを体感できると予想して
行ったのだけれど、果たしてその通りだった。
8人もの奥さんを渡り歩いたこの劇の一部がマラ祭り化していて
マジで面白かった。もう一度観たい下品さ、生演奏もあって豪華だし、
アイディア豊富な絶好調の公演だった。
観光地だと思ってナメてはいけない。
というか、お前らが観光でくるならオレたちはこんな風にやるぜ!
という風に舞台が観客をナメていて、それが良かった。
今日はこれから、黄金のカエル劇場の子ども劇→フィルハーモニア管の
『2001年宇宙の旅』コンサート→アンネ・ソフィー・オン・オッターの
ナイトコンサート。初めての3本立てだ。
2022年6月 2日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note
今日から週末までイギリスは連休になった。
本日木曜はもともとの祝日で、明日金曜も休みにして4連休とし、
在位70周年を迎えるエリザベス女王のお祝いをする週末にしたようだ。
私がこれを把握したのは最近だったため、
何か拍子抜けしたような感じで今日の朝を迎えた。
ポカンと予定が空いたので、身辺を整理することに使おうと思う。
こういう時に気を抜くと、あっという間に夕方になり、
ああ、1日を無駄にしてしまったと後悔に苛まれることになる。
まず、部屋の掃除をしよう。
最近はよくチーズを買って食べるようになった。
物価の高いロンドンで安いのがチーズやアイスクリームだが、
後者は恐れをなして食べていない。あの味を思い出して
際限がなくなってしまうことが目に見えているので、
4ヶ月間食べずにきている。
チーズはカバンの中に忍ばせておいて、お腹が空いたらかじる。
これは便利なことに気づいたが、パルミジャーノがボロボロと
こぼれることがあり、部屋の掃除は必須である。
次に英語の練習をする。
これは日本にいた頃から続けているもので、
ネイティブの人が喋っているのを追いかけてこちらも発語し、
完コピを目指すというもの。そうすることで、しゃべり言葉が
何を示しているのか、そのパターンを自分に叩き込む。
「洗濯機」という言葉を知っていても、日本人は口語で
「せんたっき」と発話する。「せんたっき=洗濯機」と体感したり
「それで、その時は」→「んでそんときは」となることを自分の中に
蓄積しないと、人の会話についていけない。
その次は傘を買いに行こう。
これはすでに4代目だ。イギリス人は傘をささない。
強風ですぐに壊れるからというのが理由のようだが、
私は日本人だし、アウェイで風邪をひきたくないから、
この予算投下を惜しめない。だいたいが粗悪品だが、
代替わりするごとに、あるホームセンターで売っている品が
強度と値段に満足できるものだと気づいた。あれを買いに行こう。
その次は都心に出る。
美術館は昼間にしか開いていないので、そのどれかに行けたら
しめたものだ。あるいは、最近ハマっているウィリアム・ブレイクの
生家や過ごした家を訪ねてみたい。ふと、気づいたのだが、
彼はロンドン指折りの繁華街であるソーホー出身で、
4月に帰国したサウジアラビア人のヤジードは
タイガー・タイガーというソーホーのナイトクラブが好きだった。
Tyger Tyger・・・、ブレイクのもっとも有名な詩の書き出しである。
ナイトクラブの創業者のセンスはたと気づき、興味を持った。
イギリスの建物には、そこここに青いマーク(プラーク)がついていて
過去の偉人との関係を教えてくれる。
夜はグローブ座に行けたら良いと思う。
『ヘンリー8世』がやっていて、歴代国王の中で抜群のキャラ立ちを
誇る彼について、シェイクスピアが書いたものだ。日本にいたら、
演目的にはマイナーでなかなか観ることができない。
今週、王室について体感するに、良い選択であるようにも思う。
さあ、ここに書いた。これから上記の予定をこなしていこう。
2022年6月 1日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑この喫茶店で過ごしていると、次から次へとピーターの友だちが
やってくる。昨日はソファの特等席に座れて特に根が張ってしまった。
昨日は朝と夕方にAlbnayで予定があり、途中が膨大に空いたので、
フィルハーモニア管の海外ツアーを終えて帰ってきた
ヴァイオリニストのペーター・フィッシャーと喫茶店で落ち合った。
主目的は、彼の新譜をもらったり、前回聴いた彼のコンサートについて
話すことだったのだけれど、自分の好きな音楽とか、今後に構想している
お互いの仕事の話になって、完全にとりとめも無くなってしまった。
私のパソコンからピーターを始めとした様々な音楽を再生して
遊んだりした。当然、お互いが生きてきた過去についても話は及ぶ。
ピーター・フィッシャーのヴァイオリン演奏は凄いと思う。
けれど、ロンドンで彼がメジャーかといったらそうでもない。
でもやはり、ひと目見た時から彼は凄いと私は思う。
ソロで活動し、室内楽団を率い、名門フィルハーモニア管に
エキストラで呼ばれながら、彼は生活している。
話の流れで、自分の子ども話をして、あなたはどうなのか?
と訊いたら、独り身だそうだ。子どもをつくるには歳を取りすぎたよ、
それに家族と子どもにはお金がかかる、もう60歳だ。
いつも陽気でパワフルな彼はそう言って、少し寂しそうだったけれど、
あとは、ひたすら楽しく、時にダラダラと話した。
途中には、お互いがケータイの向こうの知り合いにメッセージを
打っているだけの時間もあった。それでも許される感じが
とても居心地が良い。
彼の友人ダニエルのお店の雰囲気も相まって、
午後の4時間をここで過ごした。この居心地の良さときたら。
ロンドンで一番なのではないか。
ミミ、エリザベス先生、ダイアン、ピーター。この4人は格別だと思う。
正直、自分は外国への憧れが強くないし、
家族と劇団員、親しい人たちがいる日本での生活の方が好きだ。
何かあればいつ帰っても構わないくらいなのだけれど、
この4人と別れるのは相当に堪えるだろうと、既に今から思う。
だからこそ、一緒にいられるうちに存分に過ごしたいと思う。
ピーターは私が通っているフォークソングの集まりに興味を持った。
まさか、バリバリのプロである彼を、連れて行くことになるのだろうか。
2022年5月31日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note 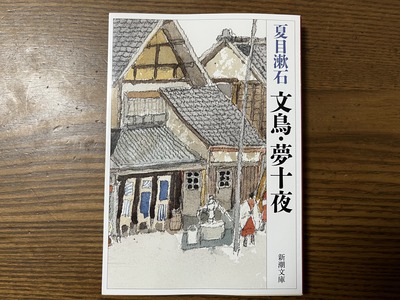
↑グラインドボーン音楽祭の庭

↑我がThe Albany Theatreの庭
『腰巻おぼろ 妖鯨篇』研究を終えてから1週間が経つ。
台本に取り組んでいないと予定に余裕が生まれる。心にも余裕がある。
先週末はブライトンのフリンジ・フェスティバルに行ってショーを見、
ケッチさんに会えた。ケッチさんの出番は短かったけれど、
そのかわりケッチさんの勧める若手女性クラウンの素晴らしい出し物を
見ることができた。このショーの感想を間に置きながら、
私たちは来年2月に創る舞台について話し合った。
その後に泊まった海辺のドミトリーは8人相部屋で面白い経験だった。
帰るのは夜中だし、朝早く起きてエントランスの広々としたカフェで
仕事をした私は、むしろ彼らに迷惑をかけた側だったと思う。
朝になっていそいそとタキシードを取り出し、
四苦八苦しながら慣れない身支度をする私を笑いながら見守ってくれた。
案の定、芸人か、友人の結婚式に備えているだと誤解された。
ちなみに、ミス・ダイアンには帰ってからこの宿泊体験を報告した。
ブライトンはゲイの街だ。そう断言する彼女に事前に宿泊先を告げたら
猛反対されたに違いない。私としては、グラインドボーンという
貴族的な土地へ赴くことへの禊としてここに泊まったのだ。
シャンパン片手にドレスアップしてピクニックを楽しむだなんて、
名古屋の地方公務員家庭に育ち、テント演劇に明け暮れてきた
自分には耐えられない。
そしてグラインドボーン音楽祭。
タキシードその他、ドレスコードを満たす準備や、
生き帰りの方法について調べるのは大変だったけれど行った甲斐があった。
この小旅行にはやたらと膨大な待ち時間がつきまとうから、
林あまりさんが教えてくれたチャペックの『園芸家12ヶ月』と、
ウィリアム・ブレイクの本を読んだ。数年ぶりにのんびりできた。
以前にのんびりしたのは、親知らずを抜くために入院した時だ。
グラインドボーンは想像していたよりもずっと人間味があって、
嫌な感じはせず居心地が良かった。演奏はいつも聴いている
ロンドン・フィルで、相変わらずわんぱくな弾き方だ。
何より、イギリスの女流作曲家エセル・スマイスの
『The Wreckers』という演目と、新たな演出が良かった。
レッカーズ、つまり"レッカー車"の"レッカー"には
"故意に物事をダメにする"という意味がある。
20世紀の貧しい漁村の共同体の中で、不倫関係を貫く男女が描かれる。
僧侶の言葉も村人の忠告も彼らは振り切り、やがて心中を選ぶ。
こんなオペラだから、衣装はジーンズやオーバーオールが目白押しで
ひどく簡素だけれど、これはブリテンの『ピーター・クライムズ』と
ワーグナー『トリスタンとイゾルデ』を掛け合わせた作品なのだ。
民主主義下の大衆の圧力にも、宗教的な抑圧にもヒロインは屈しない。
イギリス人にも関わらず、イギリスの地方都市を舞台にしたオペラを
フランス語の作品にしたスマイスの反骨心が溢れていた。
彼女はレズビアンだったらしい。女性の闘争心が全開のオペラ。
演出もそういう要素をさらに先鋭化させていて痛快だった。
休憩時間には、ウィンザーからきたという常連さんのおじさんに
話しかけられて、楽しく過ごすことができた。
ビルギット・ニルソンを生で聴き、マリア・カラスに会ったことが
あるという彼は、大の音楽ファンで、一年で何回か、ここに来るそうだ。
最近の歌手には不足を感じるとこぼしていた。
彼は手荷物を庭に置きっぱなしにして客席に戻る。
ロンドンの喫茶店では、トイレに立つ時には全ての荷物を
持っていかなければならない。それと、ここでの人々の振る舞いが
好対照を成していた。誰も盗みなんかしない。なんと贅沢な。
してみると日本は豊かだ。落とした財布が返ってくる世界。
私はと言えば、売店でこの音楽祭の過去公演CDが1枚5ポンドで
叩き打っているのを発見し(定価30ポンド)、狂喜して大量買いした。
まるでディスクユニオン。この買い物には本当に満足した。
無事に深夜に帰って翌日。朝の本読みWSを終えた後、
今度はオールバニーの庭でのアフリカ音楽フェスだ。
巨大スピーカーを持ち込み、街中に響き渡る音量でガンガンにレゲエを
かけていると、オシャレした若者たちが集まり、踊り始める。
参加無料のイベントだが、酒やスナックが飛ぶように売れる。
面白かったのは、トイレの数が全然足りず、若い女子たちが茂みに
飛び込み、ギャハハと笑い合いながら用を足していたことだ。
そしてまた踊りに戻る。若さと健康を撒き散らしていた。
グラインドボーンとオールバニー。
表面的にはぜんぜん違う両者は、しかし、
劇場、庭、オシャレ、飲み食い、音楽という衝動において
まったく同じ欲求に根ざしている。どちらかを侮るなかれ。
オールバニーを回りくどくするとグラインドボーンになる。
この回りくどさが文化だと、栗本慎一郎先生なら言うだろう。
日曜の夜は夜で、バービカンに行き、
ロンドン響とゴスペルのジョイントコンサートを聴いた。
いつもより格段に観客に黒人や子どもが多く、活き活きしたライブだった。
途中から立って踊り出す人さえいた。
昨日で、渡英してから鑑賞したものが100本に達した。
2022年5月27日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑なぜか道端にナイフが落ちていた。日本ではあまり見ない。
今日はAlbanyで予定されている会議が直前でキャンセルになった。
これまでもこういうことはあったのでさして驚かないが、
何か発言を求められるかも知れないと身構えているこちらとしては、
多少は拍子抜けした。
AlbanyやWe Are Lewisham絡みで見聞きしたものを中核にしつつ、
不慣れな異邦人として、この界隈での生活全般についてお届けする。
私に与えられる時間というのは、みんなにとってはリラックスタイム
だろうから、せめてここだけは面白くありたい。
シニアたちとの交流においては、あそこに行け、ここに行けと
指示を受けるので追っかけて回って、翌週に再開して話すのを
楽しんでいることや、ドキュメンタリー演劇づくりでは、
いきなり人生のヘビーな話題が目の前で展開したので
面食らった話をしようと思っていた。
来年に日本でつくるキッズプログラムに、
Albanyでの観劇体験が生きるだろうことや、
週末のグラインドボーン音楽祭に向けて七転八倒したことも
伝えたかった。側から見たらずいぶん間抜けだろうが、
こっちは必死だ。唐ゼミ☆の運営や大学〜劇場の仕事の中で何度も
壁を感じたことがあったが、今回のは種類が違った。
荷造りから各種の予約から、すでに準備はあらかた終えたけれど、
決して油断はできない。現地で、どれだけ所在ないだろうかとか、
終演後のバスにきちんと乗れるかどうか、電車の駅から間違えずに
ロンドンまで戻って来られるかどうか。とにかくトラップだらけだ。
ところで、久々に語学学校が面白い。
さほど英語が進歩しているとも思われないが、
新入生としてやってきたドイツの青年たちが楽しませてくれる。
彼らの英語はスピーディで、発音も綺麗に感じる。
それでいて、休憩時間に一緒にコーヒーを買いに行きながら話した
エリザベス先生に言わせると、文法はメチャクチャなのだそうだ。
それを計るだけの技量は、自分にはまだない。
授業中に日本の話になり、節分の可笑しさについて説明した。
鬼の格好をする。豆を投げる。年の数だけ豆を食べる。
このくらいまでは良かったが、恵方巻きの説明はひどく難しかった。
ノンカット・スシロールのサイズ感は、彼らに分かりにくい。
一通り話すと、今度はドイツ人青年アレックスが、
タケシ・キャッスルが好きだと言い出した。要は「風雲!たけし城」だ。
あれ、ヨーロッパでも放送されていたんだ、と驚いたが、
トラックにパンツを引っ張られながら走るゲームの、
たけし軍団が力尽き、スピードに負けて皆が全裸になってしまう面白さ。
あれを伝えきれず悔しかった。英語は難しい。
2022年5月26日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑曇天だったし、花も盛りを過ぎていた。左下の紫の花はイチハツ。
↑こういうのを見ると、造園家は、自分にできるはずだと思うらしい。
イギリス人の園芸にかける情熱、あれは一体なんなのだろう。
彼らは本当に熱心に造園する。古い建物を大事にするから
自ずとリフォームも多く、出来るだけ自分の手でやろうとする。
楽しみなようだが、週末は庭づくりで大変だった、などとミミは話す。
何か、マゾヒスティックな快楽が潜んでいる感じだ。
Albanyでは、新たに参加するべきプログラムが一つ増え、
これで、月・火・木にルーティンを持つことになった。
英語にも慣れ、しゃべっている雰囲気は醸し出せるようになった。
土地勘も備わり、楽である。
シニアの中には毎回熱心に話しかけてくれる人も現れ、
こちらはもっぱら聞きやくだ。あまり複雑な話はできないから、
そのほうが私も助かる。
WSに参加する中で一人、ボランティアスタッフの女性が
自作の絵画をプリントしたオリジナル葉書にメッセージをくれた。
そこにはチャールトン・ハウスを訪ねるべし、とある。
チャールトンと言えば、同名のフットボール・クラブを頂く土地だ。
今まで訪ねたことはなかったけど、語学学校から歩いて30分強。
次に彼女に会う来週火曜までに行きたいと思い、授業後に向かった。
郊外型の巨大商用施設を横目にスタスタと歩き、
チャールトン・ハウスにやってきた。建物を囲む公園がデカい。
ベストコンディションでは無いものの庭があり、
なかなか大きな建物があって、サンドイッチを食べたり、
資料展示室で説明を聴いたりした。
カントリーハウス。そう呼ぶらしい。
この地域にはカントリーハウスがたくさんあるらしいのだ。
ここから先は私の推測だが、グリニッジ公園にある
エリザベス1世の別荘クイーンズハウスといい、
ロンドンのセントラルからテムズ川沿い南西のこの地域は、
幾多の来客に備えた屋敷を必要としたのではないか。
飛行機もユーロスターもない時代。
ヨーロッパの大陸からロンドンを目指したかつての人々は皆、
このルートを通ったはずである。かなりゆっくりとしたペースで
人々は行き交っただろう。
式典へのご招待ともなれば要人もいたはずだ。
自分はこれまで、花鳥風月への興味に乏しかった。
が、ロンドンに住み、ダイアンの渡仏の間に庭に水をやったりして、
興味が湧いてきた。ロンドンには巨大な公園がたくさんあるので、
ここを通り過ぎる時間を楽しくしてくれるとも思い、
花の名前を調べるアプリをダウンロードした。
これからは、いろいろな花の名前を調べて回りながら、
匂いも嗅いでみるつもりだ。ジャスミンの香りは確かに良い。
明日〜明後日のブライトン行きに備えて、グリニッジ駅で電車の切符を
買うなどして準備している。きっと様々な植物にも会うだろう。
2022年5月25日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑2016年に補陀落寺を訪ねて撮った写真。この小さな船に和尚さんを
乗せて、太平洋に送り出すらしい。
ものすごい時間がかかった。
さすが最長作品。こんなにもかかったのは初めてだったが、
2回り読みこんでかなり把握することができた。
執筆当時、よくこれだけの内容が頭に入っていたものだと眩暈がした。
唐さんは頭パンパンで、はち切れそうだったんじゃないか。
追いかけるだけの私も、最後の方は冒頭からの情報と緊張を維持しながら
読むのに苦労した。気をつけないと、すぐにその場で起こることだけに
飲まれ過ぎてしまう。
誰も彼もが死んでいるような世界で、文字通り死中に活を見出そうと
するのがこの台本だ。『唐版 風の又三郎』を書いてしまってから、
『唐版 滝の白糸』『夜叉綺想』そして『腰巻おぼろ-妖鯨篇』と、
まるで魅入られているかのように死の影が濃い。根っこが暗い。
本読みワークショップでこれを展開したならば、5ヶ月かかる量だ。
大物が終わって、少し解放されている。
もう6月が近いというのに、イギリスは暖かくならない。
今日など雨が数回にわたってドカ降りし、冬に戻ったかのような冷え込みだ。
暑さが苦手な自分には過ごしやすいが、この気候にはさすがに驚いている。
自分は1月末に来たものだから、英国の本当の冬を知らないように感じる。
1月や2月はどんなものだろうか。サマータイムの終わりが10月末だから
急激に日没が早くなり、きっと昼間がすごく短い体感になるだろう。
研修を2月スタート、12月終了にして良かったと思う。
同じ11ヶ月でロンドンの気候なら、冬場をカットできた方が良い。
台本を読みながら、何度も新宮を思い出した。
あそこには石川淳の『補陀落渡海記』のもとになった補陀落寺があって、
一定年齢に達した和尚さんを流すという船を見に行ったこともある。
それにしても、ある年齢になった住職は
補陀落(仏教における伝説の山)に向けて旅立たなければならない。
ひとり船に乗って太平洋に漕ぎ出し、信仰に範を示すため、
拒むことや止めることは許されない。・・・恐ろしい習慣だ。
『普賢』の好きな唐さんのことだから、影響があるかも知れない。
『補陀落渡海記』の主人公は、先ほどの習慣に抗う。
補陀落に行けるなどというのは迷信、自分は生きたい、
追い込まれた主人公はジタバタして渡海の途中で逃げ出すが、
結局は村の人々に見つかって殺されてしまう。
おぼろはかなりジタバタして、生き延びる。
最後のシーンは生きるということへの執着を見せつける大仕掛けの
場面だが、これはどうしたものか・・・。唐さんのイメージはわかる。
けれど、『盲導犬』で犬が飛ぶようなもので、難儀しそうだ。
上演を目指すとしたら、一番にクリアしなければならない問題だ。
2022年5月24日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑一昨日に行ったジャマイカ音楽のライブを以って、
渡英以来、鑑賞してきたステージ数は92になった。92/112日。
イギリスに来る前、同じ文化庁の制度を使ってフランスで研修した
先輩演劇人に「自分は200本観た。その全てに鑑賞の記録を取ってあり
今も時々見返すことがある」と聞いた。それに感化されて、
数も、記録も素直に真似することにした。
しかし、今後は少し本数を絞ったり、工夫しようと考えている。
週末にロンドン近郊のブライトンに向かうのを皮切りに、
いよいよ遠出しようと計画しているからである。
遠出すれば、交通や宿泊代がかかる。
食事だって近所では安く済むけれど、かさむに違いない。
きっかけは週末に予約したグラインドボーン音楽祭だ。
金曜にブライトンに行き、フリンジに参加しているケッチさんの
参加するショーを観て一泊する。
先にFacebookで発表したが、プロデューサー・テツヤの剛腕により、
帰国後、2023年2月に『3びきのこぶた』を原作にキッズプログラムを
演出する。ケッチさんこそ、その出演者なのだ。
こちらは一方的に存じ上げてきたけれど、初対面だ。
そして、翌日はブライトンから電車で20分のルイスに移動し、
そこから送迎バスに乗ってグラインドボーンに行こうと計画した。
ところが、新作オペラに惹かれて予約した後、
この音楽祭には、今まで自分の人生には経験の無かった
「ドレスコード」があることが分かったのだ。かなり狼狽えた。
男は絶対にタキシードが必要なのだそうである。
これに対し、自分は「スーツ タキシード 違い」とググるところ
から出発しなければならなかった。襟が違うらしい。
すでに予約してしまったので、諦めたらチケット代が無駄になる。
そんなことは許されないし、何より自分が情けない。
日本にいたら唐ゼミ☆の衣裳を動員するのに・・・
何とか希望を繋いで、庶民の味方、
ルイシャム・ショッピングセンターのTK-Maxに行った。
ここは結構なハイブランドの売れ残りを結集させた店だ
ひょっとしてタキシードが無いか探したが、もちろん無かった。
それによく考えたら、ズボンの裾上げが間に合わない。
悲嘆に暮れてダイアンに打ち明けたところ、
「Boss Brosでhireすべし!」と言われた。レンタルがあるらしい。
昨日、朝の語学学校を終え、午後にエンテレキー・アーツのすごく
高度なシニアのドキュメンタリー演劇創作に立ち会った後、
夕方にBoss Brosに殺到し、対応してくれた女性のベテラン店員に
「オレ、グラインドボーン、分からず、予約した」と伝えたら
すべてを察して、一発でジャストサイズを見繕ってくれた。
金曜の昼過ぎに受け取りに行った時、蝶ネクタイのつけ方も教わる。
果たして帳尻は合うのだろうか。
こういうこともあって、今後はできるだけ、
無料で入れるミュージアム、教会でのイベント、読書に精を出そう。
タダだけど、ロンドンではすごく良質なものに触れることができる。
そして、ストラトフォード=アポン=エイボン、コーンウォール、
バーミンガム、エディンバラ、ウェールズなどを目指すのだ。
2022年5月20日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note 
↑テツヤとの対話。ここで話しながら企画が生まれた。
劇団をやり、劇場で働く。
主宰と演出をし、コミュニティワークと劇場運営を身につける。
目下わたしが行っている取り組みだ。
今日は演出家としての話題。
コロナ以降、配信番組をつくってたびたび対話し、
去年のお盆には太田省吾さんの『棲家』リーディング公演を
一緒に行ったプロデューサー・テツヤから、
新たなお題が来た。キッズプログラムをつくろう!
今日が情報解禁日で、詳細はコチラ↓
http://yorunohate.net/
オオカミだ!- 『3びきのこぶた』に出てくるオレの話 -
日にち:2023.2.18.sat,19.sun
会 場:本多劇場
「第33回下北沢演劇祭参加作品」
出演:ケッチ
演出:中野敦之
企画製作:ヨルノハテの劇場
主催:合同会社ヨルノハテ
原型は『3びきのこぶた』。
去年の終わり頃、テツヤはこの童話とロシア文学を並べて
「どっちがいい?」と訊いてきた。
ロシア文学は好きだけど『3びきのこぶた』と即答した。
ロシアの方だとつい難しぶったり、カッコつけそうで良くない。
『3びきのこぶた』の方が逃げも隠れもできない感じがしたのだ。
ひたすら子どもたちのための劇をつくる。
そう思ってより平明な方を選んだつもりだったが、
なかなかどうして、このイギリス産の童話には、英国の人たちの
生活に根ざしたメッセージがあることがロンドン暮らしの中で
わかってきた。

ただ一人の出演はケッチさん。
これはすごい。テツヤの剛腕だ。
すっかり張り切って、今から構成台本製作や演出プランを
つくっている。年末には、帰国後すぐに稼働できるよう体調を整える。
初めてキッズプログラムを演出する。
初演以降の展開もすでにテツヤは狙っている。すごいぞ、テツヤ!
2022年5月19日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note 
イギリスの食事は不味いと言われるが、自分はそうじゃないと思ってきた。
前にも書いたが、フィッシュ&チップスは美味いところは美味い。
パイ&マッシュに付いてくる鰻の煮凝りも、ほとんどの英国人は
気味悪がるが、自分は大好きだ。野菜中心のインド料理も良いし、
かのイングリッシュ・ブレックファーストは豪勢だ。
イタリアンとかハンガリーとかアラブの料理もある。
ともかくも自分は満足してきた。しかし・・・
最近、パリに住む日本人の知り合いと会う機会があった。
そこで自分は、グリニッジで気に入っているパン屋の
チョコレートケーキとハニーケーキを差し上げることにした。
これらは間違いない。そう自信満々に思っていた。
が、彼女が勧めるパリのクロワッサンをひとかじりして、
これは勝負にならないと思った。ダイアンが好きなので、
毎週日曜の朝はクロワッサンを食べているが、格が違った。
時間も経っているのに、驚異の美味しさである。
それに、このレベルの店はざらにあり、値段はロンドンの半額だという。
この衝撃は、例えばこんな感覚。
小さい頃から大好きな『北斗の拳2』には、
中国大陸に渡ったケンシロウをたちを待ち受ける敵がいる。
そのちょっと前にケンシロウと互角に渡り合った元斗皇拳の
ファルコがその敵と闘ったわけだが、死力を尽くして相打ちがやっと。
問題はその敵が、中国大陸に無数にいるザコの一人に過ぎないことだ。
そのことを死にゆく彼が告げた時の絶望感といったら無かった。
子ども心に戦慄し、ケンシロウの今後を思って天をあおいだ。
・・・という時のことを思い出した。恐るべしパリのクロワッサン。
さらに、今となっては私が差し上げたふた品が心許ない。
彼女は美味しいと言ってくれたけれど、別のものにすりゃ良かったかな。
2022年5月18日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑みなさんよく体を鍛え、ビジュアルのセンスを磨いている人たちだった
日本でいうところの知的障害、英国では学習障害者のための企画。
高齢者のための創作企画。こういったものにレギュラーで参加できる
ようになってきた。彼らの英語は容赦ないわけだが、
話しかけられたら何とか返事できるようにもなってきた。
わからなくても、今こんなこと言いそうだな、と推測して返事する。
トンチンカンな受け答えかもしれないが、こちらにそれは分からない。
分からない側の強みってあるよな、と自分を励ましている。
開き直るところまではさすがに行かないけれど。
そんな流れの中で、LGBTの人たちが大集合する
ファッション&ダンスのイベントに行ってきた。
これもルイシャム区とAlbanyの企画なのだ。
コロナによる行動規制が多い日本からすれば
考えられないほどの密着と熱狂だった。
みんな、ここぞとばかりに思い思いの、
大概は露出度の高い格好をしてランウェイを歩き、踊り、歓声を上げる。
初めは目を丸くしたが、しばらくいると、警備員の多さに気がついた。
そういえば、入口のチェックもかなり厳しかった。
チケットはもちろん、荷物も。サイトを見れば、
犯罪行為する人はつまみ出しますよ、と強調してある。
これを見てわかってきた。
彼らは強面に見られがちだ。
旧世代からすると鼻じらむようなイベントかもしれない。
けれど、よく考えてみると、彼らはなかなか苦労多き人生を歩んで
きたのかも知れない。自分の好みをに気づくのに時間がかかったり、
思いを打ち明けるのにハードルがあったかも知れない。
そして、それを素直に発露できる場所に行こうとすると、
どうしてもそこは都心であり、ドラッグや犯罪に近づいていくことに
なりかねない。誰だってそんなのは怖い。
そんな危険に自ら近づきたい人はいない。
だから、公共の仕事で安全性を確保することが大事なのだ。
格好は奇抜に見えたとしても、それは趣味の問題だから、
内面が暴力的だということには全くならない。
ところで、公共の仕事というものは、どこかソフトに
行儀よくなってしまいがちだが、このイベントにはそんな要素は
微塵もなかった。一見するといかがわしい。それが彼らを存分に
燃焼させる。けれど、安全である。健全である。
良いイベントだと感心した。
2022年5月17日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑大好きな真横の席から
『唐版 風の又三郎』浅草公演が終わった後、
私と林麻子はサントリーホールに行った。
林は音大のピアノ科を出ていて、その能力を活かして
劇中歌ワークショップを行っている。彼女は内田光子さんが
好きだそうなので、それで初めて生を聴きに行ったのだ。
私が内田さんのCDを初めて聴いたのは大学1年生の時で、
当時、横浜国大の先生だった許光俊さんの本『クラシックを聴け』
の中で、内田さんのモーツァルトのピアノソナタへの解説があった。
あの本はいまもしばしば読み返す。
自分にとっては、時間芸術とは何かを教えてくれた本。
渡英後に気づいたのはロンドンでの内田さんのリサイタルの多さ。
彼女にとってここは地元だ。だからけっこう頻繁に、
それもあまり高くない値段で聴くことができる。
オーケストラとの共演も、ソロでの演奏も、すでに何度も聴いた。
最も印象に残っていうのは渡英直後に行ったモーツァルトの協奏曲の
演奏会で、アンコールに呆然とした。モーツァルトK.545ソナタの
第2楽章のみ。人の人生を数分間に叩き込んだような演奏に、
打ちのめされた。
そして昨日も、それとは別の素晴らしい経験をした。
室内楽やバロック音楽用のウィグモアホールで、
内田さんはテノール歌手のマーク・パドモアの伴奏をしたのだ。
パドモアは当代随一のテノール、
彼の声の爽やかなこと理知的なことは見事なもので、
昨日、彼はこれまで見たどの時より格段に燃焼していた。
それは、内田さんの伴奏があったからだ。
とにかく煽る、煽る。
いま、パドモア相手にあんなに攻めの伴奏が
できるのは内田さんだけだろう。
それでいて、歌詞が終わって伴奏だけになると、
今度は内田さんがあっという間に主役になって、
アップダウンの強い、ロマンティックな演奏を繰り広げる。
達人同士が燃え盛っていた。
伴奏は大事。
神奈川には竹本駒之助師匠という娘義太夫の人間国宝がいて、
師匠の人間描写の徹底した味付けの濃さと燃焼にはいつも唸らされる。
そしてここでも、重要なのは三味線による伴奏。
伴奏はボクシングのスパーリング・トレーナーのようなもので、
ミットの差し出し方や位置で、次に打ち込むべき場所をリードする。
打ち手の力を何倍にも引き出すことができる。
僕らの芝居の音響や、集団シーンも同じだ。
せりふと音響、話し手と周囲が見事にキャッチボールする時、
人の力は何倍にも増幅される。昨日観たものは一生忘れないと思う。
2022年5月13日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑人種が入り乱れて、日本の会議より華やかに感じる。
ちなみにこれは自分の報告があると知る前で、人の多さに浮かれて
撮影した。直後に追い詰められるのをまだ知らない。
昨日は木曜。
学校を終えて電話や買い物をしながらAlbanyまで歩く。
劇場直前の十字路、先週に刃傷沙汰があった場所でまたケンカだ。
ただし今回は口論のみ。捨ててある段ボールをめぐって、
商店主とホームレスが激しく言い争っていた。
捨てられたばかりの段ボールを持って行きたいホームレスを
きちんと業者に持って行かせたい商店主が咎める。
「捨てたんだろう。なぜこの段ボールがお前に必要なんだ!?」
とホームレスの男は怒鳴り散らしていた。
周囲もやきもき見ていたが、暴力沙汰にならずに済んだ。
その後オフィスに行き、Albanyでの定例会議である。
いつものように末席に座り、フンフンと半分くらいしかわからない
彼らの話を聞いていた。15:00から1時間ほどこれは行われ
(英国の会議は短い)、わからないところは後でミミに聞く、
というのがいつものやり方である。
それにしても、対面とリモートが並行して行われてきた会議への
出席者が、今日は妙に多い。4月に加わった新人スタッフが
二人いるし、繁忙期が迫っているということだろう。
あとで自己紹介しようかな、と思っていたら、
一個めのトピックが終わった後で、いきなり全員がこちらを向いた。
聞けば、自分の番だったのだ。開始時間10分前に送られた会議進行の
メールをまじまじ見ると、確かにAtsushiとある。
「We Will Be Happy Hereについて報告してみて」と言われた。
確かに、皆は忙しいので自分が一番張り付いている。
それで、渡英以来もっとも大人数の前で喋ることになった。
これが恐怖との遭遇である。ビビったが、すぐに頭を切り替えて。
We Will Be Happy Hereがどんなだったか。
学習障害を持つ参加者それぞれによって、リハーサルの内容が
どう変わったか。かなり念入りに伝え、1980年台のファミコン的
世界であったこと、その時分に小学生だった自分にはそれがよく
わかるという話をした。
演出家のレベッカの一人一人に対する真剣さには驚かされる。
真のアーティストの迫力。アーティストであるが故に狂気も感じる。
プロジェクトに厳しく、参加者に優しい。
皆さんもぜひ土曜に見て、参加者それぞれによって生まれる
世界の違いを見てください。この企画の一人への向き合い方に、
全ての人たちに開かれたメッセージがある、と伝えた。
ついでに、最近参加しているMeet Meについても話し、
初めはミミと「ミート・ミー」の区別がつかなかったことや、
参加者のシニアをお世話するどころか、むしろ英語の歌を教わり、
全員が英語の先生状態になっていることを告げた。
・・・ということで、10分以上しゃべったが、
皆は声を上げて笑ったり、ニヤニヤしながら聞いていて
それがまた自分を調子づかせた。いけなくはない。
終わった後は飲み会に誘われたので、当日券でどこかに行こうと
していたのをやめてこれに加わった。
ロミカと英国内で訪ねるべき場所について喋り、
文学少女だと分かったリヴと、イギリスの詩人や小説について話す。
それも20:00過ぎに散開となり(英国の飲み会はサクッと終わる)、
早めに家に帰って、頭が疲れたので22:00に寝た。
そして今日は、苦もなく5:00に起きることができた。
明日からダイアンが遠出するので、先日の庭の水やりに続き、
トイレ掃除の仕方をこれから教わる。
ちなみに、『腰巻おぼろ-妖鯨篇』2周目は絶好調だ。
一度目はとりとめもなく感じたせりふの中に、二度目は多くの伏線や
つながりを感じて、遥かに緊密に感じる。やってみたくなってきた。
2022年5月12日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note 少し雨が降っただけでカタツムリ大量発生。1m四方に30匹以上いて爆笑
今日は雑感でいく。いくらか気になったことを。
(1)金芝河さんが亡くなった。
私は唐さんを通してこの方を知っているのみだが、
やはり1972年に始まった友情は熱い。
言葉の違う二人がどうやってコミュニケーションしていたのか
想像もできないが、きっと通じ合うものがあったのだと思う。
日韓反骨同盟。
この二人は揃って叛逆児だけれど、叛逆の種類が違うとも思う。
文化とは何か、という問答になった時、
金芝河さんは「闘争の結果である」と答えた。
対して唐さんは「瓦礫の前を横切る少女のくるぶしのようなもの」
と応じたそうだ。
・・・なんだか大上段な金時河さんを向こうに回し、
唐さんがとりとめもない感じもする。が、実際この通りと自分も思う。
背負っているものがあるから金時河さんは偉い。
けれど、唐さんにとって文化とは、人を驚かせる大いなるいたずらであり
チャームを持つものなのではないかしら。そんなことを思った。
(2)学校の友人がケータイを盗まれた
トルコ人の彼は、ここ二日無断欠席をしていた。
それが、今日は遅刻して悲壮な感じでやってきたのだった。
開口一番「先生、ごめんなさい。ケータイを盗まれてしまい」と。
続けて、ペッカムというまあまあ治安の悪い場所でバス停で
ケータイをいじっていたところ、黒人男性がそれをヒョイと
つまみあげ、走り去ったという。驚くべきは、彼がなかなかの
偉丈夫だということだ。背も高いし筋肉も多そう。
普通はもっとか弱い人を狙うと思うが、容赦なし。
自分にも緊張が走った。
(3)コインを拾いすぎ
いつかまとめて書くが、最近はもう確実に1日1枚+αのペースで
拾ってしまう。最も多くて1日に15枚拾ったことがあり、
先週の土曜は8枚、今日は13枚拾った。
特筆すべきは、あ、ここにホームレスの人が座っていた感じ、
というスーパーの前に、まとめて5枚が転がっていたことだ。
これはどうなのだろう? せっかく人がプレゼントしてくれたのに。
流石に「もっと必死になれ!」と怒っても良いのではないだろうか。
(4)アルメイダ劇場で新作劇『THE HOUSE OF SHADES』を観る
3時間の芝居を観ました。女流作家の新作書き下ろし。
20世紀後半のイギリス中流家庭が、共産主義にかぶれた息子を
力づくで更生させて無気力人間にしたり、娘が秘密裏に妊娠した
赤ちゃんをゴミ捨て場に捨ててでも表向き幸せを保つ。
当然ながら、対面を保っているものの、家族の誰もがいつも表面下に
ストレスを抱えている、という物語。
俳優は上手かったしスタイルも洗練されて、何よりアルメイダ劇場の
舞台後方のレンガの壁がカッコ良かったけど、はっきり言って趣味じゃ
なかった。ロンドンの人は実感を持って観ているのかなとも思ったが、
案外これは日本で数年後に翻訳されて上演していそうな気がする。
2022年5月11日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note
昨日は二つの事業に参加して、劇的に理解を深まった。
3週前から通い始めたシニア企画「Meet Me」と、
学習障害をもつ人たちのための「We Will Be Happy Here」。
まず「Meet Me」だが、やっと事業の枠組みがわかった。
The Albanyには小ぶりな事務所がたくさんあって、
劇場本体の事務局や企画、技術などの部屋の他に、
レジデントしているアーティストや企画団体がたくさんある。
「Meet Me」はエンテレキー・アーツとこの劇場の共同企画なのだ。
なぜ今までそれがハッキリしなかったのかというと、エンテレキーの
スタッフが休暇中だったからなのだ。このへんが英国っぽい。
ちなみに私は、この劇場のどこかにエンテレキー・アーツという
団体があって、福祉的な文化事業をここが主導して行っていることは
日本にいた時から知っていた。しかし、今日に至るまで、ミミなどに
紹介を頼むのを避けていたのだ。
なぜかというと、ただ会っても話が続かなくてしんどいのが
予想できたからである。現場に潜入していけば会うだろうと
思っていたが、果たして今日がその日となった。
ロクサーヌとジャスミンという女性スタッフとシニアを迎えたり、
作業したりしながら喋るのは愉しい。親しくなったので、
これからは事務所にガンガン遊びに行くことにする。
今日はもっぱら合唱の部屋でローズマリーさんという名前のお婆ちゃんと
一緒に歌い続けた。彼女の楽譜を見せてもらい、時には英語の歌詞の
読み方を教わりながら参加した。
"見学です"などと硬い姿勢は現場にとって迷惑でしかない。
新人で、英語ができなくて、そういう自分なりに現場を活気づかせる
ことができると思っている。
私はすでに地元に詳しいので、彼女が住んでいる場所も検討がつく。
オススメの店を教わったり、ローズマリーさんのお孫さんの話を聞いて、
こちらの子どもの話をして、終了後も盛り上がった。
参加者の一人一人が、エンテレキー・アーツが提携している
病院=お医者さんの勧めて参加したそうだ。医療行為の延長として
ドクターは劇場プログラムへの参加を進める。
そういう信頼関係とシステムができているらしい。
午後は「We Will Be Happy Here」。
今週はその企画に注力すると聴いていたが、会議に出席しても
ウェブサイトを見ても、正直その内容がよくわからなかったものが、
今日のリハーサルを見て氷解した。
てっきりWSをすると思って劇場に入ると、すでにセットが組まれていた。
ホール1階には三つの部屋が作られていて、明らかに仕掛けがたくさん。
そこに3人のパフォーマーがいた。彼らが何かやるんだと思っていたら、
お母さんとお兄さんに連れられた青年がやってきた。
その物腰から、彼に学習障害があるのだと分かった。
それから、彼は3人の女性パフォーマーと体をほぐして、
マントのような衣装を羽織って、各部屋を巡り始めた、
モンスターと闘ったり、踊ったり、キーボードを演奏したり、
光るボールで遊んだり、絵を描いた紙を吊るしたり、
最後は真ん中の部屋で大きなロール紙が引き出されて、
そこに、「We Will Be Happy Here」という言葉が書かれていた。
この間、ずっとファミコンめいた音楽が鳴ったり、シーンに合わせて
照明が変化していた。
・・・つまり、こういうことなのだ。
このインスタレーションは、学習障害者ひとりひとりから
内面世界を引き出してホール全体に立体化したものなのだ。
河合隼雄さんの箱庭をスタジオ規模に大きくした。
そんな感じだ。物語の作り手である彼は主人公として冒険する。
明日には他の3人のリハーサルが行われ、明後日はまた別の人の
リハをして、そうして週末の発表に向かっていくことだ。
完全にピンときた。見終わって演出家のレベッカに会い、
「彼はTVゲーム好きなのでしょう?
ひとりひとりに合わせてカスタマイズするのでしょう?」
と訊いたら、そうだと返事が返ってきた。恐るべき労力だ。
だからこれは、個々のパフォーマンスもさることながら、
「わたしはあなたと徹底的に向き合いますよ」というメッセージを
発信するためのプロジェクトなのだ。
「この人と向き合ったやり方と深さで他の全ての人と向き合う」
というメッセージを贈る。執念と狂気を感じる企画だ。
レベッカから信念が噴き出している。そういう雰囲気の糸田。
お金がどうやって回っているか、とか謎は多いけれど、
上記のことが完全に理解できた。
この企画を主導しているのは劇団スペアタイヤ。
良い劇団名だ。スペアタイヤの事務所もAlbanyにあるので、
これからは遠慮なく訪ねさせてもらう。
もともと3ヶ月くらいかかると思っていたが、機が熟したを感じる。
この研修は第二段階に入った。
2022年5月10日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note 
↑人は優しい。先週末、前から気になっていたハンガリー料理を初めて
食べた。腕利きの店員さんに説明されながらオススメを頂いた。
英国での生活はドラブルに満ちている。
例えば、最近はワクチンパスを手に入れたいと思い、かなり苦労した。
ワクチンを打つにもかなり手間がかかったが、事後だけでもこんな具合。
まず、接種後2週間が経ったのを確認して、119に電話。
そうすると高速の英語と闘うことになる。当然、相手の顔は見えない。
外国人用の対応窓口につないでもらっているにも関わらず
「ゆっくり喋ってくれ」と何度言ってもスピードが落ちない。
ネイティブの人にとって、ゆっくり話すのは難しい。
自分も可哀想だが、相手も可哀想だ。こちらが電話を置くまで
相手をしてくれるものだから、最後は申し訳なさでいっぱいになる。
埒があかないので、今度は登録の病院に直接に行く。
ここ数週間、保険証登録などでもすっかりお世話になってきたので、
こちらのことを覚えてくれている。受付の人は優しい。
スマホにこのアプリをダウンロードしてみて、
というアドバイスをもらい、GoogleからのDLに挑戦する。
すると今度は、ダウンロードのためのパスワードを、
Gmailアドレスに紐づいた私の日本のケータイ番号に送るという。
当然それは凍結してあるわけだから、キャッチできない。
そこで、現在持っているイギリスのケータイ番号に紐づいた
アドレスを新たに作ることにした。これ、病院の受付の前の
イスで焦りながらやったものだから、自分の名前なのに
アカウントがAtusshi Nakanoで登録されてしまった。
「アトゥッシ ナカノ」。でも、まあいいやと気を取り直す。
名前がどうでも今回は関係ない。
今度こそDLを試みると「あなたのデバイスではキャッチできない」
という。日本で買ったスマホだからなのか。ここで、方針転換。
同じアプリをパソコンに落とそうとしたが、これもダメ。
さらに別の方法を入れ知恵してもらって、
健康保険のウェブサイトから取り寄せることにした。
ここにもハードルがあって、フォーマットに入力するうち、
自分の写真を添付で送ったまでは良かったが、
「Movieも送れ。その際にこの4ケタの数字を言え」と続く。
この時、なぜか自分のPCのカメラが作動してくれない。
いつもZoomもLINE電話もこのMACでしているのに、
どうやってもカメラが動かない。
仕方ないから、Albanyの金庫番であるセリに頼むことにする。
ミミやロミカは親しいが、リモートワークが基本だ。
チケット売り場のリヴやアレックスやイオシフィナも優しいが、
彼らのパソコンは共用のものだし、いつ掛かってくるかわからない
チケット予約に備えている彼らを巻き込むことはできない。
そこでセリだ。若手スタッフと会議をしていたセリに
「後で時間をください」とお願いし、わざわざ自分のデスクまで
来てくれたセリに「あなたの部屋で話したい」と切り出す。
何事かと、彼女は神妙に私を招いてくれたが、結果こんな要件である。
果たして、セリのデスクトップのカメラで映像を撮影するわけだが、
悪いことに、自分のパスポート写真はメガネを外しているから、
裸眼で挑まねばならない。
そこで、指定4ケタの数字を記憶して臨んだのだが、
初回はテンパって「よんなな・・」とやってしまいセリに爆笑された。
再トライして、ようやく24時間以内にメールを送るという通知を得た。
果たして、明日にこれは届くのか。
最後まで気が抜けないのが外国での生活だ。
5/6(金)
学校→VACCURSE会議→買い物→Albany→ナンヘッド霊園
→『腰巻おぼろー妖鯨篇』打ち終わり→BBC交響楽団
5/7(土)
Zoom会議→洗濯→『鐡假面』本読み→ハンガリー料理
→チャールズ・ヘイワードLive
5/8(日)
掃除→本読みWS→買い物→ロンドン響
5/9(月)
学校でテスト→ワクチンパス取得のため病院→Albany
→ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団
2022年5月 7日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑Linton Kwesi Johnsonさんと。気さくであった。
先のブログを書いて買い物をしに劇場を出たところ、
ついに目の前で事件に遭遇してしまった。そこで今日は連投する。
Albanyを出て100mほどのところに、馴染みのカレー屋がある。
よく昼飯を食べるし、入らない日も挨拶する。
今日もそうして通り過ぎようとしたところ、
私の後方5mほどの所でガラスの割れる音がした。
さっきからワーワーやっている黒人たちのうち3人がケンカを始め、
一人はナイフを取り出す。「ナイフはやめろ!」と周囲から
怒号が飛ぶなか、敵対する男2人は周辺の店の看板を武器にして
殴りかかった。結果、ナイフが地面に転がり、味方のいない彼は
何度か殴られ、それでも素手でやり返した。
少し距離をとって睨み合うと、
看板を破壊された中華料理屋の女性店員が猛り狂って突進した。
負傷した男の肩をつかみ、大声で「ヤーメーロー!」と怒鳴り続けた。
男は怒りのやり場がなさそうだったが、本能的に女性に危害を加える
わけにもいかず、事態は沈静化した。
改めて周囲は彼の流血に気づき、彼もようやく痛みを感じたのか
上着を脱いでTシャツになった。簡単な手当をするうち、
警察が来て、救急車が来て、あっという間にバリケードが張られ、
インド料理屋は店じまいを余儀なくされた。
自分は予定通りスーパーに行ってオレンジジュースを買い、
そこから2時間、劇場での催しを観たが、終わって外に出ると
まだ警察はそのままで、サイレンの音こそないものの
パトカーの明かりが強烈に周りを照らし続けていた。
驚いたのは、警官の視界の届く範囲内で、
ベンチにたむろしていた別の黒人の青年たちがまたぞろ口ゲンカを
始めたことだ。さすがに今度は暴力に至らなかったが、
けっこうな大声だった。
今日のAlbanyで催しは、Linton Kwesi Johnsonという当地の
伝説的な黒人抵抗詩人のレクチャーで、満席の場内に集まった
聴衆の中にはたくさんの若者もいて、熱心に彼の話と朗読を聴いた。
劇場の内外で観た出来事を自分はどう理解したら良いのだろう。
2022年5月 6日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑Deptfordは造船業が盛んだったらしく、商店街の端に錨が飾られている。
イースター明けの4/18(月)以来取り組んできた『腰巻おぼろ 妖鯨篇』。
二日ほど前に峠を越えた感じがあったが、いよいよ踏破が見えてきた。
130ページの台本に毎日6ページずつ向き合って、残りあと8ページ。
今回はさすがに堪えた。肩も背中も痛いし何より目が霞む。
イギリスの照明は暗く、室内灯を煌々とつけることは、
倹約家のダイアンの手前、憚られる。
だから早朝や昼間に時間を見つけて取り組んできたが、
用事たくさんで夜にもつれこむ日もある。そうなるともう泥試合。
暗い中とり組むことになるから、負荷が高い。
蛍雪時代という言葉を思い出した。
例えば、ドストエフスキーやトルストイを今の生活の中で読むことは
難しい。あれは20代の暇な時だったから何度も何度も読めたのだ。
ラブレーやセルバンテスは大学1年の時に読んでおいて良かった。
プルーストは来世に託すしかない。
『チボー家の人々』やムージルの『特性のない男』も同じ。
今年は降ってわいた学生時代なのだ。
とにかく、『腰巻おぼろ 妖鯨篇』と『下町ホフマン』を仕留めること。
そうすれば70年代まではほぼ頭に入る。
80年代唐作品にも『あるタップダンサーの物語』とか『住み込みの女』
『ねじの回転』などがあり、先は長いけれど、とにかくこの2作が
ずっと引っかかってきたのだ。
手もとの様式で現在290ページ。
渡英後初めて打ち込んだ『秘密の花園』のざっと倍だ。
その実、プロットが非常に単純なのだが、唐さんは赴くままに
せりふを書いてここまできてしまったのだ。
34〜35歳の唐さん。まず体力がすごい。
『白鯨』の主人公エイハブ船長の気迫を感じる。
巨大なクジラに銛を撃ち込まんという勢いだ。
あとはひと息に。今日と明日は1日6ページのルールを完全無視。
空いた時間の全てを唐さんに捧げて畳みかける!
こんな事をしながら気づいたが、今年は全体が合宿なのだ。
中年以降をよく働くための強化合宿。
2022年5月 5日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑カーテンコール。8人で上演できちゃうのだ。
5月なのにロンドンは寒いままだ。
ジャケットこそお気に入りのTK-MAXで買った薄手のものに変えたが、
インナーはまだヒートテックのまま。なのに、そう汗をかくわけでもない。
気になってダイアンに訊いてみたら、これは異常なのだそうだ。
例年の5月の気持ちよさといったら。それなのに今年は・・・
そう愚痴こぼしていた。
暖かくなるのを心待ちにしてきたのには理由がある。
グローブ座に行ってみたい。が、あそこは吹き抜けの青天井。
しかもシェイクスピアだから3時間弱を覚悟しなければならない。
こんなアウェイで体調崩したら面倒だ。そう思ってきたが、
今日は他に鑑賞の予定もないし、『ジュリアス・シーザー』は
超メジャー演目でもないから£5の立ち見席が空いていた。
語学学校を終え、Albanyで事務をして18:30。
Deptfordからグローブ座まで30分ほど。行くべし。
初めてグローブ座で劇を観ることができた。
たった8人の役者で全編を演じ切り、最後に素朴な踊りまであった。
衝撃的な大感動を呼ぶわけではないけれど、町中華で食べるラーメンの
ような安心の美味しさがあった。
今日は観客がまばらだったし徐々に寒さが増していく。
観光客が多いからか、休憩時間に帰ったお客もたくさんいた。
けれど、役者たちは熱演して、演出により、時には観客と絡んだりした。
『ジュリアス・シーザー』は革命青年たちがクーデターを起こす話だ。
そして大義を持ったはずの殺人のあと、彼らは追い込まれ、滅ぶ。
後方のベンチシートで観ていた中年男性が嗚咽するように泣いていた。
学生運動に挫折した経験でもあるのだろうか。
主役のブルータスは黒人の若い女性が演じていて眉毛が繋がっていた
このメイクに、役柄の一徹さが表れていた。相棒のキャシアスは白人女性。
衣裳はスーツやミリタリーを使った現代服でシンプル、そこに少しずつ
古風に見えるように工夫されていた。
太鼓やタンバリンなど打楽器を使った原始的な演奏が随所に見られ、
最後にはダンスがあって、盛り上がって終わった。
地面はコンクリートで、照明も電気だけれど、
吹き抜けによって見える空だけは400年前と変わらない。
テントや野外劇をやってきたから、雨の日の様子も含めて気になる。
それに、さまざまな演目を立て続けにやっているから、
『ジョン王』とか『ヘンリー8世』とか、珍しい演目を観られる。
オーセンティックな衣裳による上演も見てみたいし、また来よう。
全体に誠実な感じがした。観光客が観にくるわけだし、
グローブ座の様子を再現するというミッションもある。
しかしその枠組みの中で、純粋に芝居としても面白い上演のために
最善を尽くしている感じがしたのだ。ダレる日もあるだろう。
でも、空だけでなく、人間も大して変わっていない。
そういうことを実感させる良さがあった。
↓お土産物売り場で異彩を放つマンガ版『リア王』。まるで漫画ゴラク
2022年5月 4日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑都心でテント小屋を発見。なかなかの安定感とエントランスだ。
グリニッジ駅前の殺人事件から二日が経った。
事件そのものにも驚いたが、輪をかけて驚異を感じるのは、
翌日も平然と事件現場となったパブが開店していることだ。
今日は都心から帰ってくる際に横を通ったが、
警官が三人いて聞き取りを行っているところだった。
お客は少ないが、三組ほどいるのが外から見て分った。
衝動に駆られて惨事を起こしてしまうのは辛うじて理解できなくはない。
しかし、淡々と開店していることは冷静な行動だ。
確かに、では何日閉めるべきかと問われたら答えに窮するが、
それにしても・・・・。献花が増えていた。
帰宅して、英国人としてどう思うかダイアンに訊いたら
普通は閉めるものだとの答えが返ってきて、少し安心した。
時間を戻すと、連休明けの今日は火曜日なので、
ソフィーの仕切るシニア向けWS「Meet Me」に参加した。
合唱と美術創作の2種目で好きな方に参加しているメンバーが
早くも自分のことを憶えていてくれて、やりやすかった。
「グリーンティーをちょうだい!」などと頼まれる。
よし来た!と思ってお茶を淹れて持っていくと「ミルクを入れて」と。
日本人としてはかなり違和感を感じたが、
怯まず「スタンダードミルクかソイミルクか?」とすかさず
訊いて、「ソイ!」とのリクエストを受けた。
日本人は緑茶にミルクを入れることに抵抗があるが、
紅茶にミルクを入れるわけだからこちらの人は緑茶も同じように
するのかと思ったが、これもダイアンに普通ではないと言われた。
簡単に国民性の違いにしてはいけないらしい。
シニアたちの英語は容赦ないが、まあ何とかやっている。
合唱に加わって英語の歌を覚えられるのは良いことで、
これは自分にとって英語学習プログラムだと皆さんに伝えたら、
ヘンリー8世をからかった俗謡を歌ってくれた。
その後は文化庁に提出する3ヶ月に一度の報告書を書いて、
都心に出かける。ウィグモアホールで初めて聞く合唱団が
色んな作曲家のアヴェ・マリアばかり歌う、という過剰な企画を
やったので当日券で入ったが、思った通りかなり面白かった。
アヴェ・マリアは唐さんも好きで、『腰巻お仙 忘却篇』や
いま本読みWSをしている『蛇姫様 わが心の奈蛇』でも使うよう
ト書きに指示がある。いつもギャグ的な使用なので、
今日のコンサートは大変に美しかったが、やっぱりバカバカしい
シーンが思い出されてニヤニヤしてしまった。
ちなみに、なぜか入場料はたった£5で最上等の席に座れた。
当日券だと安いのだろうか。よくわからないが幸運だった。
2022年5月 3日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note 
↑終了後の稽古場。チェンバロが見える。
これをロンドンの都心で書いている。
飲食店はどこも高いこの街では、屋内にフリーで座れる場所は貴重だ。
ナショナルギャラリーの横にある教会セント・マーティン・イン・ザ・
フィールズの地下は落ち着いてデスクワークができる場所だ。
それにこの教会はイベントに大変熱心で、
3月にはここでBBCシンガーズの『ディドーとエネアス』を聴いた。
今日は地下1階のテーブルに陣取ったところ、地下2階に稽古場が
あるのを発見した。このゼミログを書いているすぐ横では、
ガラス1枚を隔てて木曜に上演予定のヘンデルのオペラ
『セルセ』の稽古が行われている。
主役級の歌手が、出番の合間にコーヒー片手に目の前のテーブルで
休憩し、電話をし、くつろいだ後、また稽古に戻っていく。
稽古場の中はは紀元前5世紀頃のペルシャ。
さすがヘンデルの地元。これがロンドンだ。
4/29(金)夜は内田光子さんのリサイタルに行ったが、苦しかった。
弱音と不協和音が連続する現代作曲家の曲に対し、周囲に沢山いた
中国人旅行者たちが騒々し過ぎたのだ。
まず、私の席に言ったところ、先に座っている人がいて閉口。
チケットを示してどいてもらった。
隣の中年夫婦はひっきりなしにお互いの体をまさぐり合うか、
姿勢悪く寝ているかだった。一方、当日パンフがオンライン配布なので、
ケータイの明るさを最弱にして読みながら聴いていたら、
二席隣のおじさんが「目に入るから電話を閉じろ」という・・・
苦いコンサートだった。
4/30(土)はサウジアラビア人の友人アジードと最後の晩餐。
その前にロンドン・セントラル・モスクに一緒に行こうと約束したが、
こちらが着いたところで電話があり「間に合わない!」と。
後でレストランに着いて分ったが、この日、彼は半年間お世話になった
ホストマザーを連れてハロッズに行き、お礼に高級なアラビアの香水を
買っていたのだ。彼が案内してくれた店でした三人での食事は面白かった。
予定の組み方も、案内の仕方も、メニューの頼み方も、
18歳の彼のアテンドはものすごく未熟だ。
でも懸命で、こちらに自国の食べ物や感謝を伝えたい気持ちが伝わってきた。
同じアラビア圏のトルコ人留学生たちと、友達になってはケンカ別れを
繰り返していた彼。彼の目標である良い医者になって欲しいし、
彼とは再会の可能性があると思う。何年後かに日本を案内できたら嬉しい。
一人で満喫したモスクでは、イスラム教の合理性がよくわかって
楽しかったし、食事も美味しかった。久々に沢山お米を食べた。
アジードに幸多からんことを!
5/1(日)は唐ゼミ☆本読みWSをしてキングスプレイスに出かけた。
ピーター・フィッシャー率いるチェンバー・アンサンブル・オブ・
ロンドンを聴くためだが、キングス・クロス周辺の文化施設は
綺麗すぎて自分はどうも馴染めない。演奏会は会心の面白さだった。
ピーターはフィルハーモニア管のツアーに同行するため、
夜中にヘルシンキに向かった。激務だ。
5/2(月)。銀行が閉まるバンクホリデー。メーデーだ。
朝から『腰巻おぼろ 妖鯨篇』と格闘して、へばり気味だが、
昼過ぎにはウィグモアでガーシュインを特集するコンサートを聴いた。
その後、今後の遠出に備えて電車に切符を買いに行った。
オンラインでの申し込みが基本だが、なぜかクレジットカードが
はじかれる。そこで現地購入。
時間の無駄とも思うが自分はこういうのが好きだ。
劇や音楽の公演も、できればボックスオフィスで買って
紙チケットが欲しい。スタッフに質問したりすることも含めて、
時間に余裕があるからできる贅沢だと思う。
そして都心を歩き回り、今、冒頭の教会にいる。
今日、ダイアンは大金持ちの友人に誘われて、
ロイヤル・オペラ・ハウスでディナー付きボックスシートだそうだ。
出がけにストールの色やバッグの色について意見を求められたが
明らかに派手な方を選んで欲しそうだったので、そちらを指さしたら
喜んでいた。
他方、土曜未明にグリニッジ駅前のバーで殺人があったそうだ。
酔っ払った30歳前後の友人二人がケンカをして、一人が刺されて
亡くなり、一人は警察に捕まった。あまりにあっけない。
これがロンドンだ。
2022年4月29日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note 
猫の捜索願いを目にするのは二度目。が、これはインパクトある。
片目の黒猫を捜している!
Albanyにいて感じるのは、ここで行われる劇場運営が
日本のそれよりはるかに多く地域の人たちに関わっていることだ。
もともとそう思ってこの劇場を研修先に選んだわけだが、
実際に一緒に過ごしてみて、強く実感する。
そのため、この劇場が行う催しは圧倒的に音楽イベントが多い。
子ども向けのプログラムを除けば、これまでにストレートプレイは
3つしか観なかった。つまり、それだけせりふ劇の間口が狭い
ということなのだ。
また、辣腕のソフィーが仕切るシニア向けの定例WSに立ち会った。
皆で染め物によるバナーづくりをしたり、サイモン&ガーファンクルの
曲を合唱するのに参加した。作業や練習そのものは90分程度の
長さだが、皆さん早めに集まってくるし、休憩時間もたっぷりとる。
劇場から供されたお茶とお菓子で団欒して過ごし、
終わった後もみんなで残って茶話会のような感じになる。
とてもステキな光景で、それら一連が終わると、
ある人は自身で帰途につき、別の人は家族が迎えにきた車に乗って
帰って行く。ソフィーはそのひとりひとりと話をしながら見送っていた。
ソフィーはオーガナイザーであり、参加者の娘や看護師のような
存在でもある。「ソフィーはどこ?」と誰もがすぐ彼女に助けを求める。
その度にソフィーは二つの会場を駈けまわっていた。
まるでデイケアサービスのようだと思った。
内容的にもアートの度合いは薄めにしてあり、そのかわり間口が広い。
そして、Albanyがこうなったのには明確な理由がある。
地域経済が逼迫したからだ。
21世紀に入った頃、この地域は困窮した。
Lewishamはシニアにかかる医療費を支えきれなくなり、
Albanyは文化予算の削減に喘いだ。そこで両者は手を取り合ったのだ。
追い詰められたもの同士が結びついて、劇場の新たな事業展開に活路を
見出した。言わば、窮余の一策ともいえる。
必ずしも英国が良いわけではないと書いたのはそういうわけだ。
医療と文化、その両方がいまだ一定水準の予算規模を保っている日本は
幸せである。しかし、若者が減り、高齢者が増える国家経済の行き先を
誰しも明るいとは思わない。だから、来るべき時のためにと思って来た、
ともいえる。
いずれにせよ、そういう苦さも含めて自分は学びの日々を送っている。
音楽イベントに集まる若者たちにとって、Albanyは劇場でなく、
DJのいるクラブとしか記憶されていなのかも知れない。
そういうことも思う。
それが良い。それで良い。やっぱり劇場だと思われたい。
こんな風に3段階の感情が湧き、正解は見えない。
やはり、劇場は最高水準の芸術性を追究するべきでしょう。
という思いもある。最高水準の芸術性・・・。
しかし、しかしである。
これらは、やりようによって共存するのではないか。
それどころか、人々の事情や暮らし向きに接していることは、
むしろ劇をつくる作業にとって必須なのではないか。
実は、そういう思いもあってここにいる。
人間を描く、人間の営みだから、と言える。
そういったことを唐さんは『下谷万年町物語』でこう書いている。
これから劇作家になろうとする少年・文ちゃんに、
ヒロイン・お瓢が覚悟を問いかける場面だ。
お瓢 転がってくるもの。
文ちゃん え?
お瓢 果てしなく、いつも、こうして、転がってくる......。
文ちゃん はい。
お瓢 なりゆきとか、ゆきずりとか、手垢にまみれた、下々の、
様々なこれらを、おまえは、これからもずっとつかんで行けんのか?
自分のいる地区には、ものづくりにとって一番大切な魂がある。
そう信じている。
他方、作品をつくるということは当然ながら技術であり、
技術は都心で学ぼうと夜はセントラルに通う。
そんなイメージで過ごしている。
技術や形式だけの学んで帰りたくないと思って行動している。
けれど、もちろん、帰国後の仕事によってのみ正解・不正解は証明される。
だから必死だ。
2022年4月28日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑普通、終演後に指揮者とソリストは抱き合ったりするが、今日は
それはなかった。慎みということだろうか。
ラトルはずっと、男性歌手とお喋りしながら拍手を受けていた。
消耗が激しい。完全にワクチンのせいである。
夜中にやや発熱したようであるが(体温計がないのでわからない)、
普通に早朝に起きて、パンを買いに行った。
体のふしぶしが痛くて、丘をおりて買い物し、
また登ってくるときにいつもダッシュが効かない。
風邪をひいて熱を出した時にいつも不思議に思うのだが、
どうしてあんなにパフォーマンスが落ちるのか。
近所のコンビニに行ってポカリスエットを買うだけでヘトヘト。
今日はそこまでではないが、学校でも授業中ずっとウトウトした。
それから、自分を苦しめているのは『腰巻おぼろ 妖鯨篇』である。
せっせと台本をつくりながら読んでいるが、とにかく長い。
一日の分量をいつもより多めにとり、打ち込み始めて10日になる。
半分まできたところでいつもの台本様式で150ページになってしまった。
つまりこれは300ページいくということだ。恐ろしい。
『ジョン・シルバー』は80ページ。『盲導犬』は100ページ強。
『唐版 風の又三郎』をして224ページである。
その上、登場人物が多く、
正直いって今の自分には物語の進行がよく分らない。
基本的には捕鯨船の元乗組員たちの話。
海で亡くなった破里夫、彼を慕うヒロインおぼろ、
おぼろに横恋慕する千里眼、という3人の物語。
それを、それらが済んだ後でおぼろに出会った主人公ガマの視点から
過去を解き明かし、決着を目指す物語だ。
『あれからのジョン・シルバー』に似ている。
恐れずに言えば、唐さんがせりふを書けすぎて、
溢れることばの洪水の中に物語が埋もれてしまっている印象だ。
自分が今、お話しのどこにいるのか、迷子になってしまっている。
とりあえず最後までいって、もう一度頭から読んで、
あと3週間くらい振り回されるだろう。
日本にいたらとても太刀打ちできない量感。
そんな中でも、夜はバービカンに出かけてロンドン響を聴いた。
演目はクルト・ヴァイルの『七つの大罪』。
怠け者の父や兄弟がいる一家の家計を背負った少女アンナが
アメリカの各都市を巡り、七つの大罪のエピソードになぞらえながら
時に身を持ち崩し、金を稼ぐアイロニカルな話だ。
ブレヒトが筋を書き、ヴァイルが曲をつける。
『三文オペラ』を当てた二人は、女優ロッテ・レーニャに充てて
これをつくった。彼女はヴァイルの奥さんである。
CDでも聴くことができる。
今日の上演も夫婦の仕事だった。
サイモン・ラトルが指揮して、奥さんのマグダレーナ・コジュナーが
アンナ役を歌った。初めにラトルが楽曲の説明をして、
「家族です」と言ってマグダレーナを紹介した。場内から笑い。
『腰巻おぼろ 妖鯨篇』の台本が書き上がった時、
李さんはどう思ったのだろうか。何でもない会話、
そこでやりとりされるせりふ一つ一つが過剰に長いこの台本、
読むだけでも大変、憶えるのはもっと大変だったと思うが、
強靭な李さんのことだから臆することなく立ち向かったのだろうか。
2022年4月27日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑軽く一発打っていかない?というくらいのニュアンスが感じられる。
今日は色々なことがありすぎた。
よって、ざっと記録を並べる。
朝起きてオリーブパンを食べ、7:30過ぎには出かける。
デプトフォードブリッジ近くのコミュニティハウスに行き、
早く仕事に行く親が学校が始まる前の小学生達を預ける施設とわかる。
ジェニーズカフェで朝食。
イングリッシュ・ブレックファーストがBill'sの半額。
メニュー構成は一緒だが、それなりの味だ。
アルバニーでソフィーのワークショップ。
ボランディアスタッフを一人で仕切り、約25人の高齢者を相手にする
ソフィーの凄みに触れる。まるでデイケアとアートの融合。
Deli-Xに行って昼食。ダニエルはいなかった。
パウンドランドでスラッグキラーを買い、
商店街で驚くほどの量の小銭を拾う。15枚で合計17ペンス。
ルイシャムでブースターを打つ。
あまりにいい加減なのでビビる。ウォーク・イン・ヴァクチネーション。
過去に何本、何を打ったかは自己申告。消毒ガーゼでの消毒なし。
パッケージに包まれているが、床に落ちた注射器もある。
打ったあとの絆創膏なし。15分待機なし。
記録のカードを後から見たら、名前のスペルが間違っていた。
これがルイシャム・クオリティ。
その後、ダイアンに頼まれた洗濯石鹸と、自分用のTシャツを買う。
さらに小銭を拾いながら家に接近、月に一度、家に納めるのが習慣と
なっているトイレットペーパーとキッチンペーパー、食器用洗剤を買い、
ATMで来月分の家賃をおろす。この作業は、毎度ドキドキする。
悪い輩がウロウロしているゾーンだからだ。
帰宅し、『腰巻おぼろ 妖鯨篇』の台本づくりをしていると、
帰ってきたダイアンから近所で火事があったと聞かされる。
19時過ぎに再び出かけ、ゴールデンチッピーでフライドチキンを買って
これを食べながら、マッチスティックパイハウスを目指す。
アダムや音楽プロデューサーのジョージと再会しつつ、
フォークソング同好会に参加する。いつもより求心力に欠ける。
お互いの演奏や歌をあまり聞かない感じだ。いつもより感心しなかった。
ただし、リーダーの歌は相変わらず凄い。あと、今までに見たことのない
ヴァイオリンの弾き方2種類に接した。
帰りに火事場を通りかかる。
10時間経った今もマンションの最上階の部屋が燃え続けていた。
鍵を家に置きっぱなししたことからドアをノックして帰宅。
今さっき、寝る前のダイアンから明日の朝も焼きたてクロワッサンを
買ってきて欲しいと頼まれる。倹約家の彼女が、自分によって
徐々に贅沢の味を覚えてきているような気がする。
左腕、少し痛い。
2022年4月26日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑川口成彦くんが勧めてくれたジャン・ロンドーを聴いた。
チェンバロによる、瞑想的な『ゴルドベルク変奏曲』。
しかし、浮かれていられないのがロンドンの帰り途なのだ。
今日はガチの話題である。
最近、ロンドンに潜む危険についてダイアンが熱弁を振るってくる。
きっかけは、最近知り合ったペーター・フィッシャー。
日曜に行ったフィルハーモニア管の演奏会に彼はエキストラで
参加していたが(様々なオケによく呼ばれるようだ)、
特にショスタコーヴィチ7番『レニングラード』は珍奇なものだった。
というのも、大編成かつ長大さがウリのこの曲において、
ほぼ9割方埋まった客席によって場内の気温はどんどん上がり、
全員で朦朧とするような演奏会だったからだ。
おまけに、曲の静かな部分で客席のケータイ電話が鳴り響き、
しばらく止むことがなかった。こうなるともう全員ヤケクソになって、
アンサンブルは乱れるがとにかく爆音で盛り上がるというエンディングに。
客席は変に興奮していた。
終演後、ホールのバーで待ち合わせて、ペーターと一緒に帰ったが、
彼は新任の主席指揮者サントゥ・マティウス・ロロヴリが好きだという。
こっちは前任サロネンのファンだから、ストラヴィンスキーや
バルトーク、ショスタコーヴィチはエサ=ペッカの方が
向いているんじゃないかと伝えたが、ペーターはそうは思わないらしい。
まあ、サロネンの指揮振りを見る限り、彼の関心は大方
パーカッションと管楽器に向けられているから、
弦のペーターとしては不満に思うんでしょう?と訊いたら、
当たりのようだった。
サントゥは優雅な感じがしたので、『シェエラザード』とか
チャイコフスキーのバレエとかが聴きたいと言ったら、同意してくれた。
それに、あなたのアンサンブルの方が遥かに面白いと伝えたら喜んでいた。
実際にそうなのだ。
で、話題を戻すと、昨日ペーターがくたびれた様子だったのは、
ある事件が起きて、前日の眠れなかったからだ。
彼はニュー・クロス・ゲイトというAlbanyの近所に住んでいるが
彼の家の目の前で、夜中に銃撃戦が起きたのだ。
16歳の女の子が5発も撃たれて、それは大きなニュースになっている。
ペーターは「テリブル!インクレディブ!」と連呼していたが、
今日は今日で、カナダ・ウォーターで同じ家に住む女性3人と男性1人が
殺されたりもしている。
さらにダイアンによれば、一昨年にグリニッジ公園脇のジャズクラブ前で
高級時計をしていた男性が殺されたり、去年も20代半ばで小学校の先生を
している女性が殺されたというのだ。
他にも、80代女性が25歳の男性にラブレターを送りまくった末、
彼の奥さんを殺してしまうという怪事件まで、去年は近所で起きたらしい。
どうりで、ダイアンの警戒心が半端ないわけだ。
とりあえず、夜道で音楽を聴きながら歩くのをやめることにした。
誰かが接近していることに気づかないと危険だからだ。
なかなかの土地だが、来てしまったものは仕方がない。やれやれ。
2022年4月24日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note 真ん中が彼である。いつも親切にしてくれるレストランのスタッフと。
今日は家にずっといた1日だった。
早朝にパン屋にクロワッサンを買いに行き、
それからはZoom会議が二つ。
朝に写真家の伏見さん、昼過ぎに津内口。
合い間にFacebookを投稿する。
最近は土曜日午前中の日課になっている。
この研修はさまざまな人の応援により成り立っているので、
少しでも日々の成果を伝えたいし、自分が立ち会った物事を
忘れないようにするためでもある。
洗濯などもするうちに3時になってしまう。
本当は散歩がしたい。このところ、ナンヘッド・セメタリーに
もう一度行きたいとずっと思っているが今日もそれはできなかった。
『腰巻おぼろ 妖鯨篇』一幕、佳境の長ぜりふの応酬にかなり時間と力を
持っていかれてしまった。結局、終わったのが6:30。
今日は8:00にAlbany近くのレストランを予約してあるので、
身支度してぼちぼち出かけた。語学学校入学時からの友だちヤジードが
来週末に国に帰ってしまうので、彼と食事することにしたのだ。
彼は一旦帰国し、秋からはアメリカの大学に入る。
お父さんは会社の経営者で、運転手付きのロールスロイスに
乗っているらしい。彼は12人兄弟の末っ子。
年上の兄弟たちはみんなお父さんの会社で働いているが、
ヤジードだけは医者になる道を選んだのだそうだ。
今はラマダンでもあるから、少し遅めの時間にして、
牛タンを焼いたのやパスタを食べた。
お腹が空いている彼は勢い込んで食べ始めたが限界は早かった。
このラマダンですっかり胃が小さくなってしまったと嘆いていた。
たくさんいる兄弟や、馬や車を買ってもらった誕生日の話、
お父さんの会社にいる7人の優秀な日本人の話を面白く聴いた。
日本に来たことがあり、道の綺麗さや和牛の旨さに感動したという。
厳格なムスリムの生活についてもいろいろ教えてくれた。
彼にとって英国での最後の1週間が始まるが、
お世話になったホストファミリーの家を出て、
明日からハイドパーク近くのホテルで過ごすらしい。
さすがセレブリティ。
帰り道、Albany周辺の街並みや行き来する人々にビビる彼と歩いた。
お金持ちの自信と、少年らしさが入り混じる。素直で面白い奴だ。
どうか良い医者になって欲しい。
2022年4月22日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑開演3分前。40人も入ればいっぱいの劇場。全部セットみたい。
今日は変な空間を訪ねた。
これまでも、地元民も立ち寄らないようなスペースを見つけては
突撃を繰り返してきたが、今日のは飛び切りだった。
きっかけはソプラノデュオのFair Oriana。
近所の教会で知り合った彼らが
先週のセント・バーソロミュー・ザ・グレイトに続き、
別の場所で同じプログラムをやると誘われたので、
カナダ・ウォーター近くの会場まで歩いて行ったのだ。
Albanyから歩いて30分強。
これが変な建物で、開館から50年近く経つフィルムセンターらしいのだが、
全ての空間が芝居がかっていることこの上ない。
小さな映画館あり、劇場あり、ライブラリーやカフェあり、
廊下もトイレも、時代劇に出てくるような衣装や仮面、
小道具の数々が溢れ、さらに映画のポスターが数限りなく飾ってある。
内装が内装が凝りに凝っていて少しの隙もない。
今日は空間の力に完全に圧倒された。
小さな劇場での配信主体のコンサートだったのでお客は少なく、
二人も歌い方をガラリと変えて贅沢な時間だったが、
この建物にはどうしてももう一度来たいと思った。
毎週火曜に古い映画を観るクラブをやっているらしい。
Albanyの人も知らないだろうから、誰か連れて行きたい。
それだけの魅力を持つ場所だ⑤。
しかし、興奮しながら約1時間の道を歩き、
ゴールデンチッピーでの買い食いもしながら帰宅すると、
ダイアンの意見はまるで違った。
私が見せる写真をしげしげと眺めながら、
「私はロンドンのあらゆる場所を知っているがこの場所は全く知らない。
それにこの内観の天井の低さは怪しい。きっと悪魔が棲んでいるから
気をつけろ」と、本気が冗談がよくわからない表情で言う。
彼女はかなり気になったらしくずっと写真を見ていたので、
それなら、毎週火曜に行われるフィルムクラブに行ってみようぜと
誘ったところ、「アツシはスウィーニィー・トッドを知っているか、
私はパイになるのはごめんだ」とも言っていた。
自分は必ずもうまた行くだろう。
どうやって経営が成り立っているのかよくわからないが、
とにかくすごい場所なのだ。
↓すべての廊下がこんな感じ
2022年4月21日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑メールするのでDeptfordのカフェで会おうぜ、と言いながら写真を撮った
ヴァイオリニストのPeter Fisherさん。
渡英から3ヶ月を目前に、最近は疲れやすい。
歩いている時はどうということもないが、
授業中とか会議中とか、じっとしていなければならない時に
足の裏がむくんでいる感じがするようになった。
こうなることは予想していた。
英国には風呂がない。湯船に浸かることなど考えられない。
これは、外国で暮らす日本人がいだく定番の不満だ。
それから、私は2014年以降、劇団員だった禿の勧めで、
とある整体に月に一回お世話になってきたのだ。
それまでは、公演が終わるごとにくたびれていたのだが、
その先生に出会ってからは、調子が良くても悪くても月に一回は通い
コンディションが上向きになって平均化した。
ちょうど同じ時期に散歩したり走ったりする習慣を得たので、
それも良かったと思う。けれど今はその両方がない。
それに歩いていると、妙に石畳のゴツゴツを感じることに気がついた。
スニーカーを裏っ返してみると、すっかりゴムが削れて、裏面が直に
地面に接するようになっている。日本にいた時からややくたびれていた
ものをずっと履き続けてきたのだが、ロンドンの舗装は良くないし、
平均すると1日あたり13kmくらい歩いているので、
この2ヶ月半のあいだにかなりダメージを受けたのだ。
それに気がついてからここ1週間というもの、各地の靴屋を見て回った。
円安だし物価は高いしで節約したいのだが、どの店も底が厚くて
蒸れにくく、要するに歩きやすそうなものは高いのだ。
ところが、今日の午後、大英博物館を初めて訪ねたついでに
コヴェント・ガーデンに行ったら、良い靴屋があった。
すでに割引している上に、学割まで効くというお店。
踵の部分にエアーが入ったナイキのを選んだ。
博物館で古代ギリシャ文明に触れて唸ったばかりだったので、
NIKEにしようと思ったのだ。
センチとインチの換算もよく分っていないので、店員さんにそれを
話して何パターンか履かせてもらい、適切なサイズを決めた。
これまで履いていた古いのと別れを惜しみつつ、お店で処分して
もらうことにしたら次回使える割引券ももらえた。
その後てきめんに調子がいい。この靴でまた色々なとこに行ける。
何とか年末まで保ってくれると良いけれど、ダメだったらまたここで
割引券も含めたトリプルコンボで買おう。
その後、Conway Hallという伝統あるホールに行って室内楽を聴いたが、
これが良いものだった。雰囲気がとてもくだけていて、古今の作曲家が
つくったトルコをモチーフにした曲を次々に紹介するユニークなプログラム。
ある曲などは、演奏を始めてから少し経った時に、リーダーがストップを
かけ、初めからやり直した。「変なマスク(曲のタイトル)だったから」
というのが理由らしい。率直で人間的で、演奏一生懸命な人で、
これでいいのだ!という音楽と演奏への愛着が伝わってきた。
アンサンブルの中に日本人の方がいて休憩時間に話したら、
終演後にリーダーのピーターさんを紹介してくれた。
ピーターさんはAlbanyのあるDeptfordに住んでいるということだ。
Deptfordで会おうぜ! そんな話をしつつ撮ったのが、冒頭の写真。
2022年4月20日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑初日なので、演奏に緊張感があった。
昨日は渡英以来、2回目のロイヤル・オペラ・ハウスだった。
思えば、ロンドンに来て初めての観劇は『Theodora』というヘンデルの
どマイナーオペラで、街を歩くにも建物に入るのも緊張していたが、
たった3ヶ月足らずで慣れるものだ。
当日券を買うのも観劇前にコーヒーを飲むのも、パンだけは安くて
美味いグリニッジの店であらかじめ買って持ち込むのも板についてきた。
はっきり言ってロイヤル・オペラは高いし、
慣れたところでやっぱり場違いだし、身を切るような表現からは
程遠い場所だから、普段の演目を観たいとは思わない。
けれど、やっぱりイースターだったから、『ローエングリン』を
観たいと思ったのだ。
と、学校で言ったら、やはり先日から興味を持っていた
ロシア人のAさんが一緒にくることになった。
彼女は大変に個性的な人で、22歳でモデルの仕事をしているそうなのだ。
先日、突然にタイのバンコクに行って周囲を驚かせたが、
それも仕事での渡航だったらしい。
今日わかったことだが、学校を終えた後はいつもジムに行くそうだ。
さすがモデル。学校の中ではいつもピンクのスニーカーを履いていて
外に出るときは黒の革靴にかわる。教室の隅にある先生用の荷物置きに
勝手にそのスニーカーを置いていて、彼女が数日休む時には、
それを観てみんなが笑っていた。
そういうわけで、授業後に一旦別れ、それぞれの予定をこなして再集合、
セントラルを目指した。聞けば、彼女は毎晩セントラルで食事をしている
そうだ。グリニッジの辺は好きではないと言う。
こちらはホストマザーに教わったグリニッジの店の方が好きだと伝えたが、
セントラルのレストランが良いのだそうだ。
どうも、お金に余裕がある人のように思える。
劇場に着いて当日券を買い、自分は寝ないようにコーヒーを、
彼女は白ワインを飲んで一幕が始まった。酒強い。さすがロシア。
有名な前奏曲から始まる一幕をかなりの集中力で聴いていたが、
面白かったのはそれからで、休憩時間の終わりがけに電話がかかって
きたのでそちらを優先させ、結局は三幕まで戻ってこなかった。
驚くべきはそれからで、気まぐれに帰ったのだろうと思って、
優れた二幕、三幕終盤に集中していき、カーテンコールで拍手していたら、
電話が鳴った。なんと、劇場のバーにいるという。
しかも、行ってみたら英語の勉強をしていた。
・・・謎すぎる。
最安に近い席だったとはいえ、あれだけ熱心に観ていたのに3分の2を
不意にし、帰ったと思いきや、ずっと待っている。しかも英語の勉強をして。
深淵なるロシア。帰り道は、マリインスキー劇場に行った話を聴いた。
2022年4月20日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑自分がクジラに最も接近したのはこの時。2016年8月。
イースターを利用してのんびりした。
語学学校もAlbanyもお休みなので、買い物しながら近所を巡ったり、
床屋に行ったり、教会を訪ねたりした。
日曜に行った教会がまた面白くて、見た目は古風なのだけれど、
新進の宗派によるもので、ずいぶん砕けたセレモニーだった。
スタッフも若いし、アコースティックコンサートのような集会。
親しみやすい楽曲を皆で合唱したり、踊ったり、
ずっと旗を振っている人もいた。
近所にある教会では、スタンダードなカトリックの素朴な儀式にも
参加できたし、セントラルにあるセント・バーソロミューでは、
ひときわ壮麗で厳粛な内観も体験できた。
そこに、昨日の経験も加わった。
一口に教会行事といっても多くのバリエーションがあるようだ。
考えてみれば、日本の仏教にもさまざまな宗派があり、
二十世紀以降に新たに誕生した分派もある。それらと同じだと感じた。
と、このようにのんびりして英気を養い、
昨日から『腰巻おぼろ-妖鯨篇』に着手することにした。
渡英前に作品集をコピーして持ってきたのだけれど、130ページもある。
あの『唐版 風の又三郎』でさえ100ページほどなのだから、相当に長さだ。
ノーカットだと4時間30分くらいかかるのではないだろうか。
作者である唐さん自身、『腰巻おぼろ-妖鯨篇』が一番長いと言っていた。
初演の稽古の時、劇団員たちは台本を「電話帳」とあだ名したそうな。
悪役に扮した唐さんが「油揚げ」300枚をつなぎ合わせた背広?を
着て登場したことでも知られる。クジラを扱う台本だから鯨油に
引っ掛けての「油揚げ」だと聴いた。
これが登場すると、紅テントの中にすえた油揚げの匂いが立ち込め、
雰囲気があったという。
こういう大作に落ち着いて挑めるのも、英国研修の効能だ。
日本にいると日々の仕事に追われて、一つの作品への集中を
維持し続けるのが難しくなる。だから、まとまった仕事の合間に
台本づくりを押し込む。一度、ちゃんと読んで、頭に入れてしまえば、
それについて考え続けることは難しくなくなる。
昨日から、1日あたり6ペーずつダイピングしながら読むのを始めた。
初めは全然進まない感があるのだけれど、日々の目標のことだけを考えて
とにかくクリアしていくと、気づけば中程になり、終盤になり、
幕を閉じる段になっている。いつもそういう感覚だ。
終盤は睡眠不足で目が霞んだり背中が痛む。
けれど、一本を踏破する快感がある。
こうしてゼミログに書くと、途中でやめられなくなる。
明日もその次の日も、自分に課したノルマを確実にクリアするようになる。
これもゼミログの効能。皆さん、いつも読んでくれてありがとうございます。
2022年4月15日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑開演直前
昨日、いつもの通り語学学校に遅刻していき、授業を受けたところ、
放課に呼び出された。何か注意でも受けるのかと思ったら、
月曜に受けたテストの点がよく、昇級すべしと言われた。
冗談じゃない。この問題はマークシートのテストみたいなもので、
実は英語がわからなくても他所の問題を見れば解く方法があり、
それで正解を出してしまったのだと先生と事務スタッフに白状した。
そういうわけで内容をいかに理解していないかも伝えたら
大笑いされた。数週間で卒業していく周囲とは違い、
僕はゆっくりやらせてもらいます。
あと、遅刻をするのはホスト・マザーが素晴らしい人で〜
などと話して、これまでよりさらに深い理解をいただくことに成功した。
まことに良い学校、良いスタッフの皆さんである。
さて、Albanyではミミが忙しい。
イースターの連休を目前に、これからますます佳境に入っていく
各プロジェクトのために新人スタッフを迎えている。
彼らに働き方を教えるのもミミの仕事だ。
さらに、ヴィッキーやエマの家族や友人に不幸があったらしく、
彼らは劇場に出てくることができない。ために、ミミはますます
追い込まれた。そばでデスクワークしていたが、切迫感が半端なく
話しかけるもの憚られた。
しかし、昨晩は観劇の約束をしていて、
午後5時半には連れ立ってロイヤル・コート・シアターに出かけた。
それもあって彼女は、鬼の形相で仕事を片付けていたのだ。
ロンドンが地元のミミとの移動は楽だ。
おしゃべりしながらスイスイと劇場入り口に着くと、
観劇予定の何人かがミミに話しかけてくる。
この人は、いま売り出し中の劇作家でヒット映画のシナリオも書いた。
この人は、この劇場のスタッフで2カ月前に出産したばかり。
この人は業界のベテランで、制作も創作も何でもやるマルチプレイヤーだ。
この人は・・・
すでに地下にあるカフェのテーブルがミミによって予約されており、
夕食を食べた。そして客席に進みながら入場料はタダで済んだという。
席は2階席真ん中1番前の、要するに最VIP席。
素晴らしい友だちがいっぱいいるから、とミミ。さすがだ。
自分にとって2度目の観劇となるこの演目は大評判だ。
新しく登用された演出家がロイヤル・コートで成功を収めた、
そうミミが教えてくれた。
帰りにミス・ダイアンに教わった隣の高級カフェに飲み物だけ
飲みに行った。なるほど、ノエル・カワード、ベケット、
ジョン・オズボーン・ウェスカー・・・、様々な人たちがこの店を
訪れた写真、舞台のポスターや写真が飾られていた。
この店は初めてだったらしく、ミミも驚いていた。
良い指南役に恵まれたものだ。
他方、現実の世界に比べれば劇場や演劇の世界は小さい。
24時近くの帰りの電車の中で、ミミに、今日もAlbanyの近くで
キリスト像の前に立ち尽くして15分も動かない女性を見たと伝えた。
それから、お互いの国の政治や経済や風習の話になった。
別れ際、家に着いたら必ずメッセージをちょうだいと、ミミ。
ロンドンで危険な目に遭いやしないかと、こちらを心配している。
小柄なミミは、実に力強い。
↓COLBERIというカフェに終演後に行った。高いので一杯だけ。
2022年4月14日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑T•K•MAXXボンドストリート店。日本にも支店が欲しいくらいだ。
冬物の衣類はかさばる。そこで、当初は冬物のみを持って渡英した。
ロンドンに着いたら数週はホテル暮らし、そのうちに住む家も決まる。
新しい家に定住したら、あらかじめ選んでおいた春・夏ものを
椎野が送ってくれる。そう思っていた。
ところが、ロシアとウクライナの戦争がこの計画を狂わせた。
現在、飛行機による国際便はすべて停止。船便ならOKだが
これには3ヶ月もかかるので、春が終わってしまう。
仕方なく、買い物に出かけることにした。
初め、ダイアンにはプライマークという店を勧められた。
ロンドンの物価は高い。例えば、春もののジャケットを買おうとすれば
100ポンド(16,000円)を超える金額がかかる。
自分はそんなお金を文化庁からもらっていない。
プライマークなら35ポンドで買うことができる。
が、しかし、お店に行って眺めたり触ったりしてみたが、
これがどうにも心許ない。何かペラペラのフワフワなのだ。
知り合いはみんな知っていることだが、私の身体は柔らかい。
柔軟性のことでなく、表面が妙にムチムチ、フワフワしているのだ。
これは遺伝の影響と、小さい頃から水泳を一生懸命やったからだと
思う。とにかく大人の男なのに幼児みたいな質感なのだ。
それで、いつも硬めの服を選ぶ。
ちなみに、室井先生が巨大バッタをやっていた時に昆虫=外骨格の
素晴らしさを盛んに訴えていたが、私は学生の頃からその意見に
個人的な意味で賛同していた。外側が硬めでありたい。
硬くて、作業しやすくて、底々フォーマル。
あと、ロンドンでのセキュリティー的に内ポケットがあることも重要だ。
そんな服がないかなと、スポーツ用品や登山用の服屋も巡った。
日々ダイアンには、なぜプライマークで買わないのか?
と訊かれるのだが、拙い英語ではうまく説明できないし、
プライマークを嫌がる気位の高い人間だと思われたくないので、
口籠るしかなかった。フワフワにフワフワが合わないんですよ。
とどう言えば良いのか・・・
が、ついに素晴らしい店を発見した。その名をT•K•MAXX。
ここは各種ブランドから売れ残りを引き取って扱う店なのだ。
10年前の新品。そんなものもある。
ブランドに興味はないが、多様な選択肢があることが私を魅了した。
初め、馴染みのルイシャム・ショッピング・センターでこれを発見し、
元々120ポンド(20,000円)する好みのものを12ポンドで買った。
だだし、この時のものは完全に夏物だったので、
系列の店舗がセントラルに2軒あったのを思い出し、さっそく回ってみた。
すると、1,500〜4,000円くらいのもので全て揃えることができたのだ。
家に帰ると、ダイアンにこの買い物を絶賛された。
プライマークより安く、良質だったからだ。
彼女はスタイリストだったから、ブランドや素材感にも詳しく、
洗濯しやすさにも敏感なのだ。
日本の業者からの買い物は航空便を使うことができる。
Amazon Japanで買った新書は5日で届いたが、
家から同期間で本を送ってもらうことはできない。
商用でない輸送が停止しているのだ。
結果的に輸送費より安くあがった。昨日から春服である。
2022年4月13日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑セントラル。車いすで横断歩道無視する人がいて痛快だった。
これに書き忘れていたが、先週の土曜日のこと。
ナショナルのビッグレースがあるとダイアンに馬券を買いに行かされた。
自分も付き合い、Each Way(おそらく三単連)で買い、楽しんだ。
店員に「日本の学生です。ホストマザーのお遣いで初めて来ました」
と伝えたら、大笑いしながら代わりに記入してくれた。
ただし、これには問題があり、
結果的にダイアンのオーダーとは別の馬に賭けていたのだ。
彼女の馬が勝たなかったから良かったものの、
これで一着だったら大問題になったところだ。ヒヤヒヤした。
ところで。
語学学校の同級生、ロシア人モデルのアナスタシアはニーチェを
読んでいるらしい。『ツァラストゥラ』だそうだ。
話してみたら、ブルガーコフやトルストイ、ドストエフスキーも
読んできたそうだ。今度『ローエングリン』を観に行くと伝えたら、
一緒に行きたいと希望された。
イースターが迫り、毎晩イエスが死んでいる。
『スターバト・マーテル』はヴィヴァルディ、ドメニコ・スカルラッティ、
ペルゴレージ×3で聴き 、『ヨハネ受難曲』と『マタイ受難曲』は
2種類ずつ、ヘンデルの『メサイア』は苦手なのでパスしても、
毎晩のようにキリストの死に触れている。
さらに、カトリック系の教会で、
キリスト像に布がかけられているのを見ながらセレモニーに参加し、
帰りには松で作られた十字架をもらった。
家では朝食にホット・クロス・ブレッドを食べたり。
スパイスとドライフルーツを入れて、表面に十字の模様をつけたパン。
このパンは本当にどこでも売っていて、
格安スーパーでも気軽に並んでおり、端午の節句が迫ると
コンビニのレジ近くで柏餅を売っているのと似ている。
プロテスタントのダイアンが「最近のコンサートはどうだ?」
と訊くので「毎晩、ジーザス・クラウストが私の前で処刑されます」、
そう答えたら、大笑いしながら「来週の月曜には復活するから大丈夫だ」
と言っていた。
これが「神は死んだ」ということなのだ。
それでも人間は、繰り返しの毎日を新鮮に生きることができる。
↓教会でもらった十字架をダイアンはたいそうよろこんだ。
2022年4月12日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑Lewishamショッピングセンターに行ったら、こんなものが。
ベルリンの壁だそうである。さすがヨーロッパ。しかしこの絵は・・・
渡英から2ヶ月以上経ち、思い立つことがあった。
ワクチンの3本目を打とう。
日本にいる皆さんのFacebookを見ていると、
何人かが熱心に副反応についてレポートしているのを見かける。
英国ではなんとなしに次のワクチンを打つ話を聞かながいが、
今後のことを考え、実行に移そうと考えた。
ワクチンを打つためにには、まず病院の登録をしなければならない。
イギリスの医療システムは、家の近所の病院に自分を登録するところから
始まる。自分の場合は、すでに日本にいた時に7〜8万円払ってあって、
これが健康保険料のような役割を果たす。
このお金を払ってあることも、英国ビザ発行の条件なのだ。
それだけの強制力がある。
あとは現地に来て病院に行き登録を済ますだけ。・・・だった。
初めはホテル暮らしだったので、そのうちに家を探し当てて、
そうしたら病院登録をすれば良いと思っていた。
ところが、こうしてミス・ダイアンのもとでお世話になること
1ヶ月以上が経過してしまった。その間、病院には行っていない。
やはり、人は病気にならなければ病院に行く気にはなれない。
だいたい、イギリスの人は病気になっても、大概は市販の薬で済ませn
治るのを待つのだそうだ。
おまけに、歯医者には気をつけろとも言われる。
日本にいた時、私がもっとも頻繁に行く病院は歯医者だったが、
今回登録するような国立の病院で歯科治療を受けた場合、
お医者さんによっては噛み合わせが悪くなったりするとも聞いた。
こうなると、モチベーションが全く湧かない。
入国するためにお金は払ったけれど実質が無いようなもので、
それで今日までサボってきたのだ。だいたい、渡英の直前直後にかけて
自分はどれだけのアカウントを作り、登録手続きを行なってきただろう。
その一々に疲れ果て、イラついていた私は病院のことを後回しにしてきた。
が、ブースターのためである。それはもちろんコロナに掛からぬように
するためだし、かかっても軽症にしたいと思う。そして、何かの拍子に
3回目の接種証明を求められることもあるかも知れないので、
余裕のあるうちにやりたいと考えたのだ。
果たして、グリニッジ公園近くの病院の受付に行って事情を話すと、
記入用紙とネットのアドレスを教えてくれた。
これを持って、近くの国立海洋博物館のカフェに移動し、
記入を始める。紙はいけたものの、ネットがよくない。
受付の女性が書いたアドレスが解読できないのである。
ロンドンではこういうことがよくある。
人の書いたアルファベットが読みづらい。内容以前に、
これはeかなrかなとやり始め、結局ヒットしないので病院に行って
また訊き、面倒なので病院の受付前のイスに陣取って、
そこで登録をさせてもらった。これにも時間がかかる。
〇〇という病気がありますか? 薬物や飲酒、喫煙習慣は?
という質問が延々続く。翻訳ソフトを使わないと、
そんなマイナーな単語にはついていけない。
と、ここまで来て、身分証と住宅の証明書が必要だというので、
家に相応しいものをとりに帰って、またすぐ戻った。
すぐに戻ります。私の家は近いのです!と言って。
戻ってきたら、受付の人たちは笑っていた。
こうして、力技で登録は成った。
1週間後には完了の通志が来て、ナンバーが授けられるそうだ。
1ヶ月遅れで、残った宿題を済ますことができた。
次は本題のワクチンに進む!
/8(金)
学校→Kings Crossで打合せ
→South Bank CenterでCarmina Burana
4/9(土)
Zoom打ち→洗濯→『鐡假面』本読み→馬券を購入
→Lewishamで服を買う→Albanyでライブ
4/10(日)
ジャムの交換→掃除→唐ゼミ☆WS
→Murcellaで食事→→Lewishamで服のタグを外す
→近所の教会のイベントに参加
4/11(月)
学校でテスト→病院の登録→Eustonで情報交換
2022年4月 8日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑さすがのド迫力。頭のお鉢がデカい。人類を代表する頭脳といえよう
ここ1週間、語学学校ではディベートが盛んだ。
元ドラマーで、日本の大学に通った経験もある新米のビリー先生は
なかなかのアイディアマンで、生徒たちが楽しく授業に臨めるよう
準備に余念がない。
「幸せはお金で買えるのか?」という問いを立てて、
賛成派と反対派に分かれて議論を行う。
「世の中は金だ!」と言い切る外科医志望の青年がいて面白い。
決して迷わず、譲らず、臆面がないところが良い。教室が湧く。
ところで、自分が好んで霊園を訪ねていることを伝えると、
決まって勧められる場所がある。Highgate Cemetery。
ロンドンのトリップアドバイザーでも高位を獲得している霊園。
ここは何といってもカール・マルクスの墓所として有名だ。
自分にとってマルクスはコミュニズムの泰斗である以上に、
「お金」について考えた人という印象が強い。
「お金とは?」「価値とは?」
ディベートしながら大学時代に読んだ本を思い出していたところ、
ミミからメッセージが入り、午後の会議が中止になったと告げられた。
自分のいるGreenwichやDeptfordからHighgateまでは少し離れている。
電車で70分ほどかかる上に、午後5時には閉園する。
今日は晴れているし、もってこいのタイミングだった。
3時に目的地に着く。
途中、手前の公園でトイレを探していたら、小さなギャラリーを発見。
受付にいたスタッフと話しこんで思ったより時間が経ってしまった。
現代美術の作品や創作ドキュメントを記録したDVDや冊子が
たくさん置いてあって、規模は小さいけれどもBANKARTを思い出した。
・・・池田さん。
話をもとに戻すと、
Highgateの入口で受付のおじさんに入園料を求められた。£4.5。
学生割引なし。説明書きをもらって進んでいくとマルクスの墓があった。
巨大な頭がついていてわかりやすい。正直言って深刻味に欠けるが。
おじさんによると、像のついたこのお墓は移転した後のもので、
霊園の真ん中あたりに元々のオリジナルがあるとのこと。
これも一応、確認した。
途中ベンチに座り、30分ほどミミとZoomしたりもして、
1時間以上のんびりした。その間、30人くらいはマルクスのお墓参りを
していた。御供物のお花がいくらもある。
しかし、マルクスのお墓が名所になって入園料をとっているとは、
本人が知ったらどう思うだろう。思わずそんなことを考えてしまう。
観光地化されすぎている感もある。
自分としては、LewishamのNunheadの方が神秘的で軍配が上がる。
最後にもう一度、受付に寄っておじさんと話した。
日本人だと言ったら「中国人はけっこう来るけど・・」と珍しがられた。
どうしてロンドンにいるのか訊かれたので、政府の派遣で約1年滞在して、
Albanyで作品づくりとコミュニティワークを学んでいると伝えた。
それから、記念にポストカードを2枚選んで買おうとしたら、
有料のパンフレットと併せて「私からプレゼントしたい」言われた。
「君のコミュニティワークのために!」とも。
・・・さすがマルクスの墓所だけある。
キャピタリズムとコミュニズムが良い具合いにブレンドされて
帰り道は得した値段以上に清々しい気持ちになった。
Gustav Mahlerの娘さん、Anna Mahlerのお墓もたまたま発見できた。
自分のスマホにはお父さんが作った曲がいくつも入っている。不思議な感慨。
↓このおじさんに会えて良かった。
2022年4月 7日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑バロックから後期ロマン派まで、ガッチガチのクラシックを一人で
歌い切った後、なぜか子どもたちをステージに上げてポップスの合唱を
したジョイス・ディドナート。ヤンキー・ディーバの異名は伊達ではない
昨日、4/6(水)を以って、YAHOO JAPAN! ニュースの
イギリスへの配信が停止してしまった。
人間とは愚かなもので、自分に不利な状況には目を背け
何故か楽観的に考えてしまう。2月に告知がなされて以来、
なんとなく危機を察してはきたが、そんなこと言っても、
なんだかんだ見られるんでしょう?と心に甘えを持ってきたのだ。
かくして4/6(水)当日。
朝は、普通に見られた。それから、見出しだけ見られるんだけど、
ニュースの中身は見られない。そんな状況になった。
この時点で、見出し見られるんだ!充分!充分!
などと、ちょっとラッキーに感じていた。
ところが午後になり、予告通り、完全に見られなくなった。
仕方がないので、ケータイにはNHKのニュースアプリをダウンロード。
こうなると、下らないなあ、などと半ばバカにしながら眺めていた
芸能ニュースを、自分がどれだけ楽しんできたか痛感している。
最近とみに激しくなった連ドラや大河ドラマのヨイショ記事。
「この図形は何のカタチに見える?」の心理テスト。
プロ野球ニュース結果、ひろゆきの本から抜粋した自己啓発系の記事。
桜情報に小林麻耶の暴走、小室圭の試験結果に至るまで、
なんだかんだ言いながら楽しみにしてきたのだ。
わざわざ自分から検索しにいく程ではないこれらニュースが無くなり、
これからのイギリス生活に、潤いが少し減るように思う。
今週に入ってから、午後はAlbany &地域調査、
夕方から観劇というルーティンが戻ってきた。
昨日はバービカンでジョイス・ディドナートの演歌歌手風コンサート、
今日はAlbanyで子ども用プログラム『SLIME』を観た。
オフィスでは、前より日常会話に入っていけるようになった。
フィッシュ&チップスはSKATEという魚が好きと伝えたら
大いに共感を得たが、パイ&マッシュの店でキドニーパイと
ジェリード・イール、それにチリ・ヴィネガーを鬼ほどかけて
常食していると言ったらドン引きされた。
この組み合わせはごく一部のコアな英国人のみが好むもので、
苦手な人が多いらしい。外国からやってきてふた月の人間に
「オレはクサヤと鮒ずし、豆腐窯が大好きなんだよね」と言われた
ようなものだろうか。美味いと思うけどな。
『黒いチューリップ』の台本打ちが約2週間で完了。
明日から誤字脱字チェックしながらまた読む。英国の室内灯は暗い。
目が疲れているので、ブルーベリーを買いにいかなければ。
2022年4月 6日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑近所のFordham Parkに石碑があって、お供え物が動物たちに食べられて
いた。リスやキツネを毎日見かける。
今日は"黒人"について書く。
昨日"宗教"について触れたので、今日は"人種"だ。
日本にいた時、こういう話題をどうして良いのか分からなかった。
一昨日、ロイヤル・コート・シアターで渡英後50本目の劇を観たが、
これが"黒人"についての芝居だった。1ヶ月くらい前、
ブッシュ・シアターで観た劇も黒人のサッカー少年3人のみの劇だった。
それに、最近はAlbanyとの関わりの中で調べ物をしている。
1981年1月に起きた「New Cross House Fire」という事件についてだ。
これにも人種の問題が深く絡んでいる。
Albanyから歩いて10-15分ほどのところで起きた出来事。
10代後半の黒人青年たち13人がホームパーティー中の火事で亡くなり、
これがきっかけで、大規模な人種差別撤廃運動が起こった。
警察当局の事件の処理の仕方に疑義が寄せられたためだ。
異人種が起こした放火や事故だったのではないか。
その上で、黒人の青年たちが自らの過失にされてしまったのではないか。
そういった疑問に対して、公式な見解は現在に至るまで、
当事者たちの過失で済まされている。真偽はわからない。
が、これが運動につながり、現在の社会を生みだす
大きなきっかけとなったのは確かだ。
この国が多様性を重視するきっかけとなった事件がここLeshamの
一画で起こった。それで、モニュメントや事件現場だった場所を
見て回っている。
日本にいる時、黒人の人を見ると正直ギョッとした。
慣れないし、たまにしか見ないから怖いし、驚いた。
知人が一人もいないので、距離感がわからなかった。
ところが、こちらに来て激変した。
まず、ミミのおかげ。それからチーフプロデューサのヴィッキーや、
技術スタッフの頼れる男ケイトリンもいる。
黒人の人といることがすっかり当たり前になった。
全体的な感想としては、体のバネやリズム感がすごい。
クラブイベントでちょっと体をゆすっているだけの姿を見て
「ほお〜」と見惚れてしまう。サマになっているし、
それくらい違いを感じる。
ただしミミは例外で、彼女は身体能力!というより知的で
いかにも育ちが良さそう。当たり前だけれど、人によって違う。
先日、シンポジウムで登壇したミミは、自己紹介で「I am a black woman.」と
言っていた。あ、こんな風に挨拶の中に人種の説明が自然に混ざるんだ!と、
ひとつ心がほどけた。ロイヤル・コートの劇の2回目はミミと行く予定。
黒人としての彼女がどう思うか、教えてもらいたい。
こうやって、信頼関係をもとにした一つ一つのやりとりの中で、
適切な距離感やエチケットを覚えている。
2022年4月 5日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑気の良い二人!初めてできたイスラム教徒の友人。モスクに行きたい!
昨日は学校に行くと、アラビア語圏の友だちがグッタリしていた。
聞けば、ラマダンに入ったからだという。
「朝ごはん食べられないから、チカラでないよ」
と英語で泣きごとを言っていた。
完全に断食ではなく、夜中のうちは飲み食いできるというシステムだ。
これがきっかけになり宗教について話し込んだ。
自分は物見遊山的な興味でもって、聖書やコーランを読んだことがある。
高校が曹洞宗系の学校だったので、仏教、禅宗の本も少々。
ゾロアスターとかグノーシスの本も暇だった学生時代にパラパラやった。
特にグノーシスの、ニセモノの神様が自分をホンモノと思い込んでいる、
というくだりは深い。世界の真実の一端がここにある。
話を戻すと、一神教の中で、イスラムは後発の宗教だ。
ユダヤ教があってキリスト教があってイスラム教がある。神様は皆同じ。
そのために、コーランには特に聖書の反省が生かされているように思う。
というのも、聖書(特に旧約!)は物語から教訓を読み取るために
異常に多くの解釈を生んでしまうのだ。それが面白いのだけれど、
同時に多くの論争を生んだ。そこへいくとコーランは実践的だ。
日に5回お祈りするべしとか、より貧しい人に財を分けなさいとか、
利子は悪しきもの、とか。具体的。目の前で友だちが苦しんでいる
ラマダンにしたって、これはみんなのために健康法なのだと思う。
年に一回デトックスしましょう。ということではないか。
僕は演劇をやっていて、高校時代からギリシャの古典劇が好きに
なったんだけど、現在にこれらが伝わったのはアラビアの人たちの
おかげなんだ、と、そんな話もする。
ローマ帝国でキリスト教が国教化されたときに、
ギリシャの神々は数も多いし怪しすぎて排除したらしいのよ。
それで、一端アラビアで保管されて、十字軍との聖戦の中で
西ヨーロッパに古代ギリシャ文化がカムバック。ルネッサンスに至る。
君たちの断食のおかげだ!とか言って。
「オレたちがブタを食べないのは、ブタは不衛生だから食べると
病気になると考えているだ」とも教わった。
「現代のブタは衛生面で大丈夫だと思うよ」とこちらは答える。
それくらいにフランクに話せるところに、この学校の良さがある。
せめて君らの前では食べないようにするよ、と約束した。
同じムスリムでもラマダンの捉え方は人さまざまで、
「オレは働いているので週末だけで良い」というナイスガイもいるし、
「ラマダンなので1ヶ月間学校を休みます」という女子もいる。
この大らかさがギリシャの文化を延命させたのではないかと思う。
唐さんとアラビアといえば、どんな関わりがあるだろう?
(1)アリババ・・・アラビアン・ナイトの外伝より
(2)盲導犬・・・・ファキイルという名前
(3)海の牙・・・・シェエラザード
※(3)はバングラディシュ公演の影響と思われる
(4)鉛の兵隊・・・小泉政権下のイラク派兵がモチーフ
「ラマダンの三日月が夜空をしゃくる!」という名ぜりふ!
と、すぐに思いつくだけでこれだけある。
4/1(金)
学校→久々のAlbany出勤→WIGMOREでヨハネ受難曲
4/2(土)
掃除・洗濯→『鐵仮面』本読み
→『WOLF!』@Canada Water Theatre→買い物@Canary Wharf
4/3(日)
『下谷万年町物語』WS※電波とぎれがちで迷惑をかけ、凹む
→『WOLF!』2回目@Albany→Roth +London Sym@Barbican
4/4(月)
学校→Albany→New Cross House Fireの調査@New Cross
→For Black Boys......@Royal Court ※渡英後50本達成!
2022年4月 1日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑この犬の絵がもっとも面白かった。
今日も方々に出かけた。
学校が終わってケータイショップに行き、これをひと月更新。
それから一度帰宅してZoom会議に臨んだが30分足らずで終わる。
拍子抜けしたところに机を見ると、ミス・ダイアンが残していった
フランシス・ベーコン展のパンフレットがある。
そこで突撃することにした。
とにかく5:00pmまでに入れば良いのだ。もちろん学生料金で。
このあたりの反射的移動が速やかになってきた。
頭の中に地図と路線図を思い描いて、最短距離を出す。
交通費が安くなることも考える。2ヶ月の成果だ。
まじまじ観たが、犬の絵がもっとも気に入った。
フランシスは、欲動が強くて、神経剥き出しで、
自分に振り回されっぱなしで生きづらい人生だったと思った。
が、ミス・ダイアンに言わせると、それ以上に周りを不幸にしたそうだ。
なんとも返答に困るやりとりを帰宅してから受けた。
『ベルセルク』『鋼の錬金術師』『ハンター×ハンター』など
多くのマンガがインスパイアされているのも感じた。
今日はもう一つ。
Sadler's Wells Theatreに行き
William Forsythe振付のEnglish National Balletを観た。
実に1990年年代的なトレンディなノリで、
まるでティーンたちの文化祭かダンスパーティのようだった。
もちろん、惜しげもなく披露されるテクニックの数々。
ガチガチの古典をやっているダンサーがたまにこういうのを
やると嬉しい、そういう喜びが溢れて、客席を巻き込んでいた。
大変な盛り上がりで幕を閉じた。
ところで、帰宅するとダイアンは盛んにチョコレートを勧めてくる。
ロンドンではキットカットなど安く大量に買えるので、
自分はつい手が伸びて、ズブズブになることを恐れている。
アイスクリームとチョコレートは大敵なのです。
と言い続けているのに、母の日のプレゼントにと息子が贈ってきたから
と勧めてくる。こう言われては断れない。
彼女は私が食べるのを見ながら嬉しそうだ。
こちらはフリで言っているのではない。
歯止めが効かなくなることを心の底から恐れているのだ。
人は、人が怖がることを仕向けてみたくたる。
そういう落語=古いコメディのお話が日本にあることを彼女に伝えたら、
笑っていた。

2022年3月31日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑古き佳きダンスホール。現役だ。
4日目に歩いた場所の記録を残したい。
この日はAlbany周辺まで行き、皆は元気かな?と思いつつもちろん建物には
入らず、まっすぐに南下するコースをとった。
Lewishamエリア中央部分の南端Honor Oak、ここを目標にした。
かなり単純な道なのだが、延々と登りなのだと実感しつつ歩く。
このゾーンは国鉄の駅がいくつもあって、
面白いのは同じ路線の駅ではないことだ。
つまり、北西のロンドン・ブリッジ駅から放射状に線路が伸びているため、
自然と何本もの線路を渡る仕組みなのだ。
つまり、地元の人たちにとって、都心に出るには簡単だが、
東西の移動にはバスを利用することになる。
自分は物見遊山なので、ゆっくり歩きながら写真を撮る。
結論から言うと、この日に歩いた地域は完全に戦後の新興住宅地らしく
いずれも同じ規格の家がズラリと並んで、それが英国の人の気質により、
大事に大事に修繕されながら使われてきた印象だった。
日本人も物を大切にして始末が良いと思うが、
イギリスの人たちの物持ちの良さはかなり突出していると思う。
↑この中が体育館化しているなんて、想像できなかった。
Brockleyで面白かったのは、覗いた教会だ。
先日、教会でStabat Materに感激してから、教会への垣根も取れ
むしろ、またあんな良いことないかなと積極的に除くように
なったのだが、ここでも意外な光景を目にした
覗いてみると、イスが取り払われて、
マットが敷かれた体育館状態の教会内で、
子どもたちが跳び箱や体操、ダンスの練習などをしていたのだ。
変なおじさんが覗いているわけだから、
レオタード姿の先生が走ってきて「何ですか?」と質問された。
「私は劇場で勉強している日本人だ」と答えたところ、チラシをくれた。
見れば、イースターに向けて出し物の練習中なのだ。
面白そうだから、これは見に行く。
↑イースター、キリスト教社会では重要な祭典だ。
さらに南下するとForest Hillに出て、大きな霊園がふたつあった。
先日の墓地が良かったので覗いたが、こちらはかなり整然としたもので、
初回以上の驚きはなかった。が、より現役感がある分、バルーンや花文字で
「DAD」とあるなど、当地の人たちが亡くなった肉親に込める
想いの表し方を知れて良かった。
↑霊園入口、ひっきりなしに車が出入りしている。墓参が盛んだ。
一帯の丘の頂上として、One Tree Hillという場所に出た。
東京でいうと戸山ハイツの箱根山的な雰囲気だが、
歴史的には古代ローマのブーティカ女王がここで現地人に敗戦したり、
エリザベス1世がここを訪れたり、第二次世界大戦中は、敵の飛行機を
撃ち落とす砲台ともなったらしい。
↑これで撃ち落としていたのだろうか。
そしてHonor Oak。
ちなみに、語学学校の同級生である超お金持ちアラビア人青年は
この地に下宿しており、翌日「なぜ来ることを教えてくれなかった?」
と責められた。語学学校の生徒たちは、みな自分より郊外に暮らしている。
うちはアクセスも良いし、街場も近い上に自然にも恵まれている。
何より、生粋のロンドン人かつ芸術に精通したミス・ダイアンがいる。
友人たちはみな愛情を以ってホストファミリーに迎えられているようだが、
自分は相性の面で恵まれたと思う。
帰りは、スタスタと下るだけだった。
巡っていた中でぶっちぎりで変な町がCatfordであることは揺るがない。
あとは、南西にあるCrystal Palaceを訪ねればLewishamひと通りだ。
2022年3月30日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑右がジュエリー・イール(ウナギの煮こごり)
紅茶の付けて1,400円くらい。豚骨ラーメン1,800円がいよいよ変だ。
今日は疲れている。
連日の遠足で疲労が蓄積してきている。
さすがに一日20キロを連日はやりすぎだったか。
そこで今日はライトに、元気になる話題を。
日本人が死ぬ前に食べたいものは鰻丼だそうだ。
ほんとか!?と怪しんできたが、最近その気持ちが分かる。
だからと言うわけではないけれど、渡英前、浦和まで行って鰻を食べた。
最近、ウナギに対する思いはイギリス人も同じだと知った。
体調を崩したミス・ダイアンに、ウナギ買ってきて!と頼まれたのだ。
ロンドンではより身近にウナギがある。
フィッシュ&チップスと並んで庶民的な料理にパイ&マッシュがあるが、
その付け合わせで、ぶつ切りのウナギを酸っぱく煮たものが
トッピングできるのだ。そして、ここが肝心なのだが、
通常は温かで食べるこの煮ウナギを、
冷たい状態で食べるのがネイティブなのだ。
ウナギは英語でEelなので、「ジュエリー・イール・プリーズ!」
と言えと教わった。周囲にまといつく煮こごりが宝石のようだと
いうことらしい。
これは美味い。チリヴィネガーをたくさんかけて食べると尚うまい。
酸味もあるし、疲れたらこれだと思うようになった。
ついでながら、英国の人は揚げ物によく塩と酢をふりかける。
酸の取り方が上手いようだ。風呂で身体を温められないので、
疲れの抜きかたを確保し、長期滞在に向き合っている。
他に、
ミキス・テオドラキス作曲のギリシャ音楽を聴いたり、
フォークソング同好会に顔を出したりしている。
遠足の成果はまた明日!
2022年3月29日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑休憩時間に話を聞いた。こんなに達者な人たちが身近にいるなんて。
3/27(日)からイギリスはサマータイムに入った。
この日だけ1日23時間にして、今後の日照時間を有効に使う工夫と
理解している。当日はすっかり忘れていて、朝起きた時はいつもより
長く寝ることができたと思った。そこから身支度をして
ワークショップのためのZoomを立ち上げると、誰もいない。
おかしいと思ってしばらく待機していると、
ミス・ダイアンが時計を1時間繰り上げてくれと頼んできた。
一気に事情が分かった。これからの日本との時差は8時間。
3/28(月)は面白いことがあった。
学校を終えた帰り、たまたま一緒になったエリザベス先生と歩きながら、
先週に彼女の住まい周辺を歩いたことを伝え、セメタリーの面白さを
話し合った。彼女も好きらしい。次はHighgateに行くべきねと教わる。
カール・マルクスのお墓で有名な墓地だ。
それから床屋に行った。英国で2回目。前回とは違うところ。
寝落ちしたら"Don't sleep!"と言われた。日本ではこちらの状態に
床屋さんが寄り添ってくれるが、ロンドンでは彼が髪を切りやすいよう
こちらが合わせるのだ。まことに厳しいが郷に従う。
さっぱりして家に向かった。
昨夜・早朝と書類を作ったので少しのんびりしようと思ったのだ。
それで坂を登って行ったが、気になって、家の直前にある教会を
初めて覗いてみた。教会は開門していればウェルカムだと聞いたけれど、
慣れないのでなかなか緊張する。
けれど、すぐに入って良かったと思った。
オルガンとヴィオラ・ダ・ガンバを弾く男性が合わせて二人、
歌手の女性が二人の合計4人で演奏会の練習をしていたのだ。
お客さんは自分だけ。
アルトの女性が歌っていたので、手の空いていたソプラノの人が
相手をしてくれた。フランスの古い歌を歌っているらしいが、
かなりレベルが高い。教会の反響によるハーモニーが抜群。
席について聞き惚れていると、アルトの人が寒さを気にし始めた。
ソプラノの人が「温かいお茶を淹れてくるね」と。
すっかり魅了されたので、思い立って坂のふもとに走り
いつものパン屋でマドレーヌを買ってプレゼントした。
今日のチケット代ということで。そこで5人で少し話ができて、
今度の演奏会の情報をメールしてくれることになった。
オルガンの人は東日本大震災前の日本に来たことがあるらしく、
当時、心を痛めたそうだ。写真を撮らせてもらって、練習再開。
イントロを聴いて驚く。
ジョバンニ・バティスト・ペルゴレージの『スターバト・マーテル』
いつか生で聴いてみたいと20年来おもい続けて来た曲だ。
アンドレイ・タルコフスキー監督作品の中でも特に好きな『鏡』の
中で使われた音楽だ。この監督は曲使いの名人で、
ヘンリー・パーセルの『インドの女王』、
バッハの『ヨハネ受難曲』や『オルガン曲BWV639』など、
大好きになった曲をいくつも教わった。
特にペルゴレージはいくつもの録音を聴いてきた。
それが突然に始まったのだ。呆然としながら練習の区切りで、
感激したこととその理由を伝えずにはいられなかった。
「excellent!」と言って向こうもよろこんでくれた。
本番は4/10(日)18時からだそうだ。必ず行く。
コンサートホールとはまた違った格別の体験だった。
たまたま入った教会で、ずっと聴きたかった曲を聴けるなんて。
音楽を進行させながら、失敗を笑って乗り越えながら工夫を重ねて
掛け合っていく姿が、本番では体験できないステキさだった。
先週末から週明けまでの動きは下記の通り。
3/25(金)
学校→本読みやWSの準備→Brackheathでギャビンやミミ、
ミミのパートナーとピザを食べ→ホールでポップスコンサート
3/26(土)
テツヤとの配信→『鐵假面』本読み→Lewisham Art Houseで
インスタレーションを観る→Southbankで『ヨハネ受難曲』
3/27(日)サマータイム始まる
『下谷万年町物語』WS→掃除・洗濯→Notting Hill GateでCD買う
→Oxford Sircusで半袖シャツ買う→WigmoreでSixteen→
帰宅後、母の日のプレゼントをミス・ダイアンに渡す
3/28(月)
学校→床屋→近所の教会でPergolesiの練習を聴く→
BarbicanでMikis Theodorakisのギリシャ音楽を聴く
毎日『黒いチューリップ』に取り組んでいる。現在、二幕序盤。
まだまだこれから先が長い!
2022年3月25日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑グリニッジで馬に乗る警察を見かけた。
今日も歩きに歩いた。
語学学校を終えて、一度帰宅した。
ミス・ダイアンにお使いを頼まれたのだ。
彼女は体調が良くないので、代わりに郵便局、スーパー、薬屋を
巡ることになった。紙に書かれた指示に従うだけだが、
おかげで、こんな近くに郵便局があることを知ったり、
便利なドラッグストアの存在に気づいた。
イギリスのスーパーで野菜を買うのも初めてで、
彼女のメモを頼りに店員に訊きながら買い物をした。
Rochetというのはルッコラのことだと分かったし、
人参は本数ではなく、重さでの買い物なのだと学んだ。
大きい方が得だろうと買った人参は、ダイアンには大きすぎた。
薬屋では、すでに電話でのオーダーもなされていて、手紙を渡せば
一式揃えてくれたが、店員が入れたティッシュペーパーがダイアンの
想定と違い、あとで返品した。返品する時に一旦断られたので、
店でダイアンに電話して、スピーカーフォンで直接会談してもらい
ことは成った。平日の午後に家の近所にいるのが初めてなので、
また違った風景が見える。聖アーシュラ女学院の女子高生たちが
紙切れ片手に大声で電話している。「国語9!数学9!・・・」
成績が出たのだろう。色気が全くないワイルドな女学生たちには
元気いっぱい。未来を切り開く元気が備わっている。
ここから散歩。
The AlbanyのあるDeptfordを少し南下すると、東西に走る道路がある。
交通量が極めて多く、国道246に似ている。多くの種類のバスが走る
ことからも、かなり重要な道路であることがわかる。
この道を主流に各地に枝分かれしていくことのだ。
今日はここを西進する。
「一品行YIP」という店があって、小さいが、ここはアジア-日本の食材が
たくさんあった。考えてみたら、横浜でもっとも韓国の食べ物が
揃うのは福富町の小さな店だ。将来、困ったらここに来よう。
↑醤油、味噌、酢、みりん、海苔...etc。日本食を振る舞うときはここ!
国鉄New Cross駅を越えると、Deptford Hallというのがあった。
残念ながら扉が閉まってて入れない。
さらに歩くとGoldsmiths University
という大学があった。かなり変な建物。中の様子が丸見えなガラス多用の
デザイン、きしめんが舞うようなオブジェ。後でダイアンに訊いて分かったが
芸大だそうで、かのダミアン・ハートの母校らしい。
New Cross Gateが栄えているのに驚いた。通り沿いの商店、
大型スーパー、ここが特に交通の要所であることがわかる。
↑近くに美味そうなハンガリー料理屋を発見
New Cross Bus Garageまできたところで、進路を南に切り替える。
Nunhead Cemeteryという墓地が見たい。イギリスの一般的な霊園が
どうなっているのか知りたかったのだ。坂を登って峠を越えながら、
途中、Telegraph Hillという公園を通った。斜面にある芝生や遊具で、
子どもも大人もよく遊んでいる。日光浴の数の多さ。
ジャグリングの練習に励む青年もいた。
Nunhead Cemeteryは今日の一番の収穫だった。
地下で眠っている人には申し訳ないけれど、お邪魔させてもらった。
ランダムに点々とする墓跡の様子、水平すらとっていない英国のお墓の
様子に文化の違いを感じた。
朽ちた煉瓦造りの礼拝施設が立ち入り禁止になっていて、
タルコフスキーの映画のようだった。日没も迫り、園内はひんやり
していたが、ジョギングする若い女性が猛スピードで駆けていった。
↑Nunhead Cemeteryの入口。正面にメインの建物。両側にお墓が点在。
住宅もお墓も、日本と英国では発想が違う。
塀を信じる日本。壁しか信じない英国。
このところ体験している、ミス・ダイアンが自宅に施すセキリュティの強さ。
閃くものがあった。
進路を戻して国鉄沿いに歩き、Nunhead駅を経てPeckhamに着く。
途中、集合住宅の共有施設では、空手の稽古帰りの少年たちや、
小さな体育館でエアリアルの練習をする女性を見た。
Peckhamは都心に近く交通の要所でもある。
Deptfordをさらに大規模にした雑然さに充ちている。
エリザベス先生の家はこの辺と聞いたが、彼女の通勤経路が想像できた。
時おり遅刻をするわけだ。帰路はバスで。ダイアンの望むティッシュは
明日に持ち越しだが、駅のフリーペーパーは手に入れた。
一旦、家に帰り、改めて9:00pmに出かけた。
ORIVER'S JAZZ CLUBが家から5分のところにあり、
有名な老舗なのだとエリザベス先生が教えてくれたのだ。
ダイアンにこれを伝えたら、あそこのオーナーはミスター・セックスだ。
同性愛の人がいっぱいいるから気を付けなさいと笑いながら言われた。
が、店に入ると客は10人ほどで、演奏もまあまあ、
夜中まで付き合うわけにもいかないので、ある程度で引き上げた。
週末にまた行って、この店の真価を知りたい。
連日20㎞以上歩く。なんだかお遍路さんみたいだ。
1月末に渡英して以来服装が冬のままだが、昼間に歩くと汗ばむ。
が、飛行機を使った国際郵便が戦争の影響で停止中らしい。
春や夏のものを買うしかないか。と悩んでいる。
2022年3月24日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note 
↑初めて、Lewishamより南に行く。あのトンガリつくるのは大変そう。
今日もよく歩いた。
早朝にBanKARTの池田修さんの訃報が届いて混乱する。
年末に会ったのが最後だった。KAIKOがオープンしたばかりなのに・・。
池田さんは常にいろんな企画を進行させていたけれど、
年に一度ほどご自身の好みを全開にした催しをやっていたと思う。
その仕事が好きだった。原口典之さんの展示の時は何度も通った。
「やっぱりファインアートすごいよね」
と言う池田さんが可笑しくて、でも本気で同感した。
劇団もしんどい時期に助けてくださった。
結婚する前、元旦に帰省するため新幹線に乗ったら、
同じ自由席に手ぶらの池田さんがいた。自分は名古屋で池田さんは大阪。
大晦日にBanKARTで宴会をやって、翌朝に帰省するところという。
現場が好きで、スタッフやお客さんといるのが好きだと言外に伝わった。
ちょっと寂しがり屋な感じを受けて、また別の意味で池田さんを信頼した。
・・・・・。
日本に電話したら止まらなくなってしまった。
室井先生の研究室が閉じられる日でもあったのだ。
もうとっくに卒業したはずの学生時代がもう一度終わってしまった
という実感に驚く。いまだに先生に依存する心があるのだと実感。
もう40歳過ぎているのに。18-34歳までのあまりに長期間、
一緒にいたから言い尽くせない。
椎野やKAATの眞野さんにも電話した。
色んな人に世話になりまくっている・・・
遅刻して語学学校に行く。
新米先生が日本に留学して名古屋に滞在していたと分かり、
授業後にいろいろと話した。その後、ミス・ダイアンに頼まれた
買い物をして一度帰宅し、すぐ散歩に出かけた。
ここからが本題。今日はLewisham駅から初めて南下する。
すぐに新興の住宅地になって、生活に余裕アリというゾーンが広がる。
Lewisam Hospitalの裏に広がるLadywell Fieldsという公園。
子育てしやすそう。こちらの人は日光を大事にする。ピクニックが上手い。

↑遊具コーナーには柵がある。親は楽だろう。
さらに南下して30〜40年前の新興住宅地を抜けると
面白い街に出た。Catford。初めCatfoodにしか見えなかった。
巨大なペット用品店でもあるのかと思った。
かに道楽のカニくらいのサイズで巨大な猫もいたし。
懐かしい雰囲気の活気ある商店街。

↑絶対にFOODだと思っちゃう。
築90年のBroadway Theatreも発見したが、
改装中のようだった。後でミミから、設備にいろいろ問題があって
改修がうまくいっていないと聞いた。

↑改修中のBroadway Theatre
交通もメディアも未発達の時代に地元に貢献してきたであろう威容。
さらに南下し、巨大なカー用品店や洗車場がいっぱいある地区に出た。
店も国道沿いの感が強い。16:00前にBellinghamに着き、
国鉄で移動しようかとも思ったけど、やはりバスでLewishamに戻った。
今日行った地域はおしなべて横浜の本牧的だ。後からできた街の雰囲気があり
整然とした住宅地や巨大なお店がある。

↑Bellinghamの国鉄。都心まで30〜40分ほど。
ショッピングセンターのカフェで16:30からミミとzoomで話す。
「まだ西に行ってないんだけど、貧しくて治安が悪いのって
LewisamとDeptfordだけ?」と周囲に慮って小声で聞いたら、
ミミに爆笑された。ほぼYesという返事だ。
最近、ミミの話をしてよ、とお願いしたら、
彼女は大学時代に舞踏に興味を持ち、ダンサーの先生に教わったことを
教えてくれた。土方巽も大野一雄ももちろん知っていると言われて、
唐十郎門下、元上星川住民の血が騒ぐ。自分はミミの役に立てる!
オレが気に入りの蕎麦屋で食べていると、大野先生の家から
出前の電話がかかってきたものだ。そう伝えてまた笑われた。
将来、ミミを日本に呼びたい。ここでしてもらっていることの
お返しを少しでもできたら、どんなに良いだろうと思う。
ところで、Zoomのためにカフェのテーブルにパソコンやケータイを
出すことには緊張感がある。警備員さんのいるセンターの中だから
大丈夫だろうか? 一店舗ずつのカフェの軒先だと場所によっては危険?
そんな風にビクビクしながら、初めて家と劇場ではない場所でZoomした。
カバンは常に視界のうちに入れる。
もう一つ、忘れないように書いておきたい。
ショッピングセンターを出たところで、電動車イスのダウン症の女性と
すれ違った。男性二人がお世話していた彼女は30歳過ぎくらいだろうか。
ふと見ると、車イス付属の荷物入れにビニール製の赤ちゃんの人形が
覗いていた。一瞬で打ちのめされた。
夕方からはセントラルに行き、書店FOYLES本店→Charing Cross
→Southbank Centreに行って帰宅。
2022年3月23日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note 
↑グリニッジ公演の南端に戦没碑があった
今日から午前中は学校に行き、午後は散歩することにした。
そもそもロンドンは32地区に別れており、Lewishamはその一つ。
研修先のThe Albanyはロンドン市が行ったコンペに勝って、
劇場が地域を盛り上げるためのフェスティバルを2022年を通じて
行なっている。それが「WE ARE LEWISHAM」だ。
自分としては、一度、区内をくまなく歩いてみたい思った。
月曜の朝シンポジウムで、久しぶりに多くの劇場スタッフに
まとめて会ったが、何人ものスタッフに「アツシはいつも劇場にいる」
と言われた。一通り顔見せは済んで馴染んだようだし、
今度は、この劇場が盛り上げようとしている地区を肌で感じてみたい。
どんな地形で、どんな歴史を持ち、どのような人たちが住んで、
地区の雰囲気がつくられているのか。歩いて把握する。
大通りだけでなく、住宅街にも分け入って、民家や学校を眺める。
家や庭の様子や子どもたちを見れば、そこに住む人が想像できる。
商店にも入って、美味い店も見つけたい。
考えてみれば、KAATでも初めにこんな動きをした。
神奈川県は広いから、車を調達して走りに走った。
イギリスでは車がないがその分狭い。徒歩で十分だ。

↑庭が広い。高級車がたくさん。
Greenwich Westにある語学学校を出て南に進む、
登りを経てBrackheathへ。ここは有名な観光地だが、
行ったことのある中心をわざと避けて、区の境界ギリギリを歩く、
高級住宅地だ。庭は広く、高級車がいたるところにある。
学校の広々としており、いかにもお金持ちの子弟がバスケットボールを
していた。

↑新築のマンション群
高級マンションが次々と新築されている様子で、
公園にはユニークな遊具があった。
さらに南進してLeeを目指すと、もう少し落ち着いた
昔から裕福な人たちが住み続けている雰囲気に切り替わる。
新築エリアには生活感がないが、住み慣れた居住まいの良さを感じだ。
国鉄Lee駅は周辺にだけお店があり、広大な公園と住宅街だった。

↑Lee駅前。「WE ARE LEWISHAM」のフラッグがあった。
この場所が自分にとって重要なのは、
好きな詩人で小説家のErnest Dowson(1867-1900)の出身地
だからだ。唐さんも好きな「酒とバラの日々」という言葉は
彼の詩による。同名の映画が作られたのを唐さんは観て
『二都物語』二幕にこのタイトルをつけた。
自分は20代の頃に岩波文庫から出た短編を読んで気に入り、
翻訳で読めるものは読んだが、土地柄を見て彼の原点を実感した。
彼が生まれる前年に国鉄開通。地方の商人がロンドンで商売を
するために屋敷を構えたこの場所には豊かな邸宅が多い。
けれど、すぐ近くにLewishamというワイルドな一帯を見下ろす。

↑Bwlmont Groveという地域。この丘のあたりでダウスンは生まれた
金持ちしか知らない金持ちと、貧しい人々を知っている金持ちは違う。
ダウスンは後者ゆえにあのような作風になったし、身を持ち崩して
破滅していくやり方を、小さい頃から体感していたのだと思う。
それにしても、何人かのイギリス人にダウスンの話題をふったが、
誰も彼を知らない。ミミも知らいという。
今度セントラルに行ったら、本屋で本を探したい。
小説には英語力が追いつかないが、詩なら辞書を引き引き味わえるかも。
Lee一帯は今日の気候の良さも手伝って、別荘地のような優雅さだった。
そこから北上しLewisamを経て帰ってきた。
途中、ダイアンに頼まれた買い物をしたりして。
合計10マイルちょっと歩いた。
2022年3月22日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note
ロンドンの町で目につくものがいくつかある。
まず、ゴミ箱。やたらたくさんあって、でも道路はゴミだらけ。
一体誰がどうやってあのゴミ袋を一つ一つ取り替えているのか、
よほど早朝の仕事なのだと思う。
あと、床屋。
床屋、美容院、こういったものは本当によく見る。
自分は床屋にすでに一度行ったが、耳のうぶ毛を除くため
お線香の炎のようなもので耳を炙られてびっくりした。
確かにキレイになったが、それにしても熱い。
ネイルサロンもよく見るし、お客が常に入っている。
緑も多い。ここは確かに都会なのだが自然が大切にされている。
住宅街の中によく芝生や花壇を見かけるし、広くて美しい公園が多い。
こういうところでお金をかけずにリラックスして休日を楽しむ方法に
英国の人は長けている。
そしてやはり、教会。
これは、かなり立派なものが数多くある。
一軒一軒見応えのある建築物で、基本的に日中は解放されており、
土曜日には無料のコンサートが行われる。
こういう体験を通してバッハやヘンデルが身近なのだろう。
街中にトイレは少ない(駅にもない!)。教会はお手洗いを
借りられる数少ない場所でもある。
自分のいるAlbanyの近くには、ワイルドな商店街沿いに
小さな教会があり、軒先に十字架にかけられたキリスト像がある。
この像、誠に申し訳ないが少しチープで、とても神々しく見えない。
けれど、劇場の行き帰りに、熱心に祈る人をよく見かける。
夕方など、みじろぎもせず、ほんとうに一心に祈っている。
像がおもちゃみたいだからこそ、この光景はかえって尊く感じる。
この地域が、決して裕福な人たちのためのエリアでないこと、
周囲が雑然としていることが、祈る姿をいっそう峻厳にしている。
ひょっとしたらそれはこちらの思い込みに過ぎず、
「息子の受験をよろしく」「トトカルチョが当たりますように」などと、
私たちが神社でするのと同じようなお願いをしているかも知れない。
貧富の激しいロンドン、多国籍が入り混じるこの地域だからこそ、
お祈りがそんな風に、例えば生存ギリギリのものでなければ良いと思う。
先週末から週明けの動きは下記の通り。
3/18(金)
学校(エリザベス先生最終回)→AlbanyでRomicaと話す
→St Martin Churchで"Dido and Aeneas"を初鑑賞、外はデモの騒音
3/19(土)
写真家・伏見さんとzoom打合せ→洗濯→劇団本読み『鐡假面』
→KAATの同僚たちが仕事で成果を出していて嬉しい
→Dolden Chippyでエビフライ→Albanyで05FEST最終日"Rap Party"
3/20(日)
本読みWS『下谷万年町物語』第7回→掃除→Murchellaが満席
→Dolden ChippyでSkate→AlbanyでJazz Live"Love is Attention"
3/21(月)
午前中、Albanyでフェスティバルのためのシンポジウムに出席。
そのために語学学校を休む。ダイアンの体調が悪そうなので、
午後は帰宅して買い物などする。方々にまとめてメールを送った。
2022年3月18日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note みな楽しく喋っている。ついていけない自分はこのレモネードと対話。
飲み干すとすることが無くなってしまう。時間をかけてチビチビやる。
昨日はアップダウンの激しい一日だった。
まず、日本の地震が心配だった。
その上、KAATの仕事のうち渡英後も継続しているものに問題があった。
相手のあることでもあるから、連絡をしてはウトウトして返信を待つ。
そんな風に前夜から明け方までを過ごした。
いつもなら直接押しかけて解決してきたのに、今回はそうはいかない。
横浜国大の後輩でもアシスタントの小野寺さんが助けてくれた。
大人になった彼女を頼もしく感じた。
そういう滑り出しなので、予定の捌きが後手に回る。
すでに打ち終えた『唐版 俳優修行』の2周目熟読がままならない。
この作業が十全でないと不完全燃焼になり、一日が重く始まる。
学校への道も電話が続くのでやや遅刻気味。
冒頭30分は、先生や級友の話が入ってこない。
頑張ってスイッチをオンにしなければ、まだまだ英語は厳しいのだ。
1時間ほど過ぎたところから、なんとか持ち直した。
放課の間、いつもなら台本に向かうが、この時間も日本との電話。
授業の後半パートは音楽に関するプロジェクト。
失恋した時、元気な時、ホームシックな時、何かに挑戦する時、
さまざまな状況に応じてどんな曲が聴きたいか、というお題なので、
パソコンを出して即席DJをして遊んだ。
唐さん直伝の『悲しき天使』とかシャンソンやカンツォーネを
混ぜたりして。ポール・アンカやヴィソーツキーも紹介した。
ちょっと癒されたところで、良いことがあった。
授業後にエリザベス先生に声をかけられて少し話ができた。
来週から次のクラスへの進級を告げられたのだけれど、
それは大した問題でなく、お互いに人間的な話ができたのだ。
それから劇場に行って、ミミに会えた。
会議もしたけれど、ちょっと疲れているせいもあって、
なかなか話に入っていけない。終わった後に気になったことを
質問したら、自分の理解にトンチンカンな部分があることがわかって
内心落ち込んだ。加えて、目の前のミミはとても忙しい。
親切な彼女はカフェに誘ってくれて、目の前にいるのだけれど、
次から次へとやってくるメールにも対応しなければならず、
時間のかかる自分との会話に縛り付けるわけにもいかない。
流れで、今日はAlbanyで二日連続で同じ芝居を観ることにした。
セントラルに行くにはコンディションが悪すぎるし、
昨日はギャビンと観たこの芝居が自分には難しかったので、
もう一度トライしたら理解がマシになるかも知れないと思ったのだ。
それに、ミミも今日観るつもりだという。
ところが、今度はそこへAlbanyの他のスタッフがやってきて、
ミミも含めた彼らは高速イングリッシュトークへと突入したのだ。
こちらは自分に鞭をくれて残るすべての力を聴力に託したけれど、
典型的な外交人の疎外感を味わった。
自分がいるために皆がやりづらくならないよう、
取り繕うので精一杯だった。この瞬間が今日の最底辺。
それから眠さを殺して観劇をしたら、良いことがあった。
昨日は歯が立たなかったこの目の前の芝居が何を言いたいのか、
完全にわかってしまったのだ。
だいたい、これが日本語だったら、自分には人のやっていることを
理解するに誰にも引けを取らない自信がある。
こちとら難解で鳴らす唐さんの頭の中をずっと解き続けてきたのだ。
芝居に限らず、音楽だろうが美術だろうがダンスだろうが、
相手がどんな風に来ようと、その意思を汲み取らずには済まさない!
少しメモを取りながら観たが、今日のは完全にいけた。
それで、終わった後にミミとかなり話し込んだ。
舞台に仕掛けられた道具や演出の数々、せりふの示すところなど、
メモも頼りに膨大に指摘して、私もそう思う、と言ってもらえた。
性暴力にあった女性のモノローグだったから非常に重かったけれど、
巷のミュージカルとは違った意味で、自分は劇にもっと希望が欲しい、
そして希望とはある種の人間の愚かさではないかと伝えた。
愚かさとは、親しい人が亡くなった時にもお腹が空いてしまうとか、
そういうことだ。愚かであることや無駄なことの素敵さを、
唐さんを通じて自分はずっと考えてきた。
それにミミは、かつて英国公演を観て感激した蜷川さんの
ファンなのだそうだ。それなら、次は中根公夫さんのことも話そうと
約束した。一緒に渡英した自分のハードディスクには、
中根さんと蜷川さん、唐さんと蜷川さんの資料が膨大にあるのだ。
また来週の月曜に会おうと約束して別れた。
朝食は無し、お昼に焼きそばを軽く食べたきりの一日だったので、
帰りにゴールデン・チッピーに寄り、フライドチキンを食べながら
家への道を歩いた。肉を齧りながら坂をのぼると力が湧く。
けれどここはロンドン。元気のない時にフライドチキンが買えない
人も多い。そういう人はどうすればいいのか? そんなことも考えた。
今日はすぐ寝よう。
2022年3月17日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note 
朝起きてブラインドを開けると曇天。しめた!
今夜はAlbanyでイベントのみ。昼間に特筆すべき打合せもない。
ということは、昼間の自由行動が許される。
これが夜に他所の劇場へ行くようなら、
必ず昼にAlbanyを訪ねなければならない。
誰に強要される訳ではないが、そうでなければ新参者の、
言葉の苦手な自分がこの劇場の一員たることはできない。
大学に入った時、唐さんに接する時、KAATに入った時も
自分はそうしてきた。こういうところには室井先生の教えを感じる。
人は自分を見ている。一番大切なものから目を切ってはいけない。
Albanyに夕方遅くに行けば良いし、典型的なロンドンの曇り空。
となれば行くべき場所は一つ。ロンドン塔。
学校では絶対に今日出掛ける場所を言わない。
一緒に行こうよ!などと周囲に言われては台無しだ。
こちらは漱石の小説も日記も読んで盛り上がっているのだ。
必ずやひとりでなければ。
授業を終えるとすぐにカティサークに行き、
初めてテムズ川のボートに乗った。横浜のシーバスより揺れる。
うねうねと上流に進みタワー・ブリッジに接岸。
途中、高級住宅らしき建物をたくさん見た。
ボックスオフィスでMature studentと主張し切符を買う。
ロンドンはメリハリが効いている。あらゆる美術・博物館の
常設をタダにしておいて、ここは約4,000円とる。
中に入ると落胆の連続だった。
当然ながらすっかり観光地化されている。
小学生たちの遠足も元気に行進。さらにやたらと写真撮影を頼まれる。
カップルに、おじさんの二人連れに、言葉が不得意なオレに
頼むなよと思うが、声をかけられるとつい全力で応えてしまう。
さすが高額をとるだけあって場内は清潔。ロンドンでは珍しい。
庭も建物内もトイレも。スタッフにも緊張感があった。
が、展示のショーケースやモニターの数々が邪魔すぎる。
ついラーメン博物館を思い出してしまう。
歩き回っていると小雨が強めの雨に変わって子どもたちが去り、
夕暮れが近づいたので少し雰囲気が出てきた。
正直に言って、夏目漱石の『倫敦塔』は最初と最後だけ面白くて、
塔内の描写は自己陶酔が鼻につく。それにジェーン・グレイの
くだりなど、あまりに絵画のパクリなので興醒めだと思ってきた。
が、実際のロンドン塔に行ってみてその中間部を見直した。
漱石が訪れたのはすでにヴィクトリア朝末期だ。
ここはもうとっくに観光地化されていたはず。
だから、彼は十二分に現実を受け止めながら、
こうであって欲しいという姿を書いたのではないかと思った。
実際を体験して小説の価値が増した。
この小編の最後、漱石は宿屋のおやじに塔の感想を述べて冷や水を
浴びせられ、もう二度とロンドン塔の話をすまいと決心する。
当然、二度と足を運ぶこともない。
一方、自分は一度も行かず小説だけ読んでいれば良かったと思う。
最後はヤケクソで売店のキーホルダーを買ってしまった。
唐さんの『鐵假面』という戯曲が好きだ。だから鉄仮面を見ると弱い。

せめて、倍の値段をとっても良いから、
全消灯のうえ蝋燭でいくナイトツアーを組んでくれないだろうか。
それなら、自分はもう一度たずねてしまうかも知れない。
ところで、最もプロフェッショナルなのはカラスたちだった。
こちらの手の届く範囲に近づいても彼らは一向に物怖じしない。
目の前1メートルのところで糞をするカラスを初めて見た。
これには感心させられた。

2022年3月16日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note 
皆でくつろいで過ごす。どこからともなく演奏と歌が起こる。
自然に合いの手が入る。コンサートには無い滋味がある。
みな凄く達者だ。気分は宮本常一。誘ってくれたアダムさんに感謝。
『唐版 俳優修行』の打ち込みが間もなく終わる。
残すところあと1ページもない。というところで寸止めする
心地よさよ。これが終わったら誤字脱字チェックがてら
もう一度読み込んで、頭を整理するのだ。
学校に行ったところ、敬愛するエリザベス先生は休みだった。
昨日から病気らしい。コロナでなければ良いが。
Albanyへの道すがら、マッシュ&パイの店に寄った。
ミス・ダイアンが、あの店にいくべきだ、
そこでチリ・ヴィネガーをかけるべきだ、と強弁するのだ。
彼女の言うことは必ず聞く。なるほど、紅茶をつけても
£5のランチはリーズナブルだし、店でゆっくりできるのも良い。
食べながら、近くロンドン塔に行こうと決める。
Albanyではセリとロンドンの人件費や物価について話した。
劇場運営に関する予算について訊き、話が派生したのだ。
アツシの好きなパン屋は高い。そう言われた。
で、夜はライブハウス「マッチスティック・パイハウス」へ。
このまえ知り合ったアダムさんに誘われて、フォーク音楽の集い
に参加しのだ。これが実に不思議なイベント。
ロビーに着くと10数人が腰かけているのみ。
アダムさんに喋りかけるとあと10分で始まるという。
実際、8:15pm頃にオーガナイザーの女性が喋って、
男性が歌い始めた。会場はロビーのまま。
これが今夜の趣向なのだそうだ。一人目だけゲストシンガーで、
あとは思い思いに歌うのだとアダムさんに教わった。
信じがたい。しかし、実際に事は起こった。
オーガナイザーが緩やかに仕切ると、
誰かがギターを取り出して歌うのだ。
おじさんたちはみな達者だった。
他にアカペラ男子もいたし、ヴァイオリン弾きの女の子もいた。
二人でハモりながら弾き語る女子は抜群のコンビネーション。
ハモり、即興でギターやリコーダーも加わる。
そこへヴァイオリンまで入ってくる。間が開くと司会の女性が歌うが、
これがまたやたらうまい。アイリッシュが中心の夜。
とりわけ面白かったのが、ずっと酒をチビチビやっているおじさんで、
彼らは歌わない。聴きながら、涙目になっているように見えた。
不思議なことにこのイベント、集まった者は皆知り合いでなく、
最大でも3人連れか4人連れのペアがちらほらあるのみ。
要するに、知り合いでもない人たちが集まって、思い思いに歌う。
楽いそうにはとても若い男の子も寝そべるようにして参加している。
最終的には、大合奏になっていった。重ねて不思議な夜だ。
歌はどれも良かった。郷愁に充ち手いた。
自分はこれがひどく気に入り、次回3/26にも参加することにした。
振られた時のために、一曲くらい仕込んでおく必要がある。
マッチ棒パイハウスの黒板。どうやら定期開催らしい。
他イベントも覗いてみると面白そうだ。セントラルにない魅力がある↓
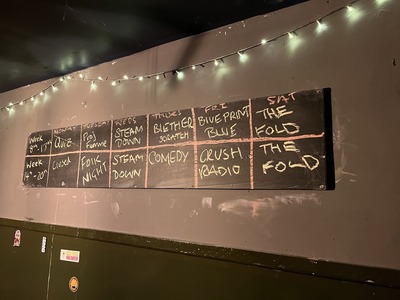
2022年3月15日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note 
↑実物を見た。オフィーリアの衣装は生地がかなり厚めだとわかった。
だから水吸って沈む。しかも清流でなく澱んだ水。絶対飲んじゃダメ。
3月13日、日曜日。この日は早く帰った。
引っ越してから1週間、初日こそ家にいたものの
以降は毎夜出かけてばかりきたが、昨日はAlbanyで行われた
子ども向けプログラムのみだったので20:00前に帰宅したのだ。
すると、話をしましょうとミス・ダイアンから声をかけられた。
彼女はこちらの行動を見てひどく心配してきたらしいのだ。
曰く、初めて会った下見の時からするとアツシはどんどん痩せていく。
ちゃんと食べているのか?と。
食べていますよ、と答えると、
このままではイギリス生活中にあなたは別人になってしまい、
日本に帰って奥さんに驚かれてしまう。それが心配だ、と引かない。
そこで、ここ数年の日本での不摂生について語ることになった。
日本では車で動いている。朝早くから夜遅くまで働いている。
夕食を家で摂るかどうかその日の流れ次第なので、
優しいワイフはちゃんと作っておいてくれる。
例え外食したとしても、そういうわけで、夜中にもう一食たべてきた。
しかも、うちには子どもがいるので、
ついつい息子の好きなお煎餅の良いやつを買ってしまう。
福祉施設への出入りも多いからクッキーも買ってしまう。
アイスクリームやケーキも買ってしまう。
それを子どもよりも自分がたくさん夜中に食べてしまう。
さらに、地元では夜中までやっている美味い店を知り尽くしている。
そもそも、日本は24時間営業の店が山ほどある。
うちの家は徒歩5分以内のところにそういう店が3軒ある。
しかも、渡英前はこれが食べ納めと言ってやりたい放題した。
結果的にかなり動きが鈍くなった。疲れやすい。
走るのが好きだが、忙しくて1日に30分弱しか走れない日も続いた。
その点、今は幸せだ。
時間に余裕があるし、ロンドンの景色が愉しいので1日12キロくらい歩く。
回数こそ減らしているが、食べるとなれば美味いものを食べる。
夜に食べないので調子が良い。店が開いていないので誘惑が少ない。
浮いたお金で劇や音楽や旅行に使うこともできる。
だいたい、自分がもっとも恐れているのは、
近所のスーパーにあるハーゲンダッツのパイント(480円相当)を
買ってしまうことだ。しかも悪いことに、置いてあるのは、
日本では見たことのないチーズケーキ味(一番好き)のパイントなのだ。
あの味を覚えてしまったら、この研修は失敗すると思う。
自分はあればあるだけ食べる人間だ。
アイスクリームのパイントを一回で食べたことも、
ケーキをホールでやってしまったこともある。
実は今日はAlbany近くの気に入りのイタリアンで奮発し、
日曜限定の軽いコースを食べた。スターターで出てきた
仔牛のカルパッチョが脳天をぶち抜かれるほどの旨さで
厨房を覗いてシェフ二人を絶賛し、記念にメニューの紙をもらってきた。
ほら、これがそれです。このデザートがまた美味いんですよ。
と、伝えたら、さすがのミス・ダイアンもI see.と言った。
そして、このエリアNo.1のピザ屋を教えてくれた。
明らかに日本より健康的だと思う。
気に入りのインド料理屋のおかげでベジタリアンぽくもなってきている。
ここ二日間の動きは下記の通り。
3/13(日)唐ゼミ☆WS→部屋の掃除→Deptford Lounge→Albany
3/14(月)学校→Albany→テイト・ブリテン→バービカンセンター
↓記念にもらったメニュー。毎週内容が変わるのでプレゼントしてくれた。
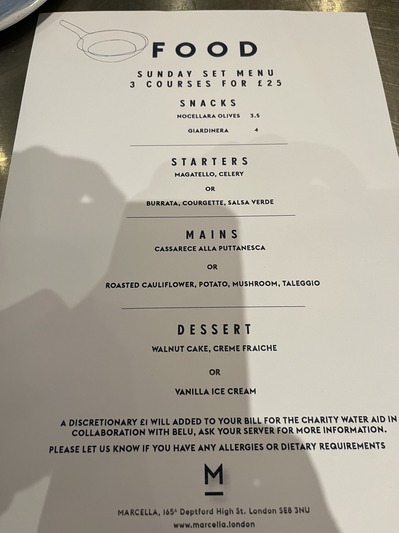
2022年3月11日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑カーテンコールから。一日の終わりにめった打ちにされてトボトボ帰宅。
今日は調子が良かったのである。
新居に越して間も無く1週間が過ぎる。
一日のルーティンも定まってきた。
ミス・ダイアンの主導によって生活の中にコーヒーやティータイムが
自然に入り、日常はやや優雅になった。
就寝は早まる。彼女が寝たら自分も寝よう。
体力はより回復するだろうから、欲張りたい作業は明日の早朝に見送る。
そういう諦めも自然とつくし、結果的には身体に良いはずだ。
朝、学校に行くと、不思議と会話が入ってくる。
エリザベス先生の言うことも、課してくる課題もよくわかる。
英語に慣れてきたのだなと思った。いいぞ。いいぞ。オレ。
午後はオンラインミーティングが日本あった。
Albanyの周囲でコロナがくすぶっているらしく、
本当はLewishamの新拠点に集結して対面の会議をするはずだったのを、
急遽Zoomに切り替えたのだ。劇場では催しがひっきりなしだ。
これらを生かすために、少しでもリスクを刈り取らなければならない。
コロナに対するロンドン全体の雰囲気は極めて緩いが、
ミミの連絡から切迫感が伝わってきた。
そして、このミーティングが楽しいのである。
明らかに先月や先週よりもわかるようになっている。
今、資金調達の話をしている。今、先々のスケジュールを組んでいる。
最後に振られた時も、テキパキと質問や確認ができるようになった。
聴くことが大幅に楽になり、喋りはややマシになってきた。
それでも、みんながダーッとまくしたててくると
頭が彼らの喋りをブロックしてフリーズに向かい、やたらあくびが出る。
わかりやすく負荷がかかっているのがわかる。
そういう時はモニターをオフにしてゴロゴロしながら聴く。
治ったら画面をオン。そうすると何とかついていけるのだ。
会議後のみんなにも励まされ、やれそうだな、などと悦に入った。
が、今日の夜にAlbanyで観た催し。これは相手が悪すぎたのである。
今回のフェスティバルに合わせて書き下ろされた新作戯曲の
サンプル・リーディング公演だ。これには参った。
7人の男女が出てきて、台本を手にしゃべる。
かなり緊密に演出・稽古されていて、道具立てこそ少ないものの、
今回自体を作品として見せよう、という意志を感じる。
完成度は明らかに高い。
しかし、内容は心底よくわからなかった。
考えてみれば、学校も会議も、文脈があるのである。
先週がこうだったから、昨日がこうだったから、そういう前段がある。
ところが、新作戯曲のリーディング公演は街場の殴り合いみたいなもんで
どう言う世界か設定を理解することが極めて難しい。
開演前、たまたま隣に座ったジャーナリストの女性と楽しく談笑した
までは良かったが(彼女もBush Theatreに入ったばかりだった)、
始まってすぐ迷子になり、90分間眠くて仕方なかった。
よくよく考えてみれば、午前や午後の予定は英語力でなく
洞察力と慣れて凌いでしまっている疑いがある。
もう今日は挫折とともに寝る。ああ、古典劇とかやっていないだろうか。
2022年3月10日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑すれ違ってアッと思った。中央の後ろ姿。その道の達人の雰囲気がある。
居候を初めて数日、ミス・ダイアンの威力は絶大だ。
まず、彼女は私に英語で喋りかけてくる。
当然といえば当然だが、これがためになる。
出かける時はどう言うか、帰宅時にはどう言うか、
スラングも含めて生活に密着した生きた英語を教えてくれる。
それに買い物や交通手段を指南をしてくれる。
あのドラッグストアに行くべし、同じ店でもこう買うべし、
ここからここは電車でなくバスを使うべし。
などとアドバイスをくれるから、少しずつ経費の節約になる。
朝にコーヒーを飲むかと訊かれ、YESと答えると上機嫌になることも
わかった。飲食は別々が原則だが、こちらがあまり食べないのを
心配している。単に日本で一日四食くらい食べまくってきたので、
ちょっとスリムにして動きにキレを出したいと思っているのだが、
心配らしい。だから、今日はカレーをたくさん食べました、
などと報告する。
そんな彼女のアドバイスの一つに、
劇場に行ったら常に「Mature Student」と言うべし、というのがある。
ロンドンは学生に手厚い。自分はAlbanyでの研修生でもあるが、
語学学校の生徒でもある。だから純然たる学生扱いで、
特に劇を見に行く時などに学割を受けられるのだ。
なるほど、先日行ったBush Theatreは5ポンド引きになったし、
今日行ったナショナル・ギャラリーでも、図録が値引きされた。
今日は〇〇を観てきます、帰りは〇〇時頃、と出がけに伝えると
「Don't forget "Mature Student" !」と念押しを忘れない。
ユーモアのある人でもある。
あと、非常に実践的な知恵もくれる。
これは臆してまだ実行できていないのだが、コンサートに行った際、
会場がガラガラであれば、より良い席に移ってしまえば良い。
と言われた。それで怒られないのがロンドンスタイルであるし、
良い席が埋まっていた方がプレイヤーも喜ぶ、と言う。
昨日、いつものサウス・バンク・センターに行った時、
注意して見ていたら、なるほど、その道の達人がいた。
演奏開始間際、指揮者が登壇する頃になり、
あるおじさんがそのタイミングでサッと位置を変えたのだ。
それまではフワフワ動いていたが、一瞬で機敏になるその動きは、
往年のサッカー選手・ロナウドを彷彿とさせた。
実は今、これを書いているのはバービカン・センターなのだが、
そのおじさんが近くにいる!
自分と同じように、毎日、劇場通いしているのだ!!
今日も彼の動きから目が離せない。
これから注意して彼を追いかけよう。
オレンジのビニール袋を持っている長身の男性。よく目立つのだ。
↓おじさんだけだと味気ないので、ナショナル・ギャラリーで
気に入った絵画も添える。楽しそうだ。
2022年3月 9日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑冬枯れで寂しげだけど、オフィスから見えるAlbanyの中庭はのどか。
土地柄を考えたら、ここには"ホッとできる場所"という意味合いもある。
『唐版 俳優修行』が愉しい。
初演は1977年の秋。同じ年の春にあの小林薫さんが大活躍した
『蛇姫様 わが心の奈蛇』が上演された後に書かれた作品だ。
唐さんによれば、あのロマンはどこへいったと、お客や批評家に
嘆かれたらしい。
けれど、今の自分にはこの悩みの薄さ、軽快さが愉しい。
まだまだ序盤だけれど、コントのような小気味の良さは、
自分が愛してやまない『恋と蒲団』に通じる。
二作品が書かれた時期は近い。それに同じ単行本に収録されている。
読んでいると明るい気持ちになる。3月は首っぴきで取り組もう。
語学学校に特筆すべきことなし。
トルコとサウジアラビアの連合軍団がうるさくて、先生が困っている。
先生は別の生徒に質問を振っているのに、彼らは横からすぐに答えて
しまうのだ。さすが10人を超える兄弟がいる家庭で育った彼らは闘いを
心得ている。より声の大きい方が勝つのだ。面白い。
美味いものが好きな日本人青年のS君をいつもの
インド料理屋 Hullabaloo に案内して二人でガッツいていたら、
長身の黒人男性が店に入ってきた。目はまどろみ、ズボンのウエスト部分
も危うげで、誰彼かまわず絡んではカウンターにもたれかかり、
「お茶をくれよ」と言っている。明らかにドラッグだ。
店の人は慣れた手つきで紙コップのお茶を外のテーブルに置き、
彼を店外に連れ出した。大家のダイアンさんは、DeptfordとLewishamには
気をつけろと言う。そう言われても毎日通うAlbanyだから避けようが
ないし、最近は慣れきってしまって当初の警戒が和らいでいたことに
気がついた。ここは危険なまちなのだ。
今日もロミカは来ない。メールにも返信なし。仕方ない。
セリに少し話を聞いてもらって、セントラルに繰り出すことにする。
我慢と粘りが肝心。焦りは禁物だ。
2022年3月 9日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note 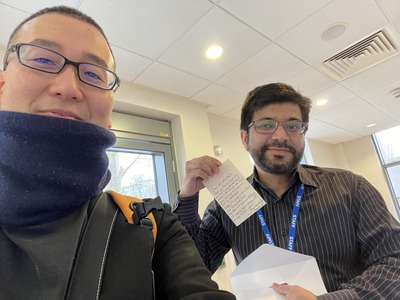
↑いろいろ面倒を見てくれたホテルスタッフのサキブさん
先週末から週明けにかけての記録を。
4(金)
イギリスの人々の週末にかける意気込みは強い。
語学学校のエリザベス先生も、今日は金曜日だと嬉しそうだ。
と同時に、クラスメイトの中には遅刻が目立つ。
初めて文法のテストで一番になることができた。
これまで周りに遅れをとってきた分、嬉しい。
この日のalbanyにはミミやセリ、エマがいない。
そこで引っ越し準備に注力するため、午後をホテルで過ごす。
物を増やさないようにしてきたが、書類や石鹸類、
買ってしまったCDなどが確実に増加している。
到着時、すでにトランクがパンパンだったので、
スーパーの買い物袋を足して対処する。
困ったのはお金の用意。大家さんに敷金と初月の家賃を現金で
渡さなければならないが、ATMで四苦八苦する。
ここにきて、近所のスーパー前にあるものでは一度に£200までしか
おろせないことが判明。後ろに人を待たせながらの繰り返し作業に
怖気付き、一回やったら次の人、その人が終わるのを待ってまた自分、
を繰り返す。が、いよいよフィニッシュと思ったら、デビットカードの
1日上限に道を阻まれた。仕方ない。
残りは明朝おろそうと先送りにして、荷造りを終える。
長い逗留だったし、初めてのUK滞在場所につき思い入れがある。
ホテルスタッフにお礼状を書いた。カードキーと一緒に封筒に入れる。
夜はアンドラーシュ・シフのハイドン・フェスティバルに向かう。
初日を聴いてもう一度行きたいと思った。当日券でステージ近くの席を買う。
フォルテピアノの音は繊細だ。聴き逃してはならないと奮発したが、
響きと演奏に陶然として悔いなし。
帰り道、オフィスビルの路地裏を通ったら、閑散とした通りに
四人の男が毛布にくるまって車座になり、サイコロを振っていた。
英国式チンチロリンだ! 彼らから10メートルほど離れたところには
明らかな人糞があり、「ペストのロンドン」という言葉を思い出した。
5(土)
引っ越しの朝。早朝に日本とzoomを行った。
ずっと唐ゼミ☆の写真を撮り続けてくださっている伏見行介さんとだ。
これまで、あまりお話もせずに10年以上も撮影してくださっているが、
初めて話し込んだ。日本に帰ったら、伏見さんに会いたい。
それからfacebookを更新し、引っ越しの仕上げにかかる。
トラブルが二つ。まず、一日経ってもお金がおろせない。
次に、出発時にお礼状を置こうとしたらサキブさんに声をかけられ、
お別れがセレモニー化してしまう。彼はチェックアウト客の捌きも
あるから、少し話しては接客に戻る、を何度も繰り返さざるを得ない。
ありがたいのだが、大家さんに10:00に行くと約束しているので、
ちょっと焦れてしまった。でも、やっぱり別れを惜しんで記念撮影。
スニーカーの袋を括り付けたトランクをゴロゴロやりながら
新居のある丘の上を目指す。息せききって辿り着くと、
これからお世話になるミス・ダイアンが温かく迎えてくれた。
まずは、部屋に荷物を運び込み、それからお金について
お詫びと説明をして、残りを待ってもらえることになった。
それから、カギの開け閉めや部屋の窓の開け方や収納の仕方を教わる。
共同生活のスタートを良好に切るためにも、この日は他に予定なし。
バスタオル、追加で必要なハンガー、昨晩壊れた傘の替え.....。
そんなものを買うために出かけようとしたところ、
どこに行けば安いか、どのように移動するべきか、丁寧に教えてくれる。
行き先は、何度か行ったことのあるLewishamショッピング・センター。
あそこは治安が悪いので気をつけるよう、何度も釘を刺される
母親のようだ。
のどかな丘を下って行くと、20分で目的地に着いた。
それから英国で、初めて生活感のある買い物をした。
何軒も店を回りバスタオルの価格を比べた。
£20の店もあれば、£5のところもある。もちろん自分は底値のを買う。
触れたところ品質に問題ないし、自分は年末までの期間限定だ。
水なども買って家に戻ると、ダイアンさんはご自身の買い物に
出かけている。そこで、Canary Wharfへ。
いつも乗り換えにだけ使ってきたが、ここにはスーパー付属のものより
精度の高そうなATMがあり、案の定、無事に引き出すことができた。
初めて Canary Wharf の商用施設も渡り歩き、
どんなお店が入っているかを確認した。ここにも一風堂がある。
6:00pm頃に家に戻って荷を解いているとダイアンさんも帰ってきた。
シャワーの使い方も聞いたが、使用後は水を拭き取ってねと言われ、
Yesと答えながら内心おどろいた。そんなことができるのか。
これはやってみると、そんなに難しくなかった。
英国は乾燥していて洗濯物などすぐ乾くが、ここのバスルームは換気が弱い。
ダイアンさんの入浴後も、なるほど、キレイに拭き取られている。
これを食べるしと様々なものを供される。
それでいて寝る前には、飲食は自分でね、と念を押される。
6(日)
翌朝起きしな、コーヒーどう?と言われて笑ってしまった。
原則があり、グレーゾーンがある。これが共同生活だ。
聞けば、これまでダイアンさんは何人もの日本人女子を受け入れて
きたらしく、最長の人は8年もいたらしい。向こうの方がプロだから
こちらは従って行けば良い。それに、下手に友だち世代とシェアを
するより、向こうにイニシアチブがあってそれに合わせていく方が、
曖昧さが無くて楽だ。ここの掃除はどっちなの? という状態で
不衛生になっていくより、規律があった方が健康に良い。
今年は体調を崩せない。
こちらの時間で9-11時まで唐ゼミ☆WSをして、
自分の声がデカすぎないか訊いたら、ダイアンさんは笑って
OKと言ってくれた。
昼過ぎに、ぜひ行くよう勧められたブラックヒースに散歩して
昼食のパンを買った。いつもグリニッジのGAIL'sという店で
買ってきたが、同地にも店舗があるらしい。
歩いて15ちょっとのブラックヒースに向かうと、
丘を下ったところに大きな教会があり、さらにその下に商店街が広がる。
自然が多く、コンパクトにお店が集まるのが魅力的な村だ。人が多い。
頼まれたダイアンさん用の水も買い込み、少し教会に寄って家に戻る。
今度は洗濯の仕方を教わった。洗濯は週に一度だそうで、
とりあえず土曜日を選択した。汗をたくさんかく夏は大丈夫か?
洗い終わりを待ちながら、さらに買い物へ。
共有物として、食器洗い洗剤、トイレットペーパー、
キッチンペーパーを月に一回収めなければならない。
また、今回は使わせてもらったが、洗濯用石鹸も別々。
そこで、これらが安く手に入るお店とグリニッジ駅への近道を
教わり、今度は今までとは別のルート、階段を使って丘をくだる。
以前は前を通り過ぎながらも決して入らなかった店がオススメの買い物先。
こうして、徐々に自分も地元の仲間入りする。
品物を揃えてレジの青年のところに持っていくと
Do you live in Dian's house?と訊かれてビビる。
Why do you know that? と訊き返すと、
歴代の住人が皆同じものを買いにくるから、と笑っていた。
あの小さな女の子はどうした?とも訊かれたけれど、
1週間前に入れ替わりで引っ越した彼女を自分は知らない、と答えた。
家に戻ってダイアンさんに報告すると、笑いながら
店員の彼は前に住んでいた女の子のことが好きだったのよ、
と教えてくれた。これまでのホテル暮らしに比べて
人間関係の入り組んでいることよ。
5:00pmに家を出て、Deptfordへ向かう。
インド料理Hullabalooで食事を摂り、その後Albanyのカフェで事務。
そして、7:00pm開場のライブを観るのだ。
7:30pm頃からお客の集まりが本格化すると、
着席で150キャパのAlbanyに倍以上押し寄せている。
今夜はオールスタンディングゆえにそれが可能なのだ。が、凄い数だ。
バーも激混みだが、リヴやケイトが生き生きとお客を捌いている。
7:45pmからDJのあおりが始まり、8:00pmからライブ本編。
3人の歌手が場を盛り上げたが、自分にはイマイチだった。
ヘイワードさんやMatchstick Piehouse でのライブの方が
断然すごかった。今日の3人は有名人なのだろうか。終演11:00pm。
遅いので急ぎ足に帰宅したが、あらかじめ帰り時間を伝えてあった
ダイアンさんはにこやか。シャワーを浴びて拭き掃除し、就寝。
↓自分の部屋。ここで色んなことがあるだろう。

7(日)
次なる研究対象を『唐版 俳優修行』と定め、台本づくりと読みに入る。
シェイクスピアの国にいるから、というのが選定の根拠。
かつてMORDの松本修さんが演出した舞台を思い出す。
その後、新居から初めての出勤。
目と鼻の先にSt Ursula's Covent School(聖ウルスラ学園?)という
女子校があり続々と生徒が登校してきていたが、校門が開いていない。
生徒たちが開門を待つ。日本とは違う景色だ。
語学学校にはヨルダンとフランスから新たなクラスメイトが加わった。
ロンドンで発見した自分のオススメスポットについて話し合う。
先生や他の生徒の話が、以前より聞き取りやすくなった気がする。
Golden Chippyで特大Skateを食べ、Albanyに移動。
先週の会議の議事録を送ってくれたロミカにいろいろ質問したいが、
いないようだ。シフト表では出勤になっているが、オフィスに荷物を
置いて何処かに行っているようだ。また明日チャンスを探ろう。
夜はBush Theatreへ。
少し遠いところにある劇場だが、演目が気になった。
フットサルと会話劇を融合させた作品だった。
16歳を演じた3人の黒人青年が優れている。
お客は半分も入っていなくて100人に満たなかったけど、
彼らの達者さといかにも青春の残酷と甘さを描いたストーリーに
終演の瞬間から総立ちで拍手していた。一体になってグータッチもする。
コロナはどこへいったのだろう。
↓村はずれの教会。日曜朝の礼拝の後で、中は良い香りがした。

2022年3月 4日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑ロゴをプロジェクションしたり、演奏中はちょっとしたライティングも
このへんはポップな感覚だ
今朝の語学学校で、例のお金持ちの青年と話した。
彼は高校での成績は常に一番、ハーバードの医学部に入ることが
すでに決まっているそう。どういうシステムなのかよく分からないが、
「オレはジーニアスだ」と言う。
「アツシはいつまで学校にいて、どうやって英国に来たのか?」
と訊かれたので国の派遣だと答えると「アツシもジーニアスだな」と。
彼はイギリスが好きになれないそうだ。
多くの人と話したいがどうもそういう風に接してくれない。
アメリカは違うだろう、と希望に思っているとも言う。
考えてみれば、学校にいる20歳前後の青年たちは皆
同じような気持ちでいる気がする。
他国で不安だし、時間があるもから連れだってはいるが、
入れ替わり立ち替わりだし目的も様々で、関係が深まるのが難しい。
今の自分には孤独でいられることがありがたいが、
それは一度多くの人間関係に揉まれる毎日を生きたからで、
彼らにとっては辛そうだ。皆の内面が少し見えた。
午後はzoomミーティング。オンラインとはいえ、ついにエマとも会えた。
実は昨日、唐突に送られてたショートメールに「ワッツアップやろう!」
というメッセージがあって、「エマ? エマですか?」と質問したら
それには答えず。今度会いましょうとだけ返ってきた。
怪しい!と思って警戒していたのだが、やっぱりエマからだったらしい。
ミミが私の電話番号を伝えてくれて、エマもメッセージをくれたというのが
経緯だったらしい。何かの営業かと恐れていたと伝えたら、皆に笑われた。
「This in Emma.」とひとこと言ってくれても良いのに。
肝心のミーティングだが、
先月に立ち上がり、年末に向けて進めている企画のあらましや
進行を知ることができた。さまざまな事情で上手く修学できない青年たちと
作品をつくるのがミッション。すでに彼らについてのリサーチを終えて、
適切なアーティストを選考する段階に入っている。
というような話が、ネイティブな英語で矢継ぎ早に繰り出される。
毎度のことながらヘトヘトになるが、末尾にベトナム・コミュニティへの
アプローチという項目があって自分を元気にさせた。
ベトナムなら行ったこともあるし、大和市のタンハーに入り浸ってもきた。
ベトナム・コーヒーをみんなで飲みたいぜ!という感想を述べたら、
またみなに笑われた。ラクなポジションでいさせてくれている。
夜はバービカン・センターへ。
開館40周年を記念してレジデント・オケのロンドン交響楽団が
ハイドンの『天地創造』を演奏するのを聴きに行ったのだ。
やっと着いたら、ロビーのそこここを駆使して演奏隊が爆音で
演奏をして、華やかな周年事業を思わせる趣き。子どもたちも混じって
演奏している。今晩は合唱こそ多いものの、ハイドンは小編成なので
降り番の一流奏者たちを一瞬とはいえ間近に見られて良かった。
この楽曲は3部から成り、下記の構成
第1部 混沌から世界ができるまで
第2部 世界に生命が生まれ生息する(鷲とか鯨とかから)
第3部 人間の誕生(アダムとイヴ)
ヘンデルの『メサイア』の向こうを張って、ハイドンは旧約聖書で
いこうと思ったのだろうか。3部はミルトンの『失楽園』から。
実際に聴いてみて、アダムとイヴも幸せいっぱいだし、
すごくポジティブな内容で楽想のオンパレードだと再認識した。
ロンドン響はもちろん達者で、超一流オケに特有の音の厚みと
弱音スタートでも全くブレぬ安定感と、アンサンブルの良さが凄い。
前に聴いたベルリン・フィルと同じように、ロールスロイスのような
高級車が静かにスーッと入ってくる感じだ。当然、合唱も上手い。
(指揮者より客席側にいた合掌の人々はどうやって指揮を見れたのか?)
と言っても、肝心の指揮者サイモン・ラトルは最近に受けた小さな
手術の回復に時間がかかっているということでキャンセル。
普通だったらメモリアルで勝負どころの演奏会だと思うが、
ベルリン・フィルをキャリアのゴールにせずにロンドン響の音楽監督に就任、
ホールの建て替えが進まぬとみるやそのロンドンも蹴ってバイエルンへ、
サーの称号を得ているにも関わらずドイツ国籍になっちゃった、
というラトルの凄みを痛感する。
演奏は、曲のせいだとも思うけれどかなり牧歌的で笑ってしまった。
「クリエイション!」だもの。日本語訳である「天地創造」という重みが
どうしてもねえ。この世界が生まれるにしてはライトだし、
今の世界を描写するにはあまりに楽天的だ。ラトルだったら、
もっと辛辣でエキセントリックなところもある演奏になったのだろうか。
ところで、今日は夜の演奏会の行き帰りにかなり消耗した。
というのも、私にとって都心に出るための要であるバンク駅が工事で
閉鎖されているために、ものすごい回り道を余儀なくされたのだ。
(横浜市民にとって渋谷を断たれるようなもの)
日本では夜中の工事を積み上げたりして、
こんなことはまず考えられないが、ロンドンは平気らしい。
しかも、私の使っているGoogleナビはそれをまったく感知せず、
「バンク駅まで〇〇分!」と元気が良い。余裕を追って出たはずの往路は
おかげでかなりせわしないものになり、消耗した。
ただし怪我の功名で、道すがら初めてロンドン塔を眺めることができた。
『リチャード三世』と夏目漱石の、あの恐るべきロンドン塔!
2022年3月 3日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑アダムさん
昨晩は面白いことがあった。夜にイベントがあったのだ。
今年オールバニーが中心となって進めているフェスティバルのイベントの
一つなのだが、会場はいつものAlbanyやCanada Water Theatreではない。
どうやら、近隣のライブハウスで行われるらしい。
チケットは売り切れのようだが、ミミがねじ込んでくれた。
それで夜に現地に向かったのだ。サイトには7:00pmスタートとある。
時間に余裕を持って出かけたがかなり迷ってしまった。
住所を打ち込んだナビは、着いてみればマンションの一室を示すのみ。
小雨のなかをウロウロして、やっと国鉄の高架下にある
Matchstick Piehouseを発見できた。
すでに7:20pm
お世辞にも入りやすいとは言えぬ扉の前に立つと中から音楽が聴こえる。
もう始まっているのかと思いきや、中に入るとまだ閑散としていた。
出た!ロンドンのライブ特有の、この開演時間のあいまいさ。
待ち合いに受付らしきものはなくバーのカウンターがあるのみなので、
飲み物を買う列に並んで、質問してみた。
アルバニーのミミに予約してもらったアツシである。
チケットはどこで手に入るのか?
すると、スタッフの中でひときわイカつい男性がこう言うのだ。
「ニホンカラデスカ?」
聞けば、彼はアダムさんと言って、
このパンデミックの2年間に独学で日本語を学んできたそうなのだ。
あと30分くらいでライブが始まる(結局8:15pmスタートだった!)ので
待つと良いと言って、コーラを注文したらプレゼントしてくれた。
さらに彼としゃべったら、15日(火)に面白いイベントがあるという。
聞けば滋賀県から来た日本人もプレイヤーの一人なのだそうだ。
自分のカレンダーを見れば、この日はバービカンでチェコ・フィルの
予約をしているけれど、即決で、行く!とアダムさんに伝えた。
すでに買ってしまった2,500円のチケットはもったいないけど、
人との出会いには断然変えがたい。
それに、語学学校に来ている若者にクラシックにチケットを
プレゼントしたら、彼らにとって良い経験になるかも知れない。
そう思ってこれを書きながら待っていたら、始まった。
内容は凄かった。ここルイシャム地区の多文化主義が生んだ
ミュージシャンたちのレベルの高さに唸る。
彼らはこともなげに役割を変える。しかも一曲の間に。
ボーカルがサックスを弾き始めたと思ったら、ジャンベを叩いていた
プレイヤーが歌い始める。コントラバスの女性がハモり始める。
ロックと聞いてきたが、フォークやカントリーが明らかに混ざっている。
即興もある。始まって3時間を過ぎたが、まだ終わらない・・・
2022年3月 2日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑このアイス販売マシンはかなり神出鬼没である。
さすがにひと月経つと落ち着いてくる。
学校→Albany→観劇、といつもの動き。食事に行ったカレー屋も3回目。
そこで、最近はなんとも思わなくなったロンドンへの違和感について
まとめてみたい。
【全体的に】
・道にゴミ捨てすぎ
・それでいてゴミ箱の数多すぎ
・Are you fine? Are you OK?と訊いてきすぎ
・地上1階を0階と数えすぎ
・生まれた瞬間から1歳と数えすぎ
・小雨多すぎ
・買った時点で傘ボロすぎ
・風が強すぎ
・建物、ムダに意匠こらしすぎ
・ホームセンターに置きもの充実しすぎ
【スーパーにて】
・入口に警備員が立ちすぎ
・生鮮食品がワイルドで不気味すぎ
・菓子パン雑に積み上げすぎ
・冷凍食品多すぎ
・ゆっくりレジ打ちすぎ
・店員、閉店作業を早めに始めすぎ
・野ざらしのATM多すぎ
・ATM付近に物乞い多すぎ
・買った時点で爪きり切れなさすぎ
【音楽会に行くと】
・事前にロビーで飲み食いしすぎ
・客席に開演間際に殺到しすぎ
・客が鎮まるの待たずに演奏に入りすぎ
・楽章間で拍手しすぎ
・余韻なく拍手しすぎ
・休憩時間にアイスクリーム食べすぎ
・トイレの小便器の位置が高すぎ
・演奏がちょっと良いだけで盛り上がりすぎ
・終演後のサイン会無さすぎ
【移動時の電車の中】
・電気が点滅しすぎ
・電車のレーンと時間テキトーすぎ
・身体デカいのに天井低すぎ
・電車の中で愛し合いすぎ
・動画の音デカすぎ
・電話の声さらにデカすぎ
・鼻歌、大声でうたいすぎ
・犬と自転車を持ち込みすぎ
【PUBなど飲食店で】
・寒いのにテラスでビール飲み過ぎ
・酒のアテ無しで飲みすぎ
・寒いのに半袖とノースリーブ多すぎ
・フライドポテトの量多すぎ
・水とサービス料の会計システム分かりにくすぎ
・・・と、これらに慣れて現在に至ります。
2022年2月28日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note
↑帰りに気づいたのだが、劇場の壁面の絵柄が変わっている。
明日、質問しなければ。
渡英以来、すでにひと月経ってしまった。
日々あちこちを歩き回っているが、本当にあっという間だ。
2/25(金)
朝は語学学校に行かず、zoomでバッカーズの会議に出席する。
VACCURS=電撃障害者商品企画会議。
これは月に一度行われている寄り合いで、可能であれば必ず参加している。
会の幹事の方が施設運営についての変革時期だと伺った。
ご本人はかなりしんどそうで心配だが、身につまされる。
いつも参加している別の人も、それに呼応して自分語りを始めた。
一人ひとりに背負っているものがあって、励まされた。
学校は出席率8割をキープすれば良い。月一の会議には今後も必ず参加する。
午後はAlbanyの近くのイタリアンでギャビンと食事しながら話した。
彼は忙しい時間を縫って来てくれている。他の2施設に行ったことや
子ども向けのプログラムに関心を持っていることを伝えた。
素晴らしかった『Underwater』の演出家さんから、
来月末にマンチェスターでキッズ向け公演のフェスティバルがあると
聞いたと伝えたら、把握していないなあ、と言われる。
ひょっとしたら自分が言葉を聞き間違えたのかも。
帰って調べ直さねば。
夜はセントラルに行く。
ピカデリーサーカス近くの文房具屋でペンを買ったり
ウィグモアホールのボックスオフィスで4-7月のチケットを購入。
時間に余裕があったので前から見たかったウェストミンスター寺院まで
歩いたところ、デモに遭遇。彼らの歌声と、ウクライナ・カラーを
手に手に四方八方から続々と集結する人々。
クロムウェルの像も印象に残った。
生前は英雄だったクロムウェルは、王政復古とともに墓を暴かれ、
遺体の首を刎ねられた末、四半世紀に及び骸をさらされた。
そして、今は銅像が建っている。
複雑な気持ちになったので、帰りにゴールデン・チッピーに寄り、
スケイクという魚を食べた。ここのおじさんは痛快だ。
お前はもっと食べるだろうと言って、A few chips!と店員に大声で
指示を出す。これがa few!?という量が盛られてくる。
人間の地力に打たれる。
2/26(土)
朝からFacebookを投稿。週末恒例の作業だ。
他にも、原稿を書いたり、『秘密の花園』の初演台本と睨めっこ
しているうちに時間が過ぎる。
3:00pm頃になって出かけ、バンク駅から歩いてバービカンに行き、
そこからさらに歩いてウィグモアホールに行った。
途中、喫茶店でチョコレートケーキを食べた。
海外旅行のお土産にもらうチョコの味だ。キャラメルや他の甘味が
入り混じっていて、甘過ぎる。
ヘンデルの合奏協奏曲やカンタータ、スカルラッティ父の歌曲を聴く。
こんなプログラムは日本では滅多に聴けない。
専らCDで聴いていたけれど、指揮者が立ったままチェンバロ片手に
弾き振りするのを初めて体感。こうなっていたのだ!
バロックなので、もとは王侯貴族の音楽だ。
美しいし楽しい。雅やかさに浮世がどうでも良くなる快感があるが、
何か後ろめたい。昨日のデモとクロムウェルが頭をよぎる。
帰りはすべて電車にせずに、歩きを混ぜながら帰った。
週末だから大勢の人が出ている。寒いのに露出度が高い。
大道芸に合わせて合唱している酔っぱらいの若者チームなど、
ノースリーブのワンピースだ。彼らは寒さを感じないのか?
2/27(日)
朝から唐ゼミ☆ワークショップ。
『下谷万年町物語』第2幕に入る。
第2幕こそ、大勢のオカマが長屋のセットにはびこって、
これぞ万年町!という光景が現れる。
その一角で、主人公3人がサフラン座創立のための作戦を練る。
1日に進む分量を抑えてやっているので、たくさん修正をして
稽古っぽい稽古。こちらも腕がなまらないように。
飛び入りで博物館に行こうと思ったが、無料だけれど予約が必要で
どこも埋まっている。メジャーなミュージカルも検討したが、
週末は値段が高い。そこで腹をくくり、完全デスクワークの日にした。
おかげで『秘密の花園』の初演版と改訂版のどこがどう違うのか、
最後まで、そして細部まで把握することができた。
夕方に食事に出かけて散歩もした。
前々から、テムズ川を徒歩で渡る方法はないものか疑問に思ってきたが、
よく見ればカティサーク号のわきに地下道に通じる階段がある。
大きな川を下から渡るだけあり、螺旋階段を長く降りる。
そして階下のトンネルは意外に狭い。
船の横の出入り口、トンネル、向こう岸...まるでドラクエ。
2/28(月)
先週の木曜日以来、三日ぶりの学校。
旅行について話したが、隣の中国人女性がバックパックで30カ国も
巡った経験があり驚いた。他の皆も国際経験豊かだ。
自分は数カ国。旅行で行った国は一つもない。
仕事で行ったベトナムのホーチミン市でけっこう高級なホテルに
泊まったけれど、早朝のジョギングを終えて朝一番でマッサージに行ったら、
女性の整体師にゴリゴリやってもらっている途中、いきなり小声で
「Special service?」と囁かれてビビった話をしたら盛り上がった。
その後、バスでルイシャム駅に行く。
渡英時にヒースロー空港で買ったSIMカードをひと月更新するためだ。
あの時、ボーッとした頭でテキトーに「3」という会社を選んだ。
後に「O2」か「Vodafone」の方が優れていると知ったけど、
今ではこの電話番号に愛着もあるし、ふた月目からは同じ条件で
3,000円程度になる。だから更新しに行ったのだ。
お金は先週に問い合わせに来た時に払ってあり、
店員さんが操作してくれて「これで良いですよ、また来月」と言われ
安心してAlbanyに向かった。しかし、道すがら全然ネットに繋がらない。
もうナビ無しでも迷わないが、到着時間を知りたくても無反応。
劇場に着いて久々に再会したミミが色々と試してくれたけど、
どうしようもない。お店に電話しても、混んでいると繋がらない。
だんだん腹が立ってきて、いっそVodafoneに乗り換えることにした。
Vodafoneならば、週末に引っ越す家の最寄り駅カティサークの前にある。
行ってみたらさほど高くなかったし、むしろ条件が良い。
「3」に払った分を無駄にしても今後の利便性を考えてこちらの方が
良いと思った。新たなSIMカード=電話番号がやってきて、
ネットも絶好調になった。大学2年時、懐かしきJ-PHONEから始まった
自分のケータイ遍歴はVodafoneを経てSoftbankに至った。
久々のVodafoneだ。
順番が前後してしまったが、もちろん今日の最重要トピックはミミとの
邂逅で、前回会った時に疲れ果てていたミミはすっかり元気になっていた。
ここぞとばかりに、今後プロジェクトに同行するためのスケジュールを
ガンガン組み、エマとも会えるように手配してもらった。
聞けば、エマは二つの職場を掛け持ちしていて、週に二日をAlbanyに割き、
しかも殆ど在宅勤務のプロデューサーなのだ。道理で会えないわけだ。
家は近くらしく、こっちから近所のカフェに行っても良いよ、と伝える。
また面白い展開になるだろう。
今日の食事はAlbany近くのインド料理屋でしたが、
(先週、地元の青年たちと写真撮影を巡って睨み合ったところ)
すでに二度目の訪問で店員さんがデザートをサービスしてくれた。
ココナッツ入りのナン。美味い。先日のチョコケーキとは雲泥の差。
この店は肉は出さない。ベジタリアン&ビーガン対応だが、米も含め、
日本で知っているカレー屋より香り豊かで旨いカレーが食べられる。
夜はウィグモアに行き、サー・アンドラーシュ・シフによる
ハイドンフェスティバルの初日を聴く。本来はソプラノ付きの室内楽を
予定していたが、コロナの影響で器楽曲のみに変更したらしい。
よって紙で配るプログラムは無し。
それを補うためにか、彼はマイクを使ってよく喋ったが、
小さな、けれど確信的な声で話す。自然と、こちらが彼の発言を
受け取りにいくよう導かれる。彼の演奏にも共通する特徴だ。
大きな音を出さないところが、かえって強く印象に残る。
弦がピチカートするところのアンサンブルが良かった。
フォルテピアノは撥弦楽器。だからモダンピアノより相性が良いのだろう。
ストリングス三重奏の趣きだ。
ともあれ、今週は何としてもエマに会う。
先週は一通りAlbanyを巡る状況を把握できたので、今度は企画に潜入する。
エマに、ノーアポで自然に会える関係性をつくりたい。
あと、渡英してふた月目なので、暖かくなればロンドンの外にも出てみたい。
2022年2月25日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note 
Deptford Lounge 館長のアネッテさんは、まるで地域のお母さん。
ヨークシャー出身の彼女と『嵐が丘』についても話した。
昨日もいろいろなことがあったので、特筆すべきことを三つほど。
一つ目。
語学学校の同級生、ヤジーズ君がサウジアラビアの大金持ちと知る。
お父さんは企業の社長(何の仕事かは不明)。
運転手付きのロールスロイスに乗っており。兄弟は12人。
前回の誕生日に彼がもらったプレゼントは良質の馬だという。
「Very Cheap!」が口グセ。
週末ごとにセントラルにあるタイガー・タイガーというクラブに
通っているが、行くと意外と奥手で、何人かの女の子とやっと
インスタアカウントを交換してもらい喜んでいるとは、同行した人の談。
二つ目。
初めて、Tha Albanyが運営する別棟施設 Deptford Lounge に行く。
というか、いつも横を通っていた図書館の建物がそれと知って驚く。
ここは日本でいえば生涯学習施設で、地域の人に集会や練習の場を
提供しているが、特筆すべきは学童を含んでいることだ。
屋上にグラウンドまである。
劇場とは直接関係ない施設を運営することで、縁遠い人たちを
公演やワークショップに招き入れるシステムの窓口になっている。
感心した。
三つ目。
Canada Water Theatreでポエトリー・リーディング公演に参加。
『OFF THE CHEST』というタイトル。
プロのMC、プロの詩人、アマチュアの中からオープンマイクに
手を上げて選ばれた10人が出演者だ。
特に面白かったのはもちろんオープンマイクで、腕に覚えのある
人たちが詩やラップを繰り広げる。少女の告白といった向きの
朗読もありました。中でも胸を打ったのは、20代半ばと思しき
大柄の黒人青年の訴えです。彼は非常にたどたどしく、けれども
他の人とは違ってノートやスマホは一切見ず、コロナにより仕事を
奪われ、孤独であることを語った。
それは、自分の語学力の低さを貫通して、たちどころに理解できる
ものだった。彼が終わった後は、皆が立って彼に拍手。全体の終演後は、
ロビーや劇場内で延々語らいが止まらず、時間が過ぎていく。
当然といえば当然だが、普通に会ったら
絶対に近寄りがたい風貌の青年が、同じ人間なのだと切実に実感した。
劇場スタッフのリヴやジェニーは、早く帰りたいなあ、とは冗談で
言いけれど、片付けられるところを片付けながら、彼らを見守って
いた。毎日、少しずつ粘ることこそ難しい。なかなか出来ないことだ。
内容や関わる人たちを尊重する姿勢が、この劇場のスタッフには
浸透している。彼らを見ているとたのしい。
働き過ぎではないかと思ってリヴにそう伝えたら、彼女は週末から
週明けまで休みをとって、イタリアに行くそうだ。片道5,000円も
せずに行く方法があると教えてくれた。写真をたくさん撮るのだと
行っていた。サッとイタリアに行く。カッコいいなあ。
お代は見てのお帰りなので、専用の回収バケツがある。
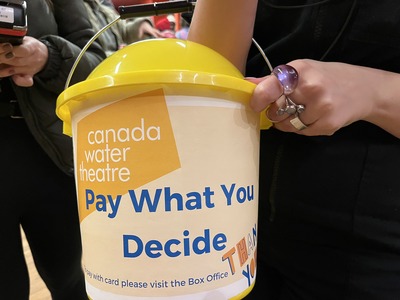
2022年2月24日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑この直後に怒られる。
一昨日から昨日にかけて起こったことを書こう。
2/22(火)
台本読みにさらに注力し始める。
『秘密の花園』は1982年に初演された戯曲だ。本多劇場にて。
それが1998年に唐組によって再演され、評判を呼んで99年にも上演された。
後者に大学入学が間に合い、自分はこれを観ることができた。
唐さんは唐組での再演にあたり、台本に手を入れた。
当時の唐組のチラシを見ると、ちゃんと改訂と書いてある。
初演版と改訂版、どこがどう違うのか調べつつ読んでいる。
ああ、日本語なら人並み以上に理解できるのに、とも思う。
慣れてきたので、学校にはギリギリ滑り込む。
エリザベス先生は授業巧者だ。それぞれの人間に興味を持っていて、
そういう彼女のスタンスが生徒の発言を活性化させる。
伝えたい内容がある時、人はその手段を必死に磨く気になる。
この日から加わった中国人の女の子も含めて、
色々な世界をそれぞれが生きてきたことを実感する。
最も饒舌なのは、サウジアラビアの青年たち。
彼らには兄弟が12人とか、20人とかいる。
お父さんには4人(許される最大数)の妻がいて、
最近、妹が生まれたばかりという20歳の青年がいる。
別の青年は、ハーバード大学に入り医者になると言う。
他にはいかにもお坊ちゃん風の質問魔の青年。
システムエンジニアとしてのキャリアアップを目指し、
英語の予習復習を欠かさない大柄の青年、などなど。
多くの兄弟に揉まれてきたのだろう。自己主張がシンプルだ。
家にラクダがいる人もいる。
片や、中国人の女の子は一人っ子。
重慶に生まれ育った後、シンガポールでアパレルの仕事をして、
ロンドンに来たのだという。今は日本料理店で働いているけれど、
イギリスで服飾の仕事がしたい一念で苦学しているようだ。
午後はAlbanyへ。
最近、劇場そばにあるインド料理屋が気になっていて、
この店が良いかどうか同僚に訊くために写真を撮った。
店や人の名前を一瞥して覚えるだけの頭が自分にはまだない。
そうしたら、店の前にいた青年3人が怒って叫んできた。
I don't allow you to take picture!
15mくらい離れていただろうか。
こちらは彼らを撮ってはいないのだが、確かに嫌な気がするだろう。
初めて英語で怒られたのでかなりビビり、かえってI'm sorry!
と異常にデカい声で返してしまった。
それがまたちょっと変な雰囲気を呼んだので、サッと劇場に入った。
Deptfordはなかなか荒くれた街だから用心しろと言われてきたが、
それにしても、昼飯を食べ損ねた。
が、これが功を奏する。
劇場に入ったところ、ちょうど催し物が始まるところ。
訊けば、0-2歳用のダンスプログラムに親御さんも含めて40人くらい
集まっている。飛び入りで観させてもらったら、これがすばらしく
感心しっぱなしだった。
が、ここにも間違いがあり、2階席で資料用にと撮影していたら、
舞台監督らしき青年に注意されてしまった。本番風景の撮影が厳禁な
ことはもちろん分かっているが、しかし、渡英してからこのかた、
その感覚がひどく麻痺していたのだ。内容も素晴らしかったし、
申し訳なく思ったので、終演後に改めて謝りに行き感謝を伝えたら、
かえって歓待してくれた。
ここにいる事情を話すと、彼はディレクターやプロデューサーに
繋いでくれた。結果的にたくさん話すことになった。
ちゃんとした映像や資料も送ってくれることになった。
その後はオフィスに戻り、方々にメールを打つ。
もちろん英語だし、システムに慣れていないので操作ミスが続き、
ひどく疲れる。一方で、リヴという女の子に系列劇場の見学を
お願いしていることをレミーというスタッフに話したら、
彼女がその場で先方にアポと取ってくれた。
大変ありがたいのだが、これはリヴと手配が重なる可能性がある。
レミーにはそのことを話して、さっそくリヴを探し回った。
果たして、やっとリヴを見つけて事情を話したら、
彼女は昨日に送った依頼メール自体をまだ読んではいなかった。
レミーにもリヴにも生真面目だと笑われたけど、こちらは新米だし、
慎重にならざるを得ない。お腹も空いているし、ヘトヘトになった。
気を取り直して、ルイシャム駅に向かう。
渡英後ひと月が経つので、ケータイ電話の更新方法について
訊きに行ったのだ。電話だと不安なので、直接が手っ取り早い。
自然と歩行距離が伸びる。店員さんがサクサク処理してくれたが、
2/28-3/1じゃないと手続きできないと言う。また来週と言って別れる。
ルイシャム駅に来るのは渡英直後に郵便局を訪ねて以来だが、
帰り途、イギリスでの初めての食事(ケバブ)を買ったあの店が
見えてきた。あの時は嬉しくて「また必ず来るよ」と言ってしまったが、
正直ケバブの肉はイマイチだった。目が合うと気まずいので、
あのナイスガイがポテトを揚げている隙にサッと通り過ぎた。
今日は色々なことがあってくたびれたので、絶対に近所の名店
ゴールデン・チッピーと決めていたのだ。
前回のcod(タラ)に引き続きrockというフィッシュ &チップスを
食べたが、やっぱりこの店は美味い。エリアNo.1と何人かが
絶賛するだけある。良いカサゴの唐揚げを食べている感じ。
食べたらすっかり元気になり、もう一つ何かしたい。
そこで、カティサーク近くのコメディ・クラブへ。
↓開演30分前。この後に全ての席が埋まっていった
火曜なのでお客は少なめ、それでも恋人同士や家族づれが
合計50人くらい入っていて、一人なのは自分だけ。
と思ったら、開演間際に入ってきた一人のおじさんがいた。
よほど通な感じがする。8:00pmに開演して、清水宏さんの
やり方の原型を見ることができた。メインのコメディアンが
場内を煽り、熱を帯びてきたところで別の二人を紹介する。
ロシア情勢やジョンソン首相のことを話しているのは分かった。
あと、ロンドンの地下鉄のうち、どの路線沿線に住んでいるかを
お客に訊いていき、その回答に反応しながら、ドッカンドッカン
ウケていた。とにかく「ファック」「ファッキン」「イディオット」
のオンパレード。これまで一生かけて聴いてきた「ファック」の数を、
今晩だけで完全に凌ぐ量だった。
面白かったけど、英語を聴くのに消耗して前半で失礼した。
これはまた行きたい。長い1日だった。
2/23(水)
早朝から作業してお腹が空いたので、初めてカフェで朝食を食べた。
口開けらしく景色の良い席に通されたが、いつもより30分早く
動いたことで出勤・通学の風景を見ることができた。
皆、険しい顔でそれぞれの目的に急行していく。どこの国も一緒だ。
語学学校は遅刻が目立つ。週半ばになるとすぐにこうだ。
11:00にやっと来た青年は、昨晩遅くまで遊んで帰宅が深夜だったらしい。
オリジナルのコンテストを考える、
自分が英語を学んできたプロセスを説明する、
という課題にチームで取り組んだ。
今日が初めての42歳トルコ人男性がいて、彼は奥さん一人と言っていた。
大量に買ったからと言って、皆にスニッカーズの小さいのを配ってくれた。
授業後は、カナダ・ウォーターに向かう。
50分ほど歩いた。初めていく場所には出来るだけ徒歩で行きたい。
土地の様子を見るためだ。水辺にある劇場に着くと、
ジェニーというスタッフが丁寧に案内してくれた。
地下鉄の真上にあって、図書館も併設しているから若者たちで
賑わっている。130席ほどの劇場が一つきりだけと、
ここにも、会議・稽古のためのスペースは6つもあった。
ジェニーは自分のために予め全ての空間の電気をつけておいてくれた。
丁寧な歓待に感謝して、明日また来ると言って別れた。
リヴが23日にこの劇場で行われるポエトリー・リーディングの
チケットを予約してくれているのだ。何度も来られて嬉しい。
↓水辺のCanada Water Theatre
30分ほど戻るかたちで歩きながらAlbanyを目指す。
途中、ホームセンターを発見して、じっくり文房具を買った。
このところずっとダブルクリップとクリアファイルを探してきたが、
英国の百均にあたるパウンドラウンドやスーパーには皆無なのだ。
ここでやっと見つけて嬉しい。他の売り物を見て周り、妙に置物が
充実しているのが可笑しかった。
↓偶像が好きすぎるのではないか
Albanyに短時間行き、セリにここ数日の体験を話しつつ、
夜の予定の確認をする。オンライン会議があると聞いていたのだが
ミーティングアドレスがどこにあるかを訊いたのだ。
全体メールで回ったカーソルをクリックするべしとの返答。
参加してみて分かったのだが、これは法人全体の年次総会だった。
2020-2021年のお金の収支、各企画の進捗、これからの展望について
それぞれの担当が話すのだが、驚くべきはそのスタイルで。
なんだかテレビやラジオの番組風に総会が展開するのだ。
全体を進行するのは若い男女で、彼らがパーソナリティーとして喋り
ギャビンの代表挨拶や担当の発表を促していく。
合間には音楽も鳴るし、企画説明の時にはそれぞれの進捗を
極めてわかりやすく、魅力的にまとめた映像が流れるのだ。
ニュース番組みたい。対外的でなく、組織内の44人のメンバーが
視聴するものなのだが、約2時間の番組風で愉しんだ。
内容にも増して、この形式を生み出すのにどれほどの労力を
かけたのか訊いてみたい。社内報や忘年会の充実に全てを賭ける
班があるのだろうか。皆が全体を把握することをいかに重視しているか
実感した。
そうだ。今日はセリにあってから年次総会までの間に時間があり、
初めて英国の床屋に行った。床屋は街中に溢れて迷ったが、
語学学校のそばの店に飛び込むことにした。
朝に通りかかった時に、スタッフの男性がシャッターを開けているのを
目撃したが、彼の耳の上の刈り上げ部分には小さなハサミのタトゥーが
あり、よほどこの仕事が好きなのだと興味を惹かれたのだ。
果たして、その男性は他にお客さんがいたので、
店主らしいおじさんが相手をしてくれた。横浜の床屋で、
髪を切り立ての自分を撮影しておいたので、それを見せながら説明したら、
任せておけと言って散髪が始まった。かなり剛腕な散髪で、
自分の場合、一才をバリカンで行ってくれた。ソケットを念入りに
取り替えて矢継ぎ早だが、終わってみて側頭部と後頭部の刈り上げ具合が
すごい。我ながらビロードのような触感なのだ。こんなのは初めてだ。
結果的に、シャンプーや顔剃りは無かった。
初めてなのでなるに任せたが、驚いたのは、両耳を炎で炙られたことだ。
高級な葉巻に火を付ける時に使う、あんなようなもので、
かなり熱い思いをした。訊けば、これで耳周辺の産毛が処理できるらしい。
しかし、驚いた。
帰りには、通り掛かりのタイ式マッサージが気になった。
横浜では定期的に整体に通ってきたので、ぜひイギリスでも行きたいが
ここは自分が入って良い店だろうか。
帰って調べようと店の写真を撮る。
今日は徒歩移動のみに終始し17km。よく歩いた。
2022年2月22日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑通りがかりのおじさんは、木に足をのせろ!と言った。
ずっと雨。ザーザー降りではないが、1日に一度は小雨が降る。
そして強風。先週の木曜、学校でもAlbanyでも
「明日からの嵐に気をつけて」と言われた。
なんぼのものかと思って金曜(18日)の朝に起き出すと、
確かに吹いている。そしてそれは週明けの月曜まで続いた。
これがロンドン名物らしい。雨でも、よほどでなければ人々は
傘をささない。よくこのような強風が伴うために、傘が壊れてしまう
のが原因のひとつだと言っていた。
学生時代にやった巨大バッタ時の強風、
テント公演で揉まれてきたいつくかの強風を思い出す。
という経験を持っているので、恐るるに足らず。
野外劇の『青頭巾』を石巻の中瀬公園でやった時、強かったな。
金曜に起こったことは、Facebookに書いた。
お世話になっている人が多く見ているFacebookは週一ペースでの
更新と決めた。ダナという女の子のフェアウェルランチに連れ立ったが
これがなかなかの激闘で愉しませてくれた。
2/19(土)
学校で知り合ったブラジル人の青年ギリアミ君と前日に約束し、
朝から国立自然史博物館を目指す。ただし現地に行ってみて、
無料ではあるが予約が必要であり、それはもういっぱいだと二人で
知ることになった。残念。と、向かいに別の博物館がある。
V&Aミュージアム。これ行こうと言って入ったが、当たりだった。
ヴィクトリア&アルバート。英国が帝国として最も輝いていた時代、
それが19世紀に長期君臨した女王に由来するヴィクトリア朝時代だが、
旦那との名を連ねたこの建物は、ものすごく広く、世界各地から
当時のイギリスが調達した品物で溢れている。当時の栄華が伝わる。
仏像も、ギリシャ神話の英雄たちの像もある。
門などに使われる金物のレリーフをギリアミ君が熱心に記録している。
彼の父は、金物を扱う職人だという。彼自身は建築家。企画や設計、
ペーパーワークが仕事だと言っていた。28歳。
ファイブガイズというハンバーガー屋で食事して別れ。
午後は雨量が増してきたので、一旦ホテルに戻り、『秘密の花園』を
読んで、少し昼寝した。夜はAlbanyでギグなのだ。
Albanyでの催しは全て出席しようと決めているから、
7:30pm開始というふれ込みに従って劇場に行く。ただし、どうも
この時間は開場時間のようで、実際にスタートしたのは8:20pm過ぎ。
これが、望外の面白さだった。
Charles Haywardというドラマーが中心となり、集めたメンバーで
繰り広げたライブだったが、Albanyはステキなライブハウスと化し、
179名(後で技術スタッフのケイトリンに聞いた)が寝そべったり、
座り込んだりしながら酒を手に手に聴いている。イスは少量。
かつてプログレと云われ、今はエレクトリカル・ロックとされている
音楽演奏。
音楽に呼応して絡みついているカップルは、セックスし始めるのでは
ないかという程に盛り上がっている。演奏は素晴らしかった。
20分ほどの曲を2曲やって、休憩。後半は別の人のドラムと
サックスの巨匠の即興。これも2曲やった。
打ちのめされた。終演後、チャールズ・ヘイワードに寄っていき、
最高だったのであなたを追う、と伝えた。11:00pm過ぎに興奮しながら
帰って、渡邊未帆ちゃんに報告すると、彼が組んでいた「ディスヒート」
というバンドが有名だという。大里先生に報告したかった。
↓ヘイワードさんと
↓ライブの様子
2/20(日)
朝から唐ゼミ☆ワークショップ。佐々木あかりが公演を終えて
帰ってきた。アシスタントを得て楽になった。
一回に約20ページずつ進む。一幕おわりまでいき、
文ちゃん、洋一、キティ瓢田というサフラン座のトライアングル完成。
急いで11:30amまでに入店した者が食べられる
イングリッシュブレックファーストにありつき、帰りに駅前にきたところ
強風で木が根こそぎ倒れている。眺めていたら、近所のおじさんが
写真を撮ってやろうと言い出した。面白い人だ。
午後はヘイワードさんのCDを手に入れようと街を徘徊するが
そして、夜にウィグモアに行き、初めてギトン・クレーメルを聴いた。
シューマン、ヴァインベルク、ラフマニノフというプログラム。
初めて生で聴くトリオの曲だが、量感がある。クレーメルは
じくじくとした弱音の手つきがエロくてあやしい。
往々にしてピアノがデカすぎると思った。アンサンブルそっちのけで
グイグイくる。
2/21(月)
今日から学校の先生がエリザベスさんという女性に変わった。
彼女とすごく打ち解ける。理由は簡単で、趣味と行動半径が激しく
一致したからだ。彼女はウェールズ出身の母と、母の故郷が嫌いな
イングランド人の父の間に生まれ、二人の娘さんがいる。
ピアノとヴァイオリンをやり、夜と週末はタンゴの教師をしている。
ロンドン・シンフォニエッタの事務局で働いた経験があり、
なんと、5年前までAlbanyに勤めていたらしい。
好きな小説は『マエストロ&マルガリータ』。
こちらも5回くらい読んでいると言って、1時間ほど話し込んだ。
日本語訳されたブルガーコフはほとんど読んでいる。
ヴェルギリウスとダンテ、ペンリー・パーセルが好きだとも
訴えて、プロ・アマ問わず『Dido & Aeneas』生演奏を逃さない
つもりだと伝えた。今後、色々と指南を与えてくれそうだ。
午後はAlbanyで事務。
方々にメールを打ち、入口管理のトムにプリントアウトを
手伝ってもらった。ここはそういう役割分担らしいのだ。
いよいよ家が決まったので、大家さんに渡す資料や、
劇場の資料も印刷。唐さんの台本も印刷してもらう。
印刷待ちの間、トムに21世紀リサイタルの動画を少し観せたら、
唐さんのボクサー姿に爆笑していた。
唐ゼミ☆のみならず、巨大バッタ、唐さん、RSCと蜷川さんが
『リア王』を作った時の眞野さんの映像が自己紹介に役立っている。
(室井先生は"哲学者"だと分かりにくいので、バッタをやった人を強調)
ミミ、エマ、アネッタ、リヴにメールを打って、
打ち合わせや施設往訪の申し入れをする。動かなければ!
夜はまたウィグモアに行って、韓国気鋭のカルテットを聴く。
ショスタコーヴィチを聴いてブルガーコフを思い出した。
グロテスクな笑い、時々メロディアス。
客席はやっと半分埋まっている程度だが、これからの人たちだと思う。
トップからアンサンブルがとても良くて、熱演も激しい。
理想的だ。と、1ヶ月前なら思うところだけれど、迷いが生じている。
イギリスに来て、全体なんかそっちのけでグイグイいく
プレイヤーに魅了されている。痛快で、潔い感じがする。
国鉄に慣れ、地下鉄の乗り換えもより便利な方を選択できるようになった。
スーパーでは、チーズの他にハムも安く、美味しい。
レストランでは、安いピザ屋を見つけた。
生活しやすくなっているが、課題はAlbany内での喰い込みと、
英語の成長実感が乏しいこと。そのうち何とかなるのだろうか。
↓エリザベス先生。今度ギャビンに会ったらこの写真を見せよう
2022年2月19日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note
昨日、芸術文化財団の上司の一人とLINEする機会があった。
やりとりのついでに語学学校での授業中の写真を送ったら、
誰もマスクをしていない、と驚かれた。
そうだ!
マスクするのを、こちらの人たちの雰囲気に押されて忘れかけている。
と言うくらいに、英国ではコロナのことを皆が気にしていないように
感じる。すでに国民の4分の1以上が感染しているイギリス。
無自覚無症状の数を合わせれば、さらに多くの人が罹患している
だろうから、集団免疫をすでに獲得しているのかも知れないけれど。
Albanyでは金曜に夜に、皆で連れ立ってパブに行った。
写真の様子は、広い広いパブの中で自分たちの陣地を確保するやり方。
劇場のロゴの入った風船を膨らませて、各テーブルに置き、
確保完了です。これはなかなか洒落ていて良い方法だと感心した。
劇場から近く、広くて安いこのお店が皆の溜まり場。
ボックスオフィスとエントランス管理のスタッフも、
総務担当も、各プロデューサーも、テクニカルスタッフも、
時間に余裕のある人がそれぞれに集まっていて、盛り上がる。
劇場が一つのチームであることを感じさせる数時間。
そしてまた、家庭や用事や疲労のある人から、
気づけば五月雨に抜けていく。これも自由な雰囲気で、良い光景。
自分は£2のジンジャーエールをカッコ良いグラスに入れてもらい
ずっと飲んでいる。英語はよく分からないけれど、こういう場だと
相手の言うことが理解できるから不思議だ。
各人の名前は、自分のノートにスペルを教えてもらい、覚えている。
あと、この二日間は、ロンドン名物の嵐だった。
とにかく風が強い。学校でも劇場でも、明日は気をつけてと言われ
何のことかと思っていたが、こういうことか。
実際に強風がやまない。
小雨もパラついているが、これがイギリス人が傘をささない
大きな理由なのだそう。この点に関しては、自分は断固スーパーで買った
折り畳み傘をさして、濡れないようにしている。
風邪ひいてなるものか。せっかくイギリスでの貴重な時間が
部屋で伏せっていたら台無しだ。マスクも、都心に出る時はしないと。
そう思って強力なやつをカバンに忍ばせている。
2022年2月18日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑テムズ川も砂浜みたいに遊べるようだ。相変わらず、1日に1度は小雨。
昨日は語学学校で、ディスカッションを行った。
パーティーの開き方について議論したところ、
サウジアラビア人の青年二人に強硬にやり込められた。
30人のパーティーをある店に予約したが、
2日前、参加者の中にベジタリアンが5名いることがわかった。
お店はそもそもベジタリアン対応はしないレストラン。
幹事の自分はどうするべきか。
①パーティーを取りやめる
②別の店に切り替える
③現在の店に交渉する
自分は③を選んだけれど、彼らは②だという。
30人分の予約はお店の準備や収益にとっても大ごとなので、
③をして対応してくれたら良し、断られて初めて②に行けば良い
と伝えたが、絶対に②だという。彼らお国柄か、若さか、面白かった。
午後、Albanyには行かなかった。
昨日は皆が自分の関係者がオフィスに来ない日なので、
(ネットで出勤状況を調べられるようになった)昼から出かけて
Facebookで椿昇さんに勧められたテート・モダンに行った。
元工場だという建物に圧倒される。
無料と有料のコーナーに別れており、まずは無料から。
初回ゆえに作品より、展示スペースの方が印象に残ってしまう。
ミュージアムショップだけで何軒もある。しかも50%オフ中。
草間彌生の有料展示は、3月末まで予約でいっぱいだ。
パンデミックでなければ、もっとすごいのだろう。
また平日のフリータイムに来るべきだと思った。
フラッシュ無しなら写真撮影OKという習慣にも驚く。
夜はコンサートに行き、ストラヴィンスキー・プログラム。
イヴァン・フィッシャーとブタペスト祝祭管のリズム感の悪さ、
もつれっぷりにイライラしたが、中盤のヴァイオリン協奏曲に登場した
パトリシア・コパンチンスカヤが状況を一変させた。
カラフルな衣装で、よく見えないがおそらく裸足、
ヘッドバンキングしながら周りの演奏を聴き、自分の演奏に
挑みかかっていく彼女により、空気が格段にハネる。
たった一人がこんなに全体を支配してしまうことがあるのだ。
素晴らしい俳優もこうだなと思いつつ、彼女が去った後半の
『ペトルーシュカ』はまたキレ無し。
終演後の拍手をそこそこにボックスオフィスに向かい、
6月にコパチンスカヤが出るプログラムのチケットを買った。
チーペストじゃなく、できるだけパトリシアに近いところで!
と伝えたら、馴染みになった髭のおじさんが笑っていた。
ところで、これまで書きそびれてきたが、一日に一度は必ず誰かに道を訊かれる。
また、ホールのロビーにあるテーブルに陣取って仕事していたら
中年女性2人に相席を申し込まれ、子どもの教育問題について
熱心にやり取りする様子に思わず笑ってしまい、彼女たちと少し話す。
コンサート中、隣の家族連れに当日パンフレットを貸して欲しいと言われ、
快諾したら、かなりの時間熟読してなかなか返ってこなかった。
何か、人間同士のやり取りが率直で、自分は居心地が良い。
一方、ホール最上階には会員限定のレストランやカフェがあり、
そこには入ることができない。
移動中、どこにどんなホームレスがいるかも頭に入ってきた。
グリニッジの隣、カティサーク駅を出ると、
足の皮が松の幹の表面のようになっているおじさんがタンバリンを
叩いて集金している。ロンドンだ。
2022年2月17日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑2週連続、曇天のバザー。管理人に出店者の若者が注意を受けている
ように見えた。ああいうのを聴き取れるようになりたいものだ。
現在、2/17(木)7:00am。
昨日も夕方に Albany から国鉄に乗って街に出ようとしたけれど、
電車が遅れていたようで、それで思い立って、やめてしまった。
7:00pmにはホテルに帰ってきて、
いろいろと状況を整理してみようと思ったのだ。
だいたい、ここ数日は小雨続きだ。
朝は晴れているのだけれど、昼過ぎからは曇り始め、夜は雨。
ロンドンらしいロンドンかも知れない。
8:25amに学校に向かい、
途中では日本にいた時から続けている英語学習をしている。
30分弱で学校につく。
一限目を受け、30分の放課ではだいたい日本に連絡をとっている。
ちょうど日本の夕方にあたり、仕事にせよ家族にせよ、
お互いの活動時間が重なる時間帯だからだ。
12:30に学校が終わると1時間ほどかけてAlbanyに向かう。
ここで食事。昨日は辛いものが食べたくなってタイ料理に行ったが、
これは失敗だった。価格はロンドン値段。それでいて量が少ない。
ロンドンでは量が多いので、一日一食のペースが身についたのだ。
その習慣を崩された。横浜にあるアジアンダイニングキッチンの
ランチの量と値段を見習え!と言いたい。
観光地だからか、価格に12.5%のサービス料ものる。
この頃から雨が降り始め、Albanyにたどり着いた。
周囲とコミュニケーションしながら、先日セリからもらった資料に
目を通している。この劇場の運営システムや組織図、進行中の企画に
ついて書かれた資料だ。合間で、一人一人知り合いが増えていく。
昨日はファイナンス担当のマークと知り合った。マークは二人いる。
今回はシニアのマークだが、彼はカティサークのそばにある
"ザイバツ"という面白い名の日本料理屋が気に入りだと教えてくれた。
ロンドンでのアジア系飲食は失敗続きだが、教わった以上は近々
行ってみよう。どんなものか。
昨日は途中、事務室を出て劇を観た。
『ONE MEAL』という子ども用の劇を上演していたからだ。
ここ2日間、45分ほどのステージを1日3回ずつ公演している。
客席の子どもたちを見ていると面白い。多文化主義の街にある
劇場なので、多様で、でも子どもの動きは万国共通だ。
あれは10歳くらいだと思うけれど、少年の俳優が、
お母さん役の女優と、狂言回し役の男性の真ん中で活躍していた。
終演後は、客席とのレクリエーションの時間で、
子どもたちはキャストと話し、写真を撮り、セットの中を冒険して
いた。運営にとってはハードな3回公演だが、とても良い雰囲気だ。
ちなみに、大人も子どももワンシート一律 £7。
と、ここで色々と頭に思い浮かぶのだが、まだ自分に話し合うだけの
語学力がない。今回の公演も各地を巡回しているプログラムの
買い取りのようだが、どんなエリアをどの程度の頻度で回っているのか。
少年の俳優がいるのがまるで大衆演劇の一座のようだが、
彼の通学はどうなっているのか。
どだい、通い慣れてくると、色々な疑問が頭に浮かぶ。
Albanyの劇場の周りでは定期的にバザーが開かれているのだが、
これが週末というわけでもなく、どういったものなのかよく分からん。
こんなことも訊いてみたい。??が頭にいっぱいある。
なんとなく習慣的に暮らせるようになってきているけれど、
まだまだだなと思う。それもあって早めに帰り、駅で配っている
フリーペーパーを読んだり、日本で買ったイギリス史の新書を読んだりした。
そういえば、ヒースローで買ったSIMカードは1ヶ月単位のものだけれど、
次回更新のやり方を知る必要もある。
というように、足回りを固める時間として昨晩を過ごした。
日本から連絡が来て、取り壊しの迫る入谷の坂本小学校(唐さんの母校)
を保存するための運動を続けている小林さんとやり取りをした。
小林さんのコツコツとした粘り強さに頭が下がるし、
いつものように駆けつけられないことが歯がゆい。
一方、ほんの近所だって、少し違う方角、違う路地に進めば、
まだまだ知らないお店や風景があることに昨日は気づいた。
慣れてきたつもりだけれど、自分はまだまだロンドンを知らない。
↓終演後の舞台。イギリスにも桟敷席はある。自分は最前列端で観た。
2022年2月16日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑英国でのビッグボス ギャビン・バロウさん。まさに大物アクティビスト。
「ビッグボス」という言葉に新庄監督により馴染んでおいて良かった。
現在、2/16(水)朝7:00。
今日は昨日のことだけ。コンパクトに書こう。
出会いと別れがひっきりなしの語学学校だが、
クラスの主要メンバーがインスタのネットワークをつくっている。
ロシア人のダナという17歳の女の子、トルコ人のセナ(年齢わからず)
という女子が声も大きくムードメーカーだが、グループを活用した
彼らの応酬が授業中に飛び交う。
明日の夜に「『シンデレラ』か『美女と野獣』を観に行かない?』と
ダナ。みんなが反応しないでいると「私だけ? 返事してよ」と言う。
自分はお誘い対象外だと思うが、夕方になって寂しそうなコメントが
続いたので、お礼とお断りのコメントをしたが、特に返事なし。
やはり、対象外だ。
今週入学した国も名前もわからないおじさんが「オレだけオールド」
と言ったので、「41歳の自分もですよ」と告げたら、デザイナーの
ロシア人・スヴェタが「私も47歳」と言った。
彼女の名前は......、『ジョン・シルバー』の「ドクリンコの唄」を
思い出して呼びかけにくい。「♪あたいたちゃスベタ・・・」
授業中、KAATの案件で津内口に取り次ぎを頼んだが、
まだやったことのない国際電話を急遽しなければならなくなりそうに
なり、焦る。「3」のSIMカードでは無理そうだ。
通い慣れたbill'sで昼食。今日は20歳のSho君と一緒に食べて、
久々に手ぶらでトイレに行けた。彼のホームステイや日本の家族、
これから2年を英国で過ごす展望を聴く、ヒースロー到着時の戸惑いは
みな一緒だと思う。
この日は雨で、自分はチープな折り畳み傘をさし、
Sho君は英国流にささない。後で劇場のソフィーやセリに傘を持たない
理由を訊いたら、風が強くてすぐに壊れるからだそうだ。
日本製をプレゼントしたいものだ。
午後は劇場に行って、やっと、ついに、やっと、
大ボスのギャビンに会うことができた。3つの施設を同時に運営し
多忙なギャビンと30分ほど話すことができた。
まずは今回の誘致に改めて大きな感謝を伝えて、
ここ2週間のこと。エマに伴走しようとしていること。
ミミの体調が心配なこと。ロンドン市内を歩き回っていること。
を伝えた。次は他の2施設を案内して、食事をする約束をする。
忙しそうだ。
そこからはセリと一緒に、オフィスの予約の仕方や、
劇場のメンバーとのスケジュールの押さえ方、運営組織を示す図を
見ながら、それぞれの立場と役割について説明を聴いた。
CEOのギャビンがとても偉そうに見えるので、
この樹形図から、ここの上下関係がどれくらい厳格なものであるか
訊いた。質問の動機を伝える中で、思いかけずKAATの眞野館長のこと、
唐さんや唐ゼミ☆のこと、室井先生と行ってきたことまで
説明することになった。
それらすべてを生かすヒントが、この劇場にはあるのではないか。
オペラやクラシック音楽や文学、古典劇などのハイカルチャーも
好きだけれど、最終的にはヒューマニティー("動物としての力"でもある)
を自分が発動させたり、人がそれを爆発させている瞬間を最重視している
ことを伝えた。
ペーパーワークに忙しいはずの彼女は、
およそ2時間以上も自分に割いてくれたと思う。
アツシに向いたギャビンの活動がある、と言っていくつかのコミュニティや
それに付随するウェブサイトを紹介してくれて(それらの拠点は、
ロンドンの外や、英国外にも及ぶ)、金曜の夜に開催される集まりにも
誘ってくれた。「でも、チケットいっぱい買ったアツシには予定が
あるかもね」と言うから、ここにいることの重要性と、優先順位が
高い予定を常に選ぶための最安席であることも念を押した。
もし「こちらにいるべきだ」という予定が飛び込んだら、チケットは
学校の同級生にプレゼントしても良いし、学校の出席日数については
規定数をクリアするよう通うし、すでに先生方や事務局にも渡英の
主目的を伝えて理解を得てあると伝えた。
セリの理解がありがたかった。
このあたり、大学一年の頃を思い出す。
6月頃、まだ親しいとはいえない唐さんが花園神社や鬼子母神での
紅テント解体に誘ってくださった時、自分は迷わず月曜の授業をサボった。
どちらのために生きているか、という優先順位の問題。
もちろん、予定なしにサボることはしない。
ここの職場は原則6:00pmまで、というセリに従って作業を終え、
今日もサウス・バンク・センターに向かう。当日券で£10。
7:00pmから「啓蒙時代の楽団」というオケを聴く。
秋にオペラシティで聴いたイザベル・ファウストがソリスト。
シューマンのヴァイオリン協奏曲は、かつて横浜国大の茂木先生に
勧められた曲だ。特に第2楽章の美しさは、気のふれた晩年の状態が
よく出ていて、不思議に魅力的だと。初めて生で聴いてそれが伝わった
けれど、いかんせんオケの規模や古楽器スタイルにはホールがデカすぎる。
アンコールを告げるために喋ったイザベルの声の柔らかさが印象的。
名前も風貌もいかつい感じがする彼女の演奏は繊細さ、玄妙さに魅力が
ある。細やかな人なのだろうと思う。
2022年2月15日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑昨日は誕生日だったので、皆がお祝いしてくれました。
現在、2/15(火)朝7:00。
前回は金曜の朝に書いたので、金・土・日・月にあったことを書こう。
2/11(金)
この日は、唐さんと娘のお誕生日だった。建国記念日に生まれた二人。
学校に行き、昼食(近所のbill'sのウェイターさんと親しくなった)
をはさんで劇場オフィスに行き、リヴ(Liv)という女性から
パソコンのログインや様々なセキュリティについて、
解除の仕方を教わった。
こちらは、バックヤードのトイレにもテンキーが付いている。
館内を自由に動けるようになり、スタッフの一員として一歩前進した。
18:00頃には劇場を出て、国鉄に乗ってロンドンブリッジ駅で降り
30分ほどテムズ川沿いを歩いてサウス・バンク・センターに到着。
今日も当日券を買おうとしたところ「今日はイベント無いよ」と受付の人。
どうやら、カレンダーを見間違えていたので、
ならば!と近くのテーブルに陣取り、夏までのプログラムや
自分のスケジュールと睨めっこし(競馬の予想みたい)、
先々のチケットを最も安い席で買う。
"チーペスト チケット"がスタッフとの合い言葉。
その中でオススメの席を!と相手にお任せした。
本来はミシン目で切れるはずのチケットが蛇腹になって出てくるのが
面白く、ボックスオフィスのスタッフと爆笑しながら買った。
10数回分買ったら割引も適応され、2万円いかないくらい。安い。
帰り途、電車の乗り換え中に電話がかかる。エージェントさんから。
下見に行った大家さんが、OKしてくれたらしい。
ついては、翌朝エージェントさんとの面談を決める。
グリニッジから30分ほどのニューエルタム駅で待合せ。
前金が必要なので、帰りにATMに寄ったが£20紙幣がたくさんになって
しまった。あと、包む封筒がない。
2/12(土)
ホテルに戻り、本を読んだりしながら過ごして、夜中(日本は朝)に
唐ゼミ☆オンライン会議。その後、早朝(日本のお昼過ぎ)にも
一本zoomで写真家の方と打合せして、先々の企画について話し合う。
こちらが寝ている間には、林麻子のWSが進行中。
彼女は、教え方やタイムコントロールなど、巧者のようだ。
いつも劇中歌の振り付けをしたり、衣裳を考えたりしている時にも
視野の広さがあると思ってきたが、当たりだった。
彼女は音大出でピアノと声楽をやってきた。
劇中歌ワークショップ、ぜひ参加してください。
『唐十郎劇中歌ワークショップ』
ここから、7:00に回転するセインズベリーに行って封筒を探す。
尋ねてみると、売り切れ。困っていると、店員の女の子は
別棚の便箋とセットになっている封筒を一枚引き抜いて
プレゼントしてくれた。本来、便箋とセットの売り物ではないのか?
幸せな気持ちになるが、買う人には一枚足りないことになる。
その後、エージェントさんと会い、
20年イギリスで暮らしているという日本人のその方に、
色々と面白い話を伺った。息子さんがサッカーに夢中だそうだ。
こちらにいるうちにサッカーの試合も観たい。
超一流リーグはレアチケットだけれど、地元のチャールトンという
チームなら手に入りやすいらしい。下部リーグの厚みこそ本場を
感じる。劇でも、音楽でも、スポーツでも、決して来日公演のない
ローカルなものを目にしたい。良いアドバイスをもらった。
午後になり、ミミとWhatsAppというアプリで連絡を取りあったら、
彼女の体調が優れないことがわかった。彼女は明らかに忙しい。
その上で、自分の家や生活の心配をしている。
なるべくオフィスに顔を出して馴染みたいが、
ミミが不在の間に劇場に行くと結局は彼女に連絡がいくことに
なりそうなので、朝は原稿書きをして午後からは出かけることにする。
金曜にサウス・バンク・センターでのチケット注文が面白かったので、
同じことをバービカン・センターでもやった。ここは、蜷川さんが
公演していた場所だ。ボックス・オフィスの青年ジャックさんと
蜷川さんの話をしながら、席をアレンジしてもらった。
その後、ピカデリーサーカスの辺りまで歩き、
聖ジェームズ教会のバレンタイン・コンサートに行ってみた。
ヴィヴァルディを立て続けに演奏するプログラムで、
協奏曲など初めて生で聴くものばかりだ。
開場時間と同時に入って、自由席だというので前から2列目
真ん中通路沿い(テント芝居みたい!)を押さえた。
トイレに行く際、荷物を置くのは危ないので、当日プログラムと
ペットボトルを置いていき、戻ってみたら、中年女性と青年の
親子連れにズラされていた。どうやら悪びれた様子もないので
こちらが良くなかったようだ。今後は、周りに人が座るまでは
その場にいて、コミュニケーションしてから動くべきと悟る。
演奏は一流ではないけれど、1600年代からあるという教会内部は
趣きがあり、とにかく周囲のカップルがイチャイチャしながら
聴いているのが面白い。ちゃんと入場料を取るライブだが、
平気で写真や動画を撮りながら聴いている。おおらかだ。
教会の人からは、平日のお昼は無料の演奏をしているから
またおいで!と言われた。ヴィヴァルディは喘息持ちで赤毛の司祭
だったというから、合っていたように思う。
催し物会場としての教会という選択肢があるのだとインプット。
2/13(日)
朝起きて、唐ゼミ☆ワークショップ。
午後はKAATの仕事で発行している「共生共創通信」の原稿書きをし、
メーテルリンクの『青い鳥』を読んだ。堀口大学の翻訳だけれど、
唐さんが『秘密の花園』に使った言葉ではない。誰の訳文か、
今後に調べる必要がある。
イタリアンレストランで昼食。ここは先週も来てかなり気に入った。
イギリスに美味いものがないというのは違うと思う。
中華料理屋に行くと違和感を感じるが、西洋のものは美味しいと思う。
雨の中、夜はAlbanyのライブに行った。
(先日スーパーで折り畳み傘を発見。チープなものだけれど)
「TOMORROW'S Warriors(明日の戦士?)」というバンドのライブだ。
劇場に行ってみると、ホールが完全にライブハウス化していて面白かった。
いつもとまるで雰囲気が違う。案内係のケイトがお客さんをリードする
様子も、明らかに先週のキッズプログラムとは違う、
2階客席の奥にあるバーカウンターでは、システム担当のリヴが
ビールを注いでいる。多芸だなと思った。
演奏と歌のレベルが高い。このバンドがどれほどメジャーか
わからないが、キーボード、ベース、ドラム、ギター、ヴォーカル、
フルートの6人組のレベルの高さはすぐに分かる。
でも、何よりも、片付けまで疲れも見せず、テキパキと働く
ケイトとリヴが素敵だった。彼女たちのお客さん対応には
人間的な温かみがあって、催しをかなり底上げしてくれている感じがした。
2/14(月)
語学学校に行き、同級生のトルコ人・セナに年齢を訊かれた。
40歳....あ、今日で41だ!と言ったら教室内が盛り上がった。
日本人は幼く見えるので、オレには妻も子もいると伝えて、笑われた。
一方、週末を経て、若者たちによる教室内のラブワゴン感が加速している。
帰り際、放課中に即席で作られていたバースデーカードをもらって、
写真を撮る。ありがたいことだ。同時に、隣の青年・マリオは卒業。
2週目に入り実感したことだが、ここは毎週、新人が来て卒業生が出ていく。
1ヶ月程度の学習の人もいる。自分のように11ヶ月コースは長い方のようだ。
午後は、各種手続きに動き回った後、夕方から初めてウィグモアホール
に行った。当日券で、CDで聴いていたマーク・パドモアのリートの
チケットを買う。開演まで時間があったので、高級感のある周辺を
ウロウロしていたら、丸亀製麺とCoCo壱番屋があった。
と、ふと気づけば、どこからかコーラスが聴こえる。しかもかなり上手い。
気になって近くの教会を覗くと、ロンドン・フィルハーモニックの合唱団が
練習中だった。女性合唱指揮者がテキパキと稽古をつけていてカッコ良い。
2022年2月11日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑ジャック・ザ・チッパーのおじさんにまた来ると伝えたが、再訪なしかも。
今日を以って『秘密の花園』を一通り打ちこみ終わった。
かなり読めたつもりだが、前半部分の「夕泣き丸」「夜泣き丸」部分の
描写が浅い。今後は睨めっこして、考え抜きたい。
それに、自分が参考にしてきた単行本は、あくまで改訂版だ。
1998年に行われた唐組秋公演の素晴らしさを受けて出版されたから、
首藤幹夫さんによる舞台写真がいっぱい。
最近はお目にかかっていない堀切直人さんと、亡くなった立花義遼先生、
そして、室井先生による解説が載った沖積舎版。
1982年に初演されたものから、唐さんによって少し書き換えられている。
その差も検証したい。
後半二幕のアキヨシといちよの会話には随所に赤ちゃん言葉があって、
これは初演バージョンの名残りなのだと、大学一年生の時に受けた講座の
なかで唐さんはおっしゃっていた。劇中歌をいちよ役の緑魔子さんが
歌ったはずでもある。これを遡ることで、執筆時はどうで、
唐さんが何を考えて書き換えたのか、これから考えてみたい。
さて、前日(2/9)に『芝居の大学』のためにお休みした語学学校に行く。
すると、受付で総務の女性に話しかけられた。
実は火曜目を終えたところで詳細なアンケートがメールで送られてきた。
自分はそれに、ちょっと講座のレベルが高く感じたことを伝えたのだ。
事務局は柔軟に対応してくれたらしく、今日、試しにもうひとつ初級を
受講できるよう手配してくれたらしい。それを受けてみて、
アツシに判断して欲しい、と。
新たな教室に行ってみて、即座にこっちだと思った。
この学校のなかで最も初級にあたるこのクラスは、明らかなタレント揃い。
アルジェリアやロシアやブラジル、そういった国々の青年たちが、
とにかく騒がしく、人間としてのパワーに溢れている。
先生もまた、お腹痛いと言いながら少し遅刻したのにも好感が持った。
さらに遅刻した生徒が後から後から入ってくる。
こう書くと怠惰なだけのようだが、授業中は質問が飛び交う。
私語も飛び交う。その度に先生は笑いながら、静かに、と嗜める。
すっかり気に入ったし、自分の英語力に合っていると思ったので即決。
デイビット先生に謝りに行ったら、気持ち良く送り出してくれた。
初日と二日目のクラスの生徒たちの何人かも「なぜいないんだ?」と
声をかけてくれ、後ろ髪も引かれたけれど、基礎クラスに編入した。
総務の女性には、アツシはいつから英語の勉強を?と改めて訊かれた。
日本では中学生からやるけれど、自分は去年から取り組んだと伝えた。
「なぜ、10代の頃からできなかったのか?」とも言われたので
「日本語を勉強するのに40年かかった」と答えた。
事務室の人たちは爆笑していたけれど、
早朝、こちらは必死に唐さんの日本語と向き合っている。
一方、体調的にはあまりに眠いし、頭も痛いので、
コスタコーヒーのメニューにチョコレートのお菓子を加えた。
ロンドンに来て以来、あまり食事をする気になれないし、
体がスッキリしていくようで悪くないので、あまり食べてこなかった。
しかし、加糖したら、頭がスッキリして2時限目はあっという間だった。
ディスカッションでは、どこでフィッシュ&チップスを食べたら良いか
を話題にした。10日ロンドンにいて、自分はまだ食べていない。
グリニッジ大学近くに数軒ある店の中から一つを勧められた。
明日においしかったか教えてくれ、と言われとなると、
こうなると今日は昼飯を食べる気になる。
JACK THE CHIPPERというお店。
タラを揚げるのに7分かかるというから、お店のおじさんと話し続けた。
パンデミックでぜんぜん観光客が来ないとぼやいていたが、
あなたは良い店を選んだ、推薦した先生の目は確かだと言って、
グリーンピースのペーストを付けてくれた。これが古典的スタイルだ、と。
ホテルに足早に戻って急いで箱を開け、食べる。
噂に聞いていたよりよほど美味しい。タラに鮮度がある。
しかし、味は薄い。日本ほど塩分が濃くないせいもあるけれど、
魚の甘味に乏しい。チップスも美味しいけれど、量が多すぎる。
グリーンピースのペーストは、砂糖と水分を加えればお汁粉のような味。
と、ここからが劇場研修。
Zoomで「HERE NOW US」というプロジェクトの進行確認会議に加わる。
もちろん途中参加だし、英語が厳しいのだけれど、まだらに理解したところに
よると、劇団スペアタイヤの代表レベッカさんを中心に進むこの企画では、
地域の学習障害がある青年たちと美術やインスタレーションを作って
彼らの活性化を図っているそうである。去年から各地でWSを進めてきたけれど、
ずっとコロナとの闘いで、中断やオンラインの活用に苦労しながらやってきた。
そういう内容だった。ディスカッションが始まると、翻訳ソフトも使いながら
ギリギリとそれにしがみつく。映像紹介があるとホッとする。
90分でどっと疲れた。
今日とったメモをもとに、次にエマに会う時、質問攻めにしなければ。
他方、電話で話したミミは体調が悪いらしい。忙しい彼女が心配だ。
さらに、今日はここからが勝負の時。
3月から入居できるかも知れないお宅の内見に行った。
そこは、今いるホテルから歩いて10分ちょっとのところで、
グリニッジ公園の通用門が目と鼻の先にあるお家。
ひとり暮らしのシニア女性が、部屋を貸しているらしい。
近々、現在の借り手が出ていくので、申し込みをすることができた。
早めに行き、教わったアドレス直前で少し迷っていたら、
知り合いだという近所の女性が案内してくれた。
出てきたのは、教養があって、少し厳格そうな女性。
部屋を見せてくれたり、コーヒーをご馳走してくれた。
何か望みは、と言われたので、少しお話ししたいと伝えて、
自分がロンドンに来た目的や、これまでの10日間のこと、
思い描く生活スタイル、家族や唐さん、唐ゼミ☆やKAATでの
仕事について話した。
彼女も、自分の家族や、便利なお店、行くべき文化施設、
大好きだというフットボールチーム、トットナムについて話してくれた。
さっきあなたが行ったフィッシュ&チップスは間違いだ、
この地域でベストなのは THE GOLDEN CHIPPY だ、とも。
あとはエージェントを通してやりとりしましょう、と言い合って失礼した。
ここで暮らせたら願ってもないけれど、どうなるか。
今日は都心に出るには充実し過ぎたので、教わった商店を確認するために
カティサーク〜グリニッジの辺りを歩いて、ホテルに戻った。
先日見つけたジブリ上映中の映画館の他に、この街にはもう一軒、
スクリーンがあることもわかった。
夜はホテルのロビーでメールを打ちまくったり、台本を読んだり、
2/14までの予約を延長した。ずっといるから、受付の人と打ち解けてきた。
もっといろというけれど、さすがに財布がもたない。
就寝は24:00。
翌2/11は唐さん82歳の誕生日、うちの娘も3歳になる。
2022年2月10日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑終演後、こうして場内で写真を撮って良い雰囲気がロンドン流らしい
昨日は『芝居の大学』の最終回だった。
日本の19時スタートは、こちらの10時開始。
だから前日の段階で語学学校には欠席することを伝えて、
早朝からzoomのリハーサルに臨んだ。
3名のゲスト、
桐山知也さん、浅井信好さん、鈴木励滋さんのお話はどれも面白く、
作品表現を追究すること、創作プロセスを全て表現と考えること、
さらに拡げて、日々の暮らしの中に表現を意識し、日常を緩やかに
変えていくことの面白さと可能性について語り合った。
後半には、前回のゲストだった横山義志さん、鈴木伸幸さんも
加わって、それぞれの思うところを述べてくださった。
"表現"を取り巻く何重ものレイヤーと、
それぞれの段階が持つ可能性と課題に触れることができた。
そして、目の前にはロンドンの下町とThe Albany があって
昨日は情報量の多さに圧倒されたけれど、午後から今朝までの
時間を使い、少し頭を整理することができた。
課題は、一直線につながっている。
そのようなわけで、午前は日本とのやり取りでホテルにおり、
午後は午後で、ミミやエマや、Albanyのスタッフが多忙だったので
これまたzoomで話し、ホテルにいた。
これから自分は、エマの担当する
"Here Now Us"というプロジェクトに伴走する。
その土台となる情報共有を、慣れない英語でやっている。
直接会うより、Zoomやメールでの内容理解は格段にくたびれる。
家探しは続いているが、良い物件が候補に上がり、希望を持つ。
2/10(木)の夕方に下見に行けるようエージェントが手配してくれた。
安価だし、すでに住み慣れ、移動に便利なグリニッジ周辺だし、
なんとかこの機会をものにしなければ。
夜は、どうしようか迷ったけれど、
ホテルばかりにいると気がふさぐので、街に出かけた。
小雨の中を電車に乗ってセントラルに出ると、
金田家というラーメン屋を見かけたので、入って食べてみた。
日本で食べるより美味く感じたけれど、会計は2,500円くらい。
外国のものは高級品だ。
それから、ウロウロした後にサウス・バンク・センターに行き、
当日券を買って、ロンドン・フィルハーモニックを聴いた。
指揮者クラウス・テンシュテットのCDの演奏を務めていた楽団だ。
ちょっと疲れていて、ウトウトしながらの鑑賞になってしまったが、
真ん中に演奏された現代曲のヴィオラ協奏曲が面白かった。
2004年に作られた曲らしいけれど、演奏後は作曲家も舞台に上がった。
メインのマーラー1番は、これまで何度も聴いてきたが、
スイングが多く、指揮者の力かオケの特徴か、
それとも今の自分の状態が影響しているのか、
分からないけれど、日本で聴いてきたのとは別モノに感じた。
ノリに乗って、ところどころ雑で、突っ込みが激しい。だから盛り上がる。
楽章間では、第2ヴァイオリン奏者が楽器の不具合で袖に引っ込んでしまい、
なかなか再開できないでいると、お客が笑いだし、ついにはリントゥさんが
「スコアに書いてあるんだよ」と大声でジョークを飛ばして場内が爆笑した。
それもあって終盤はさらに特攻的演奏。
お客さんの入りは6割程度だったが、みんな立ち上がって
掛け声を飛ばしながら盛り上がった。掛け声だ。もうコロナは関係なし。
それにしても、今日は最安席£14=2,500円で聴いたけれど、
とても良い環境に感じた。ラーメンより若干安いって・・・
これからはこういう感じで数を鑑賞していこう。
帰りに、雨が強くなっていて、
そういえばまだ傘を買っていないことを思い出す。
いくつかのスーパーを見て回ったが、日本のように雨だと軒先に
設置して売る様子もなく、どこで買ったら良いか、今だに分からない。
語学学校で訊いてみよう。
それにしても、ロンドンの街にはたくさんのホームレスがいて、
コスタコーヒーの紙コップなどを置いて、寄付を求めている。
何人か、傘をさしながら地べたに座り込んでいる人を見かけたが、
彼らはなぜ屋根のあるところに移動しないのか。
追い出されてしまうからか。あの状態の方がお金が集まるからか。
よく分からない。彼らが傘をどこで手に入れたかも、よく分からない。
帰ってから24:00に寝て、6:00に起きる。
久々に理想的な就寝・起床タイムだ。
2022年2月 9日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑サドラーズ・ウェルズ・シアター。安藤洋子さんが活躍してきた場所。
学校や劇場が二日目の昨日も、面白い一日を過ごした。
午前中の講座は二部制。9:00-11:00まで発音、文法、単語を学ぶ。
30分の休憩をはさんで、11:30-12:30がディスカッションの時間。
完了のニュアンスの違いや、接続詞を学び、すぐに使い始める。
会話の時間には、学校で初めて、少し打ち解けて話す人を得た。
彼女はスペインの方で、大学で数学を教えているのだそう。
担当教官デイビットさんや、総務のマホメットさんと個別に話しができた。
デイビットさんは、かつて船橋で一年を過ごしたらしい。
自分は一度しか行ったことがないので、彼の方が断然詳しいわけだが、
当然、『続ジョン・シルバー』に出てくる船橋ヘルスセンターの話をする。
歴史・哲学・神学を学ぶことを趣味とするマホメットさんは、
自分が舞台の仕事について名刺を渡しながら説明すると、興味を持って
くれた。ロンドンで見るべきものを、どんどん教えてくれるよう依頼。
午後は劇場に行き、昨日よりさらにスタッフの名前と顔を覚えつつ、
ミミが自分の滞在先探しを手伝ってくれた。
彼女が見つけておいてくれたサイトはMixBより良くて、
すぐに入居できる情報をたくさん得ることができたが、いかんせん高価。
月初めには情報が増える傾向にあるので、サイトに網をかけつつ、
2月半ばからは、今より安価で朝食付きのホテルに移動するのが吉、
という判断に至りました。このホテルへの以降手続きを明日に行おう、
そう言ってミミと別れた。
何しろ、彼女は忙しそう。
今年、The Albanyはずっと特別なフェスティバル期間中なので、
いくつもの企画とトラブルを抱えている様子。彼女が同僚とする会話から
"angry"という言葉が何度も聞こえ、家が遠いらしいこともわかったので、
俺は大丈夫だと言って、こちらは次の行動にうつることにした。
ちなみに、今日はAlbanyにあるいくつもの集会室の中で、
一階にある大きめの部屋に地域のシニアの皆さんが集っていた。
KAATでは演劇やダンスを志す人を集め、創作する仕事をしてきたが、
こちらは劇場の規模からしてもより地域密着型で、車椅子の方、
杖をついた方が散見される。当然、人種も入り乱れている。
という様子を見ながら、今日もセントラルに行くことにした。
公演やステージを見る前に、まずは各地に道をつける。
そして、パンフレットやフライヤーをもらうというのが目標だ。
ホテルに帰ると疲れが出てすぐに寝てしまい、夜中に起きる生活が
連続しているので、きっと英語のストレートプレイには耐えられない。
まずは顔見せ、観劇は後日にする。動いていれば、起きていられるし。
少し遅めに帰って23:00-5:00くらいに睡眠時間をもっていきたい。
Albany最寄りのデトフォード駅から国鉄に乗ってロンドンブリッジに着く、
出発時にオイスターカードをタッチし忘れて、駅員さんに補い方を
訊いたら、初めて切符を買って駅を出ることになった。
案内も親切で、ありがたい経験。
そこから地下鉄に乗り換えて、ロイヤル・コート・シアターを目指す。
去年KAATで上演され、今月末に米澤が出演する『ポルノグラフィ』が
初演された劇場だ。若手の育成と発掘に力を入れ、登竜門の一つらしい。
地下にはパブと演劇関係書を扱うさほど大きくない本屋
「サミュエル・フレンチ」がある。現在公演中の演目のチラシをもらい、
受付の女性や書店のおじさんと喋って、次の目的地へ歩く。
明らかな高級住宅、ブランド店が集まるカドガンを抜けて、
立派なケンジントン駅の裏手からハイドパークに入った。
1999年に、さいたま劇術劇場でロイヤル・シェイクスピア・カンパニー
との共同制作『リア王』が上演された時、そのロンドン公演の様子も
撮影されたドキュメンタリーの中で、真田広之さんがランニングして
いたのはこの公園ではなかったか。日本のスターは当然ながら、
良い待遇を受けていたんだなと、土地柄を把握して実感。
公園を抜けてノッティングヒルに至る。
ここには、京都のレコード店「ラ・ヴォーチェ京都」の御店主に
教えてもらった「Classical Music Exchange」がある。
(ロンドンのディスクユニオンみたいな感じ)
御店主に挨拶して、日本から来た、この店を教わって来たと
伝えると、地下のクラシックコーナーは改装中だと言われた。
仕方ない。一階の商品の中から気になるジャンルを物色していると、
特別に地下を開けてくれて、さっそくレアものを発見。
日本だと滅多になく、ネットでは5,000〜10,000円するCDを2枚
それぞれ3ポンドずつで譲ってくれた。
また来ます、と伝えて地下鉄へ。
ノッティングヒル駅からセントポール・カテドラル駅に行き、
そこからの乗り換えがよく分からない。何故か訊けそうな人もいない。
そこで次なる目的地であるアルメイダ劇場まで歩き出した。
夜のオフィス街と静かな住宅街を抜けて、エンジェル地区に到着。
アルメイダでもフライヤーをもらった。この道すがら2ペニーを拾う。
お金を使うばかりの英国で得た初収入だ。
同時に、看板で名前を発見したので、さいたまゴールド祭のために来日し、
安藤洋子さんもイギリス公演の党打ち会場にしていたという
サドラーズ・ウェルズ・シアターにも行った。
途中、とんこつラーメンの金田屋、ユニクロ、無印良品を発見した。
帰りは、どうもバスの方が良いようなので、ここで渡英初めてバスに乗車。
ロンドンブリッジ駅から、直通でグリニッジ駅に行く電車を見定めて、
今日はストレートに帰ってくることができた。
電車を待つ時間が25分近くまったので、駅構内のお店でサンドイッチを
買ったが、レジに並んでいるお客を目掛けて、一人一人に懇願している
中年男性がいる。どうからお金が無くて一番安いピザのピースを
リクエストしているようだ。私は英語が分かりません、と伝えたら
次の人に行ってしまったが。彼はどうやって改札を通ったのだろうか?
電車賃はあるけど、食べるものを買うお金はないのだろうか?
不思議に思いながら、21:30頃にホテルに帰り。
歩き続けて20㎞以上、疲れて22:00には寝る。
3:00に起きて、これを書いています。
今日はこれから、講座『芝居の大学』の最終回!
↓英語の担当教員・デイビット先生
2022年2月 8日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑帰り際のミミ。彼女は7分後に出発する電車に乗らなければならない。
昨日から全てが始まった。
1/31にロンドンに来てからはあくまで肩慣らし、
時差を克服して生活リズムを整え、周辺の環境を知ることに注力してきた。
そして、いよいよ第二週から劇場研修と語学学校と、
自分がロンドンに来た主目的がスタートした。
正確に言うと、研修先のThe Albanyには前日2/6(日)に初めて入った。
『The Dark』という子ども向けのプログラムを上演するとHPで見たので
ミミさんにリクエストすると、招待してくれたのだ。
が、昨日はミミさんも、劇場のトップであるギャビン・バロウさんも
いないとのこと。日本だと「今日はアツシが初めて来るから」と
特別に出張ることもありそうだが、きっと休日に対する意識や就業体制が
しっかりしているんだな、と推察しながら劇場を訪ねた。
演目は巡回しているものをThe Albanyが受け入れたもので(買い取り?)、
この劇場のオリジナルではなかったけれど、演者は流れるように喋り、
歌い、踊り、パントマイムし、客席の子どもたちと即興で対話していた。
暗闇を怖がるというのが万国共通の子どもの習性だが、
少年に扮した俳優を、"闇"を演じる女優さんが脅かしながら劇が始まり、
やがて最後には友情を結ぶ。女優さんは電子ピアノやエレキギターも
演奏したりして、とにかく万能。
スタッフ(おそらく2名ほど)や美術も含めて、
ハイエース1台に乗る量の、とにかく洗練された1時間弱の劇だった。
実は、面白かった一方で、不安にもかられた。
それは、劇場空間そのものがとても小ぶりで、はっきり言えば
チープな感じがしたからだ。例えば、KAATの大スタジオや
世田谷のトラムなどの方が大きいくらいのサイズ。
設備は比べるまでもない。まあ、自分はテント演劇の徒なのだから、
これが向いていると自分を鼓舞する一方で、11ヶ月間研修する場所として
不安を覚えなかったと言ったら嘘になる。
と、ここまで読んで気づかれたと思うが、
さらに正直に言うならば、自分がここに実際に来るのは初めてなのだ。
我ながら、これはあまり良いことではない。研修先というものは、
やはり実地に目で見て選ぶのが本道だと思う。けれども、
自分は、いつかさいたま芸術劇場で聴いた劇場主ギャビンさんの講演と
伝え知る情報によってこの場所を選んだし、研修への応募を本格的に
思案した2020年の初頭は、パンデミックの始まりでもあったから、
渡英など考えられない状況だった。だから賭けをした。
賭けをして自信がずっとあったけれど、それは訪問初日で少し揺らいで
ホテルに戻った自分を少しナーバスにしたというのが、偽らざるところ。
果たして、初日。
すべてが始まったと冒頭に書いたのは、今日が語学学校の初日でも
あったからだ。すでに週末に確認済みなので、自信満々に学校までの
道を往き、建物の2階に入った。
事務局のあいさつしたら、9:00まで待っていてと言われる。
その間に、PCとケータイのWi-Fiを登録し、朝だけでは足りなかった
『秘密の花園』の研究時間を補った。
9:00になると、今日が初日の生徒を集めてイントロダクションがあり、
学校について、ロンドンでの生活について、細かな説明があった。
説明してくれた男性はマホメッドさんといって、
僕の趣味は、哲学・歴史・神学を学ぶことだと言っていた。
さすが、ムスリムの預言者の名を冠する男だと思った。
初めの2時間は各種登録作業や英語力を測るためのテストで
瞬く間に過ぎ、英語を学ぶ簡単な個別面談を経て、授業へと案内された。
と言っても、この時間は座学ではなく、いきなり各チームに別れて
先生が課したお題で話すというもの。自分が参加を命じられた
女子3人チームの関係性や話題はすでに流れに乗っており、
しかも彼らがイタリアやドイツから来たティーンだったので、難儀した。
「ア・ツシ?」「ジャパン?」「スシを思い出すわ」
「もうお昼だからお腹すいた」そんな感じだった。
こわばった1時間は異様に長く感じた。
事務局に、初日は難しかった、また明日!と大声で伝えて学校を後に。
ホテルに一旦戻り、荷物や身支度をし直して、劇場に向う。
ちなみに、ホテル〜学校は徒歩25分、ホテル〜劇場は15分。
15時少し前にThe Albanyに着くと、
受付の男性(トム)がセキュリティを解除してくれて、案内された。
カフェに、ミミとヴィッキーが打ち合わせしながら待ってくれていた。
Zoomで会ってきた彼らと、やっと初対面。
皆、自分にも分かりやすく話してくれた。
日本茶と両口屋是清の二人静というお菓子をプレゼントした。
足柄(神奈川)と名古屋である。特にミミには、1/3に広隆寺で入手した
弥勒菩薩のポストカードを渡して、自分の変な英語と付き合い続けて
くれているお礼をした。
そのうち、エマというスタッフの女の子も加わって、重鎮ヴィッキーの
長広舌が始まった。このあと年末まで、この劇場を拠点に周辺一帯の
ルイシャム地区を巻き込んで行う様々なプロジェクトについて
説明してくれた。これは聴き取るのにさすがに苦労したが、
①地域の人々から集めたエピソードを音楽化する企画
②伝統から最新流行までを網羅したダンス企画
③LGBT問題に取り組む企画
④貧困の問題に取り組む企画
があると理解できた。全体のアテンドをミミが行ってくれ、
まずはエマの担当する企画にくっついて動くべしと言われた。
説明の全ては理解できないけれど、一緒に動きながら理解していくだろう
と伝えて、ヴィッキーにお礼を行った。
それから、オフィスに案内された。
スタッフの誰も彼もが女性。ハーレムのようだと伝えると、
ミミは笑いながら、うちは女性23人、男性は4人、アツシで5人目と言う。
KAATも女性が支えている。世界的な傾向なのだろうか。
ちなみに、デスクは全てシェアするシステムで、日ごとに予約して
押さえるのだそうだ。だから全てのデスクはキレイで、
1日の終わりにはそれぞれが自分の痕跡を消して帰る。
役割によってだいたいの定位置が決まっている感じもしたが、
原則はシェア&予約制で、代表のギャビンはだいたい家で仕事しているそう。
ここにきて、ギャビンは腹痛により今日は来られないことも分かった。
それから、新しいメールアドレスをもらった。
これで劇場のメーリングリストに加わるということだ。
ただし、ログインの仕方が分からず四苦八苦していると、
明後日にセリという総務担当の女性が詳しく指南してくれると教わる。
いずれにせよ、生まれて初めて末尾が「.UK」のアドレスを入手。
さらに施設案内を受けたが、これが良かった。
この劇場には昨日見た小さなホールの他に、三つの会議・稽古スペースと
数多くのオフィスがあり、さらに広い庭もあった。
「うちには今、26のレジデントカンパニーがある」とミミが言った。
しかも、たまたま今日はカフェミーティングの日で、フェスティバルに備えて
創作中のアーティストたちがカフェに大勢集まってきて、賑やかになった。
ここにきて、昨日の印象は完全にくつがえった。
The Albanyを日本と同じ感覚で単なる劇場と捉えてはいけないのだ。
ここは"拠点"であって、多くの人が出入りしているその規模は、
KAATなどを遥かに凌ぐ。この劇場の小さなホールも公演会場だが、
発表の場はそれだけではない、劇場前の広場も、街のそこここも、
巨大な会場なのだ。このことを実感して、完全に安心した。
自分の選択は間違っていなかったと思った。
創作の基地だとすると、とてもデカい基地なのだ。
安心して、改めて年末までを過ごすことができる。
昨日の感慨を、皆さんに謝りたいような気持ちになった。
夕方を過ぎると、近所のパブに連れていってもらい、
気の向いた何人かがアフター5を過ごす輪に加えてもらった。
「アツシは初日だから」と、ミミとキャロリンという女性音楽家が
一杯ずつジンジャーエールをおごってくれた。
皆、食べずに飲んでいる。飲んで、たくさん話している。
キャロリンの相棒らしきアナという女の子、ロミカという女性とも
たくさん喋った。ここ1週間、自分がロンドンに着いて経験した
トラブルの数々は、皆を愉しませることができたようだ。
喋るのは簡単だ、ブロークンでもなんでも、自分が何を言っているかは
当然ながらよくわかる。問題は聴く力。早く、皆の話を詳しく正確に
聴き分けられる英語力を身につけたいと思った。
19:30過ぎにミミが帰るというので、自分も店を後にした。
彼女の家は遠いらしい。それを知って、なおさら頭が下がった。
明日は13:30に合流して、ランチをともにし、家探しを手伝ってくれる
という。ミミが菩薩に見える。
20:00頃にホテルに戻ったが、当然ながら英語ばっかりの初日に
疲れて、すぐ寝てしまう。夜中に起きて、これを書きました。
↓デスクをシェアするシステムなので、いきなり自分もデスクで仕事できる
2022年2月 4日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑グリニッジの王立天文台
睡眠時間が夜にまとまらないために、常に軽い頭痛。
しかし、早朝に起きて『秘密の花園』にあたり、英語の勉強もする。
『秘密の花園』は1幕の終わりに差し掛かり、大学一年の秋に観た
紅テントでの上演から、堀本さんや飯塚さんの声が聴こえてくる。
堀本能礼さんは唐組を辞めた後、
オルガンヴィトーの『黄金バット』に出演されているのを拝見した。
飛んだり跳ねたり、体当たりの演技で、あの美声が健在だったし、
あの公演には飯塚燈子さんも出ていた。
自然と色々な記憶が蘇るペアだった。
その後、堀本さんは2017年に46歳で亡くなってしまった。
自分が唐さんに親しく教わるようになっていったのが2001年頃、
丁度その頃に退団された堀本さんとのやりとりは殆ど無かったけれど、
唐十郎ゼミナール一期生の先輩たちは、音響操作の助っ人として
関わったはずだ。
『24時53分「塔の下」行きは竹早町の駄菓子屋の前で待っている』の
上演に、おそらく唐さんに請われてやってきていた。
音の強弱によって身をくねらせながらオペレーションする堀本さん。
演じるような、ダイナミックな仕草が狭い客席の隅で光っていた。
それらを終えたら、近所の中華街で坦々麺(想像と別モノだったけど)を
食べて、週明けから通う語学学校の場所を確認しに行った。
道すがら、国立海事博物館やクイーンズハウスを見かけたので、
帰りに寄ってみた。皆、無料で入れる。満喫した後、天文台にも行く。
帰りには、スーパーでオレンジジュースや水(最重要!)、
寒いのでカップスープの素を探して買った。
これで部屋で温かいものを体に入れることができる。
辛ラーメンのカップ版も見つけたが、お箸がないので見送った。
さらに、スーパーの外のATMに、利用者も物乞いもいない場所を発見。
これはと思い、何度かのトライの後についにお金をおろすことに
成功した。やれやれ。徐々に生活に慣れてきた。
と、思った矢先、
送られてきたエージェントによる生活の手引きには、
野外のATMは危険だから使うなと書いてある。
背中にリュックを背負って歩くのも、
音楽を聴きながら移動するもの避けるべし、とある。
どれくらい真剣に受け止めれば良いのだろうか悩みつつ、
バスの乗り方などは参考になった。
週明けには、ミミさんはじめThe Albanyの人たちに会える。
今は何を危険に思い、何に安心したら良いか掴めず疑心暗鬼だが、
彼らに会えば、ある程度ここでの常識や習慣がわかる。
オススメの店や買い物先も教えてくれるという。
歓迎会的にレストランに連れて行ってもくれるそうだ。
今日は身辺整理に終始したので、そろそろ初めて観劇に行きたい。
↓まいばすけっと的スーパー「セインズベリー」左端にATMがある
2022年2月 3日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑ピカデリー・シアターにて。偉大なり、中根公夫!
一晩が経ち、さまざまなメールやZoomのやりとりを経て、
どうやら昨日に椎野に来たメールは、一度目の間違ったフォーム入力が
原因だったことがわかってきた。ということで、割と自由らしい。
一方で、相変わらず生活基盤が整ったとは言い難いので、
自分が何を不安に思っているか、書き出して整理してみた。
①2/14(月)以降の住居が決まっていない
②デビットカードでお金をおろせることを確認していない
③語学学校のオリエンテーションの日時変更が必要(2/7実施の予定)
④語学学校への道を確認しておかなければならない
⑤コインランドリーの位置を含む、洗濯の仕方がわからない
⑥グリニッジにいるのに以外と忙しく、天文台に行っていない
以上である。
①については、ネットで物色しつつ、2/7のミミさんとの接触を待った方が
良さそうだ。交通や治安についての助言がいる。だから一旦放っておく。
②昨夜、スーパーの前にATMらしきものがあったが、英語に自信がないので
ぜひ他に利用者がいない時にトライしたい。しかも、そのATMの前には、
物乞いの女性が陣取っていて、話しかけてきたり、お祈りの言葉を始終
ブツブツやっているのだ。あれは怖い。
③これはメールを打ち、返事待ち。
④散歩がてら解決しよう。
⑤友人のYさんにLINE電話したら、風呂で石鹸で洗えとアドバイスを受けた。
合理的だ。とりあえずホテルのシャワーとボティソープでゴシゴシやる。
イギリスは乾燥しており、乾くのが早そう。
⑥ ④とともに早々に行くべし。
・・・というように、まだまだ生活基盤が整っているとは言い難いが、
こんな「受け」にばかり終始していると気がふさぐので、ここは一度
セントラルを攻めてみることにした。
初日は何しろ余裕が無かったし、日没しかけのロンドンを移動した。
が、今日は荷物も軽いし、余裕がある。外の景色を見ながら、目に入る
文字を片っぱしから電子辞書に入力しながら都心部を目指す。
果たして、Forylesという本屋に行って品揃えを見る。
舞台については照明やメイクの本まで充実しており、
DVDやCDのコーナーもあった。Jordi SavallのCDが潤沢で安い。
日本語の本のコーナーもあったが、520円の新潮文庫に13ポンドの
シールが貼ってあった。暴利を感じる。
『ハリー・ポッター』のパレス・シアターを通り、
ラーメン一風堂を発見しながら、ロイヤル・オペラ・ハウスを確認。
ラインナップを観て、今日がヘンデルの『Theodora』初日だと知る。
日本では希少かつ来日公演も乏しいバロック・オペラを観るのも
今回の目標の一つ。今日は夕方にZoom会議なので出直そうと誓う。
ピカデリー・サーカスにも行ってみた。
中根公夫さんが1990年代に格闘したピカデリー・シアターを見る。
中根さんはここで清水邦夫さんの『Tango at the end of Winter』
ロングランを行い、チケット会社の倒産という憂き目と闘ったのだ。
中根さんの挑戦の大きさを、改めて実感する。
他にも目に飛び込んでくるものはいくつもあったが、
会議に備えて余裕を持って引き上げる。Greenwich st.直前の車中で
電車の不具合があり、途中の駅で降ろされたりした。
日本では人身事故だが、こちらでは車両の不具合・・・。
いずれにせよ、慣れないうちは関わる人たちの信頼を得るために
余裕を持って行動しよう。ホテルに戻ってミミさんとZoomで話したら、
安心して急激に眠くなった。
時差ボケと食糧難、初めての街や英語での会話......
どれが決定打なのか自分でも分からないけれど、無意識な消耗を感じる。
一方、ロイヤル・オペラをきっかけに観劇の計画を練り始めたが、
豪華プログラムが、しかも安い。
チケットの予約入力に不安があるし突発的な予定が入る可能性があるので、
しばらく当日券で飛び込んでみよう。Covid-19の影響で空席は多そうだ。
攻防一体の一日。
↓高額の値がついた日本書籍
2022年2月 2日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note
ロンドンに着いたばかりの昨日は、夕方に一度寝てしまった。
で、夜中に起きた。
起きて、水が尽きようとしているのに気づいた。
思えばこれは飛行機内でもらったペットボトル。
いまやコップ一杯分もない。これはまずい。
そう思ってホテルの外に出た。
ところが、駅前にも関わらず店がない。自販機もない。
仕方ないので、戻って昨日のゼミログを書く。
Facebookに記事を上げたらエールがたくさん来て嬉しい。
が、水を手に入れるのに四苦八苦しているこの研修が、
果たしてどこまで行き着けるのか、不安。
本格的に寝たのは深夜で、しかし、早朝に目覚めた。
やっぱり喉が渇くので、ホテルの受付にいた女性に質問した。
すると彼女はカウンターの裏に自動販売機があるのを
教えてくれた。ところが、である。
ホテルの自販機の水は500mlで2ポンド(約320円)もする上に、
硬貨でしか買い物ができない。
イギリスはカードで何でも買える。そう言われていたが.....。
手もとのコインを結集させてもに2ポンド分に及ばず。
見かねた女性は、でかい紙コップに食堂のウォーターサーバーから
並々と水をくれた。これで当座が凌げる。
それから、抗原検査をして陰性の結果を四苦八苦しながら入力。
英国政府のフォームは優しくない。最近に様々つくった登録情報を
次々に入れる必要があるが、どれがどれやら混乱。
何とか送信して、いつものルーティンに入る。
台本を読み、英語を勉強し、メールをチェックする。
そうこうするうちに政府から返信が来た。
どうやら、これで動いて良いらしい。
2kmほど歩いてルイシャムという地区の郵便局を目指した。
ここに自分のビザのカードがあるのだ。
道すがら、ケバブと水を手に入れることができた。
安い買い物なので、やはりカードは使えない。
道の渡り方、横断歩道の位置がわかりくいので、
周囲を見回して人々のを真似した。
郵便局は混んでおり対応もゆっくりだ。
ようやく自分の番がきてパスポートを見せ、ビザを取りにきたと
伝える。受付の人は初めピンとこなかったが、自分のカードが
あるはずだと伝えると裏に入っていった。
果たして、BRPカード(生体認証付滞在許可カード)が手に入った。
ちゃんと年末までいて良いとの記載に胸を撫で下ろす。
気分を良くして、今度はThe Albany Theatreに向けて歩き出す。
実は出発前の自分は、数日間はホテルにいなければならないと
思っていたが、直前にそうではないと知った。
アテンドしてくれているミミさんにはそれを伝えられずに
来てしまったので、いっそ直接に訪ねてみようと思ったのだ。
劇場に近づくについて、商店街が広がる。
アジア系やアフリカ系のお店と人々が入り乱れて、
なかなかにハードな場所を研修先に選んだものだと改めて思った。
ところが、Albanyのそばにやってきたところで引き返すことになった。
日本の椎野のもとに、英国政府からのショートメールが入り、
アツシは8日間の隔離と2度目の検査が必要だ、というのだ。
しかも、ちゃんとホテルにいるか場合により連絡する、とも。
ひょっとして劇場に迷惑をかけてはいけないので、
急いでホテルに帰る。この時、歩いて15分の距離だと知った。近い。
部屋に帰って冷静に考えてみると、羽田で入国のためのフォームに
誤りを指摘され、やり直したのを思い出した、椎野への連絡は、
一度目の間違った申請に対するものではないか。
そんな風に考えながら、とりあえず現状をミミさんにメール。
明日の午後にzoomで話そうということになった。
そして、疲れたので少し寝た。19:00くらいに起き出して、
スーパーを探し始める。今朝、自分は駅の南側を歩いて
何もないと思ったが、どうやら北に行けば繁華街があるらしい。
行ってみると、確かに繁華街があった。
スーパーもカフェもレストランも、たくさんあった。
紅茶輸送船として活躍したカティサークや本屋、映画館もあった。
昨日は湘南モノレール沿いと書いたが、やはりここはロンドンだった。
水不足の恐怖から逃れるため、合計3リットル買ってしまう。
2リットル0.5ポンドのスコットランドの軟水が美味しい。
映画館では来週からジブリ特集が始まる。第一弾は『PONYO』。
今日動いたゾーンでは、マスクの人は半分以下。
殆どがはずして動いている。ダースベーダーみたいな男女が一組だけいた。
2022年2月 1日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note ↑部屋は簡素かつ広め。合理的で悪くない。
ちゃんと熱いシャワーが出る!
現在、イギリスの時間で2/1(火)の0:24。
こちらの夜中に起きてしまったので、これを書き始めた。
昨日の午後にロンドンに着いた。
飛行機内での12時間は充実して過ぎた。
本をいくつも読み、映画も観た。
途中ウトウトしたけれど、本格的には眠れない。
興奮しているし、外の景色も面白くて目を丸くし続けた。
ロシアの大地だ。
200人以上を収容する飛行機の中で乗客は30人ほど。VIP待遇。
CAさんとお話ししたら、新国立演劇研修所にいたことがあるらしい。
自己紹介をしたら、帰りにプレゼントを頂いた。
ヒースローにつくと、まずSIMカードを買った。
どれも日本のケータイ会社より安い。
ネットがたくさん使えて、電話とメールは無制限。
そういうものが安く手に入った。大事なのは英国での電話番号を
取得できること、イギリスの人はLINEをしない。
WhatsAppというアプリを使って、これがLINE的機能を果たす。
違いは、これが電話番号に紐付いていることで、だから番号も必要なのだ。
次いで、オイスターカードに課金した。
これはSuicaやPASMOみたいなもので、渡英する知り合いが
花向けにプレゼントしてくれた。ここにクレジットカードでチャージする。
チャージの仕方も、電車の乗り方も、
ぜんぶ分からないので、いちいち聞きながらひとつひとつ行った。
対応は丁寧で、何より、まだ陽が高いので希望が持てる。
地下鉄は狭く、ボロっちく感じた。
身体の大きな人が多い割に、日本より窮屈で室内灯が点滅する。
日本にいるときに、
リュックを背中に背負ったり、イヤホンを付けて歩くのは
防犯上よくないと言われてきた。
けれど、地元の人は平気でこの二つをこなしている。
早くこんな風になりたい。
自分の宿は時計台で有名なグリニッジにあり、
郊外にある空港から都心を経て、また郊外に来たという感じ。
着く頃に日没したせいもあり、駅前は殺伐として寂しい。
それにパッと眺めてお店が見当たらない。
大船駅から湘南モノレールに乗って数駅いったところ。
そんな風景を思い出した。
ホテルの受付ではハードルが3つあり、
支払いのこと、注文しておいた抗原検査キットのこと、
Wi-Fiのこと、これらを質問してクリアしなければならないが、
混み合う時間だったせいもあり、フロントの女性はイラついていた。
とりあえず一つ目だけ手続きして部屋に入ったあと、
着替えを済ませ、頃合いをみてもう一度行った。
こちらは自然と大袈裟にお願いしたり、解決すると大感謝してしまう。
すると、相手も笑いはじめて人間的な対応になった。
と、ここまできて猛烈な睡魔に襲われて寝た。
明日の第一目標は、コンビニかスーパーを見つけて買い物をすることだ。
飛行機の中で食べまくったせいでお腹は空かず、今のところは
機内でもらったペットボトルの水で充分だ。
日の出とともにウロウロしてみよう。
そしたら、街が少しは自分のものになるはず。
↓飛行機内で頂いたプレゼント。ありがたい。
2022年1月31日 Posted in
2022イギリス戦記 Posted in
中野note 今日から渡英します。
今これを書いているのは、出発前の5:04。
このあと、8:00には家を出て、津内口や椎野が送ってくれる車で
羽田空港に行き、11:30の便でイギリスに向かいます。
初めて一人で、国際便に乗ります。
初めてヨーロッパに行きます。当然、イギリスも初めて。
空港に着いたら保険に入ろう、とか、円をポンドに換えようとか、
やるべきことがいっぱいあって、ひとつひとつクリアしなければ
ならないことを数えています。実に不慣れ。
自分は、一度行った場所にはフットワーク軽く何度も通うのですが、
行ったことのない場所に対してはかなり出不精です。
何か、大学受験の時にたいそう緊張して新幹線に乗った時のことを
思い出します。一年経ったら、すべてが何でもなくなって
ホイホイとヨーロッパに行くようになる。
そのための研修でもあります。
しかし、このところはやはりドキドキしてきました。
牛乳を買うときなど「あ、賞味期限が2月に入っている」
タワーレコードの新譜情報を観て「発売は2月か・・・」
Amazonを見ていても「オレがいるうちに届かない・・・」
とこんな具合に、迫り来る今日を実感して来ました。
一方、なるべくいつものペースを崩したくないので、
今朝は4:00には起きて、台本を読み、これから走ってから行きます。
読んでいる台本は『秘密の花園』。唐さんがニューヨークに滞在中、
ホテルにカンヅメになって書いたそうですから、今の自分に
向いているように思いました。
私が大学に入った年の秋に、
唐組が素晴らしい上演をした演目でもあります。
曙橋のフジテレビ跡地で観ました。霧雨の降る高台で見た
新宿や池袋を臨む夜景は今も忘れません。
まだ唐さんを身近に感じる以前のことです。
今年の秋に唐組が上演するそうですが、これも観られない・・・
というわけで、長い長い今日が始まります。
時差がありますので、自分の1月31日は24+9=33時間ある。
ヘトヘトになるのではないかと思い、先にこれを書いておきました。
昨日の米澤の投稿を読んでもらいたいので、アップは夜にします。
それでは、「イギリス戦記」始まります。
現在位置は、
ホーム >
ゼミログ >
中野note >
2022イギリス戦記
です。