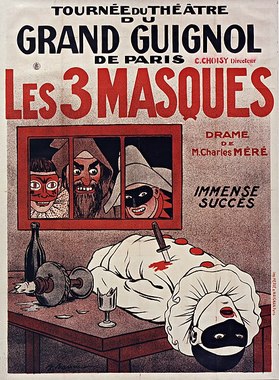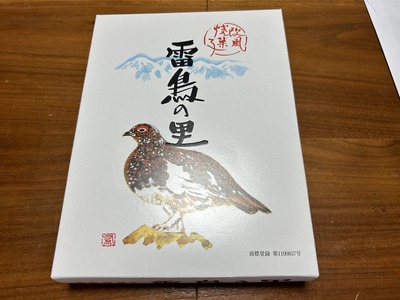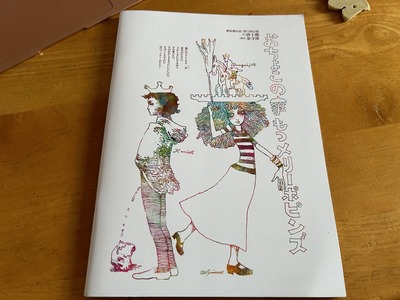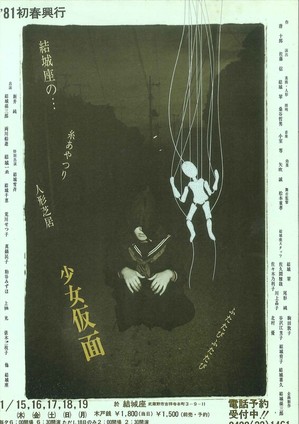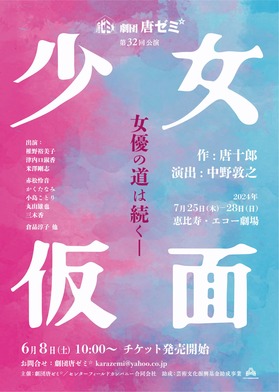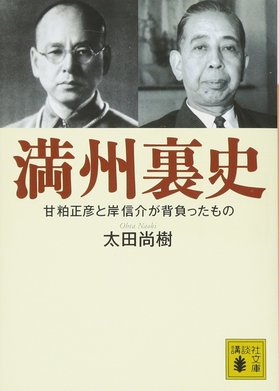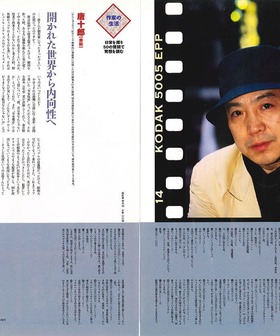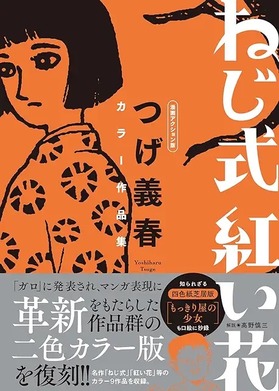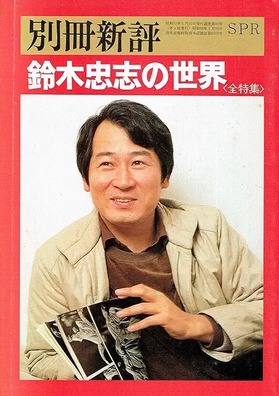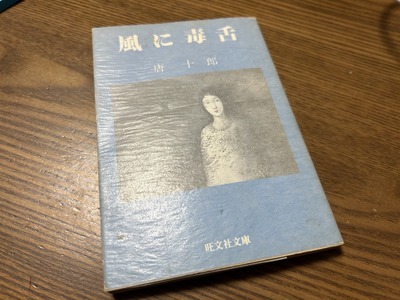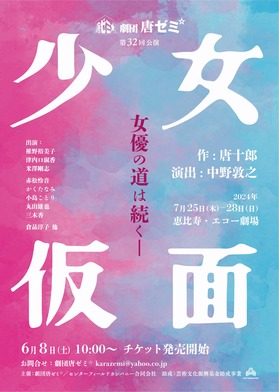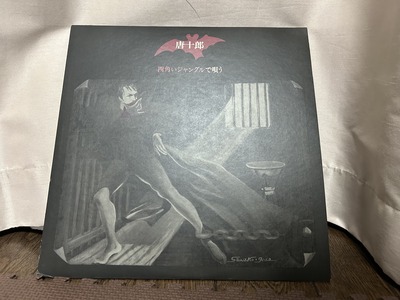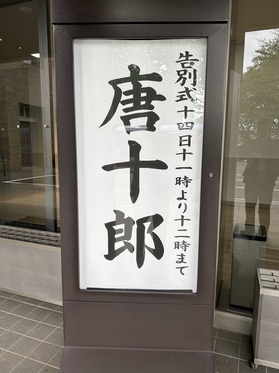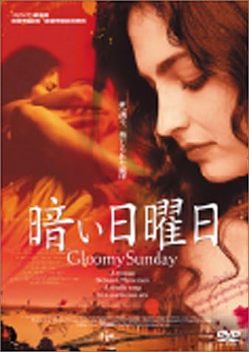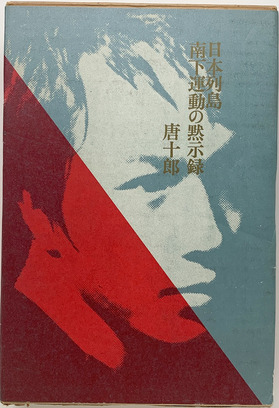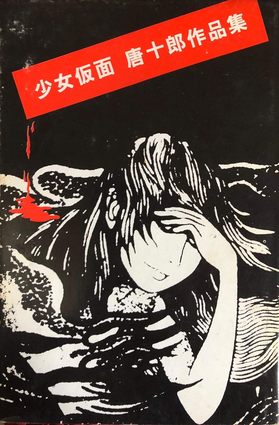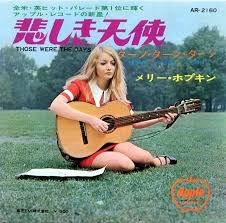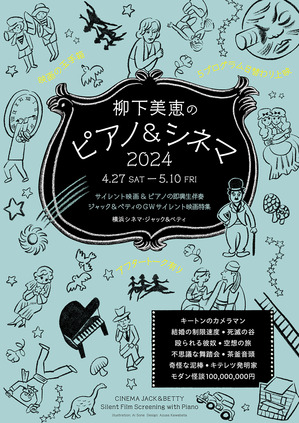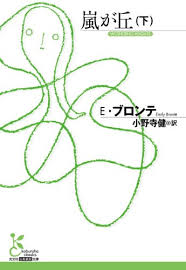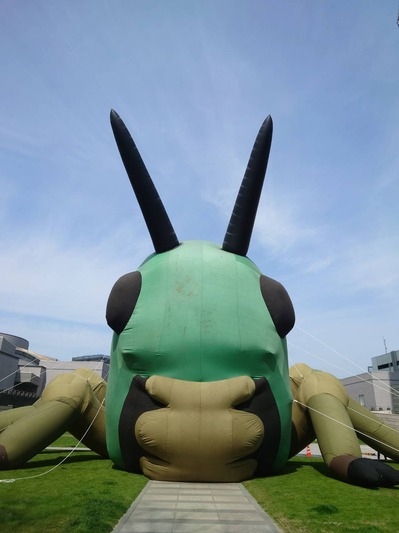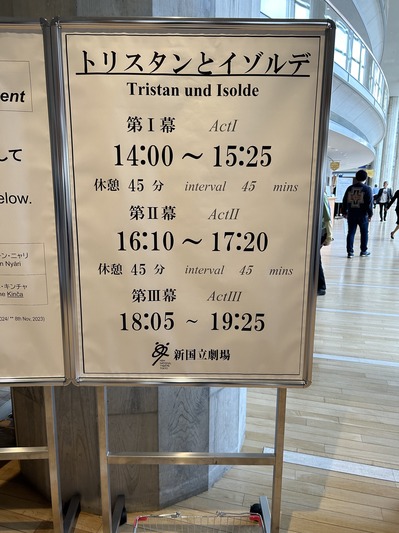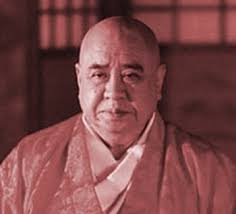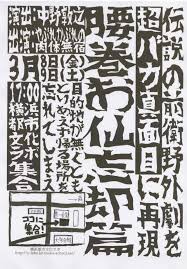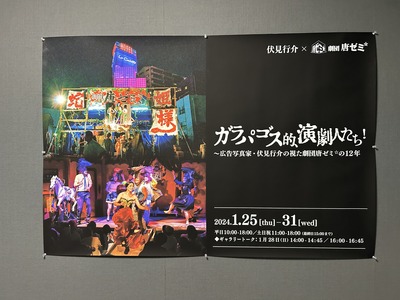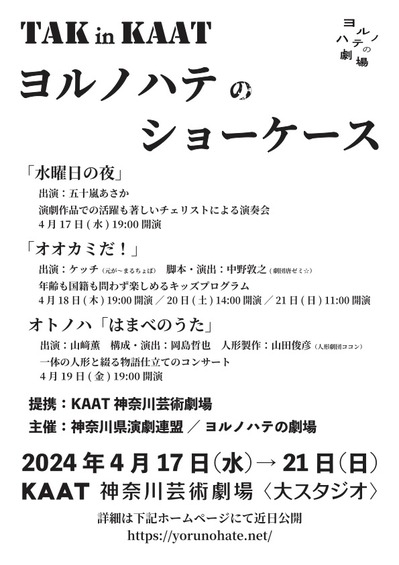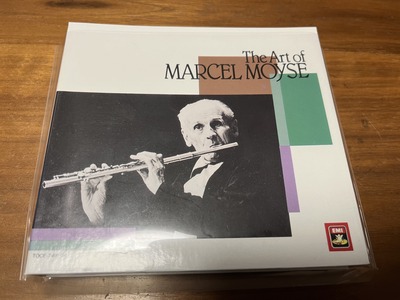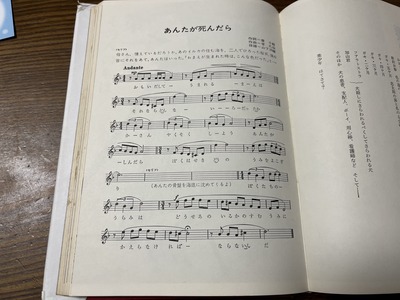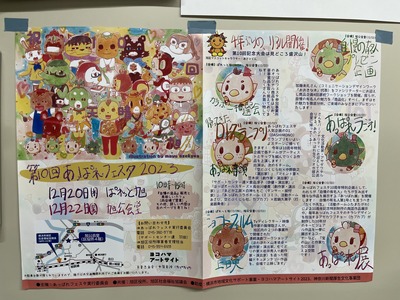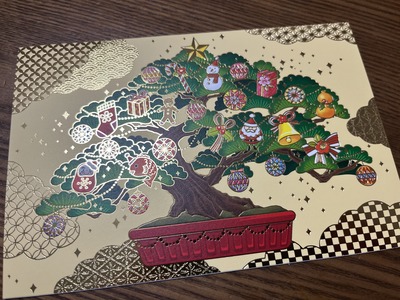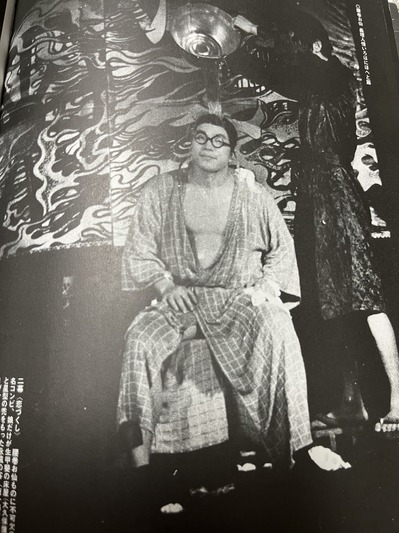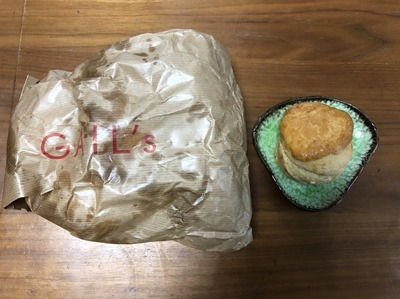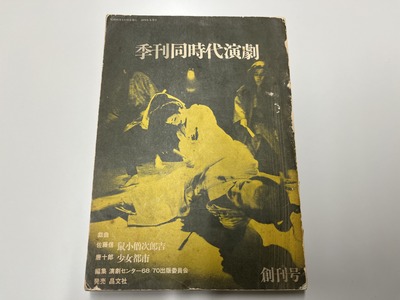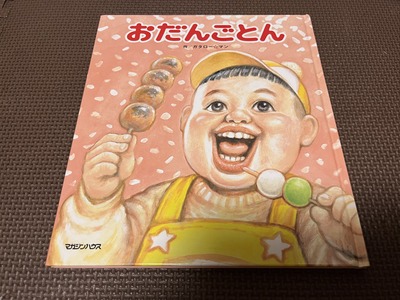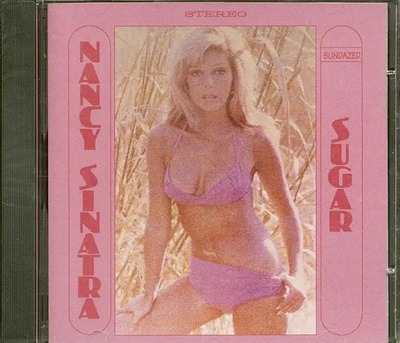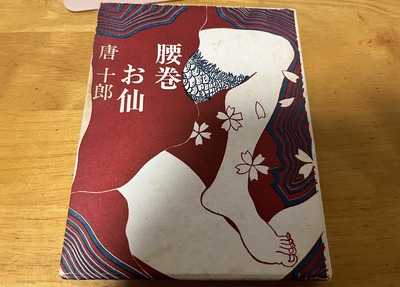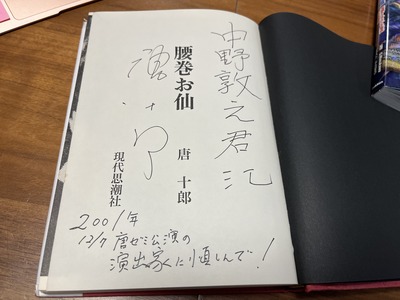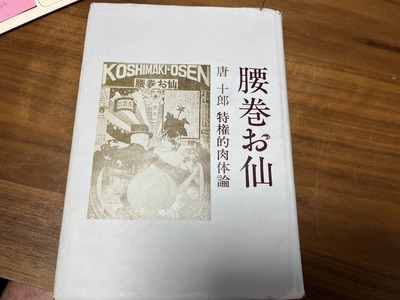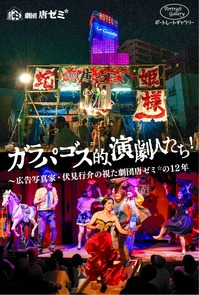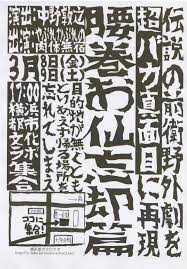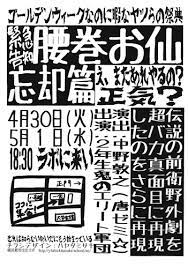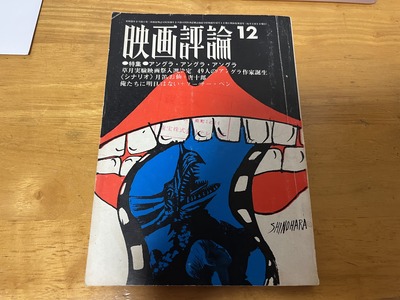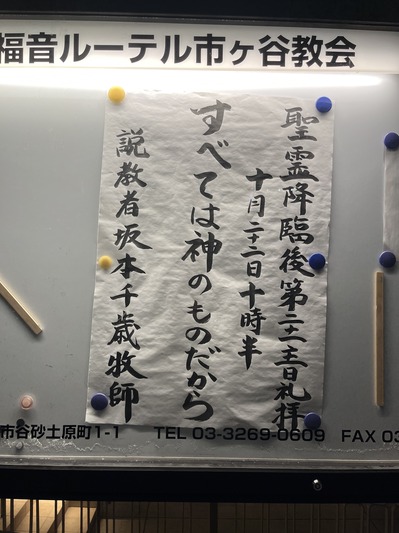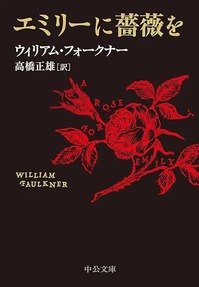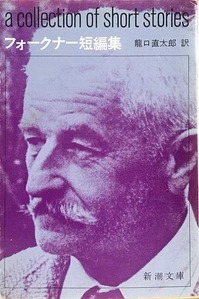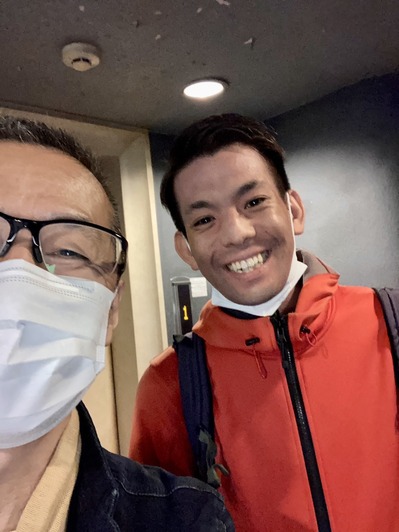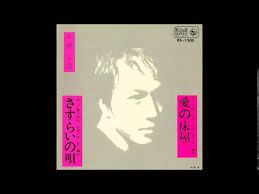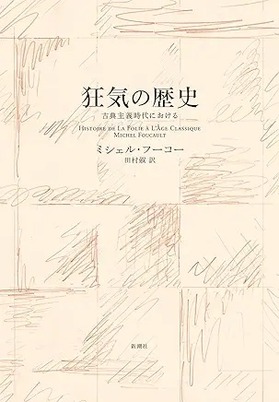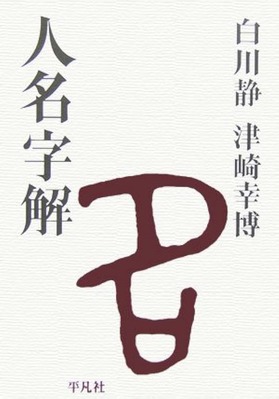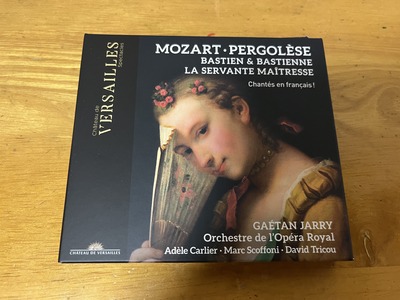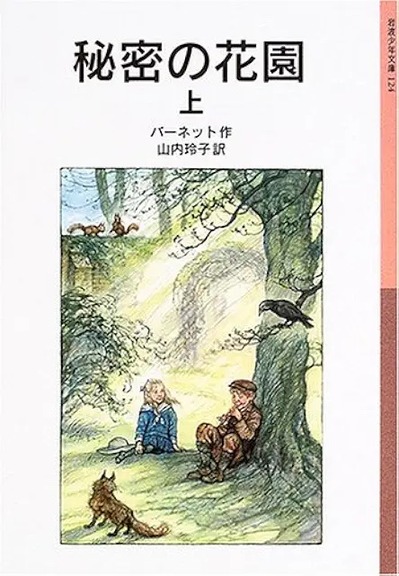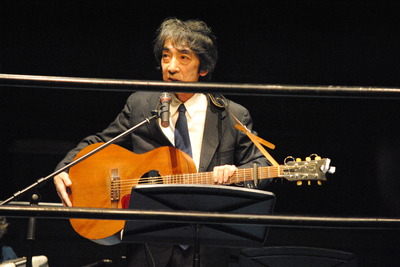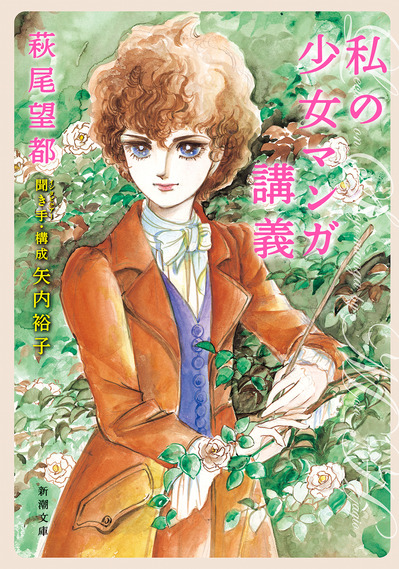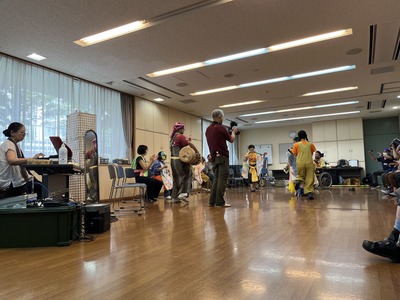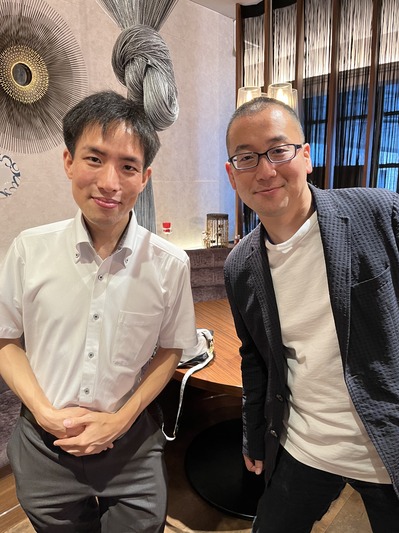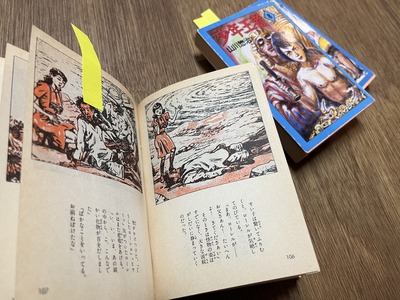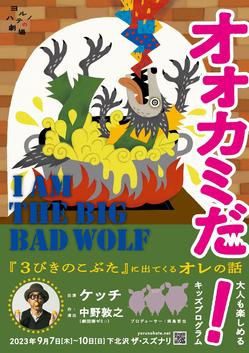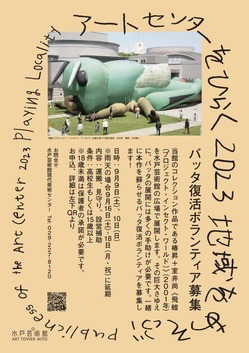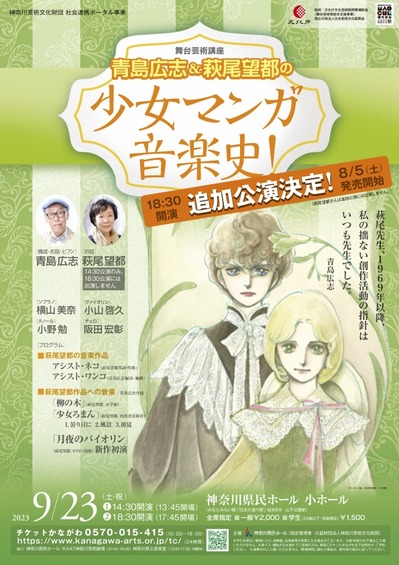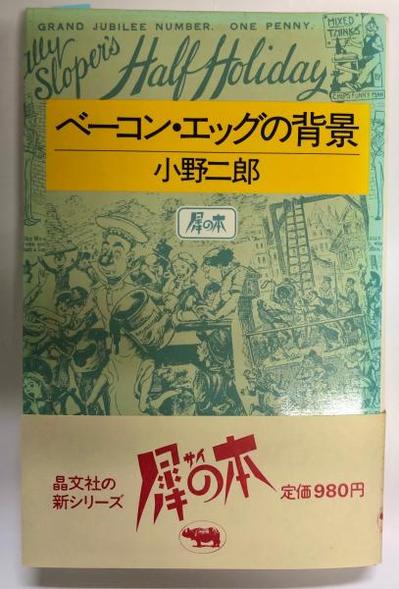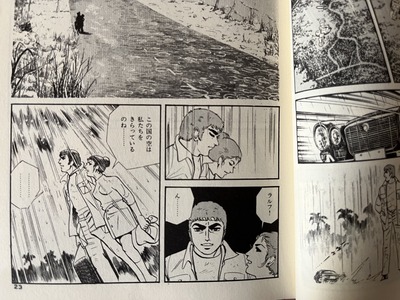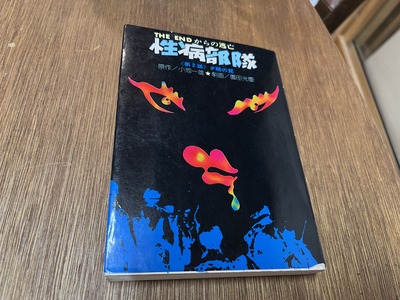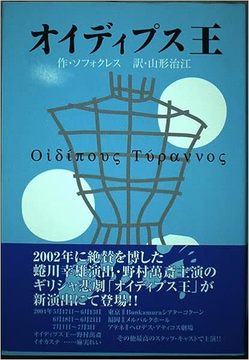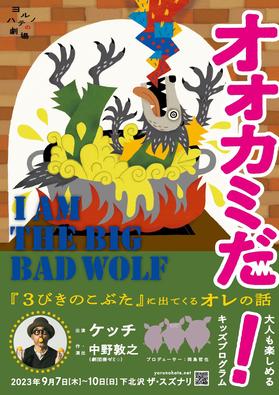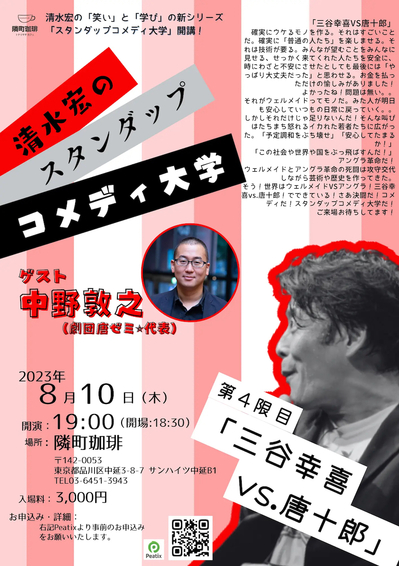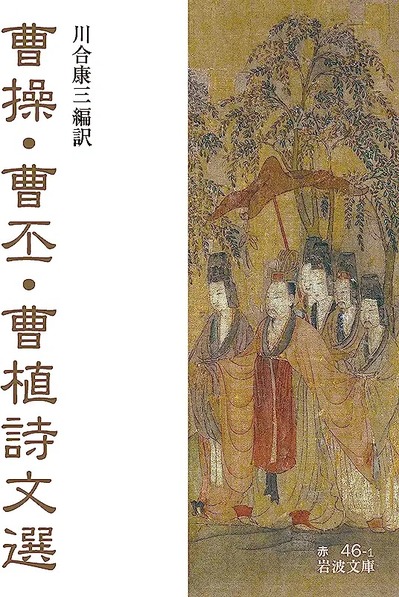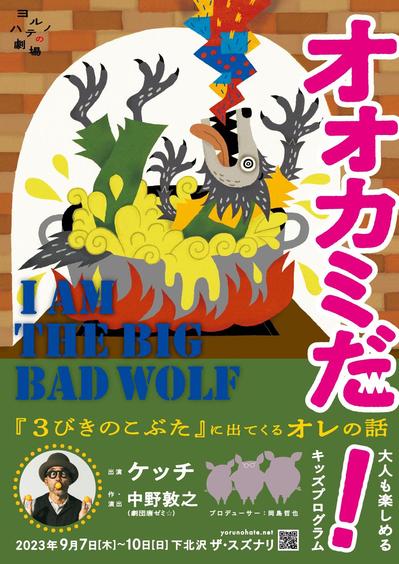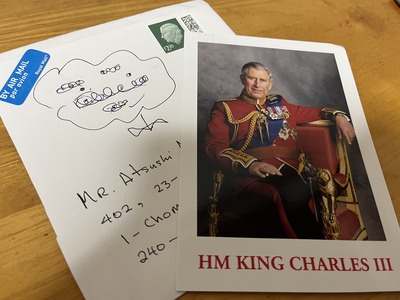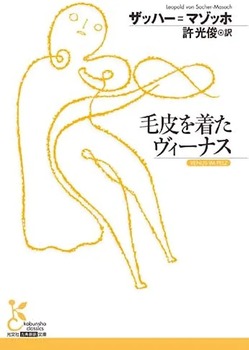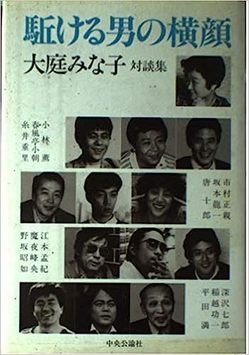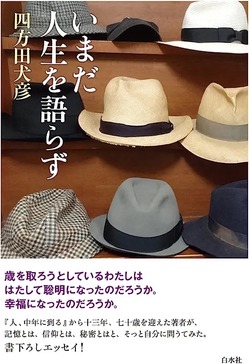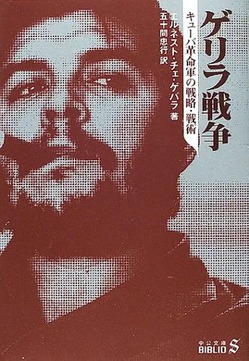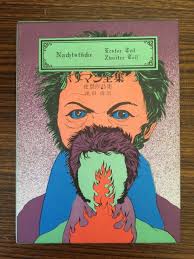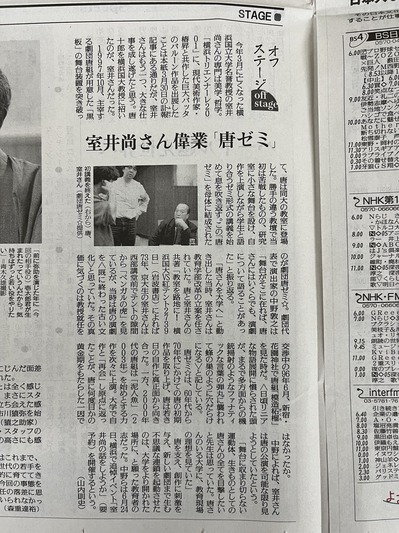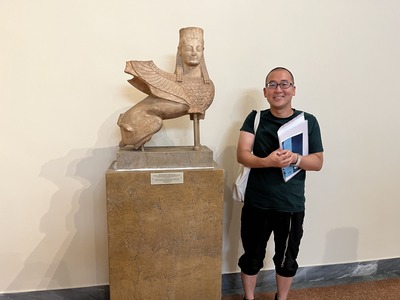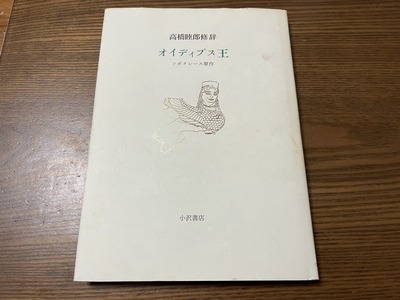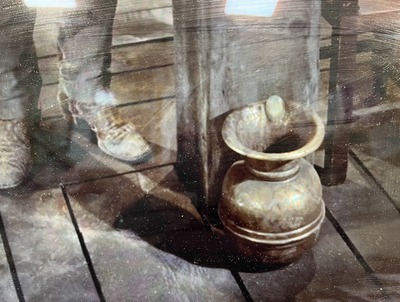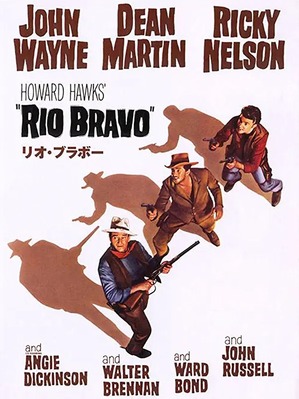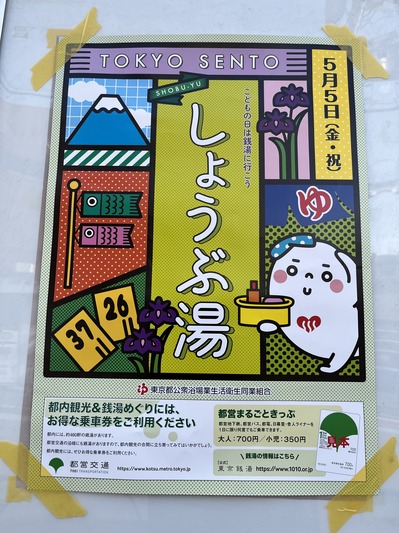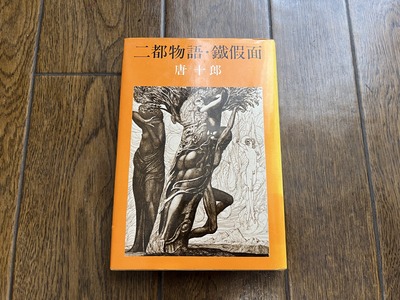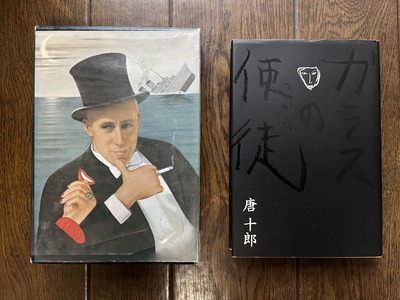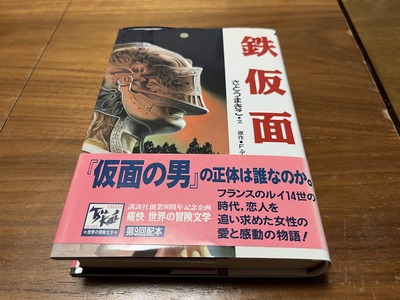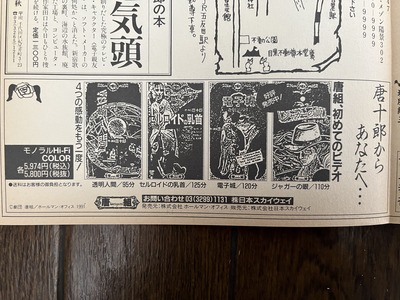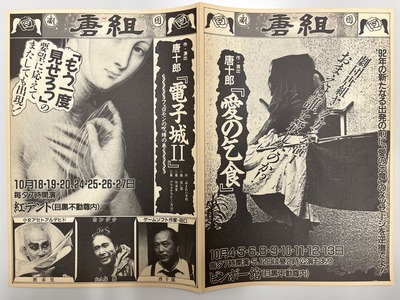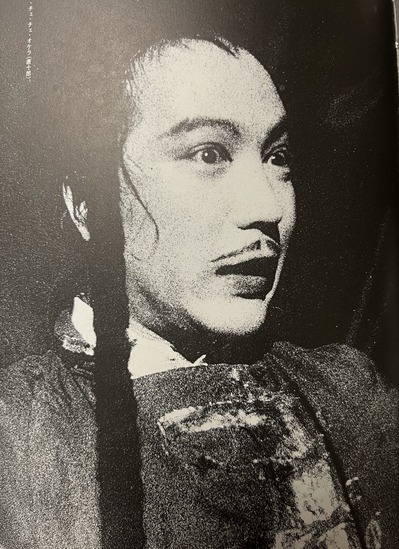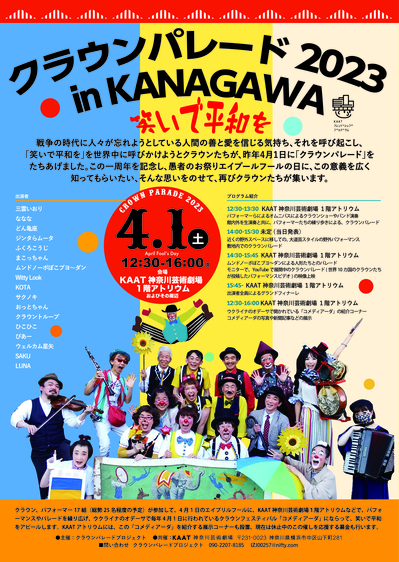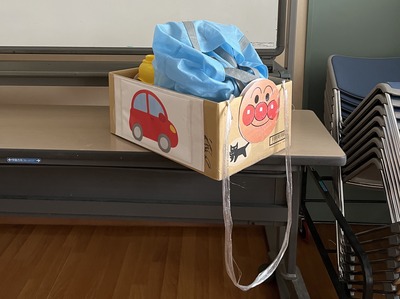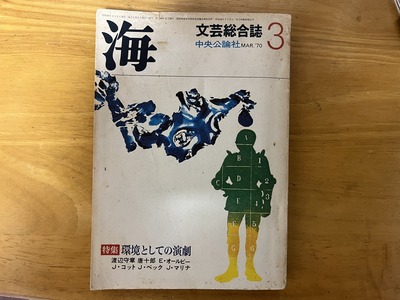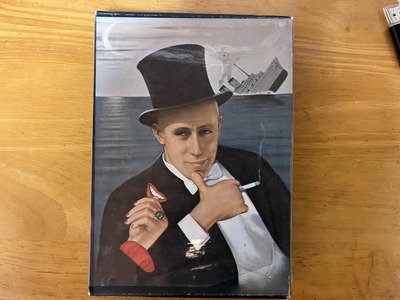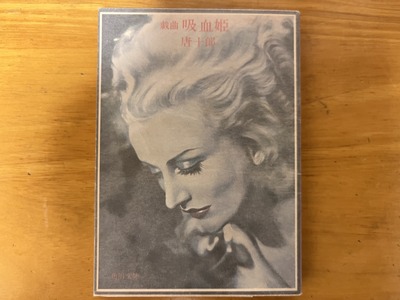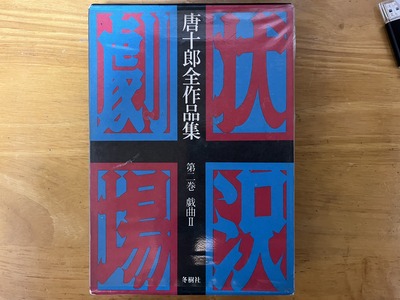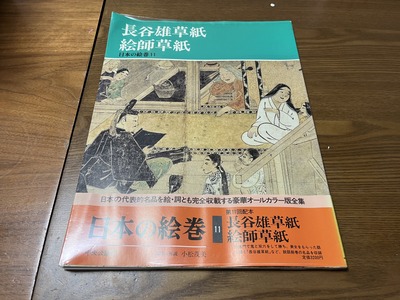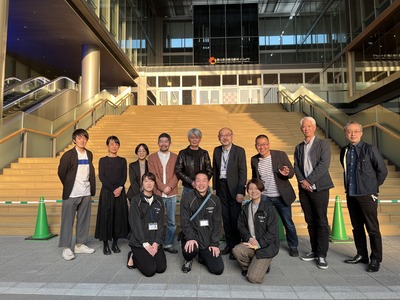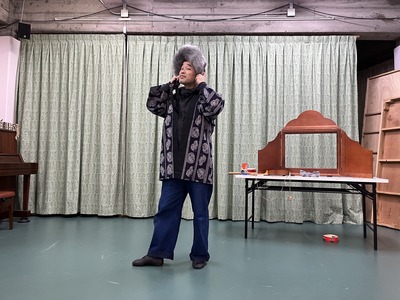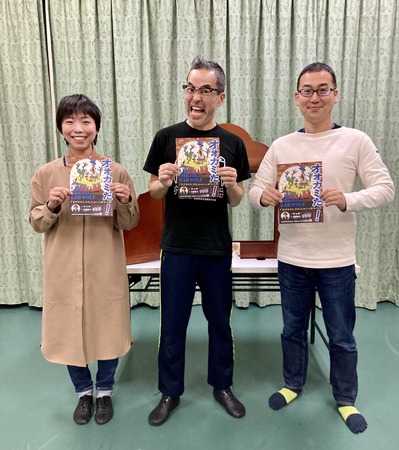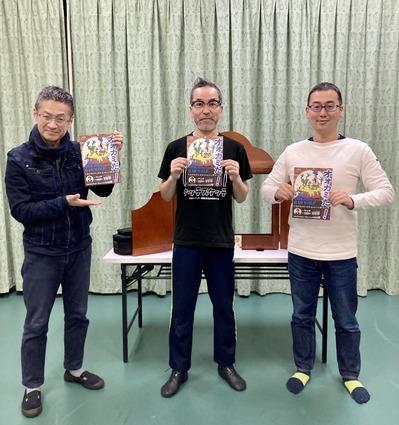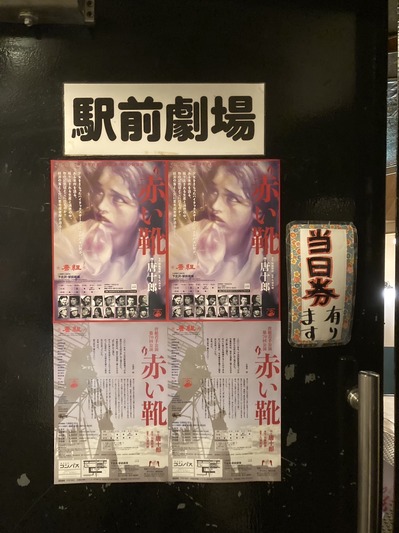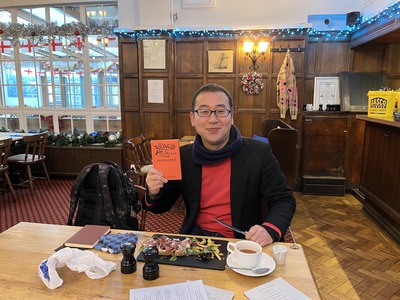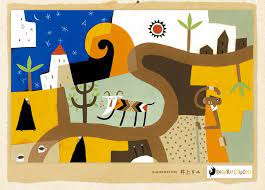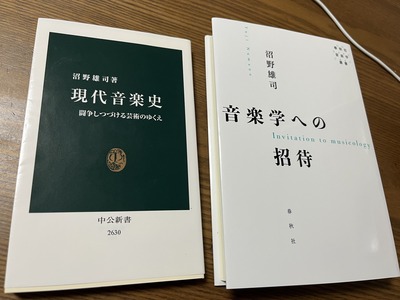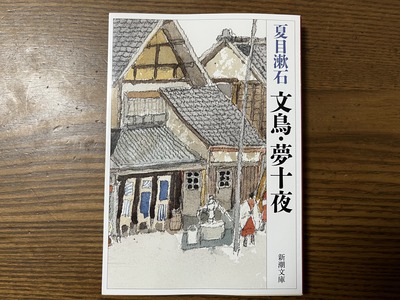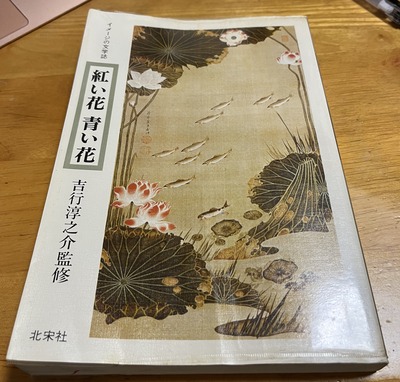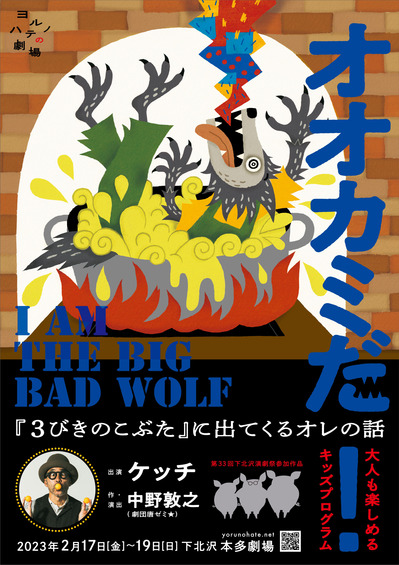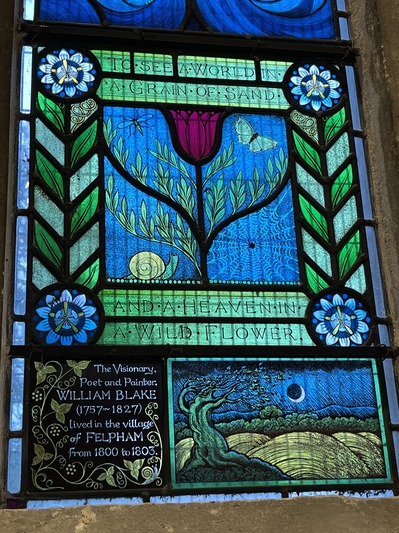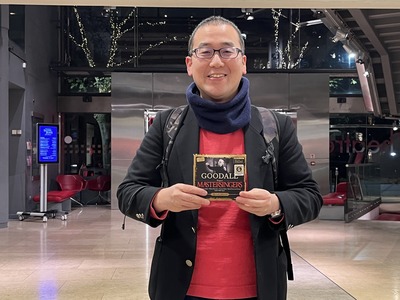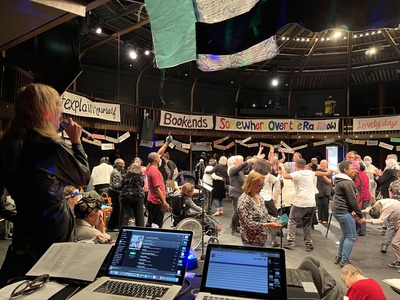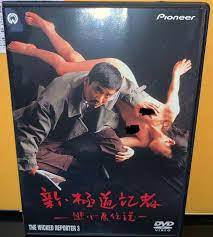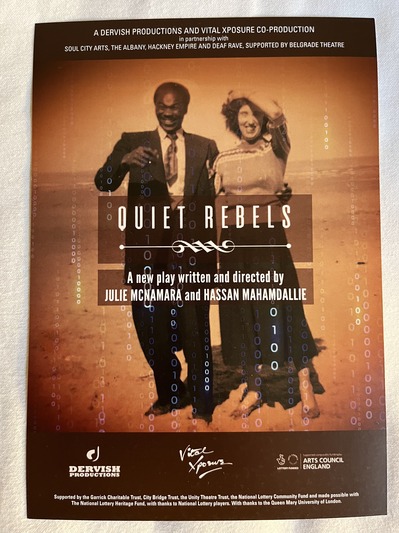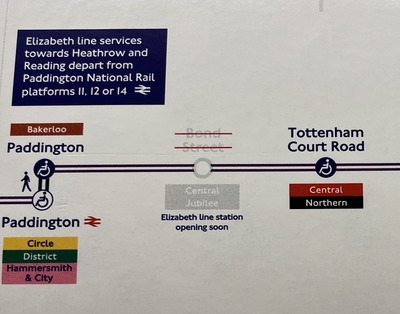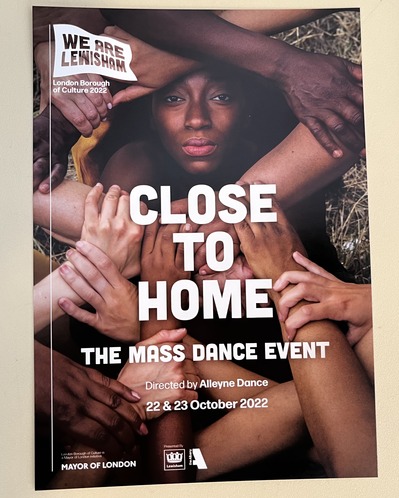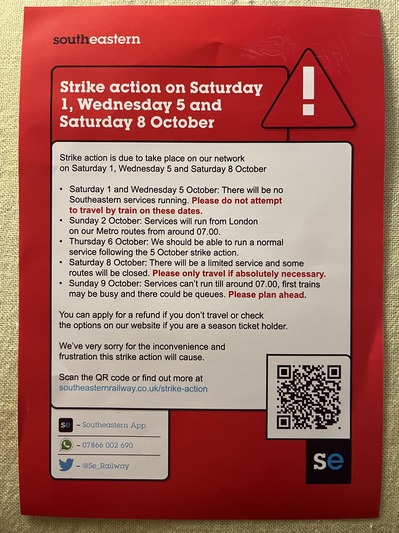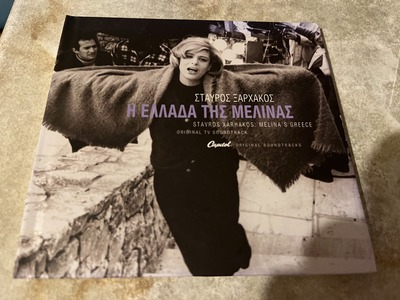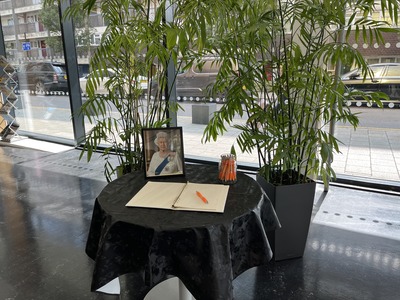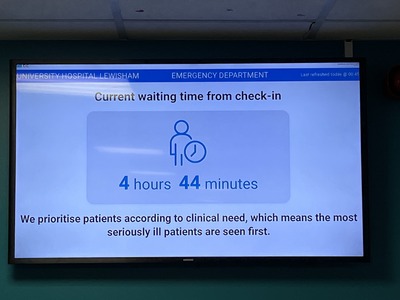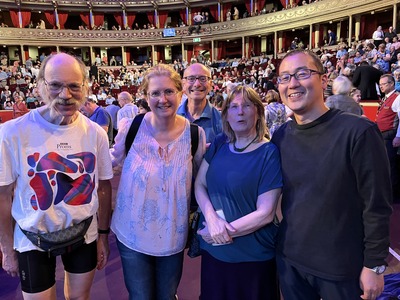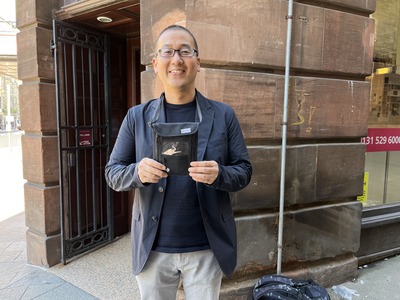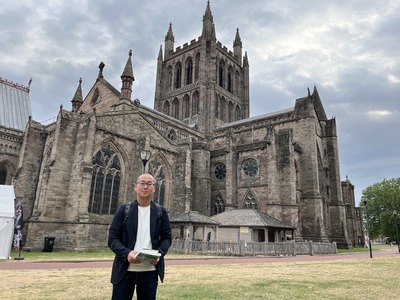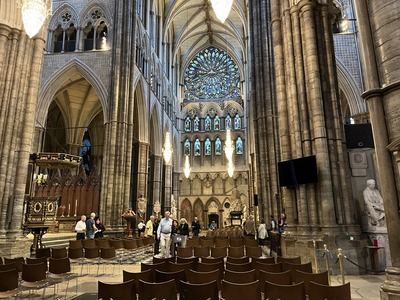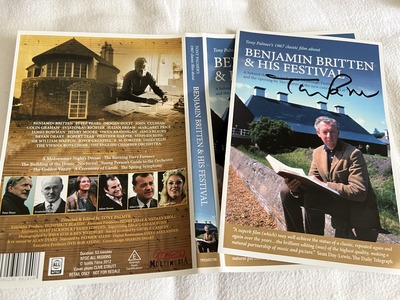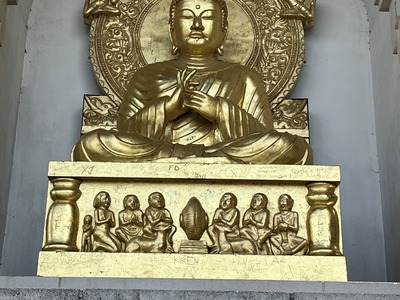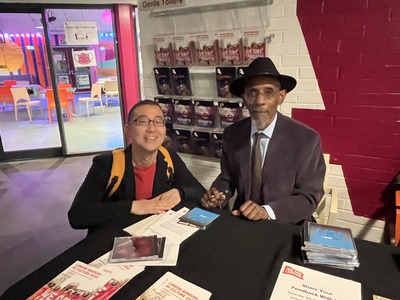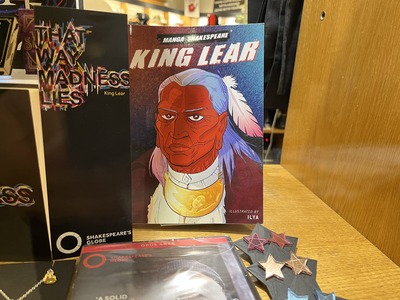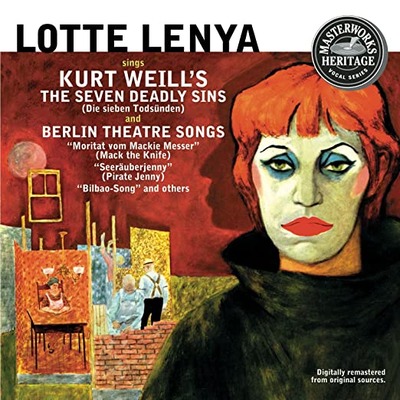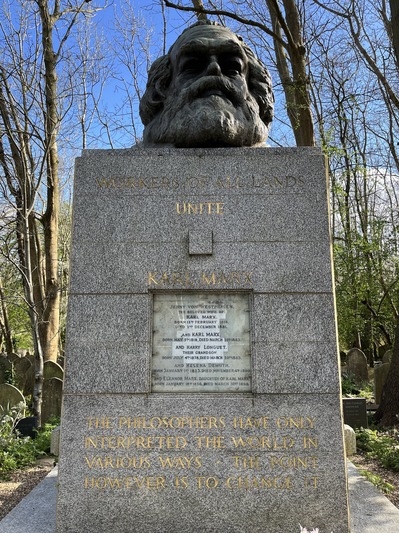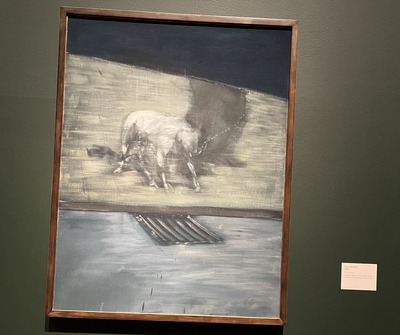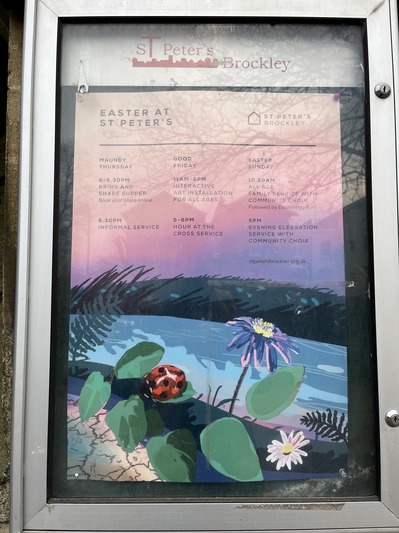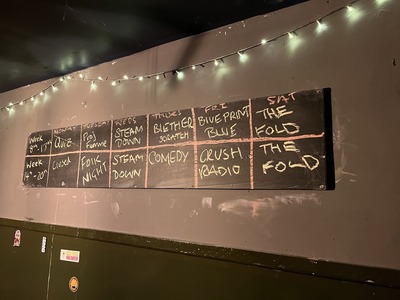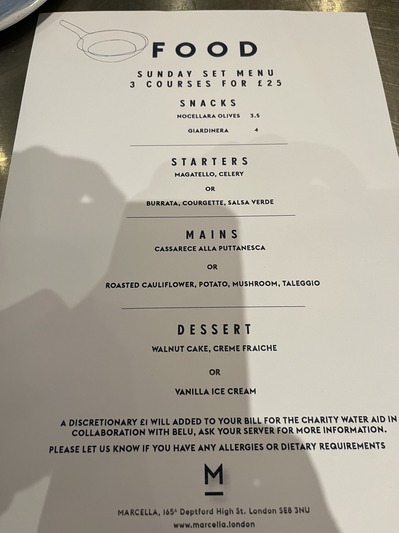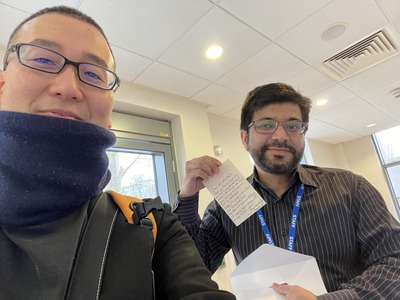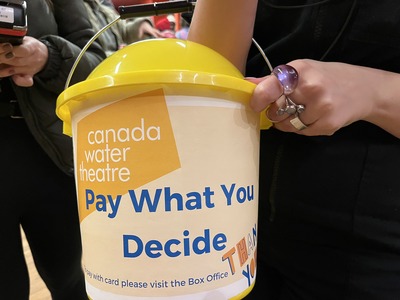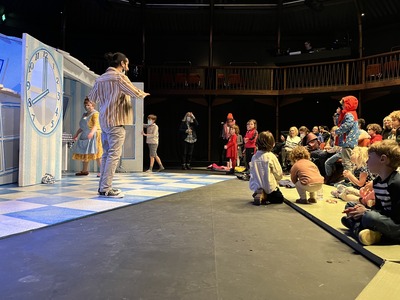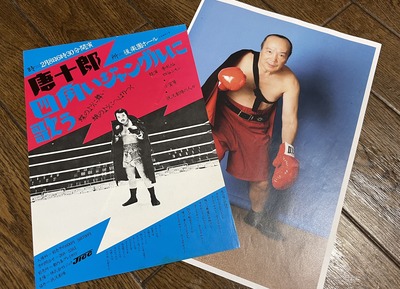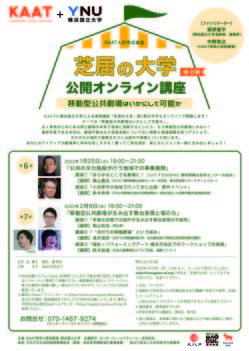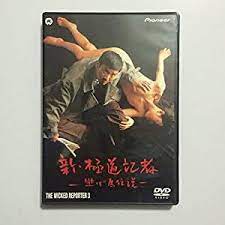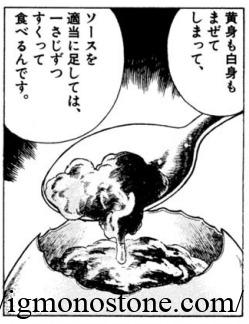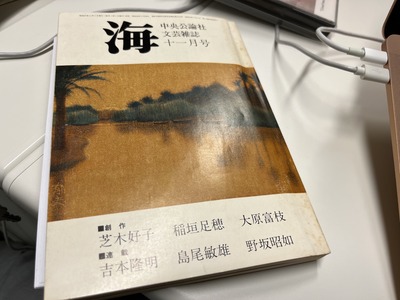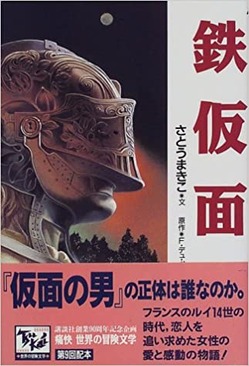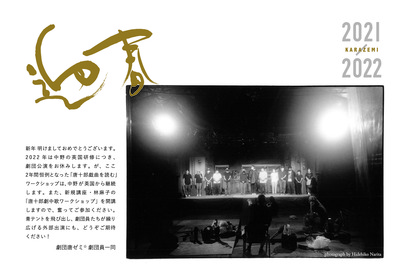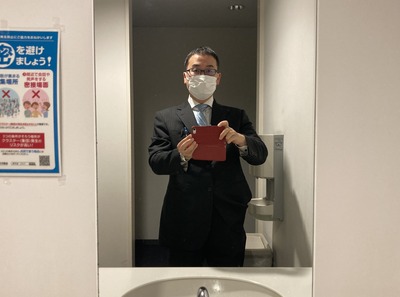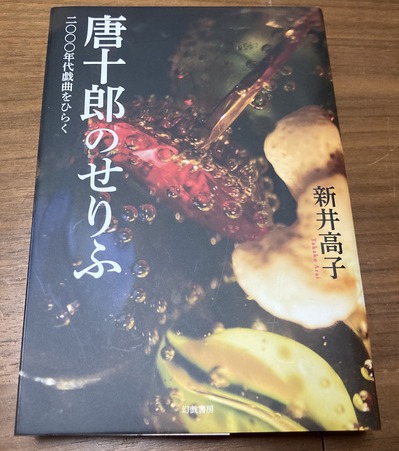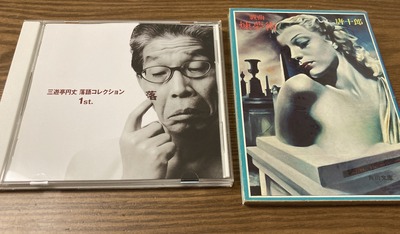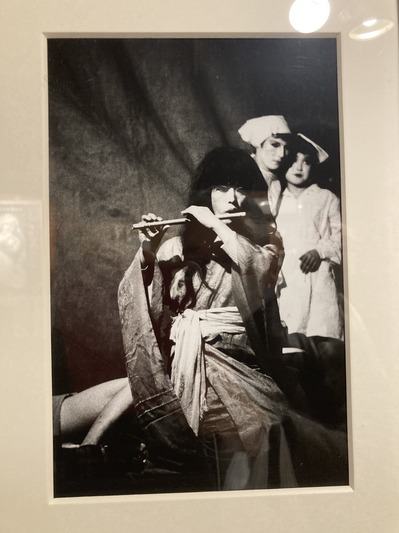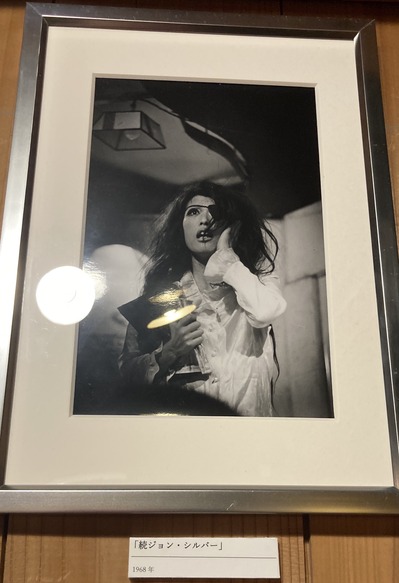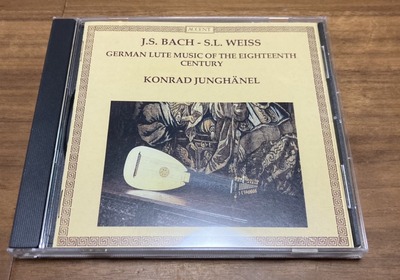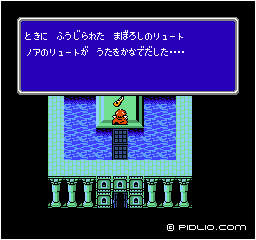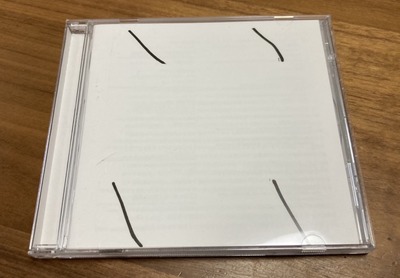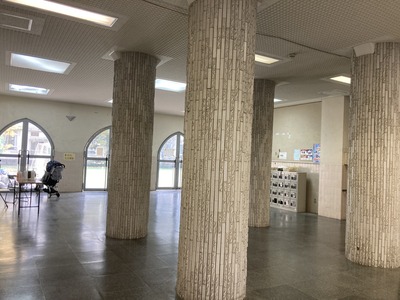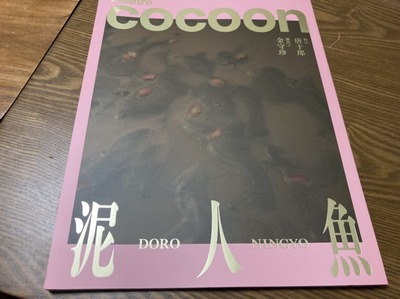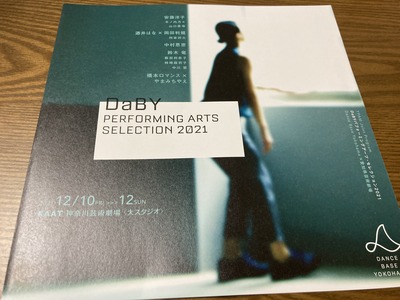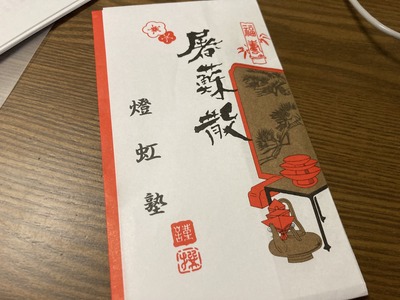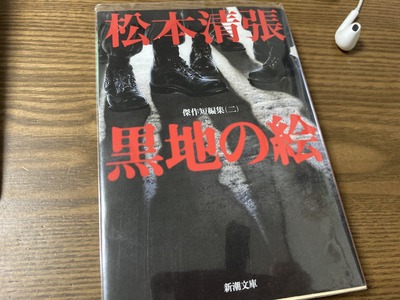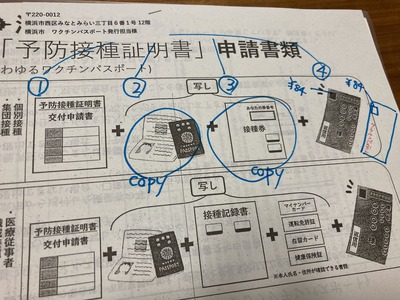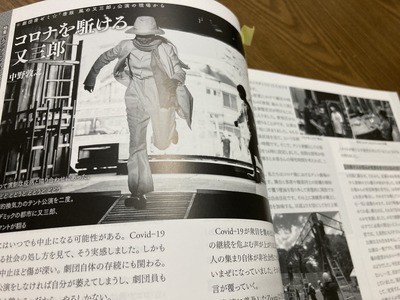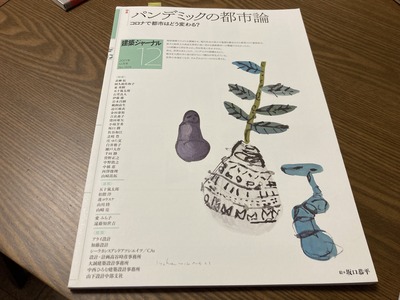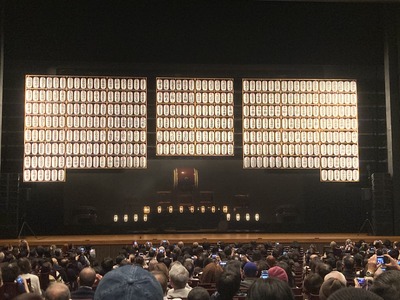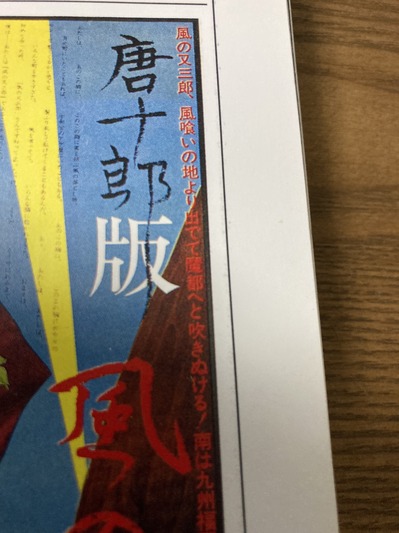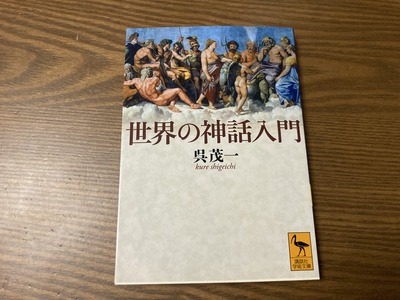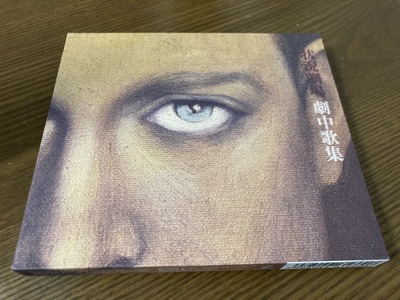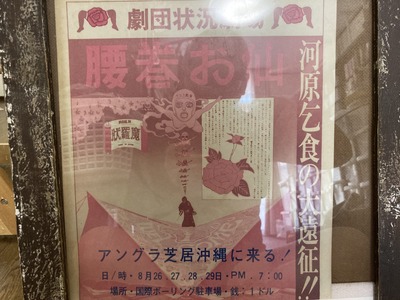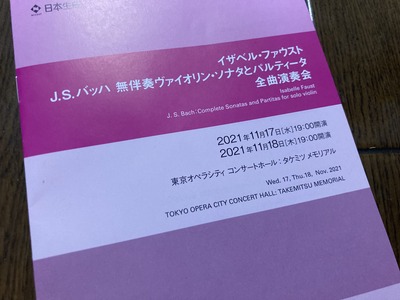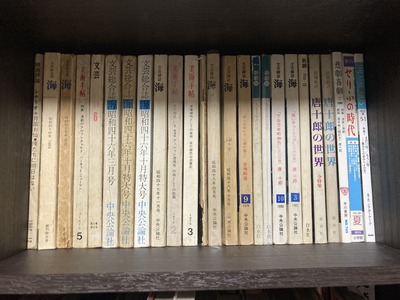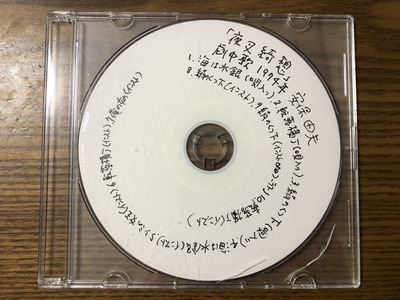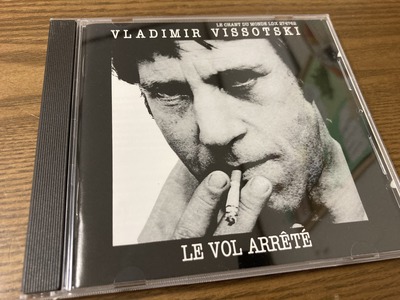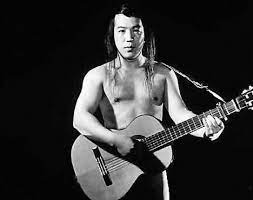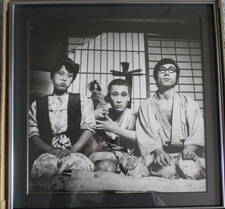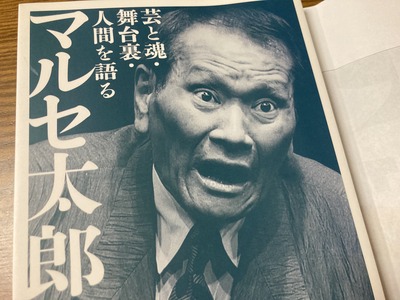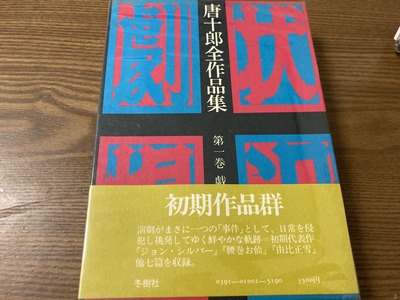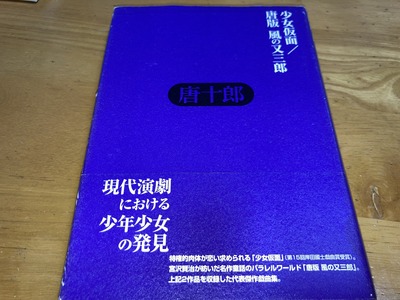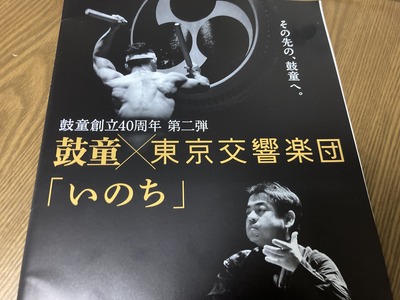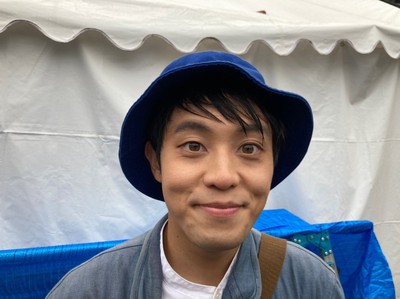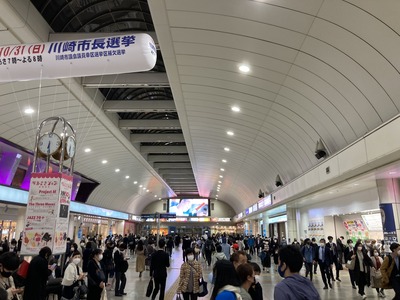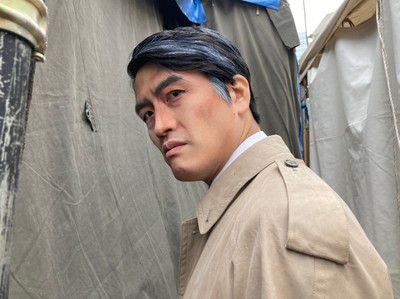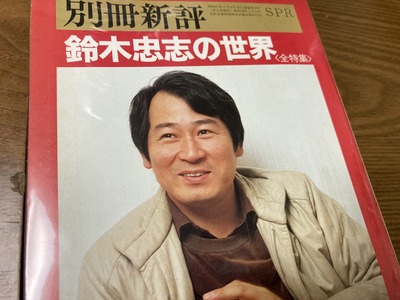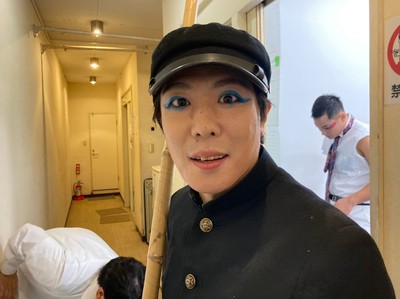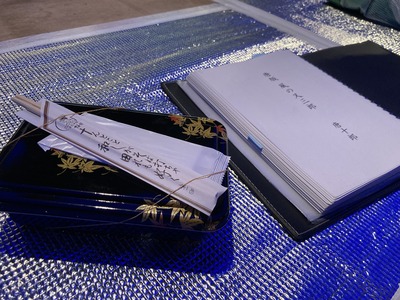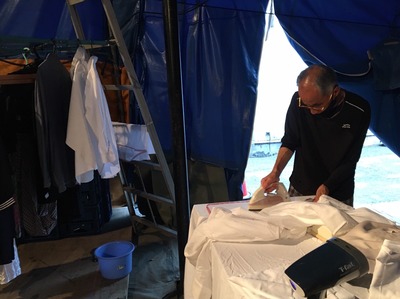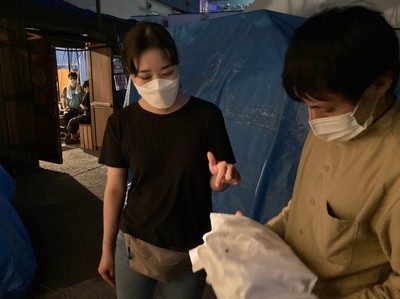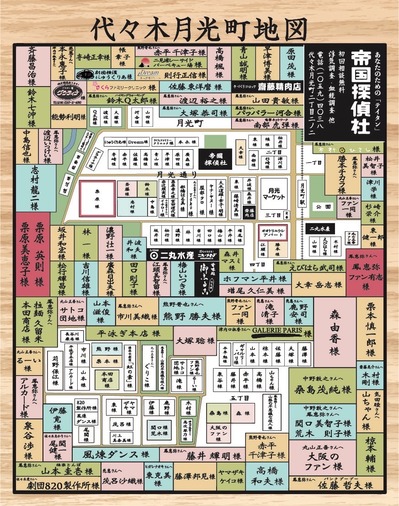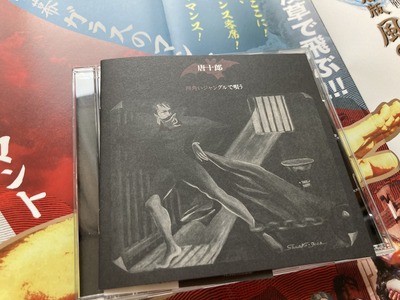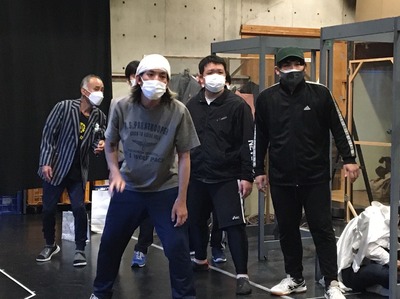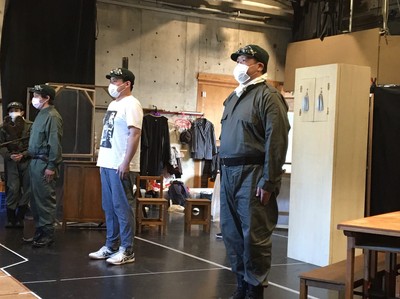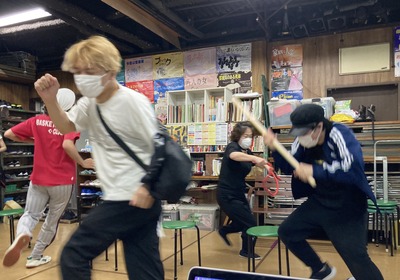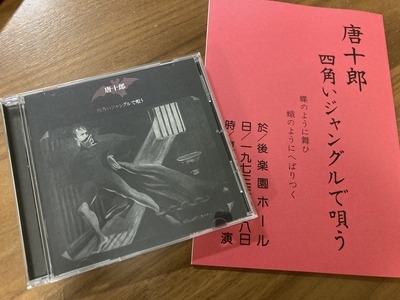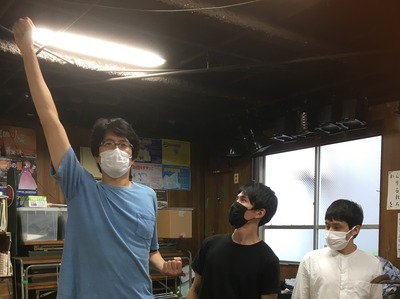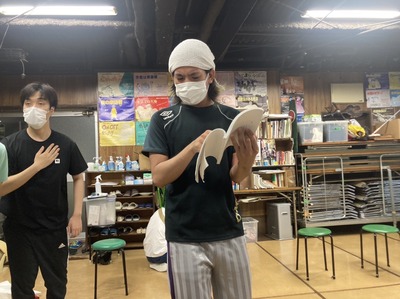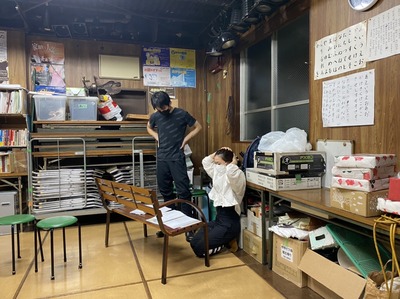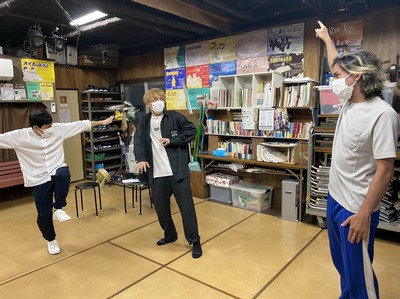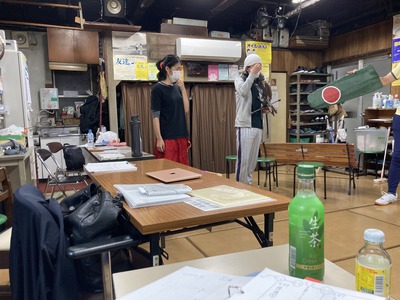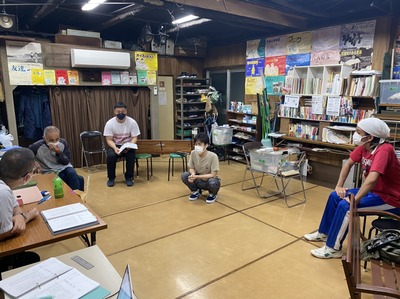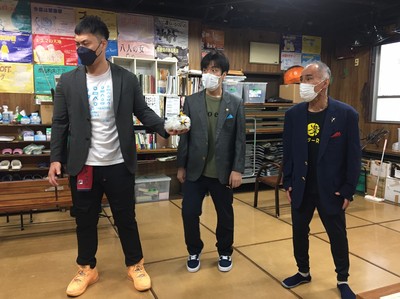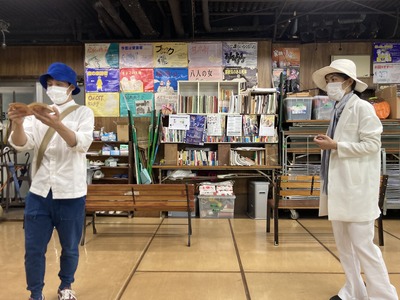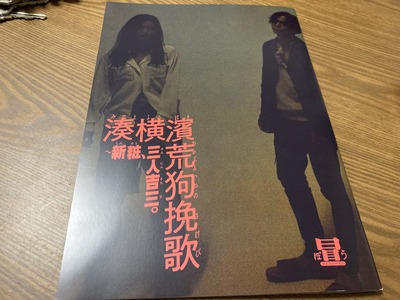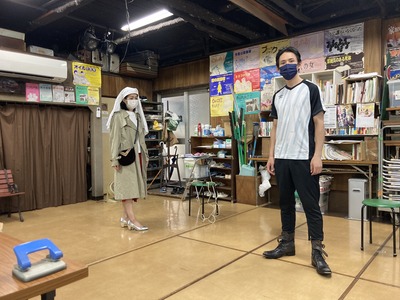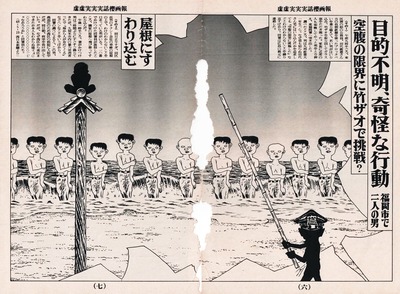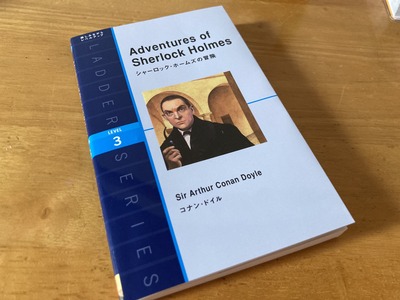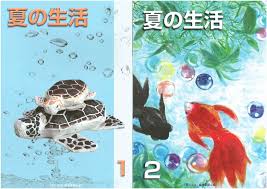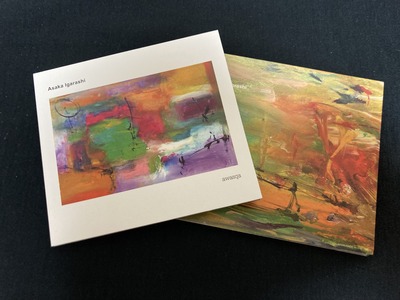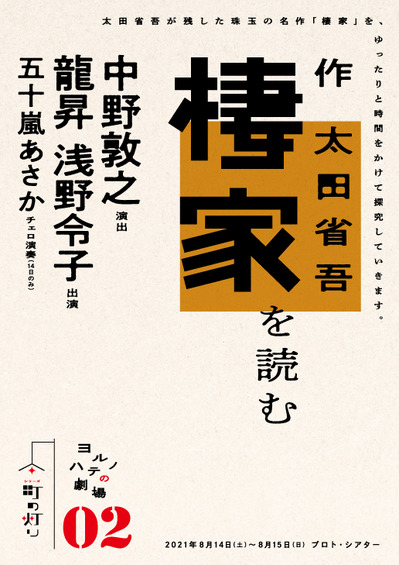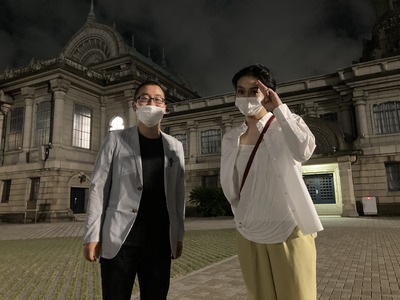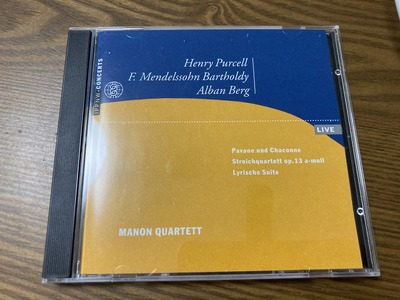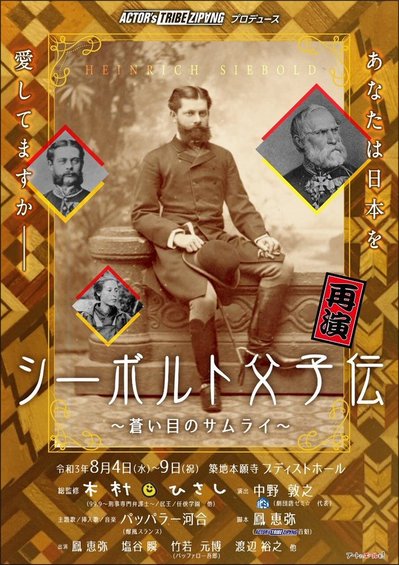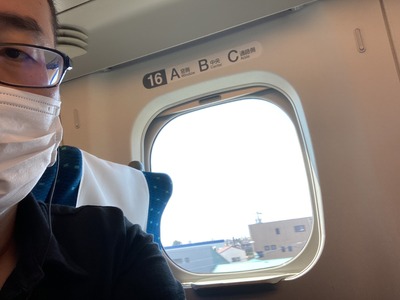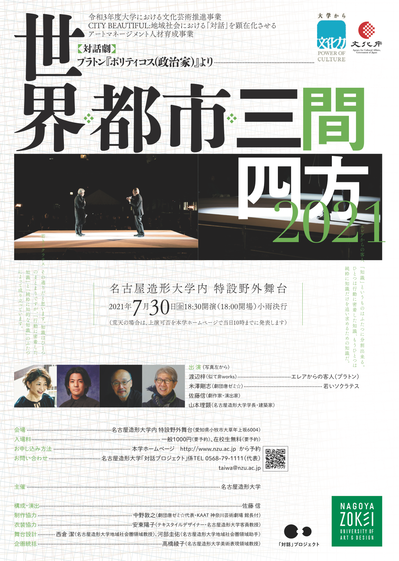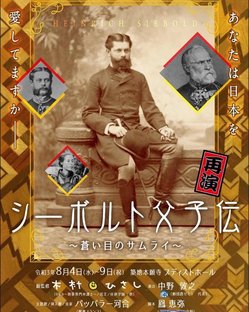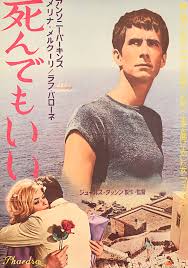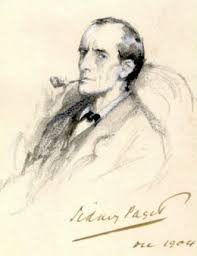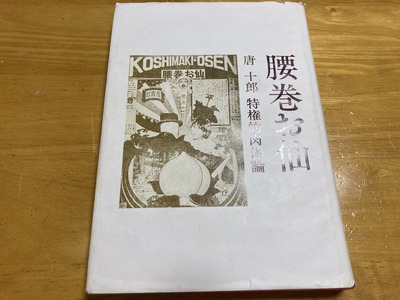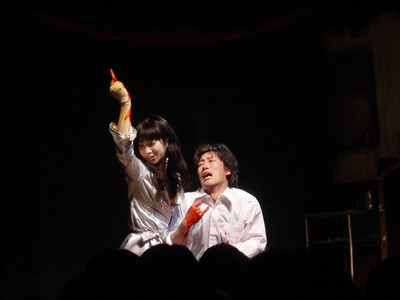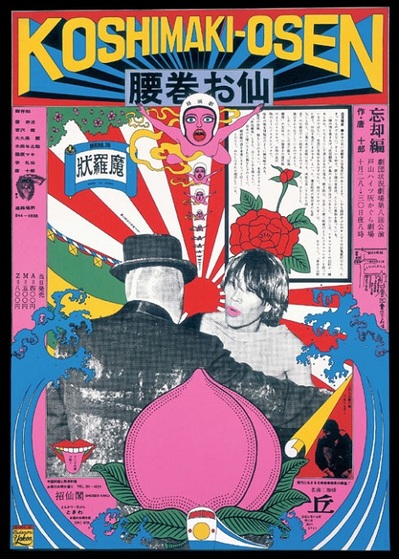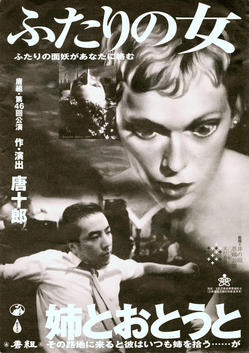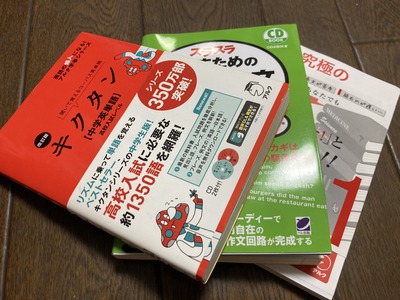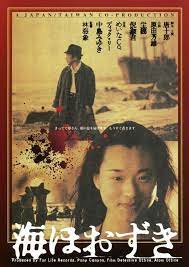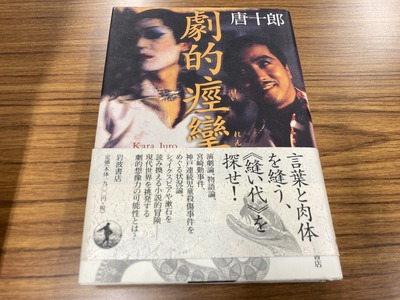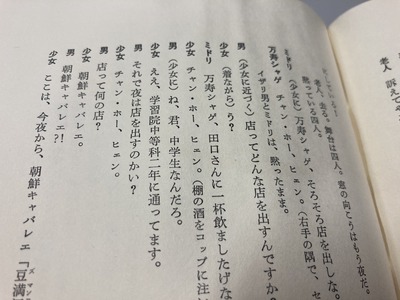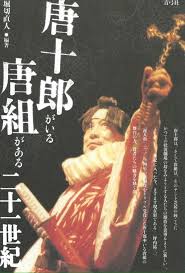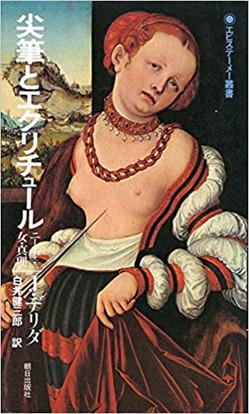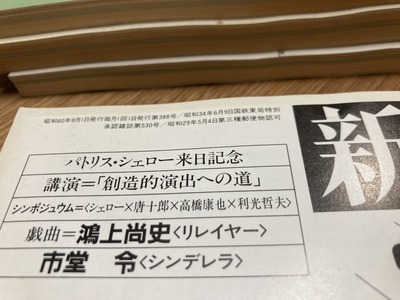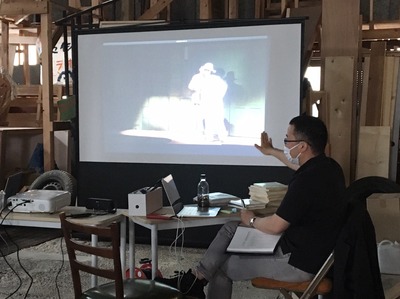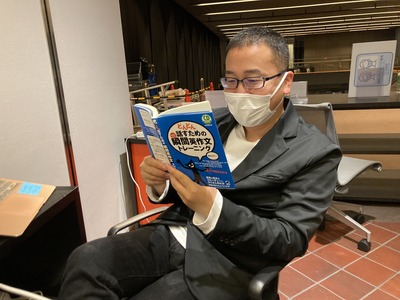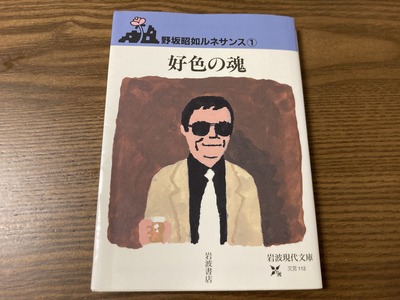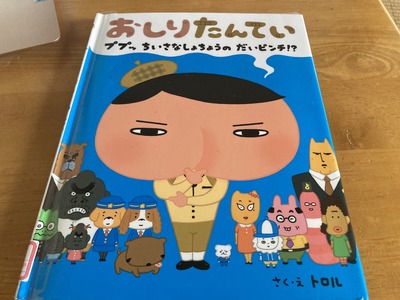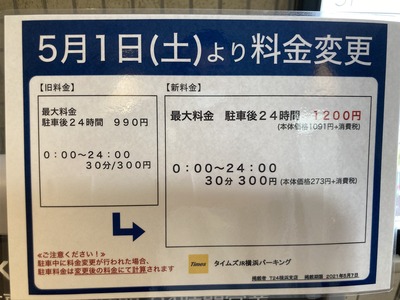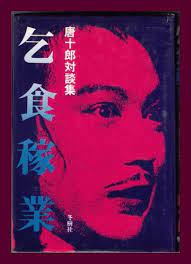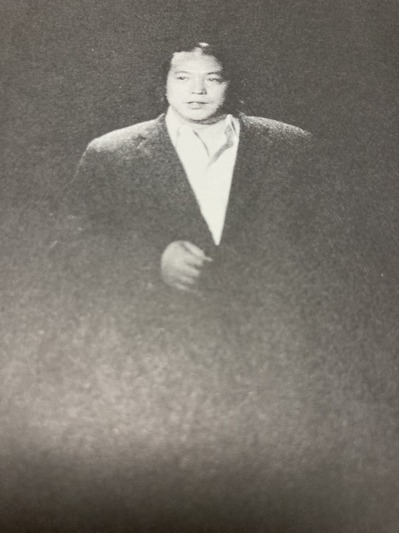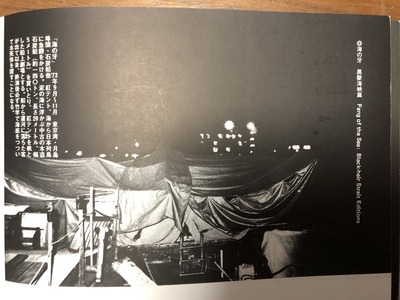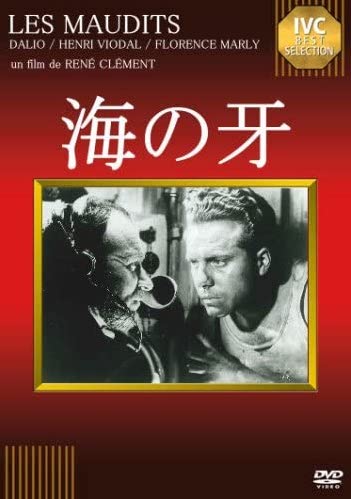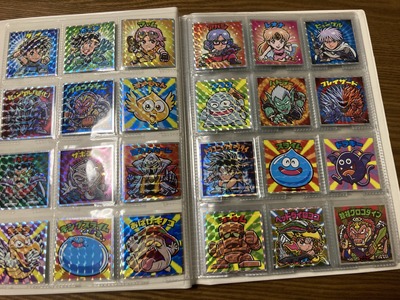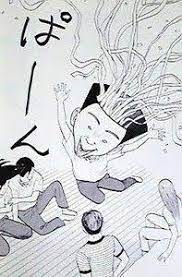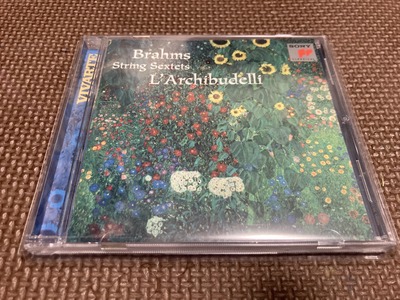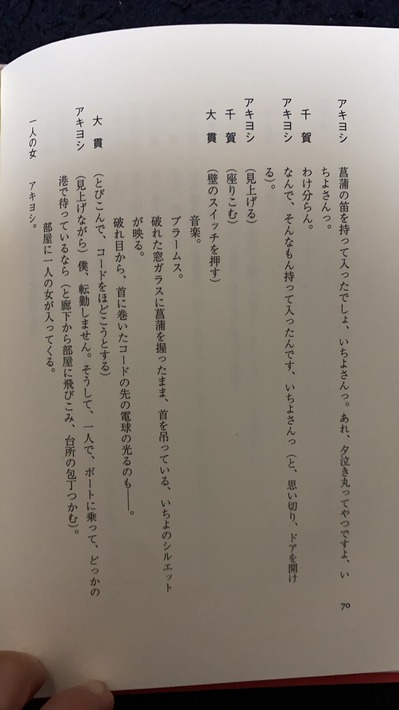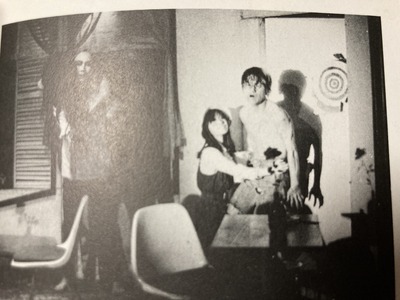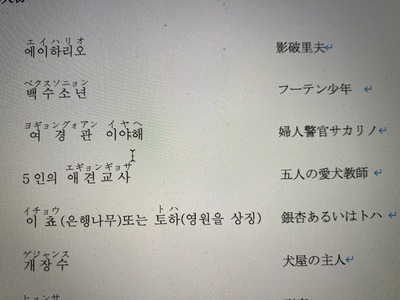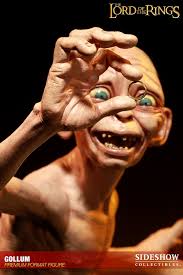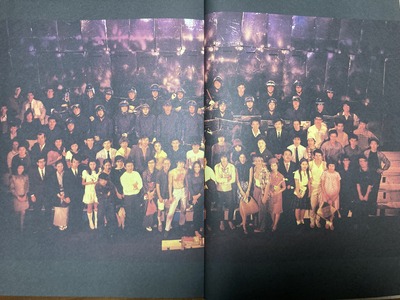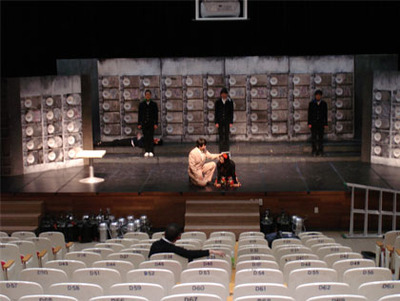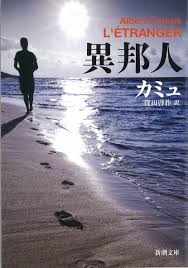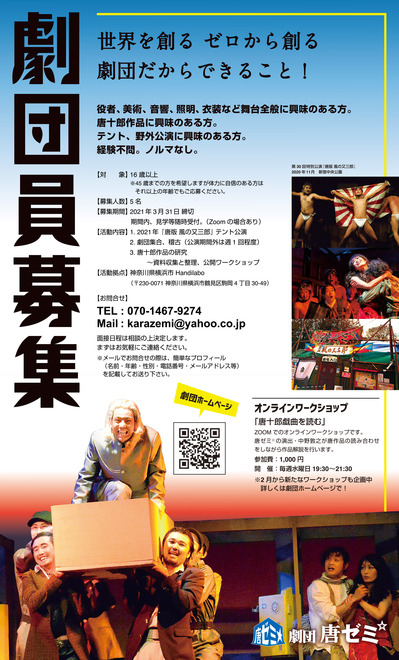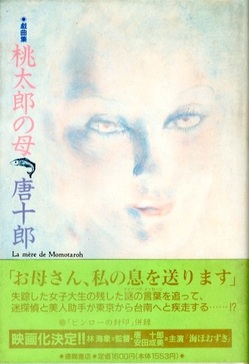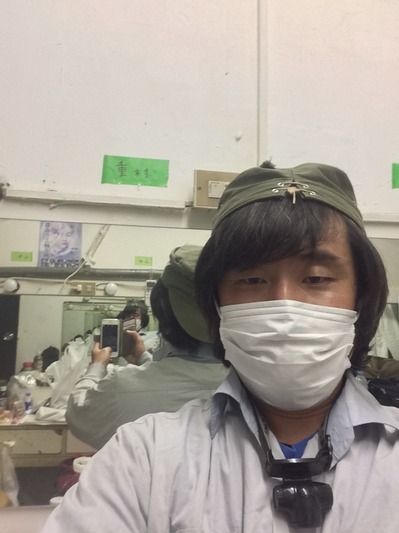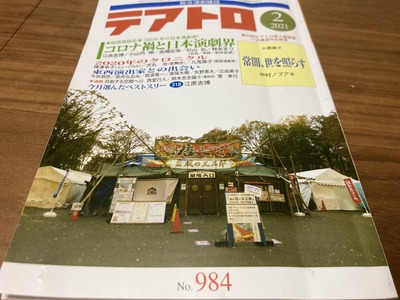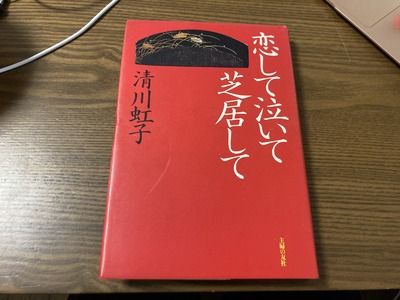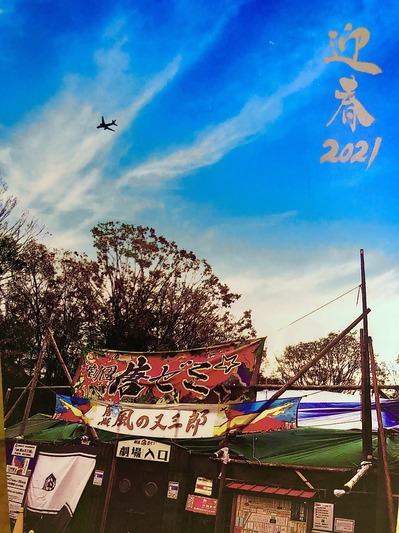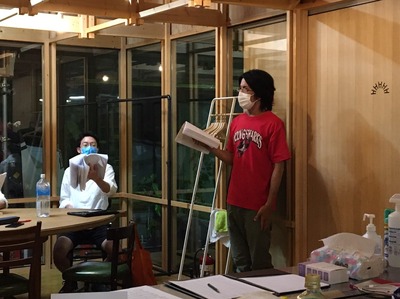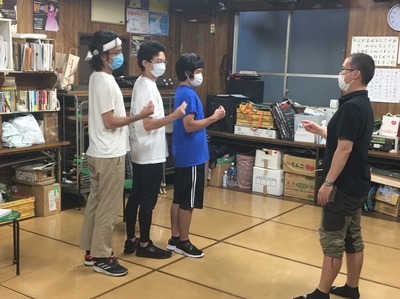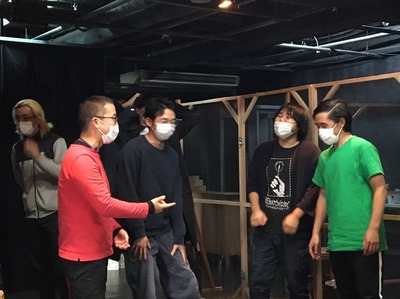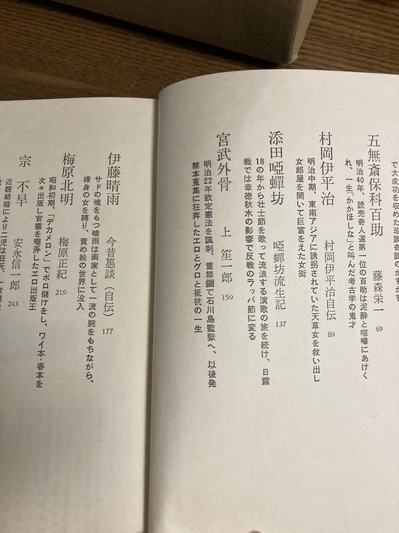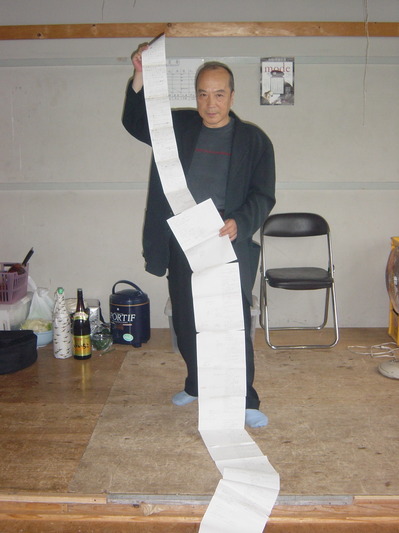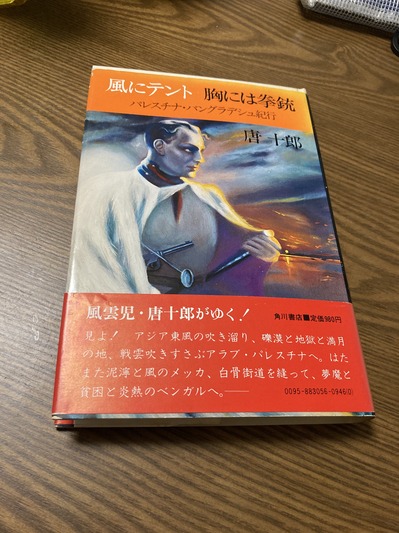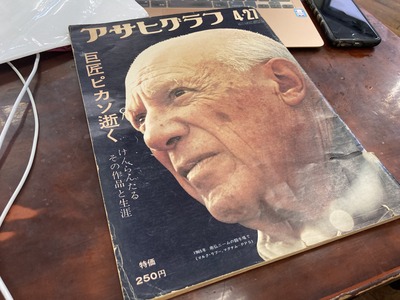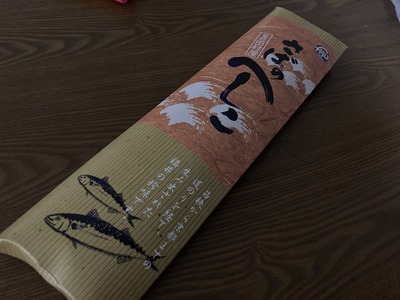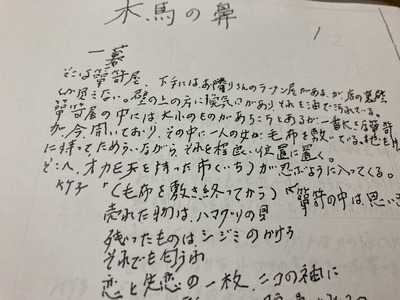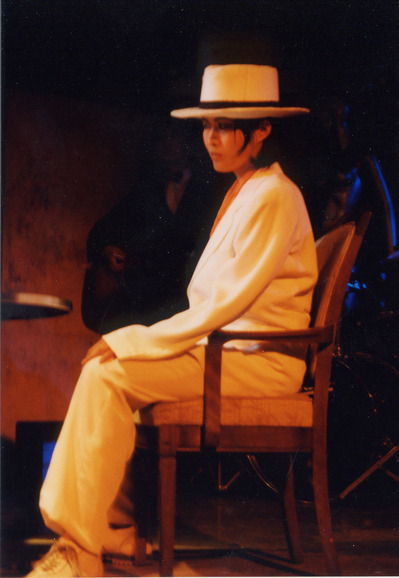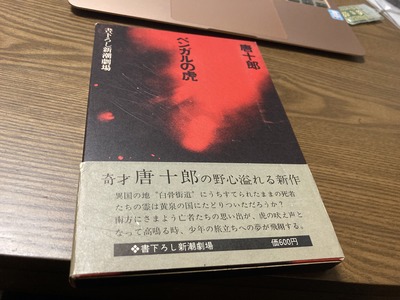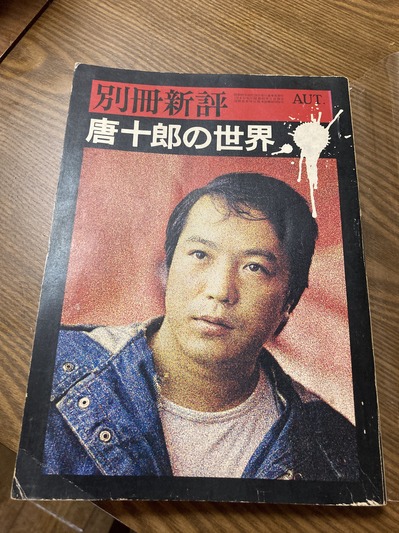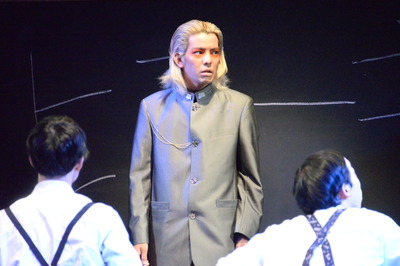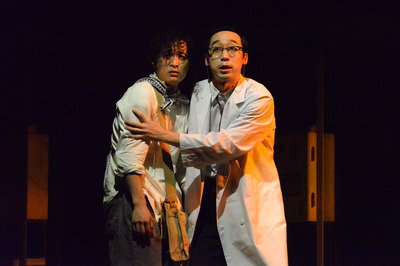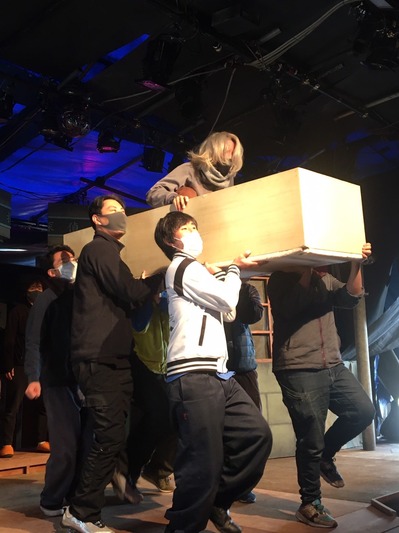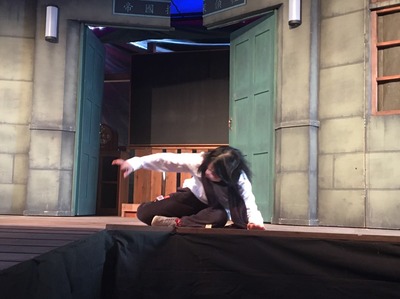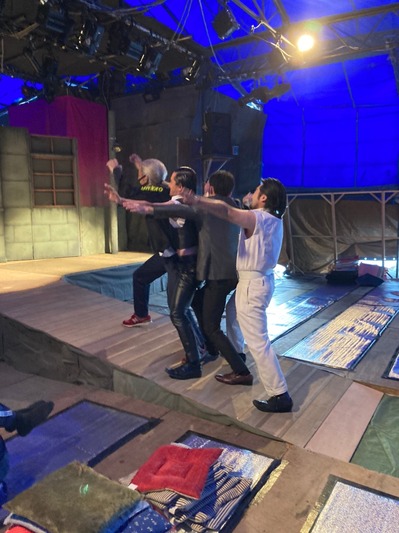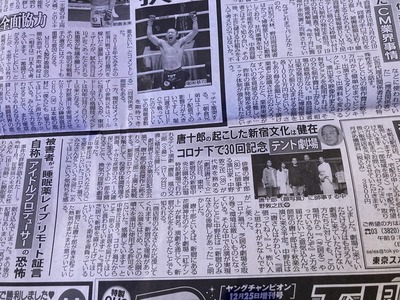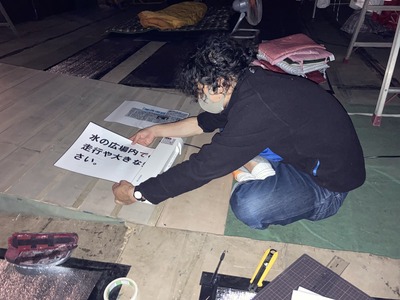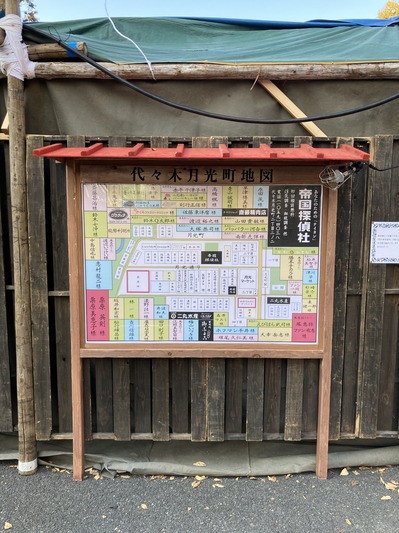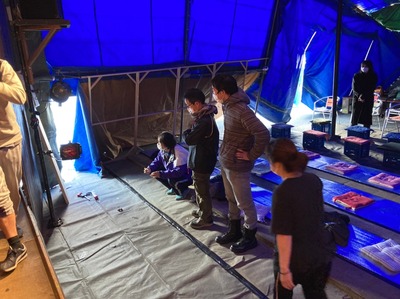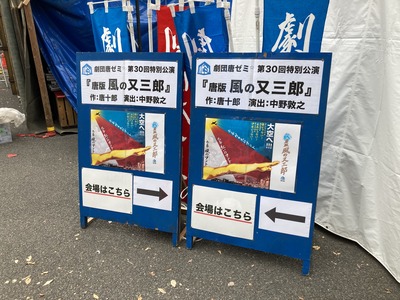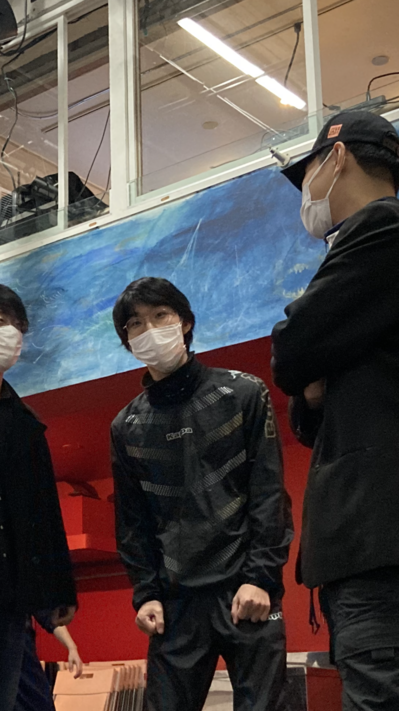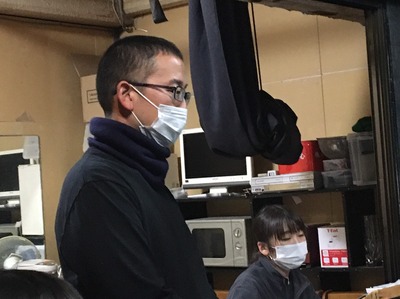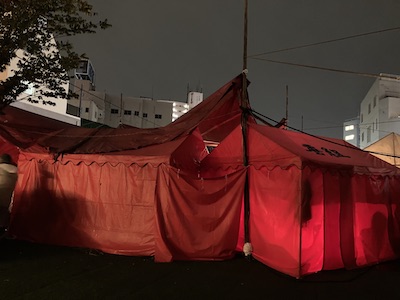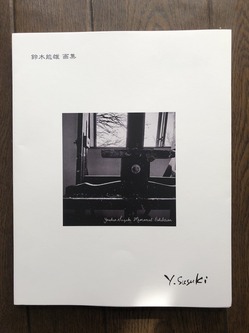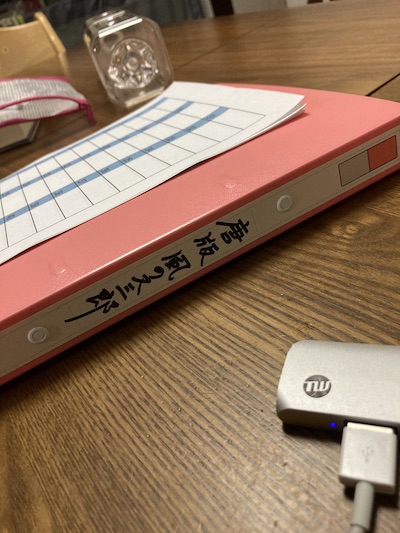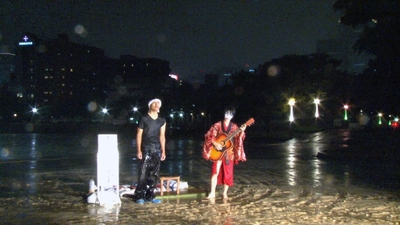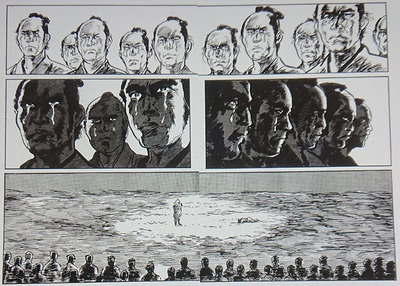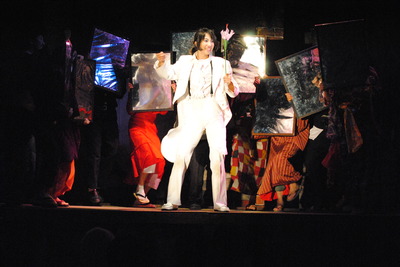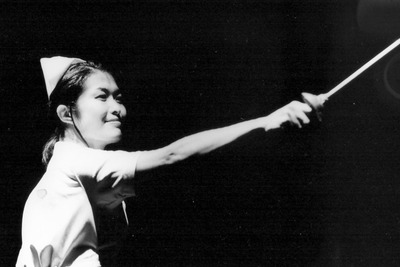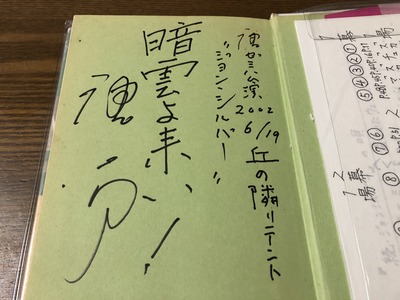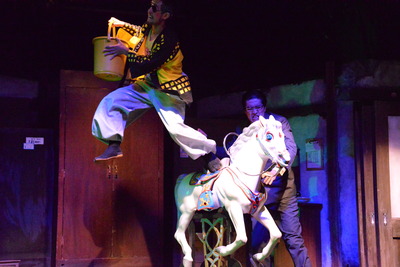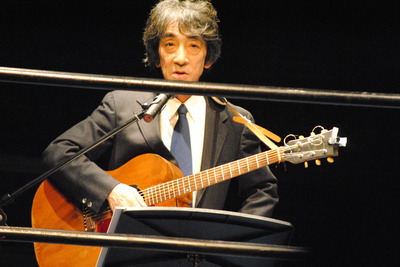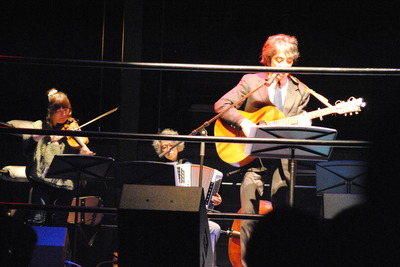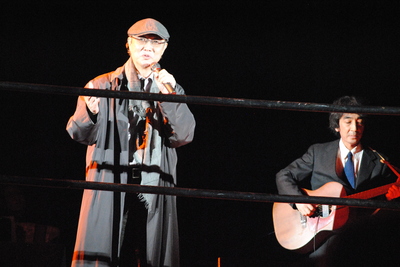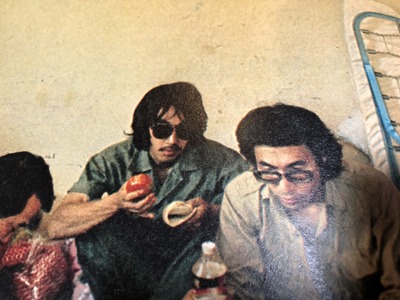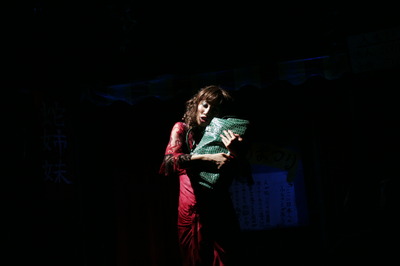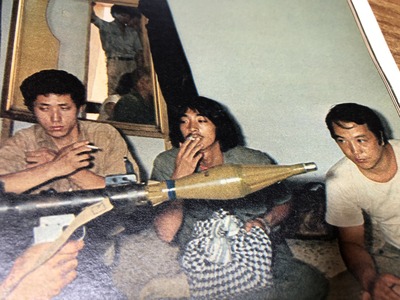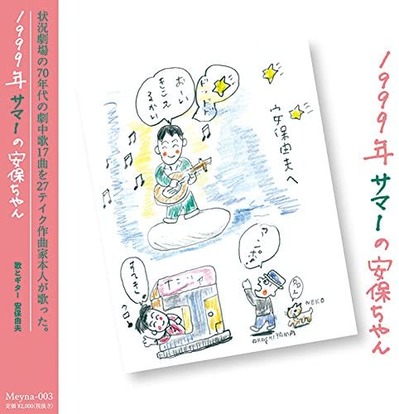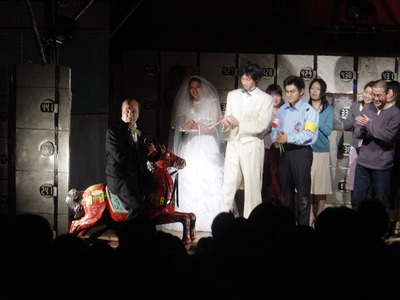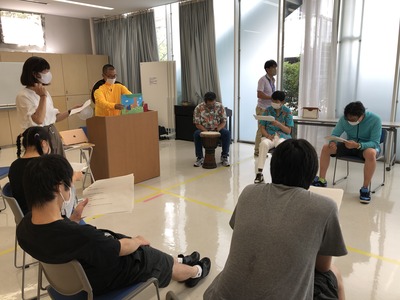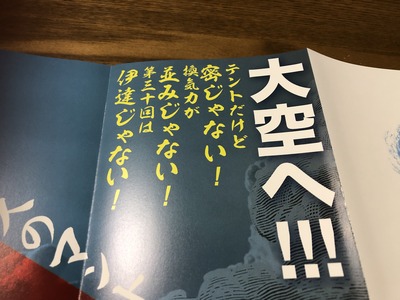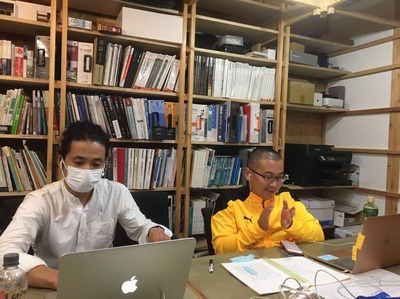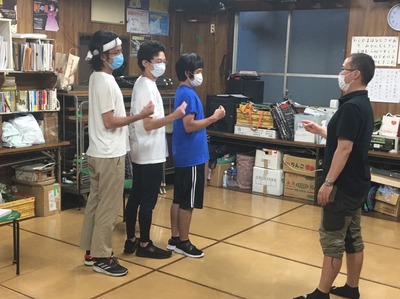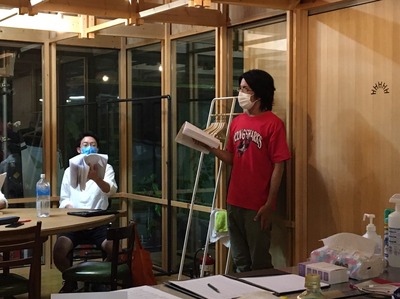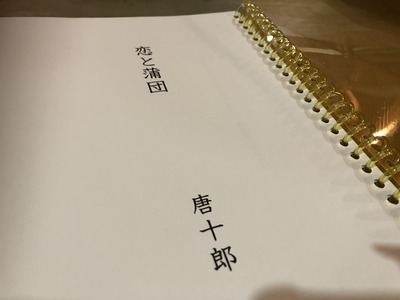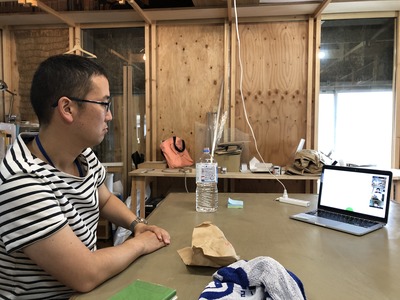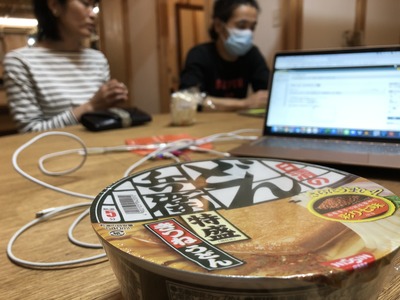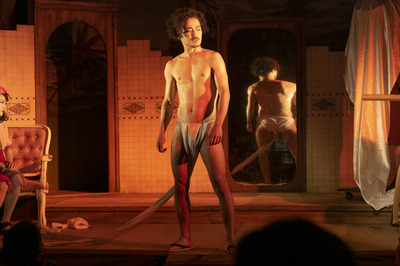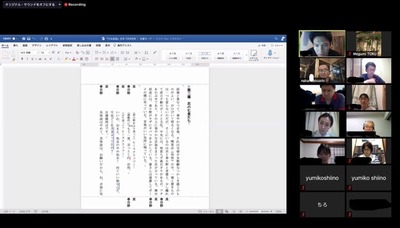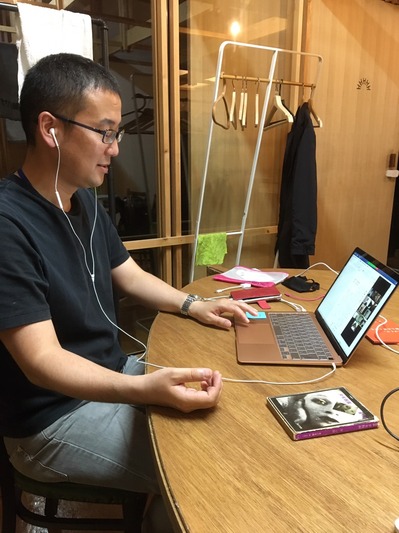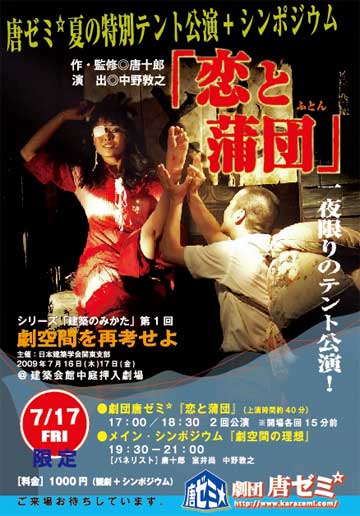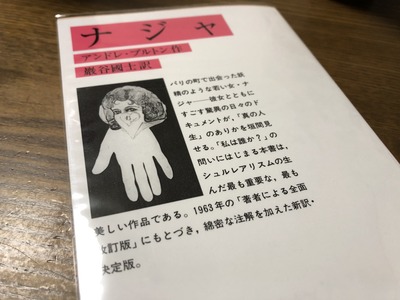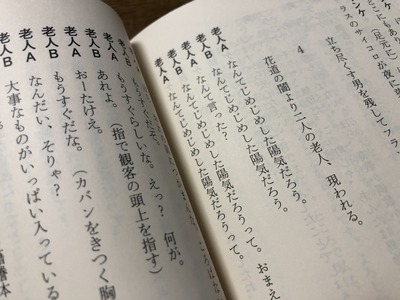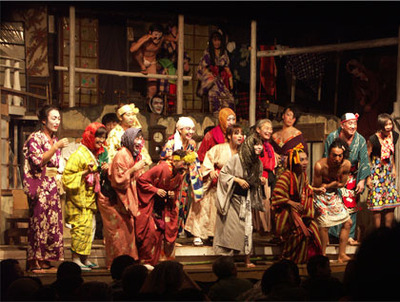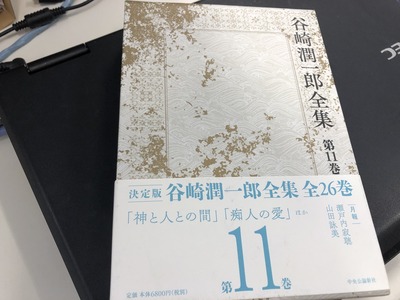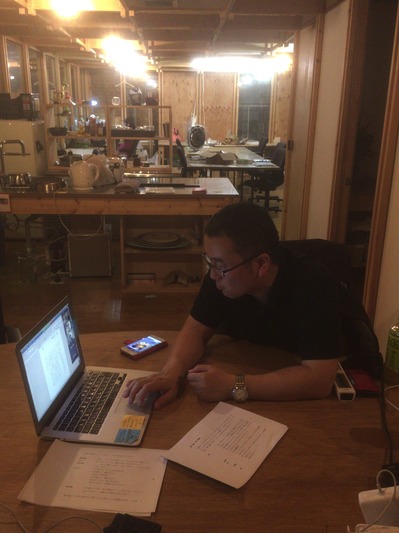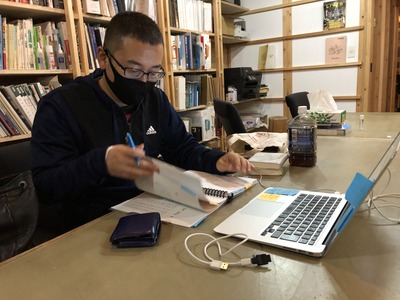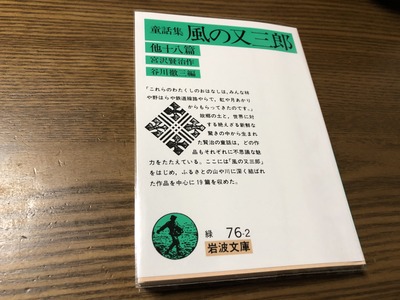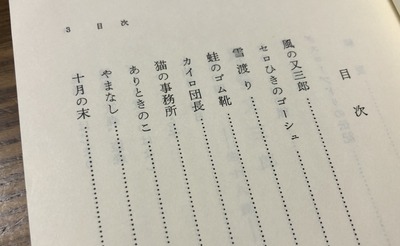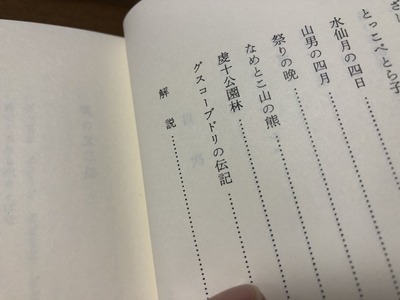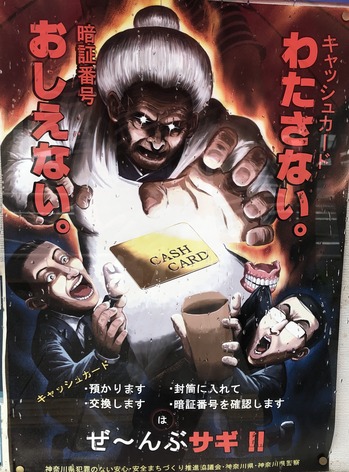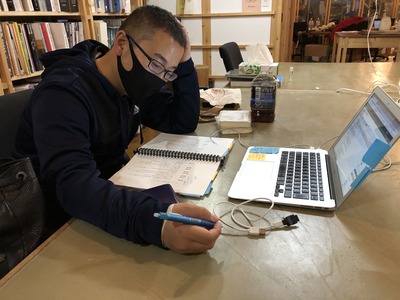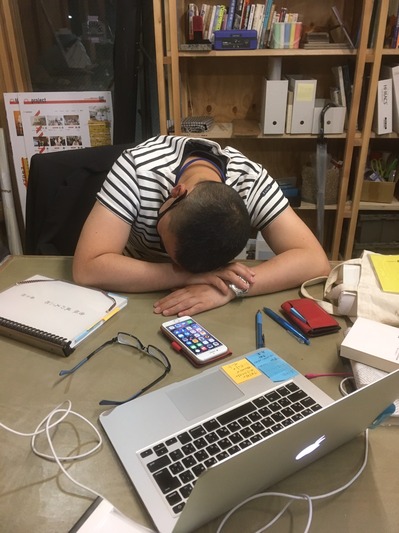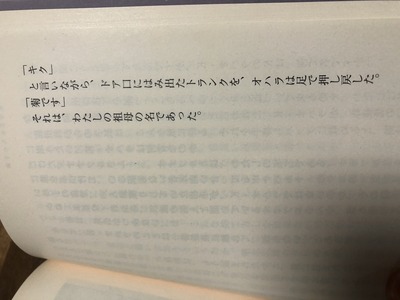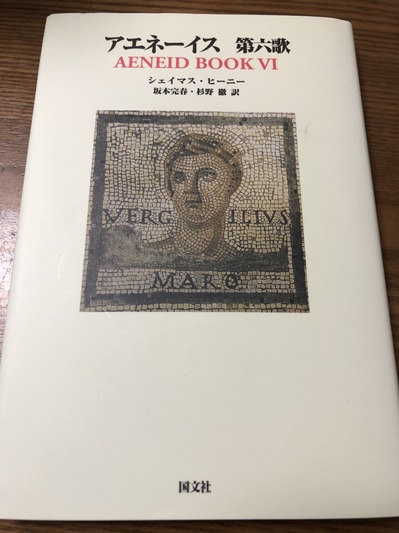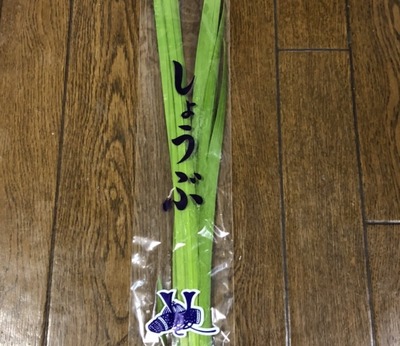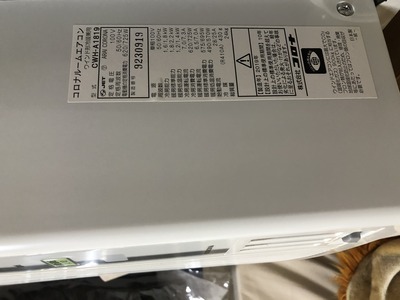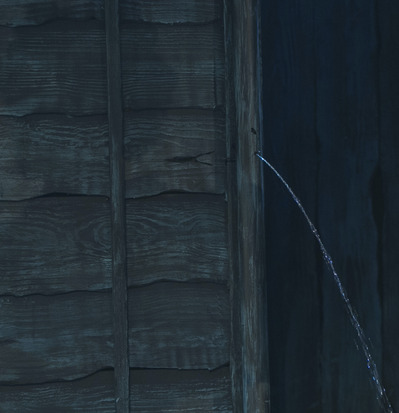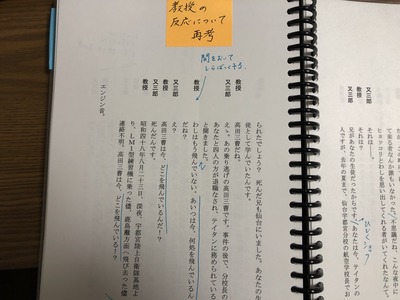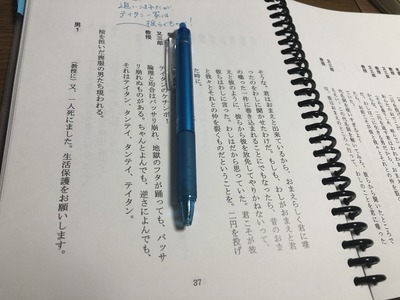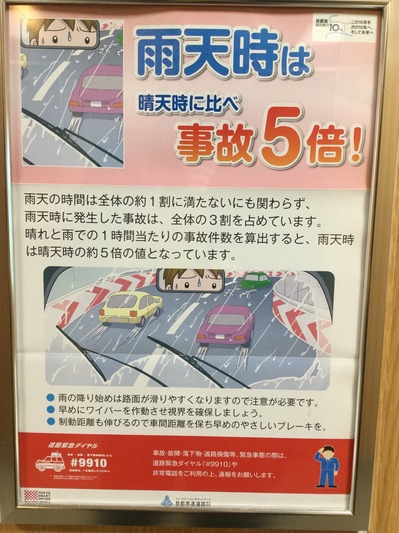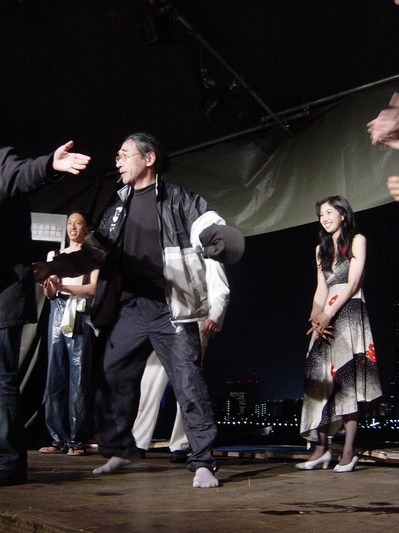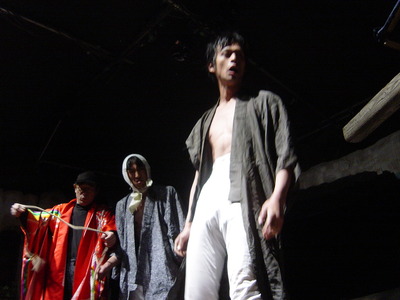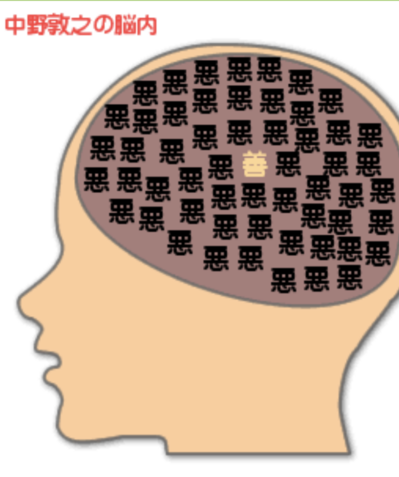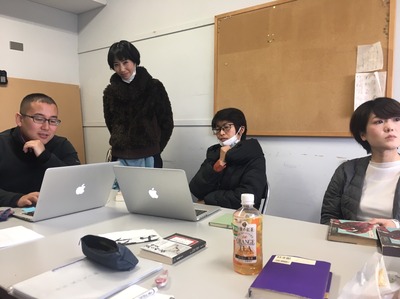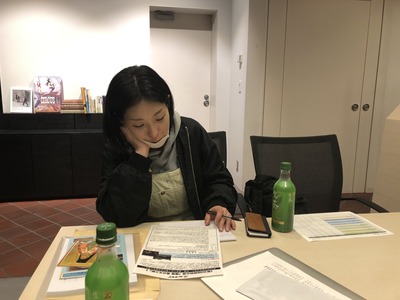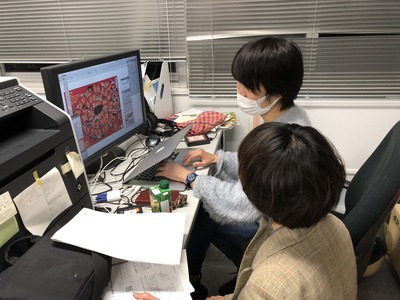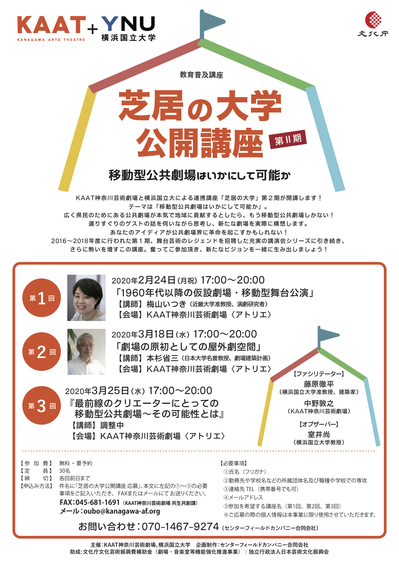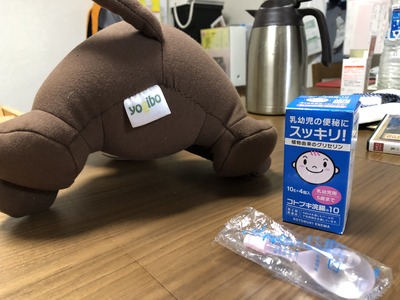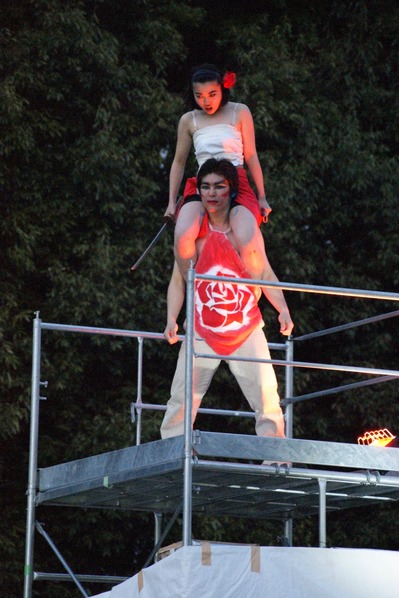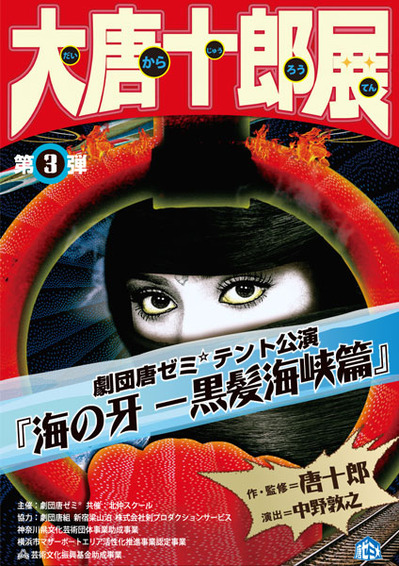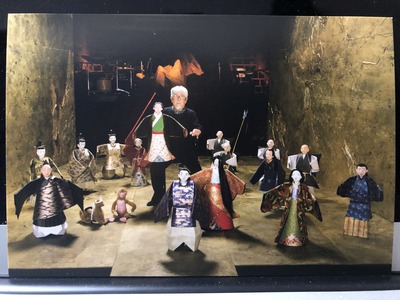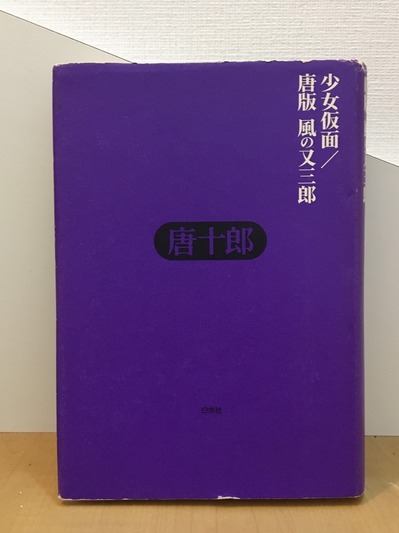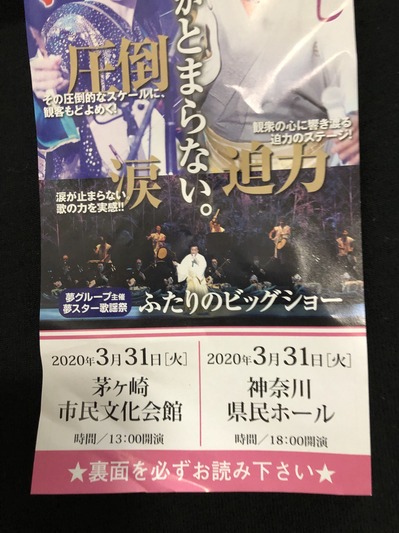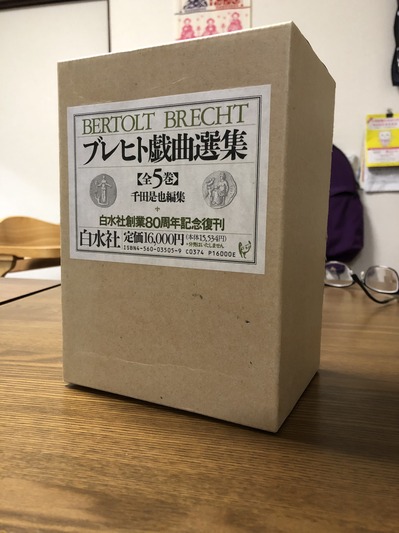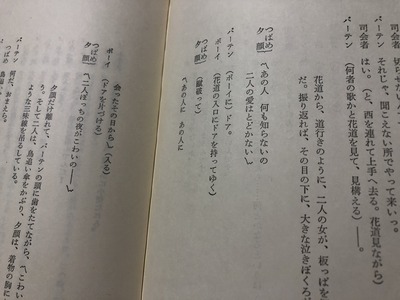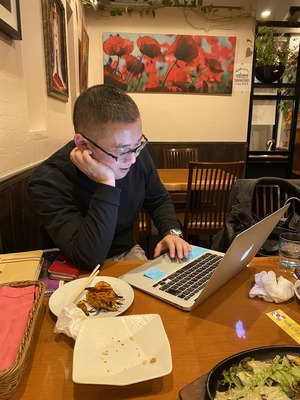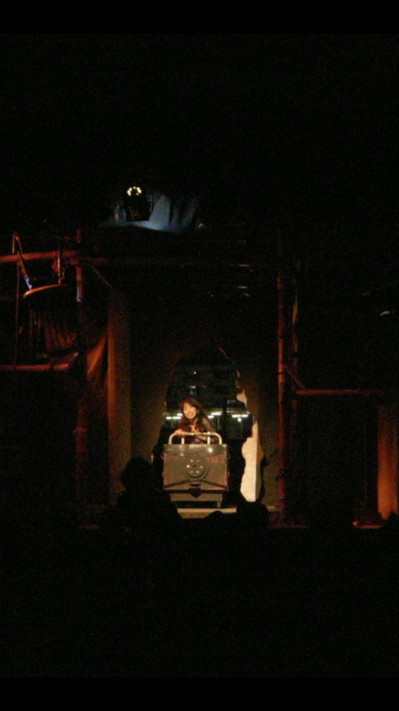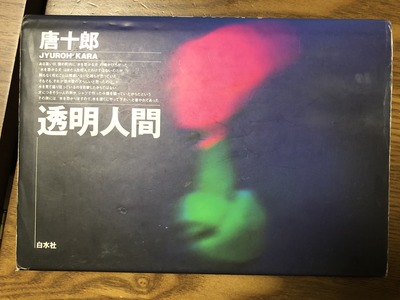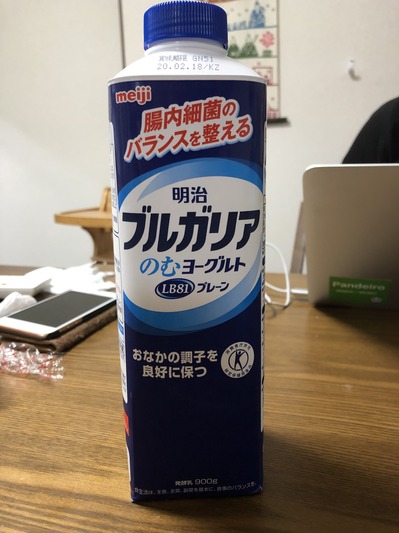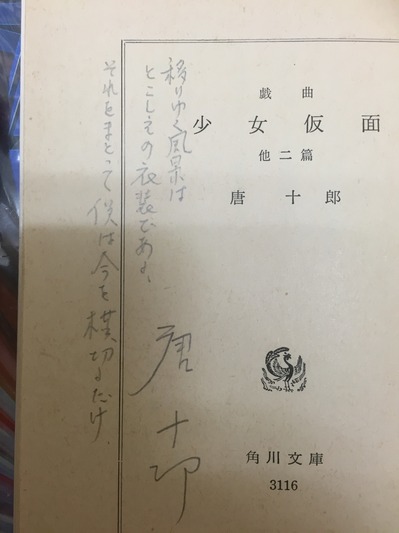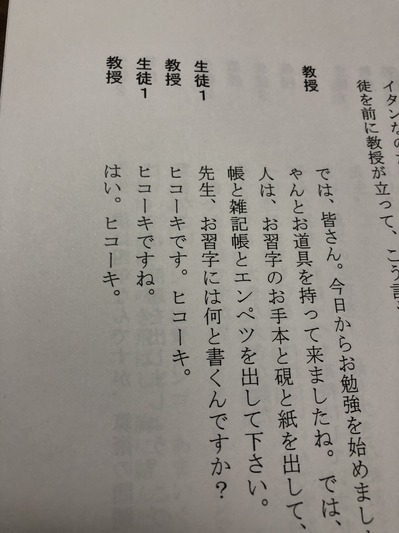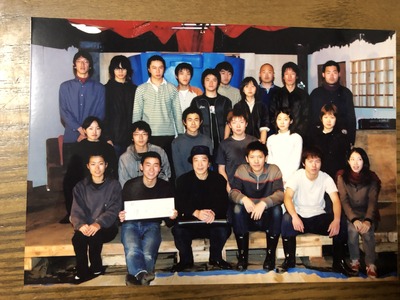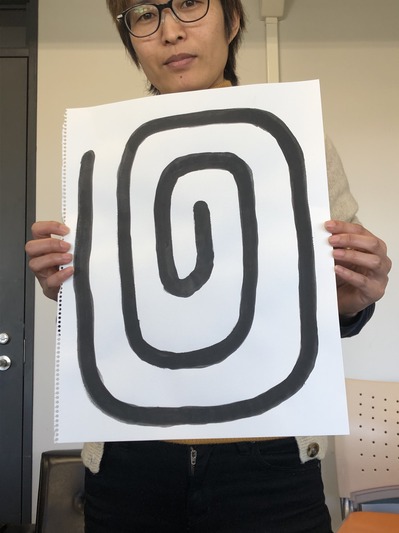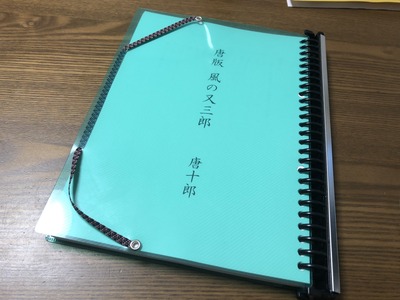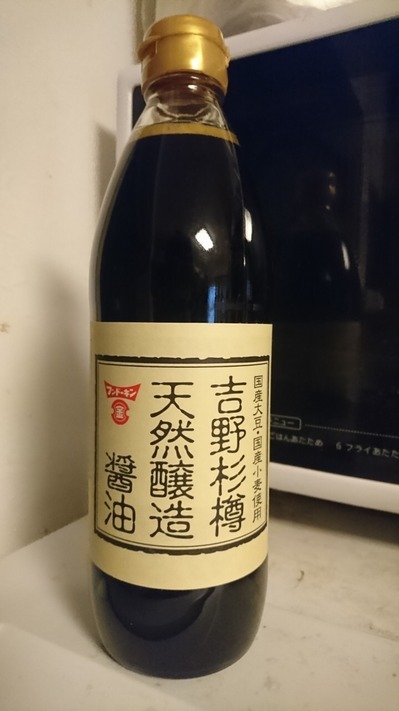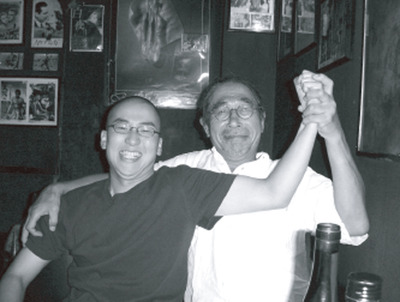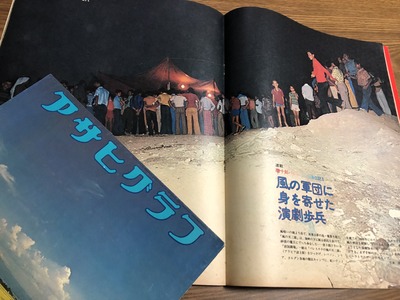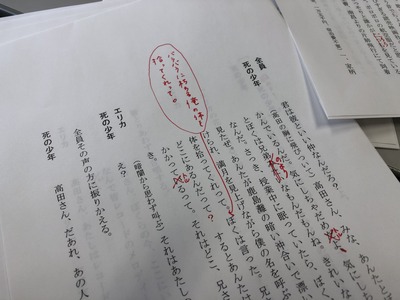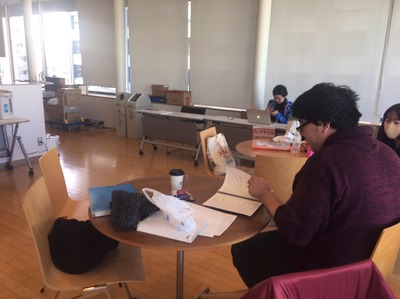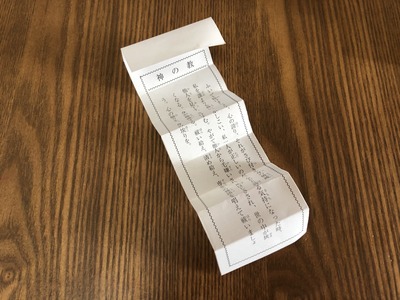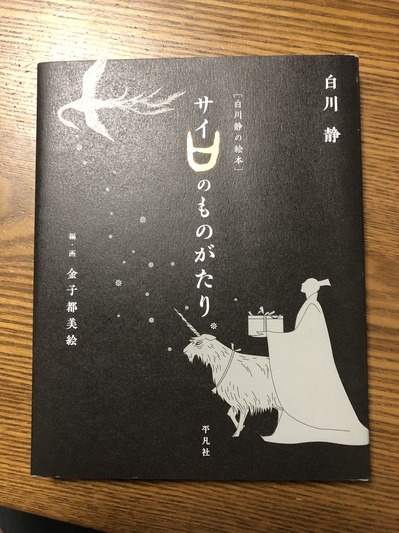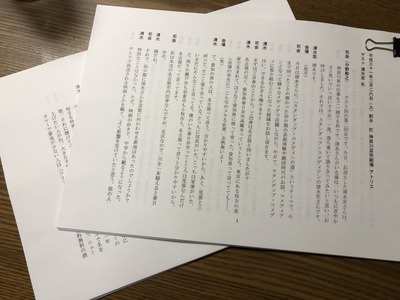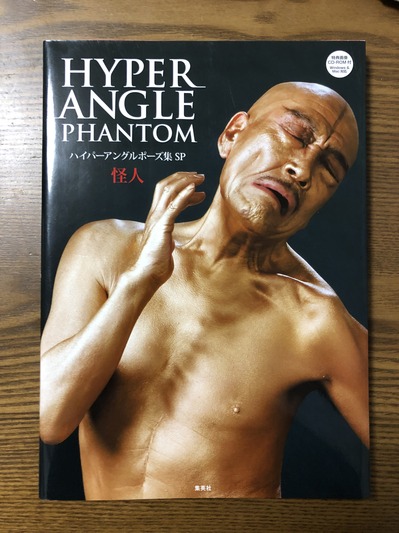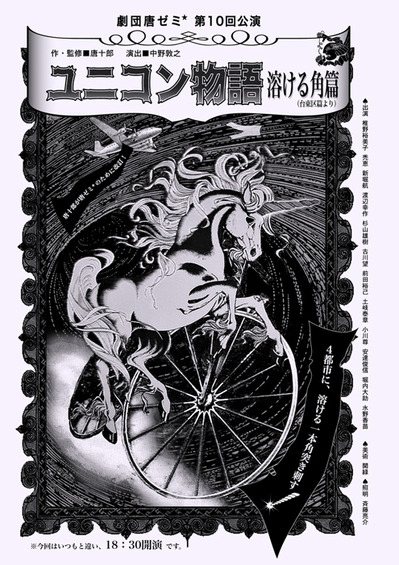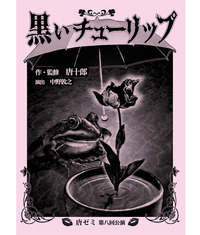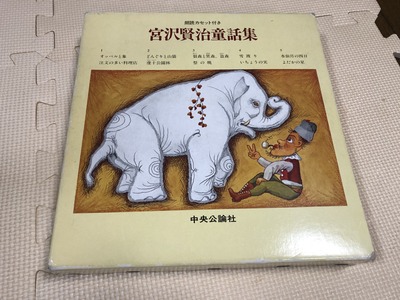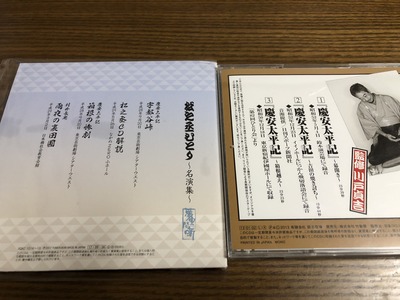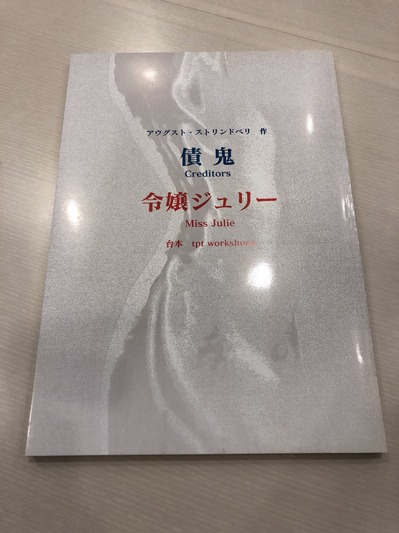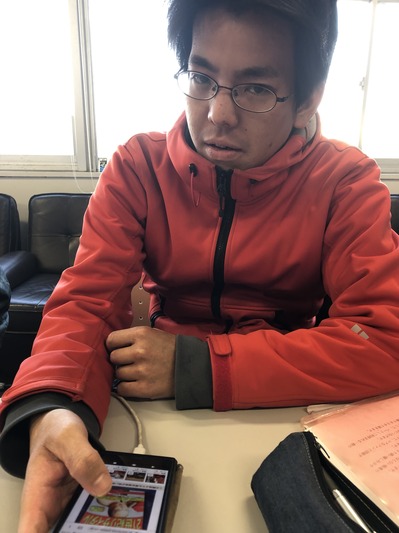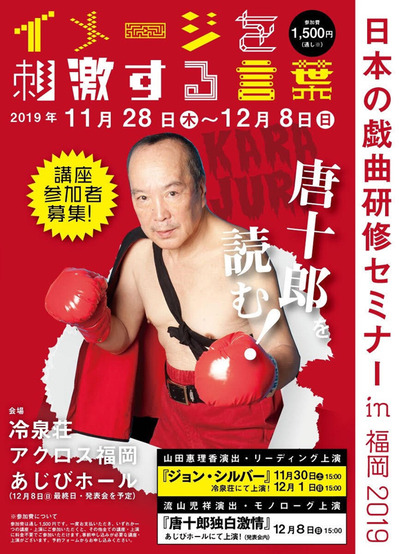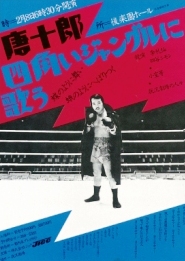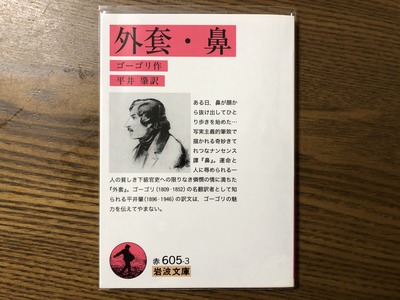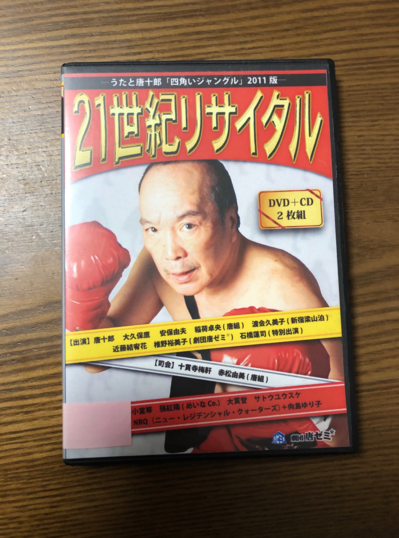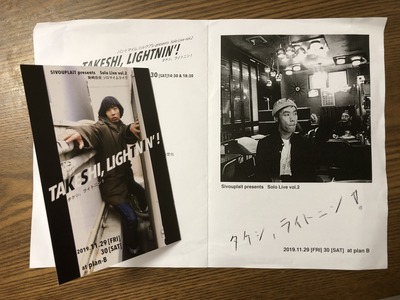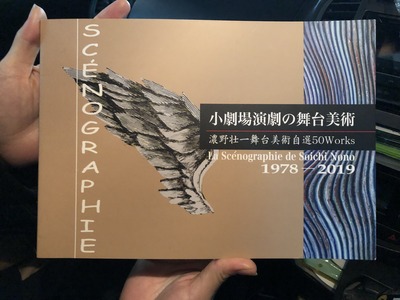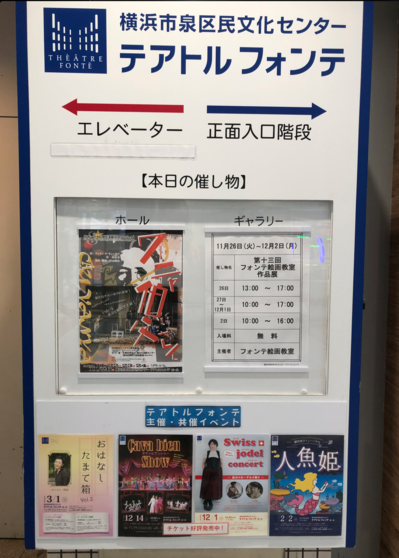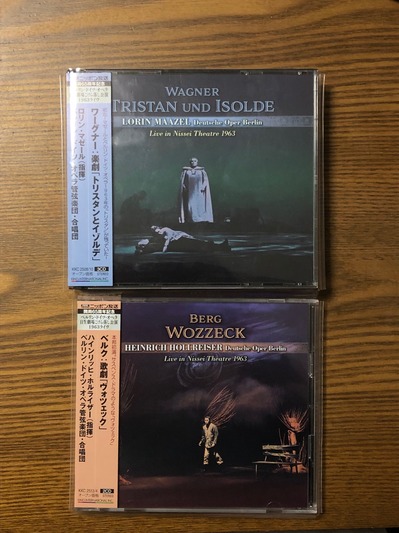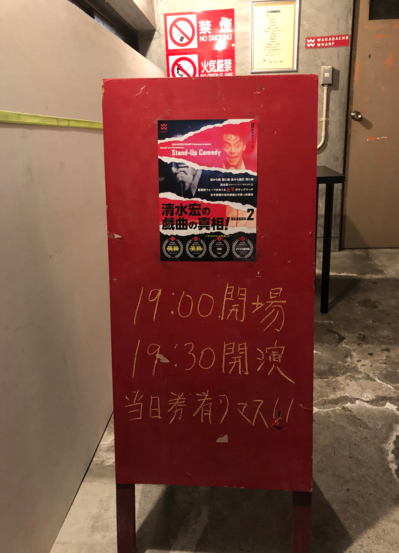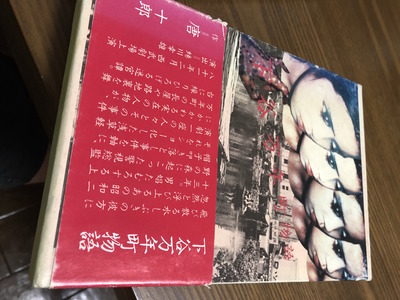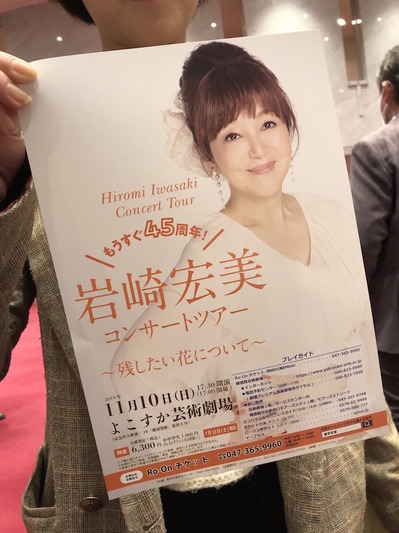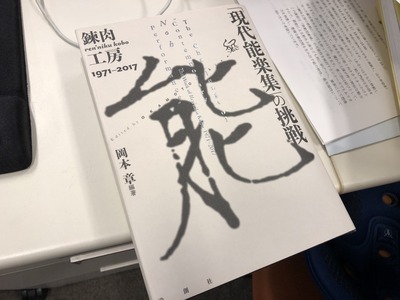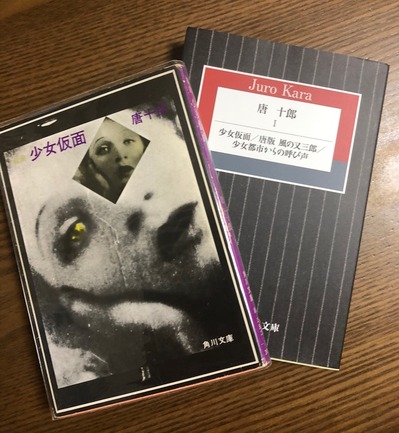7/26(金)エコー劇場4日目〜公演2回目
7/25(木)エコー劇場3日目〜ゲネプロ・初日
7/24(水)エコー劇場2日目〜場当たり
7/23(火)劇場入り〜セットがたつ
7/22(月)積み込み〜明日から劇場入り
7/21(日)若葉町WHARFから撤収!
7/20(土)最後の調整日
7/19(金)さらに通し稽古
7/18(木)今日も通し稽古
7/17(水)追い込み稽古、はじまる
7/16(火)若葉町WHARFへ
7/13(土)グラン・ギニョールの2場
7/12(金)結局、雷鳥の里!
いますでに、帰りの新幹線のなかです。
昨晩23:12に着いて翌日19:08に発つということは20時間の富山滞在で
あったということです。その間、いくつかの文化施設に行き、
運転もよくしつつ、かなり富山を満喫しました。
まず、昨晩は26:00までやっている店で食事しました。
白エビ、ウニ、ホタテの焼いたのを醤油をつけずに食べてくれと
店主に言われ、隣にいたおじさんが色々とツマミをご馳走して
くれました。
早朝から起き出し、周辺を歩いてまわりました。
例のオーバードホールのそばに行くと、記憶が蘇りました。
そして朝食。泊まったホテルに恵まれ、なかなか豪華でした。
そこで、ます寿司、ほたるいか沖漬け、焼き鯖。
その後、あらかじめ通達されたスケジュールによれば
昼食抜きとされていましたが、思ったよりも移動に
時間がかからないことがわかり、訪ねた先でアジフライを
ご馳走になりました。
・・・というなわけで、
振り返ってみればなかなかの豪遊な出張でした。
帰り道、なんとかお土産をと思いましたが、食傷気味のせいか
富山ものにはまったく食指が動かず、大好きな「雷鳥の里」を発見。
これは長野のものだけれど、
かつて何度も行った長野公演の際は、スーパーで小さいのを
買って常食するほど私はこれが好きなのです。
名物よりも美味いもの、というわけで劇団へのお土産は雷鳥の里です。
富山、良いところでした。
7/11(木)富山の思い出
7/10(水)今日の作業と残り時間
7/9(火)ハンディで作業中
7/6(土)読売新聞で紹介されました
7/5(金)再び全編を通す!
7/4(木)今日は稽古休み
7/3(水)ぜんぶ通した
7/2(火)3場を通す
6/29(土)衣装を探しに
6/28(金)共働きについて
6/27(木)難問が解けつつある
6/26(水)3番序盤の難しさ
6/25(火)当時の春日野八千代さんを誰に例えよう?
6/22(土)1場の目処がたつ
6/21(金)「劇空間を再考せよ」を再考せよ
6/20(木)現代の古典
6/19(水)華麗なる罵倒語
6/15(土)先生の幼なじみ
6/14(金)稽古は1場の終わり
6/13(木)今日はタップダンスに挑戦!
6/12(水)元劇団員・重村の活躍
6/11(火)音楽を探して
滑り出しは、老婆と貝の冒頭シーン。
6/8(土)新潟の『唐版 風の又三郎』
6/7(金)明日はチケット発売開始!
6/6(木)本読みを終了、来週から立ち稽古
6/5(水)三場は難所
6/4(火)集合して公演準備がはじまる
6/1(土)久々に見つけたことば
5/31(金)ひとつ原稿を提出
5/30(木)朝からとんかつをペロリ
5/29(水)懐かしすぎる下井草
5/28(火)初夏のあらし
5/24(金)今日は美術打ち合わせでした
5/23(木)本読み2回目!
5/22(水)『風に毒舌』
5/20(月)今日は『少女仮面』本読み初日
5/16(木)LP版の『四角いジャングルで唄う』
5/15(水)原因は唐さんのあの歌い方ではないか!
↑このなかで唐さんが楽しく唄っています
『少女仮面』の劇中歌について考えています。
その中でどうも謎めいているのは、
喫茶《肉体》のボーイたちがタップダンスしながら歌う
『あの人にあったら』。
〽あの人にあったら、
そっと云ってほしいの
〝乙女の花が枯れたって
月経帯に千代紙はったって
女が一人うたってたって〟
でも、あのひとはもう来ない、
きっと来やしないのよ
だって、あたしゃ皆既日蝕〽
適齢期の女性にとってかなりキツい歌です。
閉経したのに好きな男に振り向いて欲しくて、
千代紙を貼って生理に見立てるなんて。
なかなか淋しい歌なのです。
問題はふたつあり。
①なぜか楽しげなメロディがついて嬉々として歌う例が多い
②初老の女性をオーナーに頂く店の店員たちがなぜこんな歌を
①はひとえに『四角いジャングルで唄う』で唐さんが
ものすごく楽しげに歌ったことに原因があると思います。
作者が歌うやり方を思わず正当と思い込みがちですが
しかしあれは、あくまでリサイタルですからね。
②の答えは稽古を通じて解決します。
実はもう、こうではないか、というアイディアを思いつきましたが、
稽古しながら検証するつもりです。
という具合に、唐さんが亡くなったショックで
止まっていた時間を動かそうと思います!
5/14(火)告別式でした
5/13(月)お通夜でした
5/11(土)超渋滞の2時間
5/10(金)知らなかった写真
5/9(木)『化粧論』の情報届く!
5/8(水)唐十郎のエッセイについて情報求ム!
5/7(火)今日の一歩
5/6(祝月)皆、紅テントを目指す
5/5(日)今日は沈黙
5/4(祝土)健気な野草
5/3(祝金)いつもと違う!
5/2(木)週末は『振袖火事の巻』!
5/1(水)『少女仮面』の美術
4/30(火)どうしようもない人間への讃歌
4/27(土)綾瀬に行く
4/26(金)川口成彦さんのショパンの一生
4/25(木)夜の公園にて
4/24(木)『オオカミ狩り』を聴いている
4/23(火)『オオカミだ!』KAAT公演が終わる
4/20(土)『オオカミだ!』2日目
4/19(金)『はまべのうた』だった!
4/18(木)『オオカミだ!』1日目
4/17(水)ヨルノハテのショーケースがはじまる
4/16(火)『横浜ローザ』を観てきた!
4/15(月)『嵐が丘』にて!
4/13(土)『オオカミだ!』稽古2日目
『オオカミだ!』の稽古はいつも短期決戦。
今回も4日間で仕上げるので、集中して稽古しています。
稽古2日目にあたる今日は、これまでにつくってきた段取りを
確認しつつ、今回の環境に合わせたやり方に変えていきました。
何しろ、初演からたった1年の間に4ヶ所で公演し、
その度にそれぞれの場所に合わせてバージョン・チェンジしてきた
演目です。アシスタントの黒子役も、SATOCOさん、
月岡ゆめさん、よし乃さんと、3人ものパフォーマーが
参加してくれました。今回は2代目のゆめさん。
必然、各バージョンの動きの違いは、
それぞれの黒子役の個性を活かすためのものでもあり、
だからこそ、今回の月岡ゆめさんには彼女ならではのやり方がある。
そういう稽古をしています。
KAAT公演にあわせ、
今回はテツヤさんがスクリーンを導入してくれました。
新たに加わった音響の大久保友紀さん、
舞台監督の吉成生子(よしなり たかこ)さんが、
こちらがお願いする変更にたちまちに応えてくれます。
そういうなかで、普遍的に『オオカミだ!』を良くする工夫を
盛り込んで、少しずつ少しずつ向上させていかれるところが
いつもの演劇とは違う幸せなところです。
ケッチさんをはじめとして、身ひとつで様々な環境で仕事を
続けながら芸を披露するパフォーマーの皆さんは、そうして
技や演目を磨いていくのだそうです。
何百回と本番を重ねるうちに
「なぜ、これを初めから思いつかなかったんだろう?」
というように、根本的パワーアップを果たすアイディアが
出ることさえあるそうです。
その時も待ちつつ、明日も稽古を続けます。
4/12(金)『オオカミだ!』稽古はじまる
4/9(火)『鐵假面』の遺産
4/6(土)真鶴・湯河原に行ってきた
4/5(土)『オオカミだ!』の台本を書いていた時
4/4(木)『オオカミだ!』の始まり〜ブライトンにて
4/3(水)『オオカミだ!』KAAT公演迫る!
↑日本大通り沿いに大きなポスター!
気づけば、『オオカミだ!』KAAT公演が2週間後に迫っています。
『鐵假面』の片付けがやっと終わり、
『少女仮面』を急いで仕込んでいるところですが、
これも私の勝負どころです!
思えば、2022にロンドンで構想を練り、
帰国後に横浜で創作して2023.2に本多劇場で初演、
その後、9月にザ・スズナリで再演のあと、
青梅の中学校や小笠原諸島のひとつである母島の小学校でも
公演を重ねてきた『オオカミだ!』です。
KAAT神奈川芸術劇場でも上演できるのがいかに幸せなことか!
下記の日時、料金、座組で挑みます。応援を宜しくお願いします。
『オオカミだ!』KAAT神奈川芸術劇場公演
4月18日(木) 19:00開演
4月20日(土) 14:00開演
4月21日(日) 11:00開演
料金(全席自由・税込):一般3,500円 小学生以下1,500円
*託児サービスは行っておりません。客席でご一緒にお楽しみください。
*乳幼児で席を使用しない場合は無料
出演:ケッチ(元が~まるちょば)
脚本・演出:中野敦之(劇団唐ゼミ☆)
アシスタント:月岡ゆめ
紙芝居原画:井上リエ
音響協力:平井隆史
企画:岡島哲也(ヨルノハテ)
提携:KAAT神奈川芸術劇場
主催:神奈川演劇連盟/ヨルノハテの劇場
4/2(火)弾丸帰省
3/31(日)角(つの)がたったらしい
3/30(土)水戸のバッタ
3/29(金)お別れがたくさん、そして初台から水戸へ
さて、それから新宿で晩御飯を食べ、『少女仮面』に必要な
3/28(木)公演後の仕事
3/27(水)『鐵假面』片付けも終了、残るは経理と報告書
3/2(土)トイレの数を数える
3/1(金)ワダ タワーも美術の腕を振るう!
2/29(木)米澤も作業中!
2/28(水)みんなで作業中!
2/27(火)ハンディラボで作業中です
2/24(土)明日は『腰巻お仙 忘却篇』第2回
2/23(金)この数日でやりたいこと
2/22(木)伏見行介×唐ゼミ☆写真展 横浜篇がスタート!
2/21(水)なんとか全幕通す!
2/9(金)オルガン&バレエ公演の合間に
2/8(木)昨日からオルガンのことを考えています

2/7(水)メガネよ、今までありがとう
2/5(月)杉田劇場に溢れたカオスの心地よさよ
それで、いつもなら今日はレポートの日なのですが、
昨日のお昼から夕方の体験が強烈だったので、
先にこちらを書きます。
横浜市磯子区の杉田劇場は私が特に親しくしているホールのひとつです。
自分が5年ほど前から関わっている
1/31(水)写真展の終わり
1/30(火)写真展6日目&『鐵假面』立ち稽古3日目

1/29(月)写真展5日目&『鐵假面』立ち稽古
1/28(日)写真展4日目! ギャラリートークの日
1/25(木)写真展1日目
1/24(水)写真展の準備 整う!
1/23(火)『鐵假面』〜立ち稽古をはじめました
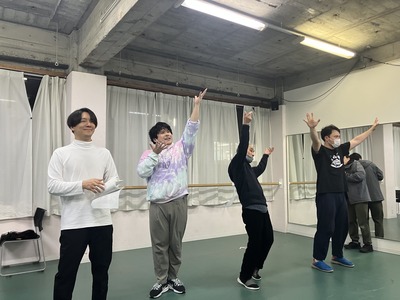
1/19(金)車にも休暇を
1/16(火)写真展準備と鉄仮面製作と稽古
1/12(金)ハンディラボ大掃除と美術打合せ
1/11(木)よみがえる堺と京都の記憶
1/10(水)大里先生の話とギャラリートークの準備
↑1/28(日は)ライトに楽しめるコミック・ソングをフューチャーします
今日、県民ホールでは週末の公演のリハーサルがスタートしました。
作曲家の夏田昌和さんと生誕150周年のA.シェーンベルクを共演させて
それぞれの作品を演奏するC×Cという企画です。
早朝に、エレクトロニクスを担当する有馬純寿さんの機材搬入をお手伝い。
初めて有馬さんとお話できました。ちょうど2001年に私たちがバッタと
格闘していた頃、有馬さんも横浜トリエンナーレに参加して激しく
プロジェクトにぶつかっていたそうです。
椿昇さんとも多くの仕事をしてきたということで、
これまで遠巻きにスゴい方だ!と思っていた有馬さんが一気に身近に
感じられました。
また、現代音楽雑誌の編集者時代にパリから戻りたての大里先生に
取材されたそうで、苦労した話を聞かせてもらいました。
自分の車になんとか機材を押し込んで、かなり愉しい移動時間でした。
それが終わると、ハンディラボに移動し、
今度の写真展で行うギャラリートークの中の劇中歌の稽古。
椎野と麻子が行うセッションをブラッシュアップしました。
工房では齋藤が鉄仮面の試作品を着々と作っており、
それによって、目指すオリジナルの仮面のかたちが見えてきました。
拘束感があって、シャープで、無表情で、
その無表情の下に演者の表情が渦巻いている。
そういう仮面を目指しています。
麻子と衣裳デザインの構想を練ったり、
サトウユウスケさんから新たな劇中歌伴奏が届いたりすると、
そういう一つ一つを吟味し尽くす時間が、もっともっと欲しい!
1/9(火)稽古しています
1/4(木)今年もやります『オオカミだ!』
1/3(水)痛恨の池ポチャ
1/2(火)スライドショーづくり
1/1(月)今年もよろしくお願いします
12/29(金)フルートの神様
12/28(木)すべての段差が眩しい!
12/27(水)唐十郎流、音楽と劇作
12/22(金)「あっぱれフェスタ」が終わる
12/21(木)浮かびあがる「鐵」の文字
12/15(金)「あっぱれ・フェスタ」まであと1週間
この秋から、複数回に渡って横浜市旭区の福祉施設 「空とぶくじら社」に通っています。この施設名、実に良い名前。
きっかけは、カプカプひかりが丘の鈴木励滋さん。 旭区内の福祉施設が集まって毎年開かれたきた「あっぱれフェスタ」 の名物コーナーD-1グランプリ(Dは演し物のD!)に挑む 空とぶくじら社のアドバイザーを引き受けることになったのです。
夏に顔合せを行って、 本格的に演し物を構想し始めてから、今日で4回通いました。 その間に、演歌歌手になるのが目標のHさんと踊りを踊りたいYさん のデュオ・ショーを作り、それから皆さんの合唱、という 2つのコンテンツを軸に全体の流れを考え、整えてきました。
今日は施設での最終稽古。 あとは現場でのリハーサルと本番を残すのみでした。
朝に私が到着すると、皆さんはかなり緊張していて、 自分が観にくるのに備えて準備を進め、そうやってドキドキ して待っていてくれたのをひしひしと感じました。
こちらは、皆さんにリラックスしてフルパワーが出せるように なっていて欲しいのに、やっぱり緊張感を与えしまっているなとも 思ったし、それはそれで超えるべきハードルとしてこの場にいれば 良いのかな、とも思いました。
そして、なんだか、私たちの学生時代に 唐さんはこんな気持ちだったのだろうかとも考えました。
大学生時代、 ゼミナールのある木曜日に唐さんがやってくると、 通し稽古に何とか私たちはそうれはもう緊張していました。 今にして思えば、唐さん自身は活き活きと演じてくれよと 願っていたと思いますが、そんなことに気がまわる余裕もなく、 喉をカラカラにしながら通し稽古を見せていたはずです。 空とぶくじら社を通し稽古を通じて、そんな記憶まで蘇りました。
1度通してからはすぐに修正点を出して、それからもう2度、 10分のショーを繰り返しながらブラッシュアップしました。 こうなるとこっちも懸命で、他のことは何にも考えなくなり、 後して、けっこうスパルタだったなと思いました。
次の木曜夜に会場の旭公会堂でリハーサルをして、 12/22(金)に本番です。初参加なのも手伝いすごくたのしみです。 仕上げに客席から、みんなに掛け声をかけたいと思っています。
12/14(木)ザクの声を聴け!
12/13(水)年末年始に向けて
12/12(火)フランチェスカよ、先に言え!
12/8(金)大野さんに会えた
12/7(木)ローエングリンの鳴る床屋
というト書きを書いています。あの壮大さをギャグにしているような
12/6(水)これも唐さんから教わっていた!
12/1(金)祭のあと
11/30(木)一人芸の世界
11/29(水)スコーンがやって来た
11/28(火)気になる『少女都市』
11/24(金)健さんの復活!
11/23(木)無意味の世界
11/22(水)シュガータウンは恋の町
I got some trouble, but they won't last
I'm gonna lay right down here in the grass
And pretty soon all my troubles will pass
'Cause I'm in shoo-shoo-shoo, shoo-shoo-shoo,
shoo-shoo, shoo-shoo, shoo-shoo Sugar Town
唐さんはこんな風に替え歌しています。
〽誰か私に教えて
かわいいベビーのつくり方
やさしい母さんになりたいの
ここはシュシュシュ シュガータウン
現在は30代で結婚、40歳前後で初産も珍しくありませんが、
当時は20代で結婚し子どもを産む時代、今より早く大人になる
時代だったでしょうし、定年も55歳という世の中です。
(今では考えられん!)
それに、同棲ブームによって、妊娠→中絶が若者世代に
溢れた時代でもありました。それが唐さんとその周辺にとっても
生々しい話題であったことは、初期のアリババや『腰巻お仙』
シリーズを読めばすぐに察せられます。
『Sugar Town』はyoutubeでも簡単に聴けますから、
ウキウキと聴いてもらいたい唐さんオススメのポップスです。
同時に、このメロディに少女のアイロニーを混ぜ込んだ
唐さんのブラックユーモアも、歌詞をあてはめて
愉しんでもらいたいところです。
11/21(火)1967年の唐さんの事情
11/17(金)唐さんのサイン
11/16(木)喫茶ヴェロニカ
11/15(水)写真展やります!
11/10(金)『腰巻お仙 忘却篇』のことも思い出してしまった
↑3月に初演して面白かったので4月にも上演しました
『腰巻お仙』シリーズについて想いを馳せていると、
これが台本としてはなかなか破天荒だけれど、
実際に上演してみると笑いが多く起こって、
稽古の現場までもがとにかく面白かったことが思い出されます。
正確にいうと、
『腰巻お仙 義理人情いろはにほへと篇』の頃は自分たちがまだ青くて、
余裕がなくて、しゃっちょこばってばかりいたので、どうにも
硬かったのですが、30歳に差し掛かる頃から徐々に余裕を覚え、
ふてぶてしさ、図々しさが身につくようになり、
お客さんもよく笑ってくれるようになりました。
なかでも思い出深いのは学生たちとつくった『腰巻お仙 忘却篇』で、
これはもう、稽古のさなかにも膝から崩れ落ちるほど笑いました。
あの時はなにしろ、集まった学生たちがすこぶる優秀だったと
思わずにはいられません。彼らは地面に埋められたり、
人形を使って屋上から飛び降りたフリをしたり、
チケットがわりの石を投げつけられたり、
照明が壊れたという設定で自転車を漕ぎ続けて
共演者に必死のライトを浴びせたり・・・。
とにかく真面目かつ余裕を持って演じてくれました。
ふざけているのではなく、杓子定規すぎもしない。
要するにそれはユーモアに満ちていたということです。
書いていてさらに思い出しましたが。
1メートル以上の高さのある帽子をかぶったり、
リアカーをくくりつけた自転車を転がして坂道を全力で駆け降りたり、
自分の転がすリアカーに轢かれたり、
バリカンで頭に星型のハゲをつくったり。といったこともしました。
自分が本読みWSで『ジョン・シルバー』シリーズを熱心に
取り上げつつも、『腰巻お仙』シリーズを避けていたのは、
これらの現場感がちゃんと伝えられるか心配していたからだと
思い至りました。でも、本読みだって、実際に声に出しさえすれば
あのウキウキ感がやってくるのではないかと思い、やってみたいと
考えるようになりました。おどろおどろしく受け取られがちな
演目ですが、あれこそ世の中を明るく照らす芝居です。
11/9(木)これが初掲載だ!
11/8(水)文字のチカラ
11/7(火)ガンダムの角 始末記
11/3(祝金)唐さんの好きな短編
11/2(木)写真でお届けするここ1週間
11/1(水)21年後の新たな『糸女郎』
10/27(金)オルガンのハロウィン・ナイトだった
10/26(木)タルコフスキーの音響センス
10/23(月)ぼくらの500円銀貨
10/20(金)影破里夫だった財津一郎さん
10/19(木)青梅の中学校で公演してきた!
10/18(水)写真家・伏見行介さんの来訪
10/13(金)唐十郎流、魚のチョイス
10/12(木)三たび『オオカミだ!』
10/11(水)床屋自身はセルフカット
10/6(金)ドリプロ発表会の準備をしながら
10/3(火)改名の過酷さについて
9/29(金)みどりのおばさんに扮する
9/28(木)観劇三昧
9/27(水)『秘密の花園』考〜モーツァルト12歳のオペラ
9/26(火)『秘密の花園』を上演するとしたら・・・
9/23(土)安保由夫さんが亡くなった日
9/19(火)ロンドンでできた友人に会う
9/17(日)我慢のはじまり
↑はじめて奮戦中
息子があと1週間で7歳になります。
7年前、私は横浜国大の丘の上にテントをたて、
『腰巻お仙 振袖火事の巻』の通し稽古に臨んでいました。
朝5時頃に産気づいたと連絡があり、昼に息子は生まれました。
あれから7年。
彼が誕生日プレゼントに望んだものは、
「メザスタ」というポケモン系ゲームのタグでした。
それ自体は600円ほどで、さして高額とはいえない品物です。
誕生日当日に私がフリーである保障がない以上、
与えられるうちにセレモニーは済まさねばなりません。
安いな、と内心思いながら買ってあげると、彼はタグを買った
イオンに入っているゲームセンターへと歩を進めました。
そうです。
このタグはゲームを進めるためのとっかかりに過ぎず、
ほんとうの勝負と予算投下はここから始まったのです。
彼はタグに込められたモンスターを駆って勝負し、
新たなタグを手に入れて嬉々としています。
まるでパチンコ玉や麻雀の点棒が自分の手元に集まって
くるのにホクホクするオッサンのようです。
500円、1,000円、1,500円・・・が
あっという間に吸い込まれ、タグに変わりました。
長い闘いになりそうです。
彼はこれから、手元のタグが誘いかける禁断症状との格闘、
我慢を始めなければなりません。酒であれ、色欲であれ、
ギャンブルであれ、時にはチョコレートやアイスクリームにさえ。
人は必ず何かに依存します。要は程度問題です。
彼はあるところで折り合いをつけられるようになるのか、
自分はあまり偉そうなことは言えないな、と思いながら
これからを見守ることにします。
9/15(金)見えない部分を強化
9/14(木)萩尾望都の世界に入門中
9/13(水)大島幹雄さんより
9/12(火)『オオカミだ!』をやりながら行ったこと
9/8(金)自分のいない本番も盛り上がっている
9/7(木)『オオカミだ!』初日
9/6(水)ザ・スズナリに入る
9/5(火)『オオカミだ!』稽古、その他
ROY ORBISON
"THERE'LL BE NO TEARDROPS TONIGHT"
9/1(金)医者に行く頃にはたいがい少しマシになっている
8/31(木)鷹さんの教え
8/30(水)下北沢にも行く!
8/29(火)夏稽古、追い込みの1週間
8/25(金)『オオカミだ!』と巨大バッタ
8/24(木)謎の歯痛が去る
8/23(水)直近の稽古から
8/22(火)すじ鉾に首ったけ
8/18(金)なぜかこの巨匠たちと
8/17(木)これもまたイギリスの効能
8/16(水)発見!幻の『性病部隊』! その②
8/15(火)発見!幻の『性病部隊』! その①
8/11(金)成功!オイディプス・リベンジ
8/10(木)清水宏と唐十郎を語る
8/8(火)怒涛!狂い咲き6輪!
春日野
あたし、今、廊下に血をこぼしちゃったの......
まるで季節はずれのひな祭りね、ここ五年、もうなくなってたのに、
あの水のみ男にシャツをひっちゃぶかれたら、
狂い咲きのように始まったのよ。
ああ、そこいらの男の子と死ぬの生きるのってジタバタしたいなあ。
8/7(月)ザ・怠惰。オレの夏休み
8/4(金)苦渋!『オイディプス』
8/3(木)薛珠麗さんが亡くなった
8/2(水)『オオカミだ!』スズナリ公演と夏稽古2日目
8/1(火)夏の稽古を始めました
7/28(金)清水宏さんの公演に出ます
↑これがチラシ!隣町珈琲という、清水さんがずっと発表の場に
してきた会場に自分も乗り込みます
今日は夕方に小田原に行きました。
たまたま今日は、パンデミック以来ストップしていた
真鶴町の貴船祭が復活する日であり、その影響が渋滞に及ぶのに
ビビった自分は、珍しく電車で行くことにしました。
ですから、帰りの電車の中でこれを書いています。
真鶴町で思い出すのは、5年前にスタンダップコメディアンの
清水宏さんとつくった「真鶴ばなし」です。
激烈で真剣な清水さんの人間性と作品創作に伴走して
我ながら熱い夏でしたが、それだけに手応えがあり、
神奈川県域でイベントを仕掛ける事業を始めたばかりの自分にとって
その後の指針となった企画でした。
町の人に生々しく食い込むことは大変だけれども、実り多い!
以来、清水さんとの共同作業はいくつもあって、
その度に大冒険をしましたが、常によく話し、よく語り合う
ヒリヒリする創作であり続けました。
そんな清水さんが、ご自身の主催するスタンダップコメディの会に
自分をゲストとして呼んでくれます。
題材が「三谷幸喜vs唐十郎」ということで、
8/10(木)19:00から荏原中延の隣町珈琲で繰り広げられる
清水さんの話芸の後に、自分も加わってアフタートークします。
詳しくはこちら
三谷さんと唐さんを並べて語られるのを聞くこと自体
初めてなので、清水さんが繰り広げる世界をよく聴き、
よく受け取って、インプロで切り返せたらいいなと思います。
果たして清水さんの切り口は?
それに自分は上手く切り返せるだろうか?
出たとこ勝負でいきます!
7/27(木)相模湖に行ってきた
7/26(水)夏とボールペンの罠!
7/21(金)曹操の詩
↑三曹の詩だけでなく『出師の表』も収録されたお得本です
先日、Amazon UK プライムを騙る者によって不正な引き落としを
発見しました。対策として、直ちにクレジットカードを凍結し、
新たな番号によるカードをつくることにしました。
それで、銀行に行きました。事情を説明して再発行の手続き。
その合い間に、本屋にも行きました。
銀行が横浜駅西口にあったので、地下街の有隣堂に。
今日の収穫は『曹操・曹丕・曹植の詩文選』です。
カエサルの『ガリア戦記』。
マルクス・アウレリウスの『自省録』。
二つの好きな本に並んで今回の詩集に共通するのは、
著者たちがいずれも激しく現世的な現場でそれらを書いたことです。
だから自分はこれらに痺れます。
私は毎日、朝に目を通した文章やせりふを
昼間に街中や劇場をウロウロしながら読んでいます。
人や風景に接する中に、本を読む作業もあるように思います。
今日は打ち合わせをし、書類をつくり、いくつもの連絡をし、
みなとみらいホールで中田恵子さんのオルガンを聴き、
下北沢で清水宏さんの主催するカルト宗教をテーマにした
スタンダップコメディを観ました。
帰りの電車が混んでいたので、立って曹操の詩を詠みます。
小さな声でブツブツ。武蔵小杉を過ぎたら席に座れたので、
このゼミログを書きます。
書き終わる前に横浜駅に着いてしまったので、
ホームのベンチでこれを書ききります。
帰宅してしまうと食べ物に手が伸び、食べ終わると眠くなるからです。
自分にとって悪くない日常です。
曹操の詩を詠むと、それが良い日常にも思えてきます。
7/20(木)9月にスズナリで『オオカミだ!』再演
7/19(水)味の素の逆襲
↑これも「味の素」製品でした
最近、関内駅のそばに新たなラーメン屋を発見しました。
「水嶋」という店で、無化調を謳っています。
「無化学調味料」ということで、これは要するに化学調味料を
使っていないという宣伝文句です。
食べてみると、なるほど味がやさしい。
が、一方でメニューに目をやると「昭和のラーメン」という
ものがあって、これはどういうものかと店員さんに訊きました。
すると、「『昭和のラーメン』には化学調味料を入れます」
との回答。あまりにサッパリそれを言うので面白くなり、
後日、劇団員の津内口を誘い、自分は「昭和の〜』を頼んで
食べはじめに二つを飲み比べました。
化学調味料はなるほど、ズキリとパンチが出て後味が残ります。
要は、ずっと食べてきた中華料理のあと口。
これが化学調味料、つまり「味の素」だ!
と、ここまではっきり違いのわかるお店のシステムに
感心しました。
ところで、この「味の素」。
バブル期からグルメブームを牽引した漫画『美味しんぼ』では
徹底的に敵視されてきました。あれは、舌をビリビリさせて
ずっと日本人の味覚をバカにしてきた。と、そんな論調。
けれどもよくよく考えてみたら、
スポーツ選手やパフォーマーなんかが飲むサプリメント
「アミノバイタル」も会社「味の素」の製品なんですね。
調味料としての「味の素」と「アミノバイタル」。
両方ともアミノ酸を扱っていて、でも、そのイメージは
ずいぶん違う。自分も疲れて、アミノバイタルを
すがるように飲んだりします。
目下、取り組んでいる『鐵假面』には「味の素」社の
社員たちが大活躍します。
中には「『味の素』は泥でできている!」なんていう、
いかにも都市伝説的な、ちょっと酷すぎるせりふもあって、
本当の「味の素」社には申し訳ないですが、笑わせます。
でも、アミノバイタルの印象を思うと、ちょっとイメージが
違いますね。かたちを変えて、やはりアミノ酸を操る
「味の素」社にゾッコンなんだと思わずにはいられません。
ラーメンは次は無化調を食べるだろうけれど、
やっぱり、「味の素」には形を変えてお世話になっています。
7/18(火)ダイアンからの返事
7/14(金)あこがれのギリシャ
7/13(木)9月の『鐵假面』公演を2024年3月に繰り延べます
7/11(火)まだあった!英国の罠!
7/7(金)今日はギャビンのお祝い!
7/6(木)京都行き、普通の日帰り出張
6/30(金)明後日から『夜叉綺想』
6/29(木)許光俊先生のこと
6/28(水)エアメイルを出す
↑一緒に出かけた時の写真
ダイアンの誕生日が迫っています。
彼女の誕生日は7/3。この1ヶ月、ずっと気になっていました。
そろそろカードを送らなければならないな、とか、
かといって早く着き過ぎたり、遅れて届くのもカッコ悪いな、とか。
ダイアンは、いつも自分に届く贈り物やカードを
戦利品のように陳列していました。
彼女の気に入りのリビングには暖炉型の暖房があり、
その上にそれらを並べるのです。
母の日(3月下旬)、誕生日、クリスマスとそんな具合でした。
大量のカードを並べておいてソファに寝そべり、
テレビを観ていたダイアンを思い出します。
あと1週間というところまで迫ったので、
仕事で行っていた小田原での合間に買って持っていた
カードに記入をして、やっと郵便局に持って行きました。
実は、海外にハガキを送るというのは初めての経験でした。
大昔、それこそ高校時代に手紙を出したことはあったけれど
それだけの昔のことですから全くやり方を覚えておらず、
ネットで記入方法を検索して書き込み、窓口に持って行きました。
その切手代にびっくりしました。
なんと70円なのです。安い。安すぎる。
日本国内が63円で、ロンドンが70円とは!
これまでの自分の不明を恥じています。
そうと知ってりゃ、さっさとたくさんのハガキを出したのに。
これからは、もっと送ろうと思いました。
こんなにライトなものだなんて。
それにしても、去年の誕生日には一緒にムンク展と
インド料理屋に行ったダイアンは、
果たして元気にしているのでしょうか。
6/27(火)室井さんの会は唐ゼミ☆大集合だった
6/23(木)小山くんを待ちながら、ふと訪れる学生時代
明日はいよいよ室井先生の横浜追悼会です。
最後の最後で、映像作家の小山祥平くんが頑張ってくれています。
資料の編集は大変な作業ですが、追い込みをかける彼を待ちながら
チェックを繰り返しています。
そして、気分が学部生時代のようになってしまった結果、
ついに唐さん関係の本を読み始めてしまいました。
『駈ける男の横顔-大庭みな子対談集(中央公論新社1984.6刊 )』です。
これは実は、ずいぶん前に買って読まずにきた本です。
何人もの著名な人たちが男女関係をテーマに平岩さんに
インタビューを受ける中で、唐さんもその一角を占めています。
冒頭で『佐川君からの手紙』に触れていますから、
1980年代半ばの初出です。前々から読もう読もうと思いながら
流されてきたものを、小山くんの作業を待ちながら
やっと通読することになりました。
唐さんとの対談部分はわずか20ページですが、侮れない本でした。
『佐川君からの手紙』以上に、これは『秘密の花園』の
創作の秘密が明かされているという点で、第一級の資料です。
そこには、
唐さんの従兄弟の名が「アキヨシ」であること(主人公そのまま!)
アキヨシさんは夫と子どものいるキャバレーの女に入れあげたこと
(子どもがいることの他は、そのまま!)
肉体関係は無いのに貢いでいたこと(そのまま!)
が明かされていました。
また、実在のアキヨシさんは、
当の子どもの子守りさえしたそうなのです。
そして、多くの親戚が彼を止めとうとしが頑として
彼女との関係を貫いたこと。それでいて、2年が経った頃に
アキヨシさんにも気持ちの変化が生じ、
芝居と同じように関西への転勤を申し出たところ、
その女性からは「あ、そう」のひと言で片付けられてしまったことが
つづられていました。(劇とは正反対!)
唐さんはそこから、
あの、トイレに行って首を吊ってしまうヒロイン・いちよを、
実際とは反対の男女関係の成り行きを構想したらしいのです。
面白いのは、本物のアキヨシさんが子守りまでしていたことで、
ここに「ねんねこ男」「いちよの夫・大貫」の要素が含まれているのを
特に面白く読みました。
嗚呼、学びの時間よ!
小山くん、もう一息だ。ガンバレ!
6/22(木)久々に杯一食堂に来た
6/21(水)こんな写真が出てきた
6/20(火)写真の哲学のために
6/16(金)世の中には美味いナルトもある
6/15(木)四方田犬彦さんの新刊
6/14(水)あのファックスは何だったのか?
6/13(火)久々の日本丸
6/9(金)小田原での二日間
6/8(木)室井先生追悼の会の準備
6/7(水)ちょっと弱っているので勇気の出る一言
6/6(火)ピーターからのメッセージ
6/2(金)本棚のホフマン全集
↑唐さんが持っていた創土社の全集。インパクト大の装丁!
昨日の夜、ホフマンについてお話しする機会がありました。
ドイツ文学における後期ロマン派の作家として活躍した、
あのE.T.A.ホフマンのことです。
自分は本当の専門家では無いのですが、
集まっている人間の中ではよく読んでいる方だったので、
10分でホフマンについて説明して欲しい、
というオーダーに応えることにしました。
18世紀の後半に起こったロマン派のムーヴメントについて、
ナポレオンやベートーヴェンや絵画の印象派や
もちろん、ドイツ文学史上の先輩であるゲーテやシラーを紹介しつつ、
ちょっと変わり者の後輩としてのホフマンを紹介しました。
私がホフマンをよく読んでいたのは20代半ばのひどく暇だった頃です。
あの頃、バルザックやドストエフスキーとともに、よく読みました。
そして、その背後には、確実に唐さんの影響がありました。
大学に入ったばかりの頃に緊張しながら唐さんの研究室を
訪ねると、そこにはまだ、後にできる小さな木組みの
ステージや暗幕はなく。タイル床とじゅうたん敷きの
スペースが半々になっていました。
壁一面の本棚に本はなく、ただそこにぽつんと、
創土社のホフマン全集のみが置かれてありました。
きっと唐さんが、室井先生にリクエストして
慣れない研究費の活用で古本屋から買ったのかも知れません。
大学1年の頃の自分に、ホフマンは未知の作家でした。
ただその装丁のサイケデリックなことと、
唐さんが好きなのだから必修課題であることだけが
インプットされました。
後から考えたら、2000年春、
唐組がホフマンの『黄金の壺』『砂男』に想を得た
『夜壺』を初演した背景には、あの全集が一役買っていたのだと
思います。あの全集は当時から貴重品で、自分は文庫本や
国書刊行会のものを掛け合わせて一作一作を読んでいきました。
皆さんの前でホフマンを語ることができたのも
そういうわけで、唐さんのおかげなのです。
6/1(木)車の6ヶ月点検と唐十郎
5/30(火)読売新聞夕刊!
5/26(金)おもしろいのは"使者"
5/25(木)恐怖!クギ3本の罠!
5/24(水)初めての山羊
5/23(火)『鐵假面』研究の日々
5/19(金)大阪の夜
5/18(木)『RIO BRAVO(リオ・ブラボー)』を観る!
5/17(水)『二都物語』に寄せられた情報
5/16(火)みんなの2022年
唐ゼミ☆、ハンディラボで集合しています
ハンディラボに集まって夏の稽古日程について話し合ったり、
zoomで台本を読んでいます。
タイトルが『鐵假面』ですから、必然的に最も重要な道具は鉄仮面です。
その造形をどうするか。本読みを通じて
どうすれば効果的になるかを探っていきます。
去年、イギリスにいた時にはずいぶん鎧兜を見ました。
そういう中で参考になるものを見せたりもします。
ヨーロッパで流布していた鎧を眺めていると、
剣や槍や矢で刺されないように隙間を塞ごうと必死です。
しかし、隙間を塞ぐほどに重量は増し、可動域は減り、
これでホントに身動きが出来たのだろうかという仕上がりです。
人間の必死は、それを俯瞰で見るとコミカルに見えます。
ひとつの芝居を巡って延々と考え、話している風景も似たようなものか。
時には、2021年に『唐版 風の又三郎』に出てくれたメンバーと再会し、
旧交を温めたりもしています。
ワダ・タワー、佐藤昼寝、赤松怜音、渡辺景日、鷲見武。
みんなゴッツくなっています。
体格ではなく、存在というか、肝が太くなった感じがしました。
あれから一年半経つ間に、多くの出演を重ねたそうです。
自ら企画を手がける立場になったり、逆に所属団体がピンチになったり、
舞台以外の声優の仕事に盛んに挑んでいるという話も聞きました。
それぞれのチャレンジ、時には修羅場を潜り抜けてきた事が
伝わってきました。
自分はイギリスにいて、時間が飛んでいるような感じです。
行動が連続していないので断絶した感じ。
あの11ヶ月がどういう風に自分の行いに影響してくるのか。
公演準備が進むと見えてくるはずです。
劇団員の齋藤は私たちの集合場所であるハンディラボを活用して
仕事をしていたそうです。他の団体の舞台監督を受けてやっていた。
重点的に掃除をしたらしく、倉庫の中の空気がキレイになった感じが
しました。具体的に動いていると、皆の変化が見えてきます。
5/15(月)『二都物語』本読みWS 第2回レポート
5/12(金)盛れば盛るほど
5/11(木)青梅で思い出した唐十郎作品
5/10(水)透明人間は囁く
唐組『透明人間』の花園神社初日を観ました。
5/5(祝金)今日は『秘密の花園』のために
5/4(祝水)ヘラ絞り、その底無しの魅力
5/1(月)すごいぞ!ディノサファリ
↑想像していたよりデブちんで可愛らしい体格! アンキロサウルス
本来であれば、今日は昨晩のワークショップのレポートをする日です。
が、昨日のお昼に観に行ったショーに大興奮したので、
その話題を先に紹介します。『愛の乞食』最終回は明日にしましょう。
もともと、東横線に乗りながら『恐竜ライブ ディノサファリ』の
中吊り広告を発見しました。何がソソると言って、
"動くトゲトゲ戦車"鎧竜アンキロサウルス初登場!と銘打ってあります。
そして、当のアンキロサウルスの姿がシークレットになっていました。
アンキロサウルス・・・
私は恐竜に興味がありませんでした。
多くの子どもたちが恐竜を好きらしいのですが、
小さい頃から全く興味がない。
ところが、息子の真義(さねよし)は恐竜が好きなのです。
そして、好きになりたての頃、数ある恐竜フィギュアの中から
彼が選んだのが、今回のショーのスペシャルとして紹介されている
アンキロサウルスでした。
初めて恐竜フィギュアを買ってやろうとした時、
もっと売れ線のティラノサウルスやトリケラトプスでなく、
アンキロサウルスを選んだ息子をどうかと思いました。
トゲトゲしているし、格好もずんぐりしてシャープではない。
けれども、初めて観に行ったこの恐竜ショーでは、
アンキロサウルスは実に見事にエースとして登場し、
気は優しくて力持ち、という振る舞いを見事に体現しました。
尻尾の先に付いている妙な膨らみは、
実は敵に対しハンマーの役割を果たし、大変な威力なのだそうです。
感心!
ショー全体としても、シンプルな空間で魅せながら、
恐竜たちの造形と動きが実にシャープに再現され、
躍動する姿にはとにかく見応えがありました。
私の人生で、初めて恐竜に興味を覚えました。
来年もまた新種を加えて新しい展開があるらしい。
あの恐竜の造形。あの動きの面白さ。気になる。
4/28(金)5月から『二都物語』
4/27(木)ミミの快挙とドガドガプラス
4/25(火)他人のせいにして悪さをする男
4/21(金)オルガンと唐十郎②
4/20(木)オルガンと唐十郎
4/19(水)軍歌というもの
↑軍歌活用ランキングNo. 1はこの場面でしょう
『唐版 風の又三郎』唐ゼミ☆2021年公演より(写真:伏見行介)
軍歌を愛好しているというと、戦後民主主義社会では波紋を呼びます。
が、唐十郎作品の中にも軍歌は登場します。
一番見事に軍歌が使われた例は『唐版 風の又三郎』で活躍した
『荒鷲の歌』です。あの、帝国探偵社の面々がふんどし姿で跳び回り、
♪ぶんぶん荒鷲、ぶんと跳ぶぞ〜と歌い上げる場面は、
誰がどうやっても盛り上がり、爆笑に包まれる鉄板シーンです。
いま読んでいる『愛の乞食』にも軍歌は登場します。
『独立守備隊の歌』『満鉄の歌』など、一瞬にして満州の空気を
充満させる効果が絶大です。
私が聞いたところでは、初期の紅テントにおいて、
芝居がはねた後の車座の宴会では、どんぶりを箸で
チンチン叩きながら、たびたび軍歌が歌われたそうです。
いわば座興の盛り上げソング。
初めてこれを聞いた時は驚きました。
初期状況劇場といえば進歩的な人たちの集まりであったはず。
どちらかといえば反体制的、左翼的な傾向が強い面々にあって、
彼らが軍歌を歌い上げている光景は想像し難い。
けれど、澁澤龍彦さんなども軍歌で盛り上がるクチらしいのです。
こうした事実を面白いと思います。
歌に込められた思想信条は別にして、小さい頃から高揚した歌に
身体が勝手に反応してしまう。そういうこともまた、
歌が持つ強い側面だということです。
小さい頃に観ていたアニメソングみたいなものか、とも想像します。
刷り込みが効いているので、『ドラゴンボール』や『聖闘士星矢』や
『北斗の拳』の主題歌に、思わず体が反応してしまう。
自分はそういう世代です。気づけば全て少年ジャンプ系。
4/18(火)兵2の衝撃
↑唐ゼミ☆2010年公演より。右が重村大介この時も兵2は彼のもの
(写真は伏見行介)
日曜に読んだ『愛の乞食』二幕一場について、
私たち唐ゼミ☆劇団員が素通りできないエピソードがあります。
それは、今は唐組で頑張っている元団員の重村大介について。
彼が横浜国大に入学してきた時、周囲は一様に驚きました。
よく「オレって人とは違うんだよね」とか、「いや、オレこそが」などと
自意識過剰な青年世代は個性的であることを競う合う風潮があります。
が、重村こそはダントツの、飛び抜けて変わり者でした。
あの喋り方、オドオドとして、その実けっこう自信満々な物腰。
4年間の浪人生活を終えて大学生となった彼は、
当時、皆に「ヨン様」と呼ばれていました。
そして、彼が大学の講座で『愛の乞食』により初舞台を踏んだ時、
それを観た学生たちは度肝を抜かれました。
・・・とにかく、何を言っているのかよくわからない。
決して唐さんのせりふが難解だからではなく、
重村のあの喋り方によって、日本語がまったく聞き取れない。
彼は顔を真っ赤にして目をつぶり、大音声で叫び続けました。
初めて登場したのはガードマンの役、長ぜりふは散々でしたが
しかし、一人二役を兼ねて2回目に登場した時、奇跡が起きました。
「兵2」です。兵2が登場するのは兵1に次いで二番目。
兵1がしたやり取り、言ったせりふを兵2もそっくり繰り返してやる、
そういう仕掛けのシーンで、重村は爆発しました。
どんな筋立て、やり取りかはあらかじめ兵1がやってくれているので、
観客は事前に何が行われるかを知ることができました。
その上で兵2に扮した重村は、他の誰にも真似できない行き方を突き進む。
例えば、「キャラメルはありません」という何でもないせりふ。
重村にかかると「ぎゃらべりばせん!」という叫びに変化しました。
重村がひとこと発する度に、狭い研究室に詰め込まれた30人が湧き、
部屋が揺れました。思えば、あの時の演出は唐さんの跡を継いで
大学に来てくださった久保井さん。
・・・あの頃に比べると、重村のせりふはずいぶん分かりやすくなりました。
少し寂しいような気もしますが、あの時は同じやり取りを繰り返す
兵2だからこそ威力を持ったのです。
『透明人間』での素晴らしいせりふ回しに期待しましょう。
4/14(金)滝沢先生の棲家
4/13(木)三浦半島にて
4/12(水)去年と今年の砂
4/11(火)そりゃないぜ、乱歩版『鐡假面』
4/7(金)こんなものまで!〜唐組初期の舞台映像VHS
4/6(木)第一級資料、来たる!
4/5(水)3月末〜4月頭に行ったイベント
4/4(火)チェ・チェ・チェ・オケラとは・・・
3/31(金)年度末だった
3/30(木)あまりに人間的な
3/29(水)期せずして夜桜、そして力道山
3/28(火)誰か教えて!〜ヤングガン公演
3/24(金)駄菓子屋讃歌
3/22(水)『愛の乞食』掲載の歴史
昨日から本読みワークショップが新たな演目に入りました。
『愛の乞食』です。もともと1970年に初演された本作ですが、
いくつもの掲載誌がありますので、内容に入る前に、
今日はざっとそれらを紹介しましょう。
1970年2月 文芸総合誌「海」1970年3月号に掲載
1971年11月 中央公論社より単行本『煉夢術』に掲載
1975年7月 角川文庫より『戯曲 吸血姫』に掲載
1979年6月 『唐十郎全作品集 第二巻(冬樹社)』に掲載
という具合です。
この台本に関して、私は版の違いによる比較検討はまだしていません。
ワークショップは全作品集版をもとに行なっていきますが、
やはり気になるのは初演より約半年前に掲載された文芸誌「海」版です。
上演を通じた現場の事情により、唐さんが台本を書き換えることは
ままあり、だからこそ着想のままに書いた原典版への興味はつきません。
この中でオススメなのは角川文庫版です。
手に取りやすく、『吸血姫』『愛の乞食』というゴールデンペアが
一冊になっています。安く見かけたら、買い!です。
ちなみに、上演記録では、この作品を状況劇場が初演した際
タイトルは『ジョンシルバー 愛の乞食篇』と銘打ってあります。
確かに「ジョン・シルバー」が大きなモチーフになっていますし、
『ジョン・シルバー』『続ジョン・シルバー』と続いてきた流れに
属する作品です。
が、内容的に第三部にあたるかといえばそうでもありません。
『愛の乞食』は独立した意味合いの強い劇ですが
おそらく、唐さんは興行成績を強く意識して公演の際に
そう名付けたものと考えられます。
その辺りは本読みを進めるうちにわかってきます。
内容はまた明日!
3/21(火)水戸に行ってきた② 回天神社その他
3/20(月)水戸に行ってきた① 巨大バッタの実験
3/17(金)冬に覚えた味
3/16(木)小山祥平くんにばったり
3/15(水)深夜の公園めぐり
3/13(月)あっぱれな看板
3/10(金)ここでもおぼっちゃまくん状態
3/9(木)あのロープワークはどうだったのか
3/7(火)岡山市に行ってきた
3/3(金)清水に行く
3/2(木)まるで温泉のような
3/1(水)発見!スカルコッタス!
2/28(火)江戸川乱歩の『鐡假面』
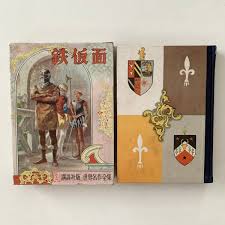
2/24(金)あのオルガン曲を聴けた!
2/23(祝木)綾瀬で旧交を温める
↑真ん中が三上宥起夫さん、向かって右が嶋田勇介さん。
今日は久々に綾瀬市に行ってきました。
綾瀬シニア劇団のメンバーを対象に、とりふね舞踏舎の
三上宥起夫さんがワークショップをしてくださるというので、
久々に現場を覗きに行かせてもらいました。
ロンドンに行く前に会って以来、1年数ヶ月ぶりの再会でしたが、
皆さん、ありがたいことに自分のことを憶えていてくれて、
元気そうな様子を確認できました。
また一緒にワークショップを受けて、特にマッサージのコーナーが
気持ち良すぎて、寝てしまったりして。
今日の会場は公民館だったのですが、
合い間に綾瀬市オーエンス文化会館も訪ねて、
ずっとお世話になってきた副館長さんとも話しました。
地域の人たちにすごく頼られて、
通り過ぎる多くの人たちが次々に挨拶して行く様子も以前と同じ。
何より嬉しく、面白かった再会は、
三上さんのアシスタントとして来ていた嶋田勇介さんに会えたことでした。
嶋田さんは、自分がほんとうに駆け出しの頃、
まだ横浜国立大学で唐十郎ゼミナールの発表公演をやっていた時から、
とりふね舞踏舎の新人ダンサーとしてチラシ折り込みに来てくれたり、
北仲スクール時代にはバンカートのスタッフとしていつも丁寧に
接してくれた人でした。これを期に、
またちょくちょく会う関係になりそうです。
初めてお話しすることのできた三上さんとは、
もと演劇実験室天井桟敷のメンバーでしたから、
1969年に起きた渋谷での状況劇場の乱闘がどんなだったか、
結局は誰が原因をつくったのか、というかなりニッチな話題で
盛り上がりました。
そういうお話ができる相手を得て、久々にボルテージが上がりました。
やっぱり一番のイタズラ者は、愛すべき四谷シモンさんということで、
一致を見ました。
2/20(月)『オオカミだ!』を終えて
2/17(金)『オオカミだ!』初日を終えて!
↑初日開場を前に、創作に関わった7人で記念撮影しました
現在、初日を終えて少し食事し、東横線で横浜に引き上げています。
稽古期間は短かったけれど、ようやく初日に辿り着きました。
パントマイムの公演をつくるのは初めてで、
ケッチさんとSATOCOさんとテツヤさんが
自分を指南しつづけてくれたような公演準備でした。
稽古はじめから3日間が特に混乱の極み。
でも、ケッチさんの創作がテクニックの羅列に終わらず、
リアリズムを基調としていることがわかるにつれ、
自分にもやりようがあることを悟りました。
唐さんの台本だって、
今ここにないものを演者の力で舞台上に現出させることに妙味があります。
ことばと所作の違いはありますが、踏まなければならない手続きに
似たものを感じました。
一方で、揺るがせにしてはならない台本があるのと違い、
現場の判断ですべてを更新していくオリジナル創作は、
リスクと希望が一緒に噴出していて、
自分の責任を痛感しながら日々を過ごしました。
初日の感触を確かめながら、
あそこはカットして、ここには小道具を足して、効果をこう加えて・・・
などと楽屋で相談するのも愉しい。
お互いに、一国一城の主が寄り集まって公演しているので、
公演の全体にそれぞれが思いを馳せ、お客さんのことを慮るチームです。
複眼チェックなので穴も少なく、目一杯サービスします。
これからいろんな場所で公演していくのが希望です。
そのために荷物も人も少数精鋭でつくってあります。
明日も、ところどころ工夫して臨みます。
午前9時集合、11時開演!
2/16(木)ロンドンからの宿題
2/15(水)絵のある生活
2/14(火)厄年が終わった
2/10(金)英国ケータイ問題のその後と『オオカミだ!』チケット完売
2/9(木)ドリプロもやっていた
2/8(水)売り切れてきている
2/7(火)稽古純度の高い1日『オオカミだ!』
2/3(金)下北沢の唐組『赤い靴』より
2/2(木)車の1ヶ月点検に来た
↑ホンダの店舗から見たミツ沢の景色。横浜国大に入ってから20年以上
この場所に親しんできたが、こんな風に眺めるのは初めて!
今朝は劇場の仕事を少しして、それから横浜市民ギャラリーに行きました。
唐ゼミ☆を横浜国大で活動し始めた時からずっと見守ってもらい、
時には川崎市市民ミュージアムでの公演をプロデュースしてもらった
仲野泰生さんが、展覧会に参加しているからです。
仲野さんの作品は、近年に行き来してきたメキシコ文化と
お住まいのある川崎の遺跡、縄文文化が融合していて、
端正なものでした。ちょっと怖いようなリアリズムもあって
まことに二枚目! 一方で、自分は仲野さんが展開してきた
小型のエロ本シリーズが好きなので、あれもまたやってほしいと
伝えました。
それから、劇団員のちろさんに会いました。
ほんとうに久しぶり。彼女にはイギリス留学経験があり、
自分は渡英準備の中でさんざん世話になりました。
だから御礼を伝え、不在の間の出来事や、これからのことを
話し合いました。ロンドンで買ったお土産をやっと渡すことも
できました。
実はまだ、林麻子と米澤と佐々木あかりには会えていません。
彼らにも会って、早くお土産を渡したいと思いつつ、
後手後手で1ヶ月。早く公演場所の算段をつけて、
具体にどうしよう?っている相談をする状況を整えたいと
思います。お土産、ずっと車に乗っています。
それから、車の1ヶ月点検を受けに来ました。
今、その待ち時間にこれを書いています。
横浜国大近くのホンダ三ツ沢店が担当店舗です。
自分が不在の間、椎野は自転車でここまで行き来し、
今乗っている車を用立ててくれました。
大学時代から慣れ親しんだミツ沢上町の交差点ですが、
店舗の中から見るとまた違った風景です。
帰国してからの1ヶ月で、走行距離は3,500kmを超えています。
ハードワークは仕方ないとして、大事に乗っていきたいと思います。
それに車の販売店の、このホスピタリティの良さよ!
今日はこれから車を家に戻し、下北沢に唐組を観に行くつもりです。
重村や山本十三、立派になった美仁音の活躍に期待!
どうだったかは明日に書きます。
2/1(水)ハンディラボに帰ってきた!
1/26(木)秘儀、ブレイク・ソサエティ
1/25(水)横浜中華街に行く
1/23(月)くたびれ果てたので楽しい話題を
↑典型的に愚兄賢弟の三男。なるほどかしこそうです
今日は月曜日です。
いつもならば日曜に行ったワークショップのレポートをする日。
けれど、心折れました。
すべての仕事を終えて帰宅したのが24:15。
そこから食事してレポート執筆にかかりましたが、
ようやくあらかた書いたところでシステムエラーが起こり、
完全に消えてしまいました。
ほとんど、9割がた完成していたというのに・・・
ですから、レポートは明日に回します。
今日は短くて楽しい話題をやりましょう。
井上リエさんからオオカミとこぶたのイラストが届きました。
『オオカミだ!』のパントマイム・ショーの中に出てくる
紙芝居をデザインし、宣伝ビジュアルも作ってくれているリエさんが
新たにイラストをプレゼントしてくれたのです。
チラシに載っているオオカミだけでなく、こぶたもいます。
井上リエさんはオシャレな輸入食品を扱うカルディのビジュアルを
担当されているクリエイターで、あのユーミンのコンサート
ビジュアルも何度も描いてきました。
知れば知るほど良い作家に引き受けてもらったものだと思います。
肝心のケッチさんのショー部分を考える際も、リエさんの絵に
大いに助けてもらっています。
以上、愉しい話題でした。現在26:00を過ぎています。
もう風呂入って、寝る!
↓カルディといえばこの絵でしょう!
『オオカミだ!』チラシの完成
↑『オオカミだ!』チラシができました。さっそく撒き始めています。
公演日時と場所はこんな感じ!
2/17(金)19:00
2/18(土)11:00
2/19(日)11:00
於:下北沢 本多劇場
今日のお昼に劇場の下見に行きました。
これまで下北沢には何度となく足を運んできましたが、
自分が公演する側になるのはこれが初めてです。
普通だったら必ずや通り過ぎるであろう下北沢ですが、
テント演劇をやっていると空き地を求めて彷徨ってしまう。
だから初体験です。
現在はちょうど修繕中だったのですが、
セットも何も無い舞台を初めて見ました。
唐さんの『秘密の花園』によりこの本多劇場が
スタートしたのだと思うと感慨がありました。
それに、駅前の変化したこと。
渡英していた11ヶ月の間に、駅前から劇場に至る道はかなり
スムーズになり、両側には新たな飲食店が多くオープンして
多くの人たちが気持ちよさそうに昼食をとっていました。
渋谷駅から井の頭線に乗り換えるルートも久々に歩きました。
すでに1月下旬に差し掛かっています。
稽古は2月に入ってからですが、
しなければならない準備は山ほどあります。
帰国以来、日本で再会した仕事や生活を定着させるために
過ごしてきましたが、今日を境に意識の中心を創作に切り替えます。
チラシを渡しながら何にかに訊かれましたが、
大人ひとりでの観劇ももちろん大丈夫です!
1/19(木)床屋の値付けにビックリ
1/18(水)井上リエさんのアトリエに行く
1/17(火)桃山邑さんの納骨式
1/13(金)ロンドン生活の名残り
1/12(木)結局どんな職業なのか?
1/11(水)身内にも分からないほどの顔面の変形
1/6(金)栄養状態の改善
↑おお!なんと美しい塩ジャケの切り身よ
馴染みの魚屋で、こんなものとも感動の再会を果たしている
帰国して以来、明らかに体の調子が良くなってきています。
時差ボケこそあるものの、お正月休みによる睡眠時間の増加。
温暖で快晴の気候、など理由はいくつかありますが、
なんといっても食生活の改善が大きく影響しています。
ロンドンでの食事は貧しくならざるをえませんでした。
イギリスの食事が必ずしも不味いわけではないですが、
とにかく値段が高かった。パンを一個買おうと思うと、
例えばクロワッサンが450円します。
だから、悩んで、悩んで、
これでお腹が膨れるだろうか、とか
そもそもオレはほんとうに空腹なのだろうか、とか
散々に考えてから、よくやくオーダーの列に並びました。
食事の一回一回が真剣勝負で、
意を決して予算投下して食べたものがハズレだった時には
かなり落ち込みました。
日本に帰ってから、馴染みの肉屋に行ったり、
野菜たっぷりの鍋をつくって食べることで、
身体の痛みがみるみるとれてきています。
イギリスでは視力を落とさないようにするためのブルーベリーと
手に取りやすいオレンジジュースだけがフルーツとの接触でしたが、
日本ではイチゴやパイナップルを安価に食べることもできる。
昨日は約1年ぶりに日本そばを食べました。
あと一週間もすれば慣れてしまいそうですが、感動が続いています。
物価の安さについて、
日本が国際間の経済競争に遅れをとっている危機を感じながらも、
スーパーで見かける値段にどうしてもホッとしてしまう。
現在のように万全であの英国生活が送れたらさらに
ステキだったろうとも思いますが、アウェーなので仕方ありません。
もうすぐクロネコヤマト・ロンドンに託した段ボール二箱も届きます。
不調ながら方々に出かけ、手に入れた公演資料を本棚に並べるのを
たのしみにしています。
1/5(木)メンテナンスという贅沢
↑靴と靴墨
仕事が始まったとはいえ、いまだペースはゆっくり。
まだ休みを続けている人もいるし、本格始動は来週からという
雰囲気なので、幸い、自分ごとに時間が使えます。
朝はゆっくりで良かったので、ネットで取り寄せた靴墨を使って
革靴をキレイにしました。この革靴はイギリスに持って行ったもの。
普段はスニーカーで動きましたが、少しフォーマルな場所に出向く時
これを履いて出かけました。
グラインドボーン音楽、ジェントルマンズクラブ、
クリスマスにテンプルホールというサロンで行われた
サラ・コノリーのコンサートにもこれを履いて行きました。
ダイアンの誕生日に出かけた時も、洗練された彼女に合わせて
身綺麗にした方が良いと思い、これを履きました。
が、合計10回ちょっと利用したにも関わらず、
一度もメンテナンスをしませんでした。
泥がついたのを拭き取るくらいのことはしましたが、
こうして汚れをとり、靴墨を塗って色を濃くし、光沢を出す作業は
できなかった。向こうでは、道具の調達が面倒すれば無駄が出るし、
高価でもありました。
こうして日本に帰ってきて、一緒に歩いた土地を思い出しながら
靴を磨くのは愉しい。この靴墨は簡単に塗れて値段も安く、
かなりキレイになります。なかなか贅沢な気分に浸らせてくれます。
新しいものを買うよりもさらに贅沢な感じです。
オレも大人になった。そういう満足があります。
そういえば、初めて畳の張り替えをやった時、
あれもかなり爽快で、やはり贅沢な感じがしました。
同じくメンテナンスの贅沢です。
今の家のもかなり陽に焼けてきたし、あれをまたやりたい。
が、下の子がもう少し落ち着いてからの方が良い気もする。
唐ゼミ☆としても畳屋さんにはずっと助けられてきました。
テント演劇をやる際、よく要らないゴザをもらってきたのです。
さらに、今年に上演すると決めた『鐵假面』の主人公は「タタミ屋」
という設定で、キャラクター名もズバリ「タタミ屋」。
ならば、やっぱり春になったらやろうと思います。
主人公の職業について身近に観察する機会になるはずです。
1/4(水)日本での仕事を再開
1/3(火)時は動きだす
12/31(土)今から飛行機に乗ります
12/30(金)イギリスの習慣ともお別れ
12/29(木)行き残した場所 フェルパム
12/28(水)重量オーバー決定!
渡英した時、トランク一個。リュック一個。書類かばん一個で出発した。
書類かばんはわざわざ買った。なぜかというと、ロンドンではリュックを
してはいけないと聞いたから。治安の悪いロンドンでは、
背負ったリュックですら気付かぬうちに背後からの盗みに遭う。
そういう触れ込みだった。書類かばんは肩からかけると体の前にくる。
が、ここで暮らすうちに、リュックは大丈夫だとわかってきた。
都心ではいつも足早に歩いているか、催し物会場の中にいる。
あまりカフェにもパブにも行かない。それが良かったのだろう。
幸い、泥棒には遭わなかった。書類かばんを持って、
荷物が常に自分の前にくるようにしていたのは
ほんの半月ほどの間だけだった。
ともかくも、行きの時にはトランクの重さを量りさえしなかった。
春夏用の服は後で送って貰えばいいやと高を括り、
当座の衣類しか持って来なかったことも荷物を軽くした。
この計画は、渡英後に起こった戦争により挫かれることになった。
だから服を買った。それからCDを買い、少し本を買い、
何より書類が増えた。300以上観た公演に関する全ての付属資料、
当日パンフレットとかチラシとか、それらをいちいち保存してきたから、
とてつもなく重くなってしまった。
で、現在である。
先週、ダンボール二個を日本に送り出した。
24kgの荷物が二つ。制限25kgだからパンパンに詰め込んだ。
それから昨日はトランクを二つ作った。
23kg制限で二つ。
こちらでできた友だちに体重計を借りて、いちいち掴んで乗り、
自分の体重を引きながら量る。結果、一つは22.5kgで収まったが、
残る一つは8割入れたところで30kgに達した。
完璧な超過である。仕方ない。料金を払って凌ぐしかない。
それにしても、お金で全てが解決できるわけではなく、
オーバーも9kgまでが限界だそうだ。最後まで闘いは続く。
しかし、20kgくらいの荷物でやってきて、
帰りは100kgに到達してしまっているということだ。
生活は恐ろしい。帰国したのち、これらがどこに収納させるのかという
問題もある。闘いは続く。
12/27(火)最後の食事
12/23(金)二つの卒業
12/22(木)会心のフィナーレ
12/21(水)Meet Me のクリスマス・パーティー
↑小さな劇場、小さなカフェだけれど、いつも人の気が充満している
昨日はその最高潮だった
昨日は3月から参加してきたシニア向け企画
"Meet Me"のクリスマス・パーティーだった。
当初は近所のパブJOB CENTERで開催する予定だったが、
1週間前に店側からキャンセルの通達があり、
プロデューサーのソフィーはげんなりしていた。
そう。英国では店側から一旦受けた予約をキャンセルされることが
ままあるのだ。日本では考えられん。
気を取り直して、
結局はいつもの稽古場で手作り開催することにした。
Albanyにはカフェがある。
そこに調理場もあるので、カフェのスタッフたちが
ヨークシャー・プティングだとかチキンのソテー、
ベジタリアンには焼きナス、人参のグラッセ、
ブロッコリーなどの和え物、じゃがいもを焼いてくれた。
昨日の出席率は極めて高く、日ごろ休みがちなシニアも沢山来ていた。
初めは、カフェスペースで合唱する。いつもアート製作に
取り組んでいるシニアたちがメインの聴衆。
そこに、カフェを利用するお客さん、クリスマス用のキッズプログラムに
訪れていた家族連れのお客さんたちも聴く側として自然に加わる。
いくつものクリスマスソングを歌ううち、
劇場事務所からもスタッフがみんな顔を出し、合唱を応援し始めた。
要するに、劇場建物に居合わせた人たちみんなが集まり、
振り付け付きで大合唱する格好になった。
唐さんの出身である長屋の家族的雰囲気が溢れ、かなり感動的な
光景だった。
それからいつものリハーサルルームに移り、みんなで食事。
みんな帽子をかぶって、クラッカーを鳴らして、
職員もボランティアスタッフもみんなで食べた。
それから、クリスマス恒例のくじ引きがあった。
続いてシニア側の幹事からボランティアスタッフたちへの
表彰があり、その中には自分も対象として入っていた。
エンテレキーアーツのスタッフで、これから産休に入るジャスミン、
それから自分は特に手厚くしてもらった自分が、順番にスピーチした。
ジャズミンは短めだったけれど、
自分にとってこれが本当に最終最後の機会だから、
日本語で挨拶する時のように時間をとって喋らせてもらった。
これまでのことを思い起こしながら込み上げてくるものが多すぎて、
御礼を伝えるのに必死で時間が経つのを忘れた。
英語についてずっと自信無く過ごしてきて、
今も大して上達しなかったという感慨の方が強い。
けれど、10分くらい、自分が英語で喋っていることを忘れて
話せるようにはなった。
そのあとはお開きとなり、一人一人と別れを惜しみつつ、
人生の先輩たちに「アツシはワイフとチルドレンを大事にしろ」と
繰り返し繰り返し言われながら彼らを見送った。
自分が一番の基礎としてきた企画が完全に終わった。
あとは明日、CEOのギャビンと総括的な話をして研修は終わる。
その後に御礼のメッセージを方々に書いて仕込んだら、Albanyはおしまい。
やること多し。もうひと越えだ。
プロデューサーのソフィーと。見た目通り終始優しかった。↓
私の八甲田山
↑雪のために道をはみ出して歩くことが難しいのに・・・
最近、なぜか映画『八甲田山』が観たくて仕方ない。
YouTubeで細切れの映像を観るのだが、やはり全体が観たい。
別にロンドンに雪が降ったからではない。
ロンドンに雪が降ったのは1週間前だが、それより遥か前、
1ヶ月半くらい前からなぜか『八甲田山』が観たいのだ。
考えてみれば、これは、すぐ隣にある危機への
シンパシーではないかと思う。英国では、通い慣れたはずの
道ですらすぐに危機が訪れる。
ストライキは起こり、予告もなしに駅は閉鎖される。
先日など、都心めがけてバスに乗ったところ、
道が混みすぎているからと運転手は一言だけ放送を入れ、
途中で勝手に進路を変えた。そして、最寄りの降ろしやすい
バス停で全員を降ろしてしまった。
看板に偽りありにも程がある。
しかし、不思議だが誰も文句を言わない。
渋滞によりバスの到着が遅れて遅刻した経験はあるけれど、
バスが引き続きの運行を放棄しての遅刻とは。
果たしてこれはよくあることなのか。さっぱりわからない。
ところで、先日はまたしても郊外に出かけた。
例によってコンサートを聴くためなのだが、
途中の道にはかなり往生させられた。
こちらはナビが2時間半での到着を予想していたところを
ビビって4時間半前に家を出た。だから最寄り駅に着くのも早すぎて、
シャトルバスが迎えに来るまでに1時間半もある。
ナビを見れば30分ちょっと歩けば良いと出ていたものだから
勇んで歩き始めた。が、あっという間に民家はなくなり、
原野みたいな光景。本当にこんなところに劇場があるのかと
思いながらも、Googleナビに従って歩道のない道を前進した。
が、道半ばでNo footwayの表示。
そんなの今さら言われても困るから、ドキドキしながら小走りに前進し、
途中ビュンビュン走る車に邪険にされながらも何とか目的地に着いた。
電灯の無い道だった。
日没したあとだったら、車は私がいると気付かずに飛ばしただろう。
陽が残っていて良かった。
あと2週間で帰国したら、何か食べながら『八甲田山』を観たい。
12/16(金)サラ・コノリーにもお別れ
12/15(木)Albanyのカフェで
12/14(水)最後の練習
12/13(火)後半の山場
12/9(金)マチルダとアンクル・ジョージ
いつ日本に帰るのか?
そう訊かれることが増えてきたので、12月31日と答えている。
すると一様に、それじゃどこでハッピー・ニューイヤーか
分からないね、と言って笑う。
12月20日(火)と21日(水)に大きなパーティーがあるから、
大半の人たちとはそこでお別れになる。
と、思っていたら、一昨日は先制パンチを喰らった。
ずっとAlbanyのチケット売り場や入場管理係として
お世話になってきたマチルダが、任期満了で退職することになった。
たった11ヶ月の滞在でさえ、これまでに何人も同じような人たちを
送り出してきた。これがイギリス流の働き方で、だいたいが一年契約。
契約者と息が合えばそれを更新するし、他に行ってもみければ
新たにチャレンジする。そうやって次々と職場を移っていくのだ。
だからこそ、今接している人たちへの敬意と
何もかも自分の腕次第という緊張感を持って働いている
感じがする。一方で、体を壊したらどうするんだろう?とか。
産休とか育休は?とか。なかなか厳しい社会でもある。
終身雇用の方が安心して安定した力を発揮できる。
人間にはそういう側面もあると思う。
イギリスで住んでいるダイアンの家にはプリンターが無いから、
自分はいつもマチルダに添付ファイルを送って印刷してもらった。
明らかに仕事に関係ない、旅行の予約や公演チケットなどを
オーダーすると、かえって丁寧に封筒に包んでプレゼントしてくれた。
イギリス人としては異例に細やかなマチルダ。
またしても突然に切り出されて面食らったメレど、
何度も御礼を言ってマチルダとお別れすることができた。
それから、夜は都心でのコンサートを聴いた後、
強行軍でAlbany近くのライブハウスにも行った。
渡英直後、衝撃を受けた音楽表現の一つが、
このMatchStick PieHouseで聴いたSteamdownというバンドだった。
ジャンルはFolkとJazzのフュージョン。
当時は特に日本でのコロナ対策感覚が残っていたから特にたまげた。
超過密なスタンディングで皆が上着を脱ぎ捨て、
熱気でサウナ状態になりながら、毎週水曜日の定例ライブで
深夜まで盛り上がってきたのだが、いきなり年内最後だと
言われたので、行かないわけにいかなかった。
24時近くになってやっとライブが終わると、
一気に解放された出入り口から強烈な冷気が入り込んで
気持ち良かったが、片付けをしているジョージに話しかけた。
みんな、アンクル・ジョージと呼んで慕っている彼は、
ライブハウスでのギグを斡旋するプロデューサーだ。
明らかにあまり儲かりそうにない業態なのだが、
それだけにいつもミュージシャンとへの愛情と熱意に溢れていて、
ある時などは、二つの会場で別々のライブを同時進行させて
本人は自転車で30分ほどの距離を行き来していた。
Folkに関心があると伝えると、いま期待できるのは彼ら!
とすぐにオススメを教えてくれて、見知らぬ土地にある会場で
ジョージと待ち合わせたのも面白かった。
別日にこのライブハウスで行われているFolk Sessionにも彼は参加し、
自らギターを片手に即興で風刺的な歌を歌って全員を爆笑させる。
この会はアマチュアの会だから、中にはそれほど上手くない人もいる。
そういう時にみんなの私語がいきすぎると、
「音楽家と歌にリスペクトを持とう」と言ってみんなを嗜め、
歌い手を励ますのも彼だった。
「アツシはファミリーはいるか?」と訊かれて家族構成を伝えると、
「オレは奥さんに離婚されちゃったよ」と言っていた。
イギリスで出会ってきた中で、最も温かみを感じる人の一人。
忘れえぬ人だ。
12/8(木)お別れの始まり
12/7(水)それなりの禁断症状
12/6(火)ウェールズへの旅
12/2(金)9つ持っている
12/1(木)私にとってサドラーズ・ウェルズは・・・
テムズ川の北は観光客用の繁華街や高級住宅地が多い。
Aegel駅の周辺もその一つだ。
お洒落な服屋やカバン屋、カフェが並び、
行くたびに青山・表参道を思い出す。
246のような大通りこそないけれど、
Aegel駅の周囲にあるお店の雰囲気はまさしくそんな感じだ。
文化的にも、
ここにはアルメイダという有名な中規模の劇場と
人形劇専門の小屋がある。そしてなんと言っても、
サドラーズ・ウェルズ劇場。
ダンスで有名な劇場だ。
クラシックからコンテンポラリーまで、
様々なダンスカンパニーがここにやってきて公演する。
日本で一緒に仕事をしてきた安藤洋子さんも、
フランクフルトバレエやザ・フォーサイス・カンパニーで
よくここに立ったらしい。
実際に私もここでフォーサイスやピナ・バウシェ作品を観た。
そしてまた、野田さんの『Q』英国公演もここで観た。
昨日はマシュー・ボーンの『Sleeping Beuty』を観た。
初日ということもあり、集まっているお客さんたちも
洗練されたファッションの人たちが多くて、
とりわけ華やかな感じがした。
この劇場は、今回の研修の候補地の一つだった。
2017年にさいたまゴールド祭で紹介された劇場が
自分の研修先選びに大きく影響している。
サドラーズ・ウェルズ劇場はシニアたちのダンス表現にも
熱心に取り組んでいるから、候補の一つにあがったのだ。
が、なんだか自分には不釣り合いな気がした。
青山・表参道的な洗練、
コンテンポラリーにアーティスティックな様子が柄じゃないように思い、
今のAlbanyにたどり着いた。ワイルドなDeptfordは上野・浅草的で
妙に馴染む。自分は唐十郎門下なのだ。
一方、この劇場には特別な思い入れがある。
サドラーズ・ウェルズは今でこそダンスの劇場だけれど、
300年以上の歴史を持ち、ダンスに特化し始めたのは20世紀に
入ってからのこと。
かつては演劇やオペラも盛んだったこの劇場で
1945年にはブリテン『ピーター・グライムズ』初演と
1968年には『ニュルンベルクのマイスタージンガー』公演が行われた。
指揮は敬愛するレジネルド・グッドオール。
彼にとってそれらは、キャリアを決定づけるエポックな公演だった。
晩年を除いていつも不遇が付きまとったグッドオールにとって
1945年は初めて脚光を浴びた公演。
それから数年で長い低迷に入った彼が復活したのが1968年の公演だった。
特に後者はライブの様子がCDになっている。
最初こそおぼつかないものの、幕が進むごとに威力を増して、
最後は宇宙的に異様な盛り上がりを見せる。
実にグッドオールらしい演奏。
大手書店フォイルズでディスクを買うことができたので、
会場前の早めの時間に行って、受付の人に写真を撮ってもらった。
この音楽は確かに、54年前にここで演奏されたのだ。
11/30(水)肩慣らしは南アフリカ国歌
毎週火曜日は恒例WSの日と決まっている。
午後から合唱の練習があった。
もうすぐクリスマス、だから12/8(木)には
都心のオールド・ヴィック座で行われるイベントに参加する。
そこで歌うために、特別に近所の小学生たちと練習。
AlbanyのあるDeptfordは移民の街だ。
アフリカ、中東、アジア・・・、まんべんなくいる。
小学生たちは95%が黒人。これが可愛い。
そして、彼らのウォーミングアップが面白かった。
国歌を歌おうという合唱指導の先生の合図で、
彼らはイギリスでなく、南アフリカ共和国の国歌を歌った。
アフリカ系でない子もいるだろうけれども、今日は南アフリカ、
そういう感じだった。
こちらのシニアメンバーの中にはアフリカ系の人もいるから、
彼らも自然に歌い始めた。それでアフリカ出身なんだと自分が
理解できた人もいた。カリブ出身も多いから、肌の色だけでは
自分には判断がつかない。
こんな風に、いくつもの出身国が当たり前に入り乱れているのが面白い。
日本にも在日の人がいて、沖縄や北海道が独自の出身地であると
誇りにしている人もいると思うが、私は日本人という人との
数の多寡がはっきりしているために、だいぶ違う。
一方で、人間みな同じだなと思うのは、先生に対する反応だった。
昨日、いつも指導に当たっているレイチェルさんがお休みだった。
一昨日の晩、彼女は自分のバンドと一緒にライブがあったのだ。
半年以上お世話になってきたレイチェル先生だし、
どんなライブハウスでどんな風に歌うか興味があって駆けつけた。
ぜんぜん別人のレイチェル。
という風に完全燃焼した翌日だからレイチェルは休んだわけだが、
代わりを務める若手の先生も大したものだった、
が、シニアメンバーの何人かは納得しないのである。
レイチェルじゃないとダメ・・・という雰囲気を漂わせて身が入らない。
こういうところは人類普遍だと思って可笑しかった。
レイチェル先生だって曖昧な指示を出したり間違えたりするが、
皆は不満に思いもしない、が、若手がやると文句が出るのだ。
・・・という具合に来週に向けて準備をしている。
オールド・ヴィック座のステージ裏に入れるのは愉しみだ。
劇を観にいったことはあるけど、裏に入るのは初めて。
高校時代、初めて手に取ったシェイクスピアの文庫本は、
新潮から出ている福田恒存訳『リチャード三世』だった。
表紙を開くと、そこには本場イギリスのロバート・ヘルプマンが
主人公を演じている写真があって、さらに「オールド・ヴィック座」
と書かれていた。今はあまりシェイクスピアなどやっていなさそうだし、
改修もされているだろうが、それでも同じ建物だ。
何か雰囲気を探ることは出来るだろう。
地震のない国の良さがここにある。
11/29(火)麺のトラウマ
↑日本ではしない替え玉。これで340円くらい
ロンドンでは、クロワッサンが一個400円する。
サンドイッチ一個とミネラルウォーターで1,000円。
だから毎日が真剣だ。
が、物価の高いロンドンにあっていくつか安いと思うものがある。
ハム、チーズ、アイスクリーム、ショーのチケット。
最後のは特に助かっている。今回の滞在はこれが目的なので。
昨日、さらに安いものを発見した。花だ。
今まで数度買い。昨日もスーパーで買って確信した。
ちょっとしたスーパーにけっこう豪華な花束がいつも置いてあって、
それらがさほど高くない。こちらの人にとって身近だからか。
そもそも花束にするような花はいずれも西欧からやってきたのが
理由か。日本で3,000円くらいしそうな薔薇の花束が、
こちらで2,500円くらい。物価の差を加味すれば半分くらいの値段。
それを持って、昨日はウィリアム・ブレイクの墓に誕生祝いに行き、
Albanyでお世話になってきた合唱のレイチェル先生のライブに行った。
こういう時、パッと花をプレゼントすることも、
自分は唐さんから教わった。人の芝居を観に行くときに、
物語に関係がある花を考えて、唐さんはよく買っていた。
が、ハム、チーズ、アイスクリーム、チケット、花、
これらは例外である。他のものは押し並べて高い。
特に高いと感じるのが日本食だ。
よく「日本食を食べたくなるでしょう?」と訊かれるが
値段を見れば到底納得できないから「いいえ」と答える。
それに、何度か経験して失敗の連続でここまで来たのだ。
親子丼、カツ丼、すし、うどん、
どれもチャレンジして強烈な違和感だけが後味として残った。
そこに、先日は一昨日は味噌ラーメンが加わった。
コンサートを聴いた帰り、いつもの通りを一本入ったところに
日本食の店を発見し、驚いた。こんな身近なところに、
しかも、閉店時間の早いロンドンなのに22:30まで営業。
それで、なんだか日本を思い出した。
何かを観て、少し食べて帰る。あれがやってみたくなった。
それで、一杯2,000円する一番安い味噌ラーメンを頼んだのである。
酷かった。ただひたすら酷かった。
スープもひどいが麺がさらにひどい。明らかに小分けにする用の
ザルでしかも茹ですぎているために(英国人はアルデンテを理解しない)、
ニチャニチャと固まった半分ダンゴのような麺が沈んでいた。
歯触りが悪すぎる。向こうから吸い付き、こちらが絡め取られる
ような食感だった。
一晩経ってもあまりにあの口の中のニチャニチャとした感覚、
おの記憶がひどいので今日は一風堂に立ち寄った。
ここは値段を除けば日本とそう変わらない。
多くの人はスープが薄いとかいうけれど自分はそう感じない。
むしろ、温度がぬるいことの方が気になる。雑なのである。
・・・という具合にトラウマを更新しないではいられなかった。
あんなに好きだった麺類そのものを嫌いさせるほどの迫力だったが、
克服して現在に至る。おかげで出費は倍。
11/25(金)ウェールズへの扉
11/24(木)働きすぎなイギリス人たち
11/23(水)キノコ・オン・キノコ
11/22(火)なぜか巨大ドッグフード
11/18(金)大里先生の命日
11/17(木)Tea Danceがあった
11/16(水)まるで横浜国大
↑スターリング大学内。劇場や図書館を含むセンター周辺の明かりを
見つけてホッとした。郊外なので、寮に住んでいる学生か劇場への観客
の他、人気はあまりない。
先週末はグラスゴーに行ってきた。
幸い天気がよく、北方にも関わらず気温もロンドンと変わらなかった。
スコットランド国立劇場の公演を観て事務局を訪ねるための
短い旅行だったけれど、この地域が持つ質実剛健さに
触れることができた。
特に初日の土曜は面白く、
グラスゴー中央駅で降りてホテルにチェックインしたらすぐに駅に戻り、
さらに北に30分強行ったところにあるStirlingまで行った。
バスも使えたけれど、初めて訪れる場所は地形もチェックしたい。
そこから小一時間歩いて目当ての公演会場を目指した。
劇場は山の上の大学の中にあった。
劇場を含むアートセンターが堂々とスターリング大学の中にあって、
一般のお客さんも自分の街の文化施設として気兼ねなく利用していた。
公演は、まるで大河ドラマだった。
シェイクスピアの歴史劇にも似て、スコットランド史に輝く英雄に
想を得ながら、現代人のセンスと美学で描いていた。
啓蒙とエンターテイメントが上手く融合した舞台で、
この地方の気質も反映してか、言葉がシンプルに書かれていたので、
自分にもよく理解できた。
現代の服装で現れた役者たちが衣裳を着て時代劇を演じ始める構造を
わざと見せるところなど、山﨑正和さんの『実朝出帆』をやった時の
ことを思い出した。
終演は22時過ぎで、向こう1時間来ないバスを待つのもかったるくなり、
結局、往復ともに駅まで歩いた。道はさらに暗く、歩道の無い箇所も
あったけれど轢かれないよう気をつけながら歩いて、
スムーズに辿り着くことができた。
日付が変わる頃にはグラスゴーのホテルに辿り着いた。
それにしても、あの坂を登る感じ。
敷地の境界が曖昧でどこからでも入れそうなセキュリティのユルさ。
電灯の少なさからくる夜の暗さ。どこもかしこも横浜国大みたいだった。
↓劇場ロビーのポスターの前で
その後にグラスゴーをウロウロして分かったが、この地域は実によく
街の景観に大学が溶け込んでいる。グラスゴー大学、市立大学、
そういったものを見かけだが、それぞれに美術館やコンサートホール、
カフェ、庭を持っており、これが周辺住民や観光客にも開かれていた。
学校が賑わっていて、留学生も多かった。日本人は見かけなかったけれど、
中国や韓国から来ている人が多くて、彼らのニーズに応える料理屋が
充実していた。久々にキムチチゲを、しかも安く食べることができた。
↓グラスゴー大学内の美術館
11/15(火)唐さんの勝ち
11/11(金)移民と闘争のルイシャム
水曜日にAlbanyで公演を観た。"QUIET REBELS"というタイトル。
映像とシンプルなステージング、4人だけの出演者による舞台だったが、
若い人たちの熱気と関心が場内に溢れ、満員だった。
これは、実話に基づいた物語だ。
労働者階級に生まれた白人女性が、移民としてカリブからやってきた
黒人男性と恋愛し、結婚をした。結果的に彼女に対し、
白人社会からのものすごい圧力や嫌がらせが寄せられることになる。
それらを、実際の当事者たちのインタビューと、俳優による演技と
虚実の両方から進行させてゆくステージだった。
今年、このような闘争を描いた様々なイベントに参加してきた。
NEW CROSS FIREについて Linton Kwasi Johnsonが語るレクチャー。
カリブからの移民第一世代が往時を回顧するWINDRUSH PEONEERS。
ルイシャム・ショッピングセンター周辺で繰り広げられた
人種差別闘争の様子を収めたドキュメンタリー映画上映会。
シニア企画に参加するアフリカやカリブから渡ってきた人たち。
ここ半年を総動員して、目の前の劇を観た。
初見では捉えきれなかった言葉のやり取りについて行きたくて
今日は二度目をこれから観る。
現在、目の前でやり取りされている平穏な日常が、
どれだけの闘争の果てに成し遂げられたものか実感できる。
ダイバーシティとか多様性とかいうけれど、日本とは土台の
複雑さが違う。平和そうに見える周辺地域に底流するものを
またひとつ感じることができた。。
日本では、カプカプひかりヶ丘×新井英夫WSが
ズーラシアの近所にある実際のカプカプで本格的にスタートした。
ロンドン時間のAM1:00〜AM9:00の長尺だが、
皆さん次から次へと押し寄せる予定に、
慌ただしく活動していると聞いた。
新井さんのコンディションがちょっと心配されたが、
ふたを開けてみれば、休憩時間も惜しんで受講の皆さんに
話し続けていたらしい。新井さんによる魂の講座だし、
カプカプの利用者さんたちが全員で講師をしていることも
今回のウリだ。引き続き正対、ストレートな運営をしていこう。
次回のB日程初回は12/23。
11/10(木)川口くんとクレメンティ・ハウスへ
11/9(水)キットカット食べすぎた
11/8(火)ペンザンスでの昼寝
11/4(金)このホスピタリティの無さよ
11/3(木)台本、教会、旅の支度
↑The London Oratory
昨日はいつもと曜日をずらして劇団や座友メンバーとの
『ベンガルの虎』本読みをやった。2幕の終わり。
いつもながら唐さんが書く3幕ものの2幕終盤は素晴らしい。
こちらがいちいち考え、理解するのを寄せ付けない勢いに満ちていた。
気持ちよく、せりふのやり取りや物語の進行に振り切られた感じだ。
直に体がうずく。
ブルース・リーの名ぜりふに"Don't think, feel."というのがある。
"考えるな、感じろ"。昔からの唐さんやアングラ・ファンの中には
こういう味わい方をしている人がたくさんいる。
けれども、遅れてきた世代である私にとって、
唐さんの作品はやっぱり考えながら読むものだと思う。
荒唐無稽に見える設定やせりふの中に唐さん流のリアリズムがある。
そうでなくては、どうやってせりふを言い、セットをつくり、
物語をつむぐのか。やる側はThinkせよ、と思ってやっている。
けれども、やっぱり唐さんの魅力の究極は、
理性ではなくて、感覚による納得でねじ伏せていく
いわく言い難い、けれども誰もが体感的に納得してしまう
吸引力や腕力だと思う。
それを存分に味わうために、私たちは分かるところは分かっておこう。
そういう考えでやっている。
そういえば、前に『トリック』という大ヒットドラマがあって、
あれも似た話だった。主人公はマジシャン、
次々と登場する霊能力者のトリックを暴きながら物語は進行する。
けれど、それは霊能力者がニセモノと言いたいために
やっているわけではない。むしろ逆。
本物の霊能力者に出会うためにこそ、
トリックを見破ること=理屈でニセモノを選り分けているのだ。
すべては、ホンモノの不思議に出会うために。
真の摩訶不思議に圧倒され、打ちのめされたい。
そういう思いで台本を読んでいる。
私たち作り手にはお客さんという存在がいるが、
まず自分たちが圧倒されて、今度はそれをお客さんにおすそ分けする。
そういう相手であると思っている。
昨日、『ベンガルの虎』二幕には気持ち良くやられた!清々しい。
イギリスでは、ここ数日は教会の催しばかりに行っている。
土曜日はオックスフォードにある大学の中のチャペルと
福音史家ヨハネ教会。
月曜にはロチェスターの大聖堂。
火曜には都心のテンプル教会。
昨日はサウスケンジントンにあるロンドン・オラトリーという
カトリックの教会、という具合。
どこも特別な内装と音響だったが、
とりわけロチェスターとオラトリーは素晴らしかった。
今日、木曜の深夜から旅に出る。
風光明媚だけれど交通の便はすこぶる悪いコーンウォールを攻める。
伝説ではアーサー王が住み、
トリスタントイゾルデの舞台ともなったティンタジェル城、
岬の野外劇場ミナックシアター。そしてプリマスの教会にも行く。
この教会ではピーターのアンサンブルによる演奏会が行われるのだ。
合い間に『下町ホフマン』研究と来年度公演の企画書づくり、
『オオカミだ!』とカプカプ×新井一座WSの準備もする。
体はイギリスの僻地、頭は日本のことを考えて過ごす週末になる。
11/2(水)明らかに助平な男たち
↑終演後のクリスティは喜色満面。足元に覗くソックスの赤が眩しい
唐組が終わった後も唐さん関連の公演が続く。
流山児事務所が『ベンガルの虎』の稽古に入っているとのこと。
自分が観られないのは無念だが、コロナに捕まることなく
最後まで駆け抜けて欲しい。
それから、状況劇場の終わりから唐組初期の唐さんを支えた
俳優・菅田俊さんが率いる東京倶楽部の『ジャガーの眼』公演もある。
菅田さんはずいぶん以前に『ふたりの女』も手掛けられていた。
今回は、宣伝のためかYouTubeで1980年代半ばの唐さんについて
菅田さんがエピソードを披露されている。これが面白い!
https://www.youtube.com/watch?v=QF9aL3X3GxM
この時代は唐さんにとって困難な時期であり、
表に出てくる情報は少なかった。だから菅田さんのお話は貴重だ。
皆さんもぜひ観てください。これまで知られていなかった当時の
様子だけでなく、強面に見える菅田さんの純真さにも打たれる。
こちらも観にいけないのが悔しい!
誰か観に行って、どんな風だったかを教えてください!
ところで、今日のゼミログのタイトルは、
別に流山児さんや菅田さんが助平だというのではない。
(二人とも色っぽいが)
目下、研究中の『下町ホフマン』に"平手"というキャラクターが
出てくる。三度笠をかぶり、侠客めいた格好だから、
おそらく講談の『天保水滸伝』に出てくる強者、
平手造酒(ひらて みき)からとられた名前だと思うが、
この男が自分は助平だと連呼するのだ。
強いと言われれば弱く、弱いと言われればあべこべに異常な強さを
発揮するところが面白い。そして、オレは助平だと訴える。
ああ、これは大久保さんに宛てて書かれたのだなと
当時の配役表を見なくてもすぐにわかる。
鷹さんも色っぽい人だが、あの雰囲気で「オレは助平だ!」と
叫んで回っていたら、舞台は湧いただろう。
英国で観た助平なパフォーマーとといえば、
第一に、フランスから来ていたウィリアム・クリスティという
指揮者&チェンバロ奏者が思い浮かぶ。
演奏もそうだし、全身黒ずくめにも関わらず
足元にチラチラと覗くソックスだけは真っ赤、
ああいうところが実に助平ったらしい。
あれは彼のトレードマークで、この間に聴きに行った
演奏会では、最前列のフリークらしき客も真似して
赤いソックスを履いていたのが目立った。
あんたも好きねえ、という感じ。
カーテンコールの時など、女性奏者の腰に手を回して
褒め称えるやり方など、露骨に助平があわられている。
堂に入ったものだ。
もう一人の助平は、ザ・シックスティーンという合唱団を
率いるハリー・クリストファーズ。
一昨日の夜も彼のライブを聴きに行ったのだが、
これは希代の助平野郎だと思わずにいられなかった。
彼がクリスティと異なるのは、
一間するとひどく真面目そうなところだ。
だが、聴くべきを聴き、見るべきを見れば
彼が心底ムッツリだということがすぐにわかってしまう。
だいたい、一昨日のプログラムは環境破壊を強く訴えたもの
だったが、実際のパフォーマンスを聴けば、
それが崩壊の美を謳っていることは明らかだ。
会場はロチェスターというロンドン近郊の古い街にある
大聖堂。そこで、ルネッサンスからバロックまでの曲を順に歌い、
また同じ曲をたどりながら元の時代に戻っていくという趣向。
いわば自然の円環を表現していたわけだが、
映像作家が作ったプロジェクションと合わせて考えるに、
人類など滅びてしまえば良いと言わんばかりの美感に
溢れていて、何度も聴いてきた彼らの演奏の中でもベストの
パフォーマンスだった。
終演後に話しかけて「あなたは実に危険な巨匠ですね」と
伝えたらニヤニヤ笑っていた。あれは、真剣に環境問題に
拳を振り上げる人の態度ではない。
誰も彼もが快楽主義者だと思わずにはいられない。
そういう助平な人たちを、私は好む。
11/1(火)頭がまっ白
10/28(金)桃山さんが亡くなった
↑2017年 横浜トリエンナーレの準備中。
作業中の桃山さんを訪ねるとすぐにビールを出された
水族館劇場の桃山邑さんが亡くなった。
桃山さんが病気だと聞いたのは渡英してからだった。
それから、春の水族館劇場公園には多くの人たちが駆けつけていた。
皆、それが桃山さん現場にいる最後の公演になると知っていて、
自分も列に加わりたかったけど、叶わなかった。
初めて桃山さんと喋ったのは、
入方勇さんの遺品を整理しに行った時だった。
入方さんは北海道出身の役者で、第七病棟の劇団員だった。
この劇団はたまにしか公演しない。だから入方さんは見世物小屋の
主としても活躍し、各地の縁日を賑わせていた。
私たちが初めて『下谷万年町物語』の上演に挑んだ時、
出演者募集に入方さんが応えてくれた。
役者としても面白い人だったけど、持ち前の見世物小屋設営の腕を
活かし、唐ゼミ☆のテントを飾り付けてくれた。
以来、入方さんから教わった方法をもとに、
テント劇場の外観を造作することもまた私たちの表現になった。
知り合ってから一年後、入方さんは亡くなってしまった。
「また出てくださいよ」と頼んでいたのに。
連絡を受けたのは『下谷万年町物語』再演の稽古をしていた時だった。
気持ちのやり場がなく困っているところに、
入方さんが借りていた倉庫の整理をするから手伝いに来ないか
と声をかけてくれたのが水族館劇場の皆さんだった。
入方さんは、"カッパくん"の愛称で親しまれた、水族館の常連だったのだ。
埼玉のどこだったかは忘れたけれど、
指定された倉庫に行くと桃山さんたちがいて、一緒に道具を整理した。
それから入方さんが住んでいたアパートにも行き、
荷物を運び出して作業は終わった。
それから桃山さんが誘ってくれて韓国料理屋に行った。
お酒と料理が並ぶと、桃山さんは「今日は入方の話をしよう」と
言って流れをつくってくれた。
それから、私たちの交流が始まった。
寿町や都内に、三重の芸濃町にも公演を観に行った。
桃山さんたちも唐ゼミ☆公演を観に来てくれた。
特に面白かったのは新宿中央公園で『唐版 風の又三郎』をやった時。
予約して来場した桃山さんは「山谷で揉め事が起きたので
初めだけで失礼させて欲しい。ごめん」と言い、
一幕だけテントの外から見て、台東区に殺到して行った。
自分が良かったと思うのは、
2017年横浜トリエンナーレのスピンオフ企画で水族館劇場が
寿町に夜戦攻城をたてるのをサポートできたことだ。
お世話役を横浜美術館の学芸員Sさんがしていて、
まずは誘致すべき土地を一緒に見立てて欲しいと頼まれたので、
喜んで案内して回った。Sさんは自転車、私はランニングで。
何箇所も候補を出したけれど、もちろん、水族館には寿町でしょう!
と言って、数ヶ月後に実現した。
当時一緒に働き始めていたKAATの眞野館長と一緒に桃山さんたちを
応援した。上の写真は陣中見舞いに行った時のもの。
台本が遅れることについて、
劇も劇場も千穐楽を終えてなお未完成であることについて、
桃山さんはわざとそれらを、信念を持ってやっていた。
そのことを心底理解できるようになってきたのは最近のことだ。
初日に駆けつけると、「なんで初日に来るんだよ!」と
冗談めかして怒られる、いつも桃山さんとのやりとりは
シャイで、優しくて、楽しかった。
帰国したら、また桃山さんに会いに水族館劇場に行こう。合掌。
10/27(木)目標は300
↑見た目は倉庫のようなスタジオでもオペラが上演される
↑中央線沿線にある小劇場と変わらないサイズ感だが、演目はかなり違う
ここ数日、朝は日本の仕事。
カプカプ光ヶ丘と新井英夫さんの講座が週末に始まるので、
その対応が急務。何しろ、こちらは朝6時でも、日本は午後2時。
就業時間も終盤に差し掛かる頃だ。なにか気忙しい。
これから2ヶ月、ずっとこんな感じになるのだと思う。
『下町ホフマン』が厳しい。
目の前のやりとりは大変に面白いのだけれど、
何しろ量が膨大だ。Wordに打ち込みながら読んでようやく
半分を過ぎたところだけれど、手元の台本様式にしてすでに
150ページを越えている。『腰巻おぼろ 妖鯨篇』に次ぐ長大さだ。
300ページ超と踏んでいる。
これまでのペースを維持してあと12日間かかる。
ひとりひとりのせりふが長く、ページをめくって
ビッシリ詰まった紙面を見るにつけ、
"ああ、唐さん、調子いいですね"などと対話。
朝の時間だけでは遅まりきらず、夕方、帰宅後、
空いた時間はすべて『下町ホフマン』に。
それから、昨日は良いことがあった。
残り2ヶ月を気遣ったギャビンが、劇場執行部と
ルイシャム評議会の定例会議に自分を招いてくれた。
神奈川で行ってきた仕事に置き換えると、これは
県の文化担当者との打ち合わせに同席するという感じ。
それにしては、皆さんフランクだったけれど、紛れもなく中枢だ。
今、劇場やフェスティバルが何にフォーカスして動いているか
たちどころにわかる。これからは二週に一度、これに参加。
初めてだったので固有名詞の多さに面食らったが、
何を喋っているか半分くらい分かるようになってきた。
あと、観劇について腹を括った。
年末までに観る公演数を目標300に設定した。昨日で241本目。
しかし、ただ観ればいいってもんじゃないこともわかっている。
これは!と思うものを、密度高く追いかけるようでなければ。
そもそも、自分が数字を意識するようになったのは
渡英前に海外研修の先輩に「オレは200ほど観たよ」と
言われたからだ。「多いですね」と答えたら「そうでもないよ」
と言われて、まずは200を目標に置くようになった。
ところが、これが意外に簡単だったのである。
達成したのが9月上旬。それからちょっと宙ぶらりんで
過ごしてきたが、もうこれは数にこだわった方がいい感じが
してきた。というわけで300。
金田正一投手には及ばないけれど、何となく気持ちが分かる。
昨日はロンドンから2時間かけてBath(バース)という街に行った。
古代の温泉地として有名な観光地だが、ここの小さな王立劇場で
『Dido & Aeneas』の舞台版を観ることができた。
これまでコンサート形式ばかりだったから、他で観た時より
歌手や演奏に弱いところもあったが新鮮だった。
ドラマに寄せきったストレートプレイのような上演。
最後の方にドキリとさせられる、それでいて理にかなった
良い演出があった。
今月中に250に迫ることができればイケる気がする。
バカバカしいと知りながら、けれども、後悔の無いようにしたい。
10/26(水)ディヴィットさんの引退
10/25(火)ドカ雨をかいくぐり・・・
10/21(木)野外テントが建った
10/20(木)週末はマス・ダンスもある
10/19(水)週末は『オオカミだ!』会議
10/18(火)エンジンかかってきた!
『下町ホフマン』の研究を開始したおかげでエンジンがかかってきた。
研修する、遠出する、公演を観る、飲食や睡眠、掃除など生活する。
それに『オオカミだ!』に工夫を凝らす。
初夏までのように一日の目が詰まってきた。
残る時間は少ない。意地でも力押しに鞭をくれるタイミングなのだ。
↑練習&本番会場であるSedqehill Academy
15日(土)
歩いて南下し、ルイシャムショッピングセンターから1時間のところに
ある高校に行った。ここのホールで、22-23 日に控えている
ダンスイベントの稽古。150人くらいで練習している。
10人のダンサーを中心に稽古を進行していく。
彼らが各チームに散る。
ティーンたち、障害者たち、子どもたち、シニアたち、など。
そこに国際性も入り乱れている。
アフリカやインドの舞踊も組み入れられている。
さすがのバラエティだ。
中心となるダンサー10人の動きがキビキビしていて気持ち良い。
小学生で、すごい身体にバネがある少年を見つけた。
ふざけてばかりだが、振り付けの飲み込みも異常に早い。
これから稽古や本番のたびに、彼に注目しよう。
↑演奏後のピーターと
16日(日)
『ベンガルの虎』本読みを終えて走って駅に行き、
2時間ちょっとかけてドーバー海峡に面した港町Broadstairsに到着。
この街の小さなホールで、ピーター・フィッシャーがグリーグの
ヴァイオリンソナタを3曲立て続けに演奏した。
ピータにとっては明らかにハードワークだったが、
今年聴いてきた彼のライブの中でベストの仕上がりだった。
19世紀のスタイルに規範を求める彼の美学が満ちていて惹き込まれ、
痛快だった。ソリストとしての彼に立ち会える機会は多くない。
来て良かった。
燃焼してハイになったピーターと海辺に行き、
ディケンズの別荘など見て、季節外れになったビーチ近くの
レストランでフィッシュ&チップスを食べた。
ゴールデンチッピー以外で初めて美味いと思う店に出会った。
かなりライトな仕上がりで、また違った美味しさだった。
演奏後のピーターは疲れが溜まっているのだろう。
何度も道を間違えながらグリニッジに帰宅。
ダイアンがピーターに会いたがるので、少し家に寄ってもらった。
彼らの関係は帰国後も続くだろう。
↑週末に向け通し稽古
17日(月)
学校に行き、午後はDeptford Loungeで
女王の崩御につき延期されていたMoving Dayの稽古。
演出家レミーやプロデューサーのジュリーと久々に再会できた。
前日に日本の三重で行われたジャパニーズ版との違いについて
話したりもした。彼らの心配をよそに、出演者たちの記憶は確かだった。
通し稽古をし、ミーティングして金曜日の本番に備える。
・・・と、ここまで書いているうちに、
放課後の高校生たちが図書館のテーブルを占拠し始めた。
彼らに囲まれてこれを書いていたが、エアドロップでエロ画像が
送られてきた。斜め横の五人組が「しまった!」とばかりに
キョロキョロしている。送ったのは彼らのうちの誰かだ。
こちらはお首にも出さないが、内心ニヤニヤしてしまう。
稽古後もここに残って仕事していて良かった。
どんなだか紹介できないのが残念だが、画像がエグい。
10/14(金)カンタベリーへの旅②
10/13(木)カンタベリーへの旅①
10/12(水)これがクリスだ!
10/11(火)今週末から『ベンガルの虎』
『ベンガルの虎』のことを考えながらカレーを食べる(ベジ専門店)
唐さんたちはバングラデシュで毎日カレーに辟易し、
醤油を惜しみながら使ったらしい。毎日はツラそう・・・
先週末に『黒いチューリップ』を終え、
今週末より『ベンガルの虎』をWSの題材として取り上げる。
唐ゼミ☆で未上演の作品をテーマにするのは、
『少女仮面』に引き続き二度目。
「僕らが上演したときには・・・」という話はできないので、
あるべき舞台の姿をより強く思い描くワークショップになる。
「唐ゼミ☆で上演するとしたら・・・」という具合だ。
もちろん、初演時の資料を紐解いたり、この演目を持って
唐さんが行ったバングラデシュ公演に思いを馳せることになる。
新宿梁山泊の舞台も観ているので、あの上演のことも思い出したい。
あの頃、私たちは開国博で巨大バッタを使ったイベントに
奔走していた。それの初日をやった翌日、
紫テントの立つ井の頭公園に駆けつけた記憶がある。
暑い中、唐さんと並んで観た。
あの公演で、それまで"広島桂"さんだった桂さんは
ヒロインの名前"水嶋カンナ"になった。
カーテンコール、金(守珍)さんがあの甲高い声で
「水嶋カンナを演じました水嶋カンナ!」と叫んだ時、
可笑しかったけれど、度外れな情熱と真剣さが伝わってきた。
それから、前によく通った入谷坂本町の景色も甦る。
2014年のお正月に私たちは唐さんの母校、
坂本小学校でやなぎみわさんが書いてくれた劇
『パノラマを』を公演させてもらった。
その前年、春からよく入谷に通った。
小野照崎神社の御山開きや坂本小学校で行われる納涼祭にも
呼んでもらった。そしてなんと言っても、朝顔市。
あんなにも賑々しいと想像していなかったのでたいそう驚いたし、
『ベンガルの虎』三幕の景色がたちどころに理解できた。
朝顔市は『ビニールの城』でも活躍し、
読売新聞紙上で唐さんが添加した連続小説『朝顔男』の
舞台にもなってきた。
日本ではコロナへの対応が長引いている。
朝顔市、浅草のほおずき市も完全復活は来年だろうと思う。
帰国したらまた行きたい。
初回はもちろん、『ビルマの竪琴』の話から入る。
ロンドンであの映画のことを考えていると、不思議な気持ちになる。
かつて東南アジアの島々で、出征したのに一発の銃も撃てず、
ただ飢餓と病気で亡くなった兵士たちも多かったという。
10/7(金)オレンジジュースに撃沈
10/6(木)古楽器集団のゆくえ
一昨夜の帰り、ロンドン・ブリッジから不思議なものを見た。
テムズ川に浮かぶ船はどちらも背が高い。
前後を挟む二本の橋より明らかに背の高い船が、
どうしてあそこにいられるのだろう?
一昨日はエイシェント室内管弦楽団を聴き、
昨日はエイジ・オブ・エンライトメント管弦楽団を聴いた。
エイシェントは古楽、
エイジ・オブ・エンライトメントは啓蒙時代
という意味。両方、ロンドンで古参の古楽器演奏集団だ。
古楽器集団は20世紀半ばに次々と現れた。
初め、カリスマ的なリーダーが中心となって発足し、
アンティークの楽器やその演奏方法を探究して、
古い道具や奏法の中から新しい響きやスタイルを生み出した。
彼らは既存の大オーケストラとは別の道を行った。
そして、当初は違和感だった演奏が、その後のスタンダードに
汲み入れられていった。
大オーケストラの地位は揺らがないけれど、
彼らの演奏の中には、古楽器集団の奏法や感覚が息づくようになった。
日本の60年代演劇もこれに似ている。
既存の団体に受け入れられない、あるいは背を向けた人たちが
小さな集団をつくって台頭した。もちろん、唐さんもその中の一人。
今や、大きな劇場で上演される劇にも、
唐さんや寺山さんや鈴木さんや信さんや串田さんのセンスが
生きている。運営そのものを直にする人たちもいる。
そういうことだ。
エイシェント室内管弦楽団の創立者、
クリストファー・ホグウッドはすでに鬼籍に入った。
お客さんの少なさが気になったけれど、後継者たちの演奏は
実にハツラツとしていて、初めて聴くハイドンのオラトリオ
『四季』の面白さを教えてくれた。
日本では滅多に聴けない、
けれどもCDではスタンダードナンバーのひとつである。
今年は一通りの楽曲を聴くというのも目標にしている。
それに自分の周囲に置きかえて、色々なことを考える。
もう10月なので、年明けから始まる日本の生活に片足は戻っている
ような感じだ。体はロンドンだけれど、頭の中で来年の帰国後を
思い描くことが多くなってきている。
10/5(水)あのパーティーがやってくる
10/4(火)失くしたものの数々
9/30(金)またストライキが来る!
初めてチラシを受け取った。
最近、また鉄道ストライキがあるらしいと噂で聞いていた。
それが、昨日、グリニッジから都心に出るために駅に行ったところ、
気の良いお兄さんがこの宣伝チラシを配っていたのだ。
10月1日と5日、8日に実施されるようだ。噂は本当だった。
今年、何回目のストライキだろう。
特に印象的だったのはエジンバラから帰れなくなった8月第3週の
ストライキで、あの時は前日に「数は少ないけど大丈夫!」と駅員に
言われたにも関わらず、翌日になってロンドン行きが全滅、
宿泊を延長する羽目になった。
もっとも、あの素晴らしいスコティッシュ・ナショナル・シアターの
仕事に立ち会えたのは収穫だった。さらに翌日、
疑心暗鬼にかられた私はかなり早朝にエジンバラを発った。
鉄道もまた一寸先が闇、これが日本との違いだ。
郵便についても似たようなことが頻発している。
こちらでもAmazonをよく使う。"JP"ではなく"UK"。
これがしばしば、勝手にキャンセルされるのだ。
最もひどい場合はこんな具合。
「翌日に配送」とあるのでポチる。
翌日に「あと三日かかります」の通達。
さらに二日後に「明日届けます」の連絡。
当日になり「うまく届けられないのでキャンセルしました」
というメッセージが届く。・・・来る来る詐欺。
悔しいのは、待ち続けている期間に、
街のお店で目的の品物に遭遇してしまう時だ。
目の前の品を買うこともできず、かといって、
本当に届くかどうかも怪しい。
体感的には、4回買い物をするとそのうちの1回は勝手に
キャンセルという頻度。これもまた日本との違い。
10月1日(土)はタイムトライアルになりそうだ。
朝のオンラインWSを終えた後、13:30キングスクロスまで余裕を
持って移動するはずだった。が、ストライキにより想定を
変えなければならない。どの電車が止まり、どの電車は動くのか。
混むであろうバスだとどの程度かかるのか。
そんな情報収集と試行錯誤が必要だ。
少し油断するとすぐにピンチが訪れる。日本との大きな違いだ。
9/29(木)昨日から一人暮らし
9/28(水)極寒、リバーサイドの野外劇
9/27(火)Croydonの教会から
↑ガラの悪い街ながら壮麗な教会がある。コンサート直前の風景。
イギリス国教会の様式
Croydonという街に初めてやってきた。
といってもロンドン市内、Albanyから徒歩と電車を合わせて
南に小一時間行ったところにある街。
ああ、また一つワイルドな場所に来た。
スリや盗難に遭わないように。ケンカにも巻き込まれないように。
けれども、見るべきものは見たいのでジロジロと周囲を睨め回しながら
歩いてしまう。
目的は9月頭に都心で聴いた合唱集団The Sixteenの公演。
彼らほどの実力者であれば、同じプログラムでも何度も
聴きたくなる。むしろ、違う会場の建築を観て、
そのアコースティックをいかに彼らのものにするのか、
愉しみは膨らむ。それにしても、なかなかの土地柄・・・
こういう新たな土地、しかも経済力や治安が良くなさそうな場所を
訪れるのにも慣れてきた。パウンドランド(英国の100円均一)や
Icelandという量販店スーパーを発見したら、その土地の平均所得は
推して知るべし、ということも分かってきた。
自然に、財布やケータイを仕舞う場所を組み替える。
後ろポケットに入れていようものなら、
ヒョイとつままれてしまうこともあるからだ。
先週末、日曜日は面白かった。
ピーター・フィッシャーの出演するフィルハーモニア管弦楽団が
マーラー1番を演奏するので、この曲が最も好きだというダイアンを
連れて行った。指揮者のサントゥ・マティウス・ロウヴァリは美音で、
精妙な優雅な音楽をやる。
主題の変遷がよくわかり、綺麗な演奏だった。
これがロンドン交響楽団ならもっと躁鬱の激しくなるけれど、
彼らの演奏は温かみがあって、高齢のダイアンを招くに
もってこいだった。
ピーターがお友達割引を駆使して、特等席を格安で用意してくれた。
私たちが座った席の周りには彼の他のお友達もいて、
終演後はその中のご夫妻のご自宅に伺った。
我ながらちゃっかりしたものだが、
ダイアンは持ち前の社交性を発揮し、サウスバンク・センターと
ナショナル・シアターから徒歩5分のところにあるその家を
「ステキな部屋だ!」絶賛しながら、私と一緒にお呼ばれした。
帰り際になって、その家のご主人に、
「昔、日本人の演出家が演出した舞台を観たことがある」
と言われた。アラン・リックマンが出ていた、とも。
ということは、蜷川さんが演出し、清水邦夫さんが書いた
『タンゴ・冬の終わりに』の英語版『Tango at the end of Winter』
に違いなかった。
1991年。プロデューサーの中根公夫さんは勝負をかけた。
それまで、十八番である『王女メディア』『NINAGAWAマクベス』
に向けられた海外での評価は高かったけれど、いずれも各地で
短期に公演したイベント的な公演だった。
その点、『Tango〜』は座組を海外でつくり「興行」を目指した。
日本の演劇人が挑んだ大ジャンプだった。
会場は、ウエストエンドの中心にあるピカデリー・シアター。
結果的には、勝ったとは言えない公演だった。
初日直前にチケット販売を行っていた会社が倒産して
売れていた入場料が全く入って来なくなった。
(それでも中根さんは、わずか当日券が売れる収入や助成金を
駆使し、赤字と闘いながら予定していた公演を全うした)
演目も、西洋のリアリズム演劇の延長にある戯曲をなぜ持ってきたのか
と言われたらしい。期待された"日本"の要素は、確かに弱かった。
けれど、観劇したその人は、面白かったので二度観に行ったそうだ。
これには嬉しくなった。
帰国したら、中根さんに伝えに行きたい。
9/23(金)店には決して近づけるな
Albanyに通うこと8か月が経とうとしている。
しかし、まだまだ知らないことは多い。
通い慣れた企画ですら、知らない計画が進行中ということもある。
これが日本語でのやりとりならば、注意して聴いていなくても
会話が自然と耳に入ってくる。「何それ?」と会話に割り込み、
情報を得ることができる。しかし、やはり英語は難しい。
そんな状態ではあるが、先日、
シニアたちを連れて都心に出かけると聞いた。
尋ねれば、数ヶ月に一度そういう外出をしているらしい。
連れて行ってよと頼んだら、ウェルカムと言われた。
結果、昨日は学校をサボって都心に出た。
朝10時にヴィクトリア&アルバートミュージアムに集合。
英国の黄金時代を築いた女王と旦那さんが世界から収集した品々を
展示した施設だ。南はアフリカ、東は中国まで、"帝国"という言葉を
強く実感させる展示品の数々。
10時に行ってみるとスタッフが集まっていた。
シニアたちはタクシーでやってくる。
今現在タクシーがどこにいるかはケータイでモニタリングできる。
それを眺めながら、導線を確認する。
このスロープを使おう、とか。
荷物置き場はここで、学芸員に話を聞く場所はここ。
最後に集合して軽食を取る場所はここ、という具合だ。
運営にあたるエンテレキー・アーツの面々は、サンドイッチや
スナック、フルーツを持参している。まことに余念がない。
今日の目当ては、常設展ではなく、
アフリカ・ファッションをテーマにした特別展だ。
コンテンポラリーにアフリカ色を反映したモードを展示していて、
華やかだった。その上で、常設展のアフリカ部門も見てね、
というコンセプトなのだが、今回は時間を限っているために、
シニアたちはひたすら特別展のみを見る。
果たして、タクシーから降り立ったシニアたちは輝いていた。
ルイシャム地区は移民の街。アフリカやカリブからやってきた婦人たち
なので、アフリカ・ファッションを地でいっているのだ。
展示場では一つ一つを食い入るように眺め、記念撮影をしてゆく。
とにかくじっくりと見て、キャーキャー盛り上がっている。
こういう性質の展覧会だから、おそらくファッションを学んでいる
学生たちが大勢来ていて、彼らもなかなかの洒落者揃いだったけど、
恰好も振る舞いも、うちの組は度外れに派手で周囲を圧倒していた。
ツアー開始前のスタッフ会議でお互いに確認しあったのは、
彼らをミュージアムショップに絶対に近づけてはならない、
ということだった。それだけで2時間過ぎてしまう。
そういうわけでショップには目もくれさせず、目的地まで案内した。
一通り終わった後は軽食を取り、迎えに来たタクシーにみんなで
乗り込み、にこやかに帰っていた。なかなかの遠足である。
9/22(木)鷹野さんに会う
9/21(水)安保さんが亡くなった日
9/20(火)まるでお正月のように
9/16(金)これは掘り出し物だ!〜メリナ・メルクーリ歌謡曲集
9/15(木)新首相は地元民
9/14(水)用意していた!
9/13(火)夏の終わり
9/9(金)200本達成と帰国への心配、女王の死
9/8(木)図書館での本番
9/7(水)野菜もカリブからやってくる
9/6(火)ロンドンの野外劇場
9/2(金)いつまでもウンコちんちん
9/1(木)基本的に間違っていた
8/31(水)ロンドンでのさまざまな体の不具合
↑投稿内容とは関係がない写真
Albanyの主催でスウェーデンの作家Ruke JerramのGAIAという作品を
展示した。てっぺんとそこの部分から3方向ずつワイヤーを引っ張って
安定させる。良いロケーションだったが、プロデューサーのメグが
仕込みも含めて4日間つきっきりだった。巨大バッタの展示を思い出した
マジでビビっている。
英国での暮らしは気楽で愉しいばかりではない。
まず体が痛い。2013年にKAATでの『唐版 滝の白糸』を
上演した後から、整体に通い始めた。
劇団員だった禿恵の紹介だったが、
あっという間に彼女より通うようになった。
回数券を買い、1ヶ月に一度身体が痛くても痛くなくても行く。
走ったり歩いたり習慣化した頃とも重なり、ルーティンになった。
と、このように、床屋、歯医者、整体、これらに月にいっぺん行く。
日本にいた頃は。
ロンドンではたくさん歩く。街が狭く交通費が高いからだ。
それは良いのだが、パソコンとスマホを見ている時間も長い。
これが結構堪える。そしてシャワーのみで風呂はないから慢性的に
首が痛い。これから寒くなる。大丈夫だろうか。
先ほど歯医者を挙げたが、歯も不安だ。
日本の自宅の隣の隣には近所で評判の歯医者がある。
これにしょっちゅう行っていた。
初め、痛かった奥歯をたちどころに治療してくれて、感激したのだ。
英国の歯医者は劣悪だと聞いた。
ロンドンで歯科治療を受けた場合、噛み合わせが悪くなることも
充分にあるらしい。語学力的に、細かく症状を伝える自信もない。
だから、歯医者に行かないために必死だ。
機会があれば歯磨き、歯磨き。
で、最後の難問は目である。
最近は目がかすむ。視力が落ちてきているのではないか。
基本的に英国の室内照明は暗い。
そしてホストマザーのダイアンは間接照明が好きなのだ。
ロシアとウクライナの戦争による電気料金の高騰は節電に拍車をかけた。
ますます、夜が暗い。
ひょっとして老眼か、とも思う。
早めにきているのかも知れない。
が、とにかく出来ることをしなければ、と思って最近は
スーパーでブルーベリーを買うことにした。
物価が高いのでブルーベリーも高い。
ひとパック400円くらいするが、仕方ない。
薬だと思って買っている。
残すところ4ヶ月である
英語に慣れ、知り合いも増え、色んなものを見聞きできたのは良いが、
この11ヶ月間の後遺症が残らないようにしなければならない。
8/30(火)深夜のルイシャム病院にて
8/26(金)Moving Day 稽古の大詰め
8/25(木)ハイドパークで
昨日は書き物の一日だった。
年明けにケッチさんとテツヤ(岡島哲也P)と作る舞台の準備をしている。
イギリス民話『3びきのこぶた』を題材にしたサイレントコメディの
ステージを作る。それで構成台本を書いているのだ。
オオカミだ! -『3びきのこぶた』に出てくるオレの話
いつもとは逆で、自分の書いたものに意見をもらって書き直す作業だ。
自分はせりふの台本は書かないけれど、イベントの構成台本を書いたり、
依頼が来て寄稿したりすることは度々ある。
それぞれに、テレビマンにエッセイストになったつもりで書く。
書くことは苦しいけれど、後から考えると充実する。
震災の後に吉原町内会から頼まれてやった節分イベントの
出し物は自信作で、ステージを見ながら近所のおばちゃんたちが
「よく出来てる!」と褒めてくれた。
吉原なので、『助六』を題材にした。
よく唐ゼミ☆に出てくれている鷲見くんがヒロインの揚巻に扮して
鬼たちが襲おうとすると上半身はだかのレスラー姿になり、
プロレス技でやっつける。彼の立派なお腹に「フライド・ロール」
というリングネームが墨で書かれているという他愛もないもの
だったけれど、よくウケたな。
東京乾電池が初期にビアガーデンでやっていた出し物は
こんな感じだったのではないかと、自分なりに考えた。
エッセイの方は、最近は岩波書店の月刊誌「図書」に書いたものが
来月に出る。こちらは、ロンドンでの生活を読書に絡めて書いた。
語学学校が終わり、Albanyでの用事が無かったので、
ロイヤル・アルバート・ホールに行って夜の演奏会の当日券を買った。
その後、ベンチに座ってZoomでテツヤにアドバイスをもらった。
ハイドパークで書き直し、テツヤの寝起きに届くよう送った。
ロンドンにはたくさんの自然豊かな公園がある。
ハイドパークはその王様だ。ハイドパークに行くということが
休日の立派なイベントになるのだ。
宮殿やモニュメント、池やアミューズメントがある。
それ以上に、やたら広くて伸び伸びとした公園だ。
こういう公園の芝生に敷物を敷いて食事したり寝転がったり
するだけで休日や遊びが成立するのが英国人なのだ。
ハイドパークのベンチで、
周りで遊んでいる子どもたちを眺めながら、
とにかく彼らにウケたい、大ウケしたいと心から願って台本を直した。
その後、夜の演奏会は22:15開演だからやたらと時間があり、
公園の反対側の中古CD屋に久々に行き、厚遇してもらえて気を良くした。
初めてハイドパークやこのCD屋に来たのは渡英直後の寒々しい2月だった。
あの時は不気味で幻想的な感じもした夕暮れだったけど、
今はのどかな馴染みの景色になった。
あと4ヶ月ジタバタして、あっという間に帰国。
帰国後の仕事について、徐々に直面し始めている。
8/24(水)あの組織を訪ねて
8/23(火)病みついた人たち
8/19(金)結局、帰れなかった。
8/18(木)再びエジンバラへ
8/16(火)夕立が降った
8/12(金)あれから色々ありまして
↑黒い服に黒い鞄で分かりにくいので、アップ写真も↓
昨日のゼミログを書いたのは帰りの電車の中だった。
エジンバラ〜ロンドン間は4時間半かかる。
東京から九州に迫ろうという時間だ。
日本にいたら長く感じるだろう。
飛行機で行こうかな、とも考えるだろう。
しかし、イギリスでは断固電車だ。
まず、景色に慣れていないから見飽きない。
そして何より確実性。
ロンドンにはたくさんの空港があり、
待ち時間があり、時間の調整があり、燃料代も変化する。
だったら、安定の電車。そう思っていた。
帰りの電車はうるさかった。
座った席が、ちょうど大家族に囲まれる具合だったために、
彼らがひっきりなしに行き来するし、頭越しに会話してくる。
イギリスの電車には必ず大騒ぎする人たちがいる。
どう処したら良いのか。物申して良いのか、自分にはわからない。
そんな中でゼミログを書き終えた。
すると彼らは二つ目くらいのニューカッセルという駅で降りた。
やれやれ。
と、この瞬間、気づいてしまった。
ずっとTシャツの中に忍ばせていた貴重品入れ。あれがない。
中には、これから観る公演チケット、国際運転免許証、
そして、パスポートが入っている。
しばらくゴソゴソやって、いよいよ手元にないことを確認する。
すると、アラン・カミング観劇中にチケットをしまうため、
客席で胸から取り出したことを思い出した。あそこに置き去り!
それから、ミミに電話し、劇場に電話し、
どちらも電話に出なかったので、問い合わせフォームに
メッセージを打った。
ピーターはその夜もエジンバラで演奏している。
明日、彼が回収してきてくれないかな、などと期待したが、
ともかく劇場に連絡をつけることが先決だ。
ちなみに、昨日に観劇したBURNはあの演目の千秋楽で、
夜公演はない。終演後、あの芝居が気になっていたピーターに
「ひどくつまらなかった」と3分くらいかけて悪口メールを打ったので、
自分は一番最後に客席を出た。だから係員以外に発見は不可能。
という好条件ではあるものの、ドキドキする。
結局、ミミにも状況をメールして、昨日はまっすぐ家に帰り、
夜遅かったので、シャワーを浴びて寝た。
ダイアンに「どうだった?」と訊かれ、「良かったよ」と簡単に伝えて寝た。
翌朝になりミミから返事があったので、どんな貴重品入れだったか、
羽田空港で撮った自分の写真などを送って説明した。
朝食時にダイアンに打ち明けると、涙目になって神に祈り始めた。
・・・やはり、昨夜に黙っていたのは正解だった。
ピーターに連絡を取ったが、彼は早朝からグラスゴーに移動していた。
今夜に別の演奏があるらしい。忙しいそうだ。
ピーター「帰りに戻ろうか?」と言ってくれたが、
見つかりさえすれば来週に自分で回収できるから安心してほしい。
そう伝えた。
すると、ミミが通常より早く電話で劇場オフィスをこじ開け、
話をつけてくれた。自分が送った写真も先方に送ってくれたらしい。
さすが劇場関係者。話が早い。あとはアツシで電話するべし、とも。
早速に先方の担当者とスピーカーホンで話し始めたところ、
横から猛烈な勢いでダイアンが喋り始め、あっさりと自分の物だと
確認された。「これはかなり重要ですね」と先方は笑っていた。
イギリス人のいい加減さに知り尽くすダイアンは油断がない。
相手が何日の何時に確かに劇場にいるかを確認し、
「変更があったら私に電話をしてくれ!」と迫っていた。
そういうわけで、今朝9:30をもって問題にはケリがつき、
巻き込んでしまったみなさんに現状と御礼を伝えて、
通常スケジュールに入っていった。
シニアの街頭劇の稽古に立ち会い、日本とZoom会議をし、
Albanyで会議をして、現在に至る。
2010年以来ファンになったフィルハーモニア管弦楽団の面々と
一気に繋がることができたので、浮かれたのだと思う。
ヤキモキした分、今日はやたら小銭を拾う。人生、正負の法則。
旅行時の装備について、もう一度考え直さなければ。
8/11(木)ロンドンへの帰路
↑一本目に観た子どもたちのための劇。素朴な感じの二人だったが、
主役の老人人形がフルに活きるよう計算し尽くされた造形だった。
最終日、エジンバラ三日目は二つの作品を観た。
1本目:A VERY OLD MAN with ENORMAOUS WINGS
シルヴプレさんが観たという人形劇を観ようと思っていたが、
道すがら、チラシ配りの女子が渡してくれたフライヤーを見て
ピント来た。開演は10分後だったが、急いで駆けつけて観劇。
しっかり者の女性とトボけた男性のコンビによる、
人形や映像、サンプラーを駆使したキッズプロだった。
と言ってもギミックではなく、マンパワーを主体として、
お客さんの想像力に訴える。ボケてニワトリ小屋に住む
老人に周囲のみんなが困惑するのだけれど、最後にはこの
おじいさんが天に召される。
最小限の規模に考え抜かれた美術の造形ひとつひとつが見事で
さりげない恰好のパフォーマーが周囲を活かしきる姿を
観ている側がどんどん好きになる公演だった。
2本目:BURN(詩人ロバート・バーンズのこと)
スコットランドの国民詩人にまつわる一人芝居を
同じく地元の名優アラン・カミングが演じるという趣向。
しかし、演出家がイフェクトを多用しすぎて、肝心のアランの
魅力が立ち上がってこない。観客は皆、くだんの個性派俳優を
観たくてきているというのに、もったいなかった。
実に嘆かわしい。最後に、緞帳の前に出たアランがカマチに
腰掛け、観客に語りかけるシーンがほんの少しだけあって、
初めからそれをやれよ!と思った。
ライティングとプロジェクションを組み合わせて、
彼の顔がよく見えない。重要なところで、
あまり上手いとはいえないダンスを見せられた。
体は鍛えられているが、そういうことではないと思った。
一本目と二本目の間に、韓国料理を食べようと思った。
学割の効く良さげな店を、昨日のうちに発見していたのだ。
が、開店までに時間があったので、木陰で寝そべってラジオを
聴いた。立ち上がると、近くのカフェからこちらを呼ぶ声がする。
ピーターとフィルハーモニア管最古参の女性奏者だった。
エレナーさんという方。日本に20回以上きたことがあるという。
席を勧められたのでコーヒーをご馳走になり、
かつてのボスであるジュゼッペ・シノーポリの話を聴いた。
昨日『ルサルカ』を観たのでオペラの話になり、歌舞伎について
訊かれたので、現在の市川猿翁が演出して、吉井澄雄さんが
ライティングした『影のない女』の話をして盛り上がった。
ロンドンに帰ったら、リハーサルを観にきなよ、と言われた。
北仲スクールをやっていた2010年にフィルハーモニアと
サロネンによる『中国の不思議な役人』を聴いてクラシックに
興味を持った。これもピーターのおかげだ。
ピーターが主宰するチェンバー・アンサンブル・オブ・ロンドンは
11月にプリマスで公演するということだ。
プリマス〜コーンウォール〜ミナックシアターの旅を
ここに入れようかと思っている。
エジンバラにはまた来週行く。
8/10(水)エンジバラの2日目
8/9(火)エジンバラに来た
↑ホルーリード・パークの崖の上
昨日からエジンバラに来ている。
有名なエジンバラ・フェスティバルに合わせてやってきた。
噂には聞いていたが、街に降り立って面食らった。
人、人、人。もう観光客がぎっしり。
街中の至るところにショーのチラシやポスターが貼り出されていて、
大きなものから小さなものまで、千や二千のプログラムが
ひしめいているのだと実感し、眩暈がした。
今回、私が目標に置いてきたものはわずか。
①ケッチさんに勧められブライトンでも観たジュリア・マシリーのショー
②ケッチさんがアドバイザーを務めたシアター・フェデリ・フェデリ
③ピーターがオケに加わっているドヴォルザークの『ルサルカ』
④清水宏さんが激闘したパブThe World's Endに行く
⑤エジンバラ城に行く
と、このくらい。
が、日曜日にロンドンでパントマイム「シルヴプレ」のお二人に
会えたことにより、目標が増えた。名優アラン・カミングが当地の詩人
バーンズの生涯を一人舞台にして公演しているらしい。
そこで、これを⑥に。
さらに、街で『一人でロード・オブ・ザ・リング』というポスターを
発見したので⑦。Summer hallという会場の演目が面白そうなので⑧。
朝からやっているパペットの公演を⑨とした。
到着から3時間で街を歩き、タイ料理屋に入ってこういう計画を組んだ。
その後は、なんだか人いきれにヘトヘトになってしまったので、
焦ってジタバタしないことにした。ジュリアのショーは22時頃に始まる。
3時間以上あるから、近くのホルーリード・パークに登ることにした
丘というか、山というか、崖というか。
数時間かかりそうだなと思ったが、麓で寝そべっているおじさんに
訊いたら「30分かからんよ」ということなので、歩き出した。
かなり簡単に辿り着き、フォース湾と市街地を眺め、
「アーサー王の玉座」と言われる岩肌も発見した。
なかなかの眺望で、『マクベス』のことを考えたり、
メンデルスゾーンの3番を聴いたりして頂上で1時間くらい過ごした。
降りるときに、一回転んで尻餅をついた。
筑波山でも、大山でも、降りるときはいつもこうだ。
ジュリアのショーは完成版というより、
エジンバラで観せるために刈り込まれていた。
ポップになっていて客席はウケていたけれど、
クリエイター力の発揮具合はブライトンの方が上だった。
ここには時間制限もある。なかなかに厳しい環境だ。
8/5(金)ショッピングセンターでの稽古
↑Lewisham Shopping Center 内部
昨日は、シニアたちと進めてきた街頭劇の稽古が
(と言っても建物内での公演だが)いよいよ本格化した日だった。
会場は慣れ親しんだルイシャム・ショッピング・センター。
ここが本番の会場であり、中のメインストリートとかギャラリー、
Albanyが今年のフェスティバルに合わせて構えたフリースペースなど
複数箇所を使って劇の各シーンが進行する。
構成・演出のレミーのテキパキとした指示のもと、
まずはどの会場でどの場面を演じるのか、それぞれで動きを
付けながら当たっていく作業が続けられた。
いつもの稽古は90分強だが、今日は2時間半以上やったので
最後にはシニアたちもくたびれていたが、開放的で賑やかな空間に
やって来られたことに誰もが嬉しそうだった。
実際、やりとりも活き活きしてきた。
もちろん、昨日の稽古はセンターの許可を得てやっているが、
普通のお客さんが往来する場所で稽古は進められ、自然と衆目が
集まったり、赤ちゃんに絡まれたりするのも面白かった。
警備員が、それとなく見守っているようだった。
思えば、自分のこのショッピング・センターに対する思いは
この半年で劇的に変化してきた。初めてここを訪れたのは渡英2日目。
中にある郵便局にビザカードを取りに来るというミッションが
あったからだが、あの時ははっきり言って怖かった。
治安への不安、言葉の壁が立ちはだかる。
政府から届けられた郵便を受け取るだけの作業にぐったりした。
それが、ダイアンの家に住み始めた頃から、
この場所はあらゆる買い物が安く便利に住む場所になった。
日用品から衣類、食料品まで、ほんとうに何でも揃うのだ。
この中にあるH&MとTK-Maxxxの服で自分の春夏秋ものを買った。
Wilkoというホームセンターでタオルや傘、歯磨き粉を買う。
他にも、パウンドランドがある。
アイスランドという、いつもオレンジジュースを買う定番の店も
すぐ近くにある。油断は禁物だが、安心していられる場所になった。
本番は9月の上旬、二日かけて3回行われる。
あと3回のリハーサルで公演だ。恐るべきスピード。
8/4(木)久々にハードなやつ来た!
↑アーネスト・ダウスンの墓参を終えた。
明らかに誰にも顧みられていなさそうだったので、年内に再訪し、
掃除してから帰国しようと思う。
※今日は生々しい話になるので注意してください。
昨日は久々にハードなやつが来た。突然に。
ダイアンには、ロンドンでは道で話しかけられても絶対に相手を
するなと厳命されている。しかし、習慣というのは拭い難いもので、
ついつい立ち止まってしまうのだ。相手もまた、
そういう自分を見透かして声をかけるのか、とも思う。
Albanyの近くで、黒人の女性に声をかけられた。
30歳くらいだろうか。彼女は私を呼び止め、
ワンピースのすそに付いたたくさんの血を見せながら
2ポンドくださいと頼んできた。
生理がきてしまったので生理用品を買いたい。ということなのだ。
オレは英語がわからん!ごめん!
と言って振り切ったが、なかなかの威力だった。
その後、最近ピーターに教わったレバノン料理屋に行った。
鶏肉をタレに漬け込んで焼いたものに、ライスとサラダが付いて7ポンド。
こちらにしてはリーズナブルな値段で味が良く、量が多い。
何より焼き方が優れている。
炭火の管理をせっせとして、うちわであおぎながら焼いてる。
焼き加減を確認するしぐさは日本の鰻屋そっくり。
調理が雑で、基本的に焼き過ぎパサパサのロンドンでは珍しい丁寧さ。
肉がジューシーなまま出てくる。さすがピーターの紹介。
昨日しくじったアーネスト・ダウスンの墓参りも達成できた。
開園時間中の霊園に入ったところ案内がないので、しばらくウロウロした。
物言わぬ墓を探すのは難しい。まして藪の中みたいなところに
いくつもの墓石が見える。暑いし、虫が多いし、植物も棘だらけなので、
そういう場所を探すのは至難の技だ。今が冬であれば!
今日もダメかと思いながら、
向こうからやってきた数少ない通り掛かりの人に訊き、
通常は留守中の管理室に施錠にやってきた係員にも訊いて、
やっと発見できた。
ダイアンからもらったあじさいと文庫本を備えて手を合わ、。
ヘタクソな英語で彼の代表作を誦じた。
昨日の彼の誕生日を祝いに来た者は自分だけのようだった。
清々しい気持ちである。
その後に冒頭の女性に声をかけられ、
今日も一日、ふんだんに人間を味わった。
来週はエジンバラに行く。今週はできるだけ大人しく
リーズナブルに過ごして、エジンバラに備えよう。
8/3(水)ダウスンの誕生日
8/2(火)特別な夜
8/1(月)『蛇姫様 わが心の奈蛇』本読みWS 最終回レポート(中野)
7/29(金)ヘリフォード〜ラドローへの旅
↑ヘリフォード大聖堂
昨日から旅行している。ロンドンに戻るのは日曜の早朝。
英国の真ん中あたり、ヘリフォードという街を中心に
行われている"スリー・コーラス・フェスティバル"にやってきた。
この音楽祭、
これまで全く知らなかったが300年以上の歴史を持ち、
周辺の3つの都市が持ち回りでメイン会場を受け持つことから、
こういう名前だという。当然、コーラスに力を入れている。
これに興味を持ったのは、
前にウィグモア・ホールで聴いたフレットワークという
ヴィオール集団がきっかけだった。
面白いと思った彼らがこのフェスに参加する。
それでフェス自体が気になるようになり、
ピーター・フィッシャーにどんなものか問い合わせたところ、
彼もフィルハーモニア管弦楽団の一員として当地に逗留、
演奏を連続的にするということだった。
こういう話を聞く過程で、メインが合唱ものだとわかったし、
スケジュール的な事情もあって、当のフレットワークは諦め、
フェスティバルが最高潮に達する最終3日間を狙うことになった。
問題が多かったのはホテルの予約だ。とにかく予約が取れない。
超高額か、車移動なら宿泊が可能なテント泊というのを音楽祭が
推していた。それとて、結構な値段だ。
考えてみれば、ヘリフォードの人口は5万人。
そんなところに普段からたくさんホテルがあるわけはない。
それに、出演するミュージシャンたちが先に近場を押さえている
に違いない。そのような事情から、自分が泊まるのは電車で
30分ほど移動した先にあるラドローという街に落ち着いた。
こちらは人口1万人強。さらに田舎だが、古城で有名らしい。
↑ラドロー城
まずはラドローに着いて古い城を見物してから、
ホテルにチェックインして荷物を置き、ヘリフォードに来た。
ラドロー城は良かった。先日に観た『リチャード3世』。
あれに殺されてしまう二人の少年王子が出てくる。
兄の方が、主人公であるグロスター公リチャードの兄
エドワード4世の長男にあたる。
彼はこのラドロー城で帝王学を学んでいたところ、
父の死の報せを受け取り、王位を継承するためにロンドンに向かった。
そしてロンドン塔に幽閉され、例の叔父さんによって殺されてしまう。
また、『ヘンリー8世』で離婚させられてしまう賢妻のキャサリン。
あの人もこの地の出身なんだそうで、なかなか高貴な場所のようだし、
実際に行ってみて、その雰囲気はかなり伝わってきた。
そしてヘリフォード。コンサートのメイン会場である大聖堂の立派さ。
これは規模と美観において、渡英以来随一と断言できる。
こんな田舎に、忽然とこんな立派なものがあるなんて。
そういえば、神奈川県には寒川神社がある。
相州一宮というくらいだから県内で格式が高さは抜きん出ている。
そして寒川町はこの神社を頂くことで、横浜市民の私から見ても、
かなり自信満々な感じがするのだ。
↑寒川神社(去年の12月)
似ている。
ちょっとした中庭なども古い建物と植物が一体になり、
よく手入れされていて抜群に美しい。
フェスティバルのために周囲に建てられた運動会用テントや
仮設トイレは美観を損なっているけれど、それにしても壮麗だ。
帰るのは日曜の早朝。あとまるまる二日間、滞在する。
↑ヘリフォード大聖堂のコンサート開演前
7/28(木)パーセルの職場②
↑ウェストミンスター寺院は11世紀に造られた。パーセルが生きた
時点ですでに500年の伝統を持っていた
ヘンリー・パーセルの生没年は1659-1695年だから、
約36年の短い生涯だった。
衛生環境、医療、栄養、あらゆる条件が劣悪だったから、
子どもが成長するのが大変だった時代だ。
実際、パーセルの子どもたちは1歳に満たず何人も亡くなった。
彼の父親もウェストミンスター寺院に勤めた音楽家で、
ヘンリーの息子も同様だったらしい。職業選択の自由はない。
面白いのは、要するに国家公務員的ミュージシャンである
彼の一生が条件闘争の連続だったことだ。
さして多くはない給料はすぐに未払いになる。
さらに、国王に随行して音楽演奏する際、移動費が自費負担に
ならないよう交渉したともいう。
つまり、それまでは出張費を自分で出していたのだ。
出かけたがるのは王様なのに、あまりに理不尽だ。
このように、当時の労働条件はなかなか過酷だったらしい。
制服にあたる衣裳が擦り切れると、これを新調するための折衝が始まる。
17世紀後半といえば、エリザベス1世の統治時代を経て、
国王が斬首されたクロムウェルのピューリタン革命も乗り越え、
王政復古がなされた時代だ。王室の財政も不安定だった。
王が旅先から帰ってくる時、パーセルは様々な詩人の詩に曲を
つけて王を迎えた。オード(頌歌 しょうか)というやつだ。
くだらない詩もあれば、優れた詩人の作もある。
それからもちろん、教会でのセレモニーのために
アンセムをつくった。讃歌とか祝歌とかのことだ。
今回のロンドン滞在中、
沢山の教会のイブニング・コラールに参加してきた。
オルガン演奏からスタートし、開会の挨拶、懺悔の言葉、
ここから合唱と神父(牧師)や会衆(氏子総代?)による
詩篇朗読が繰り返される。合唱団と神父さんが対話的に
歌う時もあって、まだ規則性や手続きの順番を完全には
掴み切れていない。
こういう時に立つ。こういう時は座る。
こういう時はひざまづく。一緒に歌を歌う。
最後に寄付を(自分はほんの少し)する。
全部見よう見まねで、ワタシは外国人です!
という空気を振り撒きながら参加している。
いずれ立派に手順をこなせるようになってから帰国したいけれど、
この時点でも、パーセルが何のために曲を作り、オルガンその他の
楽器を演奏し、時にはバスとカウンターテナーで歌ったのかが
想像できるようになった。
彼は一生をずっとウェストミンスターの周りに住み、職場とした。
ロンドンを離れるのは国王の随行時だが、上記のことから想像するに、
そんなに生やさしいものではなかっただろう。
食事中の演奏を所望され、聴いても聴いていなくも演奏し続ける
という習慣が当たり前だった時代だ。
パーセルは劇場用の曲も作ったから、これまではそちらに惹かれてきた。
『ディドとエネアス』の他に、『妖精の女王』『アーサー王』
『テンペスト』『インディオの女王』などを好きで聴いてきたけれど、
今回の滞在を通じてオードやアンセム、王や女王の死に捧げた葬送曲を
もっと聴いてみたくなった。
作曲の経緯が経緯だから、似たり寄ったりの曲がたくさんあって、
駄作も傑作も入り乱れているらしいけれど、とにかく聴いてみたい。
生で聴いて、録音で確認して、そういう繰り返しの残り5ヶ月に
なると思う。
7/27(水)パーセルの職場①
7/26(火)幾多の空間を巡る二つのフェスティバル
7/25(月)『蛇姫様 わが心の奈蛇』本読みWS 第13回レポート(中野)
↑本物の伝治が登場して、ニセモノが暴かれる。胸には骨壷。
その中身は本物の薮野一家の骨。しかし、こんな格好で働いている人は
この世にいないだろう。これも唐十郎流のギャグ(撮影:伏見行介)
昨日は『蛇姫様 わが心の奈蛇』WSでした。
謎解きが立て続けに展開し、劇の興奮が高まっていくシーンです。
唐さんの筆も乗っているし、その勢いに任せて読んでいけば面白い。
けれども、ところどころ、唐さんの強引すぎる設定を味わいながら読むと
さらに面白い。もちろん、唐さんは、そういうことをわかって書いています。
辻褄の合わなさをシャレにして笑い飛ばしています。
まず、二つの映像を見るところから始めました。
天知茂主演 明智小五郎VS怪人二十面相の予告編
https://www.youtube.com/watch?v=DU2nSdNmYY4
片岡千恵蔵主演 多羅尾伴内シリーズ 正体を明かす場面
https://www.youtube.com/watch?v=xkheg50m3rw
これらを観ておくと、唐さんが思い描いたノリや
造形がよく見えてきます。両作とも、演技が二枚目すぎて笑いの域に
達しているので、おもしろ動画としても楽しめます。
その上で、
ドラゴン=鏡 という引用元不明の理論。
小林と伝治の対決による、小林の敗北。
バテレンの加勢が序盤。
というシーンが展開。
そしてここから、バテレンの壮大な謎解きが始まります。
まとめてみると、
①伝治はニセモノである
これまで伝治を名乗ってきた男はニセモノだと暴かれる。
彼は白菊丸に乗って密航した男で、当時は12歳。
シノが輪姦されるのを見ていたに過ぎない。
ちなみに、バテレンは従軍牧師として乗船していた。
②本物の"伝治"は日本人
小倉で乳飲み児(あけび)を抱えた恩人
シノを世話した。その東京に出て薮野一家の居候をしていたが、
脳卒中で倒れ、今は半身に障害を抱えてバスの整理係をしている。
シノが送った写真を、自分のニセモノになる男にユスられる
③薮野一家もニセモノである
大きい兄ちゃん(蛇)、文化や青色申告、知恵も密航者。
三年前に死に絶えた床屋の薮野一家を乗っ取った。
内縁は、もともとの薮野一家で生き残ったお婿さん、
だから文化たちを恐れている。
④白菊丸で起こったこと
シノが輪姦されたことは間違いない。
しかし、ニセモノ伝治が加わっていたかは不明。
バテレンは、当時12歳だった少年にそれは無理だという。
一方、ニセモノ伝治本人は満15歳だったと主張。
そのため、相変わらず自分はあけびの父親かも知れないと強硬に主張。
真の名前は「李東順(りとうじゅん)」
※唐さんによる「李東順」という名の引用元は不明
・・・と、このように、さまざまなロジックが展開します。
シリアスとコミカルが激しく交錯して、真剣なのかふざけているのか
分からないのがポイントです。劇的なやり取りが連続しながら、
あけびの出生がますます謎めいたことは確かで、
だからこそショックを受けた彼女は三度目の癲癇の兆候を見せます。
次の7/31(日)で最終回。かなりの力技で大団円に突入します!
7/22(金)デビットカード始末記
7/21(木)テンプル・チャーチに行ってきた
7/20(水)山火事も自然発生
↑22:15開演→23:00終演という大人の集まりだった。帰りは涼しかった。
昨日は火曜日恒例のWS"Meet Me"だったが、オンライン化された。
最高気温40度というあまりの高気温であったために、シニアたちに
とって劇場に来るプロセスそのものが危険と判断されたためだ。
そこで、スカイプによる電話ミーティングが繰り広げられた。
要するに、ビジュアル無しでグループ通話をしたのだ。
Zoomやモニター付きの会議でないのは、
シニアたちのメディア環境に配慮してのことだ。
みんな、電話には慣れている。
結果的には1時間以上も話していたために、
皆さんの腕や耳が疲れないか心配したが、それは大丈夫だそうだ。
このあたり、パンデミックのロックアウトの経験が生きている。
話題として、来年の"Meet Me"10周年をどう祝うかが
話し合われた。そう。この企画が誕生してから、間も無く
10年が経つのだ。参加者たちから次々にアイディアが出て面白かった。
・それぞれの家族を巻き込みたい
・それぞれの出身地・出身国の特色を出したい
・お世話になってきたボランティア・スタッフにお礼がしたい
・これまでを振り返るレトロスペクティブがやりたい など。
初めてこの企画に誘われて参加した時のエピソードを
話し始めるシニアもいて、感慨深い話し合いだった。
10人強のメンバーずつ、2グループに分かれて、
約1時間ずつ行われた。
その間、私はずっと家の、自分の部屋から会議に参加していたが、
今日はダイアンの友人一家が泊まりがけで遊びに来る日で、
隣の部屋でパーティーめいたランチが繰り広げられた。
休憩時間にあいさつした。
会議を終えて近所に買い物に出た。日用品を買う。
あまりの直射日光と気温だから、日本から持ってきた
善光寺の笠を付けた。
買い物をするたびに店員に話しかけられるので、
これは日本の風習であると伝えた。我が国ではみんな被っている。
夏の常識である。特にこのモデルは最近の流行りである。
という具合だ。
それから、ベトナム料理屋にも行った。
ベトナムには似たような笠「ノンラー」があるから
親近感があるらしかった。米食民族同士、親しみが湧くのだ。
そして、このままBBCプロムス行く。
ハーフパンツに善光寺笠だが、やむを得ない。
昨日、ロイヤル・オペラ・ハウスでハーパン・Tシャツを
何人も見かけたので、強気である。
カジュアルにクラシックを愉しむ。それがBBCプロムスなのだ。
郊外に住むミミの家の近所では、山火事が自然発生しているらしい。
7/19(火)ロンドン沸騰中
↑暑さがもっとも伝わりやすいからこれを選んだ。撮影は先日の土曜
日本の終戦記念日を思わせる暑さである。
快晴。真上から直射日光が照りつき、影が短く、濃い。
40度近くまでいっているらしい。おかげで街から人がいなくなった。
ロンドンは涼しいと思い続けてきたが、今週は暑さのケタが違う。
当地に住む人たちにとってみれば、これは異常事態のようである。
この気温は、仕事を休むに足る立派な理由だそうだ。
そのようなわけで、今日はWSも打ち合わせもキャンセルされ、
午後はフリーになってしまった。
お金持ちは都会を離れ、所有するカントリーハウスに行ったという。
9月を以って任期を終えるボリス・ジョンソン首相も例外ではなく、
自身の別荘で、お得意のパーティーをまた開いたらしい。
コロナ禍の度重なるパーティー開催により国民感情を逆撫でした彼は、
すこしも臆することなく昨日もこれを続けている。筋金入りのパリピ。
本気になって怒っているイギリス人には言えないが、
私はそんな彼が嫌いではない。
皆の家は暑くて仕方ないという。
学校も、劇場も、両方の友人たちが口々にそう言う。
暑くて寝られない、昼間は家にいられない、そういう状態らしい。
ところがダイアンの家は、冷房もないのに何故か涼しい。
分厚いレンガの壁と、二重サッシのおかげだと思う。
ここにきて、都心の居心地が良い。
普段は人で溢れかえっているのに、何しろ人がいない。
閑散としていて気持ちが良い。暑いことに違いはないが、
自分の地元、あの蒸し蒸しする名古屋と同じくらいだと思う。
Albany近くのカフェでミネストローネを食べ(夏野菜!)、
馴染みのパイ&マッシュの店でサイドメニューである
ジェリード・イール(うなぎ!)のみをオヤツに頂く。
そういう充実の食事を摂って、今日もロイヤル・オペラ・ハウスへ。
演目は『オテロ』。
私が買ったのは2,000円程度の立ち見席だが、
お金持ちたちは15,000〜30,000円くらいの席を軽々と放棄する。
必然、私の目の前には幾つも空席が現れ、開演と当時に、
これにサッと座るのがロンドン流。
日本では考えられないが、より良い席が空いていた場合、
こちらの愛好家たちは躊躇なく席を移り、
よほどマナーが悪くなければスタッフがこれを見咎めることもない。
むしろ、幾つかの劇場では、最安席に座っている人を、
案内係が率先して前に移るよう促してくることすらある。
ルーズというか、余裕というか、ロンドンはゆるい。
とここまでが昨日のこと。
今日の気温は41度まで上がると言っている。観測史上、最高だそうだ。
7/15(金)夏の雑感
シェイクスピアの故郷を旅行して気づいたのだが、
Tシャツの数が足りない。私は毎週土曜日に洗濯することにしている。
が、手持ちの半袖が6枚しかない。
これまでは必ずに肌寒い日があったのだが、
遠出の時には洗濯日もズレ込むだろうし、余分も持って
おいた方が良い。というわけで、Tシャツを買い足した。
場所は気に入りのルイシャム・ショッピングセンター。
カフェやレストランが高いイギリスだが、服は高くない。
増して貧しき者の味方のルイシャム地区なので、
良いものが買えた。
しかし、英国ではほとんどのTシャツが柄モノかロゴ入りだ。
私には、どこのブランドやメーカーか分かるものを着るのが恥ずかしい。
やっと無地を見つけたと思っても、胸にポケットがついている。
Tシャツの左胸のポケットに何か入れている人を
私は見たことがない。あれは、なんのためについているのか。
さすがのロンドンも暑くなり、30度を超える日が頻発するように
なった。それに伴い、ダイアンが庭の植物を心配している。
最近の私は、通学前にアジサイに水をやるようになった。
根っこの部分だけでなく、葉っぱや花びらの部分に上から水をかける。
日本ならば根腐れするほどの量を容赦なくかける。
それでも、あっという間に乾燥する。これが英国の気候だ。
語学学校では、トルコ人の女子がやたらと話しかけてくるようになった。
彼女の上半身は常に水着のような格好だが、手にはいつも毛皮の
カーディガンを持っている。暑さ寒さに極端で、中間部が全くないのが
面白い。露出度の高いロンドンの人々の中でも、彼女の極端さは
際立っている。
辛いものが食べたくなってインド料理屋に行くと、
今日は店員だけでなく、オーナーもいるのを発見する。
彼は面白い人で、店に入る時、食べ終わって出る時、握手を求めてくる。
今日はアレが美味かったと伝える。インドの梅干みたいなやつを
付けてくれるようになった。暑さの分だけ、美味く感じる。
バケーションを重視するヨーロッパ人にあって、
今年のAlbanyは特殊だ。一年間のフェスティバル期間中、
夏が最盛期なので、フル稼働する予定なのだ。
今日も目前のイベントへの準備が優先されて、定例会議が中止になった。
皆、顔を真っ赤にして働き続けているが、土台、働き方に対する
意識が進んでいる分、この先、誰かが音を上げるのではないか。
野外イベントが増えるに伴い、
私が渡英時に持ち込んだ善光寺笠の出番が迫っているのを感じる。
あれを日本で付けているとたいそう目立ったものだが、
こちらでは大したことがないように思う。
人種だけでなく、人々の格好も、こちらはバリエーション豊かだ。
7/14(木)修学旅行の思い出
奥さん、アン・ハサウェイの実家。目下読んでいるジョイスの
『ユリシーズ』では、彼女は徹底してエロ女扱いを受けている
いま思い返してみると、
ストラトフォード・アポン・エイボン行きは完全に修学旅行だった。
だいたい、修学旅行生が多い。あの様子はおそらく中学生だろう。
街に溢れかえっていると言って良いレベルだった。
私もベタなコースを回った。
シェイクスピアの生家、彼が成功者として買った屋敷跡。
勉強し、初めて旅回りの劇団の芝居を見たという学校。
友人たちの家の跡、埋葬された教会、奥さんの実家。
こんなところだ。そしてエイボン川に浮かぶ白鳥を眺め、
川沿いを歩く。
必然的に、どこもかしこも修学旅行の群れ。
彼らのほとんどはシェイクスピアに興味無いだろうが、
イギリス人はこうして国民作家に通じる教養をインプット
されるのだ。私たち日本人が誰でも奈良の大仏を知っているように、
彼らはいくつかの劇のタイトルを言えるくらいに仕込まれるのだ。
ケータイでシェイクスピアが育った家を撮影していたら、
「私たちのことを撮っているでしょ!」と女子中学生に
怒られたのも面白かった。イエゼンタイヲトリタイ、と
訴えてどいてもらった。
あと、学校の案内をしてくれたおじいさんが熱心すぎて
大幅に時間を取られてしまったこと、それと、
昨日、水曜日は特別に教会の営業時間が短く、
結果的にシェイクスピアのお墓参りができなかったのは残念だった。
ウィリアムと妻アン、二人の実家の距離感や、
ともにお金持ちの出であったことを実地に確認できたのも良かった。
そういうことは、彼の描く恋愛に、必ず反映されてしまうものだと思う。
予約した安めのホテルは居酒屋の2階で、
それだって物価の高いイギリス、観光のメッカたる当地では
1万円くらいかかったけれど、これも趣きがあって良かった。
観劇を終えて帰ったところ、開け放しにした窓から大量の虫が
入ってきていたが、部屋を暗くしてあっという間に追い出せた。
何か、旅籠屋という言葉を思い出させる宿泊だった。
名古屋の小学生として、京都・奈良県物をしたことを思い出した。
とてもおもしろかったです。
7/13(水)RSCとグローブ座
RSCとはロイヤル・シェイクスピア・カンパニーのこと
昨晩、この劇団の本拠地ストラトフォード・アポン・エイボンで
『リチャード3世』を観た。結果、期待したほどではなかった。
この劇の魅力はタイトル・ロールを演じる俳優に依存するところが
大きいと思うけれど、さほど惹かれなかった。
何より、この劇場の構造が良くないと思った。
どう良くないかと言うと、同じシェイクスピアを専門にする
グローブ座と比べると判りやすいと思う。
自分はグローブ座が好きだ。
先日に書いた通り、特に『ヘンリー8世』は最高だった。
けれど、グローブ座が好きだとロンドンで劇場関係者に言うと、
意外に思われる。「あそこは観光施設だからね」という
コメントも即座に寄せられる。
だから、私は好きなのだ。
あの劇場の役者たちは、観光客を相手に闘っている。
正確に言うと、闘わなかったりもする。
まるでうらぶれた芸人のようにやる気がないかと思えば、
急に大熱演して場内を盛り上げ、また急速に意気をしぼませたりする。
要するに、緩急を心得ているのだ。
それに、人間としての自然の姿があって、好感が持てる。
要するに芸能、大衆演芸的なのだ。
そこへいくと、RSCも街ぐるみで観光客を相手にしているが、
彼らは芸術家っぽい感じで、どこかお高い。
劇場は近現代風で、中身もそうかと言えば、ステージ様式は
グローブ座と同じ張り出しを採用しており、演出家の美学が
あらわれにくい。この辺が中途半端なのだ。
何より重要なのは、シェイクスピアは明らかに大衆演芸路線の
作家だということだ。私はグローブ座で、なぜこの作家が書く
台本にラブシーン、下ネタ、残酷シーン、決闘が多いのかを知った。
あれは明らかに、野外上演で途切れがちな集中をつなぎ止め、
庶民で構成される客席のウケを狙ったものなのだ。
チケット料金の取り方や客席の様子も違う。
グローブ座は、舞台近くの立ち見はすべて5ポンド、
椅子席には25〜75ポンドをとる。そして観劇中も飲み食いできる。
野外なので、完全暗転はないし、昼の上演は明るい。
RSCは全て椅子席で、ステージ近くが高くて最高値が65ポンド。
安い席でも40ポンドする。中には10ポンドの席もあるが、
これは柱で視界がさえぎられる席だ。客席は暗く、
周囲に迷惑をかけないように飲み物を口にすることはできる。
ちなみに、双方ともにせりふが徹底的に上手い。
このあたりはさすが専門家だ。
世間の評価は逆だろうけれど、私にはグローブ座の圧勝に思える。
この後は『テンペスト』『ジョン王』『ヘンリー5世』
『タイタス・アンドロニカス』が控えている。
『タイタス〜』では、我が子の死体でつくったミート・パイを母親が
食べてしまうシーンを、観客を大爆笑しながら観るのではないか。
残虐極まりないがゆえに、突き抜けすぎてギャグになってしまう。
芝居とシェイクスピアの不思議な魅力、その真骨頂だと思う。
7/12(火)辣腕の政治家
↑車窓からは山羊が見えた。シェイクスピアは田舎の小さな村から
世界に挑んだのだ
リチャード3世のことである。
今、ストラトフォード・アポン・エイボンに向かいながら
これを書いている。午前中にAlbanyのシニア向けWSを終えて、
ロンドンを飛び出した。シェイクスピアの故郷で、
これからロイヤル・シェイクスピア・カンパニーによる
『リチャード3世』を観る。
現地に到着してから開演までさほど時間は無いだろうから、
各所を見て回るのは明日だ。
そういうわけで、先週末は読み進めていた『ユリシーズ』を一時中断、
シェイクスピアの伝記と『リチャード3世』の台本をおさらいした。
思えば、高校2年の時に初めて読んだシェイクスピアがこの本だった。
以前より格段に面白く読めた。
ロンドンに暮らすことになって5ヶ月半。
台本を読みながら、彼が王位を手に入れるため、あるいは、
望みを叶えてからは逆賊を退けるために、いかに素早く立ち回ったか、
実地に想像できるようになっていることに気づいた。
何にもの邪魔者に矢継ぎ早に死を与え、
同時に、必要な人間は最短距離で口説き落としている。迅速だ。
史実としては、リチャードはもっと時間をかけて
一手一手、策を実行に移していったのかもしれないけれど、
シェイクスピアのスピード感は5日間くらいの出来事のように感じさせる。
ロンドン塔、聖ポール寺院、ホルボーン、
ベイナード城があったブラックフライアーズ、
戴冠をしただろうウエストミンスター・・・・など、
新宿区の端から端までの広さをひたすらかけずり回っている。
「ロンドン、街路」とあるだけのト書き、今まで無味乾燥だった
このト書きが色彩を帯びて、豊かに想像できる。
そこここに、忙しなく行き交っては足を止め、持ち前の饒舌を尽くす。
そんなに広くないセントラル・ロンドンをコマネズミのように立ち回り、
口八丁と切った張ったで人生を切り抜けていったことがわかる。
後半の敵軍との闘いのために進軍した場所も想像できる。
最近は英国地図と首っ引きで旅行計画を練っているためだ。
それぞれの都市の位置と距離感がだんだん身体に入ってきた。
そういえば、前にYouTubeの動画で銀座のママさんが語っていた。
デキる男は皆、素早くて可愛げがあるのだそうだ。
グロスター公リチャードは素早くて、可愛げがある。
主人公のキャラ立ちは良くても、若書きだから緊密さに欠けると思っていた。
けれど、辣腕政治家の一代記として、この台本は面白い。
面白いように出世して、政務を取る間も無く殺される。
作者のタイムコントロールに喝采してしまう。
もうすぐ目的地だ。
7/8(木)オペラ5連投
7/7(木)その名もビスマルク
書類を作り、他にもいくつもの文章を書いている。
外国にいてもけっこう日本の案件があるし、それができるのが現代だ。
パンデミックを経験した今、オンライン会議も常識だ。
書き物をするときは、各地を転々とする。
授業後の語学学校の教室、Albanyのデスク、観劇前のロビーを渡り歩く。
行き詰まると場所を変える。すると、歩きながら頭の中が整理され、
また書き進められるようになる。
昨日はカフェにも寄った。Albanyの近所にあるDeli-Xだ。
ピーター・フィッシャーに紹介されたここは居心地が良く、値段も安い。
コンセントも使えるから、たくさんの人たちがパソコンをつなげて
仕事している。よし、原稿の最終直しをするぞ!
そう意気込んでコーヒーを注文し、奥のソファを見ると
ピーターが座っていた。
即座に、仕事を放り出した。ちょうど、彼を必要としていたのだ。
二日前、私はスリー・コーラス・フェスティバルという音楽祭を発見した。
期間は今月末。場所はイングランドとウェールズの境目にある
ヘリフォード(Hereford)という小都市を中心に、
周囲の街を巻き込んで行われるらしい。
これは面白そうだ。
田舎町に点在する教会を総動員して、各地でプログラムが組まれている。
小規模な城砦めぐりもできそうだ。
さらに調べてみると、フィルハーモニア管弦楽団がやたら出演している。
ピーターはこのオケによく参加しているから、話を聞きたかったのだ。
果たして、彼も出演し、オケと一緒にずっとヘリフォードに滞在することが
わかった。どこに宿をとったら良いかも訊くことができた。
そんな話をしていると、ネコが割り込んでくる。
Deli-Xには一匹の飼いネコがいて、彼の名前はビスマルクというそうだ。
店主のダニエルによれば、ビスマルクこそこの店のCEOらしい。
こういう冗談の感覚は、日本も英国も変わらない。
7/6(水)ロミカの卒業
7/5(火)ダイアンの誕生日
7/1(金)おそるべき義手の女
6/30(木)パレストリーナを聴く
6/29(水)コロンビアからやって来た
6/28(火)私は悪魔ではない
↑これがウィリアム・ブレイクのステンドグラス
先週末は久々に現場仕事をした。
都心にあるキングス・プレイスという会場で「能」のイベントを手伝った。
早朝に家を出、帰りは24時を過ぎた。鉄道ストライキも気苦労の理由だった。
面白い人たちの現場にいさせてもらったけれど、疲れた。
翌日曜日はワークショップや劇団本読みをして、そのあと遊びに出かけた。
2週間前に訪ね、閉まっていたバタシーの教会でセレモニーがあったのだ。
あの教会は基本的に午前中しか開いていない。
この機会でなければ、午前中は学校かAlbanyにいる私が訪ねるのは難しい。
バスを乗り継ぎ、片道1時間半。今度こそ扉は開いていた。
私が興味を持ったのは、詩人ウィリアム・ブレイクが婚式を行ったからだ。
教会内には彼を表すステンドグラスもある。
儀式に参加するわけだから、入り口で聖書を受け取った。
聴衆は20人。コーラスが15人。オルガンの伴奏でアンセムが歌われ、
説教師のお話が繰り返された。そこで事件が起きた。
1時間が過ぎたところで、説教師の話が途切れ、
突然、奇声とともに倒れたのだ。明らかに癲癇の発作だった。
もちろん、人がこんなことになるのを初めて見た。
皆が慄き、合唱隊の一人が救急車を呼んだ。
ピアノをどかしてマットを敷き、彼を寝かせる。
聴衆はそれぞれの判断で、五月雨にその場を去った。
悪いことに、私は最前列の一番端に座っていたから、
立ち去りずらくなってしまった。ここに座ったのは、
すぐ横にブレイクのステンドグラスがあったからだ。
通路をバタバタと人が行き交う間、
私はじっと祭壇を見て、周りの状況が落ち着いたところで
そっとその場を後にした。そして水を飲みながらすぐそばのテムズ川を眺めた。
それから気付いたのだ。自分の怪しさに。
考えてみれば、ここはローカルな教会だ。
あの場にいたのは誰も彼もが知り合いに決まっている。
しかも、外に置いてあった看板を読んだところ、
この日は、永年ここに勤めてきたあの説教師の、
引退前、最後のセレモニーだったらしいのだ。
思い返せば、合唱隊の若者の何人かは騒然とする教会の中で
私の方を見ていた。200人以上入る席の中で私だけが変な位置に
座っていたし、見知らぬ顔だし、無表情だし、一言も喋らず、
なかなか動かなかった。あの視線には明らかに、
何か不気味なものを見る感じがあった。
確かに、ドストエフスキーやブルガーコフの小説に出てくる悪魔は、
さっきまでの自分みたいな物腰なのだ。
このままではいけないと思った。
しばらく待ち、戸口で救急車を見送った若者に挨拶することにした。
自分の身分やここに来た訳を話し、また来ますと伝えた
彼は初めは訝るような感じだったが、少しフレンドリーになった。
救急車に乗せられていく説教師を見る限り、命に別状は無さそうだった。
6/24(金)タッチか、挿入か
6/23(木)永い出稼ぎ
6/22(水)ストのはじまり
6/21(火)オールドバラ音楽祭に行ってきた
6/17(金)それは彼の王国だった
↑わざわざスコアを持たされて撮影したのだろう。
後ろに見えるホールに行く予定。
今週末、再び遠出するつもりだ。
前回に行ったブライトンとグラインドボーン音楽祭から3週間。
次なる目的地はオールドバラ音楽祭である。
これは『戦争レクイエム』で有名なベンジャミン・ブリテンが
1948年に創立した音楽祭だ。彼は20世紀イギリスが生んだ最大の
作曲家だが、その最晩年期に自分の故郷オールドバラでの音楽祭を
立ち上げるに至った。ロンドンから電車で2時間半の土地。
その後、彼自身は1976年に亡くなってしまったが、
半世紀を越えた今も、音楽祭は健在、今年も6月に行われている。
音楽もさることながら、ホール自体も愉しみだ。
もともとウィスキー工場だったところを改装してできたというのだ。
音楽祭が開始されて程なく火事になったが、また復元されたらしい。
趣きもあって音響も良いと聞くから、期待が高まる。
ところで、先日、いつも都心に出た時に立ち寄る大型書店で、
この音楽祭に関するDVDを発見した。これは行く前に見ておきたい。
けれど15ポンド=2,500円する。一回見てしまえばおしまいなのに
高いと思い、Amazon UKを調べたら2ポンド送料無しの出物を発見、
注文した。
たった三日で届き、蓋を開けると監督のサインまで付いていた。
サインしてもらったのにとも思うが、ふとどき者のせいで恩恵に
あずかることができた。早速に本編を見たら、創立時の様子、
ブリテンの奮闘、若かりし日のエリザベス女王が祝辞を述べるところまで、
経緯が良くまとめられていた。
ホールの様子も 予習することができたが、
そのうち、気になることが出てきた。妙に少年たちがものを
食べるカットのインサートが多いのだ。
それに、ボーイソプラノのコーラスの稽古を熱心にやるブリテンにも
しつこいくらいにフォーカスしていた。
・・・要するに、そういうことなのだ。
ブリテンの盟友といえばピーター・ピアーズという男性歌手であり、
その関係が公私にわたるものであることは有名だ。
加えて、この監督は、ブリテンが音楽祭を立ち上げるに至った
モチベーションを潜ませたのではないかと思う。
少年たちを故郷の田舎に集め、熱心に指導をし鍛え上げる。
当然、都会からは遠いので合宿状態。
これは、ブリテンのモチベーションを大いに高めたに違いない。
私は、こういう仕事の仕方が心から好きだ。
個人的な動機があってこそ、仕事はただの仕事以上の迫力を帯びる。
そう考えてみると、『春の交響曲』『シンプル・シンフォニー』
『青少年のための管弦楽入門』など、ブリテンの仕事はまた違った
角度からも強く輝き始める。明日の昼過ぎ、オンラインの本読みを
終えたら出発だ。
6/16(木)神より仏
6/15(水)すべてティー・ダンスに通じる
6/14(火)苦みばしったフォー
↑単にタダ飯を食べたのではないが、それにしても美味かった。
ロンドンにもようやく夏の気配が感じられる。
日差しも強いし、昼間にひなたを歩いていると汗ばむ。
日本と違ってじめじめしていないので、夜になると冷え込む。
いつも朝8:30過ぎに家を出、方々巡り歩いて帰るのは23:00頃だから
どうしても寒い状態に衣類を合わせる。昼間は余計に暑い。
先週の土曜はかなりユニークなイベントに参加した。
Albanyの一角に事務所を構えるレジデントカンパニーのひとつ
New Earth Theatreによるイベント"Sonic Pho"だ。
Pho=フォーとは、あのベトナム料理屋で出てくる麺類のこと。
ルイシャム地区にはベトナム人コミュニティがあり、
食を絡めた面白い劇場プログラムをつくり、
同時に相互交流を図ろうという狙いだ。
受付を済ませると、スタジオに行き、
そこで、フォーづくり、主にスープづくりのデモンストレーションを見る。
ハーブや香味野菜について説明を受けながら匂いを嗅ぎ、
出汁の取り方も目の前で料理してもらいながら、見る。
普通はチキンだが、ベジタリアン用には昆布を使う。
昆布だしなんて、4ヶ月半ぶりだった。
試飲させてもらったが、さすがにしみる。
アジア人が大好きな、これがグルタミン酸ナトリウム。
昔、唐さんが飲み会で上等の生ハムを食べながら
「これはアジアじゃ無理だ!」と絶賛していたのを思い出した。
ああ、オレも慎ましきアジア人の一人。
同時に、ベトナム人女優さんが、簡単にベトナムの現代史、
特にベトナム戦争の影響で世界中にベトナム人コミュニティができた
エピソードを紹介してくれた。
そして、移動。
近所のベトナム料理に皆で移動して、席についた。
そこでは、配られたヘッドホンをして、供されるフォーに向かう。
メインの具は好みによって指定でき、私はビーフにした。
本格的なフォーだ。
別皿にミント、もやし、コリヤンダー、唐辛子の輪切りが大量に盛られ
レモンも付いている。明らかに移民の人による店。
英国人は麺をすする音を嫌うから気を付けて食べ始めると、
すぐにヘッドホンから音楽が、続いて、ベトナム戦争を含めた現代史を
誦じる詩。要するに『ミス・サイゴン』的に国を追われた人たちが
この本格的なフォーをロンドンに持ち込んだのだ。
私はヒヤリング能力の貧弱さゆえにけっこう美味しく一杯を食べたが、
周囲の参加者にとって、けっこう苦い味だったのではないかと思う。
戦争の話題とフォーの味・・・。
はっきり言って今はあまり上手くいっているとは言えない
実験段階の企画だったけれど、その心意気が素晴らしい。
味覚をきっかけに地域のコミュニティにアプローチしたいという
着想が面白い。こちらも一所懸命アンケートを書き、連絡先を交換した。
近く、事務所に行くつもりだ。
劇団スペヤタイヤ、エンテレキー・アーツに続いて、
知り合った三つ目の団体ニュー・アース・シアター。
今回行ったベトナム料理屋にも、
これからアジアの味を求めて通うことになるだろう。
6/10(金)久しぶりに学校で震撼
6/9(木)橋の上の天国と地獄
6/8(水)痛恨のスリースター
6/7(火)立体駐車場にて
↑向こうの方にグランドピアノが見える。天井が低い!
先日、ピーター・フィッシャーに誘われて面白い催しを見た。
会場はペッカム。なかなかガラの悪い場所で、語学学校の同級生は
この街でケータイを擦られた。駅前の歩道はゴミの散乱がすごい。
それで、迷いながらフラフラとナビを頼りに進んだら、
ゲームセンターみたいな建物の裏手にたどり着いた。
名門フィルハーモニア管がこんなところでやるか!
っていう場所で、立体駐車場の上の方でたった1時間の
コンサートをやるという。
どうせ客は少ないだろうと舐めきって受付に行ったら
完売だと言われて返り討ちに遭い。しょげていたところを
ピーターのショートメールが助けてくれた。
これを見せろ!と。
で、スマホのモニター見せたら、
仕方ないなあと正価で入れてくれた。ああ、友よ!
入っていってのけぞった。
こんなんで満席って頭おかしいんじゃないか、と。
どんどん入れりゃ、いくらでも入るような隙間がいっぱいあって
演奏が始まってからも壁が吹き抜けてるから、ノイズだらけ。
近所を通る国鉄の軋みはすごいし、周囲のゲームセンターの放送も
元気よくなだれ込んでくる。
一方、肝心のフィルハーモニア管は、
大男だったら頭擦っちゃうんじゃないかという低い天井の空間で
ノイジーなスクリャービンを2曲弾いた。
『法悦の詩』『プロメテウス』という、
どっちも官能性充分、ノイズも充分という曲なので、
周囲の雑音と妙にマッチしちゃって、後ろの方の聴衆はみんな
ケータイかざして聴いてるし。心から堪能した。
まざまざ思い出したのは、
自分の青テントの舞台を後ろの方から眺めているあの感覚。
同時に、オレたちはいつも周囲のノイズにハラハラしてたけど、
案外と観客は平気なもんだって気づいて、開き直りも含めた
無頼な気持ちになった。
こんな感じでここれまでやって来たし、
我ながらやっぱり好きだなあという確認。
他方、こういうのは忘れ難くて最高だけど、
一回性のイベントで処理されちゃうから、
本心からやりたいこっちと、作品を評価するラインに乗せた公演、
両方やらなきゃならんのだあということをこのオケから教わりました。
周囲のノイズに負けないために音圧を強くして、
反響しすぎる空間に対処するため、アーティキュレーションを
クッキリ。彼らの腕前もいつもより分かった公演だった。
音楽について、これは2度と無い経験だろうなと思う。
またテントを自分でやって味わおう。
6/3(金)今日はトリプル・ヘッダー
6/2(木)今日から連休
6/1(水)友人ピーター・フィッシャー
5/31(火)渡英からちょうど4ヶ月目
↑グラインドボーン音楽祭の庭
↑我がThe Albany Theatreの庭
『腰巻おぼろ 妖鯨篇』研究を終えてから1週間が経つ。
台本に取り組んでいないと予定に余裕が生まれる。心にも余裕がある。
先週末はブライトンのフリンジ・フェスティバルに行ってショーを見、
ケッチさんに会えた。ケッチさんの出番は短かったけれど、
そのかわりケッチさんの勧める若手女性クラウンの素晴らしい出し物を
見ることができた。このショーの感想を間に置きながら、
私たちは来年2月に創る舞台について話し合った。
その後に泊まった海辺のドミトリーは8人相部屋で面白い経験だった。
帰るのは夜中だし、朝早く起きてエントランスの広々としたカフェで
仕事をした私は、むしろ彼らに迷惑をかけた側だったと思う。
朝になっていそいそとタキシードを取り出し、
四苦八苦しながら慣れない身支度をする私を笑いながら見守ってくれた。
案の定、芸人か、友人の結婚式に備えているだと誤解された。
ちなみに、ミス・ダイアンには帰ってからこの宿泊体験を報告した。
ブライトンはゲイの街だ。そう断言する彼女に事前に宿泊先を告げたら
猛反対されたに違いない。私としては、グラインドボーンという
貴族的な土地へ赴くことへの禊としてここに泊まったのだ。
シャンパン片手にドレスアップしてピクニックを楽しむだなんて、
名古屋の地方公務員家庭に育ち、テント演劇に明け暮れてきた
自分には耐えられない。
そしてグラインドボーン音楽祭。
タキシードその他、ドレスコードを満たす準備や、
生き帰りの方法について調べるのは大変だったけれど行った甲斐があった。
この小旅行にはやたらと膨大な待ち時間がつきまとうから、
林あまりさんが教えてくれたチャペックの『園芸家12ヶ月』と、
ウィリアム・ブレイクの本を読んだ。数年ぶりにのんびりできた。
以前にのんびりしたのは、親知らずを抜くために入院した時だ。
グラインドボーンは想像していたよりもずっと人間味があって、
嫌な感じはせず居心地が良かった。演奏はいつも聴いている
ロンドン・フィルで、相変わらずわんぱくな弾き方だ。
何より、イギリスの女流作曲家エセル・スマイスの
『The Wreckers』という演目と、新たな演出が良かった。
レッカーズ、つまり"レッカー車"の"レッカー"には
"故意に物事をダメにする"という意味がある。
20世紀の貧しい漁村の共同体の中で、不倫関係を貫く男女が描かれる。
僧侶の言葉も村人の忠告も彼らは振り切り、やがて心中を選ぶ。
こんなオペラだから、衣装はジーンズやオーバーオールが目白押しで
ひどく簡素だけれど、これはブリテンの『ピーター・クライムズ』と
ワーグナー『トリスタンとイゾルデ』を掛け合わせた作品なのだ。
民主主義下の大衆の圧力にも、宗教的な抑圧にもヒロインは屈しない。
イギリス人にも関わらず、イギリスの地方都市を舞台にしたオペラを
フランス語の作品にしたスマイスの反骨心が溢れていた。
彼女はレズビアンだったらしい。女性の闘争心が全開のオペラ。
演出もそういう要素をさらに先鋭化させていて痛快だった。
休憩時間には、ウィンザーからきたという常連さんのおじさんに
話しかけられて、楽しく過ごすことができた。
ビルギット・ニルソンを生で聴き、マリア・カラスに会ったことが
あるという彼は、大の音楽ファンで、一年で何回か、ここに来るそうだ。
最近の歌手には不足を感じるとこぼしていた。
彼は手荷物を庭に置きっぱなしにして客席に戻る。
ロンドンの喫茶店では、トイレに立つ時には全ての荷物を
持っていかなければならない。それと、ここでの人々の振る舞いが
好対照を成していた。誰も盗みなんかしない。なんと贅沢な。
してみると日本は豊かだ。落とした財布が返ってくる世界。
私はと言えば、売店でこの音楽祭の過去公演CDが1枚5ポンドで
叩き打っているのを発見し(定価30ポンド)、狂喜して大量買いした。
まるでディスクユニオン。この買い物には本当に満足した。
無事に深夜に帰って翌日。朝の本読みWSを終えた後、
今度はオールバニーの庭でのアフリカ音楽フェスだ。
巨大スピーカーを持ち込み、街中に響き渡る音量でガンガンにレゲエを
かけていると、オシャレした若者たちが集まり、踊り始める。
参加無料のイベントだが、酒やスナックが飛ぶように売れる。
面白かったのは、トイレの数が全然足りず、若い女子たちが茂みに
飛び込み、ギャハハと笑い合いながら用を足していたことだ。
そしてまた踊りに戻る。若さと健康を撒き散らしていた。
グラインドボーンとオールバニー。
表面的にはぜんぜん違う両者は、しかし、
劇場、庭、オシャレ、飲み食い、音楽という衝動において
まったく同じ欲求に根ざしている。どちらかを侮るなかれ。
オールバニーを回りくどくするとグラインドボーンになる。
この回りくどさが文化だと、栗本慎一郎先生なら言うだろう。
日曜の夜は夜で、バービカンに行き、
ロンドン響とゴスペルのジョイントコンサートを聴いた。
いつもより格段に観客に黒人や子どもが多く、活き活きしたライブだった。
途中から立って踊り出す人さえいた。
昨日で、渡英してから鑑賞したものが100本に達した。
5/27(金)ドイツのタケシ・キャッスル
5/26(木)ロンドン、その園芸の世界
5/25(水)『腰巻おぼろ-妖鯨篇』ひと区切り
5/24(火)まずは週末に備えて
5/20(金)ヨルノハテより第二指令!〜帰国後の舞台
↑テツヤとの対話。ここで話しながら企画が生まれた。
劇団をやり、劇場で働く。
主宰と演出をし、コミュニティワークと劇場運営を身につける。
目下わたしが行っている取り組みだ。
今日は演出家としての話題。
コロナ以降、配信番組をつくってたびたび対話し、
去年のお盆には太田省吾さんの『棲家』リーディング公演を
一緒に行ったプロデューサー・テツヤから、
新たなお題が来た。キッズプログラムをつくろう!
今日が情報解禁日で、詳細はコチラ↓
オオカミだ!- 『3びきのこぶた』に出てくるオレの話 -
日にち:2023.2.18.sat,19.sun
会 場:本多劇場
「第33回下北沢演劇祭参加作品」
出演:ケッチ
演出:中野敦之
企画製作:ヨルノハテの劇場
主催:合同会社ヨルノハテ
原型は『3びきのこぶた』。
去年の終わり頃、テツヤはこの童話とロシア文学を並べて
「どっちがいい?」と訊いてきた。
ロシア文学は好きだけど『3びきのこぶた』と即答した。
ロシアの方だとつい難しぶったり、カッコつけそうで良くない。
『3びきのこぶた』の方が逃げも隠れもできない感じがしたのだ。
ひたすら子どもたちのための劇をつくる。
そう思ってより平明な方を選んだつもりだったが、
なかなかどうして、このイギリス産の童話には、英国の人たちの
生活に根ざしたメッセージがあることがロンドン暮らしの中で
わかってきた。
ただ一人の出演はケッチさん。
これはすごい。テツヤの剛腕だ。
すっかり張り切って、今から構成台本製作や演出プランを
つくっている。年末には、帰国後すぐに稼働できるよう体調を整える。
初めてキッズプログラムを演出する。
初演以降の展開もすでにテツヤは狙っている。すごいぞ、テツヤ!
5/19(木)ロンドン。パリに屈する。

5/18(水)同じくマージナルなもの
5/17(火)おそるべき伴奏
5/13(金)恐怖との遭遇
5/12(木)今日は雑感
5/11(水)研修らしくなってきた
5/10(火)実にハードルだらけ
↑人は優しい。先週末、前から気になっていたハンガリー料理を初めて
食べた。腕利きの店員さんに説明されながらオススメを頂いた。
英国での生活はドラブルに満ちている。
例えば、最近はワクチンパスを手に入れたいと思い、かなり苦労した。
ワクチンを打つにもかなり手間がかかったが、事後だけでもこんな具合。
まず、接種後2週間が経ったのを確認して、119に電話。
そうすると高速の英語と闘うことになる。当然、相手の顔は見えない。
外国人用の対応窓口につないでもらっているにも関わらず
「ゆっくり喋ってくれ」と何度言ってもスピードが落ちない。
ネイティブの人にとって、ゆっくり話すのは難しい。
自分も可哀想だが、相手も可哀想だ。こちらが電話を置くまで
相手をしてくれるものだから、最後は申し訳なさでいっぱいになる。
埒があかないので、今度は登録の病院に直接に行く。
ここ数週間、保険証登録などでもすっかりお世話になってきたので、
こちらのことを覚えてくれている。受付の人は優しい。
スマホにこのアプリをダウンロードしてみて、
というアドバイスをもらい、GoogleからのDLに挑戦する。
すると今度は、ダウンロードのためのパスワードを、
Gmailアドレスに紐づいた私の日本のケータイ番号に送るという。
当然それは凍結してあるわけだから、キャッチできない。
そこで、現在持っているイギリスのケータイ番号に紐づいた
アドレスを新たに作ることにした。これ、病院の受付の前の
イスで焦りながらやったものだから、自分の名前なのに
アカウントがAtusshi Nakanoで登録されてしまった。
「アトゥッシ ナカノ」。でも、まあいいやと気を取り直す。
名前がどうでも今回は関係ない。
今度こそDLを試みると「あなたのデバイスではキャッチできない」
という。日本で買ったスマホだからなのか。ここで、方針転換。
同じアプリをパソコンに落とそうとしたが、これもダメ。
さらに別の方法を入れ知恵してもらって、
健康保険のウェブサイトから取り寄せることにした。
ここにもハードルがあって、フォーマットに入力するうち、
自分の写真を添付で送ったまでは良かったが、
「Movieも送れ。その際にこの4ケタの数字を言え」と続く。
この時、なぜか自分のPCのカメラが作動してくれない。
いつもZoomもLINE電話もこのMACでしているのに、
どうやってもカメラが動かない。
仕方ないから、Albanyの金庫番であるセリに頼むことにする。
ミミやロミカは親しいが、リモートワークが基本だ。
チケット売り場のリヴやアレックスやイオシフィナも優しいが、
彼らのパソコンは共用のものだし、いつ掛かってくるかわからない
チケット予約に備えている彼らを巻き込むことはできない。
そこでセリだ。若手スタッフと会議をしていたセリに
「後で時間をください」とお願いし、わざわざ自分のデスクまで
来てくれたセリに「あなたの部屋で話したい」と切り出す。
何事かと、彼女は神妙に私を招いてくれたが、結果こんな要件である。
果たして、セリのデスクトップのカメラで映像を撮影するわけだが、
悪いことに、自分のパスポート写真はメガネを外しているから、
裸眼で挑まねばならない。
そこで、指定4ケタの数字を記憶して臨んだのだが、
初回はテンパって「よんなな・・」とやってしまいセリに爆笑された。
再トライして、ようやく24時間以内にメールを送るという通知を得た。
果たして、明日にこれは届くのか。
最後まで気が抜けないのが外国での生活だ。
5/6(金)
学校→VACCURSE会議→買い物→Albany→ナンヘッド霊園
→『腰巻おぼろー妖鯨篇』打ち終わり→BBC交響楽団
5/7(土)
Zoom会議→洗濯→『鐡假面』本読み→ハンガリー料理
→チャールズ・ヘイワードLive
5/8(日)
掃除→本読みWS→買い物→ロンドン響
5/9(月)
学校でテスト→ワクチンパス取得のため病院→Albany
→ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団
5/6(金)その② ついに事件に遭遇
5/6(金)死闘『腰巻おぼろ 妖鯨篇』
5/5(木)グローブ座へ
5/4(水)アヴェ・マリア大集結
5/3(火)先週末から週明けのロンドン
↑終了後の稽古場。チェンバロが見える。
これをロンドンの都心で書いている。
飲食店はどこも高いこの街では、屋内にフリーで座れる場所は貴重だ。
ナショナルギャラリーの横にある教会セント・マーティン・イン・ザ・
フィールズの地下は落ち着いてデスクワークができる場所だ。
それにこの教会はイベントに大変熱心で、
3月にはここでBBCシンガーズの『ディドーとエネアス』を聴いた。
今日は地下1階のテーブルに陣取ったところ、地下2階に稽古場が
あるのを発見した。このゼミログを書いているすぐ横では、
ガラス1枚を隔てて木曜に上演予定のヘンデルのオペラ
『セルセ』の稽古が行われている。
主役級の歌手が、出番の合間にコーヒー片手に目の前のテーブルで
休憩し、電話をし、くつろいだ後、また稽古に戻っていく。
稽古場の中はは紀元前5世紀頃のペルシャ。
さすがヘンデルの地元。これがロンドンだ。
4/29(金)夜は内田光子さんのリサイタルに行ったが、苦しかった。
弱音と不協和音が連続する現代作曲家の曲に対し、周囲に沢山いた
中国人旅行者たちが騒々し過ぎたのだ。
まず、私の席に言ったところ、先に座っている人がいて閉口。
チケットを示してどいてもらった。
隣の中年夫婦はひっきりなしにお互いの体をまさぐり合うか、
姿勢悪く寝ているかだった。一方、当日パンフがオンライン配布なので、
ケータイの明るさを最弱にして読みながら聴いていたら、
二席隣のおじさんが「目に入るから電話を閉じろ」という・・・
苦いコンサートだった。
4/30(土)はサウジアラビア人の友人アジードと最後の晩餐。
その前にロンドン・セントラル・モスクに一緒に行こうと約束したが、
こちらが着いたところで電話があり「間に合わない!」と。
後でレストランに着いて分ったが、この日、彼は半年間お世話になった
ホストマザーを連れてハロッズに行き、お礼に高級なアラビアの香水を
買っていたのだ。彼が案内してくれた店でした三人での食事は面白かった。
予定の組み方も、案内の仕方も、メニューの頼み方も、
18歳の彼のアテンドはものすごく未熟だ。
でも懸命で、こちらに自国の食べ物や感謝を伝えたい気持ちが伝わってきた。
同じアラビア圏のトルコ人留学生たちと、友達になってはケンカ別れを
繰り返していた彼。彼の目標である良い医者になって欲しいし、
彼とは再会の可能性があると思う。何年後かに日本を案内できたら嬉しい。
一人で満喫したモスクでは、イスラム教の合理性がよくわかって
楽しかったし、食事も美味しかった。久々に沢山お米を食べた。
アジードに幸多からんことを!
5/1(日)は唐ゼミ☆本読みWSをしてキングスプレイスに出かけた。
ピーター・フィッシャー率いるチェンバー・アンサンブル・オブ・
ロンドンを聴くためだが、キングス・クロス周辺の文化施設は
綺麗すぎて自分はどうも馴染めない。演奏会は会心の面白さだった。
ピーターはフィルハーモニア管のツアーに同行するため、
夜中にヘルシンキに向かった。激務だ。
5/2(月)。銀行が閉まるバンクホリデー。メーデーだ。
朝から『腰巻おぼろ 妖鯨篇』と格闘して、へばり気味だが、
昼過ぎにはウィグモアでガーシュインを特集するコンサートを聴いた。
その後、今後の遠出に備えて電車に切符を買いに行った。
オンラインでの申し込みが基本だが、なぜかクレジットカードが
はじかれる。そこで現地購入。
時間の無駄とも思うが自分はこういうのが好きだ。
劇や音楽の公演も、できればボックスオフィスで買って
紙チケットが欲しい。スタッフに質問したりすることも含めて、
時間に余裕があるからできる贅沢だと思う。
そして都心を歩き回り、今、冒頭の教会にいる。
今日、ダイアンは大金持ちの友人に誘われて、
ロイヤル・オペラ・ハウスでディナー付きボックスシートだそうだ。
出がけにストールの色やバッグの色について意見を求められたが
明らかに派手な方を選んで欲しそうだったので、そちらを指さしたら
喜んでいた。
他方、土曜未明にグリニッジ駅前のバーで殺人があったそうだ。
酔っ払った30歳前後の友人二人がケンカをして、一人が刺されて
亡くなり、一人は警察に捕まった。あまりにあっけない。
これがロンドンだ。
4/29(金)必ずしも英国が良いわけではない
猫の捜索願いを目にするのは二度目。が、これはインパクトある。
片目の黒猫を捜している!
Albanyにいて感じるのは、ここで行われる劇場運営が
日本のそれよりはるかに多く地域の人たちに関わっていることだ。
もともとそう思ってこの劇場を研修先に選んだわけだが、
実際に一緒に過ごしてみて、強く実感する。
そのため、この劇場が行う催しは圧倒的に音楽イベントが多い。
子ども向けのプログラムを除けば、これまでにストレートプレイは
3つしか観なかった。つまり、それだけせりふ劇の間口が狭い
ということなのだ。
また、辣腕のソフィーが仕切るシニア向けの定例WSに立ち会った。
皆で染め物によるバナーづくりをしたり、サイモン&ガーファンクルの
曲を合唱するのに参加した。作業や練習そのものは90分程度の
長さだが、皆さん早めに集まってくるし、休憩時間もたっぷりとる。
劇場から供されたお茶とお菓子で団欒して過ごし、
終わった後もみんなで残って茶話会のような感じになる。
とてもステキな光景で、それら一連が終わると、
ある人は自身で帰途につき、別の人は家族が迎えにきた車に乗って
帰って行く。ソフィーはそのひとりひとりと話をしながら見送っていた。
ソフィーはオーガナイザーであり、参加者の娘や看護師のような
存在でもある。「ソフィーはどこ?」と誰もがすぐ彼女に助けを求める。
その度にソフィーは二つの会場を駈けまわっていた。
まるでデイケアサービスのようだと思った。
内容的にもアートの度合いは薄めにしてあり、そのかわり間口が広い。
そして、Albanyがこうなったのには明確な理由がある。
地域経済が逼迫したからだ。
21世紀に入った頃、この地域は困窮した。
Lewishamはシニアにかかる医療費を支えきれなくなり、
Albanyは文化予算の削減に喘いだ。そこで両者は手を取り合ったのだ。
追い詰められたもの同士が結びついて、劇場の新たな事業展開に活路を
見出した。言わば、窮余の一策ともいえる。
必ずしも英国が良いわけではないと書いたのはそういうわけだ。
医療と文化、その両方がいまだ一定水準の予算規模を保っている日本は
幸せである。しかし、若者が減り、高齢者が増える国家経済の行き先を
誰しも明るいとは思わない。だから、来るべき時のためにと思って来た、
ともいえる。
いずれにせよ、そういう苦さも含めて自分は学びの日々を送っている。
音楽イベントに集まる若者たちにとって、Albanyは劇場でなく、
DJのいるクラブとしか記憶されていなのかも知れない。
そういうことも思う。
それが良い。それで良い。やっぱり劇場だと思われたい。
こんな風に3段階の感情が湧き、正解は見えない。
やはり、劇場は最高水準の芸術性を追究するべきでしょう。
という思いもある。最高水準の芸術性・・・。
しかし、しかしである。
これらは、やりようによって共存するのではないか。
それどころか、人々の事情や暮らし向きに接していることは、
むしろ劇をつくる作業にとって必須なのではないか。
実は、そういう思いもあってここにいる。
人間を描く、人間の営みだから、と言える。
そういったことを唐さんは『下谷万年町物語』でこう書いている。
これから劇作家になろうとする少年・文ちゃんに、
ヒロイン・お瓢が覚悟を問いかける場面だ。
お瓢 転がってくるもの。
文ちゃん え?
お瓢 果てしなく、いつも、こうして、転がってくる......。
文ちゃん はい。
お瓢 なりゆきとか、ゆきずりとか、手垢にまみれた、下々の、
様々なこれらを、おまえは、これからもずっとつかんで行けんのか?
自分のいる地区には、ものづくりにとって一番大切な魂がある。
そう信じている。
他方、作品をつくるということは当然ながら技術であり、
技術は都心で学ぼうと夜はセントラルに通う。
そんなイメージで過ごしている。
技術や形式だけの学んで帰りたくないと思って行動している。
けれど、もちろん、帰国後の仕事によってのみ正解・不正解は証明される。
だから必死だ。
4/28(木)夫婦の仕事
4/27(水)3回目のワクチンを打つ
4/26(火)ロンドンに潜む危険の数々
4/23(土)わが友・ヤジード
4/22(金)悪魔の棲み家
4/21(木)靴を買い替える
4/20(水)ローエングリンとロシア人の友だち
4/19(火)『腰巻おぼろ-妖鯨篇』〜超大作に挑む
4/15(金)ミミのちから
4/14(木)戦争の影響と買い物について
4/13(水)死から復活までのあいだ
4/12(火)最後の砦
/8(金)
学校→Kings Crossで打合せ
→South Bank CenterでCarmina Burana
4/9(土)
Zoom打ち→洗濯→『鐡假面』本読み→馬券を購入
→Lewishamで服を買う→Albanyでライブ
4/10(日)
ジャムの交換→掃除→唐ゼミ☆WS
→Murcellaで食事→→Lewishamで服のタグを外す
→近所の教会のイベントに参加
4/11(月)
学校でテスト→病院の登録→Eustonで情報交換
4/8(金)マルクスの墓参り
4/7(木)YAHOO JAPAN! ニュース停止の衝撃!
4/6(水)I am a black woman.
4/5(火)友のラマダン
4/1(金)チョコレートこわい
今日も方々に出かけた。
学校が終わってケータイショップに行き、これをひと月更新。
それから一度帰宅してZoom会議に臨んだが30分足らずで終わる。
拍子抜けしたところに机を見ると、ミス・ダイアンが残していった
フランシス・ベーコン展のパンフレットがある。
そこで突撃することにした。
とにかく5:00pmまでに入れば良いのだ。もちろん学生料金で。
このあたりの反射的移動が速やかになってきた。
頭の中に地図と路線図を思い描いて、最短距離を出す。
交通費が安くなることも考える。2ヶ月の成果だ。
まじまじ観たが、犬の絵がもっとも気に入った。
フランシスは、欲動が強くて、神経剥き出しで、
自分に振り回されっぱなしで生きづらい人生だったと思った。
が、ミス・ダイアンに言わせると、それ以上に周りを不幸にしたそうだ。
なんとも返答に困るやりとりを帰宅してから受けた。
『ベルセルク』『鋼の錬金術師』『ハンター×ハンター』など
多くのマンガがインスパイアされているのも感じた。
今日はもう一つ。
Sadler's Wells Theatreに行き
William Forsythe振付のEnglish National Balletを観た。
実に1990年年代的なトレンディなノリで、
まるでティーンたちの文化祭かダンスパーティのようだった。
もちろん、惜しげもなく披露されるテクニックの数々。
ガチガチの古典をやっているダンサーがたまにこういうのを
やると嬉しい、そういう喜びが溢れて、客席を巻き込んでいた。
大変な盛り上がりで幕を閉じた。
ところで、帰宅するとダイアンは盛んにチョコレートを勧めてくる。
ロンドンではキットカットなど安く大量に買えるので、
自分はつい手が伸びて、ズブズブになることを恐れている。
アイスクリームとチョコレートは大敵なのです。
と言い続けているのに、母の日のプレゼントにと息子が贈ってきたから
と勧めてくる。こう言われては断れない。
彼女は私が食べるのを見ながら嬉しそうだ。
こちらはフリで言っているのではない。
歯止めが効かなくなることを心の底から恐れているのだ。
人は、人が怖がることを仕向けてみたくたる。
そういう落語=古いコメディのお話が日本にあることを彼女に伝えたら、
笑っていた。
3/31(木)Lewishamを歩く④ Deptford〜Brockley〜Forest Hill〜Honor Oak
3/30(水)ウナギがなんとかしてくれる
3/29(火)タルコフスキーが教えてくれた
3/25(金)Lewishamを歩く③ Deptford〜New Cross Gate〜Peckham
3/24(木)Lewishamを歩く② Lewisham〜Catford〜Bellingham
↑初めて、Lewishamより南に行く。あのトンガリつくるのは大変そう。
今日もよく歩いた。
早朝にBanKARTの池田修さんの訃報が届いて混乱する。
年末に会ったのが最後だった。KAIKOがオープンしたばかりなのに・・。
池田さんは常にいろんな企画を進行させていたけれど、
年に一度ほどご自身の好みを全開にした催しをやっていたと思う。
その仕事が好きだった。原口典之さんの展示の時は何度も通った。
「やっぱりファインアートすごいよね」
と言う池田さんが可笑しくて、でも本気で同感した。
劇団もしんどい時期に助けてくださった。
結婚する前、元旦に帰省するため新幹線に乗ったら、
同じ自由席に手ぶらの池田さんがいた。自分は名古屋で池田さんは大阪。
大晦日にBanKARTで宴会をやって、翌朝に帰省するところという。
現場が好きで、スタッフやお客さんといるのが好きだと言外に伝わった。
ちょっと寂しがり屋な感じを受けて、また別の意味で池田さんを信頼した。
・・・・・。
日本に電話したら止まらなくなってしまった。
室井先生の研究室が閉じられる日でもあったのだ。
もうとっくに卒業したはずの学生時代がもう一度終わってしまった
という実感に驚く。いまだに先生に依存する心があるのだと実感。
もう40歳過ぎているのに。18-34歳までのあまりに長期間、
一緒にいたから言い尽くせない。
椎野やKAATの眞野さんにも電話した。
色んな人に世話になりまくっている・・・
遅刻して語学学校に行く。
新米先生が日本に留学して名古屋に滞在していたと分かり、
授業後にいろいろと話した。その後、ミス・ダイアンに頼まれた
買い物をして一度帰宅し、すぐ散歩に出かけた。
ここからが本題。今日はLewisham駅から初めて南下する。
すぐに新興の住宅地になって、生活に余裕アリというゾーンが広がる。
Lewisam Hospitalの裏に広がるLadywell Fieldsという公園。
子育てしやすそう。こちらの人は日光を大事にする。ピクニックが上手い。
↑遊具コーナーには柵がある。親は楽だろう。
さらに南下して30〜40年前の新興住宅地を抜けると
面白い街に出た。Catford。初めCatfoodにしか見えなかった。
巨大なペット用品店でもあるのかと思った。
かに道楽のカニくらいのサイズで巨大な猫もいたし。
懐かしい雰囲気の活気ある商店街。
↑絶対にFOODだと思っちゃう。
築90年のBroadway Theatreも発見したが、
改装中のようだった。後でミミから、設備にいろいろ問題があって
改修がうまくいっていないと聞いた。
↑改修中のBroadway Theatre
交通もメディアも未発達の時代に地元に貢献してきたであろう威容。
さらに南下し、巨大なカー用品店や洗車場がいっぱいある地区に出た。
店も国道沿いの感が強い。16:00前にBellinghamに着き、
国鉄で移動しようかとも思ったけど、やはりバスでLewishamに戻った。
今日行った地域はおしなべて横浜の本牧的だ。後からできた街の雰囲気があり
整然とした住宅地や巨大なお店がある。
↑Bellinghamの国鉄。都心まで30〜40分ほど。
ショッピングセンターのカフェで16:30からミミとzoomで話す。
「まだ西に行ってないんだけど、貧しくて治安が悪いのって
LewisamとDeptfordだけ?」と周囲に慮って小声で聞いたら、
ミミに爆笑された。ほぼYesという返事だ。
最近、ミミの話をしてよ、とお願いしたら、
彼女は大学時代に舞踏に興味を持ち、ダンサーの先生に教わったことを
教えてくれた。土方巽も大野一雄ももちろん知っていると言われて、
唐十郎門下、元上星川住民の血が騒ぐ。自分はミミの役に立てる!
オレが気に入りの蕎麦屋で食べていると、大野先生の家から
出前の電話がかかってきたものだ。そう伝えてまた笑われた。
将来、ミミを日本に呼びたい。ここでしてもらっていることの
お返しを少しでもできたら、どんなに良いだろうと思う。
ところで、Zoomのためにカフェのテーブルにパソコンやケータイを
出すことには緊張感がある。警備員さんのいるセンターの中だから
大丈夫だろうか? 一店舗ずつのカフェの軒先だと場所によっては危険?
そんな風にビクビクしながら、初めて家と劇場ではない場所でZoomした。
カバンは常に視界のうちに入れる。
もう一つ、忘れないように書いておきたい。
ショッピングセンターを出たところで、電動車イスのダウン症の女性と
すれ違った。男性二人がお世話していた彼女は30歳過ぎくらいだろうか。
ふと見ると、車イス付属の荷物入れにビニール製の赤ちゃんの人形が
覗いていた。一瞬で打ちのめされた。
夕方からはセントラルに行き、書店FOYLES本店→Charing Cross
→Southbank Centreに行って帰宅。
3/23(水)Lewishamを歩く① Brackheath〜Lee 〜Lewisham
↑グリニッジ公演の南端に戦没碑があった
今日から午前中は学校に行き、午後は散歩することにした。
そもそもロンドンは32地区に別れており、Lewishamはその一つ。
研修先のThe Albanyはロンドン市が行ったコンペに勝って、
劇場が地域を盛り上げるためのフェスティバルを2022年を通じて
行なっている。それが「WE ARE LEWISHAM」だ。
自分としては、一度、区内をくまなく歩いてみたい思った。
月曜の朝シンポジウムで、久しぶりに多くの劇場スタッフに
まとめて会ったが、何人ものスタッフに「アツシはいつも劇場にいる」
と言われた。一通り顔見せは済んで馴染んだようだし、
今度は、この劇場が盛り上げようとしている地区を肌で感じてみたい。
どんな地形で、どんな歴史を持ち、どのような人たちが住んで、
地区の雰囲気がつくられているのか。歩いて把握する。
大通りだけでなく、住宅街にも分け入って、民家や学校を眺める。
家や庭の様子や子どもたちを見れば、そこに住む人が想像できる。
商店にも入って、美味い店も見つけたい。
考えてみれば、KAATでも初めにこんな動きをした。
神奈川県は広いから、車を調達して走りに走った。
イギリスでは車がないがその分狭い。徒歩で十分だ。
↑庭が広い。高級車がたくさん。
Greenwich Westにある語学学校を出て南に進む、
登りを経てBrackheathへ。ここは有名な観光地だが、
行ったことのある中心をわざと避けて、区の境界ギリギリを歩く、
高級住宅地だ。庭は広く、高級車がいたるところにある。
学校の広々としており、いかにもお金持ちの子弟がバスケットボールを
していた。
↑新築のマンション群
高級マンションが次々と新築されている様子で、
公園にはユニークな遊具があった。
さらに南進してLeeを目指すと、もう少し落ち着いた
昔から裕福な人たちが住み続けている雰囲気に切り替わる。
新築エリアには生活感がないが、住み慣れた居住まいの良さを感じだ。
国鉄Lee駅は周辺にだけお店があり、広大な公園と住宅街だった。
↑Lee駅前。「WE ARE LEWISHAM」のフラッグがあった。
この場所が自分にとって重要なのは、
好きな詩人で小説家のErnest Dowson(1867-1900)の出身地
だからだ。唐さんも好きな「酒とバラの日々」という言葉は
彼の詩による。同名の映画が作られたのを唐さんは観て
『二都物語』二幕にこのタイトルをつけた。
自分は20代の頃に岩波文庫から出た短編を読んで気に入り、
翻訳で読めるものは読んだが、土地柄を見て彼の原点を実感した。
彼が生まれる前年に国鉄開通。地方の商人がロンドンで商売を
するために屋敷を構えたこの場所には豊かな邸宅が多い。
けれど、すぐ近くにLewishamというワイルドな一帯を見下ろす。
↑Bwlmont Groveという地域。この丘のあたりでダウスンは生まれた
金持ちしか知らない金持ちと、貧しい人々を知っている金持ちは違う。
ダウスンは後者ゆえにあのような作風になったし、身を持ち崩して
破滅していくやり方を、小さい頃から体感していたのだと思う。
それにしても、何人かのイギリス人にダウスンの話題をふったが、
誰も彼を知らない。ミミも知らいという。
今度セントラルに行ったら、本屋で本を探したい。
小説には英語力が追いつかないが、詩なら辞書を引き引き味わえるかも。
Lee一帯は今日の気候の良さも手伝って、別荘地のような優雅さだった。
そこから北上しLewisamを経て帰ってきた。
途中、ダイアンに頼まれた買い物をしたりして。
合計10マイルちょっと歩いた。
3/22(火)まちなかで祈る人々
3/18(金)ジェットコースターな1日
3/17(木)ロンドン塔に行ってきた
朝起きてブラインドを開けると曇天。しめた!
今夜はAlbanyでイベントのみ。昼間に特筆すべき打合せもない。
ということは、昼間の自由行動が許される。
これが夜に他所の劇場へ行くようなら、
必ず昼にAlbanyを訪ねなければならない。
誰に強要される訳ではないが、そうでなければ新参者の、
言葉の苦手な自分がこの劇場の一員たることはできない。
大学に入った時、唐さんに接する時、KAATに入った時も
自分はそうしてきた。こういうところには室井先生の教えを感じる。
人は自分を見ている。一番大切なものから目を切ってはいけない。
Albanyに夕方遅くに行けば良いし、典型的なロンドンの曇り空。
となれば行くべき場所は一つ。ロンドン塔。
学校では絶対に今日出掛ける場所を言わない。
一緒に行こうよ!などと周囲に言われては台無しだ。
こちらは漱石の小説も日記も読んで盛り上がっているのだ。
必ずやひとりでなければ。
授業を終えるとすぐにカティサークに行き、
初めてテムズ川のボートに乗った。横浜のシーバスより揺れる。
うねうねと上流に進みタワー・ブリッジに接岸。
途中、高級住宅らしき建物をたくさん見た。
ボックスオフィスでMature studentと主張し切符を買う。
ロンドンはメリハリが効いている。あらゆる美術・博物館の
常設をタダにしておいて、ここは約4,000円とる。
中に入ると落胆の連続だった。
当然ながらすっかり観光地化されている。
小学生たちの遠足も元気に行進。さらにやたらと写真撮影を頼まれる。
カップルに、おじさんの二人連れに、言葉が不得意なオレに
頼むなよと思うが、声をかけられるとつい全力で応えてしまう。
さすが高額をとるだけあって場内は清潔。ロンドンでは珍しい。
庭も建物内もトイレも。スタッフにも緊張感があった。
が、展示のショーケースやモニターの数々が邪魔すぎる。
ついラーメン博物館を思い出してしまう。
歩き回っていると小雨が強めの雨に変わって子どもたちが去り、
夕暮れが近づいたので少し雰囲気が出てきた。
正直に言って、夏目漱石の『倫敦塔』は最初と最後だけ面白くて、
塔内の描写は自己陶酔が鼻につく。それにジェーン・グレイの
くだりなど、あまりに絵画のパクリなので興醒めだと思ってきた。
が、実際のロンドン塔に行ってみてその中間部を見直した。
漱石が訪れたのはすでにヴィクトリア朝末期だ。
ここはもうとっくに観光地化されていたはず。
だから、彼は十二分に現実を受け止めながら、
こうであって欲しいという姿を書いたのではないかと思った。
実際を体験して小説の価値が増した。
この小編の最後、漱石は宿屋のおやじに塔の感想を述べて冷や水を
浴びせられ、もう二度とロンドン塔の話をすまいと決心する。
当然、二度と足を運ぶこともない。
一方、自分は一度も行かず小説だけ読んでいれば良かったと思う。
最後はヤケクソで売店のキーホルダーを買ってしまった。
唐さんの『鐵假面』という戯曲が好きだ。だから鉄仮面を見ると弱い。
せめて、倍の値段をとっても良いから、
全消灯のうえ蝋燭でいくナイトツアーを組んでくれないだろうか。
それなら、自分はもう一度たずねてしまうかも知れない。
ところで、最もプロフェッショナルなのはカラスたちだった。
こちらの手の届く範囲に近づいても彼らは一向に物怖じしない。
目の前1メートルのところで糞をするカラスを初めて見た。
これには感心させられた。
3/16(水)アイリッシュの夕べ
皆でくつろいで過ごす。どこからともなく演奏と歌が起こる。
自然に合いの手が入る。コンサートには無い滋味がある。
みな凄く達者だ。気分は宮本常一。誘ってくれたアダムさんに感謝。
『唐版 俳優修行』の打ち込みが間もなく終わる。
残すところあと1ページもない。というところで寸止めする
心地よさよ。これが終わったら誤字脱字チェックがてら
もう一度読み込んで、頭を整理するのだ。
学校に行ったところ、敬愛するエリザベス先生は休みだった。
昨日から病気らしい。コロナでなければ良いが。
Albanyへの道すがら、マッシュ&パイの店に寄った。
ミス・ダイアンが、あの店にいくべきだ、
そこでチリ・ヴィネガーをかけるべきだ、と強弁するのだ。
彼女の言うことは必ず聞く。なるほど、紅茶をつけても
£5のランチはリーズナブルだし、店でゆっくりできるのも良い。
食べながら、近くロンドン塔に行こうと決める。
Albanyではセリとロンドンの人件費や物価について話した。
劇場運営に関する予算について訊き、話が派生したのだ。
アツシの好きなパン屋は高い。そう言われた。
で、夜はライブハウス「マッチスティック・パイハウス」へ。
このまえ知り合ったアダムさんに誘われて、フォーク音楽の集い
に参加しのだ。これが実に不思議なイベント。
ロビーに着くと10数人が腰かけているのみ。
アダムさんに喋りかけるとあと10分で始まるという。
実際、8:15pm頃にオーガナイザーの女性が喋って、
男性が歌い始めた。会場はロビーのまま。
これが今夜の趣向なのだそうだ。一人目だけゲストシンガーで、
あとは思い思いに歌うのだとアダムさんに教わった。
信じがたい。しかし、実際に事は起こった。
オーガナイザーが緩やかに仕切ると、
誰かがギターを取り出して歌うのだ。
おじさんたちはみな達者だった。
他にアカペラ男子もいたし、ヴァイオリン弾きの女の子もいた。
二人でハモりながら弾き語る女子は抜群のコンビネーション。
ハモり、即興でギターやリコーダーも加わる。
そこへヴァイオリンまで入ってくる。間が開くと司会の女性が歌うが、
これがまたやたらうまい。アイリッシュが中心の夜。
とりわけ面白かったのが、ずっと酒をチビチビやっているおじさんで、
彼らは歌わない。聴きながら、涙目になっているように見えた。
不思議なことにこのイベント、集まった者は皆知り合いでなく、
最大でも3人連れか4人連れのペアがちらほらあるのみ。
要するに、知り合いでもない人たちが集まって、思い思いに歌う。
楽いそうにはとても若い男の子も寝そべるようにして参加している。
最終的には、大合奏になっていった。重ねて不思議な夜だ。
歌はどれも良かった。郷愁に充ち手いた。
自分はこれがひどく気に入り、次回3/26にも参加することにした。
振られた時のために、一曲くらい仕込んでおく必要がある。
マッチ棒パイハウスの黒板。どうやら定期開催らしい。
他イベントも覗いてみると面白そうだ。セントラルにない魅力がある↓
3/15(火)ミス・ダイアンとの対話
↑実物を見た。オフィーリアの衣装は生地がかなり厚めだとわかった。
だから水吸って沈む。しかも清流でなく澱んだ水。絶対飲んじゃダメ。
3月13日、日曜日。この日は早く帰った。
引っ越してから1週間、初日こそ家にいたものの
以降は毎夜出かけてばかりきたが、昨日はAlbanyで行われた
子ども向けプログラムのみだったので20:00前に帰宅したのだ。
すると、話をしましょうとミス・ダイアンから声をかけられた。
彼女はこちらの行動を見てひどく心配してきたらしいのだ。
曰く、初めて会った下見の時からするとアツシはどんどん痩せていく。
ちゃんと食べているのか?と。
食べていますよ、と答えると、
このままではイギリス生活中にあなたは別人になってしまい、
日本に帰って奥さんに驚かれてしまう。それが心配だ、と引かない。
そこで、ここ数年の日本での不摂生について語ることになった。
日本では車で動いている。朝早くから夜遅くまで働いている。
夕食を家で摂るかどうかその日の流れ次第なので、
優しいワイフはちゃんと作っておいてくれる。
例え外食したとしても、そういうわけで、夜中にもう一食たべてきた。
しかも、うちには子どもがいるので、
ついつい息子の好きなお煎餅の良いやつを買ってしまう。
福祉施設への出入りも多いからクッキーも買ってしまう。
アイスクリームやケーキも買ってしまう。
それを子どもよりも自分がたくさん夜中に食べてしまう。
さらに、地元では夜中までやっている美味い店を知り尽くしている。
そもそも、日本は24時間営業の店が山ほどある。
うちの家は徒歩5分以内のところにそういう店が3軒ある。
しかも、渡英前はこれが食べ納めと言ってやりたい放題した。
結果的にかなり動きが鈍くなった。疲れやすい。
走るのが好きだが、忙しくて1日に30分弱しか走れない日も続いた。
その点、今は幸せだ。
時間に余裕があるし、ロンドンの景色が愉しいので1日12キロくらい歩く。
回数こそ減らしているが、食べるとなれば美味いものを食べる。
夜に食べないので調子が良い。店が開いていないので誘惑が少ない。
浮いたお金で劇や音楽や旅行に使うこともできる。
だいたい、自分がもっとも恐れているのは、
近所のスーパーにあるハーゲンダッツのパイント(480円相当)を
買ってしまうことだ。しかも悪いことに、置いてあるのは、
日本では見たことのないチーズケーキ味(一番好き)のパイントなのだ。
あの味を覚えてしまったら、この研修は失敗すると思う。
自分はあればあるだけ食べる人間だ。
アイスクリームのパイントを一回で食べたことも、
ケーキをホールでやってしまったこともある。
実は今日はAlbany近くの気に入りのイタリアンで奮発し、
日曜限定の軽いコースを食べた。スターターで出てきた
仔牛のカルパッチョが脳天をぶち抜かれるほどの旨さで
厨房を覗いてシェフ二人を絶賛し、記念にメニューの紙をもらってきた。
ほら、これがそれです。このデザートがまた美味いんですよ。
と、伝えたら、さすがのミス・ダイアンもI see.と言った。
そして、このエリアNo.1のピザ屋を教えてくれた。
明らかに日本より健康的だと思う。
気に入りのインド料理屋のおかげでベジタリアンぽくもなってきている。
ここ二日間の動きは下記の通り。
3/13(日)唐ゼミ☆WS→部屋の掃除→Deptford Lounge→Albany
3/14(月)学校→Albany→テイト・ブリテン→バービカンセンター
↓記念にもらったメニュー。毎週内容が変わるのでプレゼントしてくれた。
3/12(土)ロンドンにも桜は咲く
↑家から5分のところにあるスーパーの前
今日は土曜日。しかし、林麻子のワークショップはお休みです。
彼女の劇中歌WSはニッチな感じもしますが、実践的で面白いものです。
なかなか参加者が増えないのでどうしてだろうと思っていたら、
"歌う"という行為に気後れするのだと聞きました。
確かに、歌のWSは参加者同士、家で家族から見られることを考えても
二重の恥ずかしさがありそうですが、唐十郎フリークにはぜひ参加して欲しい。
唐さんは若い頃からシャンソンやカンツォーネに目がなく、
劇中歌は唐さんの芝居の全編を集約する宝石です。
ひとつの歌を歌詞を読み解きながら歌ってみるだけでなく、
その同じ歌が、物語の進行とともにどう意味を変えていくか
知ることも重要かつ愉しい作業です。
楽しい歌が悲しい歌に変わり、主人公を励ます讃歌になったりする。
観劇後につい口ずさんでしまう劇中歌のある劇は名作です。
今ならまだ少人数。ぜひ讃歌してください。
さて、私の方は徐々に暖かくなるロンドンを味わっています。
今日は土曜日なので朝の動き出しに余裕があり、
家の近くに桜があるのを発見しました。
しかし、ロンドンはしばしば強風。
そのために雨が降っても誰も傘をさしません。
それほどの強い風がいつも吹いています。
当然、咲き誇る桜にも容赦なく風が吹き、
日本で見るような雅やかさは望むべくもありません。
他面、「ガンバッて咲いています。一瞬の命です」という峻厳な感じする。
ここ数日も色んなものを見ていますが、
一番すごいと思ったのはナショナル・ギャラリーでした。
これだけ錚々たる絵画をいとも簡単に、しかもタダで見て良いのか?
と思うくらいに、ロンドンは恵まれています。
日本の美術館では考えられませんが、ここでは、
フラッシュをたきさえしなければ誰でも撮影OKで、
有名な絵と記念撮影する老若男女をたくさん見ました。
日本だと"印象派展"という風にならざるを得ませんが、
ここには数百年間の絵画が勢揃いしていて、それぞれの時代に
人が世界をどう見ていたか、実感することができます。
被写体がキリストや聖人たち、王様ばかりの時代、
平面的で、画角いっぱいに光の当たる世界観から、
徐々に陰影がつき、遠近法が導入され、"人間"が自らの個を
強く信ずるようになった過程がダイレクトに実感できました。
あれだけのものを見て街に出ると、
ああ、自分の前に広がる景色のこの見え方も、
自分が生きている時代固有のものに過ぎないのだなと痛感します。
普段、自分が文学や歴史、もちろん演劇を通して味わっている愉しみ。
それぞれの時代や地域の人たちと交流する面白さを、
この日は絵画を通して味わいました。
当日にネットで予約すればすぐに飛び込むことができるのも魅力です。
カタログを読んで、また行ってみたいと思います。
↓大天使ミカエルが悪魔をやっつけている絵
3/11(金)激しく打ちのめされる
3/10(木)変なおじさん
3/9(水)ここは危険なまち
3/8(火)引っ越しを終えて
↑いろいろ面倒を見てくれたホテルスタッフのサキブさん
先週末から週明けにかけての記録を。
4(金)
イギリスの人々の週末にかける意気込みは強い。
語学学校のエリザベス先生も、今日は金曜日だと嬉しそうだ。
と同時に、クラスメイトの中には遅刻が目立つ。
初めて文法のテストで一番になることができた。
これまで周りに遅れをとってきた分、嬉しい。
この日のalbanyにはミミやセリ、エマがいない。
そこで引っ越し準備に注力するため、午後をホテルで過ごす。
物を増やさないようにしてきたが、書類や石鹸類、
買ってしまったCDなどが確実に増加している。
到着時、すでにトランクがパンパンだったので、
スーパーの買い物袋を足して対処する。
困ったのはお金の用意。大家さんに敷金と初月の家賃を現金で
渡さなければならないが、ATMで四苦八苦する。
ここにきて、近所のスーパー前にあるものでは一度に£200までしか
おろせないことが判明。後ろに人を待たせながらの繰り返し作業に
怖気付き、一回やったら次の人、その人が終わるのを待ってまた自分、
を繰り返す。が、いよいよフィニッシュと思ったら、デビットカードの
1日上限に道を阻まれた。仕方ない。
残りは明朝おろそうと先送りにして、荷造りを終える。
長い逗留だったし、初めてのUK滞在場所につき思い入れがある。
ホテルスタッフにお礼状を書いた。カードキーと一緒に封筒に入れる。
夜はアンドラーシュ・シフのハイドン・フェスティバルに向かう。
初日を聴いてもう一度行きたいと思った。当日券でステージ近くの席を買う。
フォルテピアノの音は繊細だ。聴き逃してはならないと奮発したが、
響きと演奏に陶然として悔いなし。
帰り道、オフィスビルの路地裏を通ったら、閑散とした通りに
四人の男が毛布にくるまって車座になり、サイコロを振っていた。
英国式チンチロリンだ! 彼らから10メートルほど離れたところには
明らかな人糞があり、「ペストのロンドン」という言葉を思い出した。
5(土)
引っ越しの朝。早朝に日本とzoomを行った。
ずっと唐ゼミ☆の写真を撮り続けてくださっている伏見行介さんとだ。
これまで、あまりお話もせずに10年以上も撮影してくださっているが、
初めて話し込んだ。日本に帰ったら、伏見さんに会いたい。
それからfacebookを更新し、引っ越しの仕上げにかかる。
トラブルが二つ。まず、一日経ってもお金がおろせない。
次に、出発時にお礼状を置こうとしたらサキブさんに声をかけられ、
お別れがセレモニー化してしまう。彼はチェックアウト客の捌きも
あるから、少し話しては接客に戻る、を何度も繰り返さざるを得ない。
ありがたいのだが、大家さんに10:00に行くと約束しているので、
ちょっと焦れてしまった。でも、やっぱり別れを惜しんで記念撮影。
スニーカーの袋を括り付けたトランクをゴロゴロやりながら
新居のある丘の上を目指す。息せききって辿り着くと、
これからお世話になるミス・ダイアンが温かく迎えてくれた。
まずは、部屋に荷物を運び込み、それからお金について
お詫びと説明をして、残りを待ってもらえることになった。
それから、カギの開け閉めや部屋の窓の開け方や収納の仕方を教わる。
共同生活のスタートを良好に切るためにも、この日は他に予定なし。
バスタオル、追加で必要なハンガー、昨晩壊れた傘の替え.....。
そんなものを買うために出かけようとしたところ、
どこに行けば安いか、どのように移動するべきか、丁寧に教えてくれる。
行き先は、何度か行ったことのあるLewishamショッピング・センター。
あそこは治安が悪いので気をつけるよう、何度も釘を刺される
母親のようだ。
のどかな丘を下って行くと、20分で目的地に着いた。
それから英国で、初めて生活感のある買い物をした。
何軒も店を回りバスタオルの価格を比べた。
£20の店もあれば、£5のところもある。もちろん自分は底値のを買う。
触れたところ品質に問題ないし、自分は年末までの期間限定だ。
水なども買って家に戻ると、ダイアンさんはご自身の買い物に
出かけている。そこで、Canary Wharfへ。
いつも乗り換えにだけ使ってきたが、ここにはスーパー付属のものより
精度の高そうなATMがあり、案の定、無事に引き出すことができた。
初めて Canary Wharf の商用施設も渡り歩き、
どんなお店が入っているかを確認した。ここにも一風堂がある。
6:00pm頃に家に戻って荷を解いているとダイアンさんも帰ってきた。
シャワーの使い方も聞いたが、使用後は水を拭き取ってねと言われ、
Yesと答えながら内心おどろいた。そんなことができるのか。
これはやってみると、そんなに難しくなかった。
英国は乾燥していて洗濯物などすぐ乾くが、ここのバスルームは換気が弱い。
ダイアンさんの入浴後も、なるほど、キレイに拭き取られている。
これを食べるしと様々なものを供される。
それでいて寝る前には、飲食は自分でね、と念を押される。
6(日)
翌朝起きしな、コーヒーどう?と言われて笑ってしまった。
原則があり、グレーゾーンがある。これが共同生活だ。
聞けば、これまでダイアンさんは何人もの日本人女子を受け入れて
きたらしく、最長の人は8年もいたらしい。向こうの方がプロだから
こちらは従って行けば良い。それに、下手に友だち世代とシェアを
するより、向こうにイニシアチブがあってそれに合わせていく方が、
曖昧さが無くて楽だ。ここの掃除はどっちなの? という状態で
不衛生になっていくより、規律があった方が健康に良い。
今年は体調を崩せない。
こちらの時間で9-11時まで唐ゼミ☆WSをして、
自分の声がデカすぎないか訊いたら、ダイアンさんは笑って
OKと言ってくれた。
昼過ぎに、ぜひ行くよう勧められたブラックヒースに散歩して
昼食のパンを買った。いつもグリニッジのGAIL'sという店で
買ってきたが、同地にも店舗があるらしい。
歩いて15ちょっとのブラックヒースに向かうと、
丘を下ったところに大きな教会があり、さらにその下に商店街が広がる。
自然が多く、コンパクトにお店が集まるのが魅力的な村だ。人が多い。
頼まれたダイアンさん用の水も買い込み、少し教会に寄って家に戻る。
今度は洗濯の仕方を教わった。洗濯は週に一度だそうで、
とりあえず土曜日を選択した。汗をたくさんかく夏は大丈夫か?
洗い終わりを待ちながら、さらに買い物へ。
共有物として、食器洗い洗剤、トイレットペーパー、
キッチンペーパーを月に一回収めなければならない。
また、今回は使わせてもらったが、洗濯用石鹸も別々。
そこで、これらが安く手に入るお店とグリニッジ駅への近道を
教わり、今度は今までとは別のルート、階段を使って丘をくだる。
以前は前を通り過ぎながらも決して入らなかった店がオススメの買い物先。
こうして、徐々に自分も地元の仲間入りする。
品物を揃えてレジの青年のところに持っていくと
Do you live in Dian's house?と訊かれてビビる。
Why do you know that? と訊き返すと、
歴代の住人が皆同じものを買いにくるから、と笑っていた。
あの小さな女の子はどうした?とも訊かれたけれど、
1週間前に入れ替わりで引っ越した彼女を自分は知らない、と答えた。
家に戻ってダイアンさんに報告すると、笑いながら
店員の彼は前に住んでいた女の子のことが好きだったのよ、
と教えてくれた。これまでのホテル暮らしに比べて
人間関係の入り組んでいることよ。
5:00pmに家を出て、Deptfordへ向かう。
インド料理Hullabalooで食事を摂り、その後Albanyのカフェで事務。
そして、7:00pm開場のライブを観るのだ。
7:30pm頃からお客の集まりが本格化すると、
着席で150キャパのAlbanyに倍以上押し寄せている。
今夜はオールスタンディングゆえにそれが可能なのだ。が、凄い数だ。
バーも激混みだが、リヴやケイトが生き生きとお客を捌いている。
7:45pmからDJのあおりが始まり、8:00pmからライブ本編。
3人の歌手が場を盛り上げたが、自分にはイマイチだった。
ヘイワードさんやMatchstick Piehouse でのライブの方が
断然すごかった。今日の3人は有名人なのだろうか。終演11:00pm。
遅いので急ぎ足に帰宅したが、あらかじめ帰り時間を伝えてあった
ダイアンさんはにこやか。シャワーを浴びて拭き掃除し、就寝。
↓自分の部屋。ここで色んなことがあるだろう。
7(日)
次なる研究対象を『唐版 俳優修行』と定め、台本づくりと読みに入る。
シェイクスピアの国にいるから、というのが選定の根拠。
かつてMORDの松本修さんが演出した舞台を思い出す。
その後、新居から初めての出勤。
目と鼻の先にSt Ursula's Covent School(聖ウルスラ学園?)という
女子校があり続々と生徒が登校してきていたが、校門が開いていない。
生徒たちが開門を待つ。日本とは違う景色だ。
語学学校にはヨルダンとフランスから新たなクラスメイトが加わった。
ロンドンで発見した自分のオススメスポットについて話し合う。
先生や他の生徒の話が、以前より聞き取りやすくなった気がする。
Golden Chippyで特大Skateを食べ、Albanyに移動。
先週の会議の議事録を送ってくれたロミカにいろいろ質問したいが、
いないようだ。シフト表では出勤になっているが、オフィスに荷物を
置いて何処かに行っているようだ。また明日チャンスを探ろう。
夜はBush Theatreへ。
少し遠いところにある劇場だが、演目が気になった。
フットサルと会話劇を融合させた作品だった。
16歳を演じた3人の黒人青年が優れている。
お客は半分も入っていなくて100人に満たなかったけど、
彼らの達者さといかにも青春の残酷と甘さを描いたストーリーに
終演の瞬間から総立ちで拍手していた。一体になってグータッチもする。
コロナはどこへいったのだろう。
↓村はずれの教会。日曜朝の礼拝の後で、中は良い香りがした。
3/4(木)クリエイション!
3/3(木)今日もギグだぜ
3/2(水)ロンドンで気づいたこと
3/1(火)ミミとの邂逅
2/25(金)広場とポエト
Deptford Lounge 館長のアネッテさんは、まるで地域のお母さん。
ヨークシャー出身の彼女と『嵐が丘』についても話した。
昨日もいろいろなことがあったので、特筆すべきことを三つほど。
一つ目。
語学学校の同級生、ヤジーズ君がサウジアラビアの大金持ちと知る。
お父さんは企業の社長(何の仕事かは不明)。
運転手付きのロールスロイスに乗っており。兄弟は12人。
前回の誕生日に彼がもらったプレゼントは良質の馬だという。
「Very Cheap!」が口グセ。
週末ごとにセントラルにあるタイガー・タイガーというクラブに
通っているが、行くと意外と奥手で、何人かの女の子とやっと
インスタアカウントを交換してもらい喜んでいるとは、同行した人の談。
二つ目。
初めて、Tha Albanyが運営する別棟施設 Deptford Lounge に行く。
というか、いつも横を通っていた図書館の建物がそれと知って驚く。
ここは日本でいえば生涯学習施設で、地域の人に集会や練習の場を
提供しているが、特筆すべきは学童を含んでいることだ。
屋上にグラウンドまである。
劇場とは直接関係ない施設を運営することで、縁遠い人たちを
公演やワークショップに招き入れるシステムの窓口になっている。
感心した。
三つ目。
Canada Water Theatreでポエトリー・リーディング公演に参加。
『OFF THE CHEST』というタイトル。
プロのMC、プロの詩人、アマチュアの中からオープンマイクに
手を上げて選ばれた10人が出演者だ。
特に面白かったのはもちろんオープンマイクで、腕に覚えのある
人たちが詩やラップを繰り広げる。少女の告白といった向きの
朗読もありました。中でも胸を打ったのは、20代半ばと思しき
大柄の黒人青年の訴えです。彼は非常にたどたどしく、けれども
他の人とは違ってノートやスマホは一切見ず、コロナにより仕事を
奪われ、孤独であることを語った。
それは、自分の語学力の低さを貫通して、たちどころに理解できる
ものだった。彼が終わった後は、皆が立って彼に拍手。全体の終演後は、
ロビーや劇場内で延々語らいが止まらず、時間が過ぎていく。
当然といえば当然だが、普通に会ったら
絶対に近寄りがたい風貌の青年が、同じ人間なのだと切実に実感した。
劇場スタッフのリヴやジェニーは、早く帰りたいなあ、とは冗談で
言いけれど、片付けられるところを片付けながら、彼らを見守って
いた。毎日、少しずつ粘ることこそ難しい。なかなか出来ないことだ。
内容や関わる人たちを尊重する姿勢が、この劇場のスタッフには
浸透している。彼らを見ているとたのしい。
働き過ぎではないかと思ってリヴにそう伝えたら、彼女は週末から
週明けまで休みをとって、イタリアに行くそうだ。片道5,000円も
せずに行く方法があると教えてくれた。写真をたくさん撮るのだと
行っていた。サッとイタリアに行く。カッコいいなあ。
お代は見てのお帰りなので、専用の回収バケツがある。
2/24(木)英語で怒られたことなど
2/22(火)先週末〜週明けにかけて
2/19(土)ひとあし先に飲み会
2/18(金)よく話しかけられる
2/17(木)足を止めてみる
2/16(水)ついにギャビンに会う
2/15(火)魚ごころあれば水ごころ
2/11(金)家が見つかりそう
2/10(木)傘がない
2/9(水)まるでお遍路のように
2/8(火)研修がはじまる
2/4(金)徐々に慣れつつある
2/3(木)受けと攻め
2/2(火)水を求めて
2/1(火)ロンドンに着いた
1/31(月)今日から渡英します
1/28(金)片付けは宝の山
1/27(木)テツヤとの時間
1/20(木)新井高子さんを祝う!
1/19(水)講座「芝居の大学」ご案内
1/17(月)劇壇ガルバを観てきた
1/15(土)必殺のブレックファースト!
1/14(金)新橋、その突撃の顛末

1/13(木)新橋、怒りの突撃!
1/12(水)最後の焦らし
1/11(火)カギを失くしてさまよう
1/8(土)メガネ3本
1/7(金)雪中行軍
1/5(水)2022年が徐々に始動〜2月以降のWSは『下谷万年町物語』
1/4(火)助走の一日
1/3(月)京都のジェンダーレス
1/1(土)今こそ〝生活〟を
12/31(金)暗雲よ来い!
12/30(木)年末の収穫③
12/29(水)年末の収穫②
12/28(火)年末の収穫①
12/25(土)今日も坂本小学校の大そうじ
12/24(金)米澤が本番中!
米澤剛志が本番中です。
演劇ユニットnoyR(ノイル)の『Beautiful Land 』という公演。
会場は若葉町ウォーフで、日程はこれ!
12/25日(土)14時/19時
12/26日(日)14時
初めはすぐに完売でしたが、現場入りして増席できたため、
数枚のチケットがあるそうです。
https://twitter.com/unitnoyR/status/1452996721206775814
ここ数年、米澤は多くのチャンスを求めて彷徨っています。
一つのきっかけは、2019年にやった名古屋造形大学のイベントで、
この時に佐藤信さんの演出を受けたのが大きかった。
そこから、2020年2月末に座・高円寺の芸場創造アカデミーの
公演『戦争戯曲集』に参加し、世界を拡げることができました。
そこでのつながりから、今年はダンスにも挑戦し、
明日はじまる舞台にもお声がかりを得ることができました。
普段、寡黙でボンヤリしている米澤は、
芸の探求だけは熱心で、フツフツとしたものを感じます。
『唐版 風の又三郎』で「教授」役に取り組みながら、
現場入り前夜、最後まで衣裳・小道具に工夫を凝らし続ける姿に
執念を感じました。
写真は、米澤の実家を訪ねて、卒業アルバムを見せてもらいながら
撮影をしました。米澤と私の実家は近く、同じ愛知県、
彼が豊田市で私は名古屋市です。
2017年3月、
私たちが藤沢市での野外劇『常陸坊海尊』に挑んでいる頃、
米澤のお母さんが亡くなってしまいました。
突然のことで、米澤は通し稽古をして、お母さんのもとに行き、
また稽古のために横浜に戻り、さらにお葬式のために豊田へ。
公演が終わると、私もお線香をあげに行かせてもらいました。
電車を乗り変えながら、当時は大学生の米澤が大変な思いをして
この景色の中を往復したことが想像せられ、口数の少ない米澤が
本気で役者をやっていきたいのだと察せられました。
ウォーフの舞台、私は明日の夜に観に行きます。
クリスマスなので、何か滋養のつくものをプレゼントしようと思います!
12/23(木)今日は天皇誕生日だった
12/22(水)ビザ、複雑怪奇!
12/21(火)年賀状の準備
12/18(土)ポオと唐さん
12/17(金)ほおずき市と朝倉さん
12/16(木)リュートにハマる
12/15(水)とがったものは苦手
12/14(火)坂本小学校の大そうじ
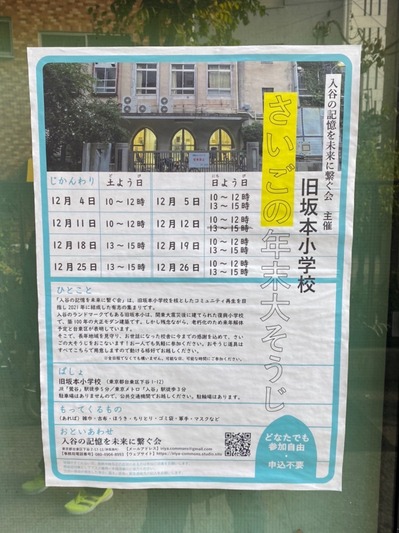
12/11(土)『泥人魚』を観てきた!
12/10(金)安藤洋子さんを観た
12/9(木)お屠蘇という霊酒
12/8(水)唐さんの学び舎
12/7(火)なぜか松本清張
12/4(土)渡航の準備
12/3(金)建築ジャーナル2021年12月号に寄稿
12/2(木)アイディアは二度使う
11/27(土)鼓童を観てきた!
11/26(金)『少女仮面』から『吸血姫』へ
11/25(木)"風喰い"とは・・・
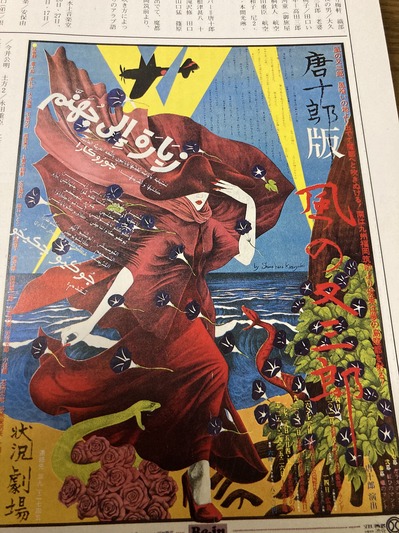
11/24(水)わたしの知恵袋
11/23(祝火)劇団集合と『黒いチューリップ』
11/20(土)禁じられた戯曲
11/19(金)国境をまたぐ至難
11/18(金)あこがれのシャコンヌ
11/17(水)大里俊晴先生の命日
11/16(火)新たな本棚がくる
11/13(土)安保さんからのプレゼント
11/12(金)あこがれの声
11/11(木)ヴィソツキイと劇団集合
11/10(水)会えなかった人
11/9(火)『アリババ』一巡目を完了!
11/5(金)子どもの頃にみた舞台②
11/4(木)子どもの頃にみた舞台①
11/3(祝水)洗面器は苦手
11/1(月)つなぎ〜佐々木は今なにをしているのか
10/31(日)カーテンコール〜禿恵
10/30(土)カーテンコール〜鳳恵弥・丸山正吾
10/29(金)カーテンコール〜丸山雄也・米澤剛志
10/28(木)カーテンコール〜佐藤昼寝・ワダ タワー
10/27(水)カーテンコール〜佐野眞一・松本一歩
10/26(火)唐さんが文化功労者に!&『少女仮面』WSレポート
10/25(月)カーテンコール〜小川哲也・津内口淑香

10/24(日)カーテンコール〜鷲見武・井手晋之介
10/23(土)カーテンコール〜ちろ・荒牧咲哉
10/22(金)カーテンコール〜林麻子・渡辺宏明
10/21(木)カーテンコール〜赤松怜音・佐々木あかり
10/20(水)ハンディラボでの片付け
10/19(火)浅草入り16日目(最終日)〜搬出・さらば浅草
10/18(月)浅草入り15日目〜舞台・テント劇場の解体
10/17(日)浅草入り14日目〜本番6日目 千秋楽
10/16(土)浅草入り13日目〜本番5日目
一方、こちらはストーリーテリングにひたすら磨きをかけ続けた
10/15(金)浅草入り12日目〜本番4日目
10/14(木)浅草入り11日目〜本番3日目
10/13(水)浅草入り10日目〜本番2日目
10/12(火)浅草入り9日目〜本番初日
10/11(月)浅草入り8日目〜最終リハーサル(マスコミ公開)
10/10(日)浅草入り7日目〜エンディング完成
10/9(土)浅草入り6日目〜第2・3幕の場当たり
10/8(金)浅草入り5日目〜第1幕の場当たり
10/7(木)浅草入り4日目〜劇場空間完成と仕掛けリハーサル
10/6(水)浅草入り3日目〜内装の完成
10/5(火)浅草入り2日目〜劇場と舞台ができあがる
10/3(日)浅草との馴れ初め〜後編
10/2(土)浅草との馴れ初め〜中編
10/1(金)浅草との馴れ初め〜前編
↑2009年10月『下谷万年町物語』開場! 浅草花やしきにて。
10月です。いよいよ週明けに浅草に入ります!
実に、6年ぶりの浅草公演。
今日は台風。
集合を休みにしましたから、皆それぞれに準備をしたはずです。
道具や衣裳・メイクの素材、テント劇場の設営への装備、
医者や散髪といった体のケア。さまざまです。
私は、来週から浅草と『唐版 風の又三郎』にどっぷり浸かるべく、
他の仕事をしました。済ませられることは、済ませておかないと。
いよいよ浅草だと思うと、胸が高鳴ります。
昨日、このゼミログに書いた着物屋の佐藤さんのこともあり、
唐ゼミ☆が浅草でデビューした時のことを思い出しました。
そこで、今日から3日間、浅草で初めて公演した時のことをお話ししましょう。
事の起こりは『下谷万年町物語』から始まりました。
20代半ば過ぎ、学生時代から劇団を支えてきた仲間の何人かが去り、
途方に暮れていた私は、一発逆転を果たすべく、この演目の上演を
決意しました。絶対に再演不可能と言われた大作です。
『下谷〜』の上演には池が必要であり、長大な長屋のセットが必要であり、
何より、登場人物表に「万年町の娼夫85人」と書かれただけの出演者を
充たす役者たちが必要でした。
2008年春。当時の私たちは、実に1年半をかけてこの準備に乗り出します。
公演場所も特別なものにしたい。そう思った私は、浅草に注目します。
唐さんが幼少〜青年期を過ごした上野・浅草が物語の舞台です。
特に、かつて浅草六区にあったという瓢箪池は重要なポイント。
そうだ!瓢箪池があった場所で公演しよう。
物語の始まりが、そもそも今は無くなってしまった瓢箪池を忍ぶ
一人の中年男の長ぜりふから始まります。ならば、私たちはその場所に
立ってこの芝居を始めたかった。
絶対に浅草で公演したいと思い定めて相談に行ったのは、
すしや通りにあるお蕎麦屋「十和田」の女将さんでした。
遡ることその2年前、2006年に墨田区で公演した際
(演目は『お化け煙突物語』『ユニコン物語〜溶ける魚篇』)
私たちは浅草にポスターを貼りに行きました。
その時に、女将さんと知り合った。
以来、年末年始や春・夏休みの繁忙期など、
私たちは浅草でアルバイトをさせてもらい、ご馳走にもなっていました。
どうにか浅草で公演できないか。テント劇場を立てられる場所はないものか。
襟を正してご相談にいったことが、全ての事の始まりでした。
9/30(木)佐藤さんが亡くなりました
9/29(水)さらば稽古場
9/28(火)作品世界への没入
9/25(土)稽古休みの今日は各地で資材調達!
9/23(祝木)ご支援のお願い〜2・3幕の通し稽古
9/22(水)『四角いジャングルで唄う』奇跡の復活!その他
9/21(火)唐十郎の世界を継ぐ!〜チケット発売と本日の稽古
9/20(日)チラシ完成!明日はチケット発売! そして、安保さんを偲ぶ
9/18(土)唐ゼミ☆の稽古休みはドリプロの本番
9/17(金)今日は作業日
9/16(木)木曜の夜は・・・
9/15(水)愛と決闘の3幕終盤
9/14(火)本日の稽古と『四角いジャングル』復活間近!
9/11(土)情報解禁!10/12-17『唐版 風の又三郎』in 浅草
9/10(金)立ち稽古の中の本読み
9/9(木)なかなかの前衛的着想
9/8(水)丸山正吾くんの稽古はじめ
9/7(火)本日の稽古と『続ジョン・シルバー』WSを終えて
9/4(土)今日は稽古休み
9/3(木)まるで海原雄山のように
9/2(木)今日も三腐人〜おかしな2幕
9/1(水)難役、三腐人!
8/31(火)夏休み最後の一日
8/28(土)鷹さんの舞台
8/27(金)原因はやや離れたところにあり
8/26(木)今回の「大学生」役は・・・
8/25(水)果たして成長のいち過程なのか
8/24(火)『唐版 風の又三郎』稽古、川崎より発進!
第30回特別公演 延長戦
『唐版 風の又三郎』
2021年10月中旬に上演!!
新宿中央公園にて。
8/21(土)選挙会場の人たち
8/20(金)賢治の2学期
8/19(木)私の小学校時代
8/18(水)宮沢賢治の奇妙な歯ざわり
8/16(月)音楽をたよりに⑤〜今日もバッハを聴いている
8/14(土)音楽をたよりに④〜『棲家』初日を終えて
8/13(金)『棲家』がはじまる
8/11(水)『四角いジャングルで唄う』の復活!
8/10(火)音楽をたよりに③
8/7(土)音楽をたよりに②
8/6(金)音楽をたよりに①
8/4(水)初日を終えて明日も初日
8/3(火)明日が初日! 築地に通っています
7/31(土)名古屋から帰ってきました!
7/30(金)陰性・陰性・陰性
7/28(水)『ガラスの少尉』によって湧き起こる記憶
7/27(火)川西町公演の思い出(『ガラスの少尉』WS 最終回)

7/24(土)佐藤信さんとの仕事
7/23(金)いくつかの稽古と書き物
7/21(水)好きなせりふを言ってみて⑤
7/20(火)好きなせりふを言ってみて④
7/17(土)好きなせりふを言ってみて③
7/16(金)好きなせりふを言ってみて②
7/14(水)好きなせりふを言ってみて①
7/12(月)『ガラスの少尉』〜唐ゼミ☆の2008年頃
7/10(土)ダンスと米澤

7/9(金)駐車場の恐怖
7/7(水)唐作品のなかの七夕
チョゴリの女たち 〽命の主の旦那さま 今夜は七夕
いつかの髪をかえして下さい
恐ろしい闇につつまれて
今夜はケン牛もまいりません
いつかの髪をかえしてください
7/6(火)シャーロック・ホームズへの憧れ
7/3(土)明日から『ガラスの少尉』WS!
主任 二人はこうして歩いているよ。今、廊下を曲がったよ。
ミノミ ええ。
主任 事務所の前を通ったよ。
ミノミ ええ。
主任 ラジオって便利だね。さあ、玄関が見えてきた!
7/2(金)『特権的肉体論』を読む
6/30(水)西洋のことなんか知るもんか!
6/29(火)明日、WS『海の牙 黒髪海峡篇』が完結!
6/26(土)李麗仙さんを悼む
↑これをやっと手に入れた時は狂気しました。現在は復刻CDあり。
李さんが亡くなりました。
唐さんを中心に、李さん、麿さん、大久保さん、シモンさんという5人を
状況劇場の第一世代として仰ぎ見てきました。
大久保さんを除いて、他の方々は唐さんを「唐は〜」という具合に敬称をつけません。
大久保さんだけは大学の後輩なので、こんな感じなのでしょう。
(学生時代の学年差は上下関係に大きく影響する!)、
お互いをそんな風に呼び合っている姿は同志的な結び付きの強さを
感じさせて、憧れでもあります。
李さんご本人と接することができたのは、
ここ10年以内のことで、お話しできたのも限られた機会だったけれど、
記録に残る歌やせりふの録音は、学生時代から膨大に聴いてきました。
やっと手に入れたカセットテープから『二都物語』の主題歌を聴いた時の驚き。
「石榴が割れて〜」と始まるAメロは、男性かと思うほどの低音だけれど、
やがて数行の歌詞のうちに果てしなく世界は盛り上がり、
終結部の「夜はどんな味がするの?」のという箇所では
女声の中でもとりわけ高音にゆきつきます。
それはそれはすごい音域の広さ。とにかく驚きました。
そしてまた、映像で見る李さんの身体能力の高さ。
芸能を志した時からたゆまず鍛え上げてきたダンスの精華がここにはあって、
動き回り、手足を動かす、身体いっぱいのダイナミズムが、
クルクル変わる表情の豊かさに結びついていて、
また、よく考えられた衣裳が、その運動を活かすように計算されている。
すごいな!と唸ってきました。
80年代の初頭にロックフェラー財団の招きで唐さんと李さんが
ニューヨークに滞在した時、唐さんはホテルに立てこもって『秘密の花園』を執筆、
李さんは毎日ダンスの稽古に行き、ブロードウェイの舞台を観て歩いたそうです。
お二人のキャラクターの違いをたたえる、自分の好きなエピソードです。
李さんの舞台に接した機会は何度かありましたが、
唐さんの作品に立たれたのは、2015年に金守珍さんがスズナリで演出した
『少女仮面』。ただ一回のみでした。正確には、
思わず同じ公演を2回観に行きました。
印象深いのは、1場最後の「春日野八千代」の登場シーン。
満を持して現れた李さんの、ゆっくり進まれることと言ったら。
驚くべきは、これが台本に、ト書きに書かれた通りの動きであることでです。
永遠の処女春日野はどこかを病んでいるふうに
吐気を催す程ゆっくり歩いてくる。
この「吐気を催す程ゆっくり」という指定を、全身で体現されていました。
突飛そうに見えて、ひたすら一徹に取り組む姿。
いつだったか唐さんが「李は真面目。あれほど真っ直ぐな役者はいない」
とおっしゃられていた真髄を見た気がしました。
もちろん他にも、3場の初めの少女・貝との稽古風景や、
水飲み男との掛け合い、満洲での天粕大尉とのすれ違いなど、
受けた印象は山ほどありますが、やはり冒頭は鮮烈でした。
たった一演目、たった一役だったけれど、
唐さんの世界に生きる李さんに接することができて、本当に良かった。
ギリギリ間に合って、本当に良かったと心から思っています。
6/25(金)プラトンと軽演劇

↑校舎は自然に囲まれて、創作のための砦のような感じでした
今日は名古屋に出張でした。
2018年12月に名古屋造形大学の依頼で行った
野外舞台『世界・都市・三間四方』のリニューアル公演を、
7/30に行うことになったためです。
この時、私は、構成・演出・舞台監督・出演までこなす
佐藤信さんの助手をしました。
この仕事のおおもとは、かつて横浜国大の先生であり、
現在は名古屋造形大の学長をされている建築家
山本理顕先生の発案によります。
同大学は、間も無く名古屋市の北にある小牧市から校舎移転する。
ついては、都市の中で大学の役割を考え、移転を告知するための
イベントを行っている。その一つを、一緒に思案してくれないか、
という相談でした。
それが、佐藤信さんにゲストをお願いし、
せっかく信さんならば、と催しが野外舞台化していったことから、
他にはないイベントになっていった。
面白いのは、取り上げる題材が、
古代ギリシャの哲学者プラトンであることです。
ハンナ・アレントを愛好する理顕先生は、
彼女が現代政治にはびこる悪しき権力構造の源を象徴するものとして
言及しているプラトンの対話編『ポリティコス(政治家)』
を取り上げました。
これを題材に野外舞台をやってみよう!
そういう流れになったのです。
初演は、名古屋市内にある東別院の境内にて行われました。
プラトンを題材に野外舞台を行う。
自分は、久々に室井先生と過ごしていた時のことを思い出しました。
こんな酔狂なイベント、採算に関わる劇場や企業では、
絶対に無理な組み立てです。
だからこそ、大学がやる意味がある。
室井先生に守られ、けしかけられながら、
大学だからこそできる企画、
大学でしかできない企画を追究した結果、
トラック演劇、野外劇も、「大唐十郎展」だって行うことができた。
この企画もまた、そういう感じがしたのです。
果たして、プラトンの訳文の難解さは、
信さんの手腕によってナンセンスでコミカルな軽演劇になっています。
ちょうど、難解そうに見えるベケットの劇が
演じられる役者によって笑えてしまう。あんな感じ。
本当に知的なものは、知的を通り越してユーモアにいきつくことを、
自分は唐さんからも教わりました。
『特権的肉体論』に出てくる軽演劇役者ミトキンに哲学者の姿を発見する。
そういうセンスが、自分の中に活きています。
本番は7/30(土)の夜。
チラシができたら、またお知らせします。
6/23(水)虫の脅威②
6/22(火)虫の脅威①
6/19(土)ついに「丘」に行く!
6/16(水)ロンドンに行きます
6/15(火)ポーの小説を読む
6/12(土)明日は本番!
6/11(金)新潟の『少女仮面』!
6/9(水)咄嗟の判断
6/8(火)PCR検査の会場で

6/6(日)向島の人々
6/5(土)誰も乗っていない
6/4(金)ぜんそく考
6/2(水)ついに現れた難題
6/1(火)昨日の劇団活動
5/29(土)失恋うらみ節
『ビニールの城』観劇後の余韻が尾を引いています。
自分の中で『秘密の花園』と『ビニールの城』こそ、
唐十郎の恋愛劇の真骨頂だと思っています。
もちろん、他の作品でも少なからず男女関係が描かれますが、
その純度において、壊れやすい繊細さにおいて、
やっぱりこの二つだと思う。
来週末にもう何回か唐組東京公演が残っていますが、
やはり二幕、ビニールの幕越しに主人公二人が
互いを求め合いながらもついにすれ違ってしまう場面こそ、
全編の白眉であるだけでなく、唐さんが描いてきた
あらゆる同種のシーンの、最高の仕上がりです。
と、ここまで書いてきて、前に唐さんから聞いた
かつての恋愛話を思い出しました。
10代の頃の唐さんはとにかく内気、
後にあれだけのことばが吹き出すことなど想像もできないほど、
寡黙な少年だったそうです。
しかし、一方で、心の内にはいつも様々な妄想が駆け巡っていたようで、
ある時、近所に住んでいた年上の女性を好きになってしまったのだそうです。
しばらく悶々とした後、ついに一念発起した大靍義英少年は、
なけなしの勇気を振り絞って告白を決行。想いを伝えました。
ところが、返ってきた答えはNO。
「よっちゃんには、あたしなんかよりきっと善い人が現れるよ」
そう言われたそうです。
「あの時は刺し違えてやろうかと思った」と唐さんはそのうらみを語りました。
このあたりの唐さんのセンスは、名作短編小説『恋とアマリリス』に明らかです。
ちなみに「善い人」といえば、思い出すのは『盲導犬』。
ヒロイン銀杏の父親が青年タダハルを評して蔑んだことばがこれなのですが、
あれには、唐さんの個人的なショックが尾を引いているに違いありません。
5/28(金)もはや天草四郎しか出てこない
5/26(水)ここにあの人がいた!
5/25(火)『ビニールの城』観ました!
5/22(土)『ビニールの城』2題
5/21(金)これでいいのか!-「新劇」まさかの1冊100円以下!
5/19(水)映像を検証する
5/18(火)狐につままれる
↑私の住む保土ヶ谷区には謎めいた公園がある。そこの草むら。
またしても、ワークショップで取り組んでいる
『海の牙-黒髪海峡篇』に気になってしまうエピソードがありました。
それは、ヒロイン・瀬良皿子(せら さらこ)が、
自らの仕事がうまくいっていないことをこぼすくだり。
彼女はパンマ→パンパンの按摩→つまり娼婦なのですが、
変な客にオーダーされて困っている、そういう話をします。
というのも、電話で呼ばれて待ち合わせの場所に行くと、
声はするのに男は姿を現さない。
そして、その声の出元が移動するというのです。
あまりに照れ屋なのか、引っ込み思案なのか、
それとも単にからかわれているのか、そういうことを愚痴こぼす。
この場面に来ると、私の胸にあるエピソードが去来します。
またしても、前に唐さんに直接聞いた話。
唐さんは中学生の頃、好きな女の子がいたそうです。
中学時代の唐さんといえば、いまだ本名の大靍義英(おおつる よしひで)少年、
これぞ内気の最たるもので、口数の少ない内向的な男子だったそうです。
それなのに、内に想いを秘めた当の相手から、呼び出しがかかった。
勢い込んで唐さんはその場所、校舎裏の原っぱに駆けつける。
「おおつるでございまーす!」
上気した唐さんは、後年、大いなる武器とするテノールで乗り込んだそうです。
が、草ふかいその場所に相手の姿はない。しかし、気配はするそうなのです。
そしてその方向に唐さんが進もうとすると、ササっと何者かが、
草むらから草むらを移動して、何度もトライしたけれどついに追いつかなかった・・・。
そう唐さんはおっしゃっていました。
・・・・・・。
どこまでが現実か分からない話ですが、唐さんの目は真剣でした。
「あれはキツネの仕業だったのではないか」とも。
完全に妄想か、現実だったとしても同級生にからかわれたのではないか、
私にはそんな考えもよぎりましたが、唐さんの夢を壊すようで、
それはついに言い出せませんでした。
だから、きっと瀬良皿子のあのせりふは、作者の実体験なのです。
5/15(土)時には子育てを語る
5/14(金)恐怖!手の甲を迷いなく刺す!
5/12(水)大河ドラマ『太平記』に見る名和四郎の祖先
5/10(月)三日会わざれば刮目して見よ
5/8(土)偉大なり、睡眠!
5/7(金)自らの勝負弱さについて
5/5(水祝)声こそが力
5/4(祝火)テツヤとの朝
5/3(祝月)前を向いてしゃべろう
5/1(土)初めて観た!〜『おちょこの傘持つメリーポピンズ』
4/30(金)必殺のコピー&ペースト
4/28(水)何が役に立つのか分からない
4/27(火)石鹸箱の残り湯、その衝撃
4/24(土)観音崎にて
4/23(金)ネイティブ・スピーカーへの道
4/21(水)驚異のロングストレート
↑これが龍眼肉(スゴい名前!)の花。ハチミツとれるらしいので、
探して舐めてみたいです。
今日は『海の牙-黒髪海峡篇』のワークショップでした。
昨日のゼミログに書いたような事情で、
最近の私の頭の中を1973年が支配しています。
正確にいうと、その時代に唐さんが何を見ただろうと考え、
感じ取りたい。そういう想像が渦を巻くのです。
『ベンガルの虎』は映画『ビルマの竪琴』のパロディから始まります。
引き揚げていく旧日本軍の男たちによって『はにゅうの宿』が合唱され、
名ぜりふ「水島、いっしょに日本へ帰ろう!」が連呼されます。
あの映画には、主人公の水島上等兵が日本に帰らず、
ビルマに残ることを決意する場面があります。
文字通り死屍累々、そこここに野ざらしになって転がる同胞の遺体を
目の当たりにし、彼は後の人生を弔いに捧げようと決意する。
実際のその土地がどうだったか。
ネットで画像検索すると多くの写真が出てきます。
戦闘によってではなく、飢餓と病気の果てに無念の塊となって
転がる人々。まさに「白骨街道」と呼ばれるにふさわしい光景です。
そこにとどまった水島の実感を、唐さんはこんなせりふに託しています。
「昭和三十二年九月十日、晴れ。おまえは見たことがないだろう?
竜眼肉の花を。ベンガル湾の陽光を。
余りに明るすぎて目の前が暗いこの白骨街道。
ここでは、真昼だというのに黒い大きなこうもり傘が丘を包んでいる。
俺が一歩ふみこむと、そのこうもり傘は大きくひらいてこなごなになる。
分るかいカンナ。それは死体にむらがるカラスの群れ。
夜の街道にぶったおれて俺は昨日夢を見た。
俺の顔にしなだれかかるおまえの黒髪すだれ。
気がつくと月もない夜だった。この暗闇の中で、今、俺は白骨を枕にしている。」
じりじりと照りつける太陽のもとで、骨はいよいよ白く、
夜になれば闇の中にぼんやりと浮かぶ光景が描写されています。
最近、、よく読んでいる白川静さんの『字統』によれば、
「白」という文字はシャレコウベのかたちに由来し、
「道」という漢字は、古代王朝「殷」に暮らす人々が異民族の首を
街道の脇に並べて魔除けとしたところに基づいているのだそうです。
とすれば、「白骨街道」こそ道の中の道であり、
そこに散らばる白が、さらに鮮やかさを増すように思います。
唐さんはきっと持ち前の古代人的な感覚をして、
そういうイメージを捉えたに違いない。
二幕終盤、競輪選手となった水島上等兵が進む白骨街道の、
あの異様なまでの直線、真っ直ぐさに、道の中の道という迫力を感じます。
4/20(火)想像力の源〜『ベンガルの虎』から『海の牙 黒髪海峡篇』へ
4/19(月)『ベンガルの虎』終幕へ
4/17(土)菊池の船出
4/16(金)イソギンチャクの宮殿
4/14(水)何でも訊いてくれ!
4/13(火)どちらが好きか? 春と秋
4/10(土)誰かが割りを食っている
4/8(木)通いすぎた唐さん
4/7(水)わが友、オガテツ
4/6(火)あんまに会いたい
4/5(月)まごころ天に通ず
4/3(土)唐十郎の頭の中に"潜入"する-『海の牙-黒髪海峡篇』WS
4/2(金)唐十郎に教わった"女"と"犬"
3/27(日)大人のチカラ
3/26(金)追いつめられた人は・・・
バテレン 伝次が伝次でないならば、床屋の藪野は何者だ。
あたしはそれから、風呂屋跡の横に建った、あの床屋に行ってみた。
しかしあけび、お前が働いていた床屋は、もうどこにもありゃしなかった。
そこには只、竹藪があるばかり。区役所に行って調べてみれば、
床屋の藪野の一族は、去年の暮れに死に絶えて、
そのヨイヨイのぶらさげている骨壺が、藪野の御霊さ。
その一族は、その一族は、よく聞けよ、蛇年なのをいいことに、
空き家の床屋に居座っていただけなんだ!
そうだろ、内縁、お前の見たことを言ってやれ!
内縁 (尻ごみして)こわいよお!
バテレン 尻ごみせずに言ってやれ、こいつらは、一体何者なのか!?
伝次と名乗る男 (緊張のタガがはずれて、急に踊り出す)
♪ワーイ ワーイ もういっぱい
渡辺のジュースの素だよ もういっぱい
俺たちゃ昔、死人に触った。世に出ることの商いが、死人に触ることだった・・・3/24(水)心をわしづかみにするせりふ
お市 あたしにひっぱり出されるのさ。この穴を通ってな。
カンナ この婆さん、ムチャクチャ云いよんねん。あたしがこの穴をぬけられると思ってんの?
お市 人間はみな、この位の穴から出てきたんじゃ。
カンナ だって、あたし大人よ。
お市 どうしてそんなに大きくなったんだ、このメスネコが!
カンナ 人間はみな、大きくなってゆくのよ。
お市 いかんっ。
カンナ いかんと云ってもいかんのじゃ。
お市 たのむ。わしにひきずり出されてくれ。わしは産婆じゃ。
3/23(火)とんかつのてんどん
3/22(月)『蛇姫様 -我が心の奈蛇』を読む
3/20(土)わたしの記念日
3/19(金)ボクシングとプロレスの違い
3/17(水)『盲導犬』と『蛇姫様-我が心の奈蛇』
3/15(月)謎めいた隣人

明日(3/16)は2020年度「芝居の大学」の最終回です。
唐ゼミ☆が長く居ついた横浜国大を撤退し、
https://www.kaat.jp/d/shibaino_daigaku202102
3/12(金)4月以降のワークショップは『海の牙-黒髪海峡篇』
♪いたずら男が「ダン」とやりゃ
尻をモジモジ彼女が「トン」
「ダン」と「トン」の調子が合って
眉にシワよせ 目元ほんのり ダダダンダン
舌を鳴らしてトンタンタン
3/9(水)旧友にあう
3/9(火)横須賀の先のエメラルドボア
今日は朝から横須賀に行って来ました。
写真は「汐入」という駅のホーム。
横須賀と唐作品といえば、
ちょっと前にワークショップを展開していた
『唐版 滝の白糸』が思い浮かびます。
謎めいたゴーストタウンを舞台に物語がスタートする10年前、
青年「アリダ」が誘拐犯「銀メガネ」にさらわれて
渡り歩いた場所こそ、この横須賀の港湾部でした。
銀メガネ そうとも、俺だよ。
一緒にエメラルド・ボアを見に行ったっけ、
帰りに横須賀のドックもぶらついた。
という銀メガネのせりふの一節により、それは語られます。
下町(唐さんの場合は十中八九、台東区界隈)で誘拐され、
「エメラルド・ボア(南米に生息するヘビ)」を見に行き、
帰りに横須賀のドックに寄ったらしい。
この"帰り"という部分が私には難題でした。
唐さんにとって"動物園"といえば、
圧倒的に上野動物園でしょうが、台東区を出発点にした二人が
上野動物園に寄り、そこから横須賀を目指したとすれば、
それは"帰りに寄った"とは言い難い。
地理関係的に、東京から見て横須賀のさらに向こう側、
三浦半島の突端にエメラルド・ボアが見られる場所がなければ
ならないのですが、三浦市にそんな施設は見当たらない。
あるのは京急油壺マリンパーク。
ところがあれは、イルカショーなんかも観られる水族館なのです。
ちなみに「エメラルド・ボア」は、
いつかこのゼミログにも書いたように、
静岡県の日本平動物園と名古屋の東山動物園にいます。
横須賀市に来るたびに気になります。
果たして少年アリダと銀メガネはどこでエメラルドボアを見、
"帰りに"横須賀に寄ってスクリューを眺めることができたのか。
唐作品はもっと自由に読むものだ、という意見がある一方、
こんなことが気になり続けて、ここ10年を過ごしています。
3/8(月)松本くんがやってきた!
3/6(土)ブラームス 弦楽六重奏 第1番
3/3(水)必殺の年度末
https://www.youtube.com/watch?v=qeIyUrk1YUI&feature=youtu.be
3/1(月)は若葉町ウォーフでテツヤとの配信。
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3w5m7WxjgICVrwPy5jOyYqlL3Pq6qHUu5toMulPbCMpStrsubFegaks8M&v=AzJcxtrmrys&feature=youtu.be
3/1(月)オレたちの『白い巨塔』
その中で、ひょんなことから、中村伸郎さんの話になりました。
2/27(土)道に倒れていた人②
2/26(金)道に倒れていた人①
2/22(月)本番前日の恒例行事
2/20(土)少年役への熱血指導
2/19(金)NHK『アナザーストーリーズ』を観て
2/17(水)酒が飲めたら・・・
2/14(日)朴淵成との仕事
「わかったよ」と言いました。それから彼は、私がメールで送った
こんな作業を重ねながら、ハングル版の『盲導犬(メンドギョン)』は完成。
私は対訳台本にを用意し、ハングルにはカタカナを振って稽古に臨みました。
韓国語を解さない私には、ヨンソン訳の威力を見極める力はありません。
が、当のヨンソン自体は、自らの仕事にものすごい達成感を覚えたらしく、
2/13(土)朴淵成の誕生日
2/12(金)時代劇がいい?
2/10(水)わが家のスメアゴル
2/8(月)コインロッカーと機動隊
2/6(土)リン・チン・リンの行方
2/5(金)ほんもののイヌ
2/2(火)明日から『盲導犬』WSだ!
2/1(月)不条理ではない!
1/30(土)テントの色は「青」
1/29(金)隣のワークショップに参戦!
1/26(火)目下、劇団員を募集中!
1/25(月)劇と子育て②
1/24(日)劇と子育て
1/23(土)雪のテント公演
1/22(金)雪子とローラ
1/20(水)『少女都市からの呼び声』はじまる!
1/19(火)テアトロの表紙に
1/18(月)今年度、最後の講義
1/15(金)ワークショップレポート(中野)
1/12(火)『セールスマンの死』と唐さん
小野碩さんが一役買っている事は間違いありません。
1/11(祝月)本日は劇団集合。あと、新資料について
1/9(土)電車と唐さん⑥
1/8(金)電車と唐さん⑤
↑引用のせりふの場面(2004.4.25)。
唐さんから「山手線」ということばを際立たせるべし、
と指導されたことも。
電車と唐さんにまつわるエピソードの第5弾です。
私の大好きな初期作品『ジョン・シルバー』の中で、
女房・小春が夫・シルバーの家出を語る際、
山手線が重要な役割を果たします。
それは、こんなせりふによく表れている。
小春 山手線の長い灰色のホームを先へ先へ、
ずっとむこうへむこうへ、つんのめるようにして行っちゃった。
正確には、小春はシルバーの家出を見たわけではありません。
(目の前で出奔されたら、普通、止めますから)
ですから、これは小春の妄想です。
彼女は、シルバーと山手線を利用するたび、
シルバーが海の方(上野を起点として品川の方角、つまり南)を
見つめていたのが気になって仕方なかった。
だからこそ、きっとこうであったに違いないと決めつけて、
先ほどのせりふを叫ぶ。
芝居本編の中で、小春が九十九里浜にシルバーを
探しにくるくだりがありますから、南方に海ありという
位置関係を裏付ける証拠になります。
ところが、私たちが学生時代にこの『ジョン・シルバー』を上演した際、
これにツッコミを入れた人がいた。
当時の唐十郎教授の同僚で、数学者の根上生也先生です。
根上先生は芝居を観た後、実に数学者らしい正確さで
「唐さん、海を目指すなら山手線でなく京浜東北線ですよ」と仰った。
その後、すっかり酔っぱらった唐さんは帰り道に
「あいつは文学がわかっていない!」と叫ぶ始末。
それでいて、教授時代の唐さんは私たちが公演する時には
いつも、「根上さん、来ないかな?」と気にしていました。
そんな指摘をして勝ち誇る根上先生の幼なごころは
結局は唐さんご自身の世界と一脈通じるところがあり、
ちょっと好きなようでもあったのです。
あるいは、十代のころ、
お父様から医者になることを嘱望されながら、
理数系への苦手意識からそれを断念した唐さんにとって、
"数学者"という存在に、畏敬の念や面白さがあったのかも知れません。
学課の忘年会の時など、親しげに喋ったり、
それでいてやっぱり子供っぽい意地を張り合ったり、
私から見て、お二人はとても仲良く感じられました。
1/5(水)電車と唐さん④
おじさん
ぼくの血を待つ間もなく死んでいった一鉄道員の―
あの朝は雨でしたね
2リットルの血をにぎりながら病院の階段をかけ上っていった時
ぼくは、あなたがもうあのベッドにはいないのを知っていたんだぜ
ベンチャーズの好きだったおじさん
あの夜更け
病院を抜け出して、遠い町のどさ廻りの一座にあなたは加わっていた、という
ここから浮かび上がってくるのは、
かつての希望や野心については黙して語らず、
淡々と働いて死んでいったおじさんの姿です。
おじさんは、ほんとうは役者になりたかった。
翻って振り返るに、彼がベンチャーズに差し向ける視線には、
単なるファンやテレビ視聴者を越えた、
もう一つ別の熱っぽさがあったように思えます。
実際の耕三おじさんがどんな方だったかを別にして、
駆け出しの唐さんが身近な存在をこのように書き上げ、
このまま役者として大成せずに同じようになってしまうかも知れない
自分の不安、同時に、夢破れた人間への愛着を示していることは、
私にはすごく重要に思える。
私たちが初めて『ジョン・シルバー』に挑戦した20代初めの頃、
わけも分からずにこのくだりを上演していましたが、
同じような年齢で、すでに唐さんには、
黙々と働いて生活している人間への共感や慈しみがあったわけです。
「若い頃の方が意識が老いていたなあ」
いつだったか、唐さんがそう私に話してくださったことがありましたが、
鉄道員だったおじさんを偲んで書かれたこのエピグラフを思い出す時、
若くしてすでに"人間"を識っていた唐さんに驚かされます。
1/4(月)今日は仕事はじめ
2021/1/1(金)年始と唐さん
12/31(金)2020年を振り返る〈後半〉
7月は、翌8月に本格化する稽古に向けての最後の準備。
12/29(火)2020年を振り返る〈前半〉
12/26(土)新たなる発見
12/25(金)電車と唐さん③
12/24(木)電車と唐さん②
12/22(火)電車と唐さん①
12/21(月)祠(ほこら)の時間⑩
今、書いているトピックについて調べものをして欲しい。
今日で10回目なので、一区切りつけようと思います。
12/19(土)私の祠の時間〜また一つ資料が届く
12/18(金)祠(ほこら)の時間⑨
12/17(木)祠(ほこら)の時間⑧
12/15(火)祠(ほこら)の時間⑦
12/14(月)祠(ほこら)の時間⑥
12/12(土)祠(ほこら)の時間⑤
12/10(木)閑話休題〜くらしのなかの創作
12/8(火)祠(ほこら)の時間④
12/7(月)祠(ほこら)の時間③
12/5(土)祠(ほこら)の時間②
12/4(金)祠(ほこら)の時間①
12/3(木)まったく歯が立たない!
12/1(火)熊野の力
11/30(月)過去の上演との比較について
11/29(日)ワークショップについて
11/28(土)米澤剛志との対話
11/27(金)ぜんそく界のヒーロー
11/26(木)次にするべきことは・・・
11/25(水)ハンディラボでの後片付け

11/24(火)現場入り16日目〜完全撤収
11/23(祝月)現場入り15日目〜バラシとお別れの準備


11/22(日)現場入り14日目〜『唐版 風の又三郎』千秋楽

11/21(土)現場入り13日目〜公演5回目
11/20(金)現場入り12日目〜公演4回目
11/19(木)現場入り11日目〜公演3回目

11/18(水)現場入り10日目〜公演2回目
11/17(火)現場入り9日目〜本番初日
『犬狼都市』、ついに観に行かれなさそうですが、
11/16(月)現場入り8日目〜ゲネプロ
11/15(日)現場入り7日目〜最終調整日
11/14(土)現場入り6日目〜3幕場当たり
11/13(金)現場入り5日目〜1-2幕 場当たり稽古
11/12(木)現場入り4日目〜寒さに揉まれる
11/11(水)現場入り3日目〜ご支援への御礼
11/9(月)新宿中央公園 現場入り

11/8(日)現場入り前日、トラック積み込み
11/7(土)荷づくり整う
11/6(金)道具づくり追い込み
11/4(木)稽古を打ち上げる
11/3(祝火)2度目の全幕通し稽古
11/2(月)稽古休み
10/31(土)全幕を通し稽古を終える
10/30(金)3幕を立て直す
10/29(木)集団シーンに行き詰まる
10/27(火)通し稽古〜まずは1幕から
10/26(月)仕上げは川崎で
10/24(土)横須賀と『唐版 滝の白糸』
10/23(金)オレたちの役づくり
10/22(木)唐さんの原点回帰
10/20(火)わたしたちはあの紅テントから生まれてきた
10/19(月)『さすらいのジェニー』を観てきた!
10/17(土)ここにも唐ゼミ☆メンバーが!

↑一番右が鈴木能雄さん。嬉々としてオカマに扮する!
今日、私が留守中のハンディラボにお客さんをお迎えしました。
10/16(金)舞い上がる鳥の羽
10/15(木)音響台本をつくる
10/13(火)今後のワークショップについて

10/12(月)背筋が伸びる
10/10(土)台風の記憶⑩〜2014年10月『木馬の鼻』大阪公演


10/9(金)台風の記憶⑨〜2014年10月『木馬の鼻』大阪公演
↑大阪入りするとすぐ、公演を誘致して下さった「犯罪友の会」の
武田一度さんを表敬訪問。恐るべき仕込みの規模に皆、ビックリ。
今度の台風は、どうやら大阪直撃らしい。
確かあの時、大阪公演のゲネプロは、
椿昇さんとやなぎみわさんという豪華ゲストを迎えて行われ、
やる気充分の私たちは、学生たちによる前座パフォーマンス〜
トラックが来襲しての劇場設営〜『木馬の鼻』本番と、
フルコースをやり切りました。
結果、お二人はよろこんでくれ、特に椿さんには
「ルーマニアあたりでやっている村芝居みたいだな!」
と褒められた記憶があります。(そう。これは褒め言葉!)
そして初日を迎える頃には、直撃は確定的に。
こうなると思い出すのは、
同じ『木馬の鼻』が中止になった2012年9年30日、足柄山の上。
あの、本来だったら公演しているはずの時刻に、
宿舎でぬくぬくと過ごしている時間の気持ち悪さ。
ちょっと補足すると、
この感情は、私たち劇団の運営状態が原因なんだと思います。
年間300ステージも公演がある売れっ子カンパニーであれば、
300分の1を中止にするに過ぎないし(それでも苦渋でしょうが)
お客さんに対しても代替が効くというものです。
しかし、私たちは、そこまでの公演回数は無し、
その頃はトータルでもせいぜい20〜30回というところ、
いきおい、一回一回が"魂の叫び"になるわけです。
だからこそ、あんな台風でも、
何か出来なかったか? もっと粘れなかったか?
そうどこまでも思ってしまうし、公演を中止にした事実を前に
自分に対して演劇人たるところを証明できず、狼狽えてしまう。
同じ『木馬の鼻』。同じ千秋楽。かくなる上は、
必ずや公演をやり遂げて二年前のトラウマを乗り越えるべし。
そう思いました。
それに今回の場合は、好条件が2つ
(1)決行・中止の判断が現場に委ねられている
この時も主催は唐ゼミ☆でなく、文化庁と横浜国大でしたが、
基本的に判断は現場に任されていました。
※もちろん、事故は厳禁!
(2)テント演劇ではなく、野外劇である
テント劇場の幕は、風が大敵。しかし、野外劇であれば勝算がある。
※絶対に、事故は厳禁!
そのようなわけで、初日を終えた夜から、
私はどのような公演であれば千秋楽の決行が可能か、
もっとも過酷な状況を想定しつつ、
上演が成立する最小単位を構想し始めました。
その時に思い付いたのは、小池一夫先生の漫画『子連れ狼』。
私の大好きなあの作品の終盤の光景でした。
拝一刀と大五郎、宿敵・柳生烈堂は江戸の外れの河原で対峙する。
彼らの最終決戦を盛り上げるかのように、天気は大荒れ。
すると、将軍をはじめ大名、配下の武士たちが屋敷を飛び出し
本来は"私闘"に立ち会うはずもない人々が現場に集まる。
しかし、闘いのあまりの凄絶さに彼らは近付くこともできず、
まして制止もできず、ただ、鎧を外して(武士としての最高の礼)
両者の闘いを見守る。
↑一番下のコマを見よ。
力尽きた一刀の傍らで、烈堂は大五郎に刺され立ったまま絶命。
こんな具合です。
よし、あれをやろう! そう私は思いました。
幸い、扇町公園は広い。
周囲に関テレや地下鉄の入り口、公衆トイレなどの建造物もある。
だから、私たちは公園の真ん中、
できるだけどこからもよく見える場所で完全燃焼し、
お客さんには『子連れ狼』の大名や武士たちのように、
安全な周囲からその姿を目に焼き付けてもらえばいい。
そう考えました。
もちろん。
すべてのせりふが怒鳴り声になっても、
雨風を超えて唐さんの言葉と物語を届ける。
一人でもお客さんがきたら、やる。
これだけのことを考えてしまうと、気持ちは実に晴れやか。
あとは現実にやってくる台風の強さを見極めながら、
中間にある落としどころを劇団員たちと探るのみ。
どうせ千秋楽だし、必ずやる!
公演2日目のお昼。
その日の晩の公演に備えながら、
私たちは嬉々として翌日の仕込みを始めていました。
〜つづく〜
10/8(木)台風の記憶⑧〜2014年10月『木馬の鼻』大阪公演
10/3(土)台風の記憶⑦〜2013年7月『夜叉綺想』浅草公演
10/2(金)台風の記憶⑥〜2012年9月『木馬の鼻』足柄公演
10/1(木)台風の記憶⑤〜2012年9月『木馬の鼻』足柄公演
9/29(火)台風の記憶④〜2012年6月『木馬の鼻』浅草花やしき
9/28(月)台風の記憶③〜2007年7月『鐵假面』池袋公演
9/26(土)閑話休題〜明日の『下谷万年町物語』WS
9/25(金)台風の記憶②〜2004年11月 唐組『眠りオルゴール』
9/24(木)台風の記憶①〜2004年11月 唐組『眠りオルゴール』
9/22(祝火)隠語と小道具
9/20(日)ハンディラボでの一日
9/19(土)安保さんに捧ぐ⑥
9/18(金)安保さんに捧ぐ⑤
9/17(木)安保さんに捧ぐ④
9/16(水)安保さんに捧ぐ③
9/15(火)安保さんに捧ぐ②
9/14(月)安保さんに捧ぐ①
9/12(土)若葉町での稽古と明日のワークショップ
9/11(金)講義の時間
9/10(木)残暑礼讃!!!
9/8(火)優しき新宿へ
9/6(日)WSいろいろ〜さまざまな友人たちと
9/5(土)チケット売り出し日でした!
9/4(金)飛ぶぜ!!! チケット発売前夜
9/3(木)キッチンジローに行こう!
9/1(火)よみがえる宿題
8/31(月)昨晩はWS通し稽古、今朝は若葉町チャンネル
8/29(土)新たな番組に参加します!
8/28(金)今後のワークショップ・メニュー
8/27(木)伴奏の面白さ
8/25(火)絵画教室にて
8/24(月)2幕での発見!
8/22(土)4年ぶりの新宿公演!
8/21(金)笠は善光寺出身
8/20(木)天丼 → 築地 → 横浜
8/18(火)9月以降のワークショップ
8/17(月)稽古とワークショップと
8/15(土)ありがたい道具の数々
8/14(金)まるで個人を尊重するヨーロッパ人のように
8/13(木)さして長くないのではないか
8/11(火)音響・新木の重要性
8/10(祝月)突然のことだが突然のことではない
8/8(土)動画を撮影する〜ワークショップの効能
8/7(金)2幕の合い間に
8/5(水)稽古前の準備
8/4(火)新しい稽古のはじまり
8/3(月)スーツの思い出
7/31(金)ワークショップ第1部 完
7/30(木)ど根性トカゲ
7/28(火)稽古の8月を前に
7/27(月)迫りくる高音域
7/25(土)パンプルムスの頃②
7/24(祝金)パンプルムスの頃①
7/22(水)CMの情報に感謝
7/21(火)『下谷万年町物語』を2回もやったのは
7/20(月)ワークショップ続けます
7/18(土)「♪即・・・」というCMソングを知りませんか?
7/17(金)「ふんどし」の可能性
7/16(木)可哀想な春日野
7/14(火)明後日のWSは劇中歌の連続
7/13(月)劇中歌の伴奏が完成!
7/11(土)恋はルネッサンスの嵐なのに
7/10(金)ついに10万キロ突破
7/9(木)横川のあまじょりご
7/7(火)音楽を探しています
7/6(月)暗雲よ来い!
7/4(土)お習字の時間
7/3(金)週明けにラジオに出ます
昨晩はワークショップでした。
10人の方が参加してくださり、21:00までの予定を30分近く延長してやりました。
『唐版 風の又三郎』を極限まで単純化するとどうなるか、
皆さんと一緒に台本の超重要部分のみを抜き出し、声に出して読みました。
皆さんが個々に台本を読まれる際に、これは必ず役に立つはずです。
唐さんの台本は、寄り道や脱線部分にパワーがあるのが面白い。
謎めいた部分や唐突な固有名詞も多く、読む人は迷子になりがちです。
そんな時、最短ルートを心得ておけば頼りになると思うのです。
これは、私たちのように実際に劇を作る者にとっても重要なことで、
部分々々を作っていると、各所の愉しさや困難にかかりきりになり、
どうしても視野が狭くなりがちです。だから大局観が大切なのです。
このような感じで、劇団の稽古もワークショップも全く同じノリで臨んでいます。
ですから、ひと仕事終わったあとは高揚感でいっぱいになる。
家に帰ってもなかなか寝つかれません。
ところで、週明けにラジオに出ることになりました。
7/6(月)14:10〜14:55に「渋谷のラジオ」でやっている
「渋谷のかきもの」というコーナーです。
去年の『ジョン・シルバー三本連続上演』を観に来てくださり、
ワークショップにも何度かご参加いただいた
パーソナリティーの華恵さんに誘っていただきました。
なんでも良いから「かきもの(書き物)」を2点、
曲を2曲というリクエストがありましたので、
早速、本棚を眺めたり、いま準備している『唐版 風の又三郎』からの
連想で「これだ!」というものを選びました。
「書き物」の中には、もちろん唐さんが書いてくださった言葉を
取り上げますが、ひとつは20年近く前のもので、
改めて、こちらが駆り立てられるようなものです。
良かったら聴いてみてください。
7/2(木)じめじめした陽気について
6/30(火)浅草での付き合い
6/29(月)浅草で公演していた頃
こういう習慣も、この時に初めて教わったのです。
6/27(土)稽古の計画を組む
6/26(金)"淫腐"を追いかけてみた結果
6/25(木)わたしの好きな名前
6/23(火)新宿映画観賞
6/22(月)子どもがやって来た!
6/20(土)リンガーハットの衝撃
6/18(木)本日のワークショップ

6/16(火)重村と熊野の対話
6/15(月)唐さんに聞いた若き日の土方さん
6/13(土)アドリブのようで確かに書かれているせりふ
6/12(金)昨晩の総括
6/11(木)イトーヨーカドー長野店
6/9(火)火曜日といえば
6/8(月)トラックに告ぐ
6/6(土)初めての人たちと
6/5(金)名古屋の思い出
6/3(水)『唐版 風の又三郎』と『ガラスの少尉』
6/2(火)すべてカーステレオのおかげ
6/1(月)遠方からの来訪者
5/30(土)引き算して、次に足し算
5/29(金)驚きのコストパフォーマンス
5/28(木)ミラクル・レフティ
↑このおばあさんも"左利き"ですね。どっちが被害者かわからない絵。
一昨日は即興で出演したライブ配信の話題でしたが、
今日はまた、右手のケガの話です。
ここ2日ばかり、上手い躱し方を身に付けたのか。
痛みがそれほど気にならなりました。
極力、左手ばかり使うように工夫しています。
これがまた何だか自分が左利きになったような気がして、悪くない。
"左利き"への憧れが、自分にはあります。
私は父母姉との4人家族で、全員が右利きの血液型A型という
典型的な日本人家庭で生まれ育ちました。
ですから、幼い頃から私には特別そうに見える左利きへの憧れがある。
この憧れ自体が極めて右利き的だと自覚しながらも、
やっぱり素敵だと思ってしまいます。
「わたしの彼は左利き」だからこそ歌になるのですし、
これが右利きではサマになりません。
中学校時代に流行ったスーパーファミコンの『ロマンシング・サガ』には
「レフトハンドソード」という最強の武器まで登場。
まさに左選ばれし者のみが使いこなすことができる。
週刊少年サンデーで連載されていた野球マンガ『MAJOR』では、
中学時代まで右投げだった主人公が投げ込みにより肩を壊し、
血の滲むような努力の果てに左投げを体得、
球速160キロ、しかもジャイロボールを投げる復活を遂げます。
この特別感、まさに"レフティ"に漂う神秘のなせる術と言えましょう。
唐さんの中で、"左利き"に注目した演目といえば
ズバリ2001年春に初演された『闇の左手』です。
ヒロインの名前が実にふるっていて、「ギッチョ」という。
自らが製作した義手を自殺志願の人々に貸し出し、
リストカットの代行をさせるという哀しい商売をしている職人です。
別に、"左巻き"に注目したものもあります。
ホラ、頭のつむじが左巻きだと"天才"とか云うじゃないですか。
2008年春初演の『夕坂童子』の劇中歌には"左巻き"に引っ掛けて
小道具の「アカガオ」に向けて唄うこんな歌詞が出てきます。
「時の針にさからいながら いつも左に巻いていく
そのつるは俺の櫂 だけど俺にもわからない......」
こうして並べてみると、唐さんが"左利き"や"左巻き"に託すものは、
単に変わっている、才気に優れていることではなくて、どこか不器用で、
ちょっと普通の人たちからはこぼれ落ちるような存在であることもわかります。
それでも、自分は断然憧れるし、だんだんと即席の左利きを楽しんでいます。
回復の兆しも見えましたから、ケガの話はこれでおしまい。
今日は良いワークショップが出来ましたから、また報告します。
5/26(火)今夜は即興で!
今日は即興で、若葉町WHARFの配信に参加してきました。
毎週火曜の19:00から行われるこの配信が始まったのが2週間前。
これまでは、レギュラーである
マコト(佐藤信さん)とテツヤ(岡島哲也さん)のコンビでお送りして
きたそうですが、突然にお声掛かりがあったので行きました。
マコトさんからは、昨今の演劇人の陳情についての所感や
「COVID-19」が世界共通問題として共有されていることの特殊性、
「新型コロナウィルス」でなくちゃんと名前で呼んでやろうぜ、
という問題提起があり、
昔「演劇を殺すな」と言ったけど、演劇は死なないよね、
というお話がありました。
あとは、オンラインで一人芝居の稽古やアカデミーの講座も
されているらしく、その面白さについて話し合いました。
テツヤさんとは、これは放送外だったのですが、
志村けんさんの話をしました。
テツヤさんこそ、ここ14年公演されてきた『志村魂』の
スタッフをされてきた方ですから、
今年、15周年の準備が着々とされていたことを伺いました。
実際に、私はテツヤさんのおかげで、
座間のホールで、本物のバカ殿様や変なおじさんを目撃することが
できたのです。
あとは例によって、お互いの接してきた唐さんの話をして、終了。
帰りがけ、
「やっぱり3人だと盛り上がるからどんどんゲストを送り込んでくれ」
と言われました。
我こそはと思う人がいたら私に連絡ください。推薦します!
5/25(月)痛みの元を取る
5/23(土)痛いけど気持ちいい
5/22(金)言えやしないこと
5/21(木)ワークショップの準備中
5/19(火)上野にある地獄
5/18(月)唐ゼミ☆奇跡の一枚
5/16(土)熊野には頭が上がらない②
↑『蛇姫様-我が心の奈蛇』のカーテンコール。車のことは乗り越えたあと。
(写真:伏見行介)
銀座三丁目〜浅草花やしきの激走で熊野にかなり世話になった話のつづき。
もはや、この車は一度うごき出したら止まれない。
どうにかして走り続けなければ。
10km/h以下にスピードを落とせば強制的にエンストして10分は動けない。
例えば、首都高上野線の入谷出口付近で停まってしまった場合、
完全にこの場所を塞いで後続車が出られない状態になってしまう。
深夜で車が少ないとはいえ、
さすがに10分も停まればスピードに乗った後続車両が
モリモリと出口付近の下り坂に溜まってしまう。恐怖。
とにかく可能な限り停車しないように走りました。
そのためには、ここではとても書けないような様々な「〇〇無視」を
繰り返さざるを得ない。
その時、周囲をキョロキョロ見回しながら私に警察がいないことを
知らせ続けるのが熊野の役目でした。
首都高はなんとかノンストップ、
入谷出口の目の前の大きな交差点はタイミングを加減して青信号で突破。
そこから右折し、しばらく直進、吉原の手前をさらに右折し
言問通りを渡って花やしきに至るいつもの定番コースを基本に、
即興の右左折も加えて駆け抜けました。
横断歩道に歩行者がいれば、完全に十字路の中で停まってしまいますから。
記憶が朦朧として定かでないところもありますが、
確か3〜4回の停車で車を休ませ休ませ辿り着きました。
停まらぬように、停まらぬように、
本来は停まらなければならないところも停まれないので停まらぬように走る。
その間、熊野は「パトカーいません」「パトカーいません」と連呼し続け、
ようやく到着しました。
翌日も本番を抱えているのに、ずいぶんなことをさせたと思います。
感謝を込め、深夜に唯一空いているお風呂
浅草ロックスの「まつり湯」を奮発しても充分お釣りがくる活躍でした。
熊野がいなければ、ここまで走り切ることはできませんでした。
5/15(金)熊野には頭が上がらない①
5/14(木)「耳」の穴に入る(ピンチヒッター熊野)
5/12(火)おそるべき帰巣本能
5/11(月)尖ったものに気をつけろ!
5/9(土)わたしのお弁当
5/8(金)来週こそ「耳」の穴に入るために
5/7(木)「耳」の中へ
5/5(祝火)しょうぶの日
5/4(祝月)お岩さんと小道具
5/2(土)まるでお岩さんのように
5/1(金)1幕の難問と向き合う日々
4/29(祝水)私のめぐり会い②
4/28(火)私のめぐり会い①
4/27(月)ZOOMで稽古をしてみれば
4/25(土)雨が空から降れば④〜小室等さんのこと
4/24(金)雨が空から降れば③
4/22(木)雨が空から降れば②

4/21(火)明後日のワークショップ
4/20(月)雨が空から降れば①
4/17(金)初めての青テント公演で③
4/15(水)初めての青テント公演で②
4/14(火)初めての青テント公演で①
4/13(月)ある日の現場検証 その②
4/12(日)ある日の現場検証 その①
4/10(金)こんなところにも"帝國"
4/8(水)続・物書きのひそむ場所
4/7(火)物書きのひそむ場所
4/6(月)あの箱は割と簡単に開くらしい
4/5(日)WS会場を「ハンディラボ」に変更します!
4/3(金)大阪の友
4/1(水)『秘密の花園』と志村さん
3/30(月)唐ゼミ☆過去作品研究会
3/29(日)よみがえる雪中行軍
3/28(土)舞台美術と言えば
3/27(金)劇にもいろいろあります
3/25(水)美術の打ち合わせをしました
3/24(火)まだまだチラシを作り続けています
3/22(日)舞台装置が無い!
3/21(土)カンチョウの話をしよう
3/20(祝金)次回WS予告:「夜の男」を追いかけろ!
3/18(水)甦える『忘却篇』②
3/17(火)甦える『忘却篇』①
3/16(月)あの店を発見!
3/15(日)唐さんの最終講義
3/14(土)最後の大物!
3/11(水)それぞれの対応
3/10(火)劇団員と仕事&ワークショップ情報
3/5(木)遠藤さんが亡くなった②
3/4(水)遠藤さんが亡くなった①
3/3(火)当時は歯が立ちませんでした
3/1(日)まさに神出鬼没の興行
2/29(土)唐さんから頂いた交通費で別役実
2/27(木)唐さんとしなかった会話について
2/26(木)「芝居の大学 第2期」と明日のワークショップ
2/24(祝火)横須賀シニア劇団の公演と甦る記憶
2/23(日)予告:第4回ワークショップの内容
2/20(木)開講!「芝居の大学 2019年度」
2/19(水)わたしの新聞配達②
2/17(月)わたしの新聞配達①
2/15(土)電車の話
2/14(金)昨日のワークショップ報告
2/12(水)突然、心を射抜くせりふ
2/11(祝火)天からの授かりもの
2/10(月)人は腸なり
2/8(土)アイディアの源泉
2/7(金)コピーライターとしての唐十郎
2/5(水)空を飛びたい
2/4(火)まさに唐十郎ゼミナール
2/2(日)トク画伯の力作!
1/30(木)台本ができました!
1/29(水)発見した懐かしいもの
1/28(火)深夜に下見を決行!
1/25(土)次回のワークショップ
1/23(木)作者は豹変する
1/22(水)ロケハン、台本づくり、出演交渉、明日のこと
1/21(火)鷹さんに頭が上がらない!
1/20(月)ホントに三週間で!?
1/16(木)『唐版 風の又三郎』を写し終わる
1/13(祝月)レバノンに向かうのはゴーンだけではない
1/12(日)重村インフルエンザ!
1/11(土)三幕に突入!

ニコライ堂といえば、
ここはかつて「赤い呼び屋」と呼ばれた稀代の興行師・神彰が、
その仕事のデビューを飾った「ドン・コサック合唱団」の招聘にあたり、
プロモーションに使った場所です。
ロシア帝国の崩壊によって難民となった兵士たちが結成した合唱団「ドン・コサック」。
彼らは羽田空港に到着するやいなや、まずは御茶ノ水のニコライ堂に立ち寄り、
ここで祈りの合唱を捧げたのだそうです。
この行為は結果的に、ギリシャ聖教の徒たる合唱団の神秘性を高め、
巨大な宣伝につながった。それが、1956年3月24日のこと。
何ともロマンチックな話ではありませんか。
話を戻して、『唐版 風の又三郎』。
年末に代々木の帝国探偵社前からスタートしたドラマは、
二幕に探偵社の中で繰り広げられる夜の学芸会、
幕間の病院を経て、御茶ノ水に行き着きました。
あと数日で、大々円を迎えます。
1/10(金)それぞれに格闘している
1/9(木)米澤に手こずる
1/3(金)今日はあの事件の日
1/2(木)おみくじの話
2020/1/1(水)作者と皆様へのご挨拶
12/31(火)2019年を振り返る
12/30(月)ここから三週間で
12/29(日)今年中に借りを返す
12/28(土)あの人にもたまたま出会ってしまう
12/27(金)たまたま会えてしまう日もある
12/26(木)時には会えない日もある
12/25(水)遅れてはならない!
12/24(火)小屋番列伝③『木馬の鼻』足柄公演
12/22(日)集合日は明日
12/21(土)小屋番列伝②『黒いチューリップ』の続き
12/20(金)小屋番列伝①『黒いチューリップ』
12/19(木)賢治で育ちました
12/18(水)ハンバーグを見て思い出すこと
12/17(火)さらに「無意味」の世界
12/16(月)狂わせたいの
12/14(土)気を付けなければならないこと
12/13(金)得は三文どころではない


12/11(水)ジュリーがジュリ子になっちゃうよ
12/10(火)北千住の教え
12/9(月)Gメンが吠える!
12/7(土)「落とし物」の世界
12/6(金)年賀状の入稿迫る!
12/5(木)九州でやっている!
12/4(火)『外套』と宝物②
12/3(火)『外套』と宝物①
12/2(月)ヤフオクにあれが登場!
11/30(土)ゲンを担ぎたい日もある
11/29(金)勝負は「池の蓋(ふた)」②
11/28(木)勝負は「池の蓋(ふた)」①
11/27(水)長屋の住人は長屋で集める
11/26(火)韓流ミュージカルからベトナム現代演劇へ
11/25(月)長屋で暮らしてくれた人
11/22(金)音二郎と唐十郎〜その③
11/21(木)音二郎と唐十郎〜その②
11/20(火)56年前の音源から
11/19(火)プロ中のプロ
11/15(金)はじまりの『下谷万年町物語』
11/16(土)薬物の嵐
11/14(木)浅草に通い始めた頃
11/13(水)神谷バーのバーテンさん
11/12(火)もしも唐ゼミ☆が上演したら
11/11(月) 歌も教わってきました
今日は劇団集合!
『少女仮面』に話を戻そう。
具体的すぎる例
下町の塔
「能」に学ぶ
水は血よりも濃い
鈴木さんは『少女仮面』をどう思ったのか。
林麻子に任せよう
劇団員と『少女仮面』〜『吸血姫』
『少女仮面』と『続ジョン・シルバー』
唐さんは宝塚を観ていたのだろうか?
去年から劇団に入ってきた岡村夏希は、
去年から劇団に入ってきた岡村夏希は、
『ジョン・シルバー』三部作で受付を取り仕切っていた女子です。
特に『あれからのジョン・シルバー』の時には出演もしていたので、
自分のいない受付を埋めるために、何人もの友達をお手伝いに呼んでくれてもいました。
私たちだけでなく、多くの信頼を勝ち得る人格者です。
彼女は、かねてより宝塚のファンだそうで、
昼間に私と津内口が働いている神奈川芸術劇場に宝塚公演がやってくると、逃さず観に来ます。
しかも、実家から家族まで呼び寄せて。
そういうわけで、彼女は宝塚事情に精通していますから、
私が歌劇団OGが出演している舞台を観に行くときには、
その方がどれだけ凄いのか、聴いてから行きます。
知恵袋です。
「あの方は"伝説"」「あの方は"トップ・オブ・トップ"」「在団時から『情熱大陸』に取り上げられた、あの方」といった話ぶりです。
そういう時、とりわけ彼女は熱っぽく語ります。
宝塚と唐さんとは、ちょっと関係があるように感じます。
何せ"男装の麗人"が現れる演目は、数限りないですから。
明日はそういうことを書いてみたいと思います。
岡村さんは小柄で、自分の約半分の年齢ですが、妙に堂々としており、
お姉さんのように感じることがあります。